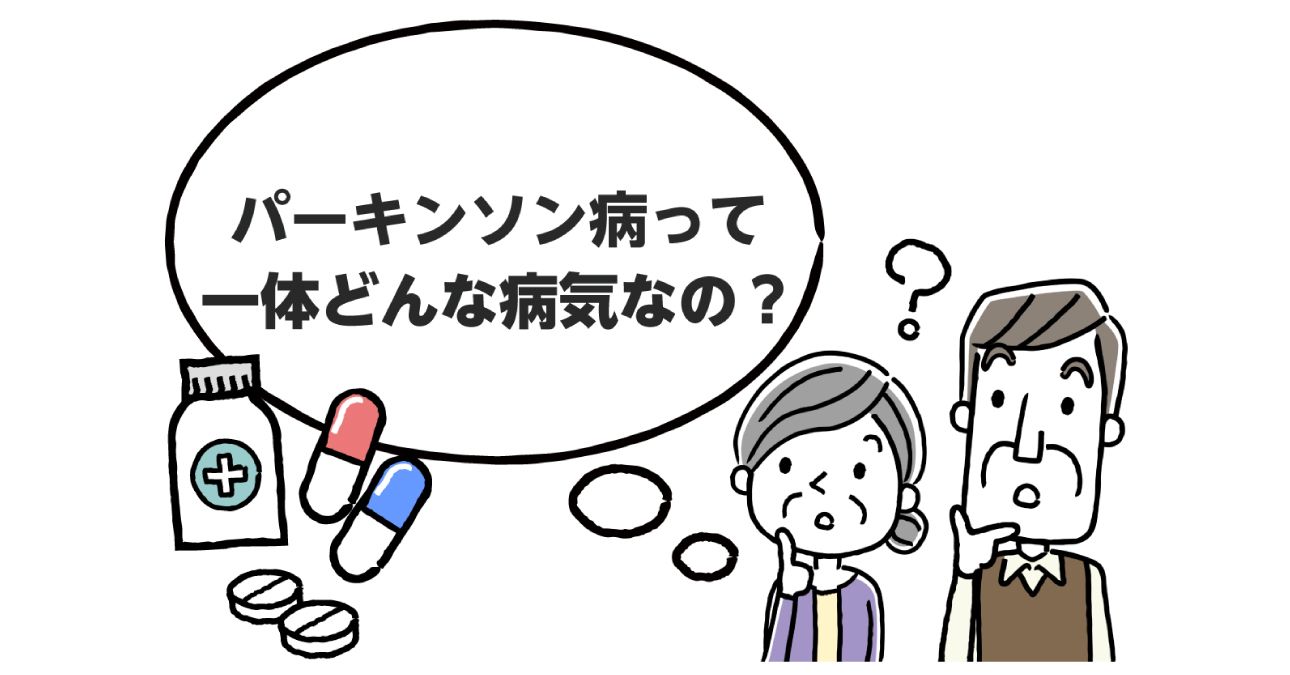若年性認知症とは
若年性認知症とは、65歳未満で発症するさまざまな認知症の種類の総称を指します。
若年性認知症は2つに区分されており、40~64歳までに発症した認知症は初老期認知症、18歳から39歳までに発症した場合は若年期認知症とも呼ばれています。
なお、日本の調査研究では、患者数は4万人弱とされています。
患者数こそ多くはないものの、働き盛りの若い世代が発症した場合には、高齢者よりも家族など周囲の人に及ぼす影響は大きい傾向にあります。
特徴としては、高齢者の認知症が女性に多いのに比べ、若年性認知症は男性のほうが多い点があります。
以下で、もう少し詳しく説明していきます。
若年性認知症になりやすい人の特徴
若年性認知症を含む認知症は、協調性がない人、イライラしやすい人、気にしやすい人がなりやすいといわれています。
若年性認知症のなかでも1番多い原因疾患は「血管性認知症」です。血管性認知症は脳梗塞や脳出血など脳血管の病気によって引き起こされます。
これらの脳血管の病気は生活習慣が関係しているため、糖尿病や高血圧、高脂血症にならないように生活習慣を整えることが重要です。
高齢者の認知症との違い
先述した通り、若年性認知症になる原因疾患は、脳血管障害が最も多いです。一方で、高齢者の認知症の場合は、アルツハイマー病が最も多い原因となっています。
また、「認知症は高齢者に多い」というイメージが強いこともあり、若年期に発症して診察を受けてもうつ病や更年期障害などと間違えられることが少なくありません。
なお、若年性アルツハイマー病の場合、高齢者のアルツハイマー病よりも症状の進行の速度が速いといわれているので、早期診断が重要といえます。
若年性認知症の年代別の数
2017年度~2019年度に実施した日本医療研究開発機構(AMED)認知症研究開発事業の調査によると、全国の若年性認知症者数の男女比は男性 52.5%、女性 47.5%となっています。
若年性認知症の年代別の推定患者数は以下の通りです。
| 年齢 | 推定患者数 |
|---|---|
| 18~19歳 | 81人 |
| 20~24歳 | 203人 |
| 25~29歳 | 201人 |
| 30~34歳 | 246人 |
| 35~39歳 | 411人 |
| 40~44歳 | 745人 |
| 45~49歳 | 1,655人 |
| 50~54歳 | 3,556人 |
| 55~59歳 | 8,333人 |
| 60~64歳 | 2万679人 |
| 18~64歳 | 3万6,110人 |
※各年齢階級別有病率(平均)と年齢階級別人口を掛け合わせて算出した場合
出典:「若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システム」(研究開発代表者所属機関)
若年性認知症の症状
続いて、若年性認知症の症状について解説していきます。
なお、若年性認知症の症状は中核症状と周辺症状の2種類に分けられます。
まずは、若年性認知症のチェックリストを仕事をしている方向けとしていない方向けの2パターン解説していきます。
若年性認知症のチェックリスト
自分や周囲の人が「若年性認知症ではないか」と思った場合、以下のチェックリストでどれくらい該当するのかを確認してみてくださいね。
以下は、仕事をしている方向けのチェックリストです。
仕事をしている方向けのチェックリスト
| チェック項目 | よくある | たまにある | ない | |
|---|---|---|---|---|
| 仕事でミスがありますか | ||||
| 会議中に集中できないことがありますか | ||||
| いくつかの業務を同時にできないことがありますか | ||||
| 残業が増えたと思いますか | ||||
| 仕事がはかどらないことがありますか (段取りが悪くなったと思いますか) |
||||
| 書類などをよく探すことがありますか | ||||
| 予定を忘れることがよくありますか | ||||
| いくつかの約束を同時に入れてしまうことがよくありますか | ||||
| 書類を忘れて取引先に出かけることがありますか | ||||
| ★ | 仕事でミスを指摘されますか(ミスがよくあると思いますか) | |||
| 同僚の態度が以前と変わったと感じますか | ||||
| 周囲に受診を勧められますか(おかしいと言われますか) | ||||
| 会社までひとりで行けないことがありますか | ||||
| 会社以外の取引先にひとりで行けないことがありますか | ||||
| 季節に合わせてスーツなどを変えられないことがありますか | ||||
| 以前と比べてお金を使いすぎることはありますか | ||||
| 怒りっぽかったりやる気がないように見えるなど、 以前と性格が変わったといわれますか |
||||
| コミュニケーションがとりにくいと感じることがありますか |
★のある項目の「よくある」「たまにある」が1つでも該当すれば受診を勧める
★のある項目の「よくある」「たまにある」は非該当だが、★がない項目の「よくある」に半数以上が該当する場合は受診を勧める
★のある項目の「よくある」「たまにある」は非該当だが、★がない項目の「たまにある」のすべてに該当する場合は受診を勧める
仕事をしていない方向けのチェックリスト
続いて、仕事をしていない方向けのチェックリストを解説していきます。
以下のチェックリストで、「よくある」「たまにある」に1つ以上該当した場合、受診をおすすめします。
| チェック項目 | よくある | たまにある | ない |
|---|---|---|---|
| ひとりで近所での買い物ができないことがありますか | |||
| ひとりで交通機関を利用して買い物に行かなくなりましたか | |||
| 同じものをたくさん買うことがありますか | |||
| 家の中が雑然としていることがよくありますか (掃除をしていない、片付けないことがありますか) |
|||
| 洗濯しないことがある・洗濯物がたまっていますか | |||
| 洗濯物を1枚でもする・繰り返すことがありますか | |||
| 子どもの世話や生活に無関心なことがよくありますか | |||
| 食事の味付けがおかしいと思うことがよくありますか | |||
| 食事の用意ができていないことがよくありますか | |||
| 食事が同じメニューばかりになることがよくありますか | |||
| 身だしなみに気を遣わなくなりましたか | |||
| 季節に合わせた洋服を来ていないことがありますか | |||
| 怒りっぽかったり、やる気がないように見えるなど、 性格が変わったと言われますか (パートナーに疑い深くなることがありますか) |
|||
| コミュニケーションがとりにくいことがありますか |
若年性認知症を疑った場合には、一人で抱え込まず、病院を受診し、周囲の人に相談するようにしましょう。
認知機能障害(中核症状)
中核症状は、脳の病変や損傷などによって起こり、認知症の人なら必ずいずれかが発生するとされているものです。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 記憶障害
- 物事を記憶する力が低下し、特に最近の体験した出来事などを覚えていられなくなる
- 見当識障害
- 見当識(時間・場所)が低下し、その日の日付や季節がわからなくなったり、迷子になったりする
- 実行機能障害
- 手順よく計画して行動する実行機能が低下し、物事を進める手順がわからなくなるなどする
- 理解・判断能力障害
- 理解・判断能力が低下し、寒いときに厚着するなど、臨機応変な対応ができなくなる。
- 計算能力障害
- 計算能力が低下し、簡単な計算などが困難になる
行動・心理症状(BPSD)
認知症の行動・心理症状(BPSD)は、中核症状によって二次的に発生することがあり症状で、必ず起こるというものではありません。
BPSDは環境やストレスの影響によって発症しやすくなるとされています。
BPSDの各症状は以下の通りです。
- 不安・焦り
- 行為の失敗による不安、周囲への迷惑などを気にして出現する
- うつ
- ふさぎ込んだり、引きこもりがちになるなど、うつ病のような症状が出る
- 興奮
- イライラして暴言を発したり、暴力を振るってしまったりする
- 睡眠障害
- 昼夜逆転などが原因で睡眠障害が起こる
- 幻視・幻聴
- 現実には存在していない人やものが見えたり、会話が聞こえたりする
若年性認知症の進行

高齢者の認知症と同じく、若年性認知症においても早期発見と早期治療が重要になります。
早期に治療を始めることで、根治はできなくとも、症状の進行を遅らせることができるケースが多いのです。
少しでも認知症が疑わしいと感じたときは、専門医もしくはかかりつけ医に一度相談してみると良いでしょう。
若年性認知症の進行速度
若年性認知症は認知症高齢者よりも進行スピードが早いです。
そもそも認知症は進行性ですが、40代で発症すると、進行速度は高齢者の2倍近くになると言われています。
なかには、5年ほどで末期に至ることもあり、年単位ではなく月単位で進行する場合があるので、早期発見・早期治療で進行を遅らせることが大切です。
初期症状
若年性認知症の初期症状は、忘れっぽくなる、味付けがおかしい、会話が成立しないなどがあります。
またアルツハイマー病が原因疾患の場合、やる気が起きないなどの症状もみられることがあります。物忘れは普通の物忘れではなく、直前の出来事を忘れたり同じことを何度も質問したりします。
原因疾患が血管性の場合は、障害された部位によって症状は異なります。主な症状として、初期のうちは物忘れは目立たず、手順通りに物事を進められない実行機能障害などがあります。
また、感情のコントロールが難しくなったり抑うつ状態になったりすることもあります。
中期
若年性認知症の中期に診られる症状は、原因疾患によってみられる異なりますが、不安や焦り、妄想、うつなどの周辺症状や徘徊などが現れるようになります。
さらに、記憶を維持することが難しくなるのもこの頃です。初期よりも記憶障害が加速して日常生活に支障をきたす場合も増え、自立した生活を過ごすことが難しいです。
そのため、介護者の負担も重くなりストレスが溜まりやすいので、周りのサポートを受けることが大切です。
本人の「楽しい」や「怖い」などの感情は残っているので、否定したり怒ったりせずに、気持ちに寄り添った対応をしましょう。
末期
若年性認知症の末期になると、記憶障害はさらに重度になり、家族のことでさえもわからなくなります。しかし、初期や中期と比べて、末期での記憶障害は自発性の低下、物事への関心が薄くなるなどによって、目立ちにくくなります。
また、歩行障害や運動障害などによってベッドの上で過ごす時間が増え、寝たきり状態になるのもこの頃です。日常生活のほとんどで介護が必要となり、失禁や筋固縮、食べ物を飲み込めなくなる嚥下などの症状が出ることもあります。
介護者はさまざまなことに気を配り、ちょっとした変化も見逃さないようにすることが大切です。
若年性認知症の原因
若年性認知症の症状を理解したところで、続いて若年性認知症の原因について解説していきます。
原因の4割が脳血管障害
若年性認知症になる原因はさまざまあり、なかでも多いのは脳血管障害で、全体の4割近くを占めています。
また、高齢者の認知症に比べて、アルコール性認知症や前頭側頭型認知症の割合が高いのも、若年性認知症の特徴です。
なお、若年性認知症の原因は、脳血管障害をはじめ頭部の外傷や変性疾患など、高齢者の場合に比べて多様であると言われています。
若年性認知症の原因はさまざま
若年性認知症の原因はさまざまです。最も多い血管性認知症の他にアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症などがあります。
アルツハイマー病は、脳にアミロイドβというたんぱく質が蓄積して正常な脳細胞を損傷することで発症します。ただ、たんぱく質だけでなく、遺伝性も関与している場合もあります。
一方、レビー小体型認知症は大脳や中脳の神経細胞にレビー小体が形成され、神経細胞の減少によって引き起こされます。
若年性認知症の予防
若年性認知症の原因として多い血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などを原因として起こる認知症です。
血管に負担を掛けるような生活習慣を改めることは認知症の予防にもつながるでしょう。
また、アルコール性認知症は、その名の通り過度な飲酒によって生じる認知症です。
過度な飲酒を控えることが、発症を防ぐうえで大切になります。
運動
若年性認知症の予防におすすめの運動は有酸素運動です。有酸素運動には、脳の新しい神経や血管が生まれることがあり、認知症の予防に効果的です。
1日30分程度の運動を週3回以上、行うのがおすすめですが、なかでも、簡単な計算やしりとりと運動を同時にするコグニサイズは、脳の活性化も期待できるためおすすめです。
また、地域の認知症を予防する体操教室や講座に参加することもおすすめです。他の参加者と交流を図りながら楽しく運動することができます。
食べ物
アメリカの研究によると、高血圧症を予防するための食事法を改善した食事である「マインド食」を普段から口にする人は、アルツハイマー病の発症リスクが53%低下したと明らかにしています。
積極的に摂取したい食品は緑黄色野菜をはじめとする野菜類、根菜類、魚、鶏肉などで、チーズや赤身の肉、ファストフードなどの摂取を避けましょう。
なお、食事の際には、よく噛んで脳を活性化させて、記憶力や判断力を高めることが大切です。
トレーニング
家にいながら簡単にできる若年性認知症の予防トレーニングは、デュアルタスクです。
デュアルタスクは電話しながらメモを取るというように、同時に2つの作業をして脳に刺激を与えます。
さらに、テレビゲームや囲碁、将棋、脳トレなどもおすすめです。
テレビゲームは指を動かしながら頭で考えて目で操作するキャラクターを追いかけるなど、同時にたくさんの動きをしているため、脳が活性化され認知症の予防になります。
若年性認知症の診断
続いて若年性認知症の診断方法について解説していきます。
認知症の診断方法
以下に、若年性認知症の検査の流れを3段階で説明しています。
1:面談
面談では、本人と家族から、現在の状態やこれまでの病気について聞き取りが行われます。
日頃気づいたことや気になったことはメモをしておき、その内容を医師に伝えるとスムーズに診断を受けることができます。
2:身体検査
面談が終わると、身体検査鑑別診断のための血液検査や心電図検査に加え、感染症検査、X線撮影といった身体検査が行われます。
時間がかかることもありますが、今後の介護方針を決めるうえで重要なデータとなります。
3:問診
面談と身体検査のあとに、問診が行われます。
ここで用いられる主な検査方法は、認知症検査の代表格とされる「長谷川式認知症簡易評価スケール」。
これは簡単な質問形式のやりとりを行い、その答えで認知機能が低下しているかどうかを判別するというもの。
30点満点のうち20点以下の場合は、認知症の疑いがあるとされています。
長谷川式認知症簡易評価スケール以外の有名な検査方法は以下の通りです。
- ミニメンタルステート検査(MMSE)
- 質問形式の検査で、図形描写など、構成的機能のチェックを行います
- ウェクスラー記憶検査(WMS-R)
- 総合的な記憶検査で、言葉や図形を使った問題で記憶力や集中力などを評価します
さらに、画像検査CT、MRI、SPECT(脳血流シンチグラフィ)などで脳の状態を調べます。
これらの検査では、脳のどの部分が萎縮しているのかや血流などを測定し、疾患のタイプ、進行度を調べます。
若年性認知症と診断されたら

若年性認知症の人は、年齢的に会社などで働いている人が多く、発症した場合の生活への影響は多大です。
また、高齢の親と同居している世帯では、若年性認知症の家族と親の介護が重なるというケースも多く、介護負担は大きなものになります。
若年性認知症を発症したときには子どもがまだ成人していない場合も多く、子どもが協力できないためにほかの家族に介護負担が集中しがちです。
若年性認知症の人がいる世帯は、収入の面から介護のあり方まで複数の問題を同時に抱えることになり、その点がこの認知症の難しさであるともいえるでしょう。
以下では、若年性認知症と診断された際にとるべき対応をまとめました。
職場に相談する
日本の就労環境においては、若年性認知症に対する認知度や理解度はまだ十分とは言えません。
厚労省の調査によると、職場に認知症であることを説明したことで、労働時間の短縮や配置転換などの配慮があった、と回答した人は全体の27.2%にとどまっていました。
「職場での理解が得られないだろうから、認知症のことを話せない・・・」というケースが非常に多いことを伺わせる結果となっています。
また、同じ調査では実に約60%もの人が発症後に収入が減ったと述べており、発症後の家計については「とても苦しい」「やや苦しい」といった回答がそれぞれ全体の約20%もありました。
もし、それまで働いていた職場での就労継続が難しい場合、障害者枠で改めて再雇用してもらうというのもひとつの方法です。
若年性認知症の場合、「精神障害者保健福祉手帳」を取得できるようになっています。
また、もし身体機能にも症状がある場合には、「身体障害者手帳」が取得できる場合があります。
市役所の障害福祉課など、担当窓口などで相談してみてくださいね。
また、ハローワークで就労訓練を受けることもできるので、生活のことを考えて、できる範囲で働いていくという割り切った考え方を持つことのも手段の一つです。
社会保障制度を活用する
現在日本には、障害年金や自立支援医療制度など若年性認知症を支援するさまざまな制度があります。
それらを上手く組み合わせて利用することで、家計の負担を軽くし、生活に余裕を持たせることもできるでしょう。
どのような制度があるのか、以下で解説していきます。
障害年金
障害年金は、病気や怪我などで障害を負ったことで、仕事が制限されている場合に支給される年金です。
給付を受けるには、一定の受給要件を満たさねばなりませんが、若年性認知症の方も給付対象となります。
受給要件には以下のようなものがあります。
- 初診日要件
- 障害の原因となった怪我や病気の初診日が、国民年金もしくは厚生年金の被保険者である期間内であること
- 保険料納付要件
- 保険料を、基準として設けられている期間きちんと支払っていること
- 障害状態該当要件
- 定められた障害等級に該当すること
障害者手帳
若年性認知症の人は「精神障害者保健福祉手帳」の交付対象です。
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を持つ方の社会復帰や自立支援を目的に交付され、交付された場合は、就職時に配慮を受けやすくなるほか、税金面での控除や医療費における助成を受けることができます。
自立支援医療制度
「自立支援医療(精神通院)制度」は、精神疾患で通院による治療を受けた際、医療費の自己負担分が助成されるという制度です。
うつ病や統合失調症などが主な対象ですが、若年性認知症にも適用されます。
医療費・介護費の自己負担の減免制度
「高額療養費」「高額介護サービス費」「高額医療・介護合算療養費制度」は、世帯における医療費や介護費の支出額が規定の「自己負担限度額」を上回った場合、超えた分についての金額が支給されるという制度です。
住宅ローン返済の相談する
どのような保険に加入していたかにもよりますが、若年性認知症によって収入が減少してローンの返済が困難になったとき、その症状が「高度障害」と認定されれば、返済が免除される場合もあります。
詳しくは、住宅ローンを契約した窓口で相談してみてください。
運転免許の返納する
認知症の診断を受けた場合には、運転免許証を返納する義務があります。
ただ、本人に返納をお願いする場合、車の運転ができなくなってしまうという本人の気持ちに配慮することも大事です。
「認知症だから、運転しないで」などと本人のプライドを傷つけるような言動は避けるようにしましょう。
家族での説得が難しい場合は、運転適性相談窓口に相談したり、医師に協力をしてもらい、今の状態で運転をすることのリスクを説明してもらうのも良いでしょう。
日常生活自立支援事業を利用する
日常生活自立支援事業とは、認知症などで適切な判断ができなくなった方を対象に、地域で自立した生活を送れるよう支援を行うサービス事業です。
実施しているのは、市区町村の社会福祉協議会です。
具体的には、福祉サービスの利用援助をはじめ、お金の管理や定期的な訪問による生活状況の確認などが行われます。
成年後見制度を利用する
成年後見制度は認知症によって判断能力が衰えた人を法的に保護し、サポートする制度です。
裁判所に認められた「成年後見人」が、本人に代わって財産管理や契約などを行います。
後見人には、親族や近親者が選ばれるのが一般的で、それが困難な場合には専門職が選任されることがあります。
公的サービスを利用する
介護保険サービス
介護保険料を納めている40歳から64歳までの「介護保険2号被保険者」であれば、認知症など特定疾病にかかっている場合に限り、介護保険サービスを利用できます。
ただ、介護保険サービスの多くは高齢者向けなので、通常の介護事業所を利用しにくいという側面があるのも事実です。
そんななか、最近では若年性認知症の人を積極的に受け入れているデイサービスなど、若い人向けの施設も登場しつつあります。
地域にそのような介護事業所があるのか、住んでいる自治体の地域包括支援センターに問い合わせてみると良いでしょう。
障害者福祉サービス
40歳未満の方は、介護保険の被保険者ではありませんが、障害者総合支援法の下で障害福祉サービスを利用することができます。
障害福祉サービスを利用すると、居宅介護や就労継続支援などのサービスを保険適用で受けられるので非常に便利です。
若年性認知症の治療方法
若年性認知症は早期発見が重要とお伝えしましたが、実際に診断を受けた後にどのように治療が行われていくのかを解説していきます。
薬物療法
若年性認知症に対する根本的な治療薬は、現在のところ開発されていません。
そのため、認知症に対する薬物治療は、症状に対応する形で薬剤を選択するという対症療法が中心です。
現在使用されている治療薬には、「アリセプト」などの中核症状向けの薬と、抗精神病薬など行動・心理症状向けの薬があります。
ただ、認知症の治療薬は副作用が起こることもあるので、もし体に合わないと感じた場合は、早めに医師に相談しましょう。
非薬物療法
若年性認知症に対しては、薬物治療も大切ですが、生活習慣の見直しなどの非薬物療法も重要であると言われています。
例えば、栄養バランスの取れた食事や質の良い睡眠など、生活習慣を見直すことで認知症の進行を抑えられると言われています。
特に食事は重要で、アマという植物の種であるアマニ油、えごま油、ナッツ類など、認知症の症状改善につながるとされる食材はたくさんあります。
また、脳に刺激を与え、活性化させる有効な方法のひとつが「アロマ」です。
アロマの香りで認知症の症状を改善する「アロマ療法」は、介護施設などでも盛んに行われています。
リハビリ
非薬物療法で行われるリハビリでは回想法や音楽療法、脳トレなどがあります。
回想法は昔の出来事や思い出を他の人に話すことにより、脳に刺激を与え進行を遅らせる効果があります。
音楽療法は自分が好きだった音楽を聴き、当時の出来事を思い出すきっかけを与えます。
認知症によって上手く話せない方でも、記憶に残る曲を歌うことで、自信を取り戻すきっかけにもなるのです。また、心地良い音楽は精神を安らげる効果があるので、症状の緩和を期待できます。
計算問題や漢字などを解く脳トレでは、物忘れの症状が軽くなったり意欲の向上につながったりします。
若年性認知症の方への対応のポイント
もし家族が若年性認知症と診断された場合、どのように対応していけば良いのでしょうか。
一番不安を感じているのは本人ですので、その気持ちに寄り添った対応が大切です。
一人で悩まずに相談を

現在国が進めている認知症施策推進総合戦略、通称「新オレンジプラン」では、若年性認知症の人への支援策が強化されています。
都道府県ごとに「若年性認知症コールセンター」という相談窓口が設置されており、ほかにも地域包括支援センターや認知症疾患医療センターなども相談を受け付けています。
もし生活のことや介護のことで困ったことが起こったら、まずは話を聞いてもらいましょう。
また、全国各地で開催されている認知症カフェや家族の集いなどに参加して、同じような境遇にある人に悩みを打ち明けるのもおすすめです。
若年性認知症の人への接し方
若年性認知症の人は年齢が若いだけに、今までできていたことができなくなることで、もどかしさを強く感じます。
その精神的なストレスが認知症の症状に悪影響を与え、抑うつや興奮、妄想などの行動・心理症状(BPSD)を悪化させてしまうケースも少なくありません。
周囲の人には、本人の残存機能を活かせるような生活スタイルを維持し、本人の自信を失わせるような言動や行動を控える配慮が求められます。
よくある質問
20代~30代でも若年性認知症は発症しますか?
20~30代で若年性認知症を発症することは、ごくまれです。
2009年の厚生労働省の調査によると、若年性認知症を発症した約3万7,800人のうち、50~64歳が3万2,210人で約85%を占めています。
40歳までに発症したケースは2,210人と少数で、平均発症年齢は51歳となっています。
20代や30代で発症することはまれにありますが、かなり少ないと言って良いでしょう。
若年性認知症の人を専門にした入居施設はありますか?
若年性認知症専門の入居施設は、今のところありません。
もし、若年性認知症を発症したときは、高齢者の方と同じ認知症対応の施設を利用します。
しかし、若年性認知症の人を受け入れ可能かどうかは施設ごとに異なります。
「みんなの介護入居相談センター」では、一人ひとりに合った施設を紹介可能ですので、是非以下のボタンからお問い合わせください。
若年性認知症の発症頻度は?
若年性認知症の発症頻度は、高齢者が発症する認知症の1,000分の1以下というデータがあります。
2009年3月の厚生労働省の発表によると、全国における若年性認知症者数は3.78万人で、18~64歳の人口を10万人として考えると、若年性認知症患者の数は47.6人でした。
この数字は、高齢者が発症する認知症の1,000分の1以下となっています。
仕事を続けていくにはどうしたら良いの?
若年性認知症になった場合、職務の変更や異動、ときには休職や退職なども考えられます。
また、仕事を続けられたとしても、記憶障害の程度や職場環境によって支援の方法が異なります。
それを踏まえ、どんな社会保障が受けられるかの調査や、家計の調整を早めに行っておきたいところです。
ちなみに、東京都にある若年性認知症総合支援センターには「若年性認知症支援コーディネーター」がおり、就労継続や休職などの相談から経済保障、介護にかかわることまで多岐にわたる情報を提供してくれます。
本人だけでなく、企業などの担当者の方も相談でき、必要に応じて勤務先へ赴くことも可能です。
また、下記の施設でも相談を行えるので、必要に応じて参考にしてください。
- 地域障害者職業センター(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- ハローワーク
- 障害者就業・生活支援センター
- 就労移行支援事業所
発症後に家族ができるサポートは?
本人に認知症の告知をするかどうかは、ご家族のなかでも争点になることが多い問題です。
仕事ができている状態で告知を受けると、精神的な打撃が大きく、うつ傾向が加速、悪化する可能性があります。
しかし、理解力がある状態で告知をしておけば、本人の意思や希望をきいたうえで治療を行うことができます。
もしも早い段階で告知を決めたなら、本人の気持ちに寄り添い、家族で団結して乗り越えていくという強い意志と手厚いサポートが必要になります。
そのときは、以下の2つの対応に気をつけるようにください。
無理強いはしない
できなくなったことにフォーカスするのではなく、一つひとつ着実にできることを継続するように工夫しましょう。
本人の話を否定しない
物盗られ妄想が出現する場合は、ご家族との関係もギクシャクしてしまいがちですが、嘘を言っていると責め立てても解決には繋がりません。
しっかりと話を受け止め、誠実に対応することを心がけることが、認知症介護の最も重要なポイントです。
他の人はこちらも質問
若年性認知症ってどんな症状?
若年性認知症の症状は、物事の記憶が低下する記憶障害、物事の手順がわからなくなる実行機能障害、時間や場所がわからなくなる見当識障害などの中核症状が見られます。
また中核症状の二次的に起こる睡眠障害、うつ、幻聴などのBPSDがあります。BPSDは必ず起きるわけではありません。
若年性認知症の原因は何?
若年性認知症の原因で最も多いのは脳血管障害です。さらにアルコール性認知症、前頭側頭型認知症の割合も高い特徴があります。
若年性認知症は何歳が多い?
若年性認知症を発症する平均年齢は男性・女性ともに51歳です。働き盛りの世代に見られ、男性の方が発症は多いです。
若年性アルツハイマーは何歳から何歳まで?
若年性認知症の年齢は18歳から64歳です。18歳から39歳までに発症した認知症を若年期認知症と言います。40歳から64歳までに発症した場合、初老期認知症と呼びます。また若年性認知症は男性の割合が多いです。



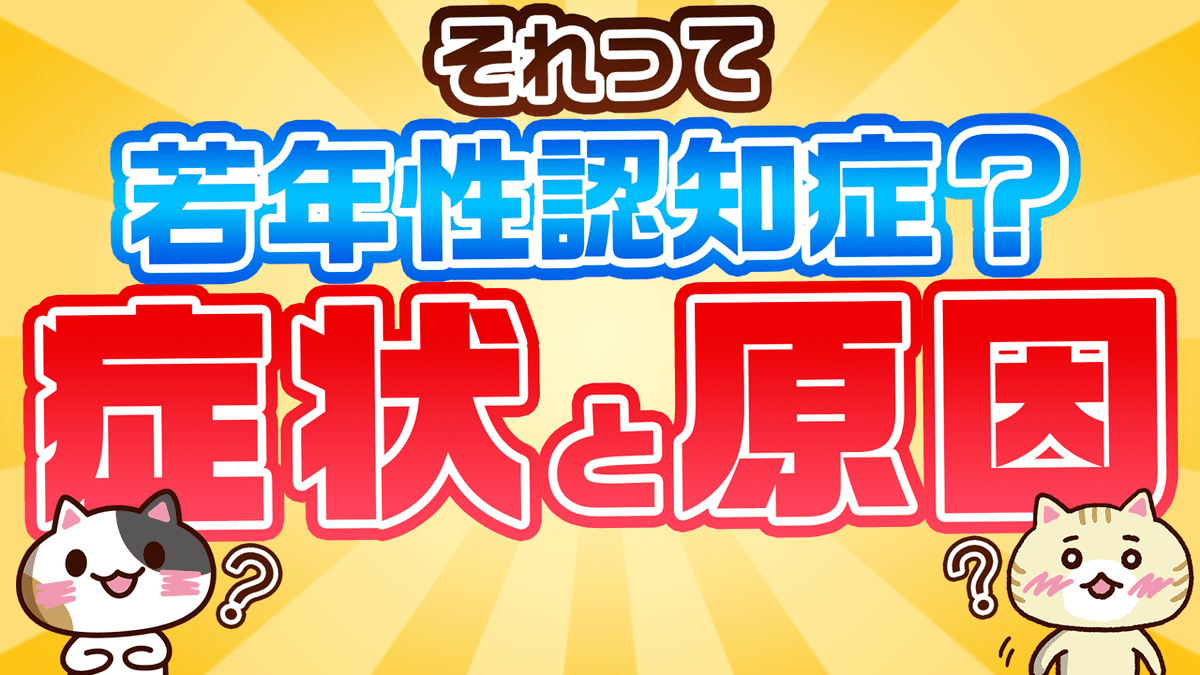




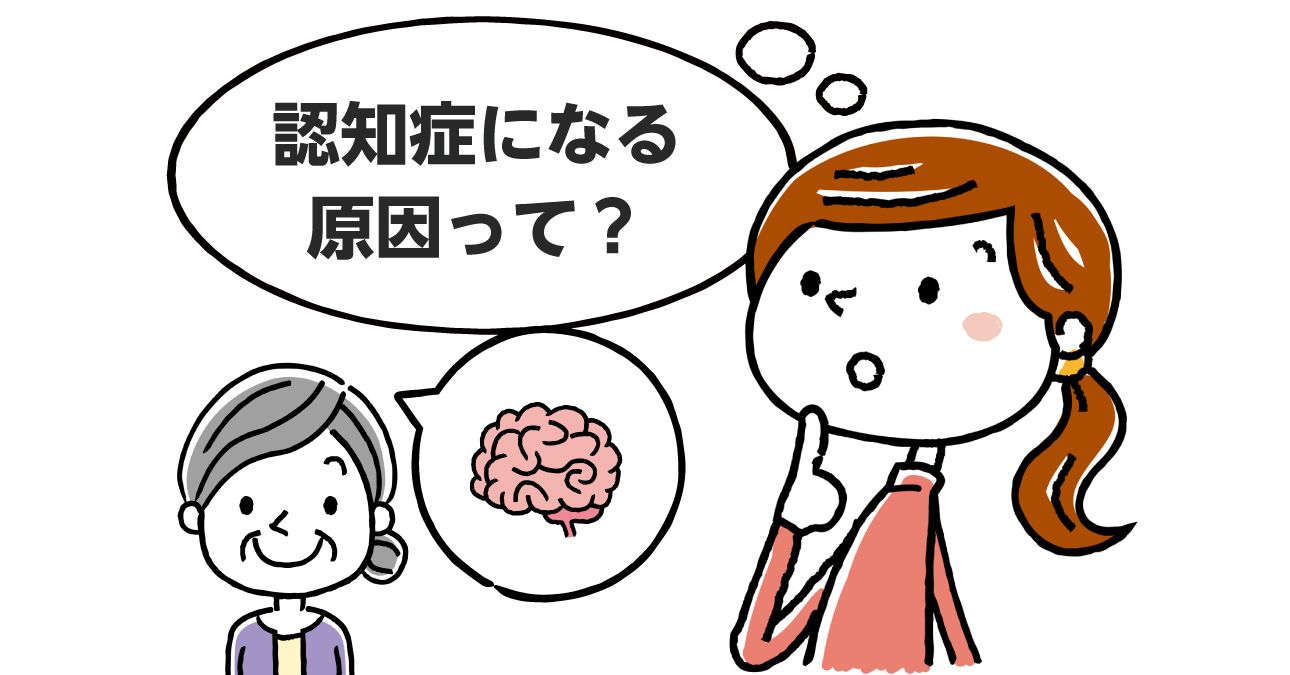

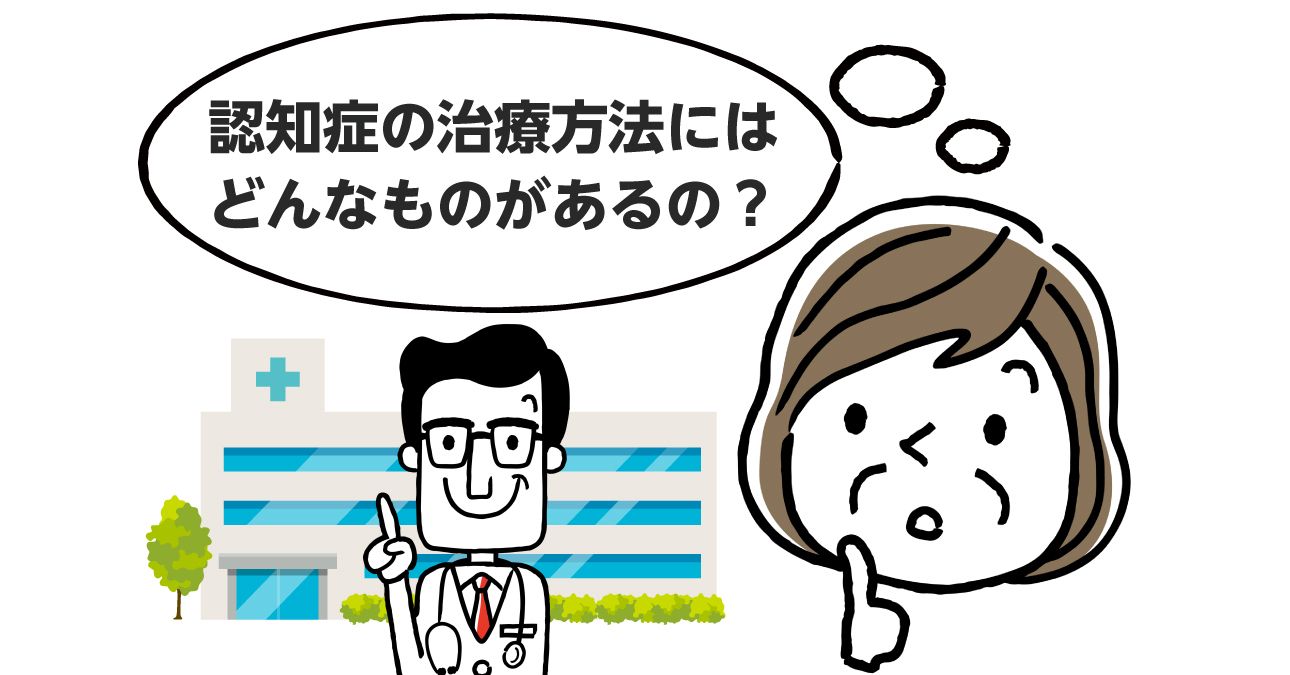


 この記事の
この記事の