生活保護でも介護保険料は支払う必要がある
介護保険サービスは、要介護認定を受けた65歳以上の方が利用できる公的制度です。
身体状況に応じて、必要な介護サービスを自己負担割合1〜3割で利用できます。なお、残りの7~9割は「介護保険料」と「国や自治体による公費」によって賄われています。
介護保険料は40歳以上の人全員に支払いの義務が発生します。それは生活保護受給者も例外ではありません。
ただし、介護保険料は生活扶助(生活保護費)によって補っており、通常のケースといくつかの違いがあります。
そこで、生活保護を受けている方の介護保険のポイントを解説します。
介護保険の年齢による区分
介護保険は年齢によって、以下の2つに区分できます。
| 区分 | 年齢 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 |
| 第2号被保険者 | 40~64歳 |
生活保護受給者であっても、いずれかの区分に該当されます。
生活保護受給者と通常との違い
生活保護を受給しているかによる大きな違いは、介護保険料や介護サービス費の金額です。
生活保護受給者の介護保険料は「生活扶助」から賄われます。
また、要支援・要介護状態と認定された生活保護受給者が介護保険サービスを利用する場合、介護保険から給付を受けられるのは通常と同じです。
ただし、自己負担額については「介護扶助」で賄われます。つまり、生活保護受給者は介護保険サービスを実質的に自己負担ゼロで利用できます。
- 生活扶助とは
- 生活保護の扶養の一つで、衣食や光熱費、日常生活費に充てられる支援金のこと
- 介護扶助とは
- 生活保護の扶養の一つで、要介護・要支援の認定を受けた人に充てられる支援金のこと
介護保険の仕組みについて詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご確認ください。
介護保険者の請求への対応方法(自費)
介護保険料は「40歳以上65歳未満」と「65歳以上」のそれぞれの年齢区分で、納入する金額が異なります。
生活保護受給者との違いも交えながら、年齢別の介護保険料を確認していきましょう。
第2号被保険者(40~65歳未満)の場合
生活保護受給者の場合、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は介護保険料の納付はできません。
何故なら、生活保護を受給すると国民健康保険から脱退しなければなりません。つまり、公的医療保険に加入していない「無保険」の状態です。
公的医療保険料を納付していない以上、上乗せされる介護保険料の納付もできなくなるからです。
介護保険料を加入できない以上、生活保護受給者は「第2号被保険者」に該当しません。この点が通常の場合との違いと言えるでしょう。
みなし2号とは
生活保護受給者は介護サービスを利用できないのでしょうか。
答えは要介護状態になった場合には介護サービスを利用できます。
制度上は「みなし2号」という位置付けとなり、第2号被保険者と「みなして」要介護認定の審査が行われます。要支援1以上の認定が下りれば、生活保護受給者であっても介護サービスを利用できます。
保険加入者ではないために介護保険適用とはならず、費用の全額・10割分が生活保護費の介護扶助によって支給されます。
第1号被保険者(65歳以上)の場合
65歳以上の第1号被保険者である生活保護受給者にも、介護保険料の納付は義務づけられています。すべての国民が加入しなければならないため、生活保護を受けていても支払いが免除されることはありません。
ただし、冒頭でも紹介したように生活保護受給者の場合、実質的に金銭面の負担はありません。生活保護費の生活扶助に介護保険料の金額分が加算されて支給されるからです。
介護保険料が日常生活に必要な経費に上乗せされて支給されます。
生活保護世帯の介護保険料の一例
| 所得基準 | 負担割合 | 年間保険料額 |
|---|---|---|
| ・生活保護受給者・老齢福祉年金受給者 | 基準額×0.25 | 1万7,900円 |
※1.世帯全員が住民税非課税が対象 ※2.消費税率改定に伴う負担軽減のため、公費投入(渋谷区の予算からの補填)により減額されています ※3.負担割合の基準額は7万1,520円で算出
介護保険料は生活扶助から賄われると紹介しました。では「これまで支給されていた生活保護費を切り詰める必要があるか?」というと、そうではありません。
介護保険料の額面が生活保護費に上乗せされて支給されることから、切り詰めて生活を送る必要はありません。例えば、上記例の場合では1万7,900円が上乗せされるかたちで支給されます。
第1号被保険者が注意したい納付方法

第1号被保険者となっている生活保護受給者の場合、通常の納付方法と異なるので注意が必要です。以下で生活保護受給者の納付方法を解説します。
介護保険料は生活保護費から天引き
生活保護受給者が介護保険料を納付する場合、福祉事務所が生活保護費から天引きして市区町村に納める「代理納付」という方法で保険料を徴収しています。
天引きできない場合もある
場合によっては代理納付ができない、つまり生活保護費から介護保険料を天引きできないケースがあります。
例えば、生活保護の受給がはじまってしばらくは生活扶助における介護保険料の上乗せ分が、現金で支給されるので天引きできません。
また、老人ホームに入居している人で住民票が別の市区町村にある場合も、福祉事務所が介護保険料を天引きする「代理納付」が難しくなる場合があります。
そうした場合に利用できるのが「住所地特例制度」です。
住所地特例制度
住所地特例制度とは、介護保険の被保険者の方が住民票のある地域から、施設のある所在地に住民票を移した場合も、引き続き転居前の市町村の被保険者で居続けられる制度です。
対象となるのは以下の施設の入居者です。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウスなど)
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
もちろん、生活保護受給者が自宅とは別の自治体にある施設に入居した場合も、住所地特例制度の適用対象です。
ただし、「介護保険の保険者となる自治体」と「生活保護を管理する自治体」が一致しない場合は、生活保護費の介護保険料分が天引きではなく、現金で支給されることがあります。
その場合、本人が現金を持って介護保険料の支払いに行かなければなりません。納付を忘れないよう注意が必要です。
要介護の場合は介護サービスが利用できる
通常、介護保険の要介護認定は65歳以上が対象です。
しかし、16種類の疾病については40~64歳の第2号被保険者でも要介護認定の対象となり、介護サービスを利用できます。
【介護保険】特定疾病とは?16種類一覧と診断基準、覚え方(第2号被保険者も対象に)
もちろん、生活保護受給者も特定疾病に罹患した場合は介護サービスの対象です。
なお、介護サービス費は冒頭で紹介したように生活保護費の「介護扶助」による全額・10割支給の対象となるので、自己負担額ゼロで介護サービスを受けられます。
サービスの利用料(自己負担額)は介護扶助で賄われる
通常の場合、介護保険サービスの自己負担割合は、所得に応じて1割から3割に決まります。
しかし、生活保護受給者の場合、自己負担割合は1割と定められています。なお、この1割の自己負担額についても生活保護の介護扶助から支給されます。
介護サービス利用時には「介護保険負担割合証」が必要
介護保険サービスを利用するには、通常のケースと同様に「介護保険証」と「負担割合証」が必要です。
- 介護保険負担割合証とは
- 介護サービスを利用時の負担割合が示された書類のこと。
要介護認定を申請した後、1ヵ月程度で交付されます。
負担割合証はケアマネージャーやサービス提供事業者等に提示する必要があるため、届いたら大切に管理しましょう。
障害者施策では介護扶助が優先される
続いて、介護扶助が介護保険でどのように適用されるのか解説します。
以下は介護扶助と介護保険の関係についてまとめた表です。要件をもとに自分がどの区分に該当するか確認してみましょう。
| 要件 | 要介護・要支援の状態にある被保護者 | ||
|---|---|---|---|
| 40歳以上65歳未満 | 65歳以上 | ||
| ・医療保険未加入者 ・特定疾病の該当者 |
・医療保険加入者 ・特定疾病の該当者 |
||
| 介護保険の適用 | 非対象 | 対象 | |
| 第二号被保険者 | 第一号被保険者 | ||
| 要介護認定 | 生活保護法による要介護認定 | 介護保険法による要介護認定 | |
| ケアプラン | 生活保護法の指定介護機関が作成 | 介護保険法に基づき作成 | |
| 支給限度額以内のケアプランに限る | |||
| 給付割合 | 生活保護法の指定介護機関からの介護サービスに限る | ||
| 介護扶助10割 | 介護保険9割・介護扶助1割 | ||
| 障害者施策関係 | 障害者手帳等を持っている場合は、 障害者施策が優先 |
介護保険・介護扶助優先 | |
生活保護受給者のうち、障害者手帳を持っている方は介護扶助よりも障害者施策が優先されます。
一方で、第1号・第2号被保険者については、介護保険や介護扶助のほうを優先して適用されます。
生活保護でも入居できる老人ホーム
生活保護受給者でも老人ホームに入居することは可能です。ただし、いくつか通常の方とは違う点もあるので注意が必要です。
条件はあるが、入居可能な施設は存在する
生活保護を受給していても入居できるのは、住宅型やサ高住、グループホームなどの施設です。
生活保護受給者の受け入れについて、各事業者ともにガイドラインを設けており、人数に上限を設けて受け入れている施設もあります。
また、料金も生活扶助の限度額内で収まる施設を探すことが前提にあります。
みんなの介護では生活保護を受けている方が入居できる老人ホームを紹介しています。以下のボタンから施設を検索してみましょう。
生活保護でも入居できる老人ホームを探す施設選びにお悩みの方は『みんなの介護入居相談センター』に相談を
老人ホームへの入居を検討している方は一度『みんなの介護 入居相談センター』にお問い合わせください。
施設掲載数49,000件以上の中から、希望予算や入居目的、心身状態に合った施設を紹介しています。相談はもちろん、資料請求や見学予約も無料です。
相談は電話とチャットで受け付けています。「住んでいる地域でおすすめの老人ホームが知りたい」「予算に合った施設を探している」など、老人ホーム探しで迷ったら、気軽に以下のボタンからお問い合わせください。
生活保護者の介護保険に関するQ&A
もし医療が必要になったら?
冒頭で生活保護受給者は医療保険の対象外とお伝えしましたが、「無保険」の状態でけがや病気になった場合はどうするのでしょうか。
生活保護受給者の場合は医療保険に入っていないので、保険適用は受けられません。しかし、「10割分」の費用が医療扶助から支給され、自己負担額ゼロで医療サービスを受けられます。
- 医療扶助とは
- 国民健康保険と同等の治療を受けるための扶助
生活保護の認定を受けられず、介護保険料を払えない場合は?
「生活保護の申請が受理されず、介護保険料が支払えない…」というケースも少なくありません。
そういったときに活用したいのが、「境界層制度」です。
「境界層措置」とは
境界層とは、「生活保護の対象になるほどではないが、経済的に困窮していると認められる層」のことです。
自治体に申請して、境界層と認められると「境界層該当措置証明書」され、以下の救済処置を受けることができます。
- 介護保険料滞納時のペナルティなし
- 介護保険料の減額
- 介護施設での食費、居住費の減額
- 高額介護サービス費の負担上限額の低下
経済的に苦しいものの、生活保護の要件は満たしていない方は境界層措置を利用できないか検討してみましょう。
申請場所は市区町村の窓口です。気になる方は一度相談してみることをおすすめします。



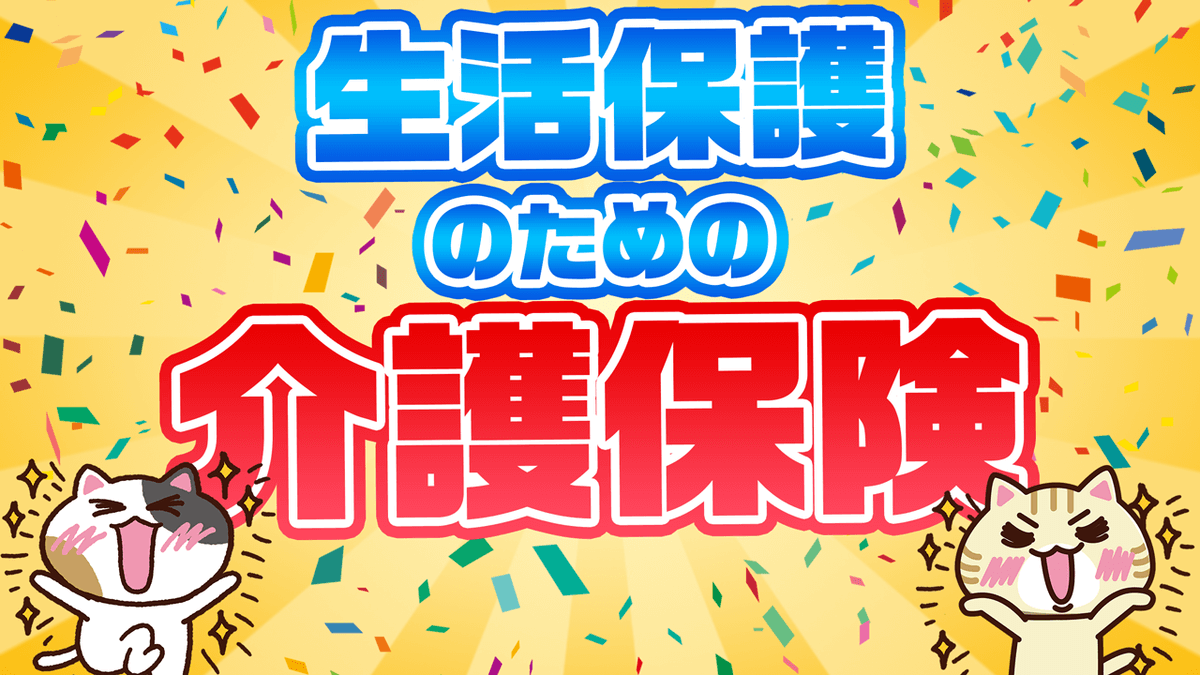



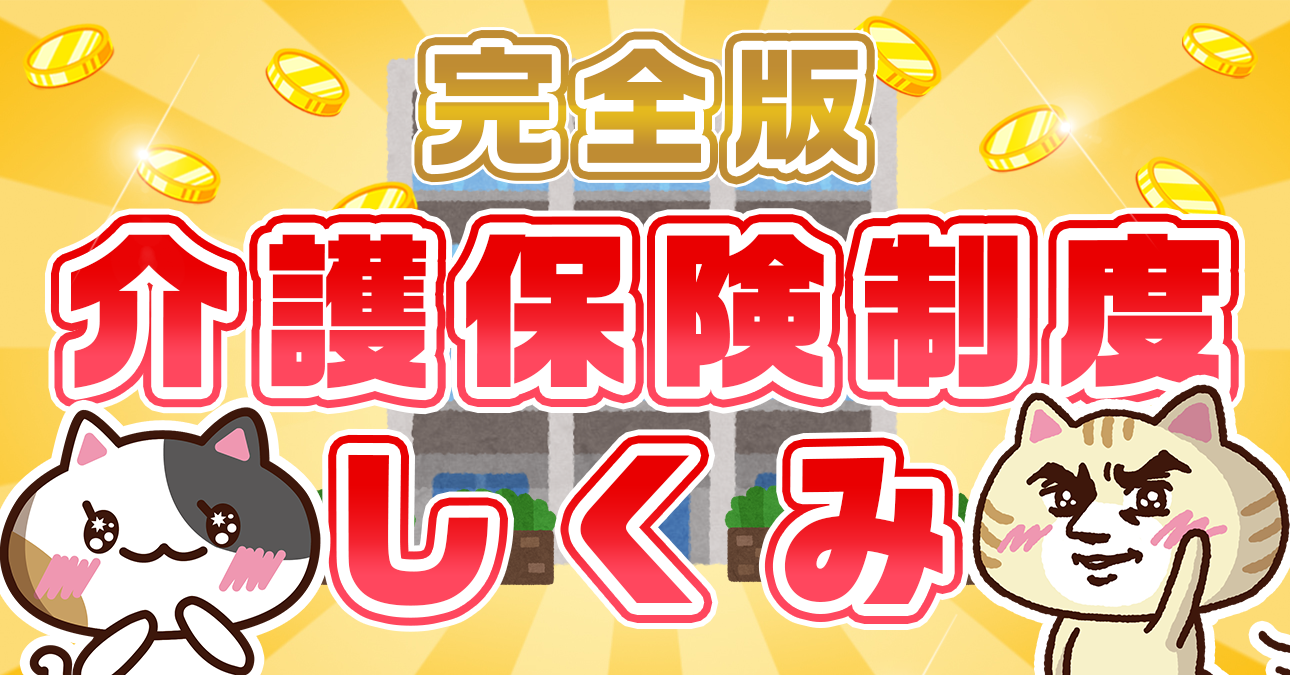


 この記事の
この記事の



