介護の準備に必要な事前知識
介護の準備を始めるとき、まず実際に介護を受けることになる親や家族がどのような生活を望むのかを確認しましょう。
介護はあくまで利用者本人が受けるものです。
その人らしい暮らしを尊重して希望に沿った生活が送れるように、サポートする視点が大切といえます。
介護が必要になったからといって、本人の希望や性格を考えずに近所の介護サービスを申し込んだり、ケアマネージャーに任せきりだったりしてしまうと、その人らしい生活は難しくなるでしょう。
希望の生活を整えていくためにも、まず介護に関する必要な知識を身につけることが大切です。
介護が必要なケースや症状
加齢によって徐々に介護が必要になるケースもあれば、病気や怪我で突然介護が必要になるケースもあります。
ともかく、介護が必要になったら時間は待ってくれません。速やかに介護サービスの申し込み・手続きをして利用を開始する必要があります。
具体的に介護が必要な原因としては、認知症や脳血管障害、加齢による身体機能の低下、骨折や転倒などが知られています。
とりわけ脳血管障害は歩行障害や運動器の麻痺などが残るケースが多いため、日常生活が大幅に制限されます。
介護の種類
介護の方法には大きくわけて、「在宅介護」「遠距離介護」「施設介護」の3種類があります。
- 在宅介護
- 住み慣れた自宅で生活しながら受ける介護のことです。同居する家族から介護を受けながら、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを利用します。
- 遠距離介護
- 介護を行う側が介護を受ける側と離れて生活しながら行う介護のことです。実家にいる要介護状態の老親を、遠く離れて暮らす子どもが通いで介護をするケースが一般的といえます。
- 施設介護
- 老人ホームに入居して受ける介護のことです。家族に介護負担が発生せず、施設のスタッフによる24時間体制での見守りや、多様な生活支援も受けることができます。
以下ではそれぞれの特徴を、メリット・デメリットに分けて紹介します。
在宅介護
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・住み慣れた自宅で過ごせる ・要介護の心身状態に合わせて、訪問介護や通所介護などのサービスを利用できる |
・家族や身内の介護負担が大きくなりやすい |
在宅介護を選択する場合によく聞かれる理由として、住み慣れた自宅や地域社会の中で暮らせるという点があります。
また、訪問介護や通所介護などの自宅で利用できる介護サービスを、要介護の心身状態に合わせて利用できることも自宅介護のメリットといえます。
一方、在宅介護のデメリットは、家族や身内の介護負担が大きいことです。
介護はいつまで続くのか終わりが見えないため、長期化するほど家族介護者の肉体的・精神的負担は増えていきます。介護を行う側まで倒れる「共倒れ」が生じるケースも少なくありません。
そのため、身体状況に合わせて施設入居を考えていくことも大切です。
遠距離介護
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・介護をする側の負担が少ない ・介護のことを客観的に捉えられる |
・緊急時の対応が難しい |
遠距離介護のメリットとしては、介護者が要介護者と同居していないので、常に介護に関わる必要がないという点があります。
介護者は要介護者と離れて暮らすことで、介護のことを客観的に捉えることが可能です。介護のことで悩み、精神的に追い詰められるという事態を避けることができます。
また、遠距離介護では介護者が今住んでいる地域を離れる必要がないので、介護を理由に勤め先を退職する「介護離職」の心配も少ないです。
一方、遠距離介護のデメリットとして、介護者が要介護者と遠く離れているため、緊急時の対応が難しいという点があります。
まずは担当のケアマネージャーに相談し、見守りや安否確認ができる介護サービスを利用することが大事です。
また、遠距離介護の場合、どうしても交通費の負担が大きいため、航空会社や鉄道会社が実施している割引制度を利用するなど、少しでも負担を減らす努力が必要です。
呼び寄せ介護
呼び寄せ介護とは、子世帯が離れて暮らす親世帯を自宅の近くに呼び寄せて、同居または近居することを指します。
都心部で暮らす子世帯が、遠方で暮らす老親を心配して呼び寄せるケースと、介護をするために呼び寄せるケースがあります。
近居の際には高齢者向け住宅(サ高住)や高齢者向け賃貸住宅を選択するシニアも多く、家族が近くにいるという安心感や緊急時にすぐ駆けつけられるといったメリットがあります。
一方で、親は知らない土地で暮らすことになるため、友人・知人が少なくなったり、生活環境に慣れるまで時間がかかったりすることがデメリットとして挙げられます。
施設介護
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・介護をする側の負担が減らせる ・家族以外の人ともコミュニケーションを楽しめる |
・金銭的負担が発生する |
介護施設の種類には「民間施設」である有料老人ホーム(介護付き・住宅型)、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームと、「公的施設」である特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウスなどがあります。
介護施設の利用による最大のメリットは、民間施設・公的施設のどちらであっても、要介護者が入居することで家族の介護負担を大幅に減らせることです。
また、施設介護では家族以外の人と頻繁にコミュニケーションを取ることも可能です。ほかの入居者や職員との会話は脳の刺激につながり、認知症の予防や改善にもつながります。
一方、施設介護のデメリットとしては、入居費用が発生することや集団での生活に馴染めない場合にストレスになることです。
介護の準備チェックリスト
- 要望を知る
- 健康状態を把握する
- 経済状況を把握する
- 生活リズムを把握する
- 人間関係を把握する
要介護者に確認しておくべきこと
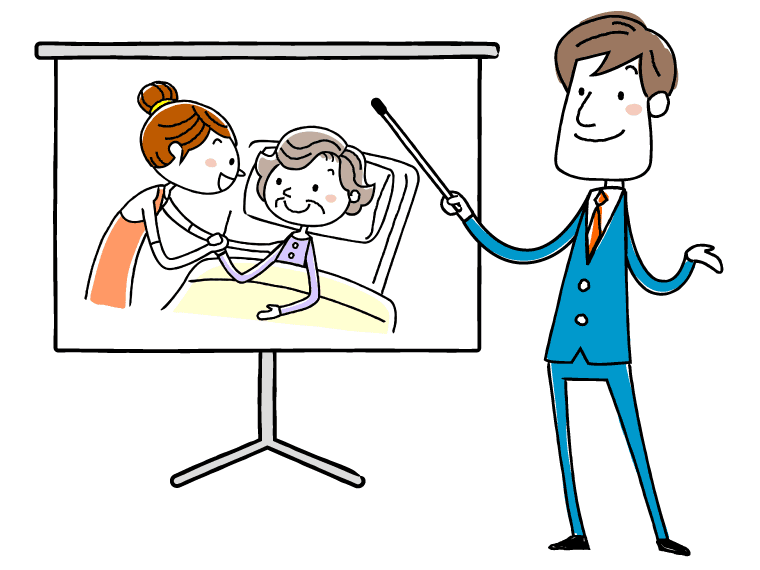
介護の準備を考えるにあたって、介護について家族で話しておくことは重要です。誰が介護の中心役となるかを前もって話し合っておくことで、実際に介護に直面した場合にスムーズに介護生活を始めることができます。
こうした話し合いは家族同士がギクシャクしていたのでは行えません。介護に備えるには、介護をする側と介護を受ける側との関係づくりにしっかりと取り組む必要があるでしょう。
要望を知る
認知症が重度化するなどして心身状態が悪化すると、自分で適切な判断を行うことが難しくなり、家族介護者が本人に代わって意思決定を行うケースがどうしても増えてきます。
その際、要介護者の意思にそぐわないような決定・判断を行うことがないように、どんな老後を送りたいのか、終末期をどのように過ごしたいのかなどを、本人が元気なうちに確認しておくことが大事です。こうした準備は、高齢者の権利を守ることにもつながります。
また、元気なうちにエンディングノートなどを執筆しておき、事前に自分の意思を明確にしておくこともおすすめの方法です。
希望条件に合う老人ホームを探す健康状態を把握する
高齢者が若い頃に経験した病気や怪我、あるいはアレルギーなどについては、家族であっても把握していないことが少なくありません。何より、ご本人が忘れていたり、気づいていなかったりすることもあります。
そのため、介護への備えとして、本人の過去の病歴やアレルギーの有無などを調べ、チェックしておくと、介護生活を始める上での手助けとなるでしょう。
また、親族の中に短命の人やがんで亡くなった人がいないか、脳卒中や心臓病などにより倒れた人がいないかも確かめておくと、将来の病状・体調確認のうえで助けとなります。
さらに実際に介護を行うにあたって、触れられたくない体の部位やできない体の動作なども、本人に確かめておきましょう。
経済状況を把握する
介護生活には介護サービスの費用や老人ホームへの入居費用など、多数の支出が発生します。こうした費用は、基本的には要介護者ご本人の年金、貯蓄でまかなうものであると考えておきましょう。
その際に必要となるのが、家族介護者が要介護者のお金を使えるようにする体制です。
特に親子の場合、お金のことを親に聞くのは気が引けるかもしれません。しかし、実際に介護をするにあたっては、年金額や預貯金額、借金の有無、加入済みの保険の種類などは把握しておきたいところです。
さらに合わせて、介護保険証、銀行の通帳・印鑑、生命保険証などの保管場所も本人に確かめておく必要があります。
日常会話の中で介護の話題になったときなどに、こうした話を切り出してみると良いでしょう。
生活リズムを把握する
高齢者には長年続けている日常生活のパターンがあることが多いです。
介護を行う場合、本人の起床時間や就寝時間、食事時間や家事、散歩などを把握し、介護を必要としても本人の生活リズムを大切にした介助を行っていきましょう。
また、日々の生活を送る中で困っていることや不安に感じていることがないかを確認することも大事です。介護者として、生活のどの場面で支援が必要なのかを把握することにもつながります。
さらに趣味についても確認しておくと、レクリエーションやイベントに参加する際の参考となるでしょう。
人間関係を把握する
近所の誰と仲が良いのか、参加している地域の集まりは何か、親戚づきあいはどうなっているのかなど、本人の人間関係についても事前に確認しておきましょう。
こうした方々は、介護生活を送る上で問題が起こった際に協力者・相談者となってくれる可能性があります。介護者としても、関係を大切に維持するよう努めることが大事です。
特に協力してくれる方が近所に住んでいる場合、関係をしっかりと作り上げれば、お願いして本人の様子をときどき見に行ってもらえるかもしれません。
帰省した際に挨拶をするなどして、関係を深めておくのも一つの方法です。
介護サービスの種類
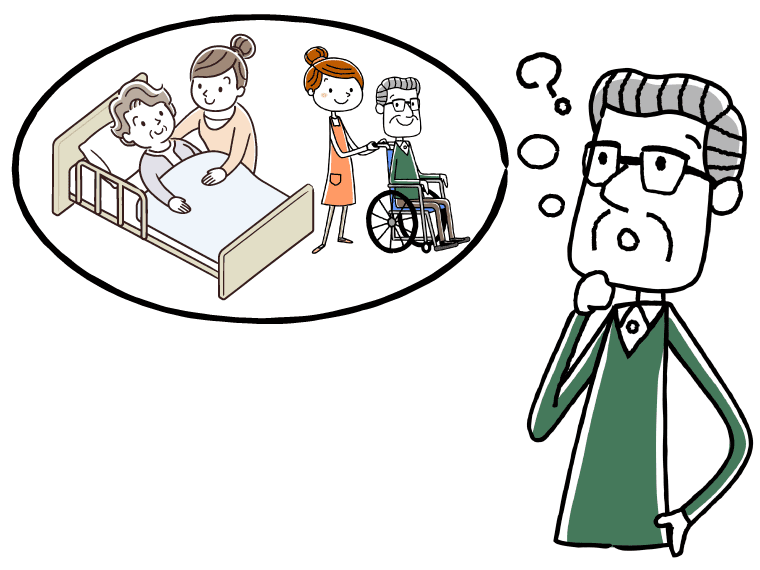
介護を行う際、社会の中にある様々なサービスを利用することが欠かせません。各種高齢者支援サービスや行政サービスなどをうまく組み合わせることで、家族の介護負担を減らせます。
こちらでは、介護保険サービスと介護保険外サービスのそれぞれについて、詳しくご紹介しましょう。
介護保険サービス
施設に入居して利用する介護保険サービスは、さらに以下の3種類に分けることができます。
- 介護保険施設で利用するタイプ
- 地域密着型で利用するタイプ
- 特定施設で利用するタイプ
介護保険施設とは公的な介護施設として利用できる老人ホームを指し、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などのことです。地域密着型サービスにはグループホームなど、特定施設には介護付き有料老人ホームが含まれます。
在宅介護の場で利用するサービスは、訪問介護や訪問入浴介護など自宅で利用するタイプ、デイサービスのような通いで利用するタイプ、ショートステイなど泊まりで利用するタイプがあります。
訪問・通い・泊まりを組み合わせた小規模多機能型居宅介護や複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)などのサービスもあります。
福祉用具の補助金制度
自宅で介護生活を送る場合、介護ベッドや車いす、手すり、スロープなどの福祉用具の利用が欠かせません。こうした福祉用具は高額ですが、介護保険制度を利用すれば保険適用でレンタルできます。
対象となるのは介護ベッドをはじめとする合計13品目。ただし、品目によって対象となる要介護状態の区分が異なるので注意しましょう。
また、ポータブルトイレや入浴補助装置などレンタルに適さない所定の福祉用具は、介護保険適用で購入できます。
サービスを利用するための準備
介護保険適用でサービスを利用するには、お住まいの市町村区役所の介護保険担当窓口にて「要介護認定」の申請を行うことが必要です。申請を行うと、30日以内に介護認定の結果が通知されます。
結果が出たら、まずは介護保険サービスの利用計画書である「ケアプラン」の作成を行いましょう。要支援1~2の場合は最寄りの地域包括支援センターで作成し、要介護1~5の場合は役所で紹介される居宅介護支援事業所を選び、そこに所属するケアマネージャーと相談して作成します。
準備しておきたい福祉用具
介護に備えて、福祉用具をあらかじめ用意しておくことも大事です。
介護保険制度の「福祉用具貸与」や「特定福祉用具販売」のサービスを利用することで、福祉用具を保険適用でレンタル・購入できます。
しかし、すべての福祉用具が介護保険適用となるわけではありません。保険適用されないものについては、早めに自費で準備しておくことも必要です。
福祉用具
「福祉用具貸与」と「特定福祉用具販売」のサービスは介護保険サービスの一種であるため、利用する場合はケアプランの中に盛り込む必要があります。
そのため、介護用品を介護保険適用でレンタル・購入したいときは、担当のケアマネージャーにまずは相談しましょう。
ケアプランを作成したら、福祉用具のレンタル事業者を選びます。その後、福祉用具専門相談員が利用者の自宅を訪問し、福祉用具を提案してくれますので、アドバイスを受けながらレンタル・購入をしましょう。
納品の際は、使いやすくするために専門相談員が介護用品の調整を行ってくれます。
ICT機器や緊急通報システムの活用
近年、家電や照明器具など日々必ず使用する家庭用品に、見守りを行える通信機器が付いているものが登場しています。一定時間使用しないままでいると家族に通知されるというシステムで、監視カメラとは異なり、プライバシーを保護できる点が大きなメリットです。
こうしたICT機器をうまく活用することは、特に遠距離介護を行う上では重要になってくるでしょう。
また、自治体の中には高齢者宅に緊急通報システムを設置するサービスを行っているところもあります。
自宅で体調が急に悪化したときなどに、緊急通報ボタンを押すことで担当のオペレーターにつながり、すぐにスタッフが駆けつけてくれるというサービスです。
お住まいの自治体でどのようなサービスが行われているのか、市町村区役所の窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。
介護保険外サービス
介護保険サービスのほかにも、以下のようなサービスがあります。
自治体が独自に提供するサービス
自治体が独自に提供するサービスの代表例といえるのが、紙おむつの助成です。
要介護度の重い方では紙おむつを利用する必要も生じますが、毎日使用すると月あたりの費用が数万円かかります。このうちの何割かを、自治体側が助成してくれます。
お住まいの自治体がどのようなサービスを行っているかホームページなどで確かめると良いでしょう。
介護リフォーム
自宅に手すりやスロープを取り付けるなどのバリアフリー改修を行う場合、自治体によっては助成金を出しているところがあります。
通常、各市区町村役場の高齢者福祉担当が相談に応じてくれるので、実際に改修を検討するならばぜひ利用しましょう。助成対象となる改修工事や助成金の金額などについて教えてくれます。
なお、自宅のバリアフリー改修については介護保険サービスの利用も可能です。要介護認定を受けている方が、申請すれば住宅の改修にかかる費用が最大20万円まで、1割(所得によって2~3割)の自己負担で利用できます。
民間が提供するサービス
一般企業が提供する民間サービスとしては、配食サービスや見守りサービスなどがあります。
地域内にある民間サービスについては最寄りの地域包括支援センターで情報収集が可能です。
交通費の割引制度
遠距離介護をする場合、ぜひ利用したいのが交通費の割引制度です。
多くの航空会社は介護を理由とした帰省客に対して割引制度を設けています。支給条件などについては各航空会社に問い合わせてみてください。各社のホームページでも確認できます。
また、格安の航空券を購入するのもおすすめ。航空会社ごとに料金は大きく異なるので、できるだけお金のかからない会社を選ぶと交通費を節約できます。
電車・新幹線で規制する場合、JRでは年齢に基づく割引制度などもあるので、ぜひ活用しましょう。往復割引を受けられるように乗車券を購入するのもおすすめです。
地域のボランティア団体などが提供するサービス
地域のボランティア団体のなかには、高齢者向けの付き添いや安否確認などのサービスを行っていることもあります。
積極的に利用すれば家族介護者の負担を減らせるでしょう。
介護で必要となる費用
介護費用は要介護度によって変わり、要介護度が上がるにつれて必要な費用も高くなってきます。要介護度が上昇すると自立して行えることが減り、その分介護サービスを利用する機会が増えるからです。
家計経済研究所の調査(2019年)によれば、日本の介護費用の平均は以下のようになっています。
| 要介護1 | 月3.3万円 |
|---|---|
| 要介護2 | 月4.4万円 |
| 要介護3 | 月5.9万円 |
| 要介護4 | 月5.9万円 |
| 要介護5 | 月7.5万円 |
要介護5の場合、介護費用は要介護1の2倍以上です。
なお、介護費用は認知症の有無や程度によっても変わり、例えば要介護4~5で認知症が重度である場合、平均で13万円程度の費用がかかります。
介護生活はいつまで続くかわからないため、経済的に余裕をもって対応できるように、事前に準備金を蓄えておくことも大切です。
お住まいの地域の施設相場を見る介護費用の捻出と資産管理
介護費用は要介護者ご本人の年金や退職金、預貯金、資産などから支払われるのが一般的です。
しかし要介護者が認知症を発症すると資産管理を自分で行えなくなることもあります。資産の一覧や通帳と印鑑の場所、各種証書類やカード類は整理し、可能なら事前に家族もその情報を知っておくことが望ましいです。
もし要介護者ご本人の収入や貯蓄、資産などで介護費用をまかなえない場合は、ほかの方法を考える必要があります。
例えば、ご本人が介護費用を捻出するために早めに個人年金に加入する、金融商品の運用を始めておくといった対策を取っておくことも有効な方法です。
もしご本人が不動産を保有しているなら、マイホーム借り上げ制度やリバースモーゲージなどに活用することもできます。
介護サービスの計画を練る

地域包括支援センターに訪問する
介護が必要となった場合、まずは地域包括支援センターに相談しましょう。全国に5,000カ所以上あり、市区町村区役所に併設されている場合もあります。
地域包括支援センターの役割を一言でいうと、「高齢者のよろず相談所」です。
介護に関するあらゆる悩み・相談を受け付けているので、積極的に利用することが介護負担の軽減化につながります。センターの中には保健師、ケアマネージャー、社会福祉士といった高齢者福祉の専門家が常駐しているので、問題解決力が高いです。
ケアプランを作成する
介護サービスを利用するために、ケアプランの作成も必要です。
ケアプランとは介護サービスの利用計画書のことで、本人の心身状態や家族の意向を踏まえてケアマネージャーが作ります。ケアプランを作ることで、介護の計画や費用をはっきりさせることが可能です。
ケアプランの作成には要介護認定を受けていることが必要で、要支援1・2の認定を受けている場合は地域包括支援センターにいるケアマネージャーがつくります。
要介護1~5の認定を受けているときは、居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーへの相談が必要です。居宅介護支援事業所は市区町村役場で紹介してもらえます。
介護に適した環境の整備

勤務先の介護休暇を確認する
「介護休暇」と「介護休業」は職場で使える介護支援制度です。
介護休暇制度は、要介護状態となった家族の介護を目的として短期的な休みを取れる制度で、育児・介護休業法にて規定されています。従業員から介護休暇の申し出があった場合、企業側は業務の忙しさなどを理由としてこれを拒むことはできません。
一方、介護休業は家族介護のために長期的に休みを取れる制度で、育児・介護休業法にて規定されています。介護休暇と同じく、申し出があれば企業側が拒むことはできません。
介護休業制度を利用できるのは、雇用形態に関係なく1年以上雇用されている従業員です。また、介護休業予定日から計算して93日を過ぎた後、6カ月以内に労働契約期間が終了することが明らかではないことも条件となっています。
緊急時のサポート体制を決める
介護生活の中では、急な体調変化など予期せぬ事態も起こります。そうした緊急時を想定して対策を考えておくことも大事です。
例えば、体調・持病が悪化した場合は本人を病院に連れていく必要が生じます。体の変化は休日や夜間に関係なく生じるため、緊急時に備えて近隣の病院が休日・夜間対応を行っているかどうかを確認しておきましょう。
介護を無理に一人で抱えると、精神的にも追い詰められます。また、介護者の側が風邪を引いたりして、思うように介護できない日もあるでしょう。
そうした場合、自分の代わりに介護に協力してくれる人がいれば大きな助けとなります。もし協力してくれる人がいない場合は、ケアマネージャーに相談して、ショートステイを利用するなどして介護する側が心身を休める方法を考えましょう。
施設入居を検討する
「在宅介護が希望だが介護ケアに時間を割ける家族がいない」「しばらく在宅介護を受けてきたものの、これ以上家族に負担をかけたくない」こうした事情から、施設介護を検討するケースが増えています。
介護が必要になる前から、在宅介護と合わせて施設介護も検討しておくと良いでしょう。
施設介護では、施設ごとに入居条件や提供する介護サービス、費用面に違いがあります。具体的に一つずつ解説していきましょう。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、幅広い本格的な介護サービスを提供している民間の介護施設のひとつです。
比較的要介護度の高い方や認知症の方が入居条件となっています。
看護職員による服薬管理や褥瘡のケアなど、医療的ケアが受けられるため、日常的に医療的管理が必要な人も安心して入居できます。
入居一時金の相場は0円~580万円、月額利用料の相場は15.7万円~28.6万円。月額利用料は定額のため、金銭面の見通しが立てやすいです。
【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)
介護付き有料老人ホームを探す住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは要介護1~2の方を中心に、幅広い身体状態の方に対応しています。
介護サービスは従量課金となっていて、自分の必要に応じて選択できます。
また、イベントやレクリエーションが充実しているのも住宅型有料老人ホームの特色です。
民間施設のため、豪華な設備やサービスが整っているところも多く、一般的な老人ホームのイメージに近い介護施設です。
入居一時金は0円~21万円、月額利用料は9.6万円~16.3万円が相場となっています。
【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説
住宅型有料老人ホームを探すサービス付き高齢者向け住宅
一般的に「サ高住」と呼ばれている、高齢者対象の賃貸マンションです。
サービス付き高齢者住宅は、一人暮らしに不安のある自立状態の人、要支援や要介護度の低い方が対象です。
そのため、生活相談サービスや安否確認を提供しています。さらに、外出や外泊も基本的に自由なので、自由度の高い暮らしが可能です。
入居一時金の相場は0円~20.4万円、月額利用料の相場は11.8万円~19.5万円です。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)
サービス付き高齢者向け住宅を探すグループホーム
認知症の方が専門の介護施設のため、入居者同士気兼ねなく暮らせます。
施設の所在地に住民票のあることが入居条件です。
グループホームでは、入居者で家事を分担しながら生活リハビリを通して認知症の進行緩和を目指します。
入居一時金は0円~15.8万円、月額利用料は10万円~14.3万円が目安です。
【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説
グループホームを探す
今から実践できる介護予防
介護への対策として最も望ましいのは、そもそも要介護状態にならないことです。
高齢になってくると、病気ではなくても心身機能の低下は避けられません。体を動かさなくなると、筋力が急速に低下してあっという間に要介護状態になる可能性もあります。
要介護状態を避けるには、まずは日常的に体を動かして、筋力の低下を防ぐことが大事です。散歩に出かけることや、家の中でストレッチや筋力トレーニングを行うことが健康を保つことにつながります。
運動は自分のペースを守ることを心がけ、週2~3回程度、1日おきに軽く体を動かすことから始めてはいかがでしょうか。
他の人はこちらも質問
介護が必要になった場合どうするべきか?
介護が必要となった場合の準備の流れは以下の通りです。
- 地域包括ケアセンターに相談する
- 要介護度認定を受ける
- ケアプランを作成する
- 介護サービスの種類を知る
- 必要な福祉用具をレンタルする
介護は何から始める?
介護が必要になった場合は、まずは地域包括支援センターに相談しましょう。
センターにはケアマネージャーなど高齢者福祉専門家が常駐しており、介護の流れや悩みに関しての相談にのってくれます。
在宅介護には何が必要?
在宅介護では、介護保険適用でサービスを利用するため、要介護認定を必ず受けましょう。申請はお住まいの市町村区役所の介護保険担当窓口にて行います。
また、結果が出たら介護保険サービスの利用計画書であるケアプランを作成しましょう。
介護用品は何が必要?
代表的な介護用品は以下になります。
- 介護ベット
- 床ずれ防止用具
- 歩行器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
- 入浴補助用具



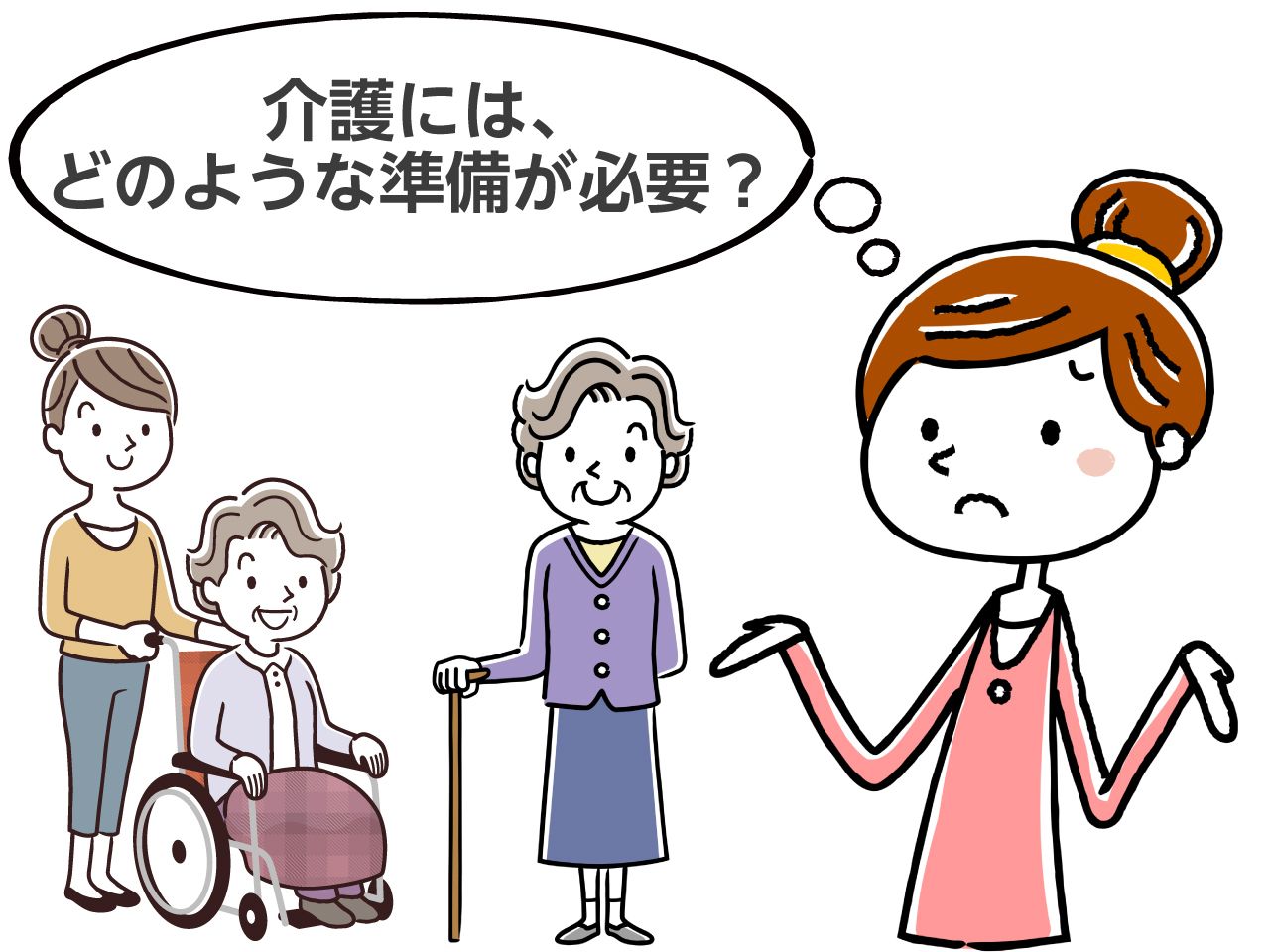


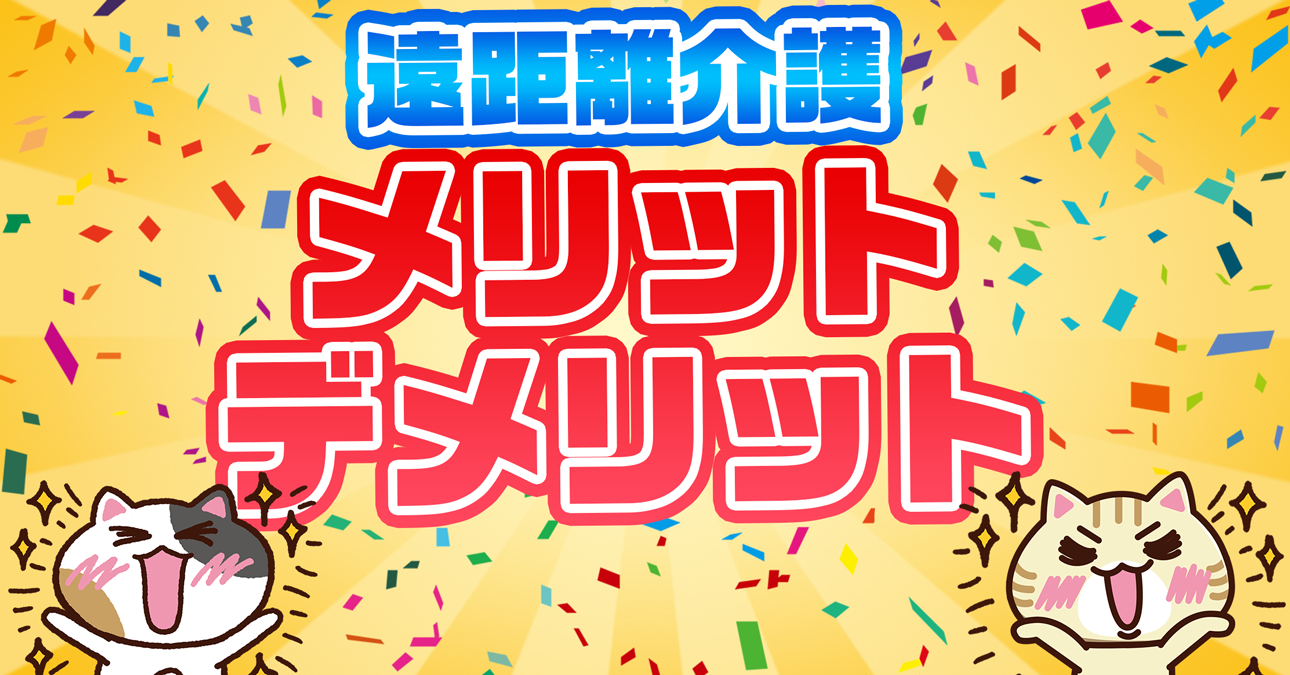


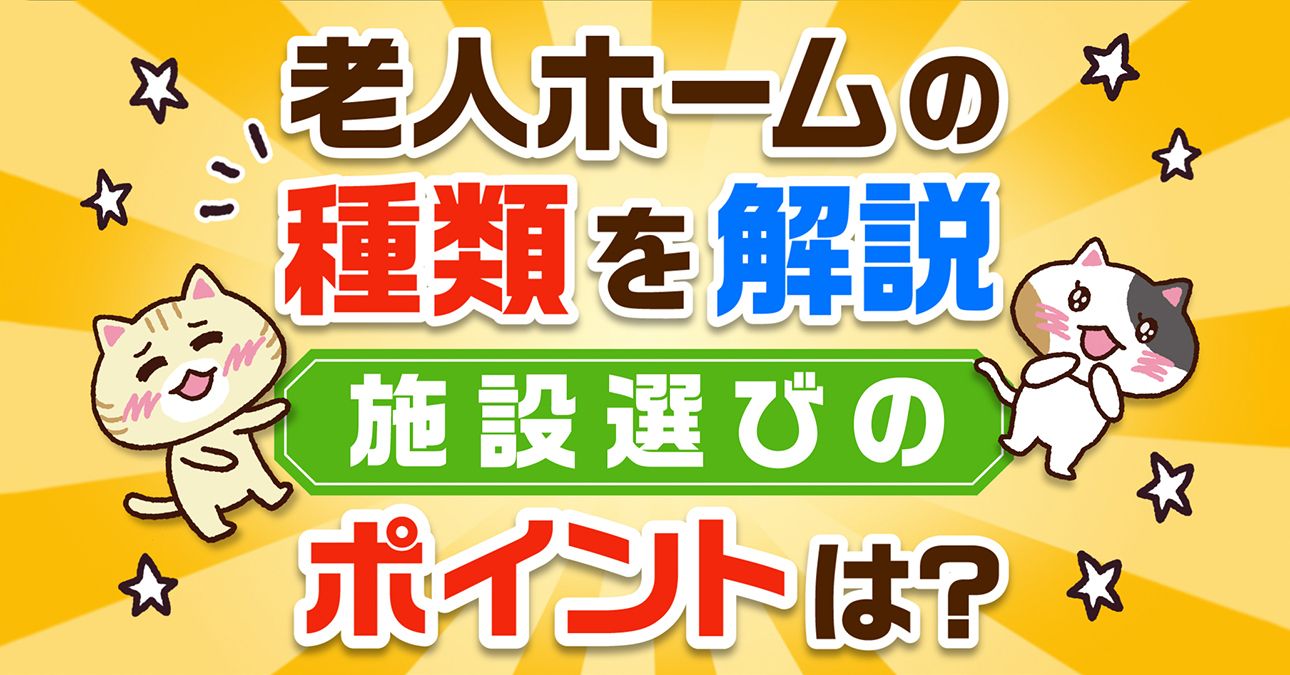




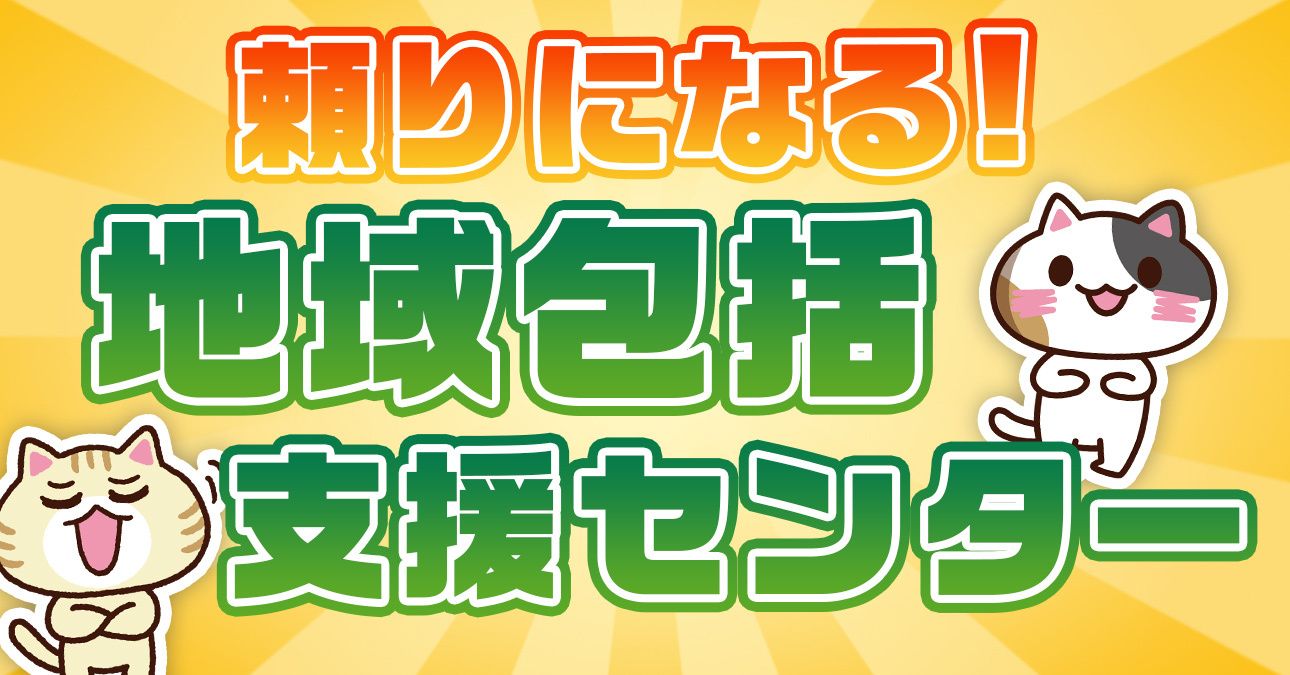

 この記事の
この記事の



