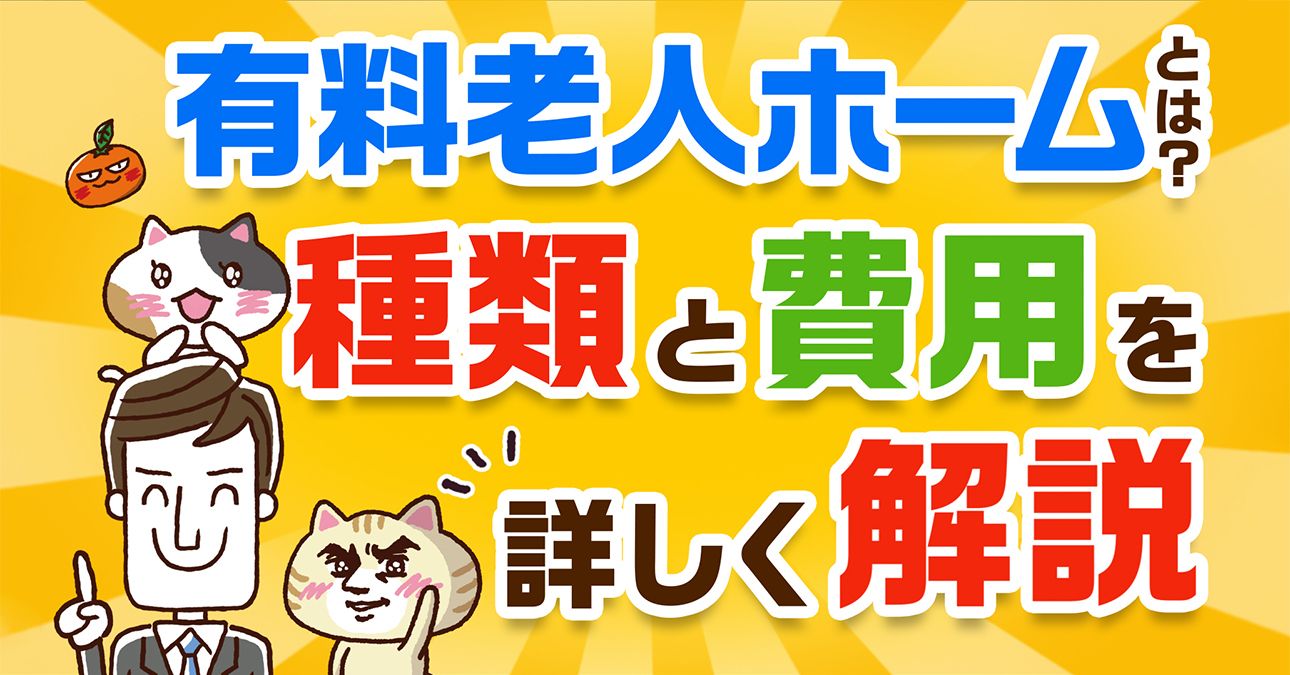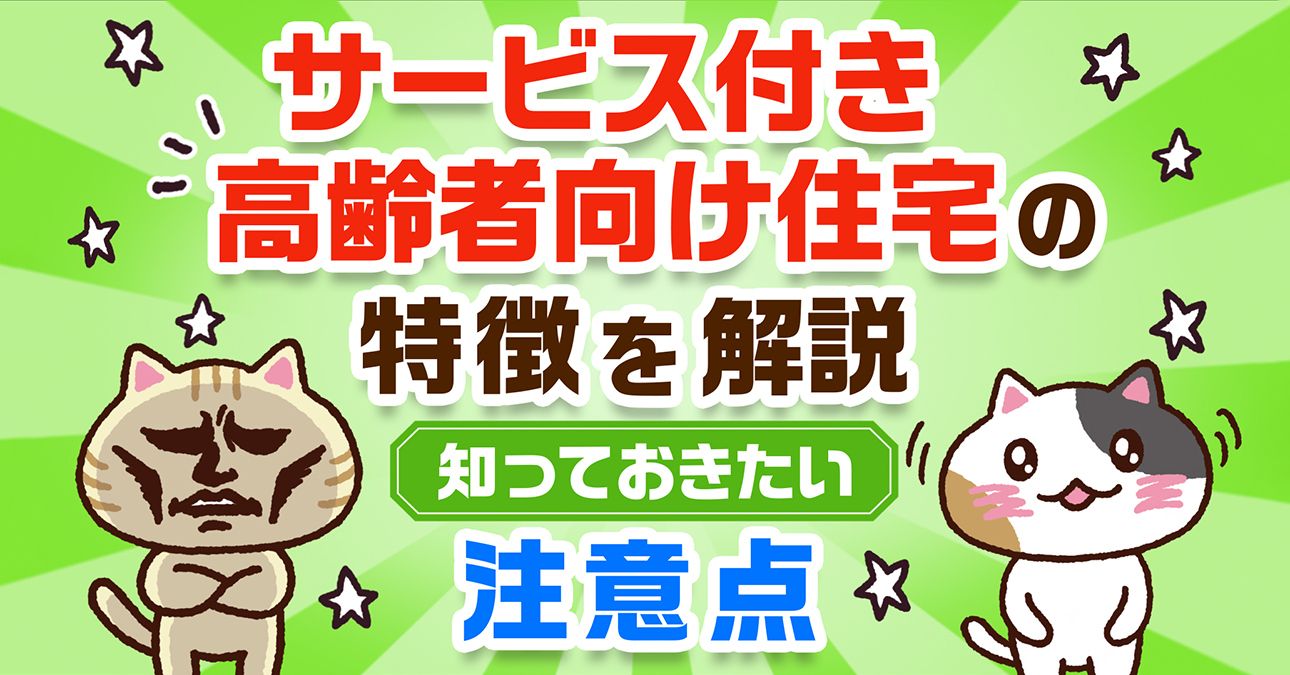介護のための部屋づくり4つのポイント
要介護状態になった高齢者の居住環境をどのように整備するかで、その後の在宅介護生活のクオリティは大きく左右されます。
親が急に倒れて在宅介護に直面した場合、介護する環境を整えるための準備期間が十分に取れないことがよくあります。
介護するための部屋作りを最低限押さえておくために、「介護ベッドの配置」「部屋の広さ」「部屋のデザイン」「部屋の選び方」の4つのポイントを見ていきましょう。
レイアウトや広さが重要な理由
介護が必要になった高齢者は身体的な問題を抱えている場合が多いため、これまでと同じレイアウトでは動きづらかったり、怪我をしたりなどの不具合が生じることがあります。
そのため、レイアウトや広さについて配慮する必要があるのです。
動線を確保し怪我を防止するため
高齢になると足腰が弱り、転倒や怪我をする危険性が高くなります。
そのため、ベッドやトイレなど、よく利用する場所の動線がしっかり確保できているかよく確認しましょう。
また、車椅子生活になった場合、スムーズに移動できる広さを確保することも大切です。
問題なく移動できるスペースがあるか確認しましょう。
精神的・肉体的な疲労を防止するため
部屋の広さは、広すぎても狭すぎてもデメリットがあります。
狭すぎた場合、閉じ込められたような窮屈な印象があり、精神的な疲労を感じやすくなります。
一方、広すぎた場合、足腰が弱ると目的地に着くまでに疲れてしまうことが考えられます。
また、高齢になると加齢や病気によって頻尿になる可能性が高くなるため、特にトイレとの距離は重要です。
トイレは近い場所、もしくは居室内にあることが望ましいでしょう。
一方、歩ける場合には少し離れている方が良い運動になる場合もあるので、必ずしもすべて近くにあるのが良い訳ではないことも理解しておきましょう。
1.介護ベッドはどこに置くべき?
部屋のどこに介護ベッドを配置するかは、レイアウトの要といえます。
介護ベッドの場所は、要介護者本人がリクライニングで上半身を起こしたときに、窓の外を見やすい位置に置くのが望ましいです。
ベッドに横になりながらでも外の景色を見られる、テレビが見やすいなどの位置に配慮して位置を決めるようにしましょう。
半身マヒのある方の場合、マヒ側(患側)が壁になるようにベッドを配置します。
ベッドから足を下ろす側が健康な側(健側)であれば、ベッド脇にある柵につかまりながら自分で起き上がることができます。
また、ベッドのシーツを交換する際に、壁との距離が近いと作業がしにくいため、壁とベッドには十分なスペースを開けておきましょう。
2.部屋の広さはどのくらい?
在宅介護を行う部屋は安全面と健康面を踏まえ、介護ベッドを置く場所以外のスペースを十分に確保する必要があります。
また家具の数と大きさも影響します。要介護者が歩いて移動できる場合は最低でも6畳、車いすを利用されるなら最低でも8畳の部屋を用意したいところです。
3.部屋のデザインはどうしたら良い?
要介護者および介護者の方が長時間過ごす場所となるため、快適に生活できるように部屋内の空間デザインを整えることは大切です。
例えば、ベッドがある部屋の壁や天井、床の色合いは、心身を安静に保てるように落ち着いた色合いでまとめておくと良いでしょう。
心地よく生活を続けられるように、おしゃれさも意識して室内の装飾を整えます。本人が好きな写真やポスターを貼るのも良いでしょう。
部屋のタイプは、和室よりも洋室が適しています。畳敷きの和室の場合、部屋の出入りの際にスリッパ等の着脱が必要となり、台所などと行き来する際に不便です。敷居があるので、つまづいて転倒する危険もあります。
洋室であれば履物のままで部屋を出入りできます。床張りなので、車椅子のタイヤが沈まないので操作がしやすいです。
室内の照明は他の部屋の1.5倍程度の明るさを確保するのが理想です。ただし、天井にあるメイン照明が明るすぎるとまぶしくなってしまいます。
メイン照明だけでなくフロアスタンドや間接照明などを併用することで、光を分散させつつ室内の明るさを確保しましょう。
4.どの部屋を寝室にしたら良い?
自宅で介護を行う場合、複数ある部屋の中から寝室を選ぶ必要があります。以下のポイントを踏まえて、寝室にする部屋を選びましょう。
- 部屋とトイレの距離
- トイレから近い部屋を選ぶ。離れた場所だと歩行介助が大変になることに加え、トイレまで間に合わないと失禁も起こり得る。
- 陽当たりや景色
- 気分転換がしやすいように、窓から外の景色がよく見え、陽当たりも十分な部屋が良い。
- 換気のしやすさ
- 換気のしやすい部屋を選ぶ。もし、間取りの関係で空気の流れが悪い場合は、部屋のドアを少し開ける、ウインドファンや扇風機、エアコンを使用する。
- 部屋の階数
- 転倒や転落のリスクを避けるために、階段を使わなくて済むように、1階にある部屋を選ぶ。またトイレや台所も併せて1階にあれば、食事や排せつの介助を行いやすい。
備えておきたい設備

要介護者の方が過ごす寝室に必要な設備についてご紹介しましょう。
必要な設備では、介護用ベッドは欠かせません。介護ベッドの選び方や使い方、ベッドの周辺機器などについては以下で詳しく解説します。
また、介護ベッド以外にもあると便利なものも併せてご紹介します。
介護用ベッド
要介護者の方が使うベッドは、通常のベッドではなく介護用ベッドを選びましょう。
介護用ベッドを使用すれば、要介護者の方がリクライニング機能で起き上がりが容易になり、ベッド柵を使って体勢を変えたり、立ち上がりすることが容易になります。完全に横になったままの寝たきり状態を防ぐことができます。
また、介護する側にとっては、介護用ベッドなら角度や高さを調節することができ、介護をする際の負担(例:食事介助)を減らすことができます。
ベッドの選び方・使い方
介護用ベッドは、ベッドの高さがどのくらいなのかに注目しましょう。最適な高さの目安は、本人が腰かけたときに無理のない足の角度になっているかどうか、足を床にしっかりと付けるかどうかがポイントです。
介護用ベッドには高さを調節できる機能(2モーター付き、3モーター付きが理想)が付いているので、調整して最適の高さになれば問題ありません。調整しても腰かけたときに足が床に届かないなどの場合は、別のベッドを選ぶ必要があります。
導入にあたって、福祉用具専門相談員などにアドバイスをもらうと良いでしょう。
また、介護用ベッドを使用する際、ベッドに置くのは布団よりも、通気性がよく清潔を保ちやすいマットレスが望ましいです。マットレスは体の沈み込みがあまりなく、介護ベッドのリクライニング機能を使った起き上がりやすいやや硬めのものを選ぶようにしましょう。
設置は半身マヒの方が介護用ベッドを使う場合、マヒのある側(患側)を壁側にして、健康な側(健側)から降りられるようにします。あと、使用する際は、介護ベッドの柵や手すりの間に首や手などが挟まれてしまう「隙間事故」に注意が必要です。
ベッドの周辺機器
介護ベッドを使用する際は、周辺機器も吟味して選ぶことが大事です。特にベッドの両サイドのフレームに柵(サイドレール)を設置する場合は、身体状態に合ったものを選ぶ必要があります。
例えば、手足に不随意運動(自分の意思とは無関係に勝手に手足が動く現象のこと)が見られる場合、サイドレールに大きな隙間があると、そこに首や体が入り込んでしまう隙間事故が起こる恐れがあります。この場合、安全性を確保するために、隙間のない板状のレールを選ばなければなりません。
また、介護用ベッドにはリクライニング機能や脚上げ機能、高さ調節機能などがありますが、これらの操作を要介護となった本人が寝たままでも行えると便利なので、手元スイッチを用意しましょう。
ベッドと合わせて揃えたい3つの設備
介護用ベッド以外にも、寝室にあると便利なものはたくさんあります。例えば、以下の3つが挙げられます。
- サイドテーブル
- 介護ベッドのリクライニング機能を使って上半身を起こしたときに使えるテーブルのことです。使用することで、ベッド上で食事を摂ったり、おやつを食べたりできます。本を読んだり、スマホやタブレットの操作もできます。
- キャスター
- 家具に取り付ける車輪のこと。介護用ベッドに取り付けると、要介護者がベッド上で横になっている状態でも、ベッドを簡単に動かすことができます。ただし、普段生活している間は、ベッドが動かないようにしっかりと固定しておきましょう。
- 移動用バー
- 介護ベッドのサイドフレームに取り付け可能な手すりのことです。介護ベッドから立ち上がるとき、車いすに移乗するときなどに、体を支えることができます。
介護リフォームを検討
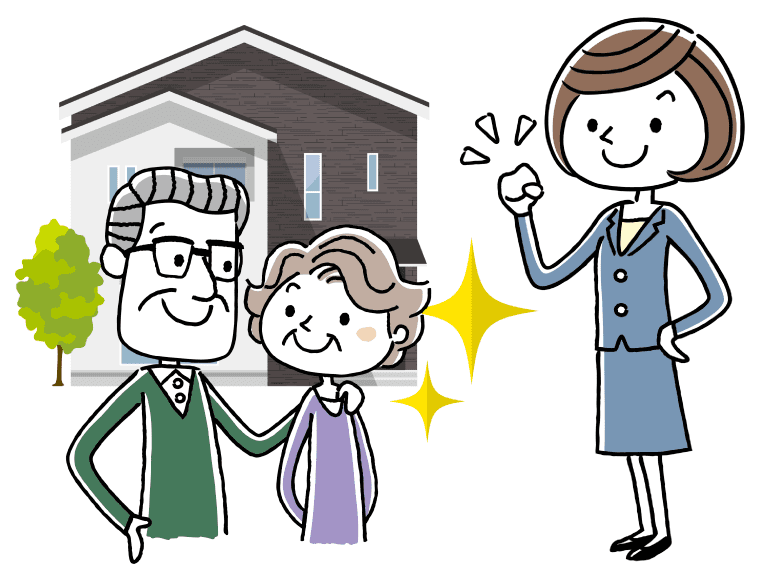
築年数が古い民家の場合、屋内に段差が多数あり、要介護状態の方が移動すると転倒のリスクが高いです。また、トイレや風呂場も、現状のままでは使いづらく、安全に使用できないことが考えられます。
その場合、要介護の方の事故防止のためにバリアフリー改修をするのが望ましいです。適切な介護リフォームを行って、転倒などの危険を防ぎましょう。
リフォーム前にチェックしたい場所
在宅介護をする場合、自宅にある「階段・廊下」「トイレ」「風呂場」「玄関」が、要介護者の方でも安全に使えるかどうかを事前にチェックしましょう。
チェックの結果、安全性に問題があると判断されたら、在宅介護が始まる前に介護リフォームを行っておくと良いでしょう。また介護が始まっていても、実際に動作を行ってもらい、危険な場所をチェックして介護リフォームするのでも構わないでしょう。
階段・廊下
階段・廊下のチェックポイントは、移動時に「手すりなどつかまるところがあるか」「階段の角度と段差はゆるやかか」「床材が滑りやすいかどうか」などが挙げられます。
階段や廊下に手すりが無い場合は、使う人の体型と身体動作に合わせた位置をアセスメントし、取り付け工事を行いましょう。階段に設置する場合は、廊下部分から繋げて取り付けることで、衣服のひっかかりによる転倒予防になります。
階段の段差が急な場合は、一段ごとの段差を緩やかにする工事を行います。また、階段・廊下の床材が滑りやすい場合は、カーペットなど滑りにくい床材への張り替え工事や踏みはずしを予防するための滑り止めマットの設置が必要です。
トイレ
トイレのチェックポイントは、「出入りがしやすいか」「トイレの中で動きやすいか」「立ち座りがしやすいか」「用を足しやすいか」「スリッパの着脱が必要か」などが挙げられます。
トイレの出入りのしやすさは、ドアの開閉のしやすさ、廊下との段差の有無によって決まります。ドアが開き戸だと開閉しにくいため、スライド式の引き戸へと改修するのが望ましいです。また、車いすでの利用や介助者の排泄介助を考えると、出入口の幅が狭い場合は「広くする工事を行う」「ドアをカーテンにする」などの方法があります。
トイレ内の動きやすさは、トイレの中に入ってから便座に座る・立つ動作がスムーズに行えるかどうかがポイントになります。手すりがあると動きやすいので、身体動作をアセスメントして設置します。使いにくい便座の向きの場合は、使いやすいように方向を変える改修を行いましょう。車いすや介助者が必要な場合は、十分なスペースを確保することも大切です。
用の足しやすさでは、和式ではなく洋式便座であること、トイレットペーパーのホルダーが使いやすい場所にあること、水洗の操作レバーや手洗いがしやすいこと、などがポイントです。
トイレでスリッパの着脱が必要だと足を取られて転倒する危険もあるため、着脱不要で移動できるように改修します。トイレ内の床材は、滑りにくく、裸足でも冷たくないものを選びましょう。冬場は温風ヒーターを設置することも検討しましょう。
浴室
浴室のチェックポイントは、「浴室への出入りのしやすさ」「洗い場の滑りにくさ」「浴槽への出入りのしやすさ」が挙げられます。
浴室への出入りのしやすさは、脱衣所との間に段差があるかどうかが大きなポイントです。特に浴室から出るときは体が濡れてすべりやすい重い状態なので、数センチの段差でもつまづき転倒のリスクが高まります。段差があるなら、バリアフリーのリフォームを行いましょう。
入浴中、浴室内は濡れているため、洗い場は滑りやすく転倒して大けがをする恐れがあります。濡れても滑らない床材にすることで、要介護者本人はもちろん、介護する側の安全性も確保できます。また、出入口のドアが開き戸ならば、安全に開閉ができるスライド式引き戸へと改修します。
浴槽への出入りのしやすさは、浴槽の高さと大きく関係します。高すぎるとまたぐときにバランスを崩しやすく、転倒の危険性があります。浴槽が高い場合は低めになる改修をすることで、要介護者の方が出入りしやすくなり、介護者も介助しやすくなります。
玄関
玄関のチェックポイントは、「出入りのしやすさ」「靴の着脱を座って行えるか」「つかまれる場所があるか」「車いすで移動できるか」「雨の日でも滑らないか」が挙げられます。
玄関の出入りのしやすさは、段差の有無がポイント。日本の民家には玄関部分に「三和土(たたき)」や「上がり框」などがあります。これらは大きな段差であり、要介護者の方にとっては転倒の原因となりやすいので、段差解消のリフォームをする、ハーフステップの台を設置するなどを検討します。また、玄関ドアが開き戸の場合は、開閉がしやすいスライド式引き戸への変更も検討してみましょう。
靴の着脱は立ったままで行うとよろけやすく、転倒する恐れがあります。座れる椅子などを設置しておくと安全に着脱できます。
また、一戸建ての場合では門から玄関までのアプローチ、玄関の中、玄関から居室までの廊下に距離があるので、手すりを設置しておくと安全性が高まります。
要介護者の方が車いすを利用している場合は、車いすが通れるだけの玄関ドアの幅を確保し、段差を解消するためのリフォームが必要です。
二世帯住宅のリフォーム
子ども家族と同居している場合は、二世帯住宅であることを踏まえた介護リフォームを行うのも一つの方法です。
大きな一戸建てであれば、親世帯と子世帯を切り離す「分離スタイル」をとることもできます。親用のスペースでは高齢者が生活しやすい設計で、要介護者の夫または妻とその配偶者が生活し、子供家族用のスペースでは若者向けの現代的な住まいに設計します。
実際に二世帯住宅としてリフォームする場合は、水道やトイレなどの水回り関係をどうするか、世帯間の距離感をどうするかを事前に決めておくことが大事です。世帯間の関係性・干渉度合いによって、完全分離型なのかそれとも共有スペースを多く設けるのかが変わってきます。
費用を抑える2つの補助金
通常のリフォームとは異なり、在宅介護を目的としたバリアフリー改修には補助金が支給されます。
補助金には大きく介護保険から支給される住宅改修費、市町村助成金により支給される住宅改修費の2種類があります。うまく活用することで改修時の金銭的負担を軽減できます。
介護保険
「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費」の制度があり、利用することで自宅の介護リフォームに対して保険適用が可能です。
支給対象となるのは住宅改修にかかる費用のうち最大20万円までで、そのうち1~3割(所得によって異なる)が自己負担額とされます。例えば、20万円の介護リフォームを行った場合、1割負担であれば自己負担額は2万円で、残りの18万円が保険適用とされるわけです。
20万円を超える工事を行った場合は、自己負担額の2万円に加えて、超えた分の全額が自己負担となるので注意しましょう。上限の20万円は数回に分けての申請もできます。
市町村区の助成金
介護保険だけでなく、各自治体も住宅改修費制度などを実施しているので、利用することで改修費に対して助成金が支給され、費用負担を抑えることができます。
ただし、助成金の支給額と支給の方法、支給対象となる条件は自治体によって異なるので注意が必要です。介護保険による住宅改修費の給付を受けている場合は対象から外れるというケースもあります。
住んでいる自治体でどのような助成制度が行われているのか、市町村区役所の介護保険課の窓口やホームページでチェックしておきましょう。
老人ホームの入居も検討

在宅介護の環境・体勢を整えることは、要介護者の生活の質の向上、家族介護者による介護負担の軽減につながります。
しかし、介護する側のスキル・専門性や、用意できる設備などを考えると、自宅でできることには限界があるのも事実です。特に要介護者の方の介護度が上がってくると介護の時間が増え、求められる介護スキルや設備がどうしても増えてくるでしょう。
その場合、老人ホームの利用を考えることが有効な選択肢となってきます。老人ホームでの介護は、在宅環境にはない利点が多いです。
以下では、老人ホームに入居することのメリットや部屋のタイプ、持ち込める家具などについて詳しく解説します。
在宅介護と比較して、施設介護を選ぶメリット
老人ホームに入居することの最大のメリットは、専門家による介護を24時間受けられるという点です。
老人ホームでは介護職員による介護に加えて、看護師や理学療法士など各分野のスペシャリストが在籍しています。
また、たん吸引や経管栄養などの医療的な対応や、寝たきりの方への体位変換など、在宅介護では対応が難しいことも、安心して任せることが可能です。
特に認知症の方で徘徊などの症状がある場合、老人ホームでは夜間もしっかりと見守りを行ってくれます。
さらに大きなメリットが、家族介護者の介護負担を大幅に軽減できることです。
在宅介護で家族による介護をする場合、訪問介護や通所介護などの居宅サービスを利用できますが、24時間利用できるわけではありません。特に要介護者の介護度が上昇してきたときは、家族介護者の負担はどうしても重くなってきます。
老人ホームを利用することで、家族が直接介護を行う必要はなく、施設の介護職員に任せることが可能です。仕事と介護をなんとか両立してきた場合、老人ホームの利用により仕事に専念できます。
老人ホームを利用すると、費用がかかると思われがちですが、実際には在宅介護をする場合とそれほど大きな差はありません。
例えば介護保険の要介護認定で「要介護3」の認定を受けた方の場合、在宅介護をすると介護サービス料や福祉用具のレンタル費用、食費や光熱費、雑費などで毎月約12万円近くの費用がかかると言われています。
一方、介護施設を利用すると、居住費や介護サービス料の自己負担分、食費、管理費などを合計すると平均約14万8,000円(「みんなの介護」調べ)となっています。在宅介護の場合とそれほど大きな違いはないといえます。
また、「みんなの介護」のサイトで調査したところ、全国の老人ホームの平均費用の相場は、入居時にかかる一時金が10万円、月額利用料が13.6万円でした。これは要介護度などに関係のない全体としての費用です。この費用額を見ても、在宅介護が老人ホームに入居するよりも各段に安いとは言えません。
おすすめの老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、自立または比較的介護度の低い方が入居する、シニア向けの住宅です。
一般的な老人ホームが利用権方式であるのに対し、サ高住は敷金や家賃で入所する賃貸物件である点が特徴です。
サ高住には大きく分けて、一般型と介護型の2種類があります。
一般型は介護サービスを利用したい場合、外部の介護事業者と契約して訪問介護サービスや通所介護などを利用します。
介護型の場合は、施設の介護職員が介護業務を担当します。
入居一時金の相場は0円から数十万円、月額費用の相場は10万円から30万円です。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)
サービス付き高齢者向け住宅を探す住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、自立~比較的要介護度が高い方まで、幅広く受け入れている老人ホームです。
自分に必要な分だけ、介護サービスを自由に利用者が選べるのが特徴です。
また、ほかの施設に比べてイベントやレクリエーションが充実しているところが多く、生活を楽しみながら安心して生活が送れます。
入居対象者は要介護1~2の人が中心です。ただし、要介護度の高い方、認知症患者の方の受け入れをしている施設もあります。
入居金の相場は0円~21万円、月額費用の相場は9.6万円~16.3万円です。
【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説
住宅型有料老人ホームを探すグループホーム
グループホームは、認知症と診断された高齢者のための老人ホームです。
一戸建て住宅やマンションなどを施設にしていて、認知症患者だけで集団生活をしています。
認知症ケアの専門スタッフのサポートのもと、日常の家事や買いものなどを分担しながら、生活リハビリを通して症状の進行緩和を目指します。
入居対象者は、施設所在地の自治体に住民票がある方です。
住み慣れた地域で暮らしながら、家庭的な雰囲気で認知症の改善や認知機能の維持を目標にしています。
【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説
グループホームを探す
愛用している家具も持ち込める
在宅介護の利点の一つに、慣れ親しんだ環境で生活できるという点があります。例えば自宅であれば、要介護状態になっても使い慣れた家具や家電をそのまま使い続けることができるわけです。
ただ、愛用の家具・家電の利用という点については、老人ホームでもある程度は実現できます。というのも、老人ホームに自宅から家具・家電を持ち込むことができるからです。
特に個室で生活できる施設であれば、部屋の中に自分の愛用の家具・家電を取りそろえることもできます。自宅の自室に似た環境を作り上げることができるわけです。
ただし、施設によって持ち込める家具の量は異なるので注意しましょう。
多床室など自分のスペースが限られている施設だと、持ち込める量には限界があります。一方、有料老人ホームのような完全個室となっている施設では、馴染みの家具・家電を持ちこめるのも利点の一つです。
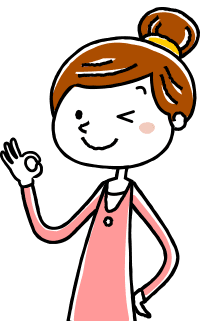 この記事のまとめ
この記事のまとめ- 介護ベッドの位置や、部屋の広さだけでなく、日当たりや風通しにも着目しよう
- 一般的なベッドではなく、介護専用のものを選ぶようにしよう
- ベッド本体だけでなく、周辺機器も揃えることで、在宅介護をより快適にする
- バリアフリーを意識した介護リフォームも検討してみよう
- 在宅介護だけに限定せず、施設入居も選択肢に入れて考えよう






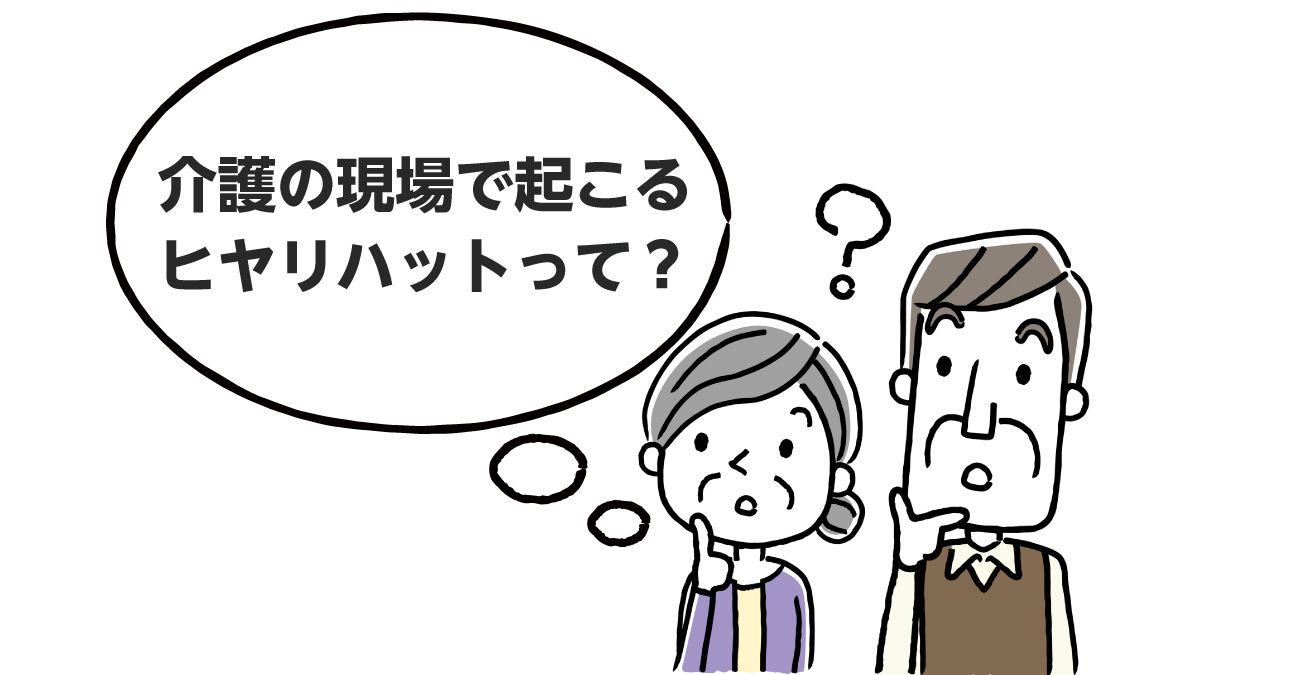



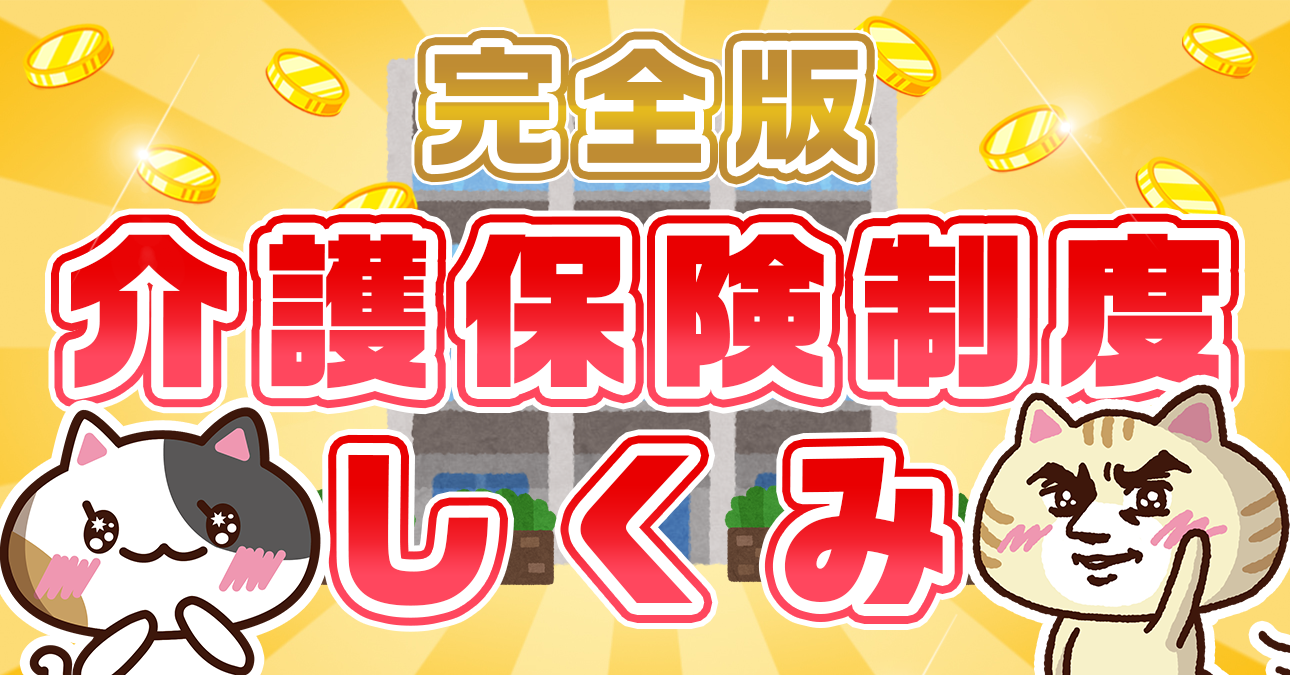
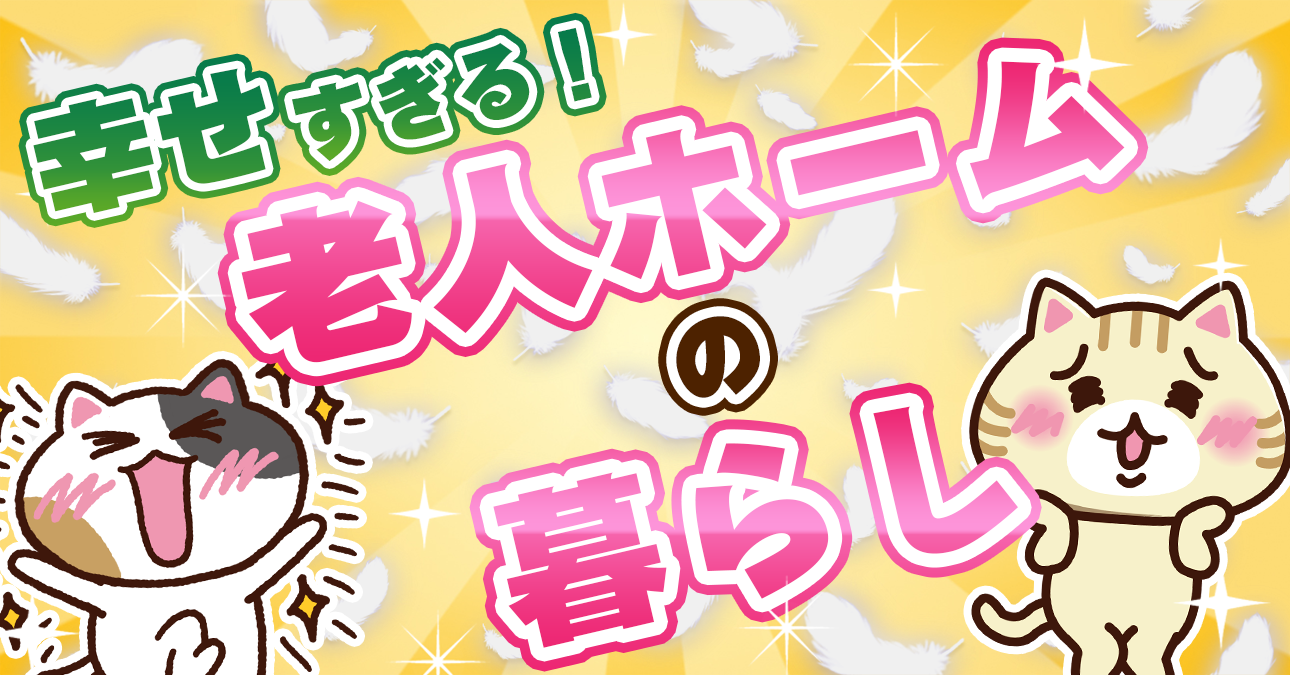
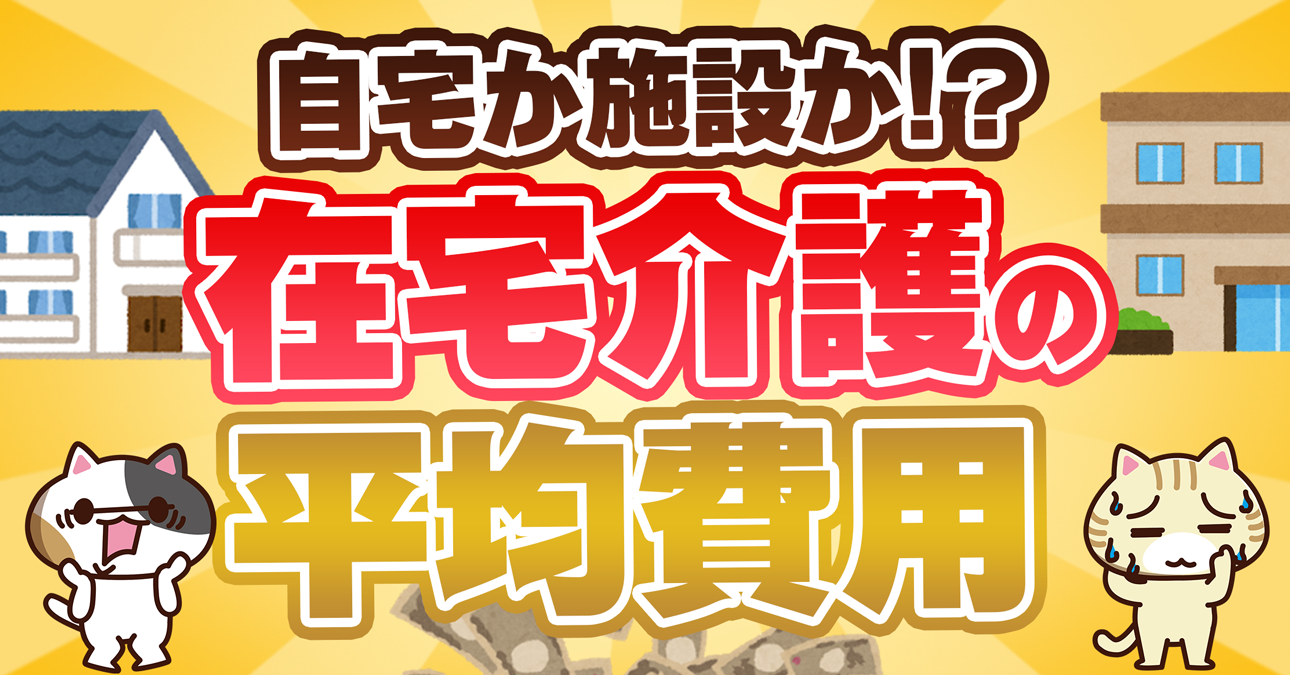
 この記事の
この記事の