認知症による妄想とは

認知症の症状として、「妄想」があらわれることがあります。
東京都の調べによると妄想は、認知症の方の約15%にみられる症状であり、その多くは自分が被害を受けたと思い込む「被害妄想」であるとされています。
普段どおりの1日にもかかわらず、急にソワソワしはじめて、カバンやタンスの中をひと通り見た後、「泥棒!私の財布をどこに隠したの!」と叫びだすこともあります。
介護する側には身に覚えのないことなので反論すると、はじめは疑いながらもその言葉を受け入れようとします。
しかし、妄想がどんどん膨らみ、揺るぎない事実として頭の中に定着してしまうのです。
妄想が表れる原因
妄想は、認知機能の低下に加えて、症状に対する苦しみや「世話になって申し訳ない」といった負い目、疎外感、不安、「自尊心が傷つけられた」という悲しみ、一人暮らしの寂しさなど、さまざまな感情が複雑に関係し合って現れるとされています。
そして妄想が現れる引き金となるのが、家族など周りの人の言動だと研究結果で明らかにされてきています。
例えば、家族そろって食事をしているとき。
本人がわからない話題でほかの家族が盛り上がっていると孤独を感じたり、「自分には誰も見向きしてくれない」と家族の無関心を意識したりすることがきっかけになる場合もあるのです。
また、被害妄想は本人にとっては真実ですから、悪者扱いされた側は悪意を感じることがあるかもしれません。しかし、本人に悪意はなく、周りに自分の感情を訴えかけているだけなのです。
認知症の初期症状のひとつ
認知症はすでに発症していても自覚が難しいです。そのため、早期発見のためには、家族をはじめ周囲の人の気づきが大切です。
認知症は早い段階から、多様な初期症状が現れます。特によく見られるのは記憶障害、実行機能障害、見当識障害、理解力の低下などの認知機能障害、そして被害妄想をはじめとする行動・心理症状です。
認知症の行動・心理症状として気分の落ち込み、混乱などが見られますが、被害妄想も発症後早い段階から見られる場合があります。例えば、本当は誰も何もしていないのに「財布を盗まれた!」と周囲の人を疑う言動や行動です。
同居する高齢者が、最近になって被害妄想と思われる言動・行動が見られるようになったら、認知症の初期症状が出ている恐れがあります。
認知症は治療で進行を緩やかにすることができます。そのため、早期発見・早期治療が大切です。
認知症による被害妄想の種類
被害妄想にもいくつかの種類があります。下記では、主な要因や具体的な症状を説明します。
1.物盗られ妄想

認知症で起きやすい被害妄想のひとつに「物盗られ妄想」があります。
物盗られ妄想は、例えば「家族に財布を盗まれた」「ヘルパーに宝石を盗られた」など、介護する時間が長い「身近な人」が疑われるケースが多いとされています。
物盗られ妄想の原因のひとつが、認知症による記憶障害を認めたくないという気持ちです。
例えば、認知症になるまで家計を管理してきた人が、財布をどこかに置き忘れてしまったとします。その事実を認めると、自分が家計を任されているという誇りを失ってしまうのです。
家族から「役に立たない」と思われることを恐れ、「誰かが盗った」と考えるようになります。このようにして、物盗られ妄想へとつながるのです。
2.対人関係の被害妄想

対人関係にまつわる被害妄想にはさまざまなタイプがあります。
介護者から暴力や暴言を浴びせられたという被害妄想の場合、介護に関わっていない家族や第三者が聞くと、本当に虐待されていると思われて、警察沙汰になってしまうこともあります。
なので、虐待のような被害妄想がみられた場合は、一刻も早くケアマネージャーや地域包括支援センター職員などに相談しましょう。
悪口を言われたと思い込む
また、暴力や暴言のほかに「陰で悪口を言っている」「のけ者にされている」「嫌われている」といった被害妄想もあります。
例えば、介護者とヘルパーの間で本人に聞かれないように打ち合わせをしていると、その様子を悪口を言っていると誤解するといったケースです。
また、自分以外の家族だけ外出するようなことがあれば、「自分は必要とされていない」と思って孤独を感じるようになります。
そうなると家族のことが信用できなくなり、部屋に閉じこもって出てこなくなるようなこともあります。
部屋に閉じこもると運動する機会が減って身体機能が低下し、人とのコミュニケーションがなくなることで、さらに認知症が進行するという悪循環に陥ってしまうのです。
もし、この妄想がみられた場合は、本人の得意なことに取り組んでもらい、その結果を認めてなくてはならない存在であることを伝えることで自信を回復してもらうことが効果的です。
嫉妬妄想
被害妄想には分類されませんが、です。
配偶者が「浮気をしている」と誤解してしまうのが嫉妬妄想です。
例えば、妻の帰りが少し遅くなったり、自分と接する時間が少なくなったりすると、「外で誰かと会っているのでは」「駆け落ちしたのかも」と思い込み、激しく嫉妬してしまいます。
嫉妬妄想を発症する原因は見捨てられ妄想と同じで、「自分は必要とされていない」と思い込んでしまうことにあります。
認知症になったことで嫌われているのではないか、配偶者の重荷になっているのではないか、施設に入れられてしまうのではないかというような不安が「必要とされていない」という考えにつながります。
その考えがエスカレートした結果、浮気をされているのかもしれないという思い込みに至るのです。
嫉妬妄想への対応方法
嫉妬妄想への対応としては、自分は配偶者にとって大切な存在であるということを再確認させて、不安や喪失といった感情をなくすことが重要です。
最も端的な方法は、配偶者がもっと時間をかけて介護に携わり、大切な存在だと伝えることです。
また、得意なことに取り組み、「自分は家族に頼られて役に立つ存在だ」という体験を積み重ねることで自信を取り戻すことも、症状を緩和することにつながります。
迫害妄想
迫害妄想とは、「他人からいじめられている」などの妄想を抱くことです。
妄想の現れ方は人によって異なり、家族・親族に対しての妄想はもちろん、「誰かにいつもつけ狙われている」など、見ず知らずの人から攻撃されていると感じるケースもあります。
訪問介護のサービスを利用しているときは、「ヘルパーから虐待を受けている」と訴えることも、迫害妄想としてよくある症状です。
家族介護者など周囲の人が言動・行動をメモするなどした上で、主治医・かかりつけ医に相談するのが望ましいです。
見捨てられ妄想
対人関係の妄想として、見捨てられ妄想もあります。
見捨てられ妄想は認知症の方が発症する妄想のなかでも、全体の3~18%と物盗られ妄想に次いで発症頻度が高い妄想です。
自宅介護よりも施設介護の方が発症頻度は高く、比較的判断力が保たれている場合に多くみられます。
認知症になると自分でできることが少なくなり、症状が進行するにしたがって日々の生活をすべて介護者に頼るようになります。
そのため、日を追うごとに「まわりに迷惑をかけている」という思いが強くなり、どんどん負い目を感じるようになります。
その負い目がいつしか「自分は邪魔な存在だ」という気持ちになり、見捨てられているという妄想に変わってしまいます。
妄想性人物誤認とは
いないはずの人物を作り出す「妄想性人物誤認症」という症状が出現することがあります。
人物誤認とは、知らないはずの人のことを昔からの知り合いだと思い込んだり、反対に身内や古くからの知り合いを知らない人と思い込んだりすることです。
主な4つの症状は下記のとおりです。
- カプグラ症候群
- 身近な人が瓜二つの他人とすり替わったと思い込む
- 幻の同居人
- 赤の他人が家の中に住んでいると思い込む
- 鏡徴候
- 鏡に映った自分の姿が認識できずに他人だと思い込む
- TV徴候
- テレビの世界と現実との区別がつかなくなる
いずれも、頭ごなしに否定せずに話を聞いてあげることが大切です。
認知症による妄想への具体例
ここからは、認知症による妄想の具体例とその対応方法について解説していきます。
作り話をする
作り話とは、認知症の人が事実ではない嘘の話をすることを指します。認知症を発症している本人は、嘘ではなく本当の出来事を話しているつもりです。
認知機能が低下することにより、出来事や経験したことに対する正確な記憶が失われるようになってきます。
そのとき、記憶が失われた部分に対して事実とは反する内容を盛り込んで、自分にとって都合の良いストーリーを自分で作ってしまうのです。
本人は自分で考えた作り話を、本当の話として周囲の人に話します。
「作り話」への対応方法
例えば、認知症を発症している75歳(女性)の方が、夫とは3年前に死別しているのに、突然「夫と買い物に行ってきた」と作り話をしている状況を考えてみましょう。
この場合、周囲の人が「嘘をついてはだめ」などと責めるのは厳禁です。否定的な対応をすると周囲の人に敵意を持つようになり、認知症の症状がさらに悪化する恐れがあります。
この作り話に対しては、「それは良かったね」「どこに買い物に行ってきたの?」などと相づちを打つのが望ましいです。本人の気分を害さないように接することが、心を落ち着かせることにつながります。
独り言を言う
「独り言」は健常者にもよく見られますが、内容によっては認知症の症状に分類されるものがあります。
例えば、誰もいないのに「何しているの?」などと誰かと話し合うような独り言をすることは、レビー小体型認知症の症状として多いです。
また、「ハサミはどこに置いたかな」「財布はどこかな」といった独り言は、1日に1~2回ならばともかく、繰り返しそのような独り言が見られる場合は、認知症の前段階である軽度認知障害が生じている恐れがあります。
「独り言」への対応方法
認知症を発症している75歳(女性)で現在は娘家族と同居し、食事をしている際に必ず独り言を言う状況を考えてみましょう。
この場合、「食事中だから静かにして」などと怒るのは禁物です。
もし何かを不安に感じている様子であれば、手をさすってあげるなど、安心できる状態を作ってあげるのが望ましい対応といえます。本人の混乱や不安感、恐怖感を増やさない対応をすることが大切です。
人物誤認をする
人物誤認とはその名の通り、人間を誤認する症状のことです。
典型的な症状としては「目の前の人を別の人と誤認する」というものですが、関連する症状としては、先述の「カプグラ症候群」「TV徴候」「幻の同居人」「鏡徴候」などがあります。
「人物誤認」への対応方法
認知症の人物誤認には多様な症状がありますが、ここでは認知症の75歳(女性)が現在は息子家族と同居していて、息子を死別した夫と間違える、という症状への対応方法について考えてみましょう。
この場合、間違えられた息子が怒ったり、間違えを正そうと注意したりするのは不適切です。本人が感情的になり、心が不安定になる恐れがあります。
対応としては、まずは本人の話をよく聞いてあげることが大切です。
本人の言葉に対して反論する、無視するといった態度をとらず、共感の姿勢でコミュニケーションをとることが、心を落ち着かせることにつながります。
認知症の種類別の妄想の特徴
続いて、認知症の種類別に表れる妄想の特徴について解説していきます。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症では「幻視」が多く、その症状に伴い「妄想」がみられます。
なかでも「替え玉妄想」が現れることが多く、目の前にいる家族が偽物にみえ、「本物の家族はどこにいるんだ」と大声を出します。
原因はわかっていませんが、人の認識と親しい人と触れたときの感情の連動が不十分により起きると考えられています。
主な症状が妄想のアルツハイマー病と異なり、レビー小体型認知症は幻視がきっかけで妄想の症状が現れるケースが多いです。
アルツハイマー型認知症とは?原因や症状、治療法を解説【日本認知症学会理事監修】
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症では「物盗られ妄想」が多くみられます。
財布をどこかに置き忘れ、どこに置いたのか忘れてしまう記憶障害が起きることで、物盗られ妄想につながるといわれています。また、不安感などによる怒りや悲しみによっても起きやすいです。
自分が置き忘れたという自覚がなく覚えていないため、瞬時に「盗られた」と認識します。
こうした物盗られ妄想は家族や介護者など、身近な人が疑われることが多くあります。
認知症の妄想への薬物療法
認知症による妄想の症状は、薬を服用することで和らげることができることがあります。
ここでは、治療薬の種類と注意点を解説していきます。
認知症による妄想に対する治療薬
妄想の治療薬として、向精神薬や漢方薬、抗認知症薬であるメマリーを使用します。
メマリーは、神経細胞の興奮させるグルタミン酸の働きを抑え、精神を落ち着かせます。
向精神薬は妄想の症状を緩和するだけでなく、認知症の進行を遅らせます。さらに、認知症の方が本来の自分らしい生活を取り戻すことも可能です。
これらの薬は、基本的に興奮型の症状が出ている方に処方される薬ですが、妄想の症状が出ている方にも処方されます。
薬を服用するうえでの注意点
認知症による妄想の治療薬は、意欲低下や眠気、ふらつきなどの副作用が起きる場合があります。そのため、介護者は認知症の方の容体に注意して見守ることが大切です。
服用後に、異変が見られたときはすぐに医師に報告しましょう。
また、飲み忘れや飲み過ぎによって、本人の容体が悪くなることもあります。こうした状況を防ぐために、医師の服薬の指示は必ず守りましょう。
さらに、服用するときは少量から始めて、本人の様子をみながら少しずつ量を増やしていきます。
認知症の妄想への対応のポイント
ここでは、被害妄想の症状が出てしまった方への接し方を説明します。
物を盗られたと訴えられた場合、否定も肯定もせず、共感しながら一緒に探してみましょう。
そして、たとえ先に見つけても、本人が見つけるようにさりげなく誘導します。うまくいけば、自分で見つけられたことで自信が回復し、少しずつ物忘れへの不安が解消されていく可能性もあります。
以下で詳しく解説していきます。
否定をしない

被害妄想が原因でドロボー呼ばわりされたり、浮気を疑われたりするような理不尽な思いをしても、頭ごなしに否定するのでは状況が改善することはありません。
本人にとっては真実を訴えているだけなのに、頭から否定されると本人は混乱してしまいます。
怒りや悔しさ、悲しさなどの感情も増幅し、結果として感情を抑えきれず、被害妄想がより強く出現することになります。
介護する側にとっては、身に覚えのないことで疑われて激しく叱責されるわけですから、否定したくなる方がほとんどでしょう。
しかし、そこはグッとこらえて否定も肯定もせず、じっくり話に耳を傾けることが重要です。
被害妄想の対応で大切なのは、本人の不安な気持ちや孤独な思いを聞くこと。抱えている「つらさ」を受け止め、感情を落ち着けてもらいます。
話に共感しながら聴く
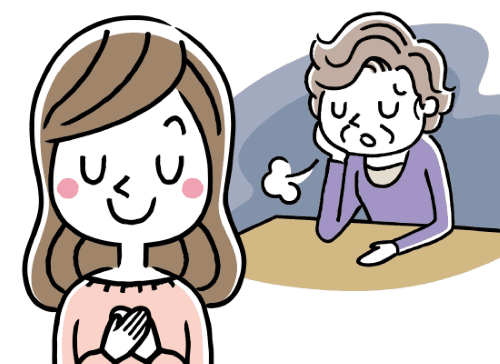
被害妄想の訴えに耳を傾けることは大切ですが、「それは困りましたね」「大変ですね」などと相槌を打ちながら聞けると、なお効果的です。
たとえすぐに妄想だとわかっても頭ごなしに否定せず、共感しながら話を聞きましょう。認知症の方の気持ちに、「この人ならわかってくれる」という安心感が生まれます。
本人の不安や悲しみに寄り添い、相談に乗ることで被害妄想が収まることも珍しくありません。
また、共感しながら話を聞くことで、その後の介護につながるヒントが得られたり、訴えの裏に隠されている本音が垣間見えたりすることがあります。
気づかないうちに妄想の引き金にならないように注意する
認知症による妄想は、介護者の無意識な発言や行動が引き金となり表れることがあります。
例えば、本人の希望を聞かずに勝手に家具の配置を変えていたり、本人の話を無視することがたびたび続いていたりするなどで妄想の症状が現れることがあります。
被害妄想は環境の変化や、周囲のちょっとした配慮の欠けた行動が原因で起こります。
それを介護者が事前に把握し、被害妄想を未然に防ぐのは難しいです。
被害妄想の訴えのなかにある隠された思いに気づくためにも、共感しながら話を聞くことを心がけてみてください。
周囲に相談する

被害妄想は認知症の症状のひとつだと頭では理解していても、実際に疑いの目で見られたり、ひどい言葉でののしられたりすると、介護する側は精神的に参ってしまいます。
そんなときは、できるだけ早く相談できる相手を見つけましょう。
家族の被害妄想に悩んでいる方のなかには、「誰かに相談してもわかってもらえない」と考える方もいますが、介護する側が心身ともに健康でなければ、しっかりと介護はできません。
まずは自身の身を守るためにも第三者に相談し、心の健康を守ることが肝心です。
介護のプロに相談することで的確なアドバイスがもらえる
相談する相手としては、かかりつけ医やケアマネージャー、地域包括支援センター職員などおすすめです。
医療や介護のプロフェッショナルですから、的確なアドバイスをもらうことができます。
また、つらい気持ちを和らげるという意味では、同じ境遇の人たちと交流を持つこともおすすめします。
被害妄想に悩む人たちのための家族会はもちろん、定期的に勉強会を開いている団体もあります。そういったところに顔を出し、同じ悩みを抱える者同士で話をするだけでも気持ちが落ち着くはずです。
距離を取る
被害妄想の対象が介護者である場合は、距離を取ることも方法のひとつです。
認知症の症状だと理解していても、あまりにも妄想がひどい場合は、介護者に極度な負担がかかってしまいます。
別の方に介護を頼めるなら代わってもらったり、介護施設へのショートステイや病院への短期入院などを検討するのも良いかもしれません。
精神的な距離を取るためにも、その間は介護のことを忘れ、自分の趣味などに没頭することが大切です。
一時的にでも環境を変えることは、本人にとってもプラスに働くことがあります。
自信やプライドを取り戻してもらう
認知症の人のプライドが傷ついて被害妄想を発症している場合には、それを取り戻してもらうのも方法のひとつです。
例えば本人が料理好きならレシピを教えてもらったり、庭いじりが趣味であれば植木の育て方をレクチャーしてもらったりします。
「教える」という行動を通じて、本人が自信を取り戻すことで、被害妄想を抑える効果が期待できます。
認知症ケアにおすすめの老人ホーム
認知症が進行すると、在宅介護を続けることが難しくなる場合があります。そのため、早めのうちから老人ホームへの入居を検討しておくことが大切です。
以下では、認知症の方におすすめの施設を紹介していきます。
グループホーム
認知症による妄想のケアは「寄り添うこと」と「共感すること」が大切です。
グループホームには、妄想の症状にも正しいケアと対応を行う、知識が豊富なスタッフが多くいます。
認知症の方のみを受け入れるグループホームの暮らしは、他の入居者と共同生活を送り、家事を自分たちで分担して行います。そのため、自信を取り戻すきっかけになり、妄想の症状が改善することが期待できます。
本人の残存能力からできることを進んで行える環境が整っており、認知症の方がストレスを抱えず無理なく生活できるのもグループホームの特徴です。
【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説
グループホームを探す住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、外部や施設に併設された介護サービスを利用します。自分の必要な介護サービスが提供されるため、要介護度の低い方は費用を抑えることができます。
好きな介護サービスが選べるだけでなく、入居前に利用していたサービスも引き続き継続して利用することができます。
さらに、レクリエーションやイベントが盛んで、他の入居者とコミュニケーションをとる機会も多いです。
認知症の症状や進行を緩和するレクリエーションに力を入れる施設もあるので、認知症の方も楽しみながらレクリエーションに参加できます。
【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説
住宅型有料老人ホームを探す介護付き有料老人ホーム
24時間の手厚い介護サービスを受けられる介護付き有料老人ホームは、妄想の症状が出てもすぐに対応してもらえます。また、看護師が常駐する施設もあり、持病のある方も安心して生活できます。
要介護度が重くても入居できたり、入居中に症状が悪化してもサービスを受けられたりすることができ、看取りに対応する施設も増えています。
介護付きは施設数が多くあるため、施設の特徴やサービスから自分に適した施設を選ぶことができます。
【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)
介護付き有料老人ホームを探すせん妄や幻覚との違い
せん妄と幻覚は妄想とよく間違えられます。
認知症による妄想が、せん妄と幻覚とどのように違うか解説していきます。
せん妄との違い
せん妄とは、意識障害の一種であり、頭が混乱した状態を指します。体調不良や薬などの影響によって急激に症状が出ますが、数週間ほどで落ち着きます。
ただし、せん妄の状態が長く続くと、脳の機能が低下して認知症を発症しやすくなります。
また、認知症の方がせん妄を発症することもあり、脳血管性認知症やレビー小体型認知症との併発が多くみられます。
一方で認知症による妄想は、現実に起きていないことが起きていると思い込む症状です。
幻覚との違い
幻覚は、本人にとっては実際に見えている状態で、レビー小体型認知症を発症した8割にみられます。症状は見えない人が見えたり、周りには聞こえない声が聞こえたりするなどです。
幻覚の訴えに対し介護者は戸惑いますが、本人の発言を否定せずに共感することが大切です。否定から、本人の不安感や焦りが大きくなり、症状が深刻になるかもしれません。
そして、妄想は自分で思い込む状態で、本人が実際になにかを見ているわけではありません。
他の人はこちらも質問
認知症による物盗られ妄想はいつまで?
認知症の物盗られ妄想は、初期症状として現れることが多く、1年以上続く場合もあります。
認知症が進行すると、消失するケースが多いです。家族に財布を盗まれた、ヘルパーが時計を盗んだなど、本人にとって身近な人を疑うパターンがよく見られます。
物盗られ妄想による認知症はなぜ?
物盗られ妄想の主な原因は、認知症で起こる記憶障害を受け入れたくないためです。
社会から取り残される、家族から役に立たないなど、と思われることが怖くて、物盗られ妄想を引き起こします。
認知症の始まりはどんな感じ?
認知症の初期症状には、記憶力や判断力などが低下する中核症状が出てきます。中核症状とは、記憶障害、見当識障害、計算能力障害、実行機能障害などです。
認知症による幻覚はなぜ?
認知症によって脳の機能が低下しているため、錯覚を起こしやすいと言われています。その結果、不安やストレスから幻覚が見られます。
また幻覚は、レビー小体型認知症の初期から中期にかけて出てくることが多いです。




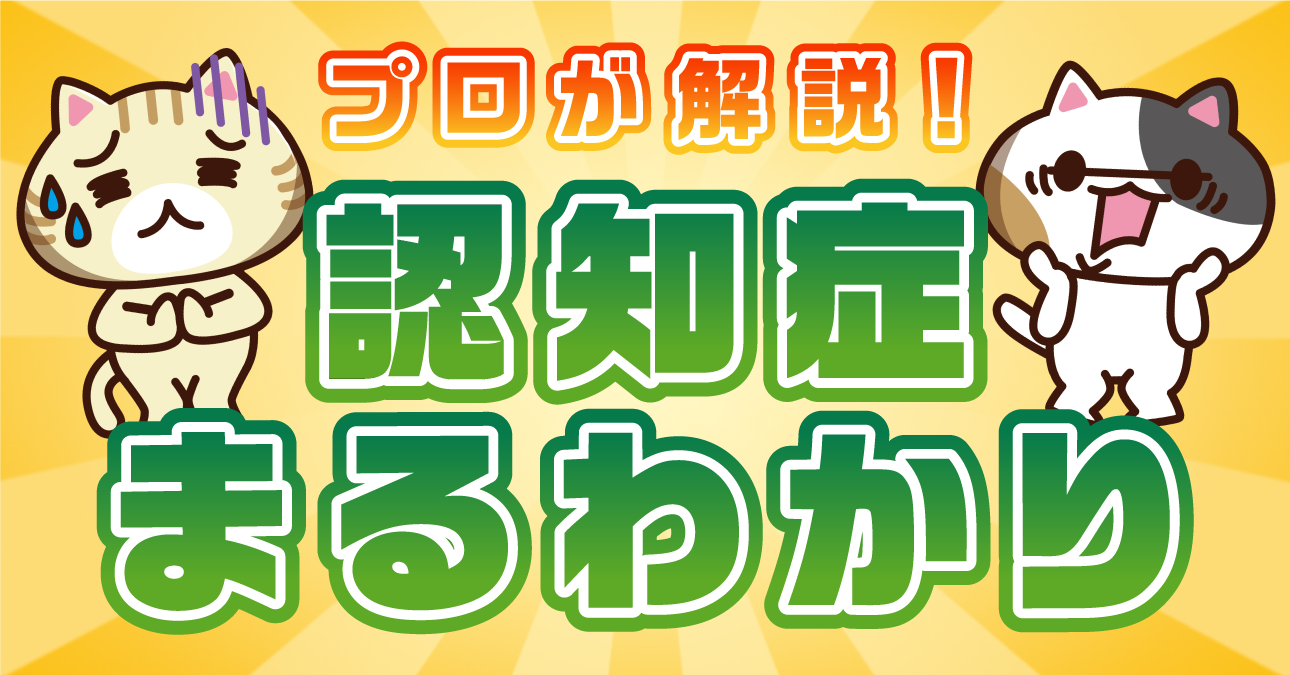



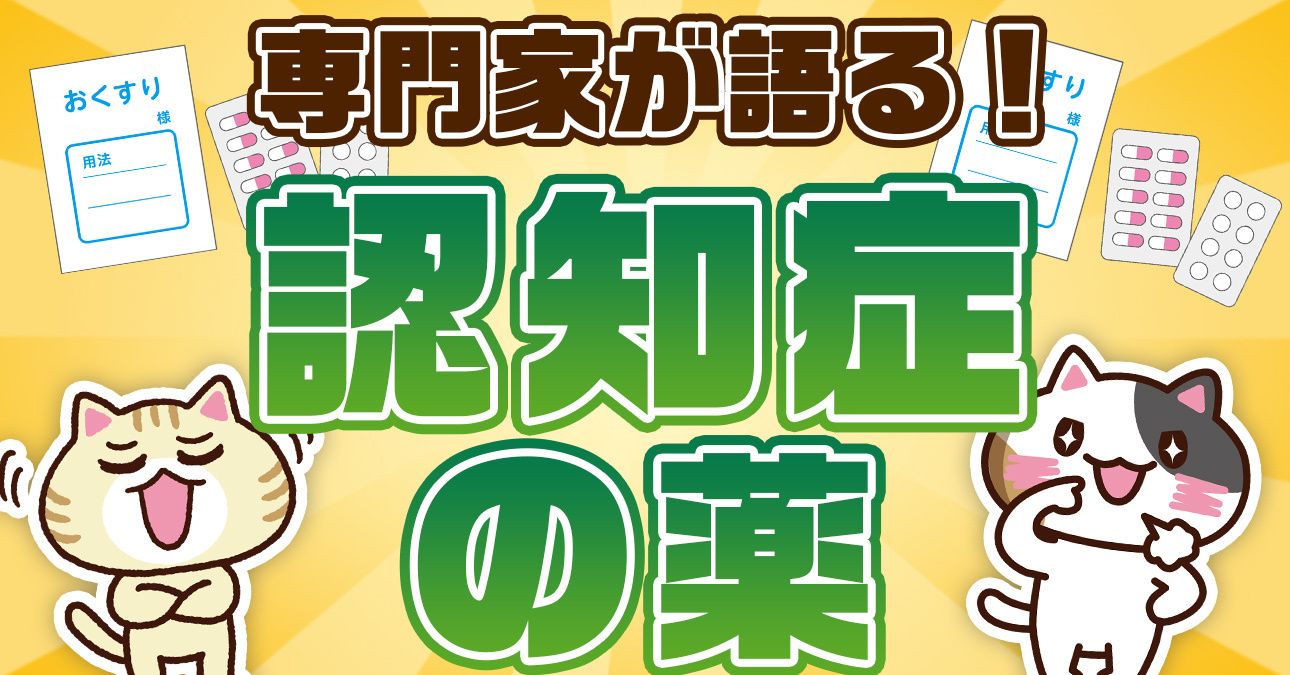
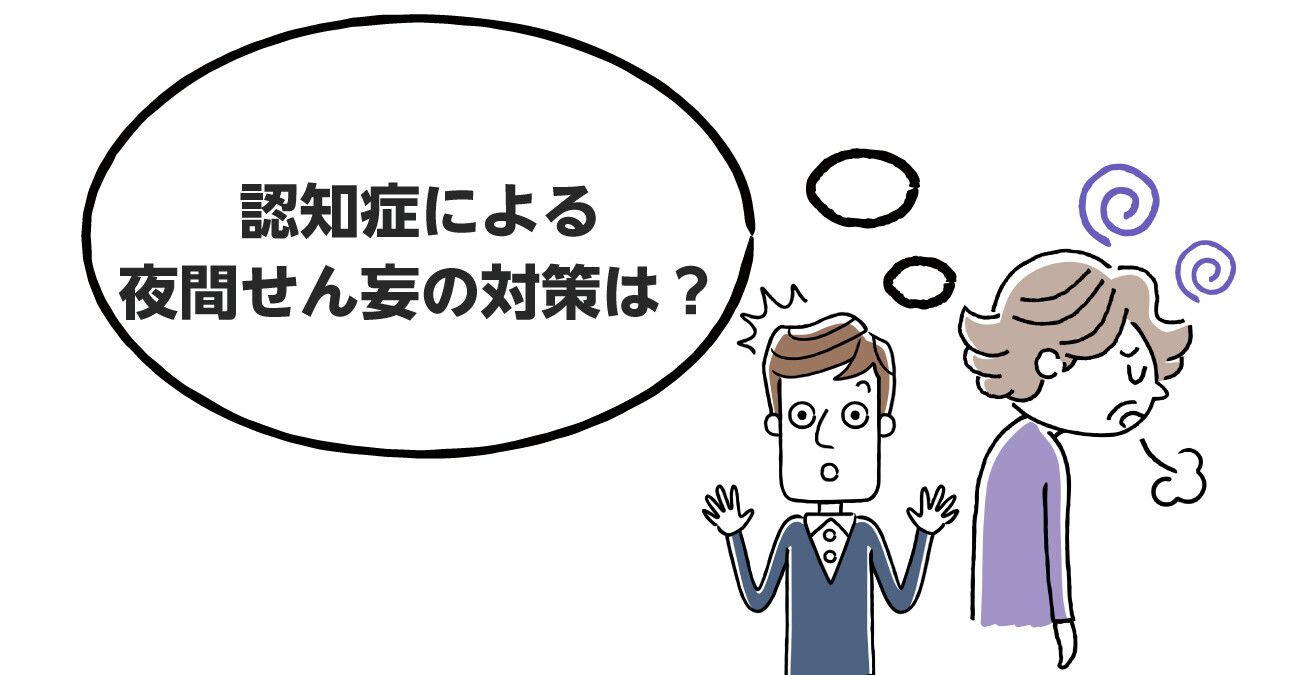
 この記事の
この記事の

