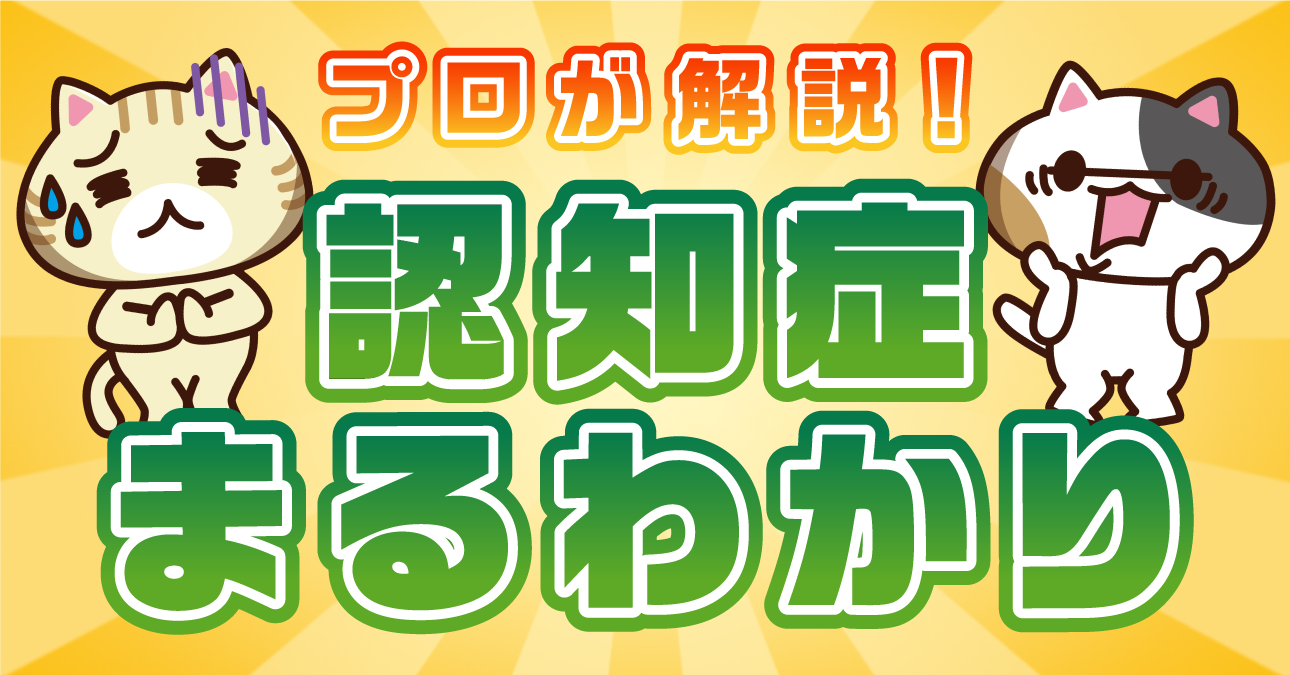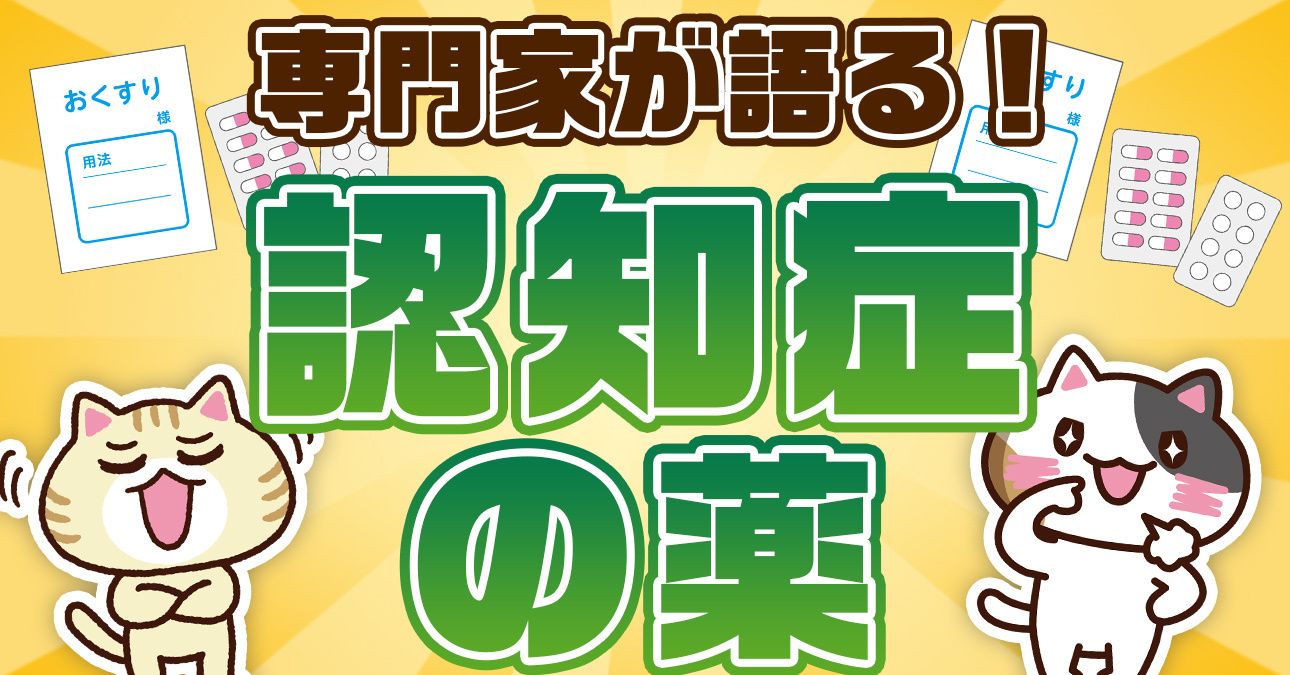認知症の対応の仕方
認知症の方は常に不安を抱えながら生活しています。そのため、日頃の生活のなかでできるだけ不安を取り除くように努めることで、多くの症状は改善されます。
そのため、介護の際には普段の何気ないコミュニケーションから、気をつけて接するようにしましょう。食事でも入浴でも、何かを始めるときは本人にわかりやすい言葉で伝え、忘れることも想定しながら繰り返し伝えます。
また、本人が自分なりに考えて口にしたことは、たとえそれが間違っていても、決して否定することなく受け入れることも大切です。
例えば、「でも」「だけど」という言葉にも要注意です。たとえ失敗したり、できると言ってできなかったりした場合も、責めることなく、自尊心を傷つけるような言動には気をつけましょう。
日々の言動、行動は本人が生きるためのサインです。いかに気づけるかが尊厳を守るカギとなります。
対応の心得は3つの「ない」
認知症の対応で大切なポイントとして、「驚かせない」「急がせない」「自尊心を傷つけない」ということがあります。
認知症の方は、判断する認知機能が低下して動作が遅くなるため、「なんでできないの」「やってあげる」など相手の自尊心を傷つける言葉は控えるのが基本です。
また、認知症の方は自覚症状がないと思われがちですが、最初に症状に気がつくのは本人の場合が多いです。
気付いた本人も不安を感じているので、周りは寄り添った対応が求められます。
認知症対応の9原則
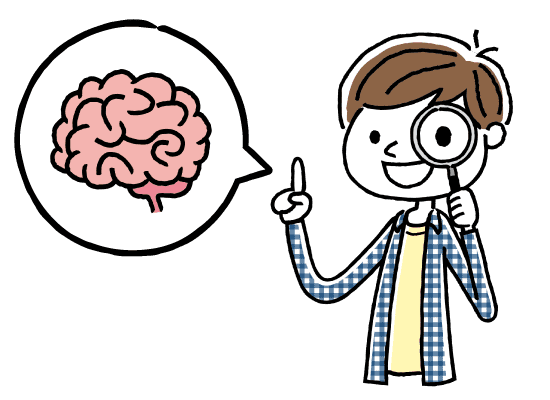
認知症に対応するために、川崎幸クリニック院長の杉山孝博氏が出版した「認知症の9大法則 50症状と対応策」(法研)が、注目を集めています。
9大法則の特徴は次の通りです。
- 行動や体験そのものを忘れる
- 身近な人に対し認知症は強く出る
- 不利なことは認めない
- 症状が出る時と出ない時がある
- 出来事で生まれた感情は残る
- 一つのことに執着する
- 反発や反抗が強くなる
- 認症の特徴の理解の理解を深める
- 老化の速度が認知症でない人と比べると3倍早い
これは、「認知症の方の世界を壊さないようにすべき」という認知症介護における原則を示したものです。これを理解することで認知症の特性がわかるようになり、介護にかかるストレスを緩和できます。
以下で詳しく解説していきます。
1.記憶障害に関する法則
認知症の人は行動や体験そのものを忘れてしまいます。
認知症の記憶障害ともの忘れの大きな違いは、そのこと自体を覚えているかどうかです。
もの忘れの場合は、体験したことは覚えていても細部を思い出せないというものです。一方、認知症の方の場合は前述のように異なります。さらに、こうした症状が現れた人を介護するうえで大事なことは、喪失した記憶はその人にとって事実ではないという点です。
周囲にとっては紛れもない真実でも、本人の認識とは異なる場合があるという事を覚えておきましょう。
2.症状の出現強度に関する法則
認知症の方の症状は、介護をする人など身近な人に対して強く出ます。来客や医師など会う頻度の高くない人や、家族であっても介護をしていない人には、症状が軽く見えるのはそのためです。
理由は判明していませんが、身近な人に信頼を寄せて甘えているためだと言われています。
この特徴を把握しておかないと、介護をする人にとって大きなストレスになるばかりか、認知症の進行について周囲と認識のギャップが生じるなどの問題が起こります。
3.自己有利の法則
認知症の方の多くが、自分にとって不利なことは絶対に認めず、平気で嘘をついたり言い訳をしたりします。
これは認知機能の低下により、相手の感情に共感できなかったり、嘘を嘘と感じずについてしまったり、さらには自分の能力が下がっていることへの自己防衛をしたりすることが原因といわれています。
こうしたことに腹を立てたくなる気持ちはわかりますが、仕方のないことだと考え、言い合わないようにして対応していくことが重要となります。
4.まだら症状の法則
認知症の症状が出るときとそうでないときが、まだらに混在しています。
こうした二面性は、介護する側にとって混乱をまねくことがあるので注意が必要です。
認知症の方の言動や行動などを、正常か否かというくくりで分けようとするのではなく、あくまでも認知症の方を相手にしているのだ、というような認識を持つことが大切です。こうした混乱を起こすことなく、介護にあたることができるようになるポイントです。
5.感情残像の法則
認知症の方は、起こった出来事をすぐに忘れてしまいます。しかし、その出来事によって引き起こされた感情は、記憶がなくなってもしばらく残り続けます。
そのため、介護する側が正しいことを伝えようとしても、そのことを忘れてしまうばかりか、口うるさく何かを言われたという嫌な気持ちだけが残り続けてしまうのです。
介護者にポジティブな印象を抱かせることで、円滑に介護をすることができます。
6.こだわりの法則
認知症の方がひとつのことに固執すると、そのこだわりを捨て去ることができなくなってしまう場合が多いです。
この際に、そのこだわりを否定したり、捨てるように説得しても、より固執したりと、さらにその説得を行った人に対してストレスをためてしまうこともあります。
そのため、認知症の方のこだわりを認めながら、それをどう和らげるか、あるいは別のものに注意を向けさせるかなど、直接的ではない対応を考える必要があります。
7.作用・反作用の法則
認知症の方を相手に何かしらの強い対応をした場合、強い反発となって返ってくるとことがあります。
リハビリなど、相手に良かれと思ってしたことであっても、本人が苦痛を感じてしまうことであれば、それを嫌がって反抗してしまうのです。強い反応が返ってきてしまうときは、自分がそれだけつらいことを相手に強いているということ。
認知症の方の状態は、介護者の状態との合わせ鏡であることを自覚し、強すぎる対応をしないように気を付けましょう。
8.認知症症状の了解可能性に関する法則
認知症の方の言動は、一見脈絡がなく理解しにくいものなので、困惑することもあるでしょう。
しかし、認知症の特徴を考えれば、そのほとんどが理解・説明できます。特に、その言動にいたる理由や背景を知ることで、さらなる理解を深めることが可能です。
そうして認知症の方の言動を受けとめることができるようになれば、認知症の方も穏やかな対応をしてくれることが多くなります。
9.衰弱の進行に関する法則
認知症の方の老化の速度は、そうでない方の3倍
だという法則です。「認知症介護研究・研修東京センター」が行った研究によれば、認知症の高齢者のグループと、正常な高齢者のグループの追跡調査を行ったところ、認知症のグループの4年後死亡率は83.2%で、正常なグループの28.4%に比べると約3倍高いという結果が出ています。
介護初期では元気な方も、いつまでも同じ状態が続くわけではないということです。
認知症症状の事例と対応マニュアル
認知症の家族を介護する際に、認知症の特徴を理解して適切に対応し、心身の余計な負担を減らしたい…。そう考える方も多いのではないでしょうか?
まず認知症では、記憶障害、時間や場所がわからなくなる見当識障害、判断力の低下が多くの場合に起こります。その結果、周囲が理解できない行動を起こすことがあります。
ここでは、その具体例と対応策をまとめました。
同じ話・行動を繰り返す
原因と対応策
同じ会話を繰り返すのは、会話そのものを本人が忘れているためです。指摘せずに相槌を打つなど丁寧な対応を心がけましょう。
また独り言の回数も増える特徴があります。独り言に対して「静かにして」と怒ると悪化するかもしれません。独り言は無理に話しかけずに優しく見守ることも大切です。
待てないで同じところを歩き回る、何度も立ち上がる「多動」は自分の気持ちを理解してほしいために自己防衛が働いている状態です。
まずはなぜ動くのか理由を聞き、本人の気持ちを汲み取るようにしましょう。
NGな対応例
- 「同じ話をしないで!」と怒り、プライドを傷つけるような発言をする
- 本人の発言や行動に対して否定的な態度をとる
- 独り言を「うるさい!」と怒ったり無理やり黙らせたりする
- 繰り返す行動を細かく指摘する
- 動き回るから家に閉じ込める
外出したがらない/外出してもトラブルになる
原因と対応策
認知症の中核症状として、抑うつや意欲の低下などにより外出したがらなくなる場合があります。日中の活動量が減ってしまうと症状が悪化しやすくなりますので、まめに話しかけたり、できる家事をお願いしたりしてみましょう。
また、外出先での転倒や失禁、居場所や目の前の人が誰かわからなくなる、人に見られることなどへの、不安や焦りを覚えている可能性もあります。
ほかにも、足腰の痛み、体力低下、持病の発症など身体的な理由の可能性もあるので、注意して確認してみるようにしましょう。
NGな対応例
- トラブルが起きることを心配して外出させない
- トラブルが起こると、責める
徘徊をする
原因と対応策
徘徊と聞くと、一般的には目的なく歩き回っているイメージがありますが、実際には本人なりに目的や理由があります。そのため、これを止めさせるのはとても困難です。
例えば、自宅にいるのに「家に帰る」という場合は、子どもの頃に住んでいた当時の自宅を思い出している可能性があります。そういう場合は本人の話にうまく合わせながら、「お茶でも飲んでからにしませんか」というような対応を心がけてください。
NGな対応例
- 「ここは私の家じゃない!」というような本人の話を、頭から否定する
- 外出しようとするのを、力ずくで無理やり止めようとする
物盗られ妄想・被害妄想
原因と対応策
認知症によって記憶障害が現れていると、大切なものをどこに置いたのか思い出せません。
さらに、介護生活への不満や認知症の症状による苦痛などのさまざまなことが影響して、思い込みで「家族に財布を盗られた!」と言い出すなどの物盗られ妄想(自分の物を盗られたと思い込む)や被害妄想が現れると考えられています。
物盗られ妄想の場合は、家族に頼りたいけどできれば頼りたくないという正反対の気持ちが現れています。「それは大変!一緒に探しましょう」など本人に共感する言葉を選んで、自分で失くしたものを見つけられるように誘導することが大切です。また、「置き忘れたのかもしれないですね」と声をかけると落ち着く場合があります。
NGな対応例
- 「そんなことはない!」と否定したり、責め立てる
- 叱ったり、無視をしたりする
ご飯を食べたことを忘れてしまう
原因と対応策
記憶力の低下により、食べたことを忘れてしまうのはよくあることです。また、満腹中枢の障害によって「お腹がいっぱい」という感覚が感じられないケースもあります。
どうしても食べないと気が済まない状態が続くようなら、1回の食事量を減らして数回に分けてもいいでしょう。
また、時計を見せながら「今15時ですね。お昼は12時にカレーを一緒に食べましたね。美味しかったですね」など、具体的に伝えるといいでしょう。
NGな対応例
- 「さっき食べましたよ。」などと否定する
- 気が済むまで食事をさせる
季節や気温にあった服が着られない
原因と対応策
体温調整機能の低下に加えて、時間や場所の認識がなくなる見当識障害、判断力の低下などにより、夏でも冬服、冬でも夏服などを着てしまうことがあります。
対応としては、否定したり、無理やり着替えさせたりするのではなく、アドバイスのようにさりげなく、「あと1枚着てみましょうか」と自然と季節にあった服が選べるような気づきを与えることが大切です。
また、家の中にカレンダーや季節の飾りを置くことで、季節を感じられるようにするのもおすすめです。
NGな対応例
- 「その服じゃありませんよ」などと否定する
- 無理やり着替えさせる
家族や友人が誰なのかわからない
原因と対応策
記憶障害が進行すると、家族や知人であっても誰なのかわからなくなってしまいます。また、自分自身の年齢もわからなくなることもあります。
パニックにならないように、本人の状況に応じて周囲が合わせましょう。
NGな対応例
- 「違いますよ」と、間違いを訂正する
- わからないことを馬鹿にする
家にいるのに「家に帰る」と言い出す
原因と対応策
認知症が進行すると、自宅に住んでいるにもかかわらず、家に帰ろうとすることは珍しいことではありません。
認知症では、記憶障害や見当識障害によって、今いる場所がどこかわからなくなることがあります。いる場所にストレスや不安を感じることで、「帰宅願望」が出ることもあります。引っ越しなどの環境変化があると、より起こりやすくなります。
もしも外出してしまったときの対策として、徘徊予防センサーを身につける、服や持ち物に名前を書く、近所の方への声がけなどをしておきましょう。
近所迷惑だと思い近所の協力は求めにくいかもしれませんが、地域と協力すると徘徊を未然に防げるでしょう。
NGな対応例
- 本人が帰りたがるのを止めようと、強い口調で怒ったり、責めたりする
夜に眠れない
原因と対応策
認知症により、睡眠障害が見られることは珍しくありません。そのため、夜間に眠れなくて外出しようとすることがあります。
原因は何なのかを考えて、少しでも眠れる環境・生活習慣づくりを心がけましょう。
多くの場合、日中の活動量の低下で昼寝が増え昼夜逆転、見当識障害による時間感覚の喪失などが原因として考えられます。
対応として、できる限り日中は散歩やおしゃべりなどをして活発に過ごせるよう心がけ、生活リズムを見直してみましょう。
ときには薬の力に頼ることも 選択肢として考えてもいいでしょう。
NGな対応例
- 怒ったり、寝られないことを馬鹿にしたりする
- 無理やり寝させる
幻覚・幻視・幻聴
原因と対応策
幻覚・幻視・幻聴は、三大認知症のひとつ、レビー小体型認知症でよく見られる症状のひとつです。
認知機能の状態に波があり機能の低下がわかりにくく、なかでも幻覚やせん妄の症状が強く現れます。
具体的には、見えない人に話しかける、いきなり何かを怖がるなどです。見えるのは、人や動物である場合が多くなっています。
突然のことで戸惑うかもしれませんが、話を聞いて共感してあげましょう。危険でないことを伝えて、まずは安心させるなど、ご本人の恐怖や不安をどう取り除くかを考えた対応がベストです。
また、暗いところで起きやすい症状のため、部屋の照明を明るくし、見通しよく片付けておくのも効果的です。
さらに幻視の場合は、本人や周囲の人が近づいたり、触れたりすると幻視症状が消えると言われています。覚えておくと良いでしょう。
NGな対応例
- 「誰もいませんよ」と否定する
転倒する、歩行が不安定
原因と対応策
認知症のなかでもレビー小体型認知症では、パーキンソン病のような症状が見られることがあります。つまずきや転倒により、怪我をしてしまえば寝たきりになることもあります。
介護保険制度なども活用しながら、自宅にスロープや手すりを取り付けるなどバリアフリー環境を整えましょう。
NGな対応例
- 「危ないから」と外出の機会を減らす
興奮・イライラ・暴言・暴力
原因と対応策
脳機能の低下により、思ったことを上手く伝えられなかったり、自制心が働かなくって急に怒りっぽくなったりする認知症。
そのもどかしさからくる不安な気持ちを上手く表現できないことで、暴言や暴力といった行動につながることもあります。
怒っている理由に見当がつかなくても、本人には必ず理由があります。このようなときは、少し距離を置いて気分を落ち着かせてもらいます。
静になった後に、怒りや不安になった原因を聞いて、解決するように努めてください。
NGな対応例
- 「どうしてそんなことをするの!?」と口論をする
- 力づくで押さえつける
- 大きな声を出して叱りつける
こだわりが強い
原因と対応策
認知症の方の特徴として、「こうしなければいけない」「こうでなければいけない」といった、強いこだわりを持っていることが多くあります。
こうした裏には、ストレスが原因でもあるといわれています。
そのため、その要因を排除するように努めたり、第三者に入ってもらったり、別のことに関心を向けたりといった対策のほか、最後の手段としてはそのままにしておくという手も。
これを否定して禁じてしまうと、より頑固に反発してしまったり、ほかの症状が悪化したりする可能性があります。
相手に合わせた対応ができるよう心がけましょう。
NGな対応例
- こだわりを否定する
- こだわりを手放すよう説得する
介護を拒否する
原因と対応策
介護拒否の多くは、不安からくるものです。本人が安心できるように工夫してあげると、多くの場合は症状も収まります。
介助をする際は、「何のために何を行うか」をわかりやすい表現で説明しましょう。本人が納得できれば症状も解消されるはずです。
例えば、食事を嫌がるときは、以前使用していた食器や箸を使うと安心することがあります。少しの環境の変化でも不安になることがあるので気をつけましょう。
NGな対応例
- 介護される側の気持ちを考えない
- 介護する側の理屈で介護を押し付ける
お風呂に入らない
原因と対応策
認知症によって記憶障害の症状が現れると、お風呂に入ったかどうかもわからなくなります。
また、思考力や判断力が低下するため、自分の身体が汚くても、客観的にそのことを理解できなくなります。お風呂に入る必要性を感じなくなり、拒否するようになってしまうのです。
対策としては、お風呂に入ることを強調せず、「薬を塗る」「足の爪を切りたい」などの理由をつけて、浴室や脱衣所まで誘導します。その後、「浴槽にお湯を入れたのでどうですか」と誘ってみましょう。
NGな対応例
- 「汚いから入ってください」など、気分を害するような誘い方をする
- 無理やり服を脱がせたり、お風呂に入らせたりする
トイレに失敗する
原因と対応策
認知症になると尿意や便意を感じづらくなります。
また、尿意を感じても、その意思を伝えられなくなります。
だからといって、頻繁にトイレに誘うと、本人にとってはその気もないのに連れていかれることになり、不可解で気味悪く感じます。そのような体験が重なることで、トイレに行くことを拒否するようになるのです。
トイレの時間や便意を感じる予兆を記録しておき、タイミングを見計らって誘うようにすれば、次第に改善することが見込まれます。
NGな対応例
- トイレに失敗したことを叱り、自尊心を傷つける
- 介護者側の都合だけでトイレに誘う
不潔な行為
原因と対応策
認知症が進むとにおいを感じにくくなります。便が漏れて便臭が酷くても気がつかないことが多く、弄便はおむつの中の便を手で触ったり、その手で服や家具などを触ったりする行為です。
様々な原因があり、おむつが気持ち悪いと自分で便を処理しようとします。手に便が付着して対処法がわからなくなると、おむつを破り捨て近くのもので拭き取ってしまうのです。
また失禁に対する羞恥心から家族に隠そうと、自分で処理するのも弄便の原因の一つです。
弄便に悪意はありません。責めると弄便が悪化するので、「気がつかなくてごめんなさい」「すぐに綺麗にしましょう」など優しい声がけを行います。
おむつ交換の回数を増やすといったトイレ習慣の見直しも効果的です。
NGな対応例
- 「汚いでしょ」「なんで触るの」と否定的な言葉を使う
- 大きな声を出して怒鳴る、感情的に叱る
- 弄便を防ぐ目的で本人に身体拘束をする
- 手が汚いからと無理やりお風呂場へ連れて行き、洗い流す
- 手についた便をそのままにする
夜になると騒ぐ
原因と対応策
認知症になると不安な気持ちから夜に眠れなくなり、昼と夜とが逆転して不眠になる場合があります。不安な気持ちを取り除き、規則正しい生活を促すと改善が期待できます。
日中はできるだけ日の光が差し込む明るい部屋で過ごし、可能であれば散歩やデイサービスに出かけるようにしましょう。
夜にぐっすり眠れるよう昼間によく身体を動かしたり、寝室の照明や音、インテリアなどを落ち着ける雰囲気のものに変えたりするなどの対策も効果的です。
NGな対応例
- 夜に眠らないことを叱ったり、不安を煽るような言動をとる
- 昼間に好きなだけ眠らせたり、不規則な生活を許容する
訪問販売で大量購入してしまう
原因と対応策
認知症によって判断力が低下すると、訪問販売によって悪質商法に騙される可能性があります。
相手の言うことの善し悪しが判断できず、言われるがままに契約をしてしまうのです。自分でお金の管理ができなくなっている場合は、特に注意が必要です。
人とのつながりがなく、孤独を感じている高齢者はなおさら騙される可能性が高くなります。対策として、お金の管理を家族がしたり、成年後見制度を利用したりするのが有効です。
NGな対応例
- 騙されたことをなじったり、叱責したりする
- 本人の意思を無視して、お金が使えないような状況にする
火の始末を忘れる
原因と対応策
認知症の場合、コンロの⽕をつけたまま、料理をしようとしていたことさえ忘れてしまい、⽕事につながってしまうといったことも起こる可能性があります。
本⼈は⾃分が⽕をつけたことや料理をしようとしていたこと自体を忘れているので、⽕事が起こってしまってもその理由がわかりません。事前に対策をしておくことが大切です。
安全のために、室内には火災警報器を設置し、⾃動消⽕機能のあるコンロやIH式のものを使うようにしましょう。
NGな対応例
- 料理を禁止する
- 怒ったり責めたりする
何をする時間かわからない
原因と対応策
時計を⾒て「何時何分」と読むことができるのにもかかわらず、何の時間なのかを問われるとわからない場合がよくあります。
「12時だからお昼」というのがわからないということを理解して、「お昼の時間ですよ」など声をかけるようにしましょう。今は何をする時間なのかを伝えるよう、日々のコミュニケーションのとり⽅を⼯夫しましょう。
NGな対応例
- イライラして怒る
- わからないことを馬鹿にする
家族介護者のたどる4つの心理的ステップ
家族が認知症の介護に関与する際、先行きの不透明さは大きな悩みとなることが多いです。大切な家族が認知症を患い、そのケアが必要となった時、家族は常に「介護者」として多様な感情に葛藤します。以下では、ご本人の認知症が診断されてから、その家族が様々な心理状態をたどり、最終的にご本人の認知症を受け入れ平穏さを取り戻すまでを整理したものです。

体力的にも精神的にも決してストレスゼロとは言えないなかで、介護生活をどう過ごしていけばいいのか、悩んでいる方も多いかもしれません。
川崎幸クリニックの杉山孝博院長は『杉山孝博Dr.の「認知症の理解と援助」』(クリエイツかもがわ)のなかで、認知症の介護をする家族は、4つの心理的ステップを経ると提唱しています。
本人の認知症が診断を通して発覚してから、最終的にその家族が認知症を受け入れるまでが4段階で示されています。これを知っておくことで、先行きの見えない不安から解放され、冷静に状況を判断することができます。
以下でその4つのステップを解説していきます。
ステップ1「戸惑い・否定」
今までできたことができなくなったり、突然言動が変になったりといった認知症による変化は、介護者に戸惑いを生じさせます。
「まさか認知症なはずがない!」と認知症であることを認めたくない気持ちが強く、なかなか周囲へ相談することができない時期と言えます。
ステップ2「混乱・怒り・拒絶」
認知症を発症した本人の現状を否定したところで、症状が良くなるわけでもないと介護者は気づきます。しかし、なんとか対処しようと思っても、どう対応したらいいのかわからないことが多いです。
「混乱」し対応の仕方がわからず、話ができない・現状が改善できない状況に「怒り」を感じるようになります。上手く対応できないことや、思い通りにならないなどの状況から、心も体も疲れ果て、介護を「拒絶」するようになります。
この段階が長引けば長引くほど、認知症の症状も悪化してしまい、負の連鎖に入ってしまいます。
ステップ3「割り切り、あきらめ」
ステップ2の段階を経ると、本人の症状や行動を認知症だから仕方がないと「割り切り」、思い通りにコミニュケーションすることを「あきらめる」ようになります。
ステップ4「受容」
認知症である本人の状況をすべて受け入れ、「人間的・人格的理解」ができるようになるステップ4は、いわば悟りの境地と言えます。
認知症介護をするうえで、この4つの心理的ステップを知っていると、自分が今置かれている状況を冷静に見つめることができます。
ステップ1、2からステップ3へと段階を経るまでの期間を短縮することは、介護者自身を守ることにもつながります。
参考:杉山孝博(2013).認知症の9大法則 50症状と対応策(法研),杉山孝博(2007). 杉山孝博Dr.の「認知症の理解と援助」(クリエイツかもがわ)
認知症介護者の負担を軽減する方法
続いて、介護者の負担を軽減するための方法を解説していきます。
介護疲れや介護うつを避けるには?
1.ひとりで抱え込まず、周囲に協力を仰ぐ
認知症のケアは容易ではありません。全てを介護者だけで対処しようとすると、疲弊してしまうかもしれません。家族や親戚とのコミュニケーションはもちろん、医者や看護師、ケアマネージャー、地域の相談機関といった専門家にアドバイスを求めることが大切です。
2.介護保険内外サービスを検討する
介護者側も自分自身の日常生活も考慮する必要があります。自身だけで抱え込んでしまうと共倒れとなるケースもございます。現在、公的なものから民間に至るまで、多様な介護保険サービスが存在しています。これらを上手く利用することで、家族の負担を軽減させることができます。
3.否定をせずに行動の背景を理解する
認知症の方が示す行動や言葉には、一見理解しにくいものもありますが、それには本人自身の背景や理由が隠れています。直接否定するのではなく、その背景や動機を探る心の余裕を持つことが大切です。行動や言葉の背後にある意味を理解すれば、どのように対応すれば良いかも多少なりとも見えてきます
4.周囲と比較しない
認知症の進行は人それぞれで、症状がゆっくりと進行する人もいれば、短期間で重くなる人もいます。他人の状況との比較は、かえって本人やその家族の心に負担をかけることがあるため、避ける方が賢明です。
まとめ
認知症の介護は、症状を理解し、本人に寄り添った対応が必要です。しかし、介護する側がストレスを溜めすぎて倒れてしまうと、その後のサポートができなくなってしまいます。
介護に限界を感じたときは、介護疲れや介護うつになる前に第三者へ相談しましょう。かかりつけ医や専門医、もしくは地域包括支援センターなどの公的機関を利用することも解決への一歩です。
最近は介護者が一時的に被介護者のお世話から離れる「レスパイト」が推奨されています。介護保険にはレスパイトを目的とした介護サービスもあるので、適宜、利用することをおすすめします。
介護は終わりがみえないものです。頑張りすぎず、ひとりで抱え込まないことが、介護者自身の心身の健康を保ち、介護を続けていくためには大切です。
認知症に関する相談窓口
介護をする際には、自分だけで抱え込まず、周囲や公共の相談窓口を利用するようにしましょう。
認知症に関する相談窓口は以下の通りです。
| 認知症に関しての悩み | 相談窓口 |
|---|---|
| 認知症の症状 | かかりつけ医認知症疾患医療センター地域包括支援センター独立行政法人福祉医療機構 |
| 介護サービス | 地域包括支援センター自治体の介護保険担当窓口 |
| 介護の悩み | 地域包括支援センター認知症の人と家族の会(0120-294-456) 介護支え合い電話相談(03-5941-1038) |
| 消費者トラブル | 消費者生活センター |
施設入居に関する相談は是非「みんなの介護入居相談センター」をご覧ください。
認知症のケアが手厚い老人ホーム
老人ホームの中には認知症のケアに特化した施設もあります。
以下では、認知症の方におすすめの老人ホームを紹介していきます。
グループホーム
グループホームは認知症の方を対象としており、少人数制で共同生活を送る施設です。
共同生活を送るメンバーは基本的に変わることがないため、環境の変化にストレスを感じやすい認知症の方も穏やかに過ごせます。
他の入居者と分担しながら掃除や料理などの家事をすることで、脳が活性化され認知症の症状を緩和します。さらに、認知症の進行を抑えるためのリハビリも頻繁に行っているのもグループホームの特徴です。
認知症を専門とする施設であるため、常駐するスタッフは認知症のケアに特化しているので、本人も家族も安心できます。
【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説
グループホームを探す住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、生活支援などのサービスが受けられます。施設内にはバリアフリーが完備しているので、足腰に不安のある方も安心して生活できます。
住宅型のメリットは、必要に応じて介護サービスを受けられることです。
入居者が求める生活援助、外部の介護サービスを自由に組み合わせて利用できるため、一人ひとりに適したサービスを受けられるのです。さらに、在宅介護の際に利用していた介護サービスも施設で継続できます。
その他に豊富なレクリエーションやイベント、ニーズに合わせた施設選びなどのメリットがあります。
【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説
住宅型有料老人ホームを探す介護付き有老人ホーム
介護付き有料老人ホームは原則として終身利用が可能なため、重度の認知症や要介護度でも住み続けることができます。慣れ親しんだ場所で最期を迎えたい本人や家族の要望に応え、看取りの対応をする施設もあります。
さらに介護付きは24時間、介護職員が常駐しており、夜中でも介護サービスを受けられます。
日中であれば看護職員も常駐し、必要に応じて看護ケアを受けられるので安心できる生活環境が整っています。
また介護付きは施設の数が多く、高齢者一人ひとりの身体状況や認知症の進行具合から施設を選ぶことが可能です。
【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)
介護付き有料老人ホームを探す認知症対応型通所介護(デイサービス)の申請方法
認知症の方の在宅介護の際、介護者の大きな助けとなるのが認知症デイサービスです。プロによる適切なケアが受けられ、介護疲れを感じたときのレスパイトとしても利用できます。
ここでは、その申請方法について説明します。
認知症デイサービスを利用できる条件
認知症デイサービスは、認知症に対応した介護が「通い」で受けられる介護保険サービスです。認知症デイサービスを利用できる方は、次の条件を満たしている必要があります。
- 認知症デイサービスの利用対象者
-
- 認知症と診断され、診断書がある
- 要介護1~5の認定を受けている
- 事業所のある地域に住民票がある
- ※要支援認定を受けている方は「介護予防通所リハビリテーション」が対象サービスとなります
手厚い介護が期待できる
専門的な認知症ケアが受けられる認知症デイサービスは、少人数制で家庭的な雰囲気であることも特徴です。
制度上、定員12名以下となっているため、手厚い介護が期待できる一方で、通常のデイサービスよりも利用単価が高く設定されています。
認知症デイサービスの利用申し込みをしよう
認知症の方を在宅で24時間介護をするのは、家族にとってかなりの負担になります。
まずはケアマネージャーに相談をし、認知症デイサービスが利用できるか相談してみましょう。
- 認知症デイサービス利用開始までの流れ
-
- ケアマネージャーに相談・検討
- ケアプランの作成
- サービス提供事業者選び
- 契約・サービス利用開始
ケアマネージャーに要望を伝えよう
担当ケアマネージャーに、「どんなことで困っているのか」「どんなサービスを受けたいのか」を伝え、候補となるサービス提供事業者を紹介してもらいましょう。利用のためには、ケアプランの作成も必要です。
認知症デイサービスには、「単独型」と他の介護施設の一部を利用している「併設型」、グループホームの共用スペースで施設の入居者と一緒に過ごす「共用型」の3タイプがあります。
それぞれ利用金額も異なるので、利用開始前には料金とサービス内容・雰囲気などを確認します。また認知症に特化したグループホーム(認知症対応型共同生活介護)の入居を検討するのも良いでしょう。
グループホームを探す認知症デイサービスの内容
重度の認知症でも利用できる、認知症デイサービスが提供するサービスは、主に次のようなサービスです。
- 送迎
- 健康チェック
- 入浴介助
- 機能訓練
- レクリエーション
- 食事介助
1日あたりの利用時間は「3時間以上5時間未満」「5時間以上7時間未満」「7時間以上9時間未満」の3つのタイプがあります。
認知症デイサービスを利用する際には、自宅までの送迎もあるので家族としては安心。
体温や血圧などの健康チェックから、入浴介助、リハビリテーション、レクリエーションなどを通じて、日中を活動的に過ごせるよう配慮されています。
一般のデイサービスとの大きな違いは、認知症デイサービスは少人数制(定員12人まで)で認知症介護を専門とするスタッフがいることです。レクリエーションでは、利用者1人ひとりの状況を見ながら対応してもらえます。
アットホームで家にいるような感覚でくつろいで過ごせるため、行動・心理症状が落ち着いてくるなどのメリットもあります。
家族を応援する認知症サポーター
高齢化社会を迎えた今、認知症の方とその家族が安心して生活するための見守り体制づくりが必要となっています。
そんな中、近年増えているのが認知症サポーターと呼ばれる「認知症を正しく理解し、支える人」たちです。
認知症サポーターとは?

認知症サポーターは、認知症を正しく理解し、認知症の方と家族を応援する人のことです。厚生労働省も「2020年までに1,200万人」という数値目標を掲げ、その養成に力を入れています。
警視庁では、現在すべての警察官・職員に対して、認知症サポーター養成講座の受講を義務化しています。
2023年6月末時点で、認知症サポーターには約1,465万人が登録されています。
出典:「サポーターの養成状況」(特定非営利活動法人 地域共生政策自治体連携機構)
認知症サポーターになるためには?
特定非営利法人「全国キャラバン・メイト連絡協議会」では、認知症サポーター養成講座を全国で実施しています。養成講座は、各都道府県や市区町村窓口で受付を行っており、無料で受けることができます。
受講時間は1時間から1時間半。専用のテキストに沿って、認知症という病気への理解を深めていく講座です。
家族や介護・医療関係者だけでなく、地域住民が認知症に対して正しく理解することは、お互いが暮らしやすい社会をつくるために必要なことです。
ぜひ、みなさんも機会があれば認知症サポーター養成講座を、受講してみてはいかがでしょうか。
認知症になったときに自動車免許はどうするのか
高速道路の逆走など、認知症の方が車の運転中に事故を起こしてしまうニュースなども多く報道されています。ここでは、家族が認知症とわかったら、運転免許に関してどのような対応をすれば良いのか解説します。
認知症の方にかかわる道路交通法改正の主な項目
2017年3月に改正道路交通法が施行され、75歳以上のドライバーに対して、認知症対策が強化されています。
主な変更点と現行の概要は次の通りです。
- 運転免許更新時
-
- 運転免許の更新時に「認知機能検査」が必須に
- 認知症の恐れがある場合には臨時適性検査もしくは診断書の提出命令
- 「認知機能検査」で認知機能低下となった場合には、3時間の講習が必須に
- 認知症だという医師の診断結果が出たら免許取り消し・停止
- 一定の違反行為があったとき
-
- 臨時認知機能検査(新設)を受けることが必須に
- 臨時認知機能検査を受けない場合には免許取り消しまたは免許停止処分
- 更新時の認知機能検査よりも臨時認知機能検査の結果が悪い場合には「臨時高齢者講習」を受講
検査で認知症を疑う結果が出たら?
車の免許更新時に行われる「認知機能検査」や、違反行為があった時に行われる「臨時認知機能検査」で認知症の恐れがあるという結果になった場合には、認知症専門医などによる診断を受けるか診断書を提出しなければいけません。
これは、認知症の疑いがある方が運転するリスクをなくすための対策で、仮に診断結果が認知症となった場合には、免許取り消しもしくは停止対象になります。
家族も運転させない環境づくりを!
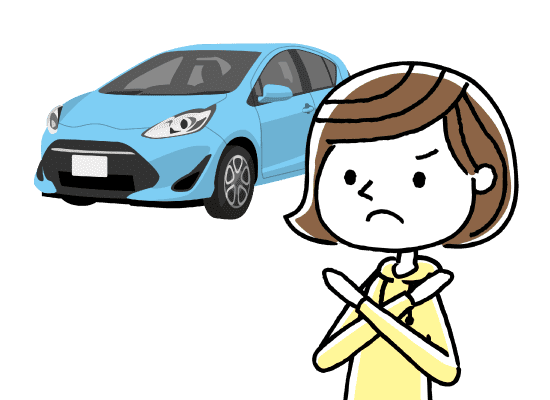
認知症の疑いがある場合、家族としては本人に運転させないことがベストです。
車を使わなくても外出できる移動手段の確保などの問題もありますが、事故を起こしてしまう前に、しっかりと対策が必要です。
もしも認知症の家族が運転を止めようとしない場合には、免許の返納や車の鍵を隠す、車自体を処分するなど運転できない環境をつくることも検討します。
その際、強い反対をされるようなら、まずはこれまでの感謝の気持ちを伝えつつ、運転ができなくなった場合の対応策や、身体的な機能の低下について指摘して説得しましょう。
最近では、運転免許証を自主返納することを推奨する自治体も増えています。
運転免許の返納は、各自治体の運転免許センターもしくは警察署で申請できます。返納すると免許証にそっくりの「運転経歴証明書」が発行されます。
また、自治体によっては免許返納を推進するために、さまざまな特典を設けていることも多いです。タクシーやバスの乗車割引、商品券、商店街・デパートやレストランの割引などお得な特典も多いので、ぜひ活用しましょう。
認知症の治療とリハビリ
最後に、認知症の治療方法とリハビリについて解説していきます。
認知症の治療方法
認知症の根本的な治療法は確立されていません。認知症の治療は進行を緩やかにしたり、症状を軽減したりすることを目的とします。大きく分けて薬物治療と非薬物治療があります。
薬物治療は、記憶障害など認知機能の低下の進行を遅らせます。また日常生活に悪影響を与える行動・心理症状を抑えるために、睡眠導入剤や抗不安薬などを処方します。
非薬物治療も薬物治療と同じで進行を止めたり、根本的に治療するものではありません。薬を使わずに脳を活性化させ、残っている認知機能や生活の質を高めることが狙いです。
非薬物治療は料理や洗濯などの生活リハビリ、脳トレやゲームなどのリハビリ、園芸・音楽療法、回想法などがあります。
行動や心理は本人にとって意味のあるもので、無理に抑制するのは良くありません。医師と相談して本人に適した治療法を選びましょう。
認知症のリハビリ

認知症には根本的な治療はありません。しかしリハビリで症状を和らげたり、進行を緩やかにする効果が期待されます。
運動療法はウォーキングや軽いジョギング、体操、ストレッチなどを行います。体を動かすことは心身の機能を高めます。本人の興味のある運動を始めると無理なく続けられるでしょう。
作業療法は食事や家事など日常生活の作業を行い、心身機能の維持強化を図り、自分らしく暮らせるように導きます。また社会とのつながりを取り戻すのも役割のひとつです。
回想法は過去の写真や映像を見たり、会話から昔を思い出して、その人の人生を振り返ります。本人の話を否定せず受容する姿勢が大切です。
音楽療法は音楽を聴いたり歌うことで脳を活性化します。1人で音楽を楽しむ、仲間や家族でカラオケを楽しむなど、本人に合った方法で行います。
レクが充実しているグループホームを探す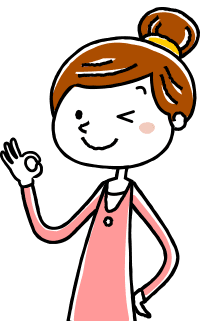 この記事のまとめ
この記事のまとめ- 認知症の方の行動や言葉にはすべて意味がある
- 認知症を理解して本人に寄り添うことが大切
- 間違いを強く否定せず、受け入れる
- 食生活の改善や、適度な運動で認知症を予防する
- 認知症の治療法は薬物治療と非薬物治療がある
- 運動療法、作業療法、回想法、音楽療法の4つのリハビリがある
- 介護疲れや介護うつになる前に第三者へ相談する
他の人はこちらも質問
認知症の人とどう接するか?
認知症の方は不安を抱えて過ごしているため、日常生活では何気ないコミュニケーションを心がけ、不安を取り除くことが大切です。また、認知症の方が考えて発した言葉に間違いがあっても否定するのは控えましょう。受け入れて自尊心を傷つけない声かけが求められます。
認知症にどう対応する?
認知症の方の対応は、本人の気持ちに寄り添うことが必要です。物事を始めるときは、わかりやすい言葉で繰り返し伝えます。また、会話をするときは目線を合わせたり、生活リズムを認知症の方に合わせたりしましょう。
高齢者が同じことを何度も言うのにどのように対応?
同じ話を繰り返していても注意はせず、相槌を打ったり肯定したりするなど、優しく対応します。温かい目で見守ることで、高齢者は安心できるでしょう。
認知症とはどんな症状か?
認知症の前兆は主に物忘れです。進行すると記憶障害や見当識障害(時間や場所がわからない)、判断力の低下などの中核症状、BPSD(行動・心理症状)などが見られます。












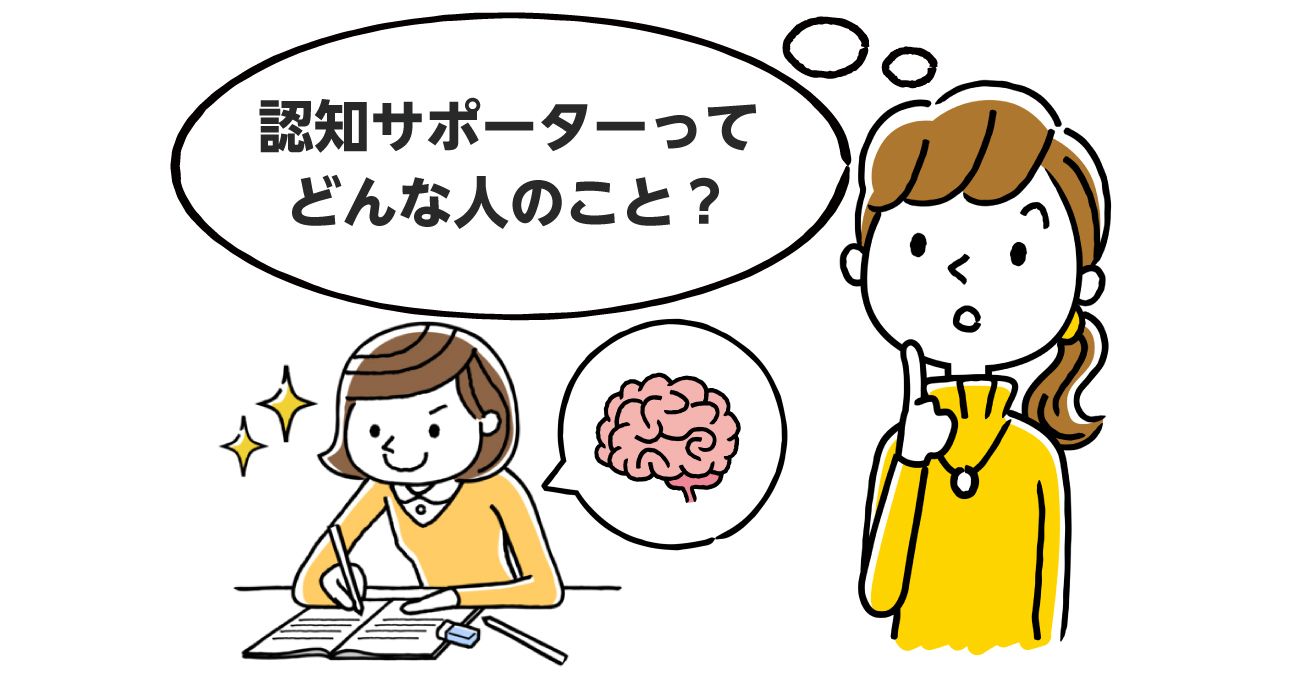
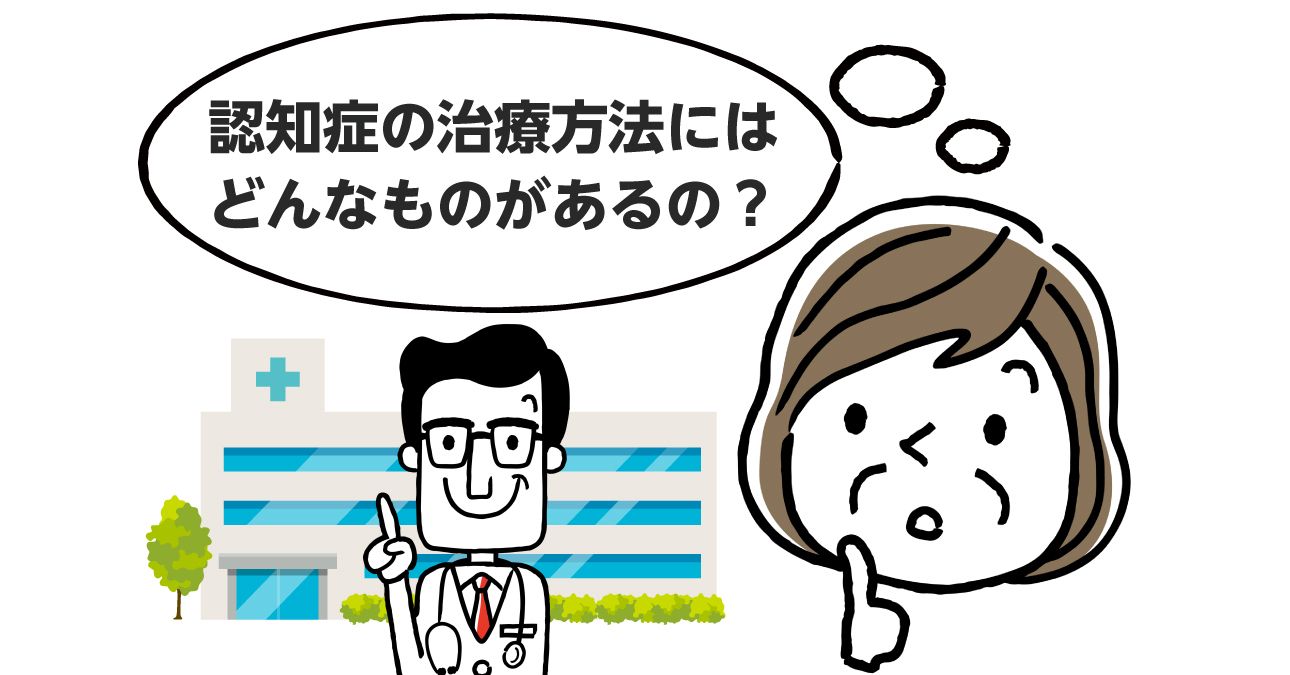
 この記事の
この記事の