老人ホーム開設の前に
有料老人ホームの定義とは
有料老人ホームとは、介護サービスや生活援助、日々の健康管理など、入居者の心身の状態に応じてサービスを提供している居住施設のことです。
有料老人ホームを運営するには、一定の基準を満たしたうえで、都道府県に届け出さえすれば自由に開設することができます。2006年4月の老人福祉法の改正によって、それまでの人員基準が撤廃されたため、有料老人ホームに当てはまらなかった小規模な施設からの申請が相次ぎ、一気にその数を増やしました。
入居条件は60歳以上、もしくは65歳以上と規定している施設が多く、夫婦で入居の場合はどちらか一方だけでも条件に当てはまっていれば入居可というケースがほとんどです。
また、有料老人ホームには自立、もしくは要支援の方が入居できる施設と、要介護の方が入居できる施設があり、それぞれ目的やサービスが異なります。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、60歳以上の高齢者であれば基本的に誰でも入居できます。食事や清掃、安否確認、緊急時の対応、生活援助、レクリエーションなどは提供されますが、介護は外部のサービスを利用します。
ただし、介護付き有料老人ホームの基準を満たしているにもかかわらず、総量規制のためにやむなく住宅型として運営しているケースもあり、在宅サービス事業所を併設しているなど、比較的介護が受けやすい施設もあります。
介護付有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、「特定施設入居者生活介護」の許可を得て、施設職員による介護サービスを提供できる介護施設です。要介護認定を受けた方だけが入居可能な「介護専用型」と、自立や要支援の方を対象とする「混合型」があります。混合型には自立状態を入居条件としている「入居時自立」という施設もあります。
サービス内容は、食事や入浴、排泄介助などの介護サービスのほかに、清掃、洗濯などの生活支援サービス、リハビリテーションや、レクリエーションなどが入居者の状態に応じて提供されます。
健康型有料老人ホーム
健康型有料老人ホームは、自立した高齢者が対象となっています。
最近は減少傾向にありますが、レストランや露天風呂、スポーツジムなど日常生活を楽しむための施設が充実しているのが特徴です。
サービス内容は家事手伝い程度ですが、一人暮らしが不安な方や家事をするのが面倒な方などが、同世代と楽しく生活するために入居されます。基本的に自立や要支援の方向けの施設なので、要介護認定を受けると退去となります。
ただし、介護付き有料老人ホームなどが要介護者を受け入れている施設が隣接している場合もあります。
サービス付き高齢者住宅の定義とは
サービス付き高齢者向け住宅は、民間事業者が設立・運営する賃貸住宅です。「サ高住」や「サ付き」とも呼ばれるこの施設は、要介護者が中心の有料老人ホームとは違い、主に自立や軽度の要介護者を受け入れています。
建物はバリアフリーであることが必須条件になっているため、段差が少ないフラットな造りであったり、スロープや手すりが付いていたりするなど、高齢者にやさしい住宅になっています。
サービス内容は主に生活支援や安否確認ですが、日中は生活相談員が常駐しているので、生活上のあらゆる相談にのってもらえます。ただし、介護が必要になった場合は施設内で対応できないため、在宅介護と同様に訪問介護など、外部の介護サービスを利用することになります。
有料老人ホーム・サ高住の開設費用はいくらくらい?
有料老人ホーム・サ高住の建設費用はアパートよりも高い!?

有料老人ホームにせよサービス付き高齢者向け住宅にせよ、家賃収入は大きな収入源です。
そこで注目されるのが、設立にあたってかかる費用です。有料老人ホームであればバリアフリー化するのは必須ですし、サービス付き高齢者向け住宅であれば、「床面積が原則25㎡以上」「便所・洗面設備などの設置」といった項目も含まれてきます。
この基準を満たすためには、一般的なマンションやアパートなどの賃貸住宅より建築コストがかさむのは避けられません。そのコストを利用者に反映するのも市場の性格上難しく、収益性がダウンする可能性が高いことを念頭に置いておいた方が良いかもしれません。
定員20人程度の施設の開設にかかる費用は約3億円!?
こちらは、実際にあった例ですが、定員18名のデイサービスを併設した住宅型有料老人ホームで20部屋の居室を有し、土地面積250坪(建物延床面積 約300坪)の場合にかかった費用です。
| 土地購入費 | 1億円(坪40万円) |
|---|---|
| 建設費 | 2億1,000万円(坪70万円) |
| 設備・備品 | 1,500万円 |
| 営業・販促費 | 200万円(パンフレット、ホームページ、広告など) |
| 求人費 | 300万円 |
| 合計 | 約3億3,000万円 |
やはり、最も高額になるのは物件の取得費用。
例えば居抜きで物件を取得したとしても、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の仕様に変更するために大規模なリフォームが必要となったり、什器などが必要になったりもするため、相応の費用がかかることが珍しくありません。
会社設立費用
新規参入で介護施設を開設するときは会社を設立するのが一般的ですが、そのためには定款作成や登記する際にかかる法定費用が必ず必要になります。代行業者に依頼すれば経費を削減することもできるので、上手に利用しましょう。
物件取得費
まずは開設する場所を確保しなければなりませんが、物件の取得や賃貸契約をする際には費用がかかります。賃料や保証金、仲介手数料、初回家賃手数料、敷金などは物件や業者によって異なるので、予算に見合った場所を探す必要があります。
設備・備品費など
物件が見つかって契約が済めば、次に必要なのは施設内で使う設備や備品などの調達です。平均して3,000万円ほど必要ですが、開設当初の資金繰りが厳しい場合は、必要最低限のものだけを揃え、後は運営をしながら揃えていくのも良いでしょう。
人件費
介護サービスを提供する人材を確保しなければなりません。一般的に人件費は売上の40%程度とされています。直接雇用するのが難しい場合は、人材派遣会社や人材紹介会社を使うことになります。コストはかかりますが、確実に人材を確保できます。
求人広告費
採用コストをできるだけ抑えたい場合は、成功報酬型の求人サイトを利用するのが良いでしょう。採用が決まった場合だけ報酬として数万円から数十万円を支払います。地域の求人情報誌などを利用すると、掲載するサイズによりますが、採用の有無にかかわらず約2~50万円の経費がかかることになります。
指定申請手数料
介護施設を運営していると、各都道府県自治体に申請・届出をする機会がたくさんあり、それに際して手数料がかかるタイミングが発生します。具体的にはサービスや利用料金の変更時、入居者の定員の変更時、施設長変更時、施設の改修や増築時などです。
有料老人ホーム・サ高住の開業資金調達
日本政策金融公庫の創業支援
日本政策金融公庫は、開業支援を積極的に行っている政府系の金融機関です。「新創業融資制度」を利用すれば無担保無保証、連帯保証人の署名不要で最大3,000万円を借りることができます。申し込みから1ヵ月ほどで融資が実行されますが、金利が少し高くなるのがデメリットです。
女性、若者/シニア起業家支援資金
事業開始からおよそ7年以内の方に向けて実施されている、起業家支援資金(新企業育成貸付)です。35歳未満から55歳以上の若者や女性、シニアが対象です。限度額の7,200万円のうち4,800万円は運転資金として貸し付けられ、担保や保証人については相談可です。
公的融資
独立行政法人福祉医療機構(WAM)が民間の福祉活動に対する助成金と融資を行っています。ほかにも、公的融資は各都道府県や市町村などの自治体によって実施されているものもあります。詳細は各自治体のホームページなどで確認してください。
銀行などからの融資
各銀行が、高齢者施設サポートローンや介護施設提携ローンなど、有料老人ホーム向けの融資を行っています。サービス付き高齢者向け住宅の場合は不動産取得税優遇、固定資産税優遇などの優遇措置があるうえに、建設や設立に対する補助金や助成金も受けられます。
固定資産税優遇
国や地方公共団体などから建設費に対する補助金を受けている場合は、要件を満たすことで最大5年間、固定資産税の軽減措置が受けられます。軽減率は各市町村によって異なりますが、最大83%から50%の減税になります。
不動産取得税優遇
サービス付き高齢者向け住宅に限ったことですが、新たにサ高住を開業するときの不動産取得時にかかる不動産取得税が控除の対象になります。
サ高住の開設では、助成金を上手く活用したい
サービス付き高齢者向け住宅の開設にあたっては、国からの補助金交付の対象となっているため、費用負担はかなり軽くなるはずです。
| 高齢者向け住宅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補助率 | 限度額 | 注意事項 | |||
| 新築 | 夫婦型 | 住戸床面積30㎡以上 (便所、洗面所、浴室、台所、収納完備) |
1/10 | 135万円/戸 | 補助申請する戸数の2割以内が上限※入居世帯を夫婦などに限定する場合を除く |
| 一般型 | 住戸床面積25㎡以上 | 120万円/戸 | ー | ||
| 住戸床面積25㎡未満 | 90/戸 | ー | |||
| 改修 | 1/3 | 180万円/戸 | 調査設計計画費用も補助対象になる | ||
この点については「」のページで詳しくご説明しているので、ぜひ参考にしてください。
一方で有料老人ホームは、そうした補助金や助成金は期待できません。国が「施設から在宅へ」という方針になっているため、仕方のないことかもしれませんが、“有料老人ホームの開設には補助金・助成金はない”ということは、しっかりと頭に入れておいてください。
オリンピックや復興による建設コストの増加
2011年に東日本大震災が発生したことから、復興需要が高まり、それに伴って老人ホームの建設費用は年々上昇。その後、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに向けた首都圏の開発事業が始まり、坪単価が20%~30%も増加している状況は、新規参入を計画する介護事業者に打撃を与えています。今後も少子高齢化は進むと考えられることから、初期投資に巨額な資金が必要であっても、新規参入は続くと思われます。
しかし、この状況に乗じて法外な請求をしてくる建設業者も増えています。まずは、信頼できる業者を見つけることが大切です。
建設コストを抑えるコツ

土地活用を提案する賃貸住宅専門の建設会社でも、介護施設を手がけるところが増えてきました。そのため、このような専門業者に依頼することで坪単価を抑えられる可能性が高くなります。介護施設の建設には数千万円から数億円かかるので、坪単価が数万円程度の違いだけでも最終的には数千万円の違いになることもあります。
ほかに建設コストを抑える方法としては、共有スペースを有効活用することが挙げられます。サ高住や有料老人ホームであれば、キッチンやお風呂を共有にしても問題ありません。管理体制や清掃などを整えることが大前提ですが、選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。
共有スペースをつくると高齢者のコミュニケーションも生まれる

こうして建築コストを抑えることは同時に、入居者同士のコミュニケーションという副産物も生み出します。
例えば食事のために食堂に行くとき、入浴のために大浴場に行くときなど、生活のさまざまなシーンでつながりができることで、毎日にメリハリが生まれたり、高齢者のQOL(=生活の質)の維持・向上を図れたりすることもあるのです。
つまり、単にコスト削減のためというだけでなく、入居者となる高齢者の生活を考えたうえでも、共同住宅にはないメリットが、共有スペースを上手く活用している有料老人ホームやサ高住にはあるということ。
もちろん、個人によっては完全にプライバシーを守りたいというニーズもあるでしょうし、ターゲット次第では共同住宅仕様にした方が良い場合もあるでしょう。
一概には言うことはできませんが、「共同住宅仕様にするのか、共有スペースを多く活用するタイプにするのか」という点についても、有料老人ホーム・サ高住を開設する際に検討してみると良いでしょう。
設立に必要な準備
開業手続き
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を開業するときは、公的施設である特別養護老人ホームなどと同様、自治体から開設許可を得るなどの手続きが必要です。
また、介護事業を始めるためには法人である必要があります。
人員配置などの要件を満たす必要がある
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅としての要件を満たすための設備、備品をそろえ、一定のスペースを確保することや、適正な人員配置が必要になります。
また、開業後は、運営基準に沿った事業運営を行わねばなりません。




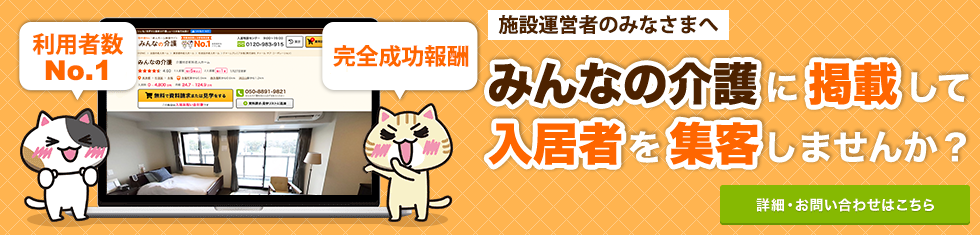
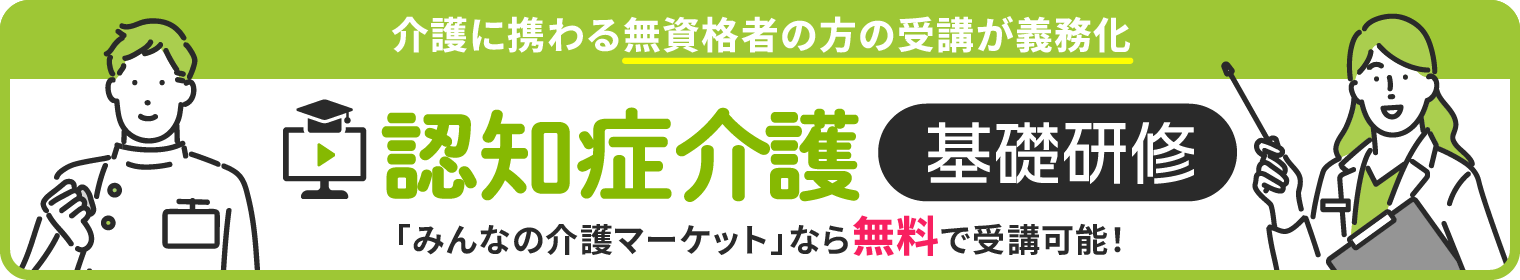


 この記事の
この記事の