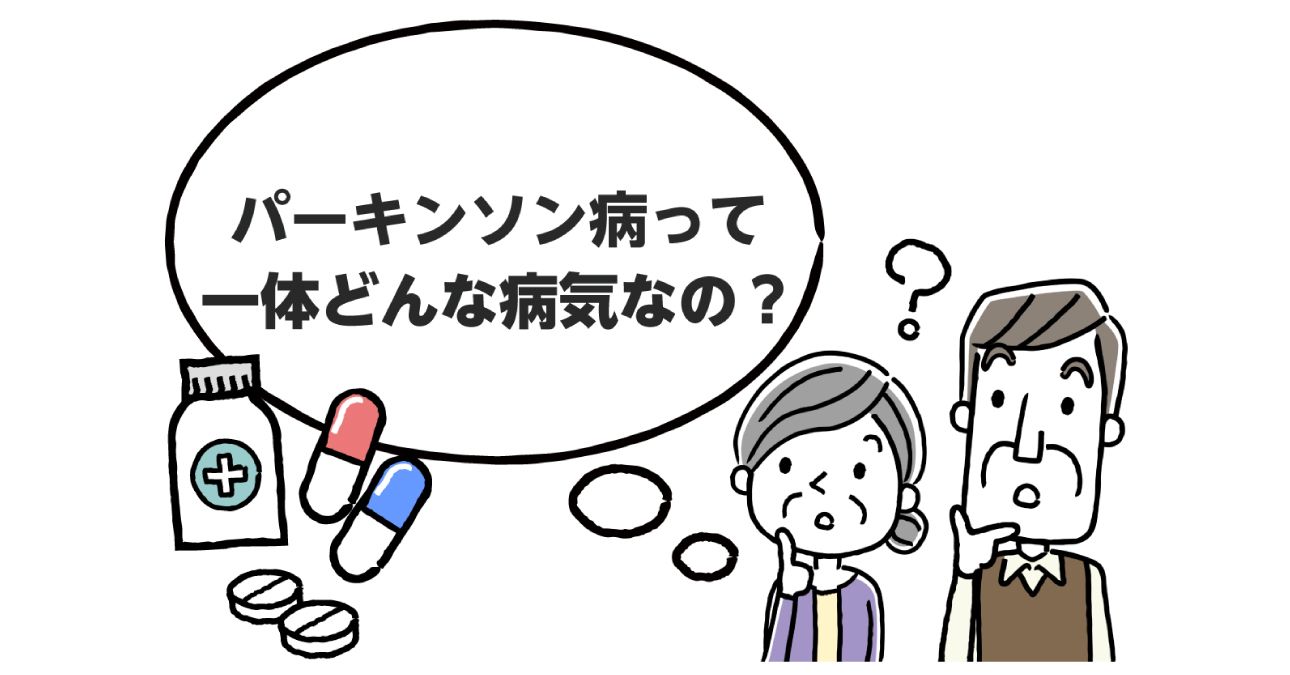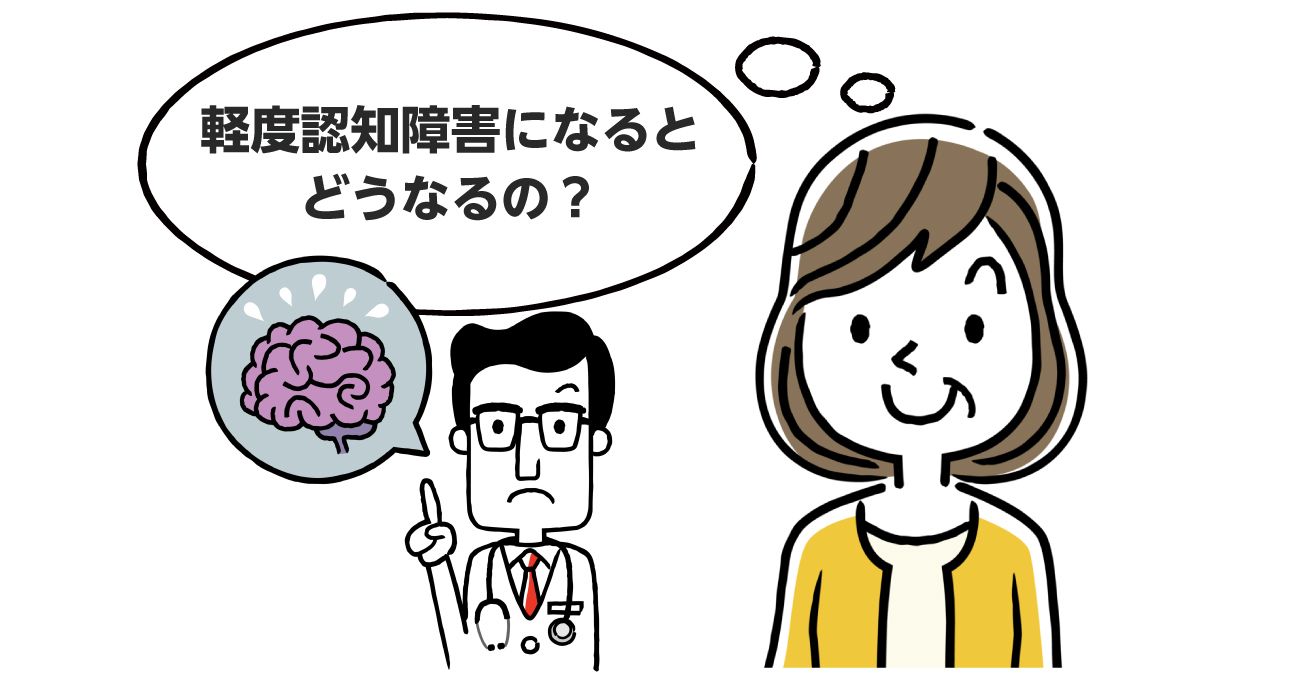認知症の検査費用
認知症の検査には問診のほかに、CTやMRIといった費用が高い検査が行われます。
その他、認知機能テストや血液検査なども行われます。脳梗塞・脳出血などの脳血管障害が原因の脳血管性認知症であれば、定期的な検査費用も必要です。
その主な検査の種類は以下の通りです。
- 認知機能テスト
- 知的機能や認知機能を把握するための心理検査で、設問に答える形が多いです
- CT検査
- X線を使って身体の断面を撮影します
- MRI検査
- 磁気の共鳴によって、身体の断面を撮影します
- SPECT検査
- ごく微量の放射性物質を含む薬を体内に投与して、臓器の状態を撮影します
- MCIスクリーニング検査
- 原因物質を排除もしくは毒性を弱めるタンパク質の状態を調べます
- APOE遺伝子検査
- 認知機能低下に関与する「ApoE遺伝子」調べる検査です
認知症検査の種類
認知症の検査は「神経心理学検査」と「脳画像検査」と「遺伝子検査」に分かれます。以下で、それぞれの特徴を解説していきます。
神経心理学検査
神経心理学検査では、認知機能を検査することができます。
最も有名な検査として、改正長谷川式簡易知能評価スケールがあります。時間や場所、人間関係や計算力を問う問題が多く、所要時間は10〜15分ほどです。
ただし、体調によって結果が変動することが多く、検査結果だけで認知症の判断をすることはありません。
その他に、MMES検査(ミニメンタルステート検査)や高齢者うつスケール(GDS)などがあります。
MMES検査は世界で使われる認知症の検査方法であり、見当識をはじめとする計算力や図形描写力が問われます。
脳画像検査
脳画像検査では、脳の形を調べます。脳の萎縮の状態や脳梗塞、脳腫瘍などを確認し、治療で症状が緩和すると、認知症が改善される可能性があります。
基本的な検査はCT検査やMRI検査で、検査から脳の記憶を司る海馬の萎縮がみられた場合、アルツハイマー病の疑いがあると判断されるケースが多いです。
また、脳の動きを調べるのに使う検査はSPECT検査、PET検査です。SPECT検査は微量の放射性物質を含んだ薬を飲み、臓器を確認します。
一方、PET検査は脳の働きを画像化し、ブドウ糖や酸素の代謝から脳の状態を調べます。
遺伝子検査
APOE遺伝子検査でアルツハイマー型認知症の遺伝的リスクを調べます。
APOE(アポイー)遺伝子は、アルツハイマー型認知症の原因でもあるたんぱく質のアミロイドβに関係する遺伝子であり、APOE遺伝子を多くもっていると、アルツハイマー型認知症の発症リスクが高まるのです。
遺伝子型は3種類あり、その中でも最もリスクの高いε4は最もリスクの低いε2やε3よりも12倍ほどの発症リスクがあります。
しかし、ε4があっても必ず認知症を発症するとは限りません。生活習慣の改善などでリスクを軽減できる可能性もあります。
認知症検査の種類別の費用

下記は、主な認知症の検査を受けたときにかかる費用の一覧です。受診する医療機関によって、金額は異なります。
| 検査種別 | 10割※ | 3割※ | 1割※ |
|---|---|---|---|
| 認知機能テスト | 700円~2,800円 | 220円~850円 | 70円~280円 |
| CT | 1万5,000円~2万円 | 4,500円~6,000円 | 1,500円~2,000円 |
| MRI | 1万5,000円~3万円 | 4,500円~9,000円 | 1,500円~3,000円 |
| SPECT | 8万円~10万円 | 2万4,000円~3万0,000円 | 8,000円~1万円 |
| MCIスクリーニング | 1万5,000円~2万5,000円 | - | - |
| APOE遺伝子 | 1万5,000円~2万5,000円 | - | - |
※自己負担割合
認知症のタイプにもよりますが、認知症の検査費用は意外と高額になることもあり、経済的な負担はある程度覚悟しておいたほうが良いでしょう。
認知症検査の流れ
認知症の検査費用がわかったところで、続いて認知症の診断はどのように受けるのか解説していきます。
認知症検査は何科で受けるのか
認知症が疑われた場合、まずは「かかりつけ医」に相談して、必要であれば認知症専門医への紹介状を書いてもらいます。
認知症専門医とは、日本老年精神医学会や、日本認知症学会が認定した認知症を専門とする医師のことです。認知症専門医の多くは全国250ヵ所以上に設置されている認知症疾患医療センターに在籍しています。
かかりつけ医が決まっていない場合は、近くの病院やクリニックの精神科や心療内科、老年内科、神経内科、脳神経外科などを受診しましょう。
最近では、もの忘れ外来や認知症外来といった認知症専門医が在籍する病院も増えてきています。これらの外来では、基本的にどの科でも認知症の検査が受けられます。
また、本人が病院に行くのを嫌がるようであれば、地域の保健所の高齢者相談などを利用してみましょう。
1.問診
認知症の検査では、まず最初に問診が行われます。
問診は医師が患者に症状を尋ねて現在の状態を調べます。主に聞かれる内容は、症状や違和感に気がついた時期、既往歴などです。
問診を通して、本人の記憶力や理解力などの認知能力の状態も探ります。ただ、認知症が疑わしい場合、本人の話だけでは正確な状態を掴みにくいこともあります。そうしたときは、一緒に生活する家族にも質問します。
医師の質問に答えられるように、普段から気になることがあればメモにしておくと安心です。
2.身体検査
身体検査では、認知症を引き起こす病気を発症していないかを調べます。
行われる検査は尿検査や血液検査、内分泌検査、心電図検査などです。検査の種類によって検査時間は異なりますが、1時間以上かかる検査もあります。
さらに身体検査から、認知症以外の病気が潜んでいないかの確認もします。今後の医療・介護の方針を決めるためでもあるので、身体検査は大切な検査となります。
3.脳の画像検査
脳の画像検査では、脳の萎縮状態などを確認したり、脳の動きをみたりするなどの検査をし、脳腫瘍や慢性硬膜下出血、特発性正常圧水頭症などの発症の有無を調べます。
これらの病気は治療して症状を改善することにより、認知症が治る場合もあります。
しかし、早期治療でなかった場合、認知症の改善が見込めないこともあります。治療で改善が見込まれる脳の疾患を見落とさないために、脳の画像検査が行われます。
4.神経心理学的検査
神経心理学的検査では、言語や思考などの高次脳機能障害を定量・客観的に評価します。
基本的に臨床心理士と1対1で行われ、知的や実行機能などが正常であるかの検査をし、結果から一定の基準を下回ると、認知症の可能性があると判断されます。
しかし、検査を受ける方は緊張や不安などから、普段通りの対応ができないときがあります。
本人の気持ちを安心させ、傷つけるために検査をしているのではないと伝えることが大切です。
認知症の治療費用
認知症の診断を受けたあとは、治療が行われます。
治療内容と費用を解説していきます。
認知症の治療にはどんなものがある?
まず最初に、認知症の治療内容について解説していきます。
認知症の根本的な治療法はない
認知症のなかには、慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症など、認知障害の原因を取り除くことで治るものもあります。
しかし、そうではない認知症の場合、根本的な治療法は現在のところ発見されていません。
症状の緩和や進行を遅らせるための対処法は、「薬物療法」と「非薬物療法」に分かれています。
次章では、その2つを詳しくみていきます。
薬物療法
薬物療法で使われる、いわゆる「認知症治療薬」とは、根治ではなく症状の進行を遅らせることを目的とした薬です。
症状が初期の段階から治療を始めれば、それだけ軽度の状態を長く維持できます。
そのため、早期発見と早期治療が認知症対策として重要になるわけです。
認知症の症状には、発症すれば誰にでも現れる「中核症状」と、本人の性格や生活歴、環境により生じる「BPSD(行動・心理症状)」とがあります。
中核症状としては、物忘れが起こる「記憶障害」、時間や場所が認識できない「見当識障害」、日常的な動作が実行できない「失行」などが代表的です。
一方、BPSDでは、不安や抑うつをはじめ、興奮や徘徊など、普段の生活に影響が出てくることも起きてきます。
認知症の薬物療法には、中核症状とBPSDのそれぞれに対応するものが使用されてきました。
中核症状が脳内の「アセチルコリン」という神経伝達物質が不足して起こることから、「アセチルコリンを抑制する酵素を抑える薬」や「神経伝達物質の効果を調整する薬」などが用いられています。
また、BPSDに対しては、主として「意欲を高めて、活動的になってもらう薬」と「気持ちを静めてもらう薬」の2種類を区別して使われているのが現状です。
以下に一覧でまとめました。是非ご覧ください。
| 効果のある症状 | 薬の種類 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 中核症状 | アリセプト | 認知機能の改善とともに、意欲改善 |
| メマリー | 認知機能の改善とともに、不安やイライラの軽減 | |
| 周辺症状 | リスパダール、アリピプラゾール | 興奮、幻覚、妄想の抑制 |
| サアミオン | 脳の活動を活発にさせる、意欲低下の解消 | |
| 抑肝散 | 興奮や幻覚、徘徊などの症状緩和 |
非薬物療法
認知症の治療としては、薬物を用いない「非薬物療法」も行われています。
さまざまな方法がありますが、基本的には、脳を活性化することや、残された身体機能を活かして生活能力を維持または向上することを目的とするものです。
本人の心身状態や気持ちに合わせて、無理のない範囲で行われます。
また、認知症の症状を穏やかにするにあたって、否定したり叱ったりしないなど、家族や周囲の人の対応方法も重要になってきます。
下記は、主な非薬物療法の一覧です。
- 回想法
- 昔のことを思い出し、人に語ることで、記憶の刺激と感情の安定化を図る
- リアリティ・オリエンテーション
- 日付を確認するなど、見当識障害を解消するために行われる
- 用理学療法・作業療法
- 運動や作業などを通して、自分らしい生活を送れるようにする 例:箸を使うという動きに失行が見られるので、食事動作の練習を行う
- 認知リハビリテーション
- 簡単な計算や字の書き写しなどを行い、自ら考えて行動するための自信を育む
- アニマルセラピー
- 動物に触れることで感情の安定化を図る
- 園芸療法・音楽療法
- 心を落ち着かせ、脳にさまざまな刺激を与える
治療費用
認知症の薬物療法を受ける場合は、当然ですが薬代が必要になります。
例えばアルツハイマー型認知症によく処方されるアリセプトやメマリーなどは、保険適用前の価格で1錠100~650円ほどかかるのが一般的。
イクセロンパッチやリバスタッチパッチなどの貼り薬も、保険適用前で1剤あたり300~500円ほどかかります。
こちらでは、月ごとの薬代を一覧にしました。また、一度に服用する成分の量などによって、1剤の金額は変動します。
| 10割※ | 3割※ | 1割※ | |
|---|---|---|---|
| アリセプト | 5,400円~1万5,000円 | 1,620円~4,500円 | 540円~1,500円 |
| メマリー | 3,900円~1万2,000円 | 1,170円~3600円 | 390円~1,200円 |
| レミニール | 2,700円~6,900円 | 810円~2,070円 | 270円~690円 |
| ・イクセロンパッチ ・リバスタッチパッチ |
9,900円~1万2600円 | 2,970円~3,780円 | 990円~1,260円 |
※自己負担割合
また、定期的にCTやMRIなど高額な費用のかかる検査を受けていかなければなりません。
入院と通院の場合でも費用は大きく変わり、慶應義塾大学の研究によると、2014年度の患者1人あたりの入院医療費は月額34万4,300円、外来医療費が3万9,600円でした。
認知症の治療を開始する場合、ある程度のお金がかかることは覚悟しておく必要があります。
認知症ケアで利用できる介護保険サービス
介護保険サービスを利用する前に要介護認定を受ける
要介護認定を受けると、介護保険サービスを自己負担1〜3割で受けることができます。
認知症の介護には、膨大なお金がかかるため、家族が認知症になった場合には必ず要介護申請を行いましょう。
【目安がわかる】要介護度とは?8段階の状態像と受けられる介護サービス
要介護認定の申請の流れ
要介護認定の申請先は、市町村の窓口です。
申請書や申請者の身元確認、主治医の意見書などを提出し、調査員が自宅訪問をして本人の心身の状態などを調べます。
その後、一次判定で、どのくらい介護に時間を要するのか(要介護認定等基準時間)を分析します。その結果や主治医の意見書の内容を基に、二次判定で要介護認定の判定を行います。
要介護認定と判断されたら、ケアプランを作成してもらい自治体に提出します。そして、ケアマネージャーと相談しながら、ケアプランに沿った介護保険サービスの利用を開始することができます。
介護保険サービスは1~3割負担
認知症を発症して介護が必要になった場合、要介護認定を申請して認定が下りれば、介護保険適用の介護サービスを受けられます。
介護サービス利用の際は保険が適用され、自己負担額は本人や世帯の所得状況によって1割から3割で済みます。
なお、介護サービスは居宅系サービスと施設入居系サービスの2種類に大別されます。
認知症が進行していくと、要介護認定の段階も上昇するのが一般的です。
それにつれてサービスの単価が上がって利用頻度も増えてくるので、特に居宅系の介護サービスを利用する際は、毎月かかる自己負担額の総額も高くなることに注意が必要です。
介護保険サービスの種類
居宅介護サービス
居宅系サービスとは、介護資格を持った専門職が要介護者宅を訪れる訪問介護やデイサービスに通う通所介護など、在宅で介護を受けている人をサポートするサービスです。
種類は、訪問介護サービスや通所介護サービス、短期入所介護サービス、小規模多機能型居宅介護です。
訪問介護サービスはヘルパーが自宅を訪問して、食事や排泄などの身体介護や生活援助を受けられます。
また、通所介護サービスは日中、デイサービスに通い入浴や食事、レクリエーションなどをして過ごします。家族が仕事などで介護ができない場合は、短期入所介護サービスいわゆるショートステイを利用し、短期間施設に入所します。
施設入居サービス
一方、施設入居系サービスは特別養護老人ホームや老人保健施設など、自宅を離れて入居施設で生活し、そこで介護を受けるサービスのことを言います。
また、介護付き有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホーム、一部のサ高住は特定施設入居者生活介護(特定施設)に分類されます。特定施設に入居している要介護者の日常生活上の費用は介護保険の対象になります。
施設内で提供される介護サービスはもちろんのこと、外部の介護サービスでも適用されます。
費用は要介護度に応じた定額になり、安定した介護サービス、看護ケアを受けられるため、安心感の高い施設と言えます。
「みんなの介護入居相談センター」では、予算や希望条件に合わせた施設を紹介しています。是非ご利用ください。
認知症介護にかかる費用
続いて、認知症介護にかかる費用についてさらに詳しく解説していきます。
在宅介護の平均費用は5万円
在宅介護をしていくうえでは、訪問介護や通所介護など介護サービスを利用した際に払う費用と、おむつ代や医療費といった介護サービス以外の費用が必要です。
1ヵ月あたりの費用では、介護サービスでは平均で約1万6,000円、介護サービス以外の費用は平均で約3万4,000円になります。
両方の費用を合わせると、在宅介護で必要となる月額利用料の合計は平均で約5万円です。
介護サービス費用は、要介護度が高くなるとその分高くなる傾向があります。介護サービス以外の費用では、要介護4の介護が最も高額な平均費用となっています。
また、認知症を発症していると介護費用が変わります。認知症では、症状が重度となるにつれて家族では対応が難しい問題行動が見られることもあります。そのため、要介護度が低いケースでも専門的なサポートを利用することで、介護費用が高額化していくのが一般的です。
なお、「高額医療・高額介護合算療養費制度」といった制度や、各自治体が実施している補助制度などを活用すると、最終的な負担額はもっと軽減できることもあります。
インフォーマルケアコストとは?
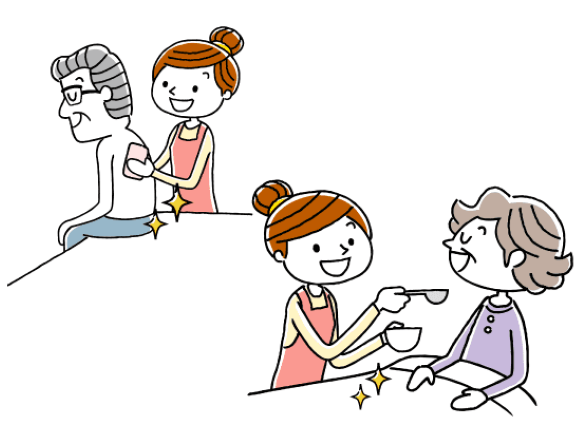
インフォーマルケアとは、介護保険外で家族や知人が無償で提供するケアのことです。
介護保険サービスのような制度による公的なケアではなく、制度に基づかずに非公式な形で行われるケアとも言えるでしょう。
また「インフォーマルケアコスト」とは、「介護にあてた時間で本来得られていたはずの就労収入」や「無償で行った介護を外部サービスに委託した場合にかかる費用」などを「コスト」として考えることを指します。
慶應義塾大学が行った試算によると、日本におけるインフォーマルケアコストの総額は6兆1,584円で、要介護者1人あたりで換算すると年間382万円にまで上るとのこと。
施設などに親を預けている人も、仕事を辞めて自ら介護を行っている人も、どちらの場合も介護者には大きな「コスト」が生じているといえます。
認知症の方が入居できる高齢者施設の費用
認知症の高齢者が入れる入居施設には、大きく分けて「公的施設」と「民間施設」とがあります。
公的施設には特別養護老人ホームや介護老人保健施設をはじめ、軽費老人ホームやグループホームなどがあります。民間施設では有料老人ホーム、さらには近年増えているサービス付き高齢者向け住宅などが代表的です。
公的施設の平均的な月額費用については、下記に概算で出しましたのでご覧ください。
| ケアハウス | 9.2~13.1万円 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 10~14.4万円 |
| 介護老人保健施設 | 8.8~15.1万円 |
なお、特別養護老人ホームなどの介護保険施設では、食費と居住費は国が定めている基準費用額に基づいて設定されているので、入居の際は事前に確認しておきましょう。
【4種類を一覧で比較】介護保険施設とは?費用やサービス内容の違い
一方、民間施設の月額費用は下記のような金額になります。
| 介護付き有料老人ホーム | 15.7~28.6万円 |
|---|---|
| 住宅型有料老人ホーム | 9.6~16.3万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 11.8~19.5万円 |
| グループホーム | 10~14.3万円 |
全体的にみると、民間施設より公的施設の方が費用は安いといえます。
ただ、民間施設のほうがサービスや人員体制が豊富な場合も多いため、予算や希望条件に合った施設探しをしましょう。
【一覧表でわかる】老人ホーム8種類の違いと特徴(介護度別・認知症対応)
「みんなの介護入居相談センター」では、一人ひとりの状況や希望条件にあった施設を紹介しています。是非ご利用ください。
認知症の対応が手厚い老人ホーム
続いて、認知症のケアが手厚い老人ホームを紹介していきます。
それぞれの特徴を知っておくことで、希望に合った老人ホームに入居することができます。
グループホーム
認知症の方のみを受け入れるグループホームは、環境の変化を苦手とする認知症の方が安心して過ごせるように、1ユニット5〜9人の少人数制で共同生活をします。
職員は認知症の知識が豊富なため、一人ひとりの症状や状態に合わせたケアを行います。
日常生活においては、家事分担をして本人のできることを活かしながら、脳に刺激を与えていき、認知症の進行を遅らせます。
また、認知症に効果的なレクリエーションやリハビリなども行っており、入居者が楽しいと思える環境が整っているのも特徴です。
【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説
グループホームを探す住宅型有料老人ホーム
バリアフリー設備の整った住宅型有料老人ホームでは、レクリエーションやイベントが盛んに行われています。認知症の方が参加できるレクリエーションも実施しているので、気軽に楽しむことができます。
また、他の入居者とコミュニケーションをとりやすく、自然と人と関わりを持てるのは住宅型の大きな強みと言えます。
介護サービスについては、外部の介護サービスを利用しますが、自分の必要とするサービスと施設で提供する生活援助を自由に組み合わせての利用が可能です。さらに、自宅で利用していた介護サービスも引き続き利用できます。
【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説
住宅型有料老人ホームを探す介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは特定施設になるため、施設内で介護サービスが提供されます。
介護職員が24時間常駐しているので、夜中でも手厚い介護サービスを受けられます。また、日中であれば看護職員が常駐しており、持病のある方や薬を服用している方も安心して任せられます。
介護付きは介護サービスの他に、居室の清掃や洗濯、買い物や行政の手続きをする代行サービスなどの生活支援も受けられます。
さらに、身体や認知機能の維持・回復を目的としたリハビリも行われており、認知症の進行を緩やかにすることが期待できます。
【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)
介護付き有料老人ホームを探す認知症ケアで利用できる費用援助制度
認知症に限らず、介護や医療費が一定以上かかる場合、日本ではさまざまな軽減制度が設けられています。
以下のような制度が主に挙げられます。
高額療養費制度
高額療養費制度は、1ヵ月に自己負担する医療費の上限を定め、それを超えた分については給付を受けられるという制度です。
上限額は年齢と年収によって規定されており、例えば年収156~370万円で70歳以上の場合、世帯ごとの上限額は5万7,600円になります。
申請をするときは、事前に手続きする場合と事後にする場合で分かれます。
事前に行う場合は、自身が加入している保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険など)に申請をします。そこで「限度額適用認定証」を交付してもらい、受診時に窓口で提示します。そうすると、自己限度額までの支払いで済みます。
一方。事後に申請する場合は、まず医療機関の窓口で自己負担分を支払い、後日、加入する保険者へ申請をして、払い戻しを受けます。
高額介護サービス費
高額介護サービス費は、毎月かかる介護サービスの自己負担額の合計が、所得に応じて区分されている上限額を超えた場合に、超えた分について介護保険から給付を受けることができます。
支給を受けるには、市区町村に申請が必要です。
高額医療・介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方に自己負担額が生じた際、合算後の負担額を軽減できる制度です。
規定されている年額の限度額を500円以上超えた場合、市区町村に申請すると超えた分について支給を受けられます。
特定入所者介護サービス費
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設に入居している人で、所得や資産が一定以下の場合、所定の自己負担限度額を超える居住費と食費が介護保険から給付されます。
利用するには「負担限度額認定」が必要になるので、市区町村に申請を行わなければなりません。
会社に勤めている方が認知症になったら
若年性認知症を発症する人の多くは40代~50代の働き盛りですから、家計を支えている家族が認知症になることで、世帯全体が経済的に困窮するケースは少なくありません。
発症によってお金に関しての問題が起こりやすいのは、若年性認知症の特徴といえます。そのような方が利用できる制度を紹介していきます。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療とは、若年性認知症を発症して通院治療を行うと、医療機関と薬局で支払うことになる医療費の自己負担額が1割へと軽減される制度です。
家計を担っている家族が若年性認知症を発症すると、収入が大きく下がることも多いので、利用したい援助制度です。
世帯の所得状況や疾病の内容などに応じて、自己負担額には上限が定められています。
申請を行わなければ適用されないので、各自治体の障害福祉課などの担当課や保健所に申し込みを行いましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、病気や怪我によって休職の必要が生じたときに受給できる手当金です。
もし、連続する3日間を含む4日目以上の期間で就業することができなかった場合に、標準報酬日額の3分の2を最長1年半まで受給ができます。最初の3日間は待機期間となるため、その期間に復帰すると支給されません。
待機期間には、有給休暇、土日、祝日なども含まれます。
また、仮に休職途中で退職となっても、支給が停止されるわけではありません。
退職した時点で傷病手当金を受けており、かつ絢子保健の被保険者期間が1年以上があれば、最長1年半まで支給を受けることができます。
申請は加入中の保険組合に対して行い、申請時は医師と事業主、それぞれの証明が必要になります。
障害者手帳
「認知症」と診断されたら、「精神障害者保健福祉手帳」交付となります。
血管性認知症もしくはレビー小体型認知症を発症して身体症状が生じているときは、「身体障害者手帳」に該当することもあるので、もしこれらの認知症を発症している場合は、市町村の障害福祉課で確認すると良いでしょう。
障害者手帳があることで、必要なサービスを受けられることを証明できるほか、企業の「障害者雇用枠」として働き続けることができる企業も増えています。
税制上の優遇措置をはじめ、施設の利用料や公共交通料金の割引なども受けることができ、交付によって得られるメリットは大きいです。
障害年金
障害年金は、病気または怪我によって仕事を続けることが難しくなった人と、その家族の生活を支援するための公的年金です。
大きく分けて、国民年金加入者が受給できる障害基礎年金と、厚生年金加入者が受給できる障害厚生年金があります。
障害基礎年金を受けるには、1級または2級の障害認定を受けていて、認知症と診断された月の前々月までに、国民年金の3分の2を収めていなければなりません。
また、厚生年金に加入しているなら、障害基礎年金に上乗せする形で、障害厚生年金を受け取れます。
以下に利用条件をまとめたので、是非ご覧ください。
- 障害基礎年金
- 国民年金加入者と厚生年金加入者が対象で、支給条件は以下の通りです。
- 公的年金(国民年金または厚生年金)の加入期間に初診日がある
- 初診日に65歳未満で、「初診日の前々月までの1年間」で未納の保険料がない
- 認定月の前々月までに、国民年金の3分の2を納付済み
- 1級または2級の障害認定
- 障害厚生年金
- 厚生年金加入者が対象で、支給条件は以下の通りです。
- 障害基礎年金の条件に加えて、1級または2級または3級の障害認定
住宅ローン支払い免除
若年性認知症を発症して収入に変化があると、残っている住宅ローンを支払えなくなる事態は十分に起こり得ることです。
通常、金融機関は住宅ローンの契約の際、融資関連の保証機関に加入することを条件にしています。
その保証機関が団体信用生命保険に加入していると、「高度障害状態」になったときに支払いの免除を受けられることがあるので、ローン契約をした金融機関に契約内容を確認してみましょう。
認知症に備える保険商品
最後に、認知症になったときに備えて入れる保険について紹介していきます。
認知症保険
最近、民間の保険会社で「認知症保険」という商品が登場しています。
保険に加入すると、認知症を発症したときに、年金や一時金として保険金を受け取ることができます。
保険金を受け取る条件としては、一般的には以下の条件がありますので注意しましょう。
- 専門医によって認知症と診断されていること
- 介護保険の「要介護1」以上の認定を受けていること
- 要介護状態が一定期間以上続いていること
- 脳の構造そのものに異変が生じて起こった認知症であること
- 認知症高齢者の「日常生活自立度」のⅢ~Mに該当すること
具体的な条件は各保険会社や商品によって異なるので、契約をする際は事前にしっかりと確認しましょう。
認知症を保障してくれる生命保険も
保険の加入者が認知症を発症し、その状態が「高度障害」に該当すると認められれば、死亡時と同様の保険金を受け取ることができる保険もあります。
保険会社ごとにどんな状態が高度障害と認められるのか異なるので、加入している保険会社に確認しておくと良いでしょう。
ただ、自分である程度身の回りのことができるほどであれば、高度障害に当てはまらないのが一般的です。
近年では、若年性認知症が進行して働けなくなった場合に備えられる保険も増えつつあります。
加入の際は、高度障害と認められる条件など、契約内容を確認してください。
認知症事故に備える個人損害賠償保険
個人賠償責任保険とは、日常生活の中で、事故や過失で他人に怪我をさせてしまったときや、物を壊してしまったときなど、法的な賠償責任が発生したときに補償を受けられる保険です。
近年では、個人賠償責任保険の補償対象は広がりつつあります。
例えば認知症を発症して被保険者本人に法的な責任をとれる能力がないとき、賠償責任を負うことになった別居の子どもや成年後見人も補償の対象とする保険会社が増えているのです。
2007年、認知症によって徘徊をしていた高齢者の男性が、列車にはねられて亡くなる事故が起こりました。
このとき、JR東海が男性の家族に対して、運行遅延によって生じた損害の賠償を求める訴訟を起こしたのです。
このケースがきっかけとなり、補償対象を拡大する個人賠償責任保険が増えたと言われています。
もし離れて暮らす高齢の親が認知症を発症しているなら、こうした保険について理解を深めておくと良いかもしれません。
他の人はこちらも質問
認知症検査にかかるお金はどれくらい?
認知症の検査にかかる費用は健康保険・介護保険3割負担の場合、220円〜3万円です。簡単な認知機能テストだと1,000円以下でできますが、CTやMRI検査は4,000円〜9,000円ほどかかります。臓器の状態を撮影するSPECT検査は、3割負担でも3万円近くかかります。
認知機能検査はいくら?
認知機能検査は1割負担の場合70円〜280円、3割負担は220円〜850円ほどです。10割負担は700円〜2,800円かかります。
認知症ってどうやって判断するの?
認知症の検査は病院やクリニックなどでできます。診療科は脳神経内科や精神科などです。また認知症疾患医療センターでの受診も可能です。
認知症疾患医療センターは全国に180ヵ所あり、認知症の診断や初期対応などを行います。
認知症検査ってどんなことするの?
認知症検査の流れは問診、面談や診察、画像・神経心理学検査です。検査の種類は認知機能テスト、MRI、CT、SPECT検査などがあります。





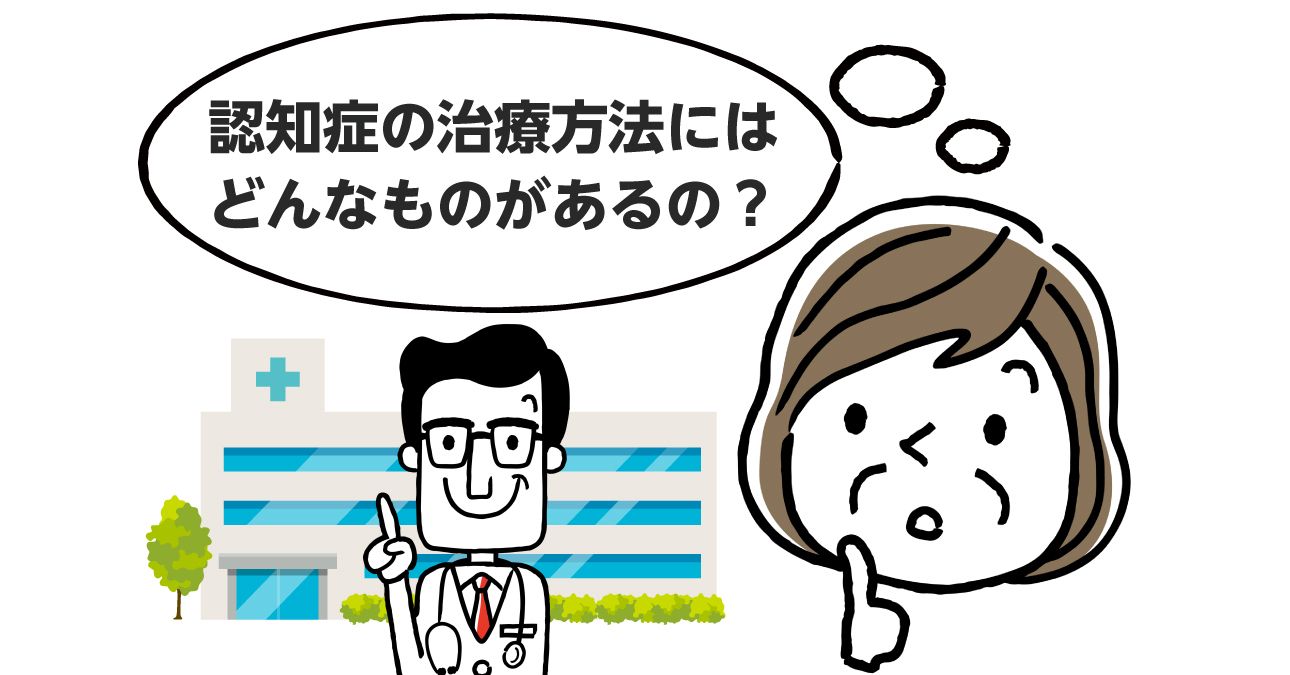


 この記事の
この記事の