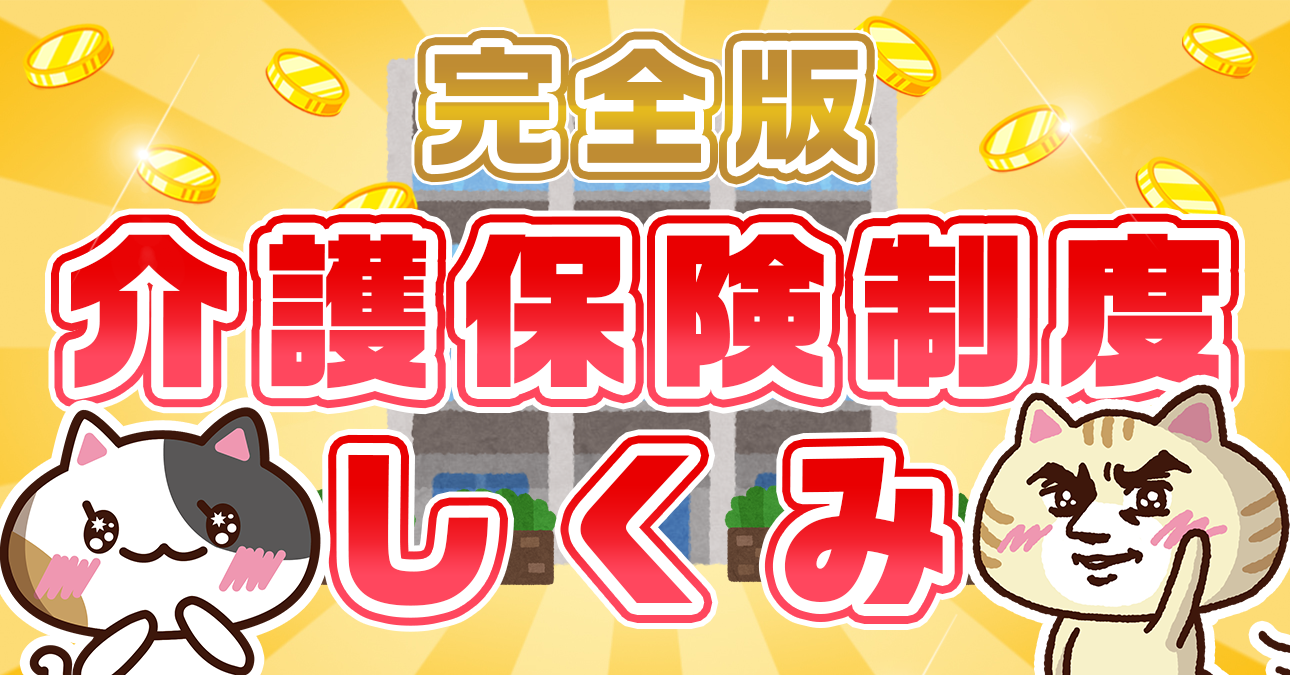特定疾病とは
特定疾病の定義

特定疾病とは、公的保険・民間保険において、特殊な扱いを受ける病気のことです。
なお、特定疾病の読み方は「とくていしっぺい」と読みます。
厚生労働省では、以下のいずれに該当する病気を特定疾病の定義として定めています。
- 心身の病的加齢現象と医学的な関係があると考えられる疾病
- 加齢とともに生じる心身の変化が原因で、要介護状態を引き起こすような心身の障害をもたらすと認められる疾病
つまり、加齢と関係があって、要介護状態の原因となる病気のことです。
特定疾病は介護保険の適用となる
介護保険制度における被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40~64歳までの「第2号被保険者」に区分されます。
このうち、介護保険適用で介護サービスを利用できるのは、原則「要介護・要支援認定を受けた65歳以上」の人です。
第2号被保険者の場合は介護が必要な心身状態になっただけでは、介護保険は適用されません。
しかし、第2号被保険者の方が特定疾病が原因で要介護状態となった場合は介護保険が適用されます。
各保険で異なる病気を指している
対象となる病気は一律に定まっているわけではなく、保険ごとに異なります。
例えば、医療保険の高額療養費制度において高額長期疾病とされている特定疾病は、「血友病、慢性腎不全、後天性免疫不全症候群」です。
一方で、民間の生命保険における特定疾病は「がん、脳卒中、急性心筋梗塞」などです。
この例からもわかる通り、特定疾病は保険ごとに対象となる病名を確認する必要があります。
次の項目では介護保険が適用される「16種類の特定疾病」について一つひとつ解説します。
【診断基準あり】16種類の特定疾病一覧
1. がん(末期がん)
介護保険の特定疾病に指定されているのは「末期のがん」です。致死性を持ち、治癒困難な状態であることが要件です。
- 致死性とは
- がん細胞が無制限に増殖して、発症した臓器から近隣の臓器やリンパ節などにも転移がみられる状態。
何らかの治療を行わない限り、結果として死に至る状態のこと - 治癒困難な状態とは
- 余命が6ヵ月程度と診断された状態
抗がん剤による治療が行われている場合でも、症状緩和や直接治癒を目的としていない治療は「治癒困難」な状態とされ、特定疾病の対象です。
2. 関節リウマチ
関節リウマチの場合、自覚症状やX線などの臨床検査の結果を総合して判断されます。自覚症状としては以下の5項目が該当します。
自覚症状の5項目
- 朝に起こるこわばりの持続時間が1時間以上続く
- 関節腫脹または関節液貯留が同時に3ヵ所以上
- 手首、近位指節間関節(PIP)、中手指節間関節(MCP)において1ヵ所以上の関節腫脹
- 両側の同じ部位で関節炎が同時に起こっていること
- リウマトイド皮下結節
3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
筋委縮性側索硬化症とは、脳の運動神経の障害によって体の運動機能に影響を及ぼす病気です。
具体的には以下のような症状がみられます。
- 構音障害・嚥下障害
- 呼吸困難
- 手足の筋力低下
- 認知症
ALSは進行性の疾患であるため、完治させたり、症状を軽減させたりすることはできません。
詳しくは以下の記事で解説していますので、合わせて確認してみましょう。
4. 後縦靱帯骨化症
脊椎をつなぐ「後縦靱帯」が骨化する疾患です。
神経が圧迫されるため、四肢のしびれや運動障害・知覚障害が引き起こされます。
こうした症状の有無や脊椎X線像の結果により、靱帯骨化と因果関係があるとされる場合に特定疾病に該当すします。
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
骨に起こる疾患で、小さな穴が大量に発生して骨がもろくなります。
腰椎骨の密度の検査や、脊椎の検査(X線)の結果によって特定疾病と認定されます。
6. 初老期における認知症
初老期における認知症も特定疾病の対象となる可能性があります。
記憶障害があること以外に「初老期における認知症と診断される認知障害」に該当していることが判断基準として用いられます。
初老期における認知症と診断される認知障害
- 失語(言語の障害)
- 失行(運動機能が損なわれていないにもかかわらず、動作を遂行する能力の障害)
- 失認(感覚機能が損なわれていないにもかかわらず、対象を認識又は同定できないこと)
- 実行機能(組織化する、計画を立てる、抽象化する、順序立てる)の障害
なお、意識水準の低下によって起こるせん妄は対象外です。
- せん妄の症状
-
- 時間や場所がわからくなる
- 睡眠リズムが崩れる
- まとまりのない言動を繰り返す
- 注意力や思考力が低下する
アルコール性認知症は特定疾病の対象外
アルコール性認知症とは、大量のアルコール摂取が原因で発症する認知症のことです。
アルコールの多量摂取によって脳梗塞などの脳血管障害や栄養障害などを発症して、認知機能の衰退をもたらします。また、多量のアルコールを飲み続けた結果、脳が萎縮するとも言われています。
一般的に認知症は高齢者に多い病気ですが、アルコール性認知症は世代に関係なく若年層でも発症することが特徴です。
アルコール性認知症の患者は、アルツハイマー型やレビー小体型といったその他の認知症を併発するケースも少なくありません。
アルコール性認知症の治療の第一歩は、まず飲酒をやめることです。合わせて、専門医の治療を受けると、症状の改善が見られるケースもあります。
なお、特定疾病には該当しません。
7. パーキンソン病関連疾患
パーキンソン病関連疾患とは、以下3つの病気の総称です。
- 1. 進行性核上性麻痺
- 「眼球運動障害や姿勢の不安定さ、後ろ側への倒れやすい」といった症状がみられる
- 2. 大脳皮質基底核変性症
- 「肢節運動失効や認知機能障害」といった症状がみられる
- 3. パーキンソン病
- 「安静時振戦や姿勢歩行障害」といった症状がみられる
特定疾病を受けるには「発症時の年齢」「症状の進行速度」「発症している症状」などについて、総合的な診断を専門医から受ける必要があります。
8. 脊髄小脳変性症
脊髄小脳変性症とは、運動を司る小脳に異変をきたす病気です。
発症原因が特定されておらず、以下のような症状がみられます。
- 運動失調
- 末梢神経症状
- 自律神経症状
- 高次機能障害
なお、特定疾病に該当するかは専門医が症状を詳しく診断したうえで、総合的に判断します。
9. 脊柱管狭窄症
脊柱管(脊椎の中にある空間)が狭くなってしまうことで、中を通る神経が圧迫され、さまざまな症状が現れる病気です。
以下に該当する場合に特定疾病として認められます。
- 頚椎部、胸椎部、腰椎部のうち、脊柱管の狭小化がみられる
- 画像所見において、脊柱管の狭小化によって神経の圧迫が確認できる
- 画像上の脊柱管狭小化と現れている症状の間に因果関係がある
10. 早老症
早老症とは、老化の兆候が実年齢よりも早く、全身に生じる疾患の総称のことです。
ウェルナー症候群、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群、コケイン症候群など約10の疾患によって判定されます。
特に、ウェルナー症候群は日本人に多い早老症として知られており、全世界の発症者のうち6割が日本人です。
- ウェルナー症候群
-
- 白髪
- 脱毛
- 声の異常
- 四股・皮膚の萎縮
- アキレス腱などの軟部組織の石灰化
老化が過度に進むと「難治性皮膚潰瘍、糖尿病、早発性動脈硬化」といった合併症状が原因で、死亡するケースも高まります。
遺伝性の疾患ということもあり、完治する方法は見つかっていません。
11. 多系統萎縮症
多系統萎縮症とは、非遺伝性の脊髄小脳変性症による代表的疾患です。発症の原因はまだ解明されていません。
大きくは以下の3つに分類できます。
- 1. 線条体黒質変性症
- 50歳以上に発症することが多い。
表情が乏しくなる、筋肉がこわばる、動作が緩慢になる、などの症状がみられる。 - オリーブ橋小脳萎縮症
- 40歳以降で発症するケースが多く、日本では最も患者数が多い多系統萎縮症。
起立時・歩行時におけるふらつき、ろれつが回らない、手先を正確に動かせないなどの症状がみられる。 - シャイ・ドレーガー症候群
- 50歳以降で発症するケースが多い。
立ちくらみ、尿失禁といった自律神経の障害症状がみられる。
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
「糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症」はいずれも、糖尿病が進行することでもたらされる合併症です。
糖尿病そのものは特定疾病とは認められていません。3種類の合併症についてはそれぞれ複雑な基準が設けられており、すべてを満たした場合に特定疾病として認められます。
13. 脳血管疾患
脳梗塞や脳出血のような、脳の血管に異常が起こったために発生する疾患の総称です。
CTやMRIを用いた検査結果を考慮したり、麻痺のような後遺症を注意深く診断したりと総合的な判断の下で、介護保険の適用が決まります。
なお、介護保険の適用は「老化に基づいた疾患であること」が前提にあるため、外傷で脳出血・くも膜下出血が起こったケースは特定疾病とはみなされません。
14. 閉塞性動脈硬化症
腹部大動脈末梢側、四肢の主幹動脈、下肢の中等度の動脈などに閉塞が確認されている状態のことを「閉塞性動脈硬化症」と言います。
以下のような場合に特定疾病とみなされるケースがあります。
- 歩行中に足のしびれや痛みが発生している
- 安静にしていてもはっきりとした痛みを覚える
- 潰瘍や壊死がある
15. 慢性閉塞性肺疾患
慢性閉塞性肺疾患とは以下の病気の総称です。
- 慢性気管支炎
- 肺気腫
- 気管支喘息
- びまん性汎細(はんさい)気管支炎
咳痰、呼吸困難といった症状がみられる場合に、特定疾病とみなされます。
16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
膝の関節か股関節が変形したことが原因で、苦痛や機能低下が確認された場合に特定疾病とみなされます。
X線を用いた検査のほか、歩行機能や痛みの度合いについて詳細な判断基準が定められています。
出典:「特定疾病の選定基準の考え方」(厚生労働省)
特定疾病と認定されたときの対応
冒頭で特定疾病に該当する方は介護保険が適用となるとお伝えしましたが、介護給付を受けるにはどうすれば良いのでしょうか。
この項目からは介護保険の申請から介護サービスの利用開始までの流れを紹介します。
要介護認定を申請する

要介護認定を受けるには、まず市区町村の介護保険担当窓口に行き申請を行う必要があります。
入院している場合など本人が窓口に行けない時は「地域包括支援センター、介護保険施設、居宅介護支援事業者」などに申請の代行をお願いすることも可能です。
申請後、市区町村の認定調査員が申請者の自宅や施設などを訪問し、心身状態や生活環境についての聞き取り調査を行います。
その後、コンピューターによる一次判定と介護認定審査会による二次判定が行われます。
申請から約30日で認定結果が通知されます。なお、認定結果に不服がある場合は、異議申し立てを行うこともできます。
申請時に必要な書類
以下は第2号被保険者が要介護認定を申請する場合に必要な書類です。
- 要介護認定申請書
- 主治医の存在を証明する書類(診察券など)
- 医療保険被保険者証(40~64歳の場合)
- 印鑑
介護保険の申請方法については以下の記事で詳しく解説しています。合わせて参考にしてみてください。
ケアプランを立てる
介護サービスを利用するには、市区町村の役所にケアプランを提出する必要があります。
- ケアプランとは
- 介護サービスの利用計画書のことです。ケアマネージャーが利用者とその家族と相談しながら作成します。
ケアマネージャーは、利用者が直面している問題・課題を把握したうえでケアプランの作成を行います。
作成後はきちんと計画通りにサービスが行われたのか、ケアプランは妥当だったのかなどの事後評価も行います。
特定疾病で入居できる老人ホーム

要介護認定を受けている人の割合は65歳以上の「第1号被保険者」が圧倒的に多いことから、第2号被保険者を対象とした施設は少ないのが現状です。
そこで、この項目では特定疾病の方が老人ホームに入居するにあたり、おさえておきたいポイントを紹介します。
施設探しのポイント
特定疾病をともなう要介護者は「医療的ケア」が必要なケースが大半です。
そのため、看護職員が常駐していたり、医療的ケアを担当する介護職員の在籍している施設でないと入居を受け入れてもらえない場合があります。
医療的ケアを受けながら安心して暮らし続けるためにも、24時間体制で介護士が常駐している施設や医療機関が併設している施設を探しましょう。
また、若いうちから施設に入居するということはそれだけ長く施設で暮らすということです。
施設の立地場所や周辺環境、職員・入居者の雰囲気も重要です。施設見学や体験入居などを通して、馴染める環境かどうか確かめることをおすすめします。
【施設の種類で比較】老人ホームで受けられる医療行為の一覧(インスリン・透析・胃ろう)
24時間体制で介護士が常駐している老人ホームを探す医療保険における特定疾病
冒頭でも紹介したように65歳未満の場合、介護ケアが必要な状態でも16種類の「特定疾病」に該当しなければ介護保険を利用できません。
しかし、特定疾病ではない場合でも「厚生労働大臣の定める疾病等」に罹患している場合、医療保険を適用して訪問看護サービスを受けることができます。
- 訪問看護とは
- 看護師が利用者の住まいに訪問。食事・入浴・排泄介助といった療養上のお世話から、病状の観察、医療機器の管理、ターミナルケアなど医療行為まで幅広いサービスを受けられます。
そこで、この項目では医療保険制度における特定疾病について解説します。
「厚生労働大臣の定める疾病等」とは

「厚生労働大臣の定める疾病等」に認定されると、自己負担割合3割で訪問看護サービスを利用できます。
週に4日以上のケアを受けることができるほか、2~3ヵ所の訪問看護ステーションに依頼することも認められています。
介護保険のサービスではないため40歳未満でも適用を受けられますが、その場合は「週に3回まで」「1日に1回まで」といった使用制限があることに注意しましょう。
「厚生労働大臣の定める疾病等」一覧
以下は、「厚生労働大臣の定める疾病等」の一覧です。
| No. | 病名 |
|---|---|
| 1 | スモン |
| 2 | 末期がん |
| 3 | 頚椎損傷 |
| 4 | プリオン病 |
| 5 | 多発性硬化症 |
| 6 | 重症筋無力症 |
| 7 | ライソゾーム病 |
| 8 | 脊髄小脳変性症 |
| 9 | ハンチントン病 |
| 10 | 脊髄性筋萎縮症 |
| 11 | 進行性核上性麻痺 |
| 12 | 綿条体黒質変性症 |
| 13 | 球背髄性筋委縮症 |
| 14 | 筋萎縮性側索硬化症 |
| 15 | 亜急性硬化性全脳炎 |
| 16 | オリーブ橋小脳萎縮症 |
| 17 | 大脳皮質基底核変性症 |
| 18 | 後天性免疫不全症候群 |
| 19 | 副腎白質ジストロフィー |
| 20 | シャイ・ドレーガー症候群 |
| 21 | パーキンソン病(ヤールⅢ) |
| 22 | 進行性筋ジストロフィー症 |
| 23 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
| 24 | 人工呼吸器を使用している状態 |
介護保険制度上の特定疾病とは異なるものの、治療が長引くことが多い疾患がこの中に選ばれています。
出典:「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(厚生労働省)
介護保険と医療保険のどちらが適用されるか
| 介護保険 | 医療保険 | |
|---|---|---|
| 対象 | 第1号被保険者 | ケアプランに準ずる |
| 利用回数 | 「厚生労働大臣が定める疾病等」に罹患 | 週4回 |
介護保険で訪問看護を利用する場合はケアプランで利用回数が決まります。
基本的に利用回数に制限はありません。
対して、医療保険の場合(厚生労働大臣が定める疾病)は週4日以上利用することが可能です。
16の特定疾病の覚え方

この項目では、介護保険の適用となる「特定疾病」の病名を覚える語呂合わせを3つ紹介します。
1. 「パセリ残したガキ外へ」
- パ=パーキンソン病ほか
- セ=脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症
- リ=関節リウマチ
- の=脳血管疾患
- こ=後縦靭帯骨化症・骨粗鬆症
- し=初老期における認知症
- た=多系統萎縮症
- が=がん
- き=筋萎縮性側索硬化症
- そ=早老症
- と=糖尿病(合併症)
- へ=閉塞性動脈硬化症
食べ物の好き嫌いの多い子どもにひっかけた、イメージの付きやすい語呂合わせです。
語呂と病名が1対1で対応しているわけではない点に注意しましょう。
2. 「シャイなパリ人こっそり変装 初老で農協はいって萎縮どうしよう!」
- シャイ=シャイ・ドレーガー症候群
- パ=パーキンソン病ほか
- リ=関節リウマチ
- 人(ジン)=後縦靭帯骨化症
- こ=後縦靭帯骨化症・骨粗鬆症
- 変=変形性関節症
- 装(そう)=早老症
- 初老=初老期における認知症
- のう=脳血管疾患
- きょう=脊柱管狭窄症
- はい=慢性閉塞性肺疾患
- 萎縮=筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- どう=閉塞性動脈硬化症
- しよう=脊髄小脳変性症
上記1と同じく、16種類すべてを含んでいるわけではない点に注意しましょう。
3. 「キノコにパセリとタコが、まっ、ソーセージ、へへ」
- キ=筋萎縮性側索硬化症
- ノ=脳血管疾患
- コ=後縦靱帯骨化症
- に=初老期における認知症
- パ=パーキンソン病ほか
- セ=脊髄小脳変性症
- リ=関節リウマチ
- と=糖尿病(合併症)
- タ=多系統萎縮症
- コ=骨粗鬆症
- が=がん
- マ=慢性閉塞性肺疾患
- ソ=早老症
- セ=脊柱管狭窄症
- へ=閉塞性動脈硬化症
- へ=変形性関節症
上記例では16種類すべての病名をさらうことができます。
生活保護を受給している場合

介護が必要になった方の中には、生活保護を受給している方もいることでしょう。
生活保護と介護保険を併用できるかどうかは年齢や医療保険の有無によって変わってくるので注意しましょう。
第1号被保険者(65歳以上)の場合
65歳以上の場合、生活保護を受けていても通常の方と同様に、介護保険の第1号被保険者としてみなされます。
ただし、介護サービス費の自己負担額は生活保護費から給付されます。
なお、障害者支援施設や救護施設といった「適用除外施設」に入所している場合は介護保険の被保険者になりません。
第2号被保険者(40歳以上~65歳未満)の場合
生活保護を受けている方は国民健康保険の被保険者資格がありません。
医療保険未加入の扱いとなるため、介護保険についても被保険者とはなりません。
この場合、「みなし2号被保険者」という扱いを受けられる可能性があります。
みなし2号被保険者に認められると、生活保護制度の下で「介護扶助」を受けることができます。
介護扶助が開始されると、介護サービス費用の全額について生活保護による扶助を受けられます。
また、生活保護を受給しながら組合保険のような医療保険の被保険者や被扶養者に該当する方は、介護保険の第2号被保険者に認定されます。
他の人はこちらも質問
特定疾病療養受療証とはなんですか?
特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が月額1万円となる制度です。
ひとつの医療機関に対して1万円と定められています。例えば、2つの医療機関を受診している場合の負担限度額は月額2万円です。
対象となる病気は以下の通りです。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病に認定されなかったらどうすれば良い?
もし発症した病気が特定疾病の対象外だったら、公的サービスを受けることはできないのでしょうか。
特定疾病と認定されなかった方でも、厚生労働省が指定する難病の方を対象とした「障害福祉サービス」を利用できます。
18歳以上の方で、以下いずれかに当てはまる場合は、障害福祉サービスを利用できます。
- 障害福祉サービスの要件
-
- 障害者総合支援法で指定されている難病患者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
上記要件を満たし、障害者支援区分認定が下りると「訓練等給付」「介護給付」が受けられます。
また、「介護給付」も支給されます。
- 訓練等給付とは
- 日常生活や社会生活を送るための支援
- 介護給付とは
- 日常生活に必要な介護のための支援
「障害福祉サービス」の申請方法
障害福祉サービスを希望する場合は市区町村の障害福祉窓口に相談して、6段階の「障害支援区分認定」の申請手続きをします。
申請を受け付けた自治体は、一次審査で認定調査員による自宅訪問やコンピューター調査などを実施します。
その後、二次審査として医師の意見書や訪問調査での特記事項などの情報に基づく審査会が開かれて、認定されます。
なお、訓練等給付と介護給付は審査の流れが一部異なりますが、受付窓口は同じです。
ターミナルケアマネジメント加算とはなんですか?
2018年の介護報酬改定により、新たに「ターミナルケアマネジメント」加算が適用されました。
加算対象は、末期がんと診断されたサービス利用者です。
通常のケアマネジメントとの大きな違いは、サービス担当者会議を省略できる点です。
通常ケアプランを変更する際は、利用者本人はもとより、各サービスの担当者が一同に会して今後のサービス利用の方向性について会議をすることが定められています。
しかし、ターミナルケアマネジメントでは、主治医の助言を得ることが前提となっていれば、サービス担当者会議の開催を省略できます。
身体の状況が頻繁に変化する利用者が、迅速に適切なサービスを受けることができます。
出典:「1.平成30年度介護報酬改定の主な事項について」(厚生労働省)
特養の入居条件は?
特養の入居条件は要介護3以上です。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などを利用すれば、費用を抑えることができます。
ただし、特養は待機者が多くて即入居できないことも多いです。そのため、待機期間だけ有料老人ホームを利用する方も少なくありません。
介護保険で認定されている特定疾病は何個?
40歳〜64歳の方が16の特定疾病による要介護の認定を受けた場合、介護保険サービスが利用できます。
16の特定疾病はがん、関節リウマチ、ALS、初老期における認知症、脊髄小脳変性症、脳血管疾患などです。
介護保険の特定疾病は何歳から?
40歳から64歳未満の第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護状態となれば介護保険サービスを利用できます。特定疾病はがん、関節リウマチ、脳血管疾患などです。
介護保険法で定める特定疾病ではないのはどれか?
高齢者に多く見られる大腿骨部骨折による要介護状態は、16の特定疾病に指定されていません。そのため介護保険制度は受けられないです。
特定疾患ってどんな病気?
特定疾病はがん、脳血管疾患、関節リウマチ、ALS、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期による認知症、パーキンソン病関連疾患、脊柱管狭窄症、早老症、他系統萎縮症、糖尿病による神経障害・腎症・網膜症などが対象です。






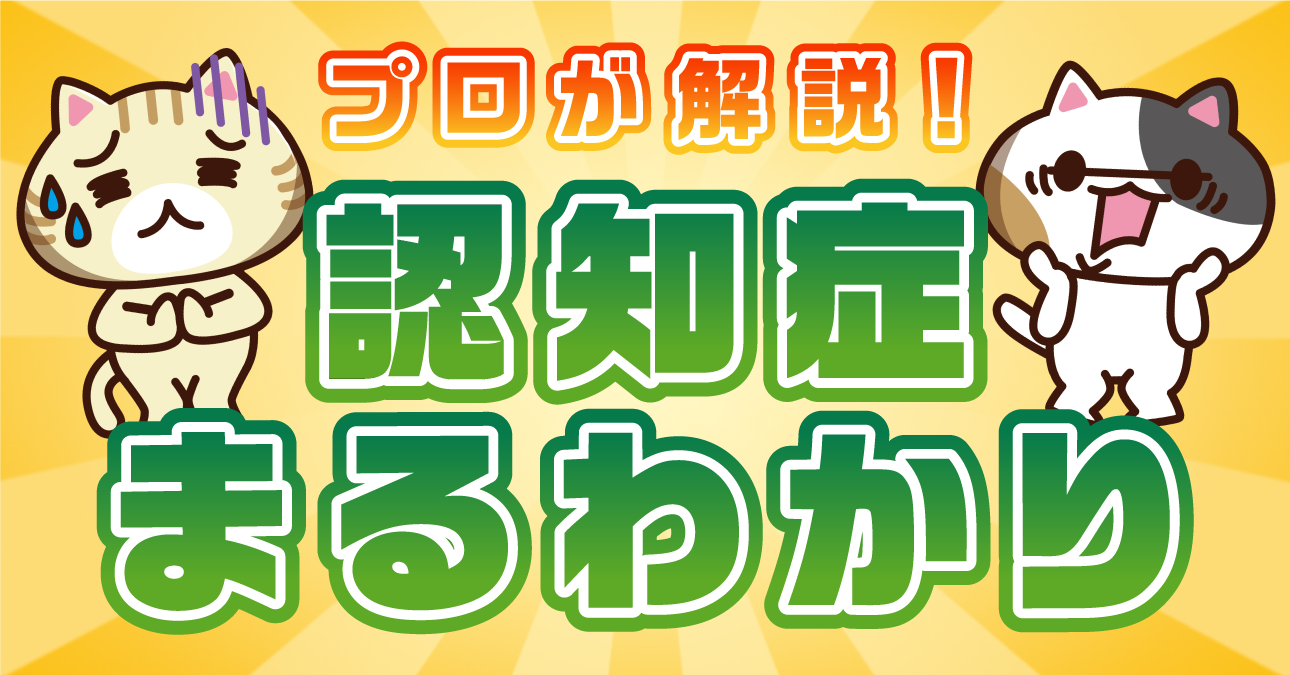
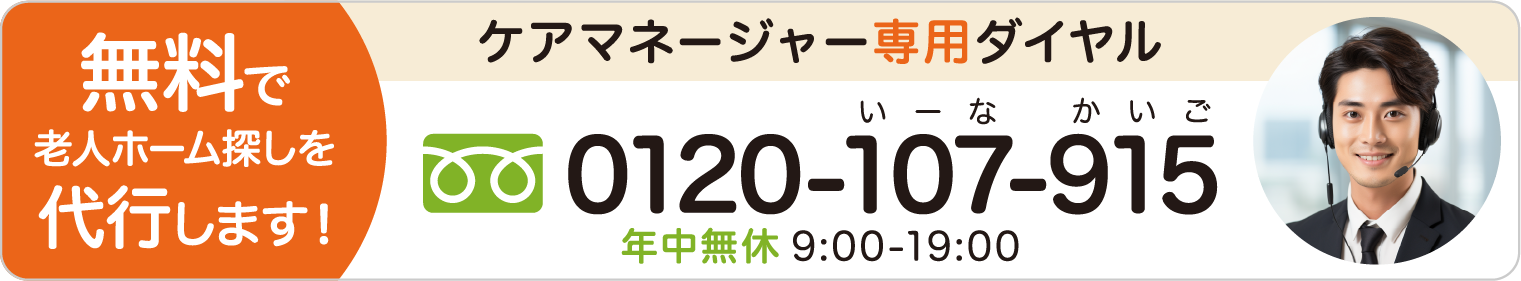



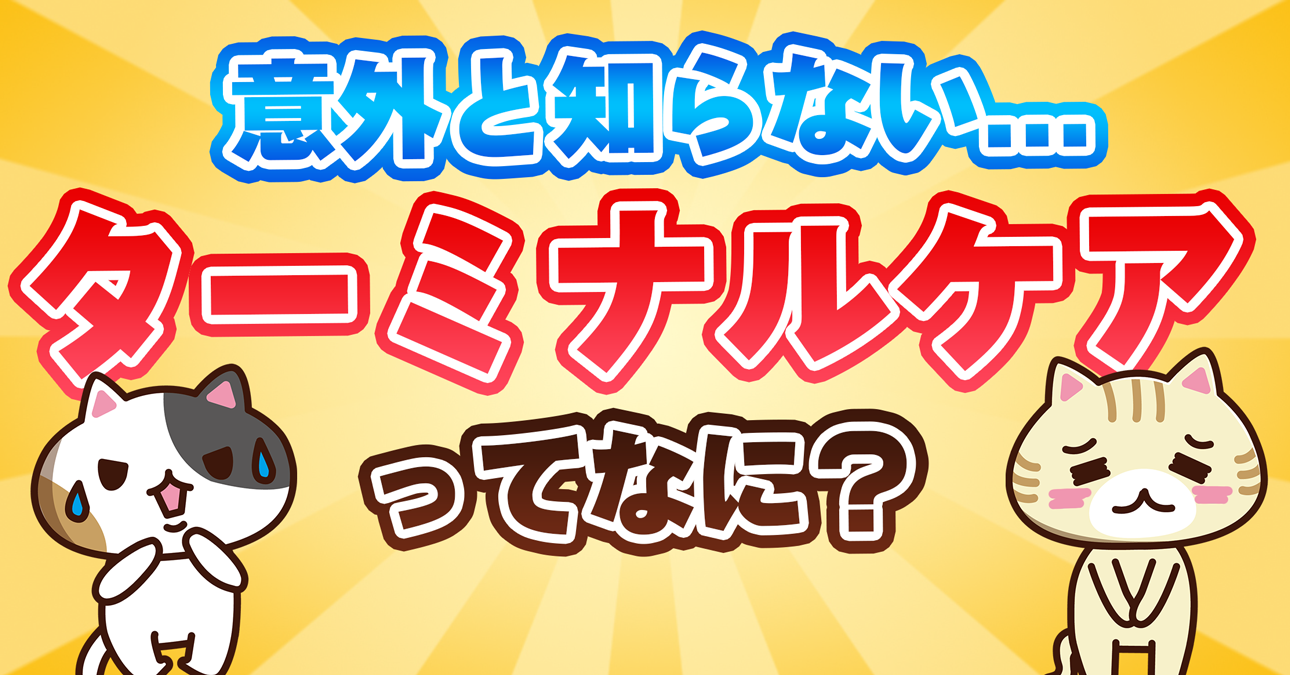
 この記事の
この記事の