介護保険サービスは何歳から使えるか
65歳から介護保険サービスが使える

介護保険サービスを利用できる年齢は原則「65歳以上」と定められています。
介護保険料を滞納することなく納めていれば、65歳になったとき、介護保険サービスが利用できる資格を示す「介護保険証」が届きます。
介護保険サービスを利用することで、施設入居や訪問介護、介護リフォームなど、介護にかかる費用を補助してもらうことができます。
40~64歳までの「第2号被保険者」はサービスを使えない
40~64歳(第2号保険者)は介護の必要がない年齢とされており、基本的には介護保険サービスを利用できません。
しかし、介護保険の特定16疾病に罹患し、介護が必要と認定された場合は40~64歳でも介護保険サービスを利用できます。
特定16疾病は以下の通りです。
- 16種の特定疾病
-
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料は何歳から引かれるか
40歳から介護保険料が引かれる
介護保険料は40歳になった月から支払いの義務が発生します。
そもそも、介護保険制度は介護を必要とする人に充実したサービスを届けるために2000年に施行されました。
介護保険制度は国民が納めている税金と、介護保険の加入者が出している保険料の2つで成り立っています。
介護保険の保険者と被保険者は以下の通りです。
- 保険者
- 全国の市町村、および特別区
- 被保険者
- 該当地域に住んでいる40歳以上の男女すべて
被保険者が介護を必要とする状態になったとき、保険者(市町村)に要介護認定の申請を行います。
保険者によって要介護認定された場合は、要介護度に応じた介護保険サービスを規定額の範囲内で利用できます。
介護サービス費の自己負担額は介護保険サービス料全体の1割負担となることが一般的です。ただ、年収によっては2~3割負担となる場合もあります。
なお、介護保険料は生涯にわたって払い続ける必要があります。
第1号保険者と第2号保険者に分けることができる
被保険者は以下の2つに区分されています。
| 区分 | 年齢 | サービスの利用条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 要支援・要介護認定を受けていること |
| 第2号被保険者 | 40~64歳 | 16種類の「特定疾病」に該当し、要支援・要介護認定を受けていること |
第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料の納付方法や要介護認定の受け方に違いがあります。
第2号被保険者は介護保険料を健康保険料の一部として支払い、第1号被保険者となると介護保険料として納付します。
また要介護度の申請では第1号被保険者は「介護保険被保険者証」が、第2号被保険者は「医療保険証」が必要です。
介護保険料はいくら納める?
第1号被保険者と第2号被保険者で納付額の計算方法が異なります。
第2号被保険者(40歳~64歳)の場合
第2号被保険者は加入している医療保険とセットで介護保険料を納付します。
健康保険や組合保険に加入している場合は給与や賞与の合計額をもとに、保険独自の算定方式を使って計算されます。
算定された金額は勤務先(雇用者)が半額を負担することになっています。
また国民健康保険に加入している場合は、前年の所得や同じ世帯に属する被保険者の人数に合わせて決定されます。
国民健康保険の場合は保険料の半額は国が負担することになっています。
第1号被保険者(65歳以上)の場合

第1号被保険者の場合、介護保険料は「年齢」「収入」「家族の状況」によって、計算方法が細かく分かれています。
地域や年度によって支払額に違いがあり、正確な額を知るには居住地域の介護保険課に問い合わせると良いでしょう。
なお、前年度の所得が少ない場合や世帯に住民税を課税されていない人がいる場合は、第1号被保険者の徴収額は少なめです。
例えば、生活保護を受けている場合は納付額が一番少なくなり、年額3万円前後で済むことが一般的です。反対に、前年度の所得が1,000万円を超えるケースでは、年額で20万円前後の保険料を求められます。
介護保険で利用できるサービスの種類
この項目からは介護保険でどのようなサービスを利用できるのか見ていきましょう。
介護サービスは大きく分けて「施設に入居して利用するサービス」「自宅で利用するサービス」の2つに分けることができます。
以下ではそれぞれに該当するサービスの種類をまとめています。
施設に入居して利用するサービス
| 区分 | 施設の詳細 |
|---|---|
| 介護保険施設 | ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老健) ・介護医療院 ・介護療養型医療施設(療養病床)※2018年3月廃止 |
| 地域密着型サービス | ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・地域密着型介護老人福祉施設 |
| 特定施設 | ・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 |
介護保険施設とは、介護保険法に基づき、介護保険サービスを利用できる公的な入居施設のことを指します。
地域密着型サービスとは、町村指定の事業者が地域住民に提供する介護サービスのことです。
その他、都道府県知事(または市区町村)から事業指定を受けた施設のことを「特定施設」と言います。
自宅で利用するサービス
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| 訪問型サービス |
・訪問介護(ホームヘルプ) ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 |
| 通所型サービス |
・通所介護(デイサービス) ・療養通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・通所リハビリテーション(デイケア) |
| 複合型サービス |
・小規模多機能型居宅介護(小多機) ・看護小規模多機能型居宅介護 |
| 生活環境を整えるサービス |
・福祉用具貸与 ・住宅改修費※介護リフォームをする際に保険適用 ・特定福祉用具販売 |
訪問型サービスとは、看護師や介護士などが利用者宅を訪れ、サービスを受けることです。
通所型サービスは訪問型と違い、利用者本人が普段生活している場所とは違うところを訪れ、サービスを受けます。
また、「訪問・通所・宿泊」を組み合わせたサービスを複合型サービスと言います。
次の項目では実際に介護サービスを利用するにあたり、必要な手続きについて解説します。
介護保険サービスを利用する方法

介護保険サービスを利用するためにまず行うのは、要介護認定を受けることです。
1. 必要な持ち物
以下の表にあるのが役所での申請に必要な持ち物です。
| 第1号被保険者(65歳以上)の場合 | 第2号被保険者(40歳以上~65歳未満)の場合 |
|---|---|
|
|
なお、医師の意見書は申請者が作成を依頼する必要はなく、申請をする市町村が担当医に作成を依頼します。
主治医がいない場合は市区町村の指定医による診察が必要です。
2. 要介護認定の申請
管轄の市役所や区役所の「介護保険課」、または「地域包括支援センター」へ届け出ましょう。
届け出は本人の家族が代理で行うことも可能です。
3. 市町村による認定調査
心身の状態を確認することを目的に、市区町村などの調査員が自宅や老人ホームなどを訪ねて認定調査を行います。
4. 審査判定
一次判定では公平な判定を行なうため、認定調査や意見書の項目をコンピューターに入力し、全国一律の方法で判定しています。
次に、要介護状態区分の認定・審査の二次判定が行われます。
一次判定の結果と特記事項、主治医の意見書を基に介護認定審査会で審査し、どのくらい介護が必要か判定が行われます。
5. 認定
市区町村は、介護認定審査会による判定を参考に要介護認定を行います。認定は要支援1・2、要介護1~5の7段階と、非該当に分かれています。
市区町村は、その結果を申請から認定の通知までの30日以内に受け取れるように郵送します。
認定の有効期間は原則6ヵ月、更新申請は原則12ヵ月となっています。
【目安がわかる】要介護度とは?8段階の状態像と受けられる介護サービス
6. ケアプラン・介護予防サービス計画書の作成
介護サービスを利用したい場合は、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼します。
ケアプラン作成の依頼について要支援・要介護で対応が異なります。
- 要支援1・要支援2
- 地域包括支援センターで作成
- 要介護1以上
- 県知事の指定を受けたケアプラン作成事業者で作成
依頼を受けた介護支援専門員は本人・家族の希望、心身の状態を考慮して、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
7. サービスの利用開始
介護保険サービスの計画にもとづいて、利用したいサービス事業者を選定。本人の状態などを確認してもらったうえでサービス利用開始の契約を行います。
次の項目では施設で介護サービスを利用したいと考えている方に向けて、身体状況や入居目的に合わせて4つの施設を紹介します。
入居者の身体状況と目的に見合ったおすすめの老人ホーム
介護施設に入居するタイミングは年齢や要介護度だけでなく、介護する側の負担も考慮して決める必要があります。
もし認知症がある場合は、進行具合も施設入居の判断材料となるでしょう。
以下では施設の特徴を交えながら、どのような方に向いているのかも合わせて紹介しています。ぜひ施設選びの参考にしてみてください。
自立した生活を送りたい方は「サ高住」がおすすめ
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、安否確認や生活支援サービス、緊急時対応サービスなどを受けられる施設です。
入居条件は「60歳以上の方」、もしくは「60歳未満で要介護認定を受けている方」です。
またサ高住は施設数が多く、自分にあった施設を見つけやすいのも特徴の一つ。安否確認や生活相談のサービスを受けながら生活できるので、一人暮らしの方も安心です。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)
サービス付き高齢者向け住宅を探す自分で介護サービス選びたい方は「住宅型」がおすすめ
住宅型有料老人ホームでは、居宅介護サービスの中から、必要とするサービスのみを選択して利用できます。
例えば、入浴時の介助を必要とする場合は、訪問型サービスに該当する訪問入浴介護を施設で利用できます。
入居条件は60歳または65歳以上、自立~要介護状態の方です。
介護サービス以外にも、掃除や洗濯といった生活援助サービスを受けることができます。イベントやレクリエーションが充実しており、入居者同士の触れ合いも多いのが特徴です。
【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説
住宅型有料老人ホームを探す認知症ケアを重視している方は「グループホーム」がおすすめ
認知症ケアに特化した施設です。最大でも18人までしか入居できないため、スタッフの目が行き届きやすく、手厚いケアを受けることができます。
入居条件は65歳以上の方で要支援2または要介護1以上の認定を受けている方。および医師から認知症の診断を受けていて、施設と同一の市区町村に住民票がある方です。
民間施設の中では費用が安価なので、経済的負担をおさえて施設に入りたい方には適していると言えます。
【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説
グループホームを探す24時間介護を必要している方は「介護付き」がおすすめ
介護付き有料老人ホームは看取りに対応し、看護師が常駐している施設です。人員配置体制も充実しており、手厚い介護サービスを受けることができます。
介護保険サービスは毎月定額にて提供されるので、どれだけ介護を受けても基本費用は変わりません。
入居条件は65歳以上の方で、要介護1以上の認定を受けている方です。入居時自立型の施設の場合は、自立の方でも入居できます。
【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)
介護付き有料老人ホームを探す他の人はこちらも質問
「共生型サービス」とはなんですか?

2018年度の介護保険制度改正によって、新たに導入された公的サービスに「共生型サービス」があります。
人の配置やサービスを効率化することを目的に、これまでは別々に扱われていた「介護福祉」と「障害福祉」を包括化しました。
この改正によって、障害福祉事業所が共生型施設として指定を受けた場合は、65歳を超えた障害者を受け入れに対応。高齢者と障害者が一緒にデイサービス、ショートステイなどを利用できるようになりました。
慣れ親しんだ事業所からサービスを受けることが可能に

共生型サービスが導入される前までは、障害者は65歳になると障害者総合支援制度から介護保険制度のサービスに切り替える必要がありました。
しかし、今回の改正によって共生型サービスの指定を受けた施設であれば、障害者は65歳になっても長年サービスを受け続けてきた事業所で同じ職員からサービスを受け続けられるようになった点も大きな変更点と言えるでしょう。
介護保険料は上がり続けているって本当ですか?
厚生労働省が公表する資料「第8期計画期間における介護保険の第1号保険料について」によると、介護保険料の全国平均は2000~2002年度当時は2,911円でしたが、2021~2023年度では6,014円にまで増えています。
高齢化によってさらに増加するとみられ、厚生労働省の試算では2025年度には8,165円にまで上昇する見込みです。
保険料が増えることを抑え、介護保険制度を持続させるためにも、介護サービスの効率化が必要となりつつあります。
誕生日の1日前に歳を取るのは何故ですか?
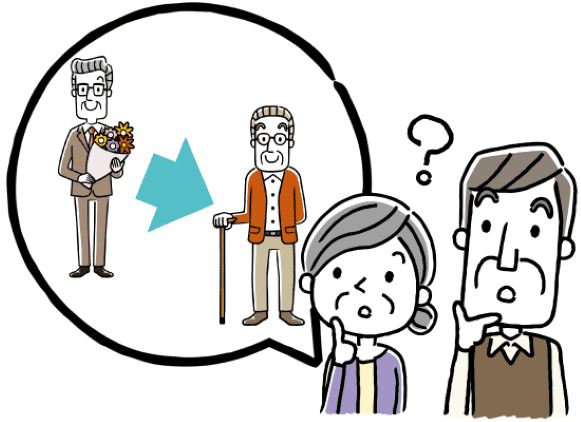
毎月1日生まれの方は、介護保険料の納付時期に注意する必要があります。
民法143条「年齢計算ニ関スル法律」では、「誕生日前日の午後12時」にひとつ歳を重ねるものと定められています。
この結果、誕生日が「○月1日」の人は、前月の末日が終わる前に年をとったものと解釈されます。
それにより、給与から介護保険料が徴収され始めるタイミングに違いが生まれます。
9月分の社会保険料を9月分の給与から差し引くケースもあれば、10月分から差し引くケースもあるので、誕生日を迎えるまで徴収されないことがあります。
国民健康保険を滞納したら、介護保険は使えませんか?
第2号被保険者のうち、自営業者など国民保険の加入者は、国民保険料と介護保険料を一緒に納付しています。
そのため、国民保険料を滞納することはそのまま介護保険料を滞納することになるわけです。
介護保険料を滞納してしまった場合、将来介護給付を受けられず、介護サービスを利用できない事態も起こり得ます。もし保険料の納付が困難になったときは、役所の窓口に相談しましょう。
災害など特別な理由によって保険料の納付が難しいときは減免措置の対象になることもあります。
健康保険、厚生年金保険との違いってなんですか?
介護保険は、納付期間や受給開始期間などが大きく異なります。以下でそれぞれを比較してみましょう。
健康保険(医療保険)
医療保険には、国民健康保険や健康保険・組合の保険といった種類がありますが、いずれも納付期間に終わりはありません。
健康保険や組合保険といった職場が用意する保険に入っていた場合でも、退職後はいずれ国民健康保険に加入しなといけません。
そして、75歳になったら「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
厚生年金保険
納付期間は勤務先を退職するまで続きます。なお、65歳以上の高齢になっても勤務を続ける場合は、70歳になったタイミングで納付は自動的に終了します。
受給開始年齢は介護保険と同様に「原則65歳」からとなっています。
介護保険は何歳から利用できますか?
介護保険サービスの利用は基本的に65歳以上からです。しかし、16の特定疾病のある要介護認定を受けていれば、40歳〜64歳の方も介護保険が適用されます。
介護保険が40歳以上なのはなぜ?
認知症や脳卒中などの発症リスクが高まるため、介護保険の被保険者を40歳からと定めています。
また親の介護の割合も高くなるので、互いに介護を支えるという目的もあります。
65歳以上の介護保険料はいくら?
65歳以上の介護保険料は年齢や収入、家族の状況などから保険料が決まります。また地域によっても異なり、保険料は各地域で10段階に分類します。生活保護を受けている方が最も保険料は安く、年間3万円前後の納付です。1,000万円の所得があった場合は、保険料は年間20万円前後です。
介護保険の40歳以上はいつから?
介護保険料は40歳を迎えた月から発生します。
年齢を重ねるのは誕生日の前日だと考える法律に合わせて、介護保険料の納付義務は誕生日の前日からとなります。1日が誕生日の場合は、前月から支払いが始まります。







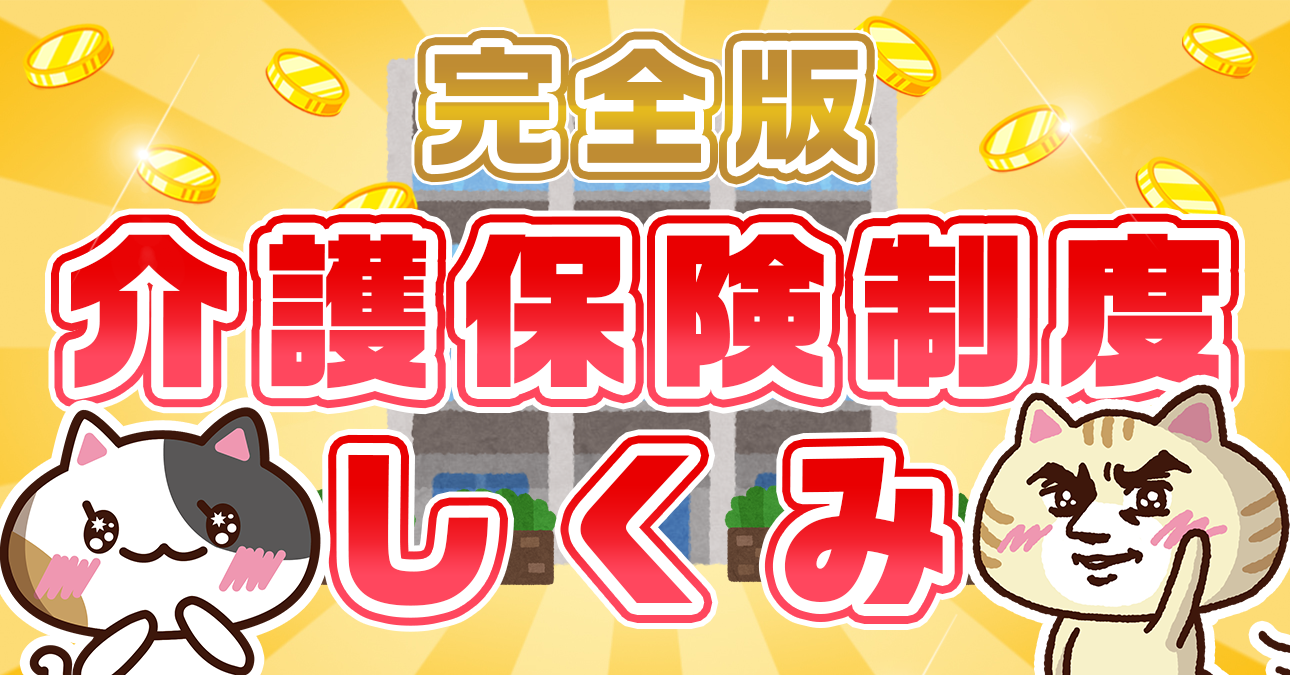
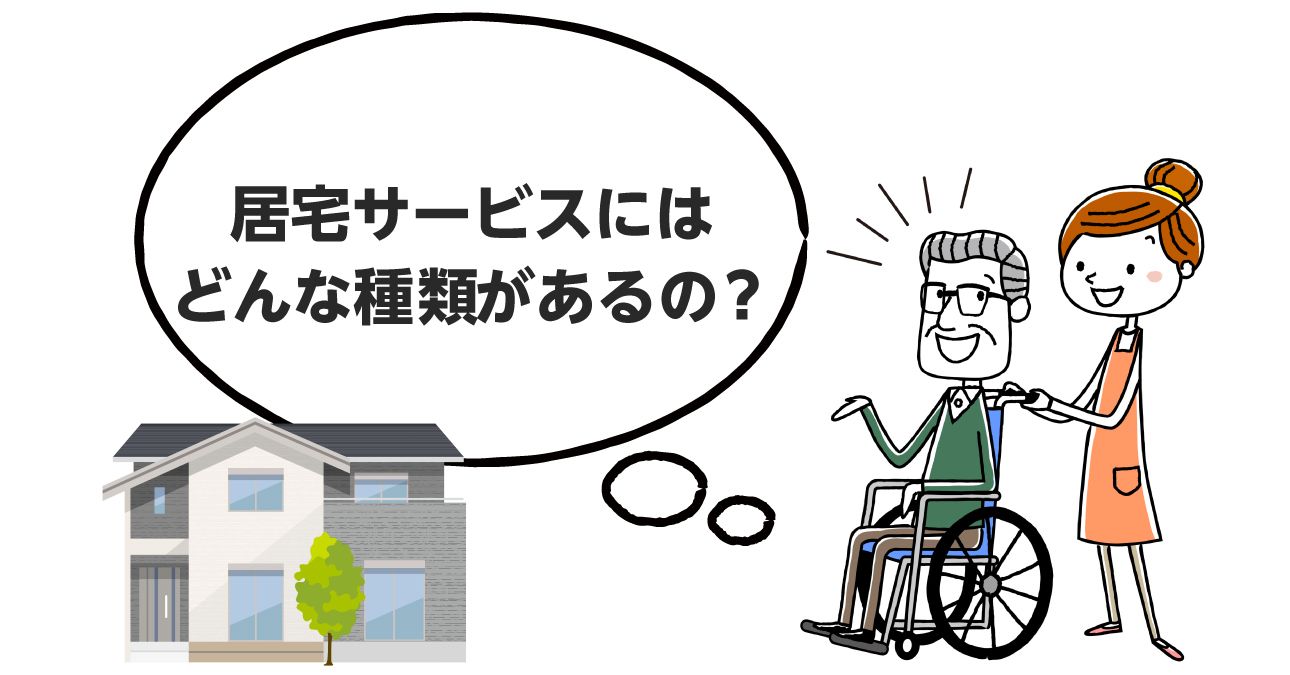
 この記事の
この記事の
