有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅建設費用の相場
有料老人ホームの設立には3~4億円はかかると言われています。まずは実際にあった事例を見てみましょう。
住宅型有料老人ホーム20室、デイサービス定員18名、土地面積250坪、建物延床面積約300坪の場合、以下のような投資額がかかりました。
| 費用項目 | 費用 |
|---|---|
| 土地購入費 | 1億円(坪40万円) |
| 建設費 | 2億1,000万円(坪70万円) |
| 設備・備品 | 1,500万円 |
| 営業・販促費 | 200万円(パンフレット、ホームページ、広告など) |
| 求人費 | 300万円 |
| 合計 | 約3億3,000万円 |
地域差ももちろんありますが、約3~4億円の費用が必要になります。
また、サービス付き高齢者向け住宅建設においては、一般のマンションの建築費用よりも高額になる傾向にあります。一般のマンションの建築費用は、坪単価で30~40万円ほどと言われていますが、サービス付き高齢者向け住宅だと坪単価の平均は80万円ほどになるのが一般的です。
サ高住として運営基盤が整うまで、人件費や設備管理費(数ヵ月~1年間分余裕)を支払える余裕も持って置かなければならないことを考えると、簡単に最低いくらの資金が必要なのかはその場合によりけりかもしれませんが、少なくとも決して小さな費用ではありません。
明確な事業計画を持って進むべきだと言えます。
オリンピックや復興の影響で建設費は増加傾向
老人ホームの建設費用は、2011年度以降、年々上昇しています。
これは東日本大震災の復興需要があったことも理由のひとつですが、東北の建築着工床面積が減少傾向に転じたのと入れ替わるように、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた再開発などが首都圏を中心に始まりました。
このことが、現在まで続く建設費用上昇の要因のひとつと考えられます。坪単価が20%~30%増加しているこの状況は、しばらく続くと見込みです。
コストを抑えるには早期に工事に取りかかる必要がありますが、これから新たに介護業界に参入しようとする企業にとっては大きな痛手になります。
介護需要が高まっていることから新規参入は止まらないと予想されますが、足元をみる建設業者が増える可能性もあるため、業者選びは慎重に行ってください。
有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅の設立で受けられる補助金・助成金について
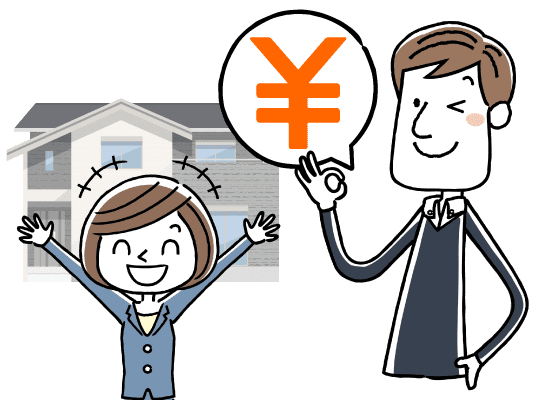
社会の高齢化が進むなか、高齢者の居住施設に対する需要は高まる一方。
国としても、その開設に対して助成金・補助金を交付し、住まいの安定確保を目指しています。
ただし、介護については「施設から在宅へ」という方針を掲げています。つまり、“施設”に該当する介護付き有料老人ホームをはじめとする有料老人ホームは、補助金・助成金の対象とはなりません。
補助金・助成金の対象となるのは、“在宅”の扱いとなるサービス付き高齢者向け住宅。2018年8月末時点ですでに約23万4,322戸となっているサービス付き高齢者向け住宅の総戸数を、2030年までに60万戸まで整備すると計画しており、そのための施策ということになります。
| 高齢者向け住宅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 補助率 | 限度額 | 注意事項 | |||
| 新築 | 夫婦型 | 住戸床面積30㎡以上 (便所、洗面所、 浴室、台所、 収納完備) |
1/10 | 135万円/戸 | 補助申請する戸数の2割以内が上限 ※入居世帯を夫婦などに限定する場合を除く |
| 一般型 | 住戸床面積25㎡以上 | 120万円/戸 | ー | ||
| 住戸床面積25㎡未満 | 90万円/戸 | ー | |||
| 改修 | 1/3 | 180万円/戸 | 調査設計計画費用も補助対象になる | ||
| 高齢者生活支援施設 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 補助率 | 限度額 | 注意事項 | ||
| 新築 | 地域交流施設など (生活相談・食事サービス・ 地域交流スペースなど) |
1/10 | 1000万円/施設 | ー |
| 介護関連施設など (訪問・通所・居宅介護支援の 介護事業所や診療所など) |
2018年度内に着手する施設のみ対象。 2019年度以降は補助対象外 |
|||
| 改修 | 1/3 | 1000万円/施設 | ー | |
サービス付き高齢者向け住宅を新築する場合は、その工事費の1/10以内(上限:135万円/戸)が助成されます。また、既存のデイサービスや診療所などに高齢者生活支援施設を合築・併設する場合にも、1000万円を上限として助成金が交付されるようになっています。
同時に、所得税や固定資産税、不動産所得税などの税制面でも優遇措置があるため、活用しない手はありません。
補助金・助成金を受けるためにはサービス付き高齢者向け住宅としての登録が大前提
設立する際に補助金や助成金を受けるには、サービス付き高齢者向け住宅として登録される必要があります。
登録を受けるには、居室の床面積を一定以上にするなどの住宅面の基準、安否確認や生活相談を行うなどのサービス面の基準、そして高齢者の生活の安定が図られた契約であることなどの運用・契約面における基準を満たしていなければなりません。
なお、税制優遇と融資に関する助成は、適用の期限が2021年3月31日までとなっています。該当する事業者は、早めに準備、申請しておく必要があるでしょう。
| 住宅 | 床面積(原則25㎡以上)、便所・洗面設備などの設置、バリアフリー |
|---|---|
| サービス | サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供) |
| 契約 | 高齢者の居住の安定が図られた契約であること 前払家賃などの返還ルールおよび保全措置が講じられていること |
サービス付き高齢者向け住宅としての概要以外に、必要な要件は4つ
- サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録するもの
- 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅と家賃の額について均衡を失しないように定められるもの
- 入居者からの家賃などの徴収方法が、前払いに限定されていないもの
- 事業に必要な資金の調達が確実であるもの
サービス付き高齢者向け住宅を新規に設立する際には、上記の要件を満たして補助金・助成金を上手く活用しましょう。
手続きの流れ
サービス付き高齢者向け住宅を開設するにあたって補助金を受けるには、まず事業計画を立てて市町村への意見聴取を行い、建築確認申請が必要です。
そののちにサービス付き高齢者向け住宅としての登録を行い、事前審査を受けたのちに交付申請を行います。審査の後、交付の決定の通知を受けたら工事を開始し、工事完了後は審査を経て補助金額が決定され、その後支給される、という流れになるのが通例です。
なお、市町村への意見聴取は2016年度以降必須となりましたが、一部の市区町村では不要なこともあります。
サ高住には有料老人ホームにはない税制の優遇が!
補助金・助成金によって現金の給付があるだけでなく、国に納める税金に関しても優遇措置が取られています。
これもひとえに、高齢者が安心して住まうための、サ高住の供給促進のため。そのどれも、開設におけるハードルを大幅に下げるような措置となっており、事業に参入しやすくなるはず。
知っていると知らないのとでは大違いですので、税制の優遇に関してもしっかりと確認して、申請できるものはきちんと申請するようにしましょう。
| 所得税・法人税 | 固定資産税 | 不動産取得税 | |
|---|---|---|---|
| 優遇の内容 | 5年間割増償却40% (耐用年数35年未満28%) |
5年間税額を3分の2に軽減 | 家屋課税標準から 1200万円控除/戸 土地家屋の床面積の 2倍にあたる土地面積相当分の価格などを減額 |
| 床面積要件 | 25㎡以上/戸 (専用部分のみ) |
30㎡以上/戸 (共用部分含む) |
30㎡以上/戸 (共用部分含む) |
| 戸数要件 | 10戸以上 | 5戸以上 | 5戸以上 |
融資制度も活用しよう
新築の場合
サービス付き高齢者向け住宅を新設するときは、住宅金融支援機構で実施されている「サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資」を利用することができます。
事業費の最大100%まで融資を受けることができ、また、35年固定年利といった長期固定金利返済ができるので、安定した事業運営ができるよう配慮された内容だと言えるでしょう。なお、金利タイプは15年固定金利を選ぶことができるので、事業状況に合わせて選択することもできます。
将来起こり得る金利上昇のリスクを避けて事業運営を行っていけるので、これからサービス付き高齢者向け住宅の運営を考えている事業者にとっては、多くの恩恵を受けられる制度です。
また、2014年4月からは、元金据え置き制度も導入され、サービス付き高齢者住宅の運営が軌道に乗るまで、返済負担額を軽くできるようになっています。
リフォームの場合
サービス付き高齢者向け住宅をリフォームによって開設するときは、「賃貸住宅リフォーム融資」を受けることができます。
最長20年の全期間固定制の金利で融資を受けることができますが、返済危難が10年以下か11年以上かによって、融資金利が異なるので事前に確認が必要です。また、融資後1年間は元本の返済を据え置いて、利息部分だけの支払いで済むので、事業開始後の返済負担を軽くすることができます。
なお、建物が建っている土地が借地である場合も融資対象です。それまで賃貸住宅の運営を行ってきた事業者が、建物を改築してサービス付き高齢者向け住宅の運営を始めるときなどは、この融資制度を活用すると負担を大きく抑えられるでしょう。




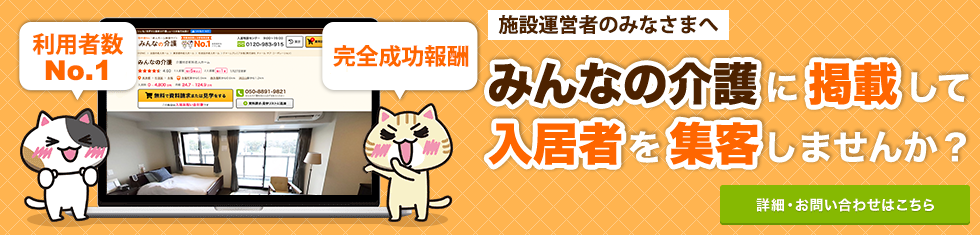
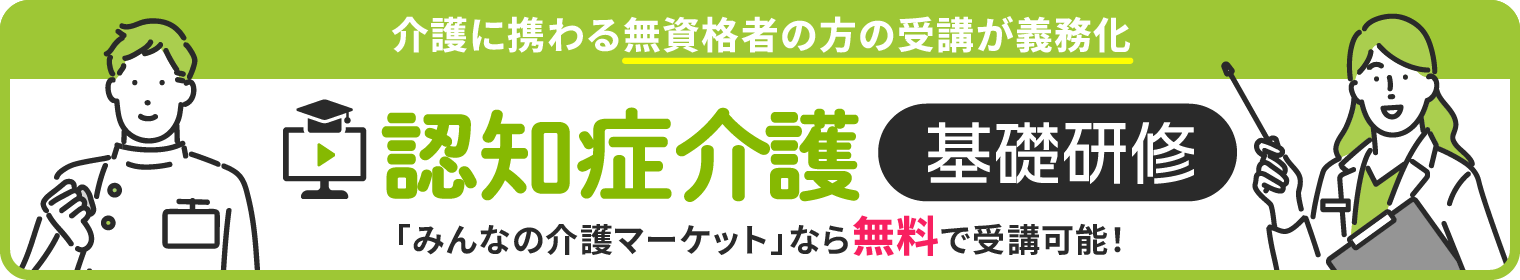
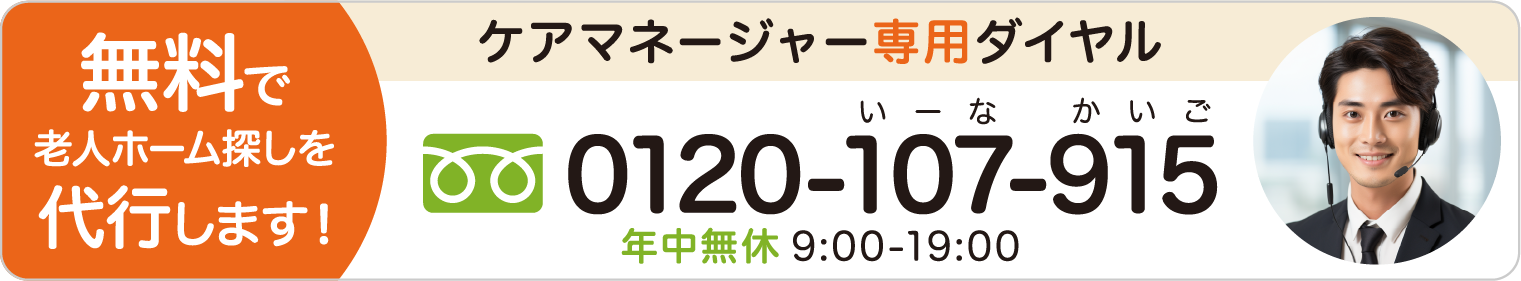
 この記事の
この記事の