特定施設入居者生活介護とは
特定施設とは
特定施設入居者生活介護における「特定施設」とは、どのような施設でしょうか。
特定施設とは、ケアマネージャーが作成したケアプランに基づき、食事介助や入浴介助、排泄介助などのほか、生活全般にかかわる身体的介護サービスと、機能回復のためのリハビリテーションを受けられる厚生労働省令が定めた施設のことです。
具体的には有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホーム、そして一部のサービス付き高齢者住宅(サ高住)があります。
特定施設の入居者が利用できる介護保険サービス

高齢者の暮らしをサポートするサービスや環境を提供する介護施設や老人ホームにはさまざまなタイプがありますが、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設は「介護付き」と呼ばれ、施設内で提供される介護サービスのほとんどを「定額制(包括報酬)」で提供します。
「特定施設入居者生活介護」とは、高齢者が可能な限り自立した毎日を過ごすことができるよう、特定施設に入居している入居者に対して提供される食事・入浴などの日常生活における支援や機能訓練などのサービスを指し、認定を受けている特定施設と一部の外部サービス事業所のみ提供できる居宅サービスとなっています。
「特定施設入居者生活介護」の指定は、有料老人ホームだけでなく、サ高住やケアハウスでも受けることができます。この指定を受けていないサ高住や住宅型有料老人ホームなどは、サ高住や住宅型有料老人ホームなどは、基本的に(併設しているかどうかにかかわらず)外部の介護サービスを、その人の状況に合わせて提供するため、同じ要介護度でも、人によって費用が違ってきます。
その点「介護付き」は「包括報酬」であるため、費用が一定額でわかりやすく、24時間切れ目のないサポートを安心して受けられることで、大変人気のある業態です。
※「特定施設入居者生活介護」とは、介護サービス(ソフト)そのものを言います。施設(ハード)のことではありません。「特定施設入居者生活介護」のサービスを提供して良いという指定を受けた施設(有料老人ホーム、サ高住、ケアハウスなど)が、定額制で介護サービスを提供でき、「介護付き〜」と名乗って良いのです。
3つの「事業種類」とは
特定施設入居者生活介護には、下記の3種類があります。
- 特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(地域密着型)
- 介護予防特定施設入居者生活介護(介護予防型)
さらに特定施設入居者生活介護は、「特定施設介護専用型」と「特定施設混合型」に分けられます。
指定を行うのは、特定施設介護専用型と特定施設混合型、介護予防型が「都道府県」で、地域密着型は「市町村」です。利用対象となるのは、特定施設介護専用型と特定施設混合型、地域密着型が「要介護者」、介護予防型が「要支援者」になります。
なお、都道府県の介護保険事業支援計画の中で定められている「必要利用定員」を超えるような指定申請に対しては、指定を行わないことができます。
短期利用特定施設入居者生活介護
在宅介護中のご家族の肉体的、精神的な負担の軽減をしたいときや、介護者が病気や事故にあったとき、冠婚葬祭や出張などで介護ができないときに、一時的に被介護者を預けることが可能なものもあります。
しかし、短期利用特定施設入居者生活介護の利用は入居定員の10%以下と定められているため、小規模な介護施設では受け入れてもらえないことも考えられます。
自費負担なら受け入れは可能なので、施設によっては空き室を利用して短期利用者を募集しているところもあります。
特定施設入居者生活介護の指定基準
厚生労働省が規定する基準とは

特定施設入居者生活介護サービスを提供できる介護施設(いわゆる特定施設)は、厚生労働省からの規定により、都道府県から指定を受けるために、一定の条件を満たすことが必要です。
人員配置や設備、運営基準などの条件を整え、都道府県に申請することで指定が受けられる特定施設の要件を整理してみましょう。
- 人員基準について
- 基本的に、入居者3人に対して介護職員、看護職員が1人以上いることが求められています。
いわゆる「3:1」というような形式で表示されていることが多 く、特定施設の中には、独自によりきめ細やかなケアを実現するため「2.5:1」「2:1」などの人員基準を定めていることがあります。 - ただし、最低基準を上回る人員基準の分は、介護保険費用に上乗せされた「上乗せサービス費」として利用者に請求することがほとんどです。
-
生活相談員 常勤1人以上
利用者:生活相談員=100:1以上(常勤換算)看護職員
介護職員要介護の利用者数に対して3:1以上
要支援の利用者数に対して10:1以上
※外部サービス利用型の場合は要介護の利用者に対して10:1以上、要支援の利用者に対して30:1以上
【看護職員】
・利用者が50人以下であれば1人以上(常勤換算)
・利用者が51人以上であれば50:1以上(常勤換算)
【介護職員】
常時1人以上配置すること計画作成
担当者ケアマネージャーを1人以上(兼務可)
利用者数に対して100:1以上機能訓練指導員 1人以上(兼務可)
※機能訓練指導員=理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のうちいずれかの資格を有するもの管理者 専従(支障がなければ兼務可) - 設備基準について
- 特定施設であるためには、一定の居室の広さや設備を整えている必要があります。
例えば介護付き有料老人ホームでは13㎡以上となっており、原則個室で提供されることが定められています。 -
必要設備 居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、機能訓練室、食堂 介護専用居室
の条件・原則個室
・介護付きの表示をすること
・プライバシーの保護に配慮し、適当な広さを確保すること
・地階でない
・出入り口が緊急避難時に問題がないこと
【介護付き有料老人ホーム】
原則個室、13㎡以上
【ケアハウス】
原則個室、床面積は21.6㎡以上
※ユニット型ケアハウスでは15.63㎡以上そのほか 車椅子移動ができる空間・構造を確保すること - 運営基準について
- 入居者が一定のサービスを享受することができるよう、特定施設では介護方針や地域との連携体制について、運営基準が定められています。 下記の表にある以外にも、利用者の体調が急変したときに備えて、事前に協力医療機関を定めておくことが努力目標として定められています。
-
サービス
計画利用者に合わせた特定施設サービス計画を作成すること 利用申込者
への同意入居前に運営規定の概要や職員体制などの重要事項を事前説明し、同意を得ること 入浴
サービス入浴を自力ですることが困難な利用者に対しては2回/週以上の頻度で入浴又は清拭すること 従業員
への教育スタッフの資質向上のための研修機会を確保すること 家族・地域
との関係地域との連携および家族との連携体制が充分にとれていること
また特定施設の開設は、自治体が「総量規制」をしているため、要件をクリアしたからといって開設ができるわけではありません。各自治体の立てる「介護保険計画」で、開設を目指す年度で、新設を許可する計画があるかを確認し、事業者募集にエントリーして、事業者として選ばれる必要があります。
すでにオープンしている住宅型有料老人ホームや、指定を受けていないサ高住などでも、条件をクリアすればエントリーはできます。エリアによっては1回の募集にたくさんの事業者が出ることもあり、とても競争の激しい業態であることも補足しておきます。
ここまでご紹介してきたように、特定施設の指定を受け、特定施設入居者介護を提供するためにはさまざまな基準が設けられています。
有料老人ホームにおいては、指定を受けていない老人ホームは「介護付き」や「ケア付き」とパンフレットやホームページに記載することが禁じられているので、注意しましょう。介護やサポートを必要とする高齢者にとって、安心できる暮らしの環境を整えた特定施設は、設置基準が設けられ、都道府県からの指定を受ける必要があります。
自治体によっては介護保険費の抑制のため、総量規制により年次ごとの新規開設数が制限されていることもありますので、事前に調べてみると良いでしょう。
指定されることのメリット・デメリット
特定施設入居者生活介護へ指定されることの一番のメリットは、利用者や家族から信頼されることです。安定した利益を生み出すには、介護事業者として信頼されることが何よりも重要です。
また、2000年に導入された介護保険によって、事業者は利用者の介護度によって一定の介護報酬が得られるようになりました。「介護付き」や「ケア付き」の老人ホームとして運営していくと、介護度の高い方の希望が多くなり、介護報酬が得られる可能性も高くなります。
さらにこのような施設では、介護保険で定めた以上のサービスや、介護保険外と見なされるサービスを提供することも可能です。もちろん、利用者や家族が選択することになりますが、事業の柱として大きな収入源になります。
デメリットとしては、特定施設と指定されることで行政側の規制やチェックが厳しくなることが挙げられます。特定施設入居者生活介護に定められた運営基準に則って、人員配置や設備、サービスの質を維持しなければいけません。
また、サービス付き高齢者向け住宅と違って、特定施設には利用者の看取りまで含めたサービスが期待されます。
指定申請の流れ
特定施設入居者生活介護の指定を受けるには、まず、市区町村と都道府県での事前相談が必要です。このとき、都道府県での協議を行う前に、建築を計画している地元の市区町村の福祉所轄課で事前に協議を行う必要があります。
その後、建築確認の申請および受理を経て、施設の登録が行われます。登録後、今度は特定施設入居者生活介護の指定申請を行い、指定予定日の前月の中旬に現地確認が行われ、翌月の1日に特定施設の指定が行われます。
なお、都道府県と事前協議を行うまでに、面積の確認ができる建設予定の施設の設計図面を作成しておかなくてはなりません。また、特定施設の指定申請は、指定予定日の前々月の末日までに行う必要があり、申請時には工事の着工が始まっているのが通例です。
それから指定予定日の前月中旬に行われる「現地確認」では、建物と必要な備品の確認が施設のある現地にて行われます。都道府県ごとにプロセスや日程は異なるので、申請を行うときは事前にしっかりと確認しておく必要があるでしょう。



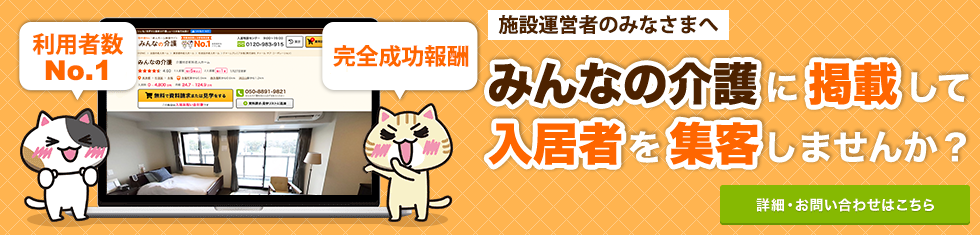
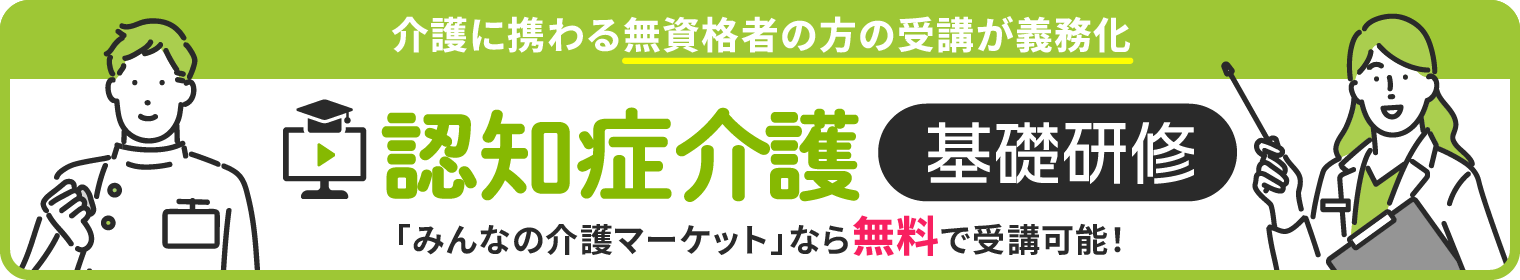


 この記事の
この記事の