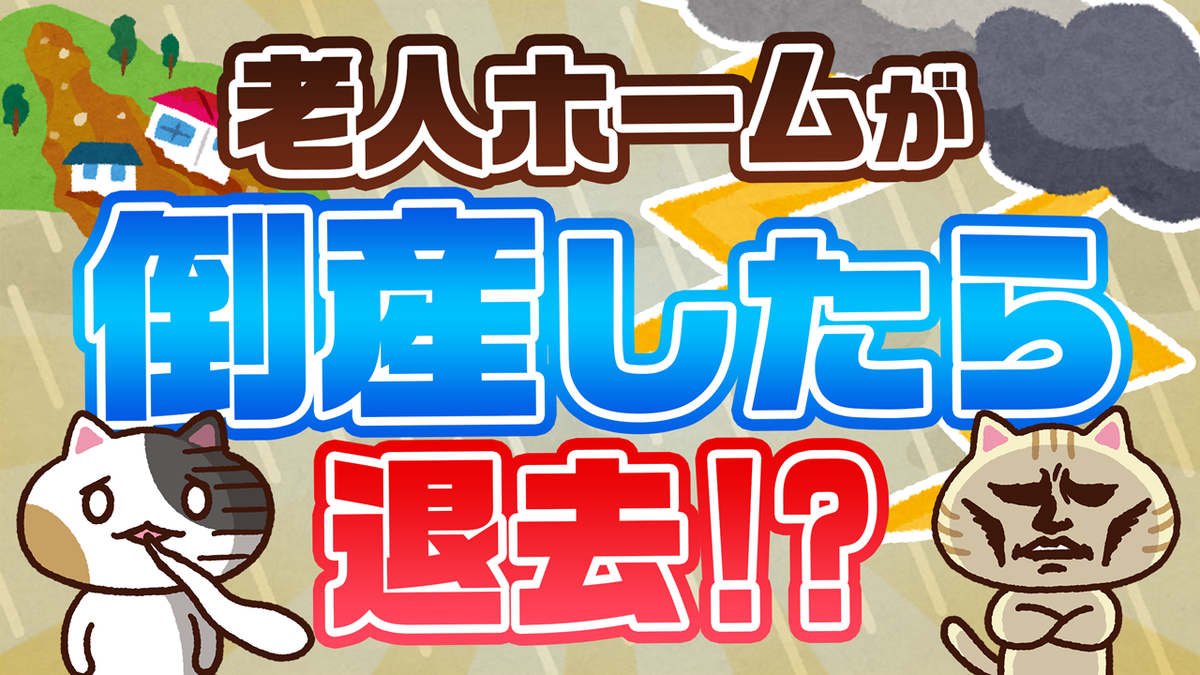潰れる介護施設の特徴

今回の記事では、潰れる介護施設の特徴を解説します。
施設探しの際には安定した介護施設を選びたいものですよね。
潰れる介護施設の特徴を知っておくと、施設見学の際に安定した施設かどうか見極めることができます。
設備が古い
設備が古い施設は注意が必要です。
年数とともに施設が古びてくることはしかたありませんが、老朽化や壊れたままの設備を放置している施設は、修繕にお金をかけられないくらい経営が悪化している恐れがあります。
もちろん、設備が綺麗だからといって倒産の心配がないわけではないので総合的な判断が必要です。
新規オープンの施設を探す入居者が少ない
入居者が少ない施設も注意しましょう。
入居者数がいない場合、施設の収入が少なくなるため、倒産のリスクが高まっていることが考えられます。
介護施設が潰れる要因でトップを占めるのは「経営不振」です。
収入が少ない施設は、設備費や人件費を節約していることが多く、サービスが十分でないこともあります。
入居者数をはじめ経営状況が安定しているかどうか、実際の見学や施設からの資料などを通してチェックしてみましょう。
職員の数が少ない
職員の数が不足していることも、潰れる介護施設の大きな特徴です。
運営に必要な介護スタッフの体制が整っていないと、入居に対してのサービスが不十分になってしまい、結果的に入居者の数が減ってしまうこともあります。
また、人件費を節約しているため職員の数が少ないというケースも考えられます。
この場合では、人件費を充分に確保できないほど経営が悪化している可能性もあります。
施設の規模のわりに職員の人数が少なく、スタッフが忙しそうにしている、ひとりの職員で多くの入居者のケアをしているなど、きちんとした介護サービスが提供できていない施設は要注意です。
希望条件から施設を探す介護施設の倒産件数と原因
社会の高齢化に伴って成長産業とも言われる介護業界ですが実は近年、倒産する事業者が増えています。
介護事業所の倒産件数の推移

「東京商工リサーチ」が行った調査によれば、2021年における介護事業者の倒産件数は計81件となり、昨年の2020年よりも減少しました。
倒産した事業者の業態をみていくと、「通所介護」もしくは「訪問介護」が最も多い64件を占めており、入所施設である「有料老人ホーム」で4件、「その他の老人福祉・介護事業」で13件発生しています。
通所介護と訪問介護の倒産数増加については、規制緩和によって新規事業者が一気に参入して競争が激化し、それにより収益が見込めなくなった事業者が相次いだことが原因です。
また、多くの利用者がいた要支援者向けの介護予防サービスが自治体の管理となったことも、要因のひとつだと言われています。
一方、有料老人ホームの倒産理由としては、運営者が安易な事業拡大を図って施設数を無理に増やした結果、入居者が想定していたほど集まらなかったり、従業員の確保が間に合わず、結果的に資金繰りが悪化したというケースが多いようです。
倒産の背景にある介護職員の人材不足
ますます顕在化してくる日本の超高齢社会を支えるためには、介護職員の増加が必要不可欠です。
しかし、ノウハウや知識・経験を持つ質の高い介護スタッフ、人材確保には多くの事業者が頭を悩ませています。
現場の人手が足りずに、ベテランスタッフへの負荷が重くなって辞められてしまったり、経験が浅い介護職がいきなり現場を一人で任され、仕事のきつさに根をあげてしまったりと、人手不足によってさらなる離職が発生するという悪循環からなかなか抜け出せずにいるのが現状です。
いくら設備や建物が新しく綺麗な老人ホームでも、働くスタッフの質が高くなかったり、そもそも職員の数が少ない状況では安心して入居できません。
事業所が増えていることも原因の一つ
介護事業所が増えていることも、倒産する介護施設が増えている原因のひとつです。
介護業界では慢性的に人材不足が続いていて、事業者数は増えているのに比べて、現場の人材不足は解消されていません。
施設側も求人に力を入れていますが、売り手市場になっているため採用の競争が激しく、施設同士で人材の取り合いが続いています。
安定した介護施設かを見極めるために
社会的信用度が高い事業者が運営している施設を選ぶ

有料老人ホームの運営会社は介護関連事業を収益の柱とした企業だけでなく、大手企業が介護業界に数ある事業のうちのひとつとして新規参入している場合があります。
名前を聞いたことのある大手企業が運営している施設は、資本があることから倒産はしにくい傾向にあるといえます。
しかし、親会社の経営判断で介護事業を他社に事業譲渡する可能性もあるので注意が必要です。
施設探しの際には、運営企業の知名度や財務状況なども確認しておくことがおすすめです。
希望条件から施設を探す常に空室数がいくつもある施設は避ける
入居希望者が殺到してなかなか入居できない人気の高い老人ホームもあれば、入居者の数が定員に満たずに閑散としているところもあります。
入居者が定員より少ない施設は、経営する事業者の収支が不安定である恐れがあります。
定員と実際の入居者数にギャップがある施設は、避けた方が良いかもしれません。
必ず施設見学に行く
気になる介護施設が潰れないためには、施設見学に行くことをおすすめします。
見学当日は、職員の様子を十分に気をつけながら確認しましょう。
施設の設備のほかに、スタッフがバタバタしていないかや入居者の表情が暗くないかなど、全体の雰囲気を観察しましょう。
ほかにも施設が綺麗に掃除されているかについてもチェックすることが大切です。
施設見学の際に気になる点があれば都度スタッフに相談するようにしましょう。
介護施設が潰れたときの施設の対応
介護施設が倒産したからといって、すぐに退去になることはまずありません。
ただし、介護施設が別の経営者に引き継がれた場合と引き継がれなかった場合で施設の対応は異なります。
新しい運営元によってどのような違いがあるのか、見ていきましょう。
ほかの運営会社に引き継がれた場合
老人ホームが倒産すると、多くの場合は別の事業者に運営を引き継ぐ「事業譲渡」が行われます。
事業譲渡が行われても施設の運営会社が変更するだけなので、入居者に退去要請が出ることはありません。
また、働いている職員もそのまま残ることが多く「倒産すると馴染みの職員がいなくなった」ということも少ないようです。
ただ、建物の老朽化が著しい場合は引き継ぎ時に改築を行い、一時的、もしくはそのまま別の施設への転居を余儀なくされる場合も考えられます。
利用していたサービスが利用できなくなる場合もある
運営する事業所が変わると、これまで施設内で提供されていたサービスが停止されて使えなくなる場合もあります。
また、サービス内容を一部変えて引き継いで利用できるケースもありますが運営方針によるので注意しましょう。
これまで同様のサービスが利用できても料金が変わることもあります。
ほかの運営会社に引き継がれなかった場合
事業の引き継ぎ手が見つからなかった場合、その施設は閉鎖となり、新たな転居先となる施設を探さなければなりません。
倒産する前に新しい入居先を紹介してくれる場合もあるようですが、あくまでもラッキーなケースだと思って良いでしょう。
また、稀なケースですが自治体側が緊急措置として、倒産した施設の入居者を近隣の特別養護老人ホームで受け入れるという措置が取られる場合もあります。
希望条件から施設を探す倒産したら入居一時金が返還される

入居一時金の保全措置を利用する
入居一時金の保全措置は2006年の老人福祉法の改正により設けられていました。
この制度では、もし施設が倒産した場合に上限500万円の返還対象の範囲にすることが義務付けられていましたが、対象が2006年4月以降に届け出が出された施設だけでした。
2021年4月1日からは全ての老人ホームで保全措置が義務化されました。
Q. 老人ホームの入居一時金が返還されるのはどんな場合?返還の仕組みを解説
入居者生活保障制度を利用する
入居者生活保障制度とは、全国有料老人ホーム協会が設けている保全措置です。
この制度を利用した場合、もし施設倒産後に入居一時金が返還されない場合、全国老有料老人ホーム協会から入居者に入居一時金の返還対象額が支払われます。
この制度の特徴として、保全措置で定められている金額の保全だけではなく、原則的に終身にわたり一定金額が保全されます。
なお、入居者生活保障制度を利用するには、入居契約者と事業者との間で「入居追加契約書」の契約をする必要があります。
入居前の確認として、入居する施設がこの「入居者生活保障制度」を利用しているか確認しましょう。