地域包括支援センターとは
日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。2025年(令和7年)には団塊の世代が75歳以上となりますが、その後も75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想され、医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれています。
このため、厚生労働省においては、2025年(令和7年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。
地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しています。
その目的は、高齢者の「総合相談」、「権利擁護」や「地域の支援体制づくり」、「介護予防に必要な援助」などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することです。
地域包括支援センターの設置場所

地域包括ケアシステムは、市町村が定める日常生活圏域(30分でかけつけられる圏域、概ね中学校区)ごとに構築するものとされ、その中核的な機関である地域包括支援センター(ないしブランチ(支所))も原則日常生活圏域ごとに設置されています。
令和4年4月末現在、その数は全国で5,404ヵ所です(ブランチを含めると7,409ヵ所)。
地域包括支援センターは、市町村が直営で実施するほか、市町村が社会福祉法人や社会福祉協議会、医療法人等に運営を委託している場合もあり、特別養護老人ホームなどの介護事業所に併設されている場合もあります。
どこにあるのかは、市町村の介護保険担当窓口に問い合わせると良いでしょう。
市町村のWebサイトでも探すことができます。
居宅介護支援事業所との違い
地域包括支援センターは高齢者の総合相談を行う窓口ですので、高齢者のためのよろず相談を受け付けています。
例えば、「近所の一人暮らしのおじいちゃんの姿を最近、見ないんだけど」「お隣の老夫婦の家にゴミがたまって困る」といったような、地域住民からの相談も受け付けています。
一方、居宅介護支援事業所はケアマネージャーが常駐する事業所で、要介護者のケアプランの作成や介護サービス事業所の紹介を行います。
また、それらを通じて、介護に関する全般的な質問・相談も受け付けています。
わかりやすく言うと、「地域包括支援センター=すべての高齢者の相談を受け付ける施設」で、「居宅介護支援事業所=要介護認定を受けている高齢者のケアプランを作成する事業所」です。
地域包括支援センターの4つの役割
地域包括支援センターには、「総合相談支援業務」「権利擁護業務」「介護予防ケアマネジメント業務」「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」の4つの役割があり、保健師(もしくは経験豊富な看護師)や社会福祉士、主任ケアマネージャーが配置されています。
また、地域包括支援センターによっては、市町村からの委託を受けて「在宅医療・介護連携」を担っていたり、認知症地域支援推進員や生活支援コーディネーターが配置されるなど、その役割は多岐に渡ります。
具体的な役割について1つずつ見ていきましょう。
地域の高齢者の総合的な相談窓口

地域包括支援センターは、医療や福祉など、地域内にあるさまざまな社会資源を活用し、制度の枠を超えて高齢者に適切なサービスを案内する役割を担っています。
高齢者の生活上の困りごとに対して、総合的に相談に乗ってくれる場所であると言えるでしょう。
在宅介護の悩みに対しても、さまざまな視点から一緒に解決策を考えてくれます。特に、初めて家族の介護に直面した人は、わからないことや悩み事が多くなりがちです。
地域包括支援センターを介護の相談窓口として活用すれば、在宅介護生活をスムーズに進めることができるでしょう。
虐待などから高齢者の権利を守る
地域包括支援センターの役割のひとつが、高齢者の「権利擁護」を実現すること。
高齢者に対する詐欺や、悪徳商法などの消費者被害へ対応するほか、高齢者虐待の早期発見や防止に努めることも地域包括支援センターの業務です。
虐待防止に関しては、虐待を受けている本人や家族だけでなく、虐待に気づいた近所の人などからの情報も受け付けています。
また、成年後見制度の手続き支援も行っています。
もし認知症を発症してしまったら、金銭管理や法律上の手続き、介護保険サービスの契約などが難しくなってくるでしょう。
そういったときに周囲の人が後見人となって、高齢者の財産を不当な契約などから守るのが成年後見制度です。
これを含む各種支援制度の利用について、地域包括支援センターでは助言を受けることができます。
ケアマネージャーへの支援
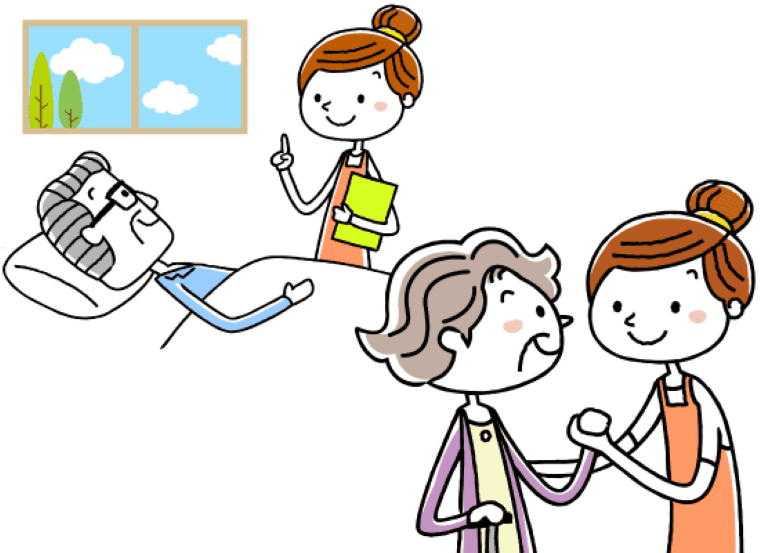
地域のケアマネージャーをサポートすることも、地域包括支援センターの重要な役割です。ケアマネージャーを対象とした研修会を実施しているほか、ケアマネージャーのネットワークづくりの支援なども行っています。
また、ケアマネージャーは要介護認定を受けた人への「ケアマネジメント」を行っていますが、ケアマネージャーだけでは対応が困難になるケースも少なくありません。そんなとき、地域包括支援センターに常駐する経験豊富な専門家がアドバイスを行うなどして、その業務をサポートするのです。
介護予防マネジメント
地域包括支援センターでは、介護認定審査において「要支援1、2」の判定が出た高齢者を対象に、「介護予防ケアプラン」の作成支援を行っています。
介護予防につながる介護サービスの利用方法を、要支援認定者と話し合いながら決めていくわけです。また、介護認定で「非該当」の判定が出た人や、「要介護認定を申請していないけれど、介護予防に取り組みたい」という高齢者を対象に、介護予防教室などを行っています。
地域包括支援センターのよくある相談事例
地域包括支援センターではどんな相談が寄せられ、どのような対応をしているのでしょうか。
実際に報告された相談事例を紹介します。
介護保険サービス利用の相談
- 相談事例1
- 介護予防や日常生活支援総合事業の利用について脳梗塞により介護が必要となった母の対応がわからないAさん。Aさんに対し相談員は、要介護認定の受け方や老人ホームなどの紹介、介護をするために必要な手続きのサポートをしました。
- 相談事例2
- リハビリ中のため一人で家事をするのが難しくて辛いというBさん。
支援員は家事代行のヘルパー、リハビリも兼ねたデイサービスの利用の提案をしました。さらに介護保険申請の手続きも支援しています。 - 相談事例3
- 父が筋力の衰え・気力の低下により外に出るのが億劫になったと相談に訪れた娘のCさん。
介護予防サービスの提案をし、Cさんの父は介護予防の運動に励むようになりました。
上記3つの事例のように少しでも不安を感じたら、地域包括支援センターへ相談をし、悩みの解決の糸口をもらいましょう。
高齢者の友達をつくりたい
- 相談事例4
- 親しんだ街から離れ、息子夫婦との同居生活を始めたDさん。知らない土地のため馴染めず友人ができないまま、家の中に塞ぎ込み困っていると息子夫婦から相談がありました。相談員はDさんに地域のカルチャーセンターや交流スペースを紹介。Dさんは将棋や茶道など地域の方々と楽しむようになり、次第に笑顔が増えていきました。
- 相談事例5
- 病気と診断されてから受診していなかった独居Eさん。地域の方が気にかけ相談されました。相談員がEさんの家へ訪問し、話を伺ったところ治療やさらに病気が見つかることが不安と話されていました。
- 説得し受診すると、定期検査が必要と診断されました。Eさんが独りで悩まないよう相談員は定期的に訪問、主治医や地域医療との連携をとり見守り支援をしています。
地域包括支援センターの利用対象者
地域包括支援センターの主な利用対象者は以下の通りです。
- 対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者の方
- 高齢者支援の活動に関わっている方
それぞれの詳しい条件についてみていきましょう。
対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者の方
対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者の方が利用することができます。
地域包括支援センターは一般的に、介護予防や介護支援を必要とする高齢者のための地域拠点といったイメージです。
市町村ごとに1ヵ所以上設けられていて、公立中学校の学区を基準にエリア分けされているケースが大半です。
日常生活のお困りごとを相談したり、介護保険の申請窓口として利用したりなどの活用方法があります。
高齢者支援の活動に関わっている方
地域包括支援センターは高齢者本人のほか、高齢者の支援活動をしている高齢者のご家族や介護職など、高齢者の介護に関わっている方も利用することができます。
「高齢者支援の活動に関わっている方」には、本人の代理で介護予防や生活全般の相談を行う家族・親族なども含まれます。
認知症などで高齢者本人の判断力が低下しているケースがこれにあたります。
離れて暮らす親に関して相談する場合は、実際に支援を必要とする親の居住区にある地域包括支援センターに連絡することがポイントです。
将来的に遠距離介護を考えている方は、子の住んでいる地域の地域包括支援センターが相談窓口ではない点に注意しておきましょう。
地域包括支援センターの利用までの流れ
地域包括支援センターを利用する際の流れについて説明します。
なお、自治体によっては「高齢者あんしん相談センター」といったわかりやすい名称を用いている場合もあります。
1. 来所または電話相談
地域包括支援センターを利用したい場合は、 まず地域包括支援センターに来所、または電話をしましょう。
その日の受付担当職員が相談内容をヒアリングして、どのようなサポートが必要なのか、アドバイスをしてくれます。
「介護のことで誰に相談して良いのかわからない」といった場合も、職員が丁寧に聞き取りをしたうえで、必要な窓口を紹介します。
2. 自宅訪問・本人との面談
相談者の情報は、受付担当職員から地域包括支援センターに配置されている各専門家が引き継ぎます。
地域包括支援センターに在籍している保健師・看護師や主任ケアマネージャー、社会福祉士や介護支援専門員のなかから担当者が自宅訪問をして、本人との面談を行います。
このとき、利用したい介護サービスが決まっている場合は、担当のケアマネージャーが同行します。
面談では、本人の状況に応じて以下の説明を行います。
- 介護保険の申請手続き代行や介護保険サービスの内容調整について
- 介護予防や日常生活支援総合事業の利用について
- 居宅介護支援事業への紹介について
3. 必要なサービス・事業所へ紹介
自宅訪問による面談を経て、担当職員は主に次の4つのサービスや対応をおこないます。
- 介護保険申請手続き代行・サービスの調整
- 本人や家族に代わって介護保険の申請手続きをします。
また、要支援1・2の方を対象に、介護保険サービスのうち通所リハビリ(デイケア)や訪問看護、ショートステイをはじめ、福祉用具レンタルや住宅改修など、本人の状況に応じた利用調整をします。 - 介護予防、日常生活支援総合事業の利用
- 要支援1・2の方、基本チェックリストの基準に当てはまる方は、介護予防などの利用が可能です。
担当職員は、訪問型サービスまたは通所型サービスのなかから本人の状況に合ったサービスの利用を調整します。 - 居宅介護支援事業へ紹介
- 地域包括支援センターでは要支援1・2の方が対象のため、介護保険で要介護相当と思われる場合は、居宅介護支援事業への引き継ぎを行います。
本人や家族が居宅介護支援事業所の利用を希望する場合も、支援がスムーズにつなげられるように対応します。 - 専門職員の対応
- 本人の状況に応じて、成年後見制度や認知症相談窓口など、専門機関への紹介をはじめ、情報に基づいて連携を図ります。
地域包括支援センターを利用するメリット・デメリット
地域包括支援センターを利用することで得られるメリットは何があるでしょうか。考えられるデメリットもあわせて説明します。
メリット

地域包括支援センターを利用する大きなメリットは、介護に関する相談をワンストップで対応してもらえるということです。
ケアマネージャーや保健師、社会福祉士など、介護やその周辺分野のプロフェッショナルに答えてもらえるため、不安を的確に解消することができます。
無料で介護相談できる
介護が必要な状態であっても、経済的な問題で介護サービスの利用をためらっていたり、相談自体に抵抗がある、といった方も少なくないようです。
そんなとき、利用料の心配のない地域包括支援センターは、 その方の心身状態や経済状況などを踏まえた適切な対応や専門機関への連携をしてくれます。
高齢者虐待などの問題を早期発見できる
介護を受けている高齢者への虐待や権利侵害に関するニュースが後を絶ちません。地域包括支援センターでは、高齢者の介護で起こりうる虐待などの相談を受け付けています。
高齢者への虐待や権利擁護などを扱うことは、地域包括支援センターに在籍する専門家でなければ対処が難しい問題です。
介護を中心とした高齢者の専門知識やスキルを身につけている地域包括支援センターの職員に相談すれば、早期発見や、迅速な対応が期待できます。
高齢者虐待の問題は、自身の家族だけではなく、近所や地域の高齢者にも起こる可能性があります。 地域包括支援センターに通報することで、地域の高齢者の生命や財産、権利が守られる機会を引き上げることができるでしょう。
デメリット
直接的な支援が受けられるわけではない
地域包括支援センターは、介護の相談窓口です。あくまで 介護や福祉などで必要なサービスを紹介して、適切な介護事業者や医療機関、行政機関などへの調整や橋渡しをしている機関であることをおさえておきましょう。
地域包括支援センターを上手に利用すれば、自立や要支援の方を中心に介護予防や介護サービスを受けながら自宅で暮らし続けることができます。
しかし、加齢、病気や怪我によって介護の必要な度合いが高くなると、家族の負担は増えていくでしょう。
そこで、施設への入居も検討しておくことをおすすめします。次の項では、 介護負担の軽減のためにおすすめの介護施設を一つずつご紹介します。
介護負担を軽減するためにおすすめの老人ホーム
ここからは、家族の負担を軽減しつつ安心して介護サービスを受けたい・受けさせてあげたい方におすすめの老人ホームを紹介していきます。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは民間の運営する老人ホームで、 要介護度が高くても本格的な介護サービスや生活支援を定額で利用できます。
施設が提供する食事や生活相談、見守りや安否確認などを安心して受けられます。
介護費用が心配な方も、月々の予算を立てやすいといえるでしょう。
介護保険サービスをはじめ、介護職員による服薬管理や褥瘡のケアなど医療行為が受けられることも特徴です。
【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)
介護付き有料老人ホームを探す住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、自立の方から比較的要介護度が高い人まで、幅広く受け入れている介護施設です。
介護度に応じて必要なサービスのみを利用できるため、使った分だけの介護費用で済みます。
イベントやレクリエーションが充実していて、充実した生活を送ることができる老人ホームです。また、入居者同士のコミュニケーションが活発なところも特色となっています。
【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説
住宅型有料老人ホームを探すサービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅は、自立の方・比較的介護度の低い方が入居する、シニア向けの住宅です。
一人暮らしは不安な方も、食事や生活相談サービスを受けながら安心して暮らせます。
「サ高住」とも呼ばれていて、一般的な老人ホームが利用権方式なのに対して、賃貸物件であることが特徴です。
一般型の場合、必要な介護サービスは外部の介護事業者と契約して利用します。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)
サービス付き高齢者向け住宅を探す認知症の場合はグループホームを検討する
グループホームは、認知症と診断された高齢者のための介護施設です。
施設所在地の自治体に住民票のある方が入居対象で、住み慣れた地域を離れることなく暮らし続けられます。
入居者全員が認知症患者のため、一般的な老人ホームに比べて周囲に対し気兼ねがありません。
グループホームでは、少人数で共同生活を送りながら、日常の家事や買い物を分担して実施。
認知症ケアの専門スタッフのサポートを受けながら、生活リハビリを通して症状の進行緩和を目指します。
グループホームを検討されている方は以下から施設をお探しください。
【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説
グループホームを探す
地域包括支援センターに在籍する3種類の専門家
地域包括支援センターには、社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーの3種類の専門家が配置されており、それぞれが専門性を発揮して連携しながら地域住民に寄り添い、適切な問題解決へと導くサポートを行います。
| 社会福祉士 | 保健師 | 主任ケアマネージャー | |
|---|---|---|---|
| 対応する内容 | ・介護や生活支援 ・消費者被害 ・困難事例 ・多問題家族 ・虐待問題 ・成年後見制度の利用援助 |
・健康 ・医療 ・介護予防 ・地域支援事業 ・虐待問題 |
・介護全般 ・ケアマネ支援 ・相談 ・困難事例 ・多問題家族 ・虐待問題 ・サービス事業者連携 ・事業者の質の向上 |
| 主な連携先 | ・行政 ・専門機関 |
・保健所 ・病院 ・薬局 |
・介護サービス事業者 |
社会福祉士
社会福祉士は、地域包括支援センターにおける相談窓口として、「総合相談」「権利擁護」に関する対応を行っています。相談は直接窓口で行うほか、電話でも可能です。
具体的な業務内容は、相談支援業務のほか、自宅や施設などへの利用者訪問、高齢者独居世帯や高齢者夫婦世帯の安否確認、成年後見制度の利用援助、消費者被害や虐待問題の解決など、さまざまな事案があります。
公的な制度だけではなく、地域にあるいろいろな団体やサービス、人を活用しながら高齢者を支えています。
保健師
保健師は病院や保健所と連携しながら、高齢者やそのご家族から受ける医療・介護の相談に対応する職種です。「介護予防マネジメント」として介護予防プランの作成にくわえて、身体機能の悪化や要介護状態になることへの予防対策などを行っています。
また、健康づくり教室や口腔ケアセミナーなどを開催したり、健康診断の受診を促したりするなど、地域住民に疾患予防の意識を根付かせる活動も業務のひとつ。ほかにも高齢者本人やご家族からの要望に応じて、主任ケアマネージャーなどと連携しつつ、その方に合ったケアプランの作成を行います。
主任ケアマネージャー
主任ケアマネージャーは、「包括的・継続的マネジメント」を担い、介護全般にかかわる相談に対応。介護サービス事業者と連携を図りながら地域で活躍するケアマネージャーへの支援などを行っています。
具体的な業務は、新人ケアマネージャーの指導や相談、育成、要介護者にケアプランを作成する際のケアマネージャーへの支援、相談など。さらに地域の介護問題や課題の発見・解決、地域の介護環境の発展などに取り組むことも期待されます。
また、地域ケア会議の開催や支援困難事例などへの指導、助言なども主任ケアマネージャーの役割です。
地域包括支援センター誕生の背景と課題
医療や介護ニーズの高まりに応えるために生まれた
地域包括支援センターは2005年に誕生しました。
団塊の世代が後期高齢者になる「2025年問題」の対策に向けて、介護保険制度改定をきっかけに構築が始まった地域包括ケアシステムの一環です。
ますます強くなる医療や介護ニーズの高まりに応えるため構想されました。
厚生労働省が主導する地域包括ケアシステムは、地域における介護を大きく変えるものです。
高齢者の生活に欠かせないサービスや事業所の連携強化が目的といえます。
そんななか、高齢者の住まいを取り巻く医療や介護、生活支援や介護予防を有機的につなぐ地域包括ケアシステムの中核拠点として設置されました。
認知度向上・地域との協力強化が課題
誕生してからおよそ20年になる地域包括支援センターには、いくつかの課題も抱えています。
まず、 介護は高齢者の家族だけの問題ではなく、地域全体で取り組むべきものという住民の意識変革です。
「老老介護」や「ヤングケアラー」などの問題が取り沙汰されているように、介護者の家族の負担が過剰に大きくなるケースも増加しています。
地域包括支援センターには、地域の高齢者の介護や見守りを地域住民全体が取り組むという啓発活動を強める必要があるでしょう。
また、地域包括支援センターの存在自体がまだあまり知られていない現状も変えていかなければなりません。
高齢者の介護問題に直面している方以外は、日常生活で地域包括支援センターを知らないまま過ごしていることも多いと考えられます。
もし自分や家族の介護が必要になったとき、地域の高齢者の介護で気になることが起こったとき、地域包括支援センターへの相談につなげられるかどうか、今後知名度アップに力を入れる必要があります。
「対応がひどい」などの苦情もみられる
地域包括支援センターに対して、ネット上では「対応がひどい」「使えない」といった口コミを見ることがあります。
実際のところ、地域包括支援センターの利用に際して嫌な思いをした、という方も少なくありません。
地域包括支援センターへのネガティブな評価がみられるのは、施設や職員に集中する業務量が多く、時間的な余裕がないと感じている点が大きいと考えられます。
厚生労働省のアンケート調査によると 「業務の種類と量が多すぎる」「通常業務が忙しいため新しい事業等に取り組む余裕が無い」といった声が聞かれました。
また、地域によって職員の知識など力量に偏りがあることも、地域包括支援センターの対応を問題視する理由となっています。
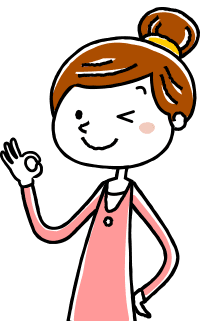 この記事のまとめ
この記事のまとめ- 地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域でサポートするためにつくられた拠点
- 相談窓口・権利擁護・支援・介護予防といった4つの役割を担っている
- 地域包括支援センターには、社会福祉士・保健師・主任ケアマネージャーが配置されている
- 利用対象者は地域に住む65歳以上とその支援者
他の人はこちらも質問
地域包括支援センターとは何をするところか?
地域包括支援センターでは地域に住む高齢者やその支援者の相談窓口、介護予防の援助、高齢者の権利を守る、ケアマネージャーの支援を行います。
設置主体は市町村で、日常生活圏内(30分ほどで行ける距離)に構築されています。
地域包括支援センターは何種?
地域包括支援センターでは社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーの3種の専門家が配置されています。それぞれの専門分野を生かした対応・連携を図り、高齢者に寄り添った適切な問題解決をします。
地域包括支援センターはなぜできた?
1989年のゴールドプランにより、高齢者やその家族が相談・援助を身近な場所でできるように、のちの地域包括支援センターとなる在宅介護支援センターを設置しました。
2005年の介護保険法の見直しにより地域包括支援センターが誕生。地域高齢者が気軽に相談できる窓口として、包括的そして継続的に支援を行います。
地域包括支援センターを設置できるのはどれか?
地域包括支援センターを設置できるのは市町村です。運営は市町村や市町村が運営を委託した社会福祉法人・医療法人などです。さらに介護事業所に併設を依頼する場合もあります。



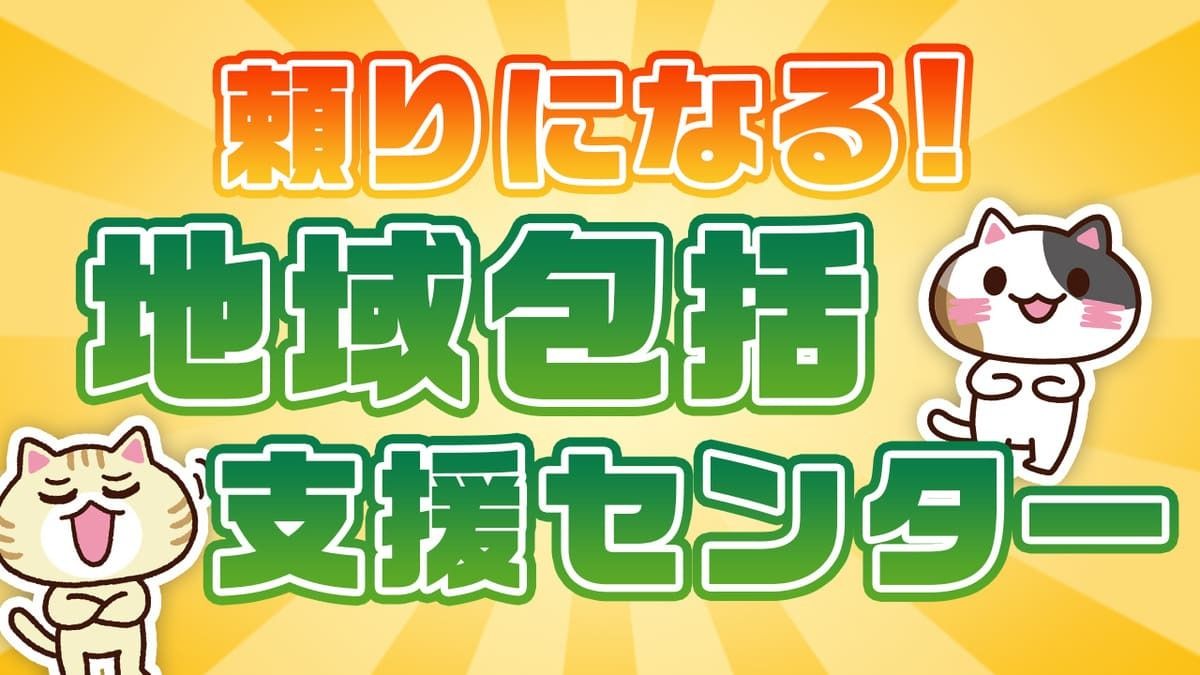





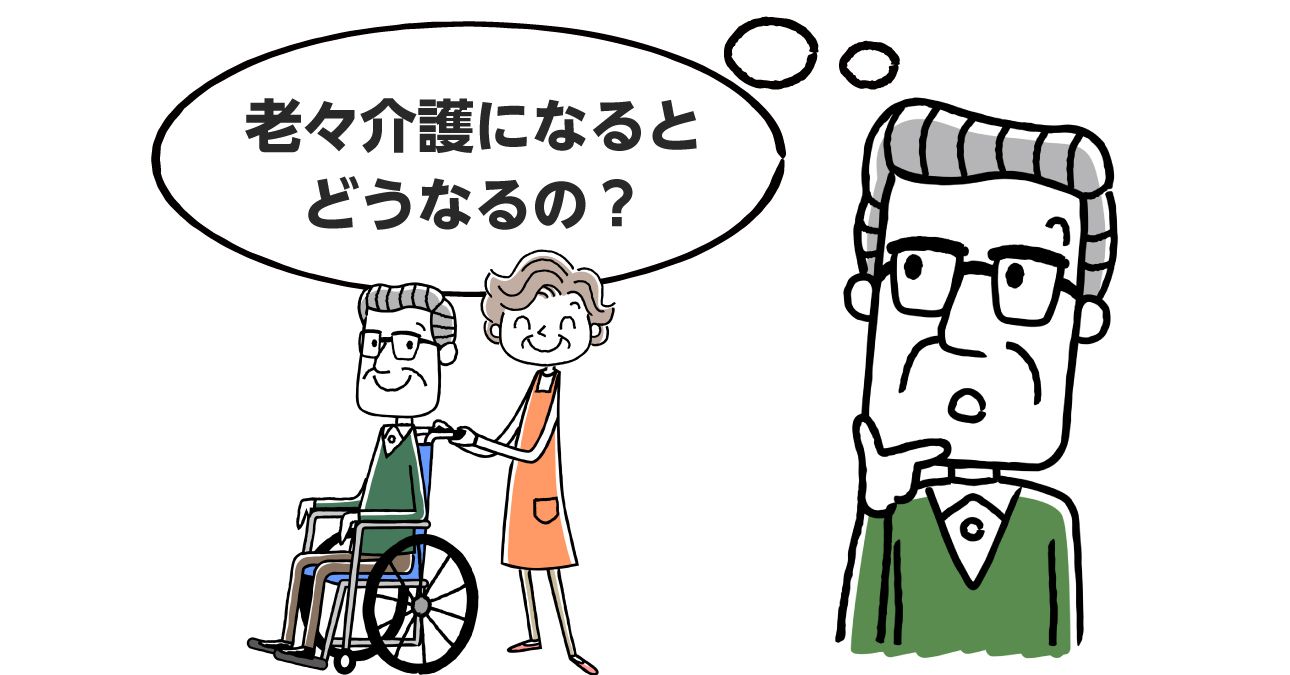
 この記事の
この記事の




