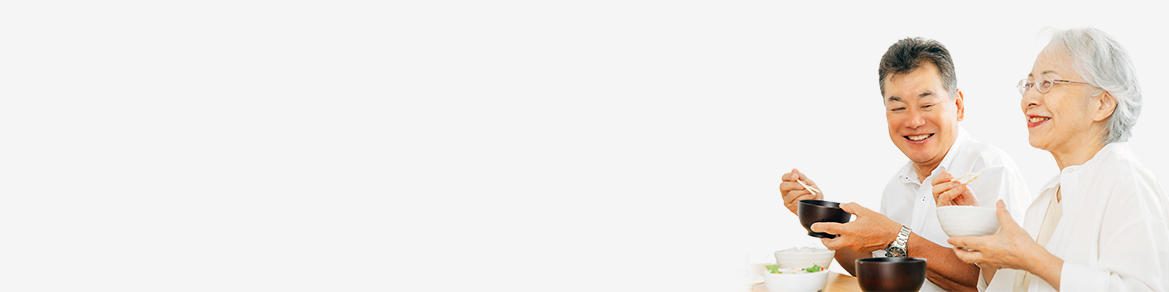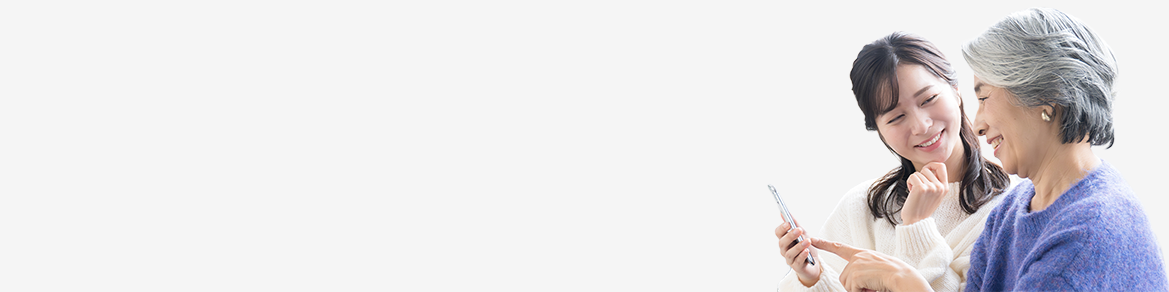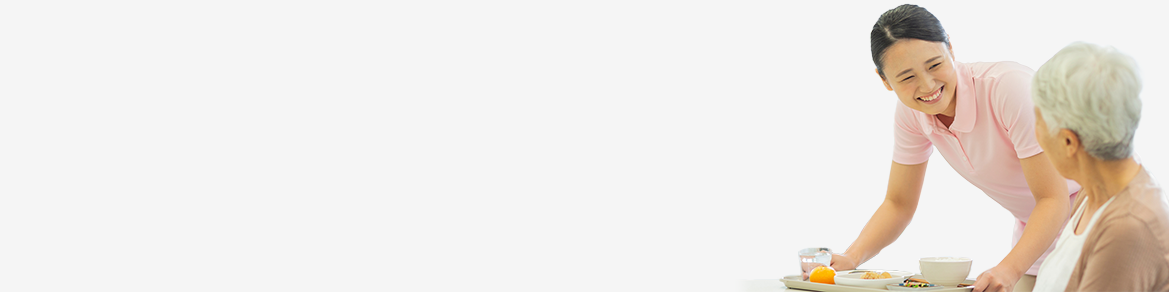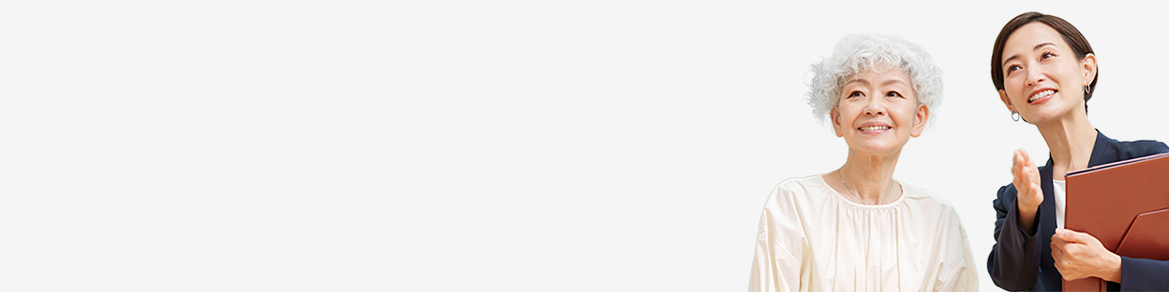機能訓練室・リハビリ室のある施設特集
機能訓練室・リハビリ室の有無は施設選びの選択基準に

高齢になると、加齢に伴った身体機能の低下や、リウマチや関節痛などの病気、はたまた病気による後遺症によって体を動かしづらくなる方も多いでしょう。そんな方にとって、機能訓練やリハビリは必須と言えます。そのための機能訓練室やリハビリ室を備えている施設も増えており、また、そこに用意されている機器も様々。昨今では理学療法士が常駐して入居者のリハビリに力を入れているような施設も多く、その整備状況は、老人ホーム・介護施設選びの選択基準のひとつと言っても過言ではありません。
適度なリハビリがQOLの向上、そして自立につながる
老人ホーム選びで「機能訓練室(リハビリ室)」の充実度を気にする方は、一体どんな点をチェックすればいいのでしょうか?
体力や筋力の低下から介護が必要になる、脳梗塞や脳出血で体の一部がマヒする、骨折で落ちた筋力を回復させるなど、リハビリが必要な高齢者は少なくありません。とくに要介護認定されている高齢者にとって、積極的に体を動かして機能を回復させることは「自立」につながり、QOL向上も期待できる重要なもの。「施設選びの選択基準」に機能訓練室(リハビリ室)の有無や、その充実度を重視する方も多いはず。では老人ホームに設置された機能訓練室とは、どのような基準を満たしているのでしょうか?
厚生労働省がさだめた「特定施設入居者生活介護の概要」によると、特定施設(有料老人ホーム・軽費老人ホーム)では食堂や機能訓練室について「機能を十分に発揮し得る十分な広さ」を設けるように決められています。特養老人ホームの場合は、食堂と機能訓練室の広さが決められており、3平方メートルに入居者定員を乗じた広さとされています。定員が50名であれば150平方メートル以上の広さが必要です。ところが広さにはある程度の決まりはあっても、機能訓練室に設置するリハビリ器具については具体的な指定がありません。各老人ホームによって差異があります。
リハビリに力を入れる老人ホームでは日常動作訓練のための階段や訓練用テーブル、歩行訓練のための平行棒、マッサージ治療やベッド上の動作訓練のためのマットプラットホーム(広めの訓練台)、患部治療のための赤外線治療器などさまざまな器具を設置しています。
機能訓練室の見学では、これらリハビリ器具が日常的に利用されているかをチェックしましょう。どれだけ立派な器具が並んでいてもホコリをかぶっていれば意味がありませんし、器具が錆びついているようならただの飾りかもしれません。入所者が実際にリハビリ器具を使って訓練していること、指導員がきちんと常駐していることを確認するのが基本。
リハビリ指導員は、理学療法士はもちろん作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の有資格者であれば誰でも従事できます。もし専門的で効果的なリハビリを望むのであれば、体の動きを主に訓練する理学療法士常駐の老人ホームを選ぶとよいでしょう。
老人ホームのなかには、食堂のすみにリハビリ用の平行棒を置いているだけ、共用施設に階段やマットを並べただけの施設もあります。このような老人ホームでは、実際にきちんとした機能訓練がおこなわれているのか疑問です。積極的に体を動かして訓練を受けたい方は、ほかの施設もあわせて見学することをおすすめします。
機能訓練室があった方が良いのはどんな人?
機能訓練室(リハビリ室)やリハビリ器具がきちんと設置され、機能訓練員による指導のもと、リハビリを受けた方が良いのはどのような方でしょうか?
厚生労働省による平成25年度・国民生活基礎調査によると、要介護度別にみた介護が必要になった主な要因(上位3位)には「脳血管疾患(脳卒中)」「関節疾患」「骨折・転倒」「認知症」「高齢による衰弱」などの理由があげられています。これらの病気やケガ、衰弱により、体が自由に動かなくなった高齢者がリハビリを受けることで「自立した生活」が実現する可能性も高くなります。またこれらの病気やケガの予防のためにも、機能訓練を受ける方が良いと言えます。
リハビリには「失った機能を回復させるための訓練」や「代替えのための機能訓練(マヒした右手のかわりに、正常に動く左手をつかって生活する訓練など)」そして「予防」の3つの柱があります。
高齢者の体の状態をみながら、一番効果的な個別リハビリメニューを理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が作成して実行、評価していきます。脳血管疾患の後遺症や関節疾患、認知症による機能低下を運動することで回復させていきますが、障害の度合いが強い場合はリハ専門病院や介護老人保健施設、デイケアでの機能訓練が適しています。老人ホームで本格的なリハビリを望んでも、設備や専門職員の配置などむずかしい面も。
老人ホームで期待できるものとしては「予防」を重視した運動でしょう。骨折や転倒、そして衰弱を起こす原因のひとつに「サルコぺニア」と呼ばれる筋肉の委縮があります。加齢や栄養不足、病気、身体の活動能力低下により体の筋肉が萎縮することで、骨折や転倒事故を起こし、要介護状態になる可能性が高まります。たとえ転倒や骨折事故を起こさないとしても、筋力や体力の低下で日常生活に支障があると要介護と判定されることも。
すでに要介護判定されている場合、これ以上介護度が進行しないようにリハビリによって筋肉量を増やし、関節の可動域をひろげる機能訓練が効果的です。
以上のことから機能訓練室があった方がよい方は「脳血管疾患や関節疾患、認知症などで体の機能になんらかの障害があり、それをリハビリによって回復させたい方」「マヒなどによって動かなくなった部位のかわりに、ほかの部位を訓練し、日常生活をスムーズにおくりたい方」「転倒による骨折や廃用症候群、要介護を防ぎたい方」となります。
高齢者にとってリハビリ・運動療法はどんな意味がある?
人が安全な日常生活をおくるためには、筋力はもちろん危険を回避する柔軟性や瞬発力も必要です。ただ闇雲に筋トレだけをおこなえば良い、というわけではありません。筋肉と感覚との一体感がなければ、危険回避のための動きはできません。筋トレだけでなく、立つ、歩く、座るなどの基本的な日常動作訓練は不可欠ですので、偏ったリハビリにならないよう注意しましょう。目や耳、皮膚などの感覚器官から入ってくる情報と、自分の体をコントロールする神経(体の動き)とが一体化することが重要です。
指導者のいない自己流の筋トレでは、無理な運動で関節や筋肉をいためてしまう可能性があります。できるだけ客観的な立場から「リハビリメニュー」を作成してくれる専門家のいる施設で、適切な機能訓練を受けるのが理想です。機能訓練の結果、どれだけの効果があがったかを評価してもらうためにも、専門スタッフが配置された老人ホームを選ぶと良いでしょう。
本格的なリハビリだけではなく、実際に外出して自分の足で街を歩き、五感で周囲の状況を把握しながら歩くこともよい機能訓練になります。施設内でトレーニングを受けるだけではなく、それを日常生活で生かし「自分らしい自立した生活をおくる」ことが最終的な目的になります。
高齢者にとってリハビリや運動療法には「筋力や体力の低下防止・維持」「ケガや病気の予防」「失われた機能を回復させる」そして「訓練によって日常生活の質を向上させること」などの意味があります。とくに最後のQOL向上は、高齢者の自立した生活のためにも重要です。リハビリは苦しいもの、つらいものという認識をもつ方もいますが、人生を豊かに生きるために積極的に受けるものという意識が芽生えれば「リハビリに対する意欲や積極性」もうまれるでしょう。
パーキンソン病でも対応が可能な施設特集
パーキンソン病では、事故が起こらない安全な環境で、できるだけ体を動かすことが大切

「手足の震え」「筋肉の硬直」「歩行困難」「嚥下機能の低下」などの症状がみられるパーキンソン症。運動症状に加え、自律神経症状や不眠、うつ症状などもみられる病気で、高齢になるほど発症率が高まっています。運動機能障害により転倒など事故の危険性が高まり、日常生活を送ることも困難になることから、介護施設選びでは安全な住環境と適度に運動に取り組めるかどうかがカギ。リハビリの充実した、施設選びをしていきましょう。
パーキンソン病患者でも安心して老人ホーム選びを
原因不明の神経変性疾患として、40代、50代から発症者数が増え始めるパーキンソン病は、日本全国で患者数10万人以上と推計されています。
患者に高齢者が多いことから、今後も高齢化に伴い患者数が増えることが予想され、老人ホームでもパーキンソン病対応をしているところが少なくありません。認知症の方が医師からパーキンソン病の疑いがあると指摘される方も少なからずあるため、介護施設や老人ホームでパーキンソン病に対応しているかどうかをチェックすることは今時点でパーキンソン病を患っていない方にとっても大切です。
老人ホーム内でパーキンソン病患者の方が安心して暮らすためには、受け入れる老人ホーム側がパーキンソン病特有の症状を理解し、ケア体制を整えていることが何よりも大切です。
主なパーキンソン病の症状としては、安静時の手足の震えや、歩行などの動きがゆっくりになる動作緩慢、姿勢保持ができなくなる姿勢反射障害、歩幅が狭くなり最初の一歩が踏み出せなくなる歩行障害、筋固縮などが挙げられます。
体力が低下したから、と思いがちな姿勢反射障害は、何もないところでもバランスを崩し、転倒にもつながってしまう可能性がありますから、ケアや生活サポートの中できちんと老人ホーム側が注意をしてくれる環境でないと、転倒時による怪我なども心配されますよね。
パーキンソン病が進行すると日常生活にも大きな支障が出てしまい、食べものを飲みこめない嚥下障害や体が動かせなくなることからくる寝たきりなどになる可能性もゼロではありません。症状が軽い場合でも、スタッフの早期かつ適切なケアは今後病気が進行していく上でも非常に大切となってきます。
また、認知症を併発したパーキンソン病の場合、問題行動が増えることが予想されますから、老人ホームによってはこうした「問題行動に対応できない」「嚥下機能低下をケアできない」などの理由で入居自体を断られることもあります。
しかしながら、近年では治療法の開発も進み、パーキンソン病を発症しても薬の服用により症状の進行を緩和し、日常生活を送れるケースは多くあります。また、歩行障害や排泄障害、摂食障害、精神障害などパーキンソン病の症状が見られたとしてもケアが可能な老人ホームはもちろんあります。大切なことは、今の症状をしっかりと入居の際に伝え、適切なケア環境にあるかどうかをじっくりと確認・相談することです。
パーキンソン病であっても老人ホームへの入居はできる、そう考えて入居先を探してみましょう。
パーキンソン病とは? その原因、症状について
日本での有病率は1,000人に1人とも言われ、決して珍しい病気ではないパーキンソン病は、50代・60代、場合によっては70代で発症するケースも少なくありません。
パーキンソン病が原因で介護が必要になる方も多く、家族にとってはきちんと症状を把握して治療や日常生活でのサポートの活かしてあげることが大切です。
パーキンソンの原因は、脳内の神経伝達物質・ドーパミンが減少することが原因と考えられていますが、なぜドーパミンが減少してしまうのかはまだ理由がはっきりとわかっていません。
ドーパミンの分泌が減少すると、体の片側から症状が始まり、全身へと進行していくのが特徴で、代表的な症状としては手足の震えやこわばり、動作が緩慢になる、姿勢反射障害により転びやすくなるなどが挙げられます。
また、便秘や立ち上がった際にくらんでしまう起立性低血圧、睡眠障害、抑うつなど、自律神経障害や精神症状が見られることもあります。
歩幅が狭くなり倒れやすいと同時に歩き始めに足がすくんでしまい、最初の1歩が出づらい一方で歩き始めると止まれない歩行障害は転倒の原因にもなりやすく、周囲のサポートや見守りが必要になります。また、字が小さくなるなども歩行障害と同様によく見られる運動障害の一つです。
ときには、気持ちや意欲が落ち込み、自発性がなくなる、認知機能が低下するなど認知症症状にも近い症状が見られると同時に、認知症と併発するケースも少なくありません。
自律神経障害、運動障害、睡眠障害、精神障害などさまざまな症状が現れるパーキンソン病は薬物治療や手術治療と合わせて運動療法(リハビリテーション)が有効な場合もあります。
パーキンソン病の方の老人ホーム入居を検討する際には、今どのような症状が見られ、どんなケアやサポートが必要なのかを医師やスタッフなどと話し合うことも大切になってきます。
| 薬の名前 | 効能 |
|---|---|
| ドパミンアゴニスト | 脳内でドーパミンを受け取る部分であるドーパミン受容体を直接刺激することで、パーキンソン病の症状を軽減する。 |
| 抗コリン薬 | アセチルコリンを抑えることで、パーキンソン病の症状を緩和させる。 |
| 塩酸アマンタジン | 脳細胞を刺激してドーパミンの分泌を活発にする。 |
| モノアミン酸化酵素 B阻害薬 |
ドーパミンの分解を阻害し、作用時間を延長する。 |
| ドロキシドパ | 脳内でノルアドレナリンという物質に変わる。 パーキンソン病の進行期にみられるすくみ足に有効な場合がある。 |
パーキンソン病患者の老人ホームでの対応は?
パーキンソン病患者の方が老人ホームに入居する際に必ず確認しておきたいのが「どのようなケアやサポートが受けられるか」という点です。
自宅で日常生活を送れなくなれば、老人ホームを頼りにすることは当然の選択肢として考えられますが、リハビリテーションの有無や早期から適切なケアが受けられるかどうかなどをチェックすることはその後の老人ホームでの生活にも大きく関わってきます。
将来、症状が進行した場合には、認知症との併発や嚥下機能の低下なども考えられること。認知症との併発による問題行動が原因で入居を断る施設もありますから、入居先を選ぶ際には今の状況で対応がしてもらえるのか、将来症状が進行した場合にはどうなるのかをしっかりと確認しておくことが大切です。
パーキンソン病の方の介護にあたっては、進行性の病気のために徐々に自分で色々な日常動作を行うことが難しくなる点が忘れてはならないポイントです。介護においては、日常生活を安心して送るためのサポートと同時に、できる限り自分で動ける・行動できる期間を伸ばすためのリハビリを積極的に行えるかどうかもチェックしたいところ。
また、日常生活を送るなかで本人が焦らないように、温かく見守ってくれる雰囲気のもと、本人ができることは自分でやれるようなサポートがあるかも大切。
運動療法によりできることを増やしていくリハビリテーションの充実は、パーキンソン病の進行を緩和したい方にはやはりとても大切なチェックポイントです。
また、食事においては料理を口に運ぶ動作がよりスムーズにできるようにするための食器や食べる環境への配慮があるかどうかは見ておきたいポイントです。また、パーキンソン病においては歩行障害が多くみられ、すり足歩行や小刻み歩行、すくみ足、前方突進減少、姿勢保持反射障害など住環境への配慮が必要な場合が多くあります。
老人ホームであればその点は安心ですが、念のためきちんと安全が確保されているのかどうかを見学時などに見ておきまそう。
「パーキンソン病患者の受け入れ可」という老人ホームも増加中!
ご自身もしくはご家族が、パーキンソン病を発症したとき、不安に感じるのがパーキンソン病でも老人ホームに入居できるか、という点です。
高齢になるにつれて発症者も増加していくパーキンソン病は、介護が必要になる原因としてそれほど珍しいことではありませんから、パーキンソン病の方が入居できる老人ホームはたくさんあります。
ただ、注意したいのが症状の進行具合によって嚥下障害や認知症の併発などが見られる場合です。飲み込む力が低下する嚥下障害になると、食事内容への配慮や食事介助の必要が生じるため、こうしたケア体制がない施設の場合は、嚥下障害のある方は入居を断るというケースもあります。また、認知症を併発し、問題行動が見られる場合も同様です。
パーキンソン病患者は、認知症発症リスクも4から6倍ほど高まるという研究もあり、認知症との併発は心配ですが、グループホームは自立ある暮らしを支援するための施設のため、パーキンソン病では入居ができないケースが多いとも言われていますので、各施設に確認してみることが大切です。
高齢者に多いパーキンソン病は60歳以上の場合100人に1人が発症するという推計もあるため、それほど珍しい病気ではありません。パーキンソン病患者の受け入れについて、「受け入れ可」と謳う老人ホームは珍しくありませんから、諦めずに、ご希望の地域や価格帯で対応してくれる老人ホームがあるか探してみましょう。
パーキンソン病が軽度の場合には、今後の症状進行に伴う運動機能の低下を緩和するためのリハビリテーションや運動療法ができるかどうかを確認することも大切です。