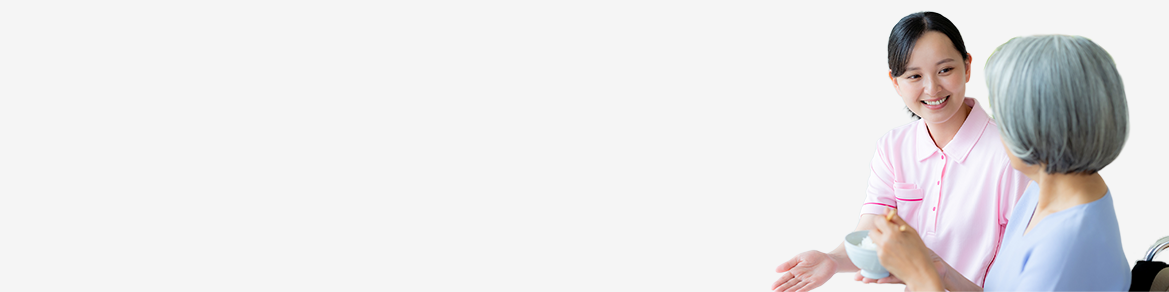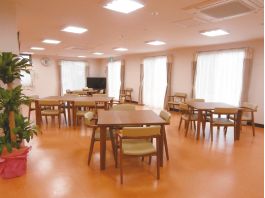都市開発が目覚しい、「小山市都市圏」のお膝元
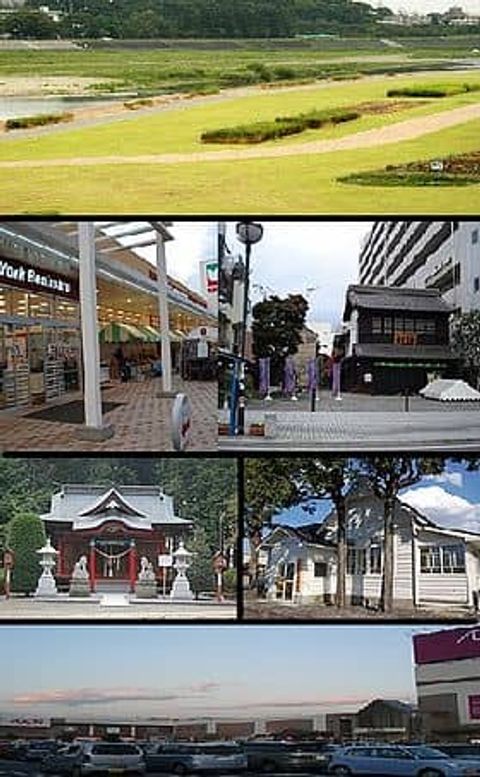
栃木県の南端に位置する小山市。
農業・工業をはじめ各産業が独特の形式にて発展している点に加え昨今は開発が進んでおり、近接する都市とあわせて「小山都市圏」と称されることもしばしばです。
北関東と首都圏に挟まれる形となっているため、両地域をつなぐという意味でも重視されてきました。
大規模な住宅地の新規開発および再開発・拡大化などの計画が現在、市内の数ヶ所で進んでおり、これからますます成長していくことは間違いありません。
産業面や都市の機能面ではもとより、文化面や福祉サービスの面でも飛躍的な進歩が見込めそうです。
それらの発展の原動力のひとつが、完備された交通インフラでしょう。
鉄道についていちばん人目をひきつけるのは、おそらく東北新幹線が停車する点でしょう。
JRの在来線に関しては宇都宮線や両毛線、水戸線が走っている点も忘れてはなりませんが。
JR線が派手に活躍している点とは対照的に、市内には高速道路が走っていません。
しかし国道4号線・50号線、さらに新4号国道を中心に地方道や県道が複雑に伸びており、住民の移動や流通を促進しています。
市内のバスについては、関東自動車の営業エリアですが、コミュニティバスの成長ぶりにも目を見張るものがあります。
小山市は、北関東地域では有数の人口伸張地域です。
高度経済成長の時代を過ぎてもあまり増加の勢いにかげりが見えることはありませんでした。
2000年代半ばに16万人を突破して以後も伸びており、当分の間減少に転じる日は来そうにありません。
外国籍の住民が増えている点も特徴的です。
これらの人口増は、決して長所ばかりではありませんが、福祉問題を考えるにあたっては歓迎すべき点が多々あります。
実際に少子高齢化の調査を確認すると、小山市は優等生と呼ぶことが可能です。
2023年の段階ではまだ高齢化率は25.8%であり、県全体の高齢化率をやや下回る数値です。
要介護高齢者のような、ただちに助けが必要な弱者に対する政策も抜かりなく行われており、今後長期にわたって住みやすい都市となっていくだろうという期待をもてます。
現在の介護施設の様子を見ていくと、公営か民営かに関係なく、ありとあらゆるタイプで施設の増加が少しずつ進んでいることが一目でわかります。
また、どの施設についても、入居費用が少なくてよい施設が混ざっています。
入居一時金などを徴収されない施設の増加も目立ちますから、まとまった元手がない世帯にとっては好都合でしょう。