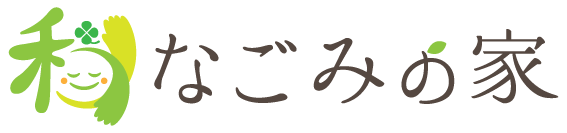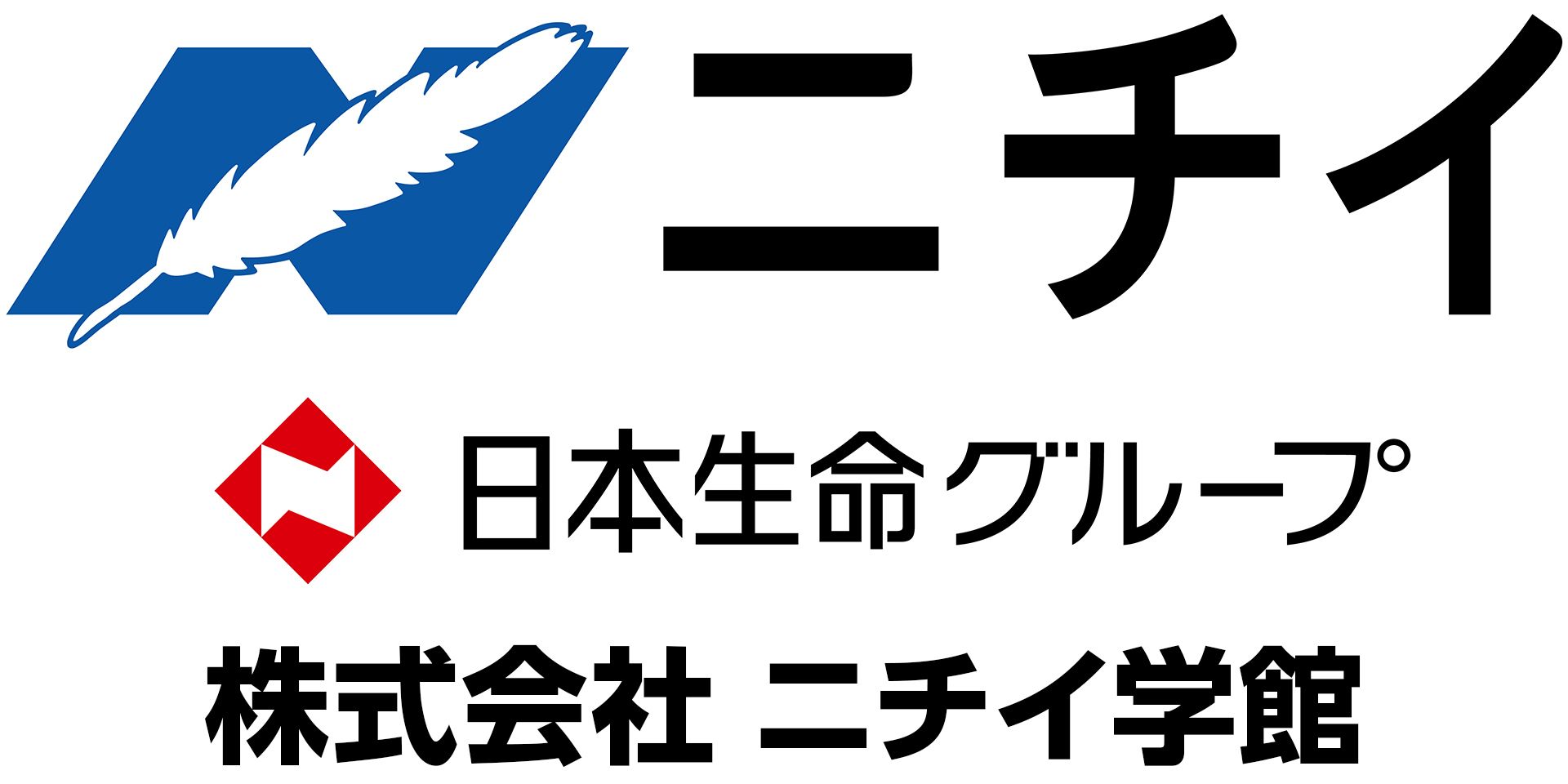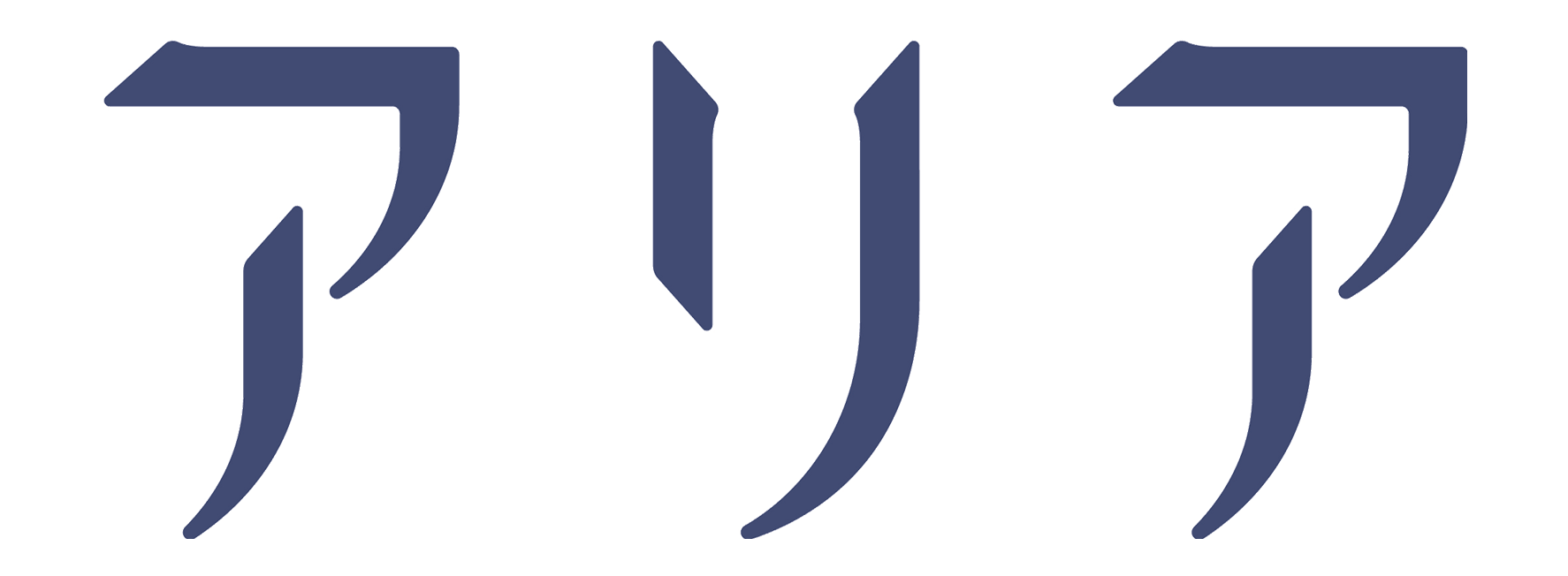アルツハイマー型認知症でも対応が可能な施設特集
アルツハイマー型認知症患者の方は認知症ケアが充実した施設選びを

認知症が進行し、日常生活での見守りや徘徊、夜間眠れないなどの症状が出てくると、ご家族が在宅で介護を続けるのにも大きな負担が出てきます。介護施設の中には、認知症ケアのノウハウが充実した専門的ケアを提供する施設も多くあり、こうした施設で適切なケアのもと生活することは症状の緩和につながるケースも。ご本人が老人ホームへの入所を嫌がる場合もありますので、じっくりと本人が安心できる環境を整えた施設探しをしていきましょう。
アルツハイマー型認知症患者が老人ホームで介護を受けたほうが良い3つの理由
アルツハイマー型認知症は、脳神経細胞が減少し脳が委縮する病気です。脳が縮んで小さくなることにより、さまざまな症状があらわれます。
記憶障害(即時・短期・長期)・判断力低下・見当識障害・実行機能の低下・失語・失行・失認などの症状は、認知症患者全般にみられることから「中核症状」とよばれています。これに対して徘徊や暴言、異食、過食、暴力、介護抵抗は周辺症状のなかでも行動障害とよばれ、さらに妄想や幻覚、憔悴、不安、抗うつ、睡眠障害は周辺症状でも精神症状と、2種類に分類されています。これら周辺症状は、必ず表面化する症状ではありません。どのような周辺症状が出てくるかは、患者本人がもつ気質、歩んできた人生などによってひとりひとり変わってきます。
在宅で認知症高齢者を介護する場合、もの忘れや判断力低下などの中核症状よりも、妄想や徘徊、暴言、暴力、異食といった周辺症状に悩まれる方ケースが非常に多いようです。自宅で介護を続けていても暴力や徘徊、妄想などの症状がひどくなり、老人ホームへの入所を決断される方も少なくありません。尿失禁や便失禁などの症状がでることで、在宅介護を断念するケースもみられます。
アルツハイマー型認知症は脳が委縮する病気で、今の医療レベルでは完治できない病気です。病気の根本治療がないため、現状、認知症の進行を遅らせる、ゆるやかにさせることしかできません。認知症の進行を遅らせるためには「脳に刺激を与えること」が有効であると言われています。つまり認知症患者は家のなかに閉じこもるのではなく、できるだけ外に出て外部からの刺激を受ける方が良いのです。
老人ホームは集団生活であるため、周囲にいる入所者と協調していく必要があります。掃除や洗濯、料理などの家事を分担しておこなうことが生活リハビリになりますし、体を適度に動かすことが脳への良い刺激になります。外出もひとりではなく、介護スタッフや他の入所者とある程度の集団でおこなうことで交通事故などのリスクがさがります。
老人ホーム内は集団生活なので、本人の体調や様子を必ず誰かが観察することになります。異常があればすぐに介護スタッフが対応できますし、認知症の症状変化や薬の効き方なども観察できます。認知症高齢者を自宅でひとり生活させるより、安全であることは間違いありません。
認知症高齢者が老人ホームで介護を受けた方がよい理由は3つ。
- レクリエーション等で脳への適度な刺激が期待できる
- 老人ホームで集団生活をすることで、生活リハビリができる
- 介護士がつねに本人の体調を把握できる
認知症高齢者が入所できる老人ホームには、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)などがあります。とくにグループホームは認知症高齢者のための共同生活施設という位置づけになっており、勤務する介護・医療スタッフは認知症患者の症状や対処法について勉強されています。老人ホームへの入所を考えるなら、施設が「認知症高齢者受け入れ可能」であるかどうか、そして受け入れ実績の有無、介護スタッフに認知症の知識があるかどうかを確認するとよいでしょう。
アルツハイマー型認知症とは?その原因、症状について
「認知症」とは、ある特定の病名をさす言葉ではなく、脳神経細胞がなんらかの原因によって破壊され、その機能がうしなわれ、もの忘れや生活動作困難、判断力の低下などの症状がでる病気をいいます。認知症のなかでももっとも患者数が多いのがアルツハイマー型認知症で全体の約55%、つぎが脳血管性認知症の19%、そしてレビー小体型認知症の18%、その他の原因で発症するタイプが8%となっています。
| アルツハイマー認知症(55%) | |
| レビー小体型認知症(18%) | |
| 脳血管性認知症(19%) | |
| その他の認知症(8%) |
アルツハイマー型認知症の発症原因はいまだによくわかっていませんが、高齢になるほど発症しやすいことから、「加齢」がリスクファクターのひとつであると言われています。遺伝や特定の病気が原因であると指摘されていますが、詳しいことはまだよくわかっていません。
アルツハイマー型認知症は脳にβアミロイドとよばれる特殊なたんぱく質が蓄積することがわかっています。βアミロイドが集まったものはβアミロイドプラーク(老人斑)とよばれ、アルツハイマー型認知症患者の脳内に大量に出現。脳神経細胞をつなぐシナプスネットワークを切断し、脳に大きなダメージを与えます。
さらにタウと呼ばれるたんぱく質が過剰にリン酸化され、からみあう「神経原線維変化(もつれ)」もアルツハイマー型認知症を悪化させます。これらの異変を察知した脳内にある掃除役・ミクログリア細胞が掃除体勢から攻撃モードへと変化し炎症を起こすことで、正常な脳神経細胞まで破壊されていきます。認知症は急性の病気ではなく、20年ほどかけてゆっくり進行しています。病気を自覚するかなり前から、脳内にはβアミロイドの沈着や神経原線維変化がはじまっているのです。40代・50代からの認知症予防が重要ですね。
アルツハイマー型認知症を発症すると、どのような症状があらわれるのでしょうか。前項でも少しご説明しましたが、中核症状と周辺症状とよばれる2種類の症状が出現します。中核症状は認知症患者全般にみられるものですが、周辺症状は患者の性格や気質、それまで歩いてきた人生経験などによって変化します。
おもな中核症状はもの忘れです。高齢になると記憶力の衰えがみられますが、それでも家族の存在を忘れるようなことはありません。ところが認知症患者の場合、脳の記憶にかかわる脳神経細胞が侵されることにより、家族のことはもちろん自分自身のことまで忘れてしまう場合があります。もの忘れと言っても通常のものと認知症によるものとでは、その深刻さが違うのです。
ほかにも「自分が今、どこにいるのかわからない」「今の季節がわからない」「仕事(家事)の手順がわからない」「注意力が低下し、鍋をこがす」「洗濯したことを忘れて、なんども洗濯機をまわす」などの症状が出てきます。これらの症状はアルツハイマー型認知症患者全般的にみられるものです。
さらに徘徊や、異食(洗剤などを食べる)、暴力、暴言、妄想、不安、抗うつなどの周辺症状がみられることも。これらの症状が介護する側に大きな負担となり、要介護者の老人ホーム入所を決断させる要因となっています。
認知症の種類は主に3つ
認知症の種類は主に3つあげられます。
まずはもっとも患者数が多い「アルツハイマー型認知症」そして脳卒中を発症することで、脳神経細胞に酸素や栄養が送られずに認知症を発症する「脳血管性認知症」、脳全体にレビー小体という特殊なたんぱく質が蓄積して起きる「レビー小体型認知症」です。これ以外にも前頭側頭型認知症・ピック病もあります。主な認知症の種類は、先ほどあげた3種類になります。
| 認知症の種類 | 症状の特徴 |
|---|---|
| アルツハイマー型認知症 | 脳の神経細胞が死滅することによって脳の機能障害をきたし、認知症状を起こす。高齢者の認知症では最も頻度が高い疾患で、全体の50~60%を占める |
| 血管性認知症 | 高血圧、脂質異常症、糖尿病などによって血管障害をきたして脳卒中を起こした結果発症する。通称「まだら認知症」とも呼ばれる |
| レビー小体型認知症 | 脳全体に「レビー小体」という物質がこびりつく事で、脳の機能障害をきたし認知症状を起こす。アルツハイマー型の次に頻度が高い |
| ピック病 | 脳の前頭葉と側頭葉の萎縮によって起こる |
アルツハイマー型認知症は長い年月をかけてβアミロイドが蓄積、タウタンパクの神経原線維変化、炎症などで認知症を発症し、進行していきます。その進行はなだらかです。
ところが脳血管性認知症の場合は、脳梗塞や脳出血が起きると急に症状がすすむという特徴があります。逆に病気の進行が止まっているようにみえることも。アルツハイマー型認知症とは違い病識があり、最後まで人格が保たれていることが多い傾向です。
レビー小体型認知症は脳内にレビー小体とよばれるたんぱく質の小さな丸い塊が蓄積し、発症する病気です。日本人医師・小坂憲司氏が世界に発表し明らかになった病気です。この病気の特徴は枕元に亡くなったはずの両親が立っているといった幻視、壁に人の顔が見えるといった錯視などの症状、また筋肉のこわばりにより体がうまく動かせないパーキンソン症状などがみられるのが特徴です。うつ症状や被害妄想の症状がでるケースも。症状がすすむと自律神経の障害により尿失禁や便失禁、便秘、そしてもの忘れや理解力、認識力の低下など認知機能低下の症状もみられます。
それぞれの病気の種類により、病気の進行状況や多くみられる症状、注意点等がやや違ってきます。病気の特徴をある程度つかみ、介護ケアに活かしましょう。
アルツハイマー型認知症患者向けの施設選びのポイント
アルツハイマー型認知症は進行していく病気です。今、とくに大きな問題はなくても、時間の経過とともに症状がすすみ、徘徊や妄想、暴力、暴言などの症状が出現するかもしれません。認知症の周辺症状により、介護者が夜眠れなくなる、心身共に疲労する、介護によって仕事や日常生活に大きな支障がでるようなら、老人ホームへの入所を検討するべきでしょう。このとき、認知症高齢者の受け入れが可能な施設を選ぶことが重要です。
認知症患者の受け入れ可能な施設は介護スタッフに認知症の知識があり、施設自体も介護実績がありますので安心です。ただすべての認知症高齢者を受け入れできるわけではなく、以下のような症状が出ている方は入所が断わられる可能性があります。
- 他人に危害を加える
- 徘徊癖があり、勝手に施設を出ていく
とくに問題となるのは1です。他の入所者を殴る、蹴るなどの暴力を加えるような方を施設に入れると、老人ホーム自体の信頼にかかわるため入所を断られるケースも。とくに体の大きな男性が暴れると、女性職員だけでは抑えることができないため危険です。徘徊癖は見守り、確認の間隔を短くすることである程度はカバーできますが、あまりにも頻繁に外にでてしまう方は入所を断れるケースも。とくにグループホームは昼間、玄関に施錠をしない施設も多いため、本人の安全を考えて入所を断わられることもあります。
問題行動が多い場合はできるだけ服薬治療をおこない、症状を緩和したうえで(トラブルが解消したうえで)の入所となります。
脳血管性認知症でも対応が可能な施設特集
脳血管性認知症の介護は再発予防と対症療法がカギ

脳の血管障害や、脳梗塞、脳出血が原因で脳の一部の部分に限定して障害が起こる脳血管性認知症は、障害が起こった場所によって症状が異なります。再発予防のためにも高血圧や糖尿病、心疾患などに充分注意した生活が必要であるとともに、病変部の治療やリハビリ指導によって症状の改善につながることも少なくありません。その点でも、介護施設での適切なケアや体調管理のもと生活することは、脳血管性認知症患者にとっておすすめと言えます。
脳血管性認知症の方の老人ホーム選びについて
脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血が原因で発症する認知症です。アルツハイマー型認知症のつぎに患者数が多いとされています。
脳梗塞や脳出血が起きると必ず脳血管性認知症になるわけではなく、障害をうけたエリアが小さいと、認知症を発症しないこともあります。脳卒中の後遺症として100%、認知症になるわけではありません。ただ大きな障害を受けると、後遺症が残る可能性が高くなります。そのため意識不明になるほど大きな脳卒中が起きたあとに、脳血管性認知症になる可能性はかなり高いと言えるのです。この病気は女性よりも男性の方が発症しやすいと言われており60歳をすぎたあたりから患者数が増えることから、60歳以上の男性はとくに注意すべきです。
脳血管性認知症を発症すると、障害が起きた部位によってさまざまな症状ができます。ただアルツハイマー型認知症とは違い、認知機能全般が低下するよりも「計算能力や理解力はあるが、急に泣きはじめたり喜んだりと、感情の起伏が激しい」「感情は安定しているが実行力が低下している」というように、特定の症状だけがあらわれる「まだら認知症」になりやすい傾向です。脳血管性認知症の患者が老人ホームに入所する際は、施設が「脳血管性認知症患者の受け入れ可能」であるかどうか、そしてすでに患者の受け入れ実績があり、介護・看護スタッフに認知症の知識が十分あるかどうか、トラブルが起きたときにすぐに対応できるかどうかを入所前にしっかり確認しましょう。
ただ、患者本人の症状によっては(暴力や暴言、徘徊)入居を断られる可能性もあります。
脳血管性認知症とは?その原因、症状について
人間の脳内には脳神経細胞が1,000億個以上あると言われています。脳神経細胞は軸索とよばれる電線のようなものを伸ばし、巨大な脳神経細胞のネットワークを形成しています。脳神経細胞に電気信号や化学信号が加わることで、言葉や物事を理解し、思考を言葉や文章で表現し、体を動かして日常生活をおくることができるのです。
ところが脳梗塞や脳出血が起きると、大事な脳神経細胞に酸素や栄養を送ることができなくなります。脳梗塞は脳の動脈がつまる病気です。血管のつまり方によって「脳血栓」「脳塞栓」の2種類にわけられます。動脈硬化などで血管自体が細くなっている部分に、少しずつ血の塊がたまっていくことで血流が完全にふさがれる状態を「脳血栓」とよびます。「脳塞栓」は主に心臓などでうまれた血栓が血流にのり脳へと流れ、脳の動脈をつまらせる状態をいいます。
脳出血は出血がおきる場所により「脳内出血」や「くも膜下出血」などに大別されています。この脳出血は60歳以上の高齢者に多くみられます。脳内の血管が破れて出血する病気で、原因は加齢、高血圧、動脈硬化、脂質異常症と言われています。生活習慣病が脳出血や脳梗塞と関連しているのです。
このような脳血管の病気になると、血管が損傷することで大事な脳神経細胞に酸素や栄養分を供給することができなくなり、脳神経細胞は死滅していきます。脳神経細胞がダメージを受けた部分により、さまざまな認知症の症状があらわれます。「記憶力にはあまり問題がないが、判断力に異常がみられる」「抑うつ症状やせん妄がみられるが、記憶力には問題がない」など、ある特定の症状だけがあらわれ、それ以外の面には大きな問題がない、というケース(まだら認知症)も見られます。
この脳血管性認知症の割合を見てみると、アルツハイマー型認知症の55%についで脳血管性認知症が19%と、脳血管性認知症はアルツハイマー型認知症のつぎに多いタイプとなっています。ただし、なかにはアルツハイマー型認知症と脳血管性認知症の混合型の患者もいるため、2つの病気の症状が同時にでる場合も。医師の診察を受け、医師の指示のもとで治療をおこないましょう。患者本人や家族が勝手に病気を判断しないことです。
| アルツハイマー認知症(55%) | |
| レビー小体型認知症(18%) | |
| 脳血管性認知症(19%) | |
| その他の認知症(8%) |
脳血管性認知症の場合、比較的多くみられる症状としては、感情失禁やせん妄、抑うつ症状や、神経障害(嚥下障害、運動障害、尿失禁、便失禁)などがあげられます。先ほどもご説明しましたように、特定の症状が出るのも血管性認知症の特徴です。脳梗塞や脳出血をおこすとさらに症状が悪化するため、できるだけ脳血管の病気を再発させないために食事の内容を見直し、喫煙や過度の飲酒を避けるようにしましょう。ストレスや運動不足もリスクファクターとなるため、適度な運動やストレスの少ない暮らしを心がけましょう。
脳血管性認知症の方の老人ホームの受入れについて
脳血管性認知症の患者の受け入れが可能な老人ホームでは、認知症に関する知識をもった介護・看護スタッフがきちんと対応するため安心できますが、認知症患者の介護経験のない施設では、介護や看護のノウハウがないため断られるケースも。できるだけ脳血管性認知症患者の受け入れが可能な施設を選んで、入所できるかどうかの問いあわせをおこないましょう。施設を探す方法としては担当のケアマネージャーに探してもらう、ネットの老人ホーム情報を探して直接問い合わせる、などの方法があります。
脳血管型認知症の初期には、患者本人に病識があることが多く「これはおかしい」「なぜ以前できたことができないのだろう」と気持ちが落ちこむことも。「なぜできないのですか?」「もっとしっかりしてください」と叱ることで本人のプライドを傷つけ、さらに落ち込ませることになります。このような言動をする介護施設ではいけません。入所後の対応なども考え、介護・看護スタッフが認知症患者の気持ちやプライドを尊重してくれる老人ホームを選びましょう。脳血管性認知症の場合、病気の原因が脳卒中(脳梗塞や脳出血、くも膜下終結の総称)であることがほとんどです。そのため認知症の症状以外にも、嚥下障害や歩行障害、尿失禁などの神経障害があらわれていることも。これら神経障害にも適切に対応できる老人ホームでなければ、入所できません。
重介護者を介護するケースもあるため、入浴施設など老人ホームの設備がしっかりしていなければ入所できないことも。グループホームでは比較的症状の軽い認知症患者の受け入れは可能ですが、重介護者になると入所ができないことも。事前の話し合いが重要です。
脳血管性認知症の方の対応方法
脳血管性認知症患者は、まだら認知症を発症しやすく、感情の起伏が激しく患者によってはうつ症状がでる場合もあります。老人ホームではこれらの特徴を把握したうえで適切に対処します。
感情失禁はさっきまでニコニコ笑って機嫌がよくても、急に怒りをあわらにするなど感情変化が激しいことを言います。このような感情失禁が起きたときは冷静に対処する、怒りや喜びに共感して話しを聞く、またある程度距離をとるなどいくつかの対処法があります。患者が感情的になっているからといって、介護者も感情的に対応するとトラブルがさらに大きくなり、お互いに嫌な思いをしてしまいます。老人ホームの介護・看護スタッフは認知症患者の対応について教育を受けているため、患者の感情やプライドを傷つけるような言動は決してとりません。
うつ症状は自発性がなくなる状態です。物事に対して「頑張って取りくもう」という意欲が低下してしまうため、一日中ぼんやりと過ごす、寝たままの状態になることも。このうつ症状は認知症によるものなのか、それともうつ病や躁うつ病によるものなのか判断つかないこともあるため、医療機関で診断をくだしてもらわなければなりません。もし、うつ病や躁うつ病を発症している場合、薬によって治療が可能です。
脳血管性認知症の場合、これらの症状以外にも失語(言葉がでてこない)や神経障害(尿失禁や嚥下障害、運動障害)、着衣失行(季節に合わない洋服を着る、上下逆さまに服を着るなど)、箸の使い方がわからなくなるなどさまざまな症状がでるケースも。朝はしっかり自分で洋服を着用できても、午後になるとそれができなくなるなど症状が出たり消えたりするのも特徴です。患者の症状にあわせて柔軟に対応、介護をすることが基本となります。
レビー小体型認知症でも対応が可能な施設特集
パーキンソン症状も見られるレビー小体型認知症は安全な環境での生活が大切

認知症の中でもアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症と並んで多いのがレビー小体型認知症とよばれる病気です。脳の神経細胞内に異常なタンパク質が溜まることで引き起こされるこの病気は、手足が震え転びやすくなるなどのパーキンソン症状に加え、物忘れ、幻覚による異常行動、人格の変化などの症状が見られます。日常生活における転倒の危険性などが高まることから、安全な環境と適切な認知症ケアが受けられる施設を探すと良いでしょう。
レビー小体型認知症の方の老人ホーム選びは?
レビー小体型認知症は1976年に、日本人医師・小阪憲司氏がレビー小体(たんぱく質がかたまってできた小さな丸い集合体)が大脳皮質にも多数見つかったことを、世界で初めて報告しました。レビー小体自体は、1919年にフランスのトレティアコフにより発見されていましたが、発見されたのは脳幹とよばれる脳の奥深く。それ以後は「レビー小体が蓄積するのは脳幹の部分だけ」という意見が支配的でした。ところがレビー小体が大脳皮質で多数見つかったことにより1996年に「レビー小体型認知症」という病名が決定され、診断基準も発表されました。つまりこの病気は、日本人医師によって最近発見された病気なのです。
この病気を発症すると、初期のうちは就寝中に叫んだり暴れるなどの症状があらわれる「レム睡眠行動障害」や気分の落ちこみや意欲低下、元気がない状態がつづく「うつ状態」、ふらつきやめまい、便秘など体の不調があらわれる「自律神経症状」、筋肉がこわばり、体がうまく動かせなくなる「パーキンソン症状」、そして目の前にないにもかかわらず「子供が部屋に2人いる」や「壁に人の顔が見える」などの幻視や誤認などの症状などがあらわれます。アルツハイマー型認知症の場合は「もの忘れ」が顕著ですが、レビー小体型認知症患者の場合、初期のうちは認知機能の低下が目立ちません。そのため「認知症ではない」と勝手に認識しがちです。レビー小体型認知症の特徴を把握し、異常な行動が目立つようになったら早めに医療機関を受診しましょう。
レビー小体型認知症患者の場合さまざまな症状があらわれるため、それぞれの症状に合わせて適切な対応が必要となります。幻視や誤認の症状がでている場合は、照明を明るくする、カーテンを開けるなどして部屋を明るくするだけでも幻視や誤認が大きく減少します。壁にかかった洋服などを人間だと見間違えることもあるため、できるだけ洋服はたたんでクローゼットやタンスのなかに収納します。
さらに注意したいことは「転倒」です。この病気の患者は視覚障害や認知機能低下、パーキンソン症状などにより、アルツハイマー型認知症の患者よりも転倒しやすいと言われています。段差の解消や手すりの設置、明るい照明、声掛け、部屋のなかの整理整頓、滑り止めマット活用、家電コードの設置場所見直しなどで転倒を防ぐことが重要です。
レビー小体型認知症患者の受け入れが可能な老人ホームの場合、患者の幻視・誤認が起こりにくいような部屋の整理整頓やバリアフリー、手すり設置、照明の強さなどの工夫、パーキンソン症状が出ている患者に対するリハビリや嚥下体操、幻視や誤認に対する的確な対応(頭から否定しないなど)、食事やトイレ、入浴介助等の支援が可能です。
とくにレビー小体型認知症認知症患者は、背後から声をかけられる、服のそでを引っ張るなどの行為でも転倒するケースが。老人ホームの介護・看護スタッフは、レビー小体型認知症に関する知識や患者に適切に対応するための教育を受けています。患者を危険にさらず、また心を傷つけるような言動はとりません。
レビー小体型認知症とは?その原因、症状について
「認知症の種類の割合について」の表をご覧ください。認知症のタイプで一番多いのはアルツハイマー型認知症で、全体の55%となっています。つぎに多いのは脳血管性認知症の19%、そしてレビー小体型認知症の18%と続きます。決して稀有な病気ではありません。ではつぎにレビー小体型認知症について、くわしくみていきましょう。
| アルツハイマー認知症(55%) | |
| レビー小体型認知症(18%) | |
| 脳血管性認知症(19%) | |
| その他の認知症(8%) |
レビー小体型認知症の患者の脳内には「レビー小体」とよばれる小さなかたまりが多数存在します。このレビー小体はたんぱく質がかたまってできた小さな円形の物質。大きさは30~50ミクロンと小さいためMRIやCTでもその映像を直接確認することはできません。もちろん人間の目にも見えません。このレビー小体が脳幹や大脳皮質に大量に発生することで脳神経細胞が変性して脱落、やがて死滅。認知機能や神経系の働きが低下していきます。
レビー小体の元をたどると「α―シヌクレイン」とよばれるたんぱく質が中心になっていることが判明していますが、これらのたんぱく質は特殊なものではなく、脳内にもともとある物質です。なぜ特定のたんぱく質が集合し、レビー小体ができるのか? この根本的な疑問、原因はいまだにわかっていません。
このレビー小体が大脳皮質で多く発生すると「レビー小体型認知症」と診断され、脳幹に多くできると「パーキンソン病」に、そして自律神経に多く発生すると「シャイ・ドレーガー症候群(突発性自律神経不全症)」と診断されます。おなじレビー小体が蓄積されて発症する病気であるにもかかわらず、体のどの部位におもにレビー小体が蓄積され、どのような症状がでているかでさまざまな病名がつけられており複雑になっています。一部の専門家では、これらの病気を「レビー小体病」と総称し、全身の病気として考えた方がよいのではないか、と考える方もいます。
レビー小体型認知症は発症する年齢や発症しやすい症状などのより「純粋型」と「通常型」という2つの種類に分類されています。純粋型はパーキンソン症状からはじまり、次第に幻視や妄想、認知機能低下などへ症状が進行する場合はレビー小体型認知症であると診断されます。30~40代の若い世代でも発症する可能性も。「通常型」は高齢者に多く、レビー小体型認知症の典型的な症例がみられます。パーキンソン症状があらわれない方が、全体の約3割います。パーキンソン病患者のなかには、レビー小体型認知症を発症する患者も。それぞれの病気が関連しあっているのです。
それではレビー小体型認知症の症状についてご説明しましょう。前項でも紹介しましたが、この病気を発症すると初期のうちは「幻視・錯視」「妄想」「うつ状態」「自律神経症状」「パーキンソン症状」「レム睡眠行動障害」などの症状が出始めます。病気が進行することにより「認知の変動」や「認知機能の低下」もみられます。認知の変動は、しっかり行動できるときとボンヤリしているときの差が激しくなることを言います。認知機能の低下はアルツハイマー型認知症と同じように、記憶障害や判断力、理解力の低下、見当識障害(今がいつなのかわからない、ここがどこなのかわからない)などの症状を引き起こします。
高齢になるとアルツハイマー型認知症を発症するリスクもアップするため、レビー小体型認知症とアルツハイマー型認知症を同時に発症することも。「母はレビー小体型認知症の患者なのだから、ほかの認知症にはならないだろう」と勝手に決めつけないことです。
レビー小体型認知症患者への適切な対応・介護はどんな方法?
レビー小体型認知症患者にはさまざまな症状がでます。とくに幻覚や幻視、妄想の症状に対しては、介護者も戸惑うことが多いでしょう。「部屋のなかに猫がいる」といるはずのない猫を追い払おうとします。介護者にしてみれば「猫なんかいませんよ」「ちゃんとしてください」と言いたくなりますが、本人にはしっかりと見えています。頭ごなしに説得しようとすると本人にとっては「家族からバカにされている」「信じてもらえない」という気持ちになり、ますます幻視や妄想がひどくなることも。幻覚や誤認に関しては頭から否定せず、本人からよく話しを聞き「それは困ったね」「もしかしたら勘違いってことはない?」と本人の気持ちに寄り添った対応をしましょう。
「レム睡眠行動障害」は睡眠中に大声をだしたり暴れるような症状がみられても、本人は夢のなかのことだと認識しています。無理に起こすと現実と夢とがごちゃまぜになり、さらに混乱、興奮します。この場合は無理に起こさない方が無難。
レビー小体型認知症の患者は「起立性低血圧」を起こしやすくなっています。急に立ち上がるとめまいやふらつきを感じ、場合によっては転倒することも。急に立ち上がらず、できるだけ頭を下げた状態でゆっくりと姿勢を変える配慮が必要です。ほかにも自律神経の障害により、嚥下障害が起きやすくなっています。水分にとろみをつけて飲み込みやすく工夫する、少しづつゆっくり食事を口に運ぶなどの配慮により、むせ込みや窒息、誤嚥性肺炎を防ぎましょう。食後は歯磨きをして、口のなかを清潔にたもつことが誤嚥性肺炎防止に役立ちます。
前頭側頭型認知症・ピック病でも入居可能な施設特集
前頭側頭型認知症・ピック症患者が入所できる介護施設は貴重な存在

ピック症(前頭側頭型認知症)は、大脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することで引き起こされる病気です。性格が変化し、同じことを繰り返すなどの行動障害や反社会的な行動をとるが症状としての特徴で、病気をなかなか周囲に理解してもらえないという悩みを持つ患者も少なくありません。介護保険対象での施設入所も可能ですが、徘徊や年齢の若さからくる介護の難しさなどから受入れ拒否をする施設も多く、入所できる介護施設は貴重な存在と言えます。
前頭側頭型認知症の方の老人ホーム選びは?
前頭側頭型認知症(ピック病)は、脳に特殊なたんぱく質が蓄積することにより脳の前頭部と側頭部が委縮し(縮んで小さくなり)発症する病気です。前頭側頭型認知症は50~60代と比較的若い方に多くみられる傾向があります。65歳未満で発症する若年性認知症のなかでも、アルツハイマー型認知症のつぎに多いと言われています。2015年に厚生労働省により指定難病となっています。
前頭側頭型認知症では、前頭葉と側頭葉が委縮していきますが、両方とも同時に発症するのではなく「前頭葉が先に委縮し、つぎに側頭葉が縮んでいく」または逆のケースも。ただし病気の症状がすすむと、結果的に両方とも委縮してしまいます。
前頭葉は人の感情や創造性、意欲、自発性をコントロールし、側頭葉は言語の理解や形態の認知などの役割があります。もしも前頭葉にダメージがおよぶと「一旦停止や赤信号を無視する」「スーパーやコンビニにある商品を万引きする」「毎日外にでて決まったコースを歩き回る」「急に人格が変わったように見える」などの症状があらわれます。側頭部がダメージを受けると「言葉を聞いても意味がわからない」「自分の話しはできるが、相手の話しが理解できない」「友人や知人の顔をみても誰なのかわからない」といった症状がみられます。
ここで紹介したような症状だけではなく、同じような行動を延々と繰りかえす、顔から感情が消えて気難しい表情になる、急に暴力や暴言に走る、集中力がなくなるなどの行動も。記憶力は比較的保たれているため、家族でも「認知症である」という認識がもちづらく「うつ病」や「統合失調症」を発症したのではないかと疑ってしまい、それが前頭側頭型認知症の発見と診断、治療を遅らせることになってしまいます。
前頭側頭型認知症患者が老人ホームへ入所する際には、本人の日頃の行動や問題点、注意点などを施設スタッフによく説明しましょう。前頭側頭型認知症患者の場合、善悪の区別がつかなくなっていることから、ほかの入所者の部屋に勝手に入りこんで個人の所有物やお金を盗む、平気で介護スタッフにセクハラをする、暴言や暴力に及ぶ可能性があります。前頭側頭型認知症患者の症状や行動にくわしい介護スタッフが常駐する老人ホームを選ぶと、トラブル時にできるだけ円満に解決できるよう配慮してくれます。ただし、本人の暴力や暴言などがあまりにも激しい場合は、入所を断られることもあります。
前頭側頭型認知症(ピック病)とは? その原因、症状について
「認知症の種類の割合について」というこちらの表をみると、一番多い認知症のタイプはアルツハイマー型認知症の55%、次が脳血管性認知症の19%、そしてレビー小体型認知症の18%、前頭側頭型認知症(ピック病)はその他に分類されており、病気の患者数は全体からみると少なめです。
| アルツハイマー認知症(55%) | |
| レビー小体型認知症(18%) | |
| 脳血管性認知症(19%) | |
| その他の認知症(8%) |
前頭側頭型認知症(ピック病)の原因は、ほかの認知症同様よくわかっていません。外国では遺伝の可能性が指摘されていますが、日本ではそのような症例はごく一部を除いて、ほとんどないようです。前項でも触れましたが、この病気は脳の前頭部、ないしは側頭部が小さく縮むことによって発症します。脳内にピック球とよばれる異常構造物やTDP-43とよばれるたんぱく質がたまることが、脳の委縮につながっているとも言われています。
前頭葉や側頭葉がダメージを受けることで、感情のコントロールや理性が利かなくなり「赤信号でも平気で交差点をわたる」「店先にあるものを万引きする」「すぐに怒る」「他人の家に勝手に上がりこむ」などの問題行動を起こすようになります。アルツハイマー型認知症とはちがい記憶力は比較的保たれており、症状が進行しても「同じものを何度も買う」「家事の失敗をする」「家をでて迷子になる」などといった失敗は少ないのが特徴です。ただし理性的な行動がとれなくなるため、セクハラや暴力、暴言、万引きなどといった非社会的な行動に走りやすくなります。
自発性の低下も前頭側頭型認知症(ピック病)の特徴です。喜怒哀楽といった感情をあらわすことが少なくなり、一日中無表情・気むずかしい表情で過ごすことが多くなります。それまで続けてきた趣味に目を向けなくなり、自発性のない生活をおくることに。一日中ベッドで横になる、椅子に座った生活では筋力の低下をまねき、それが結果的に認知症の進行を早めることになる可能性があります。
前頭側頭型認知症(ピック病)の患者でよく見られる症状としては、毎日同じものを食べる、濃いめの味付けの食事を好む、甘いものを食べ続けるなどの常同行動や嗜好の変化があげられます。決まった時間に家を出て決まった散歩コースを周回する行動も。この場合、家を出て道に迷うことはほとんどなく、決まったコースをたどって家に帰りつきます。
側頭葉がダメージを受けることで言語障害があらわれることも。「電話」「ドア」など知っているはずの言葉を聞いても、その意味がわからくなります。また状況に関係なく、同じ言葉を何度も何度も繰り返すのは前頭側頭型認知症(ピック病)の特徴です。
脳血管性認知症の初期では、患者に病識がある場合が多く「もの忘れが多く変だ」「以前はできていたことができない」と自身の異変に気がつき、落ちこむことも。ところが前頭側頭型認知症(ピック病)の患者の場合は病識が一切ないため、本人が「病気である」ことを自覚できません。それが結果的に病気の診断や治療の遅れにつながります。
前頭側頭型認知症(ピック病)患者の介護のコツは?
前頭側頭型認知症(ピック病)の患者には「反社会的な行動」「自分勝手な行動」「無関心」「常同行動(つねに同じことを繰りかえす)」「言語障害」「喜怒哀楽の消失」などさまざまな症状があらわれます。とくに反社会的な行動は患者自身の名誉を傷つけ、家族にも迷惑をかける行為です。もしも患者が万引きや痴漢行為で警察に捕まったとしたら、家族としては怒りを感じたり、幻滅することでしょう。けれどそれが本人の意思ではなく、病気がさせたことだと気づく必要があります。反社会的な行為をしても罪悪感が一切ない、同じ反社会行為を何度も繰りかえすようなら、前頭側頭型認知症(ピック病)を発症している可能性が高くなります。できるだけ早く患者本人の異常に気づき、専門の医療機関を受診させて治療を始めましょう。
前頭側頭型認知症(ピック病)は常同行動や意味のない言葉の繰りかえし、自分勝手な行動という症状がでますが、家族が「やめなさい」と指示しても、その命令を聞くことはほとんどありません。毎日決まった時間に外にでて散歩をする常同行動がみられるなら、それを生活の一部にしてしまうことです。また毎日同じ食事ばかり食べると栄養バランスの偏りが、健康状態に悪い影響を与えることも。同じ食材ばかり買わないようにしましょう。嗜好の変化により甘いものばかり食べたがる患者もいますが、甘いものの食べ過ぎは生活習慣病の原因になります。好きなものばかりを買わないように配慮しましょう。
前頭側頭型認知症(ピック病)の患者は異食をしやすいとも言われています。甘い香りのする洗剤を「お菓子」と認識して食べてしまう可能性も。大変危険です。異食しそうなものは患者の手の届かない場所に保管しておきましょう。
前頭側頭型認知症(ピック病)患者の症状は理解できないことも多く、さらに激高すると暴力に走るケースもあるため、介護サービスを上手に利用して適度に息抜きの時間をつくることが重要です。