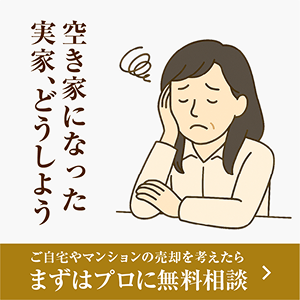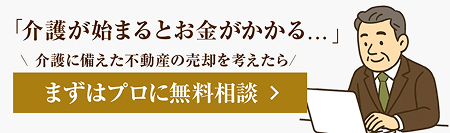Q.63 「高齢者」の定義を75歳以上にすることに意味はありますか?高齢者の定義が変わると何が変わるのでしょうか?(くらげ・会社員)
Q.63 「高齢者」の定義を75歳以上にすることに意味はありますか?高齢者の定義が変わると何が変わるのでしょうか?(くらげ・会社員)
先日、「高齢者」の定義を75歳以上にしよう、という案があがりましたが…この定義付けに何か大きな意味があるのでしょうか?高齢者の定義が変わると何が変わるのか、具体的に教えてください。
将来的に、70~74歳の医療保険の自己負担率が見直されることになるかもしれません
非常に重要な問題なので少し流れを整理しましょう。
そもそも事の発端は、2017年1月5日に日本老年医学会が「10~20年前と比較して加齢に伴う加齢に伴う身体的機能変化の出現が5~10年遅延する『若返り』現象がみられ、65~74歳の前期高齢者は、心身の健康が保たれており、活発な社会活動が可能な人が大多数を占めている」という事実から<65~74 歳を准高齢者、75~89 歳を高齢者、90 歳以上を超高齢者>と呼ぶべきではないかという提言をしました。
この提言は、あくまで医学的なもので、提言の目的も「従来の定義による高齢者を、社会の支え手でありモチベーションを持った存在と捉えなおすこと、迫りつつある超高齢社会を明るく活力あるものにすること」という観念的なもので、何か制度的な含意があるわけではありませんでした。
他方で、この提言が出された翌日の1月6日の塩崎厚生労働大臣の記者会見の場で、この提言に関する質疑応答がありました。
その中で塩崎大臣が「社会保障制度における年齢の定義を見直すことについては、企業の雇用慣行や、あるいはお年寄りも含めて国民の意識の状況を十分踏まえた上で、慎重に議論しなければいけないことなので、今回は医学的な立場からご意見をいただいたと思っています。」 というような発言をしました。この発言は日本老年医学会の提言とは異なり、明らかに“社会保障制度における年齢の定義”という制度論にまで踏み込んでいます。
ここで重要なことは、塩崎大臣は高齢者の年齢の定義の見直しについて「慎重に議論しなければいけない」と述べて、決してその可能性を否定しなかったことです。そしてあわせて「医学的な立場からご意見をいただいた」との発言もしています。
ここから読み取れる政府のスタンスは、「(将来的に)高齢者の年齢の定義を見直し、社会保障制度の適用を考え直す可能性もある」ということなのだと思います。
では「実際に高齢者の定義を見直すということになった場合どうなるか?」という点についてですが、事実上“医学的な観点”からのお墨付きは出ているわけですから、可能性として最も高いのは70~74歳の医療保険の自己負担率の見直しということになるでしょう。