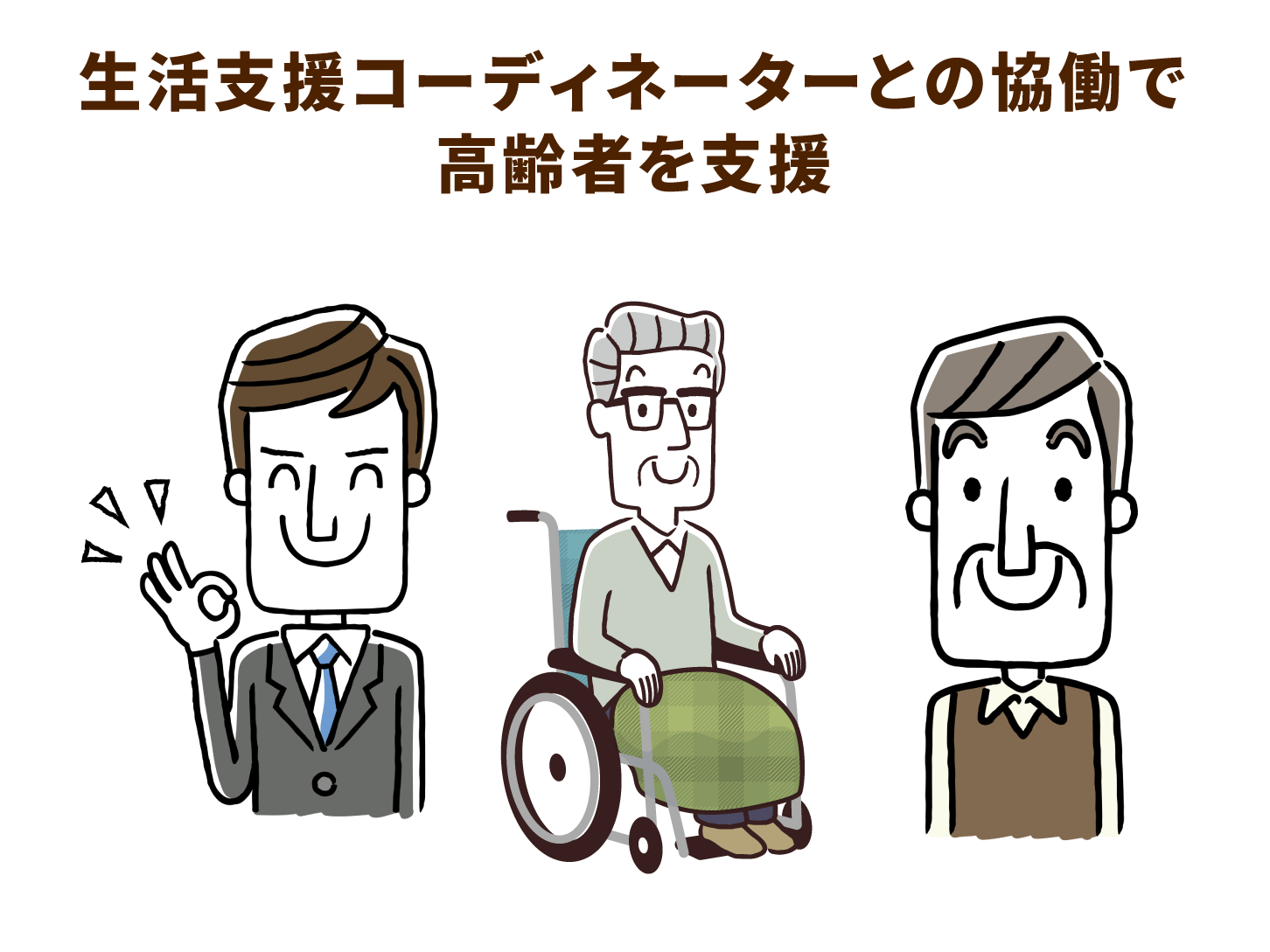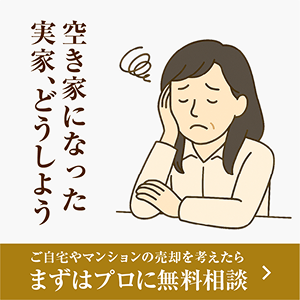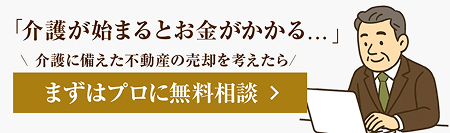高齢者が住み慣れた街で安心して暮らすためには多くの課題があります。特に、私が担当している千葉県富津市のような過疎高齢地区は課題が山積みです。
減り続ける人口、増え続ける高齢者、廃止されていく公共交通機関、小売店の減少…。
過疎高齢化に起因する課題はたくさんありますが、人がいなくなることで営利目的の企業の撤退が進み、より過疎化に拍車をかけています。
その結果、買い物や通院難民が発生し、適切な食事や医療を受けられなくなり、高齢者の生活が困難になっています。
今回は、こうした地域での課題解決に向けた取り組みと、そのキーマンとなる生活支援コーディネーターの活動を紹介します。
人手不足によって実現が困難な地域包括ケアシステム
地方における課題はテクノロジーの進化が解決してくれると信じています。
奇しくも新型コロナウイルスによってもたらされた「新しい生活様式」は、リモート勤務やウェブ会議、タブレット教育など社会に急速に浸透させました。
また、スマートフォンを始めとしたデバイスの進化はとどまることを知りません。20年後の高齢者は、今よりもっと進化したデバイスを使い、買い物や受診など、家から出なくても社会とつながることが容易になっていると予想されます。
ネットショッピングで購入した品物をドローンが運び、自動運転車に乗って外出する。そんな社会が来る日はそう遠くはないと思います。
しかし、それはまだ少し先の話になるため、私たちは現時点で少子高齢社会で失われた人的ネットワークや社会資源を、高齢者のために何とか補完していかなければなりません。
その解決策が地域包括支援システムなのですが、実現するのは簡単ではありません。
地域包括支援センターのスタッフは、地域包括ケアシステムの推進のため活動していますが、そのほかにも高齢者が介護福祉サービスを利用するための給付管理も行わなければなりません。
ケアマネ不足という状況の中、これが業務をひっ迫させているのです。

生活支援コーディネーターの3つの役割
そこで活躍が期待されるのは「生活支援コーディネーター」です。
生活支援コーディネーターは、2025年問題(※)を目前に地域包括ケアシステム推進のために厚生労働省が定めました。その活動内容はとても重要です。
※「団塊の世代」である約800万人が75歳以上の後期高齢者になることで起こる社会問題
厚生労働省は、生活支援コーディネーターの役割について以下のように定めています。
生活支援コーディネーターは「地域支えあい推進員」とも呼ばれ、国や都道府県が生活支援コーディネーターの研修を実施しています。
その主な役割は次の3つです。
- 地域の社会資源を適切に把握し、地域の住民のニーズに合わせた新しい福祉サービスの開発と育成
- 地域における新しい福祉ネットワークの構築
- 地域においての支援に関するニーズと取り組みのマッチング
生活支援コーディネーターの支援例
私が担当する地域では、生活支援コーディネーターが民生委員も兼ねており、ほぼ包括支援センターの一員と言っていいほど密な連携を取っています。
例えば、地域住民に認知症や高齢者虐待、消費詐欺の被害に高齢者があわないよう啓発することを目的とした「地域ケア推進会議」などにも参加してもらい、住民の理解を深めるためにバックアップしてくれたりもします。
また、心身機能の低下により、引きこもり状態にあった高齢者に対しては、包括支援センターと協働して活動もしています。
ある高齢者は、生活支援コーディネーターの支援によって、地域で開催している「いきいき100歳体操」に参加することが叶い、これまで失われていた地域住民との交流が復活しました。
地域の体操に自身で歩いて参加できるようになった結果、これまで介護保険で利用していた訪問リハビリを卒業することができたのです。
このように、生活支援コーディネーターは、地域住民とより密着した関係性を持っていることもあり、住民との距離が近いことも特徴です。
私たちの担当するエリアでは買い物、通院難民、加齢により草刈りなどができなくなった高齢者に対して住民が主体となって支援する団体が誕生しましたが、その裏でも生活支援コーディネーターの活躍がありました。
つまり、地域住民と行政の橋渡しをする役割も担っているのです。介護保険では補えない支援が利用できるようになったことに、住民は大変喜んでいました。
私たち地域包括支援センターは、住民とより密着した関係性にある生活支援コーディネーターと共に活動することで、地域課題を解決する社会資源の開発にも尽力しているのです。