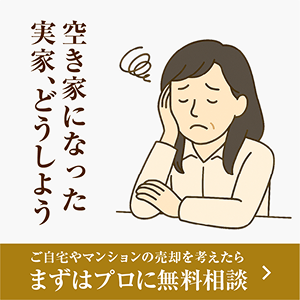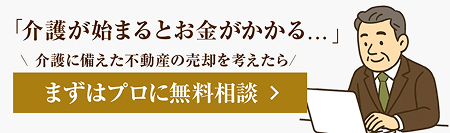森田朗「頑張ればまた、人口が増えて経済が発展していくんじゃないか?なんて漠然と考える人もいるが、そんなのは幻想でしかない」
東京大学大学院院長、東京大学政策ビジョン研究センター長、学習院大学法学部教授などを歴任し、現在は国立社会保障・人口問題研究所で所長を務める森田朗氏。専門とする行政学・公共政策について、幅広く、かつ深い知見から制度設計の議論をリードしてきた第一人者である。前編となる今回は、そんな森田氏にまずは、現状の社会保障体制が抱える問題点…中でも少子化について詳しく伺った。
文責/みんなの介護
日本が経済大国にまでのし上がってこれたのは、“日本人が勤勉だから”ではない
みんなの介護 人口問題研究所の所長でいらっしゃる森田さんに伺います。日本の人口に関して、もっとも問題だと思われるところはどのようなところでしょうか?
森田 少子化でしょうね。徐々に日本の人口が減るということは、国際的な存在感も弱くしていきますし、国内では、いわば社会を支える力が低下してきます。さらに、少子化の反動で、高齢者が多い人口構成になってきます。
みんなの介護 少子化の反動で、高齢化が進んだ、と。
森田 よく言われているように、昔は毎年かなりの数の高齢者が亡くなっていたのが、医学の発達などで亡くならなくなってきた。高齢者は減らずに、少子化が進んできたので高齢化率が高くなってきたのです。
みんなの介護 高齢化率がピークになるのはいつ頃でしょうか?
森田 2040年くらいです。要するに、団塊の世代の人たちが亡くなれば、高齢者の数は減り始めます。そうはいっても、10人のうち4人くらいは65歳以上です。この構成は変わりませんから、大変な時代に突入しました。
重要なのは、死亡者がすごく減ったところにあります。なぜかというと、昔は亡くなっていたお年寄りが亡くならなかったからです。死亡者がすごく減ったことも要因のひとつですが、高齢者が少なくて、生まれてくる子どもが少なかったときには、養う人口に対して養われる人口の比率は下がるわけです。
みんなの介護 現役世代に対して、子どもやお年寄りの人口が少なかった。
森田 要するに、ある年だけ生き残っているお年寄りが少なくて生まれてくる子どもが少ない時期は、従属人口が少なくなるんです。1960年代から90年代はじめのころ、この時期には生産人口によって生み出された富の大部分は次の世代を養ったり新たな投資に向けたりすることができます。決して高齢者を養うためではありません。
みんなの介護 そのときが、ちょうど日本の高度成長に重なっているわけですね。
森田 何が言いたいかというと、日本は別に、“日本人が勤勉だから”とか“社会の仕組みがいいから”という理由で高度成長が起こったのではなく、たまたま従属人口指数が少なかったから高度成長がうまくいった、というのが私の考えです。
もちろん、従属人口が少ないだけでは必要条件で十分条件ではないですが、その条件が失われたときに経済成長が止まった。2000年ごろですね。これからは、高齢の老年人口が急増して、従属人口指数が増えていきますから。

日本人には「人口が増えて経済が発展して豊かになって経済大国になっていく」というDNAが刷り込まれてしまっている
みんなの介護 「たとえ子どもが増えても人口が減り続ける」。これはもう、どうしようもない問題…として割り切って考えなければならないのでしょうか?
森田 どうしようもありません。だから、この現実を前提にして、社会をどのように考えていくか、ということでしょう。楽観的に話している場合ではありません。
みんなの介護 それに備えていくには、社会保障を含めて国全体の形をどのように考えていくか、ということが大事ですね。
森田 少子化がずっと続いて生産年齢という働く世帯の人たちが減ってきていますよね。一例を挙げますと、日本の自動車が最も売れていた1990年代、770~780万台売れていました。でも今は400万台売れないわけ。もちろん「車離れ」もありますが、だんだん消費者自体が減ってきています。国内市場を前提にして作る力があった産業というのがそれだけ弱くなってしまうわけですから。国外でも売って1000万台突破する企業もあるわけですが、世界で売っていかなければならないわけです。逆に、それができなれば大変なことになります。
経済というのは非常に短い時間で大きく変わります。人口も、30年くらいで大きく変わる。でも、人間の頭の中にある意識は、変わるまでのスパンが長いんです。
みんなの介護 少子化対策が決まったとしても、そう簡単には少子化が解決されるわけではないように…。
森田 少子化を防ぐにしても、“子どもをたくさん産みましょう”という施策を立てたとして、生まれる子どもが今以上に増えたとしても、子どもを産む世代の女性が過去の少子化で減ってきていますので、50年くらいは楽観的に見ても人口が減り続けるでしょう。
みんなの介護 お話を伺えば伺うほど絶望的な気持ちになるのですが…。
森田 日本という国はある意味、人口が増えて経済が発展して豊かになって経済大国になっていく、というDNAが刷り込まれてしまっています。そういう認識のギャップと社会の作り方へ頭の切り替えができるかどうかが勝負になってきます。
頑張ればまた人口が増えるんじゃないかとか、増えるとはいかなくても減らないんじゃないかとか、幻想を持ちがちですし、現に今の内閣でも、少なくとも急激に減らなくとも人口1億人ベースで横ばいになるぐらいのことをやりましょう、というようなことは言っていますね。具体的に、どのようにやるかは言っていないようですが。

2040年、毎年一つの県が消滅していくイメージ。“移民を入れればいい”は虚しい議論でしかない
みんなの介護 第三次ベビーブームの山が現れると思って…もし来なかった場合の最悪のシナリオを考えていなかったのでしょうか?
森田 考えていなかったんでしょうね。毎年人口は増えていっていたわけですから、トレンドがこう進むだろうという、これも幻想ですよ。それで、人口が減り始めてはじめて大騒ぎになった。じゃあ、「減ったからまた戻せ」と言っても、もう無理なわけですよ。
みんなの介護 人口が維持する、あるいは増えるということを前提に政策を考えるのは間違っている、と。
森田 人口が減るのを前提にしてどうしますか?という話。それでいて高齢者が増えてきますからね。人口バランスを取るだけならば、はっきり言えば高齢者に死んでもらうのが一番いいわけですよ。高齢者に死んでもらうのはできないことではないけれど、いきなり20歳の人口が増えるということはありえないわけです。
そうしてよく持ち上がるのが移民の話ですが、そんなに都合よく来るわけがないですよ。ヨーロッパで大騒ぎしているシリア難民が数年合わせて100万人くらいという話で、EUが正式に受け入れるというのが10数万人から30数万人と言っているときですからね。毎年それくらいの人口が減っている日本に移民を入れれば何とかなるというのはどれだけ非現実的か?という話になるわけ。
2040年ごろになると、毎年100万人くらいの日本人が亡くなります。100万人以下の県はけっこうありますから、イメージとしては、毎年その県が一つずつ消滅していくという感じです。
みんなの介護 2010年度の国勢調査の結果によれば、100万人以下の県は鳥取県や島根県、高知県、徳島県、福井県などですね。
森田 その数に置いてみると、“移民を入れればいい”というのがどれだけ虚しい議論かというのがおわかりいただけるのではないでしょうか。
「限られたパイの取り合い」をしているだけに過ぎない。次は首都圏が高齢化する。
森田 高齢者や介護に関連する問題で他に考えられることは、地域の問題があります。今までは農村部で減っていて、都市部では統計上は増えています。本当はもうすぐ減るはずなんですが、思ったよりも減っていない。でも結局は日本全体の人口としては減っていくわけなので、都市部か、それ以外の地域のどちらかに分けるかの話なのです。
みんなの介護 限られたパイをどちらから移すかという話なのですね。
森田 地方創生とかって、地方消滅を避けるため、地域振興して人口を集めようと言っていますよね。でも今、仮に東京の人口を抑制して若者が地方に行って頑張ろうとしたとしても、次の世代になったときはまた減るわけです。そうすると、それが同じような形で維持できなくなりますから。限られたパイの取り合いをしているのが、昨今の地方創生のような話。
地域に関する大きな問題がもう一つ。子どもの数も生産年齢人口も減ってきて、まあ高齢者は増えていますが、これから急速に増えるのは、特に首都圏の高齢者です。この人たちをどうするか、非常に深刻な問題です。
みんなの介護 どれぐらい増えるのでしょうか?
森田 東京だけで、2010年から40年までに、150万人ぐらい増えます。さらに言えば、首都圏だと400万人にまで増えます。この人たちは、高校卒業と同時に集団就職で地方から上京してきて、東京周辺に住んだ。そういった人たちが高齢化して、人口あたりの医師数を見ると顕著ですよ。
みんなの介護 一番少ないのは、埼玉県ですよね。その次が千葉県。これからの首都圏の高齢者数を考えると、介護施設が不足する問題も出てくるのでしょうか。
森田 あると思いますね。一方では、島根県や秋田県もそうですが、人口がどんどん減ってきている県は高齢者自体の絶対数として減り始めています。若者はもっと減っていますから、高齢化率は上がっているけれど、高齢者の数も減っている。そういうところだと、医療や介護の施設が余ってくる可能性もあります。数合わせだけすると、首都圏の高齢者の人にそっちに移り住んでもらおうよ、という話になりますが、人間の生活ですから、そう簡単にはいかないわけで。

政治家に行動を取らせるのは難しい。科学的根拠で戦わなければならない。
森田 どういう形で経済を活性化して、その富でもって高齢者を支えていくのか。その働き方の問題や生産性の問題などさまざまな形で言われていますが、富を多く作り出せば作り出すほど配分できるわけです。でも、誰が作り出すか、どうやって作り出すか、という問題に、減っている生産年齢の人たちが頑張りましょう、という話になってくる。
一方では、その介護や医療で高齢者は増えますから人手は必要なわけです。雇用は増えるので見かけ上のGDPは増えますが、基本的に介護のために何かをして、介護を受けるとその人が払うわけじゃないですが。しかし、そのお金がどこからくるかと言えば、彼らが稼いで生み出した富、お金から来るわけではないんですよ。
ときどき、政治家の偉い方が医療や福祉サービスをやればGDPは増えるし、ハッピーになると言いますが、そんな簡単な話ではありません。将来世代から借金をして回すお金ですから。そこが苦しくなったら大元の蛇口を閉めたらみんな止まる話になりかねません。今でもそこは余裕がなくて苦しいものですから、介護労働力の賃金が非常に低いというわけで。
みんなの介護 政治家のみなさんはなぜそういうことをおっしゃるのでしょうか?
森田 簡単に言えば、彼らの目的は次の選挙で当選することだからでしょうね。つまり票数を得ること。有権者に占める高齢者の比率が高くなっているのはみなさんご存知でしょうが、その人たちの多くは、首都圏に集まっていますから。ここだけ人口が増えていてまわりが減ってきていますから。
一票の価値を平等にすればするほど、都市部の政治力は強くなってきます。だから、都市部の、自分で“貧しい”と思っている高齢者が喜ぶような政治をやれば票が集まる、という構図になってしまっているわけです。最高裁も、一票の価値は平等だと下していますから。ますます地方を代表する議員の数が減ってきて、その分、相対的に都市部が増えてくる。それがある以上は、政治家の人たちに行動を取らせるのは非常に難しいでしょうね、今の世代の負担を増やすとかサービスを減らして持続可能な社会保障制度にしていくというのは。
みんなの介護 そんな現状の中で、国立社会保障・人口問題研究所の役割というと…。
森田 私たちは政策提言を直接的にすることをミッションにはしていません。と言うのも、政治家が選挙で勝つために都合の悪い数字を操作する可能性があるわけです。そうすると、政策が歪んでしまいますから、ここは国の研究所としてあくまでも科学的な方法にしたがって政府が良いと言おうが、悪いと言おうが、客観的なデータを出す。
みんなの介護 そのデータをもとに政策が作られるわけですね。
森田 そうなんです。厚生労働省や内閣官房、内閣でその先にどのような政策をお考えになるかは、我々の外で判断してやってください、というスタンスです。
今の官僚の方たちは、筋を通すことに関して、少し弱腰なところがあるように感じます。内閣が何と言おうと、科学的な根拠でこうなっている、ということをきちんと言っていかないといけない。かなり言っていらっしゃるとは思いますが。
やはり、政治家の方と戦わなくてはならないですからね。人って、自分にとって不安を煽ったり嫌なことを数字で証明されたりしたら反発するものです。それは違う!と思いたがる。そこを、こう、強く言っていただく必要はあるかなと。
あとはメディアの方も。科学的根拠に基づく数字ということを、もう少し強く言っていただけるとね。

メディアの影響は大きい。「何が本当か分からない。」不確かな情報に踊らされている人はかなりいる。
みんなの介護 正しい数字を発信することの重要性を感じます。
森田 ここの研究所もそうですが、どのような形で数字を出していくのかということと、その結果を受けて社会のあり方を考えていきましょう、そうでなければ部分的な数字と都合のいい数字でもって一種の思い込みでもってかなりいろんなことをおっしゃる。でも数字を見ると、また別のかなり厳しい現実が見えてくるでしょうね。
でもね、役所がもっとちゃんとしましょう、と言ったとしても、自分たちがやってもさらに政治家からのプレッシャーがありますから。
だから、“事実”を受けてメディアがどのように発信するか。メディアで次の選挙にどう影響を考えるかという政治家が判断するか。そして政治家は短期的な次の選挙へ。で、厚生労働省にプレッシャーをかける…という循環になっています。そこを、科学的根拠でもって戦うというのはなかなか…。根性のある人がいないのか!っていうね(笑)。
みんなの介護 学習院大学の鈴木亘先生なんかは、官僚の方がリスクを負える制度を作るべきだとおっしゃっていましたが。
森田 それはそうだと思いますよ。本来であれば、政治が判断して責任を負う。今もそうなっていますが、ただ、何十年後に政治家が責任を負うかとなるとそうではなくて、またそのときは責任を官僚制に押しつけるわけですから。それは“やってられないよ”という気分にもなると思いますよ。責任をはっきりしろ、と言えばその通りなのですが、猫の首に鈴を付けるかの話だから。
みんなの介護 では、国民の一人ひとりが科学的な根拠のあることを学んでいくことが必要になってくるのでしょうか?
森田 まあ、それはそうなのですが、もっと言えば、国民だってそこまで科学がわかるわけではないですから、やっぱりメディアなりの影響が大きいと私は思っています。活字メディアでは、ある程度はきっちりした頭で読むんですが、テレビのニュースショーやインターネットでいい加減な医療情報が出てきたりね。根拠が不確かな情報に踊らされている人がかなりの数いるのではないでしょうか。
選挙で落ちるような公約を掲げて当選しろよってのは無理な話で、そうすると、いまのデモクラシーの仕組みである限りは難しくなってきてですね。無視するという意味ではトランプみたいな人が出てきて、年寄りには我慢してもらって若い世代をあれしよう、ってのを強引にやらなければ、民主主義を無視してやらなければ無理かな、と。お年寄りが、“ああ確かに自分は十分長生きしたからこれからは若い人たちのために…”というように理性を発揮するか。
みんなの介護 でも、それはもう、性善説に基づく話のような気もします(苦笑)。
森田 そうそう、両方とも期待できない(笑)。でもこれ、認識してくださいって。まだ若い人のほうが多いですから。世代間で戦ったときにね、少し自分たちのことを言わないと大変なことになりますよっていうようなことは。
みんなの介護 若者がおとなしすぎるのでしょうか。
森田 そう思います。去年か一昨年の安保の騒ぎのときにSEALDsが中心となった問題がありましたよね。この研究所の辺りをずっとデモしてたんですよ。そうするとデモ隊がわーっときて、ざわざわしているから見てみたら、一番後ろはテレビカメラ持ってるテレビのクルーの人たちがいて、前にリーダーの人たちがいて、その後ろ、全体の行列から言うと20%くらいですけれども乳母車押してるお母さんとか若い人がいて。そのあとは、私と同じ60歳以上くらいの人たちが昔の思いで安保反対とかなんとかやってるんですけれども。私に言わせれば、前で頑張っている人の本当の敵は後ろにいる(笑)。そっちの人たちと戦わないとあなた方は大変なことになりますよ、と。
高齢者の意識を変えたり、こういう問題があるってことをちゃんと認識してもらうためにはやっぱり、正しく数字をだしてそれを正しく伝えるっていうメディアとか媒体の責任は大きいと思いますよ。昔はだから、活字にしろなんにしろ、メディアのプロの人が発信してましたから、まあそこでコントロールしてたわけですけれども、いまSNSみたいになってきたら、かえってこう、ブレが激しいわけだよね。もちろん、メディアも合わせて大本営発表しかやらないときに対して真実はこうだ、という発信はできるわけですけども、それはいまのフェイクニュースの話じゃないですけども何が本当だかわかんない。
とにかくアクセス数が多ければいいっていうそういう情報になって来るから、フィクションとノンフィクションの区別がつかなくなって。とにかくウケる情報をいかに早く、どのタイミングで出すか。簡単なのはだから、いわゆる「disり」ってやつで(笑)。そちらのほうがウケるだろうね。そういう話になってきてますから。ただ、問題が何かってのを数字で出さないと、人口が減ってないよ、というのだけ出すとそれは全くの嘘になりますけども。
みんなの介護 確かに数字というのは一番目に見えてはっきりしているので、一番信じるに値するかなというようにも思いますが。
森田 人口なら人口で、ここの研究所のスタンスはとにかく、ナマの数字、ベースとなるあれを出しますと。それをどう解釈してどうするかは、それはみなさんなんです。
「資産の抱き込み」は手厚い福祉で解消する。若者への負担は合理的じゃない。
みんなの介護 メディアのあり方について伺いました。
森田 明らかに若者の利益の立場に立って発信するのは何が問題か。「もっと若者に回せよ」「財源を将来にとっておけよ」「もらいすぎだぞ」という若者からの主張があって、「いや、何を言っているんだ」「これだけいい国にしていないのは我々なんだからちゃんと年寄りの面倒を見ろよ」というのがぶつかり合えばいいのだけれど。
今はどちらかというと、“お年寄りはお年寄りだから大事にしなければいけませんね”という意見が先にきて、その後、おまけ程度に“でも若者も大事ですね”となっている。で、どうやってそれができるんですか?っていうのを聞くと、黙られちゃう。
みんなの介護 今の制度のまま続くと、長生きすればするほど生活が苦しくなってしまうのではないかと感じます。
森田 苦しいでしょうね。自分にだって回ってこないのに、もう亡くなった人たちがつくった借金のために払っていて、今の年寄りまで回せるかなんて話になりかねないわけですよ。それがだんだん可能性が高くなって、なんとかしようぜ、みたいな話になっている。
その一つは、みんながある程度我慢せざるをえないんだけれども。我慢するときに、たくさんお金を稼いでいる人、お金を持っている人から、そうでない人に回すというのをやっていきましょうよ、と。そのひとつの方法というのが消費税。それを駄目だって言っちゃってるもんだから、どうなっているの?というね。
みんなの介護 例えば資産課税というのがあります。財産や土地などの資産に税金をかけるのがいいのではないかという声もありますが。
森田 それもやらざるを得ないと思います。だから何が問題かというと、今の若い人たちが頑張って働いて納めた税金を今のお年寄りに渡すのではなくて、お年寄りはいつ死ぬかわかんなくてまだ長生きしそうだから将来の不安があるっていうんで資産を抱えこんでるわけじゃないですか。
みんなの介護 いまの年金収入としてはそこまでない人も、数千万円の資産を持っている人もいると言われています。
森田 そう。そこまでの大金をあの世まで持ってけないわけですから、一刻も早く吐き出せ…とまでは言わないけれど、自分たちの世代の人たちがお互いに支え合うために使ってはどうですか?と。少なくとも、その人たちはその人たちで抱えこんだまま、若い人たちに貧しいお年寄りを養わせるているのは、これはあまり合理的じゃないんじゃないですか?って、私なんかは思いますけれども。
そのためには、フローとしては、基礎年金だけだと毎月5万円いくらしか入りませんが、数千万の資産を持ってる人はその資産を使ってください、と。資産を吐き出させるためには、資産に直接課税するのもありますけれども、間接税、消費税を。そして後から所得のない人に給付をする、てのが一番合理的じゃないですか。
そのために北欧諸国ではその仕組みを入れてるじゃないですか。日本と違うのは、スウェーデンだと消費税率は25%です。もう一つは完全なマイナンバーみたいな番号制度でもって給付と負担の調整をしているわけですよ。きめ細かくね。日本でもそれをやるしかないんじゃないですか。だから、ウェーデンに限らず北欧諸国がどうしているかというと、みんな資産を持ってないわけですよ。もたなくていいわけですから。
みんなの介護 福祉がちゃんとしているから。
鴨下 そうそう。だから、老後の生活が不安だから介護のための費用がいるから貯蓄しておくのだとするならば、国が面倒見るなら貯金としてとっておく必要はないわけです。そのへんは割り切っていますよね。

CCRC…と言ったって、高齢者向けのサービスの全体に影響を与えるほどの人数が移住するとは考えづらい
みんなの介護 話題を介護に戻しますね。現在、国としては施設介護ではなく在宅介護を推進しています。
森田 財源の面からいうとそう言わざるを得ない、というのと、もともと在宅というのが「地方で親子3代で暮らしているところで、孫子に囲まれ」というイメージだったんですよ。ただ、そうすると悲惨なことになりかねない、なんとかしようということで、たとえばURなんかでも、建て替えるときにできるだけ人を集めてサービスそのものを効率的にしていかないと、という話が挙がっていますね。
エレベーターのないURのアパートの4階や5階でほとんど一日寝たきりで、ヘルパーさんが毎日来てくれて訪問看護師の人が週に2回来てくれて、先生は月に1回…みたいなところで、「やっぱりこれからは住み慣れたところの在宅ケア」なんて言ったって虚しいでしょ?
みんなの介護 とすると、介護・医療が必要な人を一定のところに集める、という策が考えられるでしょうか。
森田 古いアパートのあちこちにナースコールをつけて、看護師さんが来るまですごく時間がかかって…で、他で呼ばれたらまた時間かけて行って、なんていうやり方よりも、同じとこに集めておいた方が効率的だし、費用面でも少なく済むじゃないですか。次の人のところにもすぐ行けるという環境を作っておくほうが良い。
ただ、そのためのお金と時間があるかって言ったら、相当厳しいのが現状。ということを、まずは多くの人に理解していただくことが重要だと思いますね。ちゃんと理解してもらえてたらオリンピックなんか呼ばなかったんじゃないか…これは余計な話ですけれども(笑)。何千億のお金があったらなにができるかっていう話。
ただし、もうひとつ言っておきますと、そういった高齢者の増加も、首都圏ですらそうですけども、やっぱり2030~40年で頭打ちになって減っていきます。東京都はまだちょっとわかりませんけどね。ただ東京都だけ考えてもだめなんで、首都圏、周辺で考えないと。だから埼玉南部とか。神奈川の北東部だとか千葉の西部だとか。そちらはみんな一帯として考えなければ駄目です。
例えば東京だと、2010年には270万人だった高齢者が2040年に420万人と、150万人も増えるわけです。首都圏だけで400万人以上増えるわけで。この人たちを、誰がどうやって面倒見ますかという話ですし。そういう人たちは、埼玉県や千葉県などのベッドタウンから東京の都心に働きに来ていた人たちですので、単身核家族で集合住宅に住んでいるわけですね。
みんなの介護 50代とか、定年前から地方移住を前向きに考えたほうがいいのでしょうか?
森田 CCRC、ですね。私もそういうところは見てきました。まあ行く人はいるとは思いますけが、何百万と増えてくる高齢者のうち、首都圏で高齢者のサービスに影響を与えるくらいの人が動くとは考えられないですね。
みんなの介護 首都圏の中で介護ってものをうまく回そうとすると、単純にヘルパーさんの数を増やす、もしくは介護自体を効率化するってやりかたがあると思うんですけども。
森田 どっちもやらなきゃだめでしょうけども。ただヘルパーさんを増やすといったって、どんな人たちがヘルパーさんになってくれますか?みたいな話になってきて。一番戦力になる、比較的賃金が安くて体力のある人というのは、残り少なくなった地方から若者を集めてくるのかっていう話になるのか?と。
みんなの介護 そこで移民の話がよく挙がるわけですが、森田先生はそれには懐疑的というお話でした。
森田 移民によって多少の数合わせはできるかもしれませんが、日本の介護に適応するためにそれ相応のトレーニングを積んで…という話になってくると大変。実際問題としてそういう東南アジアの良質な労働力っていうのはヨーロッパも介護労働力として狙っていますしね。
ドイツなんかはインドネシアやフィリピンなどにちゃんとドイツ語を教えてあげってのを、ドイツのお金でもってそういう学校を運営して、養成しています。で、そのままドイツに連れて行って。日本は、「ちゃんと現地で日本語勉強してきて、試験に合格したら入れてあげるよ」みたいになっているから、国際的な競争という面でも不利なんですよ。

コンパクトシティや人口の集約化をどうやって進めていくか。それが人口減少社会を乗り切るための術
みんなの介護 移民政策もあまり現実的ではない…とすると、少ない人材で最大の効率化をはかるには、どのような策が考えられるでしょう?
森田 さっき言った資産やマイナンバーもそうですし、カルテかなんかもそう。ITによって医療を効率化するのが重要でしょうね。遠隔診療もそうですよね。今大変なのは、病院の場合には狭い空間ですから患者さんについての情報というのは、主治医も看護師も薬剤師も、すべてを共有できたじゃないですか。同じノートに書いておいて、みんなでそれ見ることができたわけですけれども、在宅になってくるとそれが大変なわけで。
お医者さんはお医者さんの都合で往診しますし、訪問看護師さんは訪問看護師さんとして一番合理的な形で行くし、ヘルパーさんはヘルパーさんで…同じことですよね。そこで情報の共有をどうしますか?どうやって効率化させますか?という話です。で、一時、多くのところでやっていたのが、枕元のノートに書いておくという方法があったんですが、それだって枕元に行かないと情報がないじゃないですか。そういった非効率を避けるために情報を共有しましょうとなったら、今だったらタブレットで、関わるすべての人が情報を共有できるようにしましょうという。それには、番号をちゃんと入れてIT化しかないんじゃないかという話です。
みんなの介護 ITの力で、遠隔ですべてを把握できればずいぶん効率化できますよね。
森田 家に行かなくても情報をパッと見て「この人たしかに悪化しているな。でも緊急性はないな」というのがすぐにわかります。「それよりも後から情報が入ってきた人のほうがもっと緊急だから優先しなくちゃいけないな」ということが手元ですぐに比較できるようになりますよ。それをやっていて、医師や看護師など高い専門性を持った人たちに合理的に働いてもらう。効率的にその人達の能力を使うためには、情報の共有というのは不可避じゃないですか。
もっと言えば、例えば褥瘡がある場合に先生が毎回往診したとしても、症状が変わってないからこのお薬を使ってくださいというだけかもしれないですよね。でも、今の時代なら、看護師さんやヘルパーさんがスマホで写真を撮って送れば、お医者さんに判断してもらえますよね。
みんなの介護 すると、往診にかかる移動時間を、他のもっと重症の方に充てることができますね。
森田 例えば、4キロ離れたところに行くっていうその往診の交通にかかるコストというのは、お医者さんでも看護師さんが行ってもヘルパーさんが行っても変わらないじゃないですか。ところが診察をするとなると、お医者さんは時間あたりで単価がものすごく高いわけですよ。だから一日24時間、働いている時間8時間なら8時間、10時間なら10時間の先生の持ち時間のうち、移動にかかる時間ってのを極力減らしましょうとなったら、やはり遠隔診療は合理的ですよねか。
それはもちろん実際に行ってみなきゃだめだってのはあると思いますが、その往診の回数をできるだけ減らす、というのが、限られた医師で多くの人に質の高いケアをするためには必要なんじゃないですか。もっと言えば、例えば東京に住んでいる人が年を取って地方へ移り住んだとしますよね。そのときに向こうでそういうケアを受けていて、症状が悪くなったときに、「過去にどういう病気をしましたか?」「どういう治療をしましたか?」という情報を、ディスプレイの前にいながらにしてアクセスできれば、もっと質の高い治療ができるじゃないですか。番号でその人の医療情報ってのは先生がみることができるようにすれば、効率的に質の高い医療ができると思うんですけどね。
みんなの介護 よく言われがちなのが「個人情報の取り扱いが…」という問題ですが。
森田 まぁなりますよね。でも、例えば認知症が始まった人に本人同意を取ること自体がナンセンスな話だと思いますし。そうまでして個人情報を守るよりも、本人の健康を守るほうが大事じゃないかと、私なんかは思いますけどね。まぁ、反対する人がいるもんですから、やれやれってちょっと過激に言ってますけども(笑)。
みんなの介護 では最後に…希望的観測は抜きにして、人口が将来的に減少する、という前提に立ったときに、(将来世代に)ツケを払わないようなやり方で国を維持していくにはどういった方法があるとお考えですか?
森田 それは最後のポイントになってくるかもしれませんけどね。要するに、1億2,000万のために日本はいろんな政策だとかハードもソフトもあるわけですね。それがどんどん減ってくとしたら、減った人口に合わせてスペックを下げてくしかないでしょう、と思います。
みんなの介護 スペックを下げていくとは?
森田 質を落とさずに資源投入量を減らしていくってためには効率化の話になってきて。そのために、さきほどのITの話もそうでしょう。高い報酬をもらってる人は移動する時間が無駄だから、どんどん減らしましょう、みたいな話になるわけ。
もう一つは地理的な話であって、最近ではコンパクトシティとかなんとか言われてますけど。今の時代は、ほっとくとみんな東京に集まって来る可能性があるので、例えば東北なら仙台、九州なら福岡…みたいに、一箇所に集まっていくという仕組みが必要でしょう。
そこで大事なのは高度急性期病院でしょう。例えば脳の血管が切れたとか心臓発作が起こったとか、そういうときに救急車で10分、20分で行ってちゃんと手術を受けて助かるような病院があるところに集まって住みましょう、と。今のようにだんだん人口が減って来て拡散しているときに、近所の病院にそれをやれというのはコストとして無理じゃないですか。
みんなの介護 ただでさえ人口が減ってきて、患者さんも減って、経営が厳しくなっているわけですからね。
森田 「そんな治療は受けなくて結構」という人はどこに住んでもいいですよ、と。だから、どこに集約化を図っていくかということがこれからの議論になる。まだ日本ではその選別…要するに、長期的に見てだんだん撤退し消滅を認める地域と、ここを核として維持していこうという地域の線引きというか、区別をしていくのも非常に難しいのが現状ですけどね。
みんなの介護 その線引も、ちゃんとデータを見て分析して。
森田 データに基づいて、そこからはもう政治的な決断でしょうね。撤退するところは説得しなければならないから。実際問題としてデータをとって見ると、医療保険の保険料は平等ですし、受ける治療はどうかっていうと、かなり格差があるわけですよ。ある県の場合には大きな都市があって、そこでは高度急性期の治療を受けることができるところがいっぱいあるんだけれども。そうでないところは、まあ小さな公立病院か私立の病院しかなかったり。
じゃあどうやって平等化しますか?同じように死んでもらいます、というわけにもいかないでしょう?かと言って、その過疎の地域に莫大なお金をかけて、病院と専門医を配置するわけにもいかないでしょ?そもそも専門医が行ってくれないですし。となると最後の策はどうするかというと、助かりたい人は病院の近くに住んでください、という仕組みを考えざるを得ないんじゃないですか。
コンパクトシティや人口の集約化をどうやって進めていくか。同じことは介護でも言えるわけで、高度急性期病院の隣に療養病床を作っておいて、その隣に老健をたくさん作っておく、と言うような形ですよね。仮に急性増悪で何か起こったとしても病院の治療が早く受けられるし、終わったあと、また療養できちんとケアする。とにかく高度急性期というのはものすごくお金がかかります。でも、助かりますから。それをどういう形で効率的に配置するかというのが、これからの人口減少社会の対処法かな、と思います。これって、本来は私が言うことじゃなくて厚生省が言うことなんですけどね(笑)。
撮影:公家勇人
連載コンテンツ
-
さまざまな業界で活躍する“賢人”へのインタビュー。日本の社会保障が抱える課題のヒントを探ります。
-
認知症や在宅介護、リハビリ、薬剤師など介護のプロが、介護のやり方やコツを教えてくれます。
-

超高齢社会に向けて先進的な取り組みをしている自治体、企業のリーダーにインタビューする企画です。
-

要介護5のコラムニスト・コータリこと神足裕司さんから介護職員や家族への思いを綴った手紙です。
-

漫画家のくらたまこと倉田真由美さんが、介護や闘病などがテーマの作家と語り合う企画です。
-

50代60代の方に向けて、飲酒や運動など身近なテーマを元に健康寿命を伸ばす秘訣を紹介する企画。
-

講師にやまもといちろうさんを迎え、社会保障に関するコラムをゼミ形式で発表してもらいます。
-

認知症の母と過ごす日々をユーモラスかつ赤裸々に描いたドキュメンタリー動画コンテンツです。
-

介護食アドバイザーのクリコさんが、簡単につくれる美味しい介護食のレシピをレクチャーする漫画です。