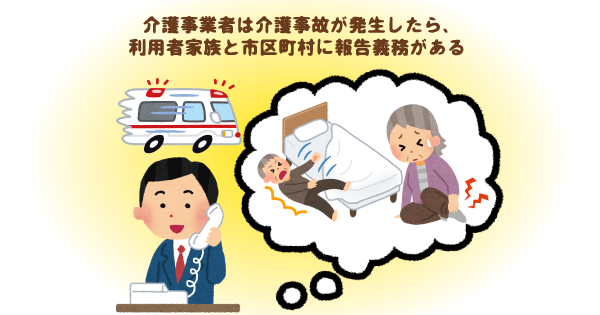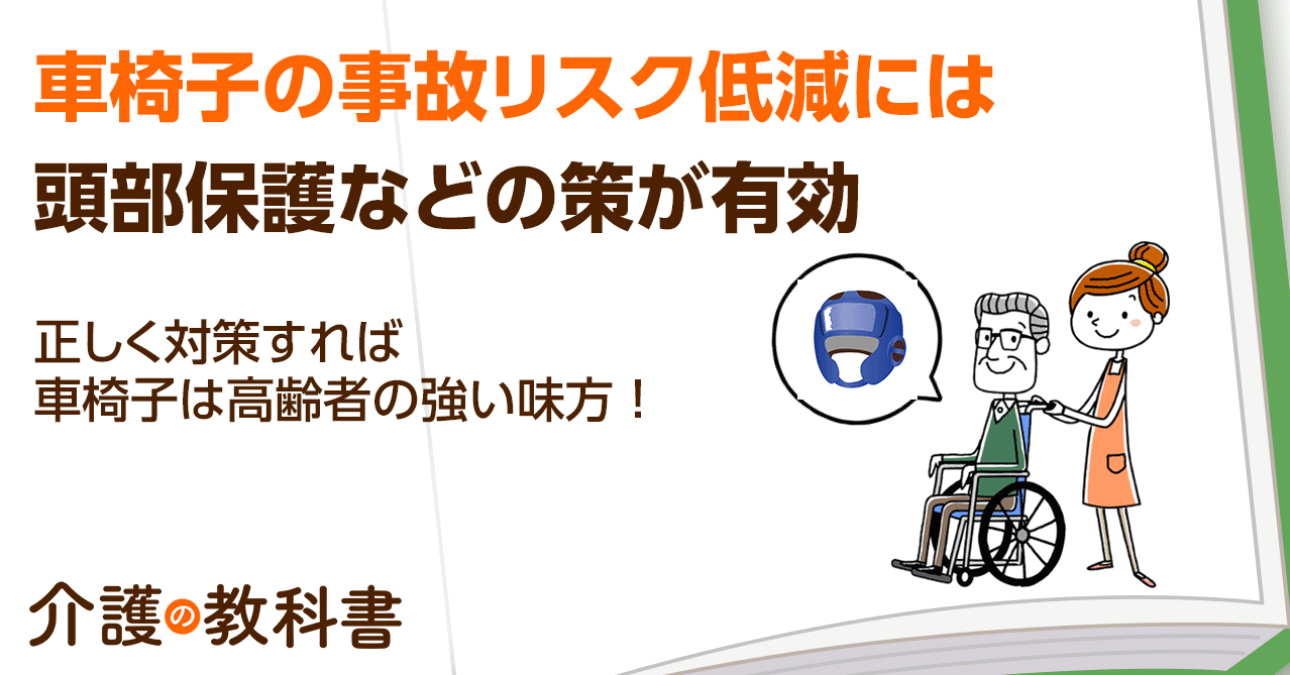みなさん、こんにちは。甲斐・広瀬法律事務所の弁護士で、「介護事故の法律相談室」を運営している甲斐みなみと申します。
これまで、私の担当する介護事故の分野では、転倒事故、誤嚥事故、入浴中の事故について、具体的な事例をもとに損害賠償請求ができるのかについて解説してきました。
これまでは主に、介護事業者側に安全確保義務違反や注意義務違反(過失)が認められるかという点を中心に検討をしてきましたが、今回は、介護事故においてもうひとつ大きな争点となる、事故と結果の因果関係について検討・解説していきたいと思います。
損害賠償を請求するには“因果関係”が認められる必要がある
介護事業者側の過失が、被害者に生じた結果につながったという因果関係が認められなければ、その結果について損害賠償請求は認められません。
この因果関係については、医療事故においても争点となることが多く、過失は認めさせることができても、因果関係の点(そのミスがなければ死亡しなかったのか、あるいは、ミスの内容と死亡が医学的機序等から結びついていると言えるのか)で苦戦するということもよくあります。
東大ルンバール事件からみる"因果関係"
医療事件において、因果関係が大きな争点となった事件の判例として、有名な東大ルンバール事件の最高裁判決(最高裁判所昭和50年10月24日判決)があります。
この事件は、ルンバール検査を受けた患者に発作や後遺症が生じ、その原因は何か、ルンバール検査と因果関係があるのか、医師に過失があるのか、などの点が争われたもの。難しい言葉が並んでいますが、オレンジ色で強調されている部分に注目してください。
「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挾まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである」と判示しています。
もし事件を科学的に立証できるのであれば話は早いのですが、多くの事件ではそれが難しいのが現実です。ルンバール事件の判決でも「一点の疑義も許されない自然科学的証明までは求めない」とされました。
そして、さまざまな事情を総合的に検討すると、一般的な人であれば「発作の原因は脳出血で、その原因はルンバール検査。そのため、ルンバール検査と発作には因果関係」と判断できるものとして、因果関係を認めました。

このように、損害賠償請求の要件となる因果関係は、必ずしも簡単に認定できるものではありません。
そして介護事故の場合は、被害者は高齢で、要介護状態であるため、若くて元気な方が被害者になる場合とは、事故後にたどる事実経過が異なることが少なくありません。
そのため、因果関係が争点になりやすいとも言えます。
介護事故は高齢者の身体機能の低下がポイント
高齢者の介護事故における因果関係を検討するためには、まず「廃用症候群」について理解しておく必要があります。
廃用症候群を理解しておこう
廃用症候群とは、「生活不活発病」とも言い、身体の機能を使わないことによって生じる心身の機能低下のことです。 健康な人でも、1週間寝たきりの状態が続くと10~13%の筋力が低下し、その状態が3週間も続くと、ひと目でわかるほど筋肉の萎縮や関節の拘縮がみられるようになると言われています。
また、健康な若者でも、3週間寝たきりの状態で過ごすと20~30%の心肺機能低下がみられると言います。
高齢者の場合は、寝たきりの状態が続くと、以下のように全身のあらゆる機能が低下してきます。
- 運動機能の低下(筋力低下、骨粗鬆症、関節拘縮等)
- 循環器系の障害(起立性低血圧、静脈血栓)
- 呼吸器系の障害(換気障害、肺炎)
- 消化器系(食欲低下、低栄養、便秘)
- 心肺機能の低下(心拍出量低下、肺活量低下、起立性低血圧)
- 精神機能の低下(抑うつ状態等)
これらのような、高齢者の身体の状態を踏まえたうえで、因果関係を見ていくことが大切です。
転倒による右大腿骨頸部骨折から肺炎になり死亡したケース
それでは、東京地裁平成15年3月20日判決の事案を参考にした以下の事例に沿って、検討してみましょう。
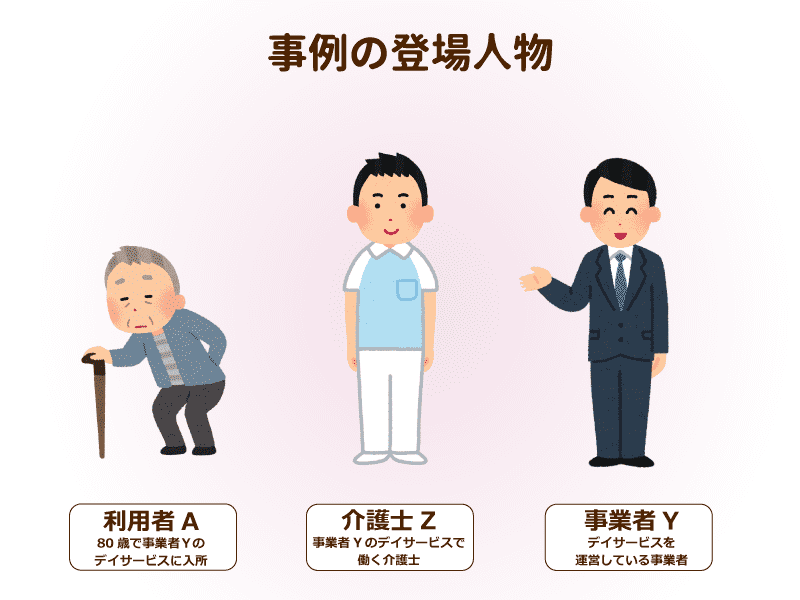
事例
80歳のAは、数年前から認知症の症状が出てきたため、Yの行うデイサービスを利用するようになりました。
ある日、Aはデイサービスの利用を終えて、自宅まで送迎してもらうバスから降りる際、送迎担当の介護士Zが十分な見守りをしていなかったため転倒してしまいました。
Aは整形外科を受診し、レントゲン検査の結果、右大腿骨頸部骨折と診断され、入院のうえ、手術を受けることとなりました。
骨折に対する手術は成功しましたが、Aは入院後、ベッドで寝たきりの状態が続き、食欲も低下してきました。
事故から約1ヵ月後、Aは肺炎となり、肺炎の治療が行われました。
Aは、いったん肺炎が改善して経口摂取を再開できるようになりましたが、誤嚥性肺炎を繰り返すようになり、徐々に全身機能が低下して、事故から約4ヵ月月後、一度も退院して自宅に帰ることなく死亡しました。
死亡診断書には、肺炎が直接死因と書かれていました。
怪我は骨折 死因は肺炎
実際の事案では、Zの過失(安全確保義務違反ないし注意義務違反)があったかどうかも争われていましたが、今回は、因果関係がテーマですので、過失は認められる前提で検討を進めます。
AがZの過失によって負った怪我は、右大腿骨頸部骨折です。しかし、Aの直接死因は肺炎です。果たして、Aは、Zの過失によって死亡したと言えるのか、これが因果関係の問題です。
個別の事案により判決は異なる
東京地裁平成15年3月20日判決は、まず、Aの事故後の経過について、次のように認定しました。
認められた事件経過
- Aは、事故で右大腿骨頸部骨折を負った後、ベッドに寝たきりの状態になり、食欲も低下してきて、肺炎を発症した。
- 治療で肺炎が改善しても、経口摂取を開始すると誤嚥性肺炎を繰り返して、徐々に全身機能が低下した。
- Aは、事故後、退院して自宅に帰ることもなく死亡した。
そのうえで、高齢者について、次のような事実が一般に認められると判示しました。
認められた事実
- 高齢者は、一般に、骨折による長期臥床により肺機能を低下させ、あるいは誤嚥を起こすことにより肺炎になることが多い。
- 肺炎を発症した場合、加齢に伴う免疫能の低下、骨折(特に大腿骨頸部骨折)、認知症などの状態にあると、予後不良(治療後の見通しが良くないこと)とされている。
これが、先ほど述べた廃用症候群に関する医学的知見です。
そして、廃用症候群に関する知見を前提にすると、高齢で認知症を煩っていたAが、大腿骨頸部骨折により寝たきりの状態が続き、肺炎を繰り返すようになって死亡したのは、Zの過失と因果関係があると認めました。
このように、介護事故では、高齢者の方ならではの身体状況も、因果関係、そして裁判の判決に関係してくるのです。
損害額と過失相殺
判決は、Zの過失とAの死亡との間に因果関係を認め、Yに損害賠償を命じました。
もっとも、Aの慰謝料については、Aの年齢や身体状況等を考慮したうえで、一般的な死亡慰謝料よりも低額の1,200万円とするのが相当だと判断しました。
また、転倒したのは、A自身の不注意による部分もあるとして、A側の過失を6割認め、YにはAに生じた損害の4割についてのみ、賠償を命じました。
二度目の骨折後に死亡したケース
もうひとつ、高齢者の大腿骨骨折に関連して、因果関係が争われた事例として、東京地裁平成16年3月31日判決を紹介します。
裁判の内容は、一回目の骨折の後、リハビリ中に転倒して、二度目の骨折を負い、二度目の骨折の手術中に急性循環不全で死亡したというもの。
一度目の骨折と二度目の骨折の間には因果関係があり、したがって、一回目の骨折と死亡との間にも因果関係があると認めました。

この判決も、大腿骨頸部を骨折した高齢者の死亡率が、一般の高齢者よりも高いことなど、大腿骨頸部骨折の高齢者に与える影響に関する知見について言及しています。
この判決では、死亡した高齢者の慰謝料は2,000万円(一般的な死亡慰謝料と同水準)としたうえで、転倒して骨折したのは当該高齢者の不注意もあったとして、4割の過失相殺を認めました。
個別の事案により判断は分かれる
直接の死因と骨折とが一見結びつかない例でも、裁判で因果関係が認められた事例をご紹介しました。
もっとも、実際には、因果関係の判断はそう簡単ではありません。個々の事例ごとに、骨折後にたどった症状経過、直接死因、死亡までの期間などはさまざまです。
裁判所の判断も個々の事案ごとに分かれるでしょう。
実は、上記の東京地裁の二例の判決の後、介護事故で因果関係の判断が微妙となる事案についての判例はあまり出ていません。
その原因は定かではありませんが因果関係の判断が微妙となる事案では、判決に至る前に、訴訟の途中の段階で和解が成立することが多いのではないかと推測します。
高齢者の介護事故の事案では、前記平成15年の東京地裁判決のように、被害者の年齢や身体状態を考慮して慰謝料自体を一般的な水準から下げたり、あるいは前記2つの判決のように被害者側の不注意を考慮して過失相殺されたりして、最終的な賠償額について一定の調整が行われているように見受けられます。
したがって、因果関係に争いがある状態でも、慰謝料の額や過失相殺等も考慮のうえで、ある程度のところで当事者間に賠償額についての合意が形成されるのではないかと思われます。
私自身の経験でも、骨折後の入院中に、骨折とは別の死因で死亡したケースで、やはり訴訟の途中で和解が成立したことがあります。
最後に一言
今回は、大腿骨頸部骨折の後、間もなく肺炎で死亡した事例をもとに、因果関係が認められるかどうかを検討しました。
次回以降も、具体的な事故類型・ケースをもとに、検討していきたいと思います。