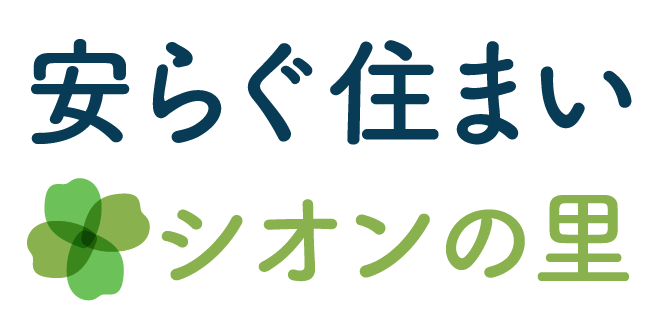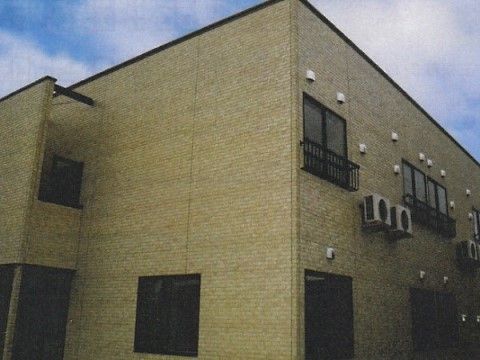ブドウ球菌感染症(MRSA)でも入居可能な施設特集
ブドウ球菌感染症(MRSA)は予防対策の徹底が重要

感染症の中でも、免疫力が低下している高齢者にとって注意しなければいけないのが、3人から5人に1人の身体にあると言われているブドウ球菌による感染症。糖尿病やガンなどの持病や老化による免疫力の低下などによって感染症状を発症することがあります。ときには命の危険にもつながりかねないブドウ球菌感染症の予防は高齢者施設でも大きな課題。感染症対策にしっかり取り組んでいる施設を選ぶことが大切です。医療ケアが充実している施設であれば、併せて処置に使った医療器具などの管理がしっかりされているかどうかも大切なポイントです。
MRSAでも老人ホーム選びは難しくない!?
MRSA(Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus:メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)という言葉、普段からあまり耳にすることがありません。これは一体どういう病気なのでしょうか?
ここで問題になるのは、普通の黄色ブドウ球菌ではなく、メチシリンとよばれる抗生物質に耐性のある黄色ブドウ球菌、MRSAです。抗生剤への耐性があるという面以外は、黄色ブドウ球菌と同じものです。この菌は私たちの身近にあるもので、空気中に存在するのはもちろん、人間の皮膚、髪の毛、傷口、口の中、鼻の粘膜などにも付着しています。ただ黄色ブドウ球菌の毒素はそれほど強いものではないため、口に中や鼻の粘膜にあっても健康な人の場合は大きな問題とはならず、自然に体外に排出されます。
ところが大手術の後で体の抵抗力が著しく低下している、抗がん剤を使用している、血管内や膀胱などにカテーテルが挿入されている患者の場合、MRSAに感染するとペニシリンやメチシリンなどの抗生剤が一切効かないため治療に時間がかかり、患者が重症化して死にいたる事例も少なくありません。健康な人にとってMRSAはとくに怖い存在ではないのですが、免疫力の落ちた患者にとっては命取りになることも。
MRSAが問題になるのは主に病院内になります。大きな手術を受けた患者や重症レベルの火傷(やけど)、抗がん剤を使用してがん治療をしている患者は、通常、老人ホームに入所することはありません。問題になるのは尿カテーテル・尿バルーンを挿入している高齢者、中心静脈栄養(IVH)の高齢者になります。カテーテル内にメチシリン耐性のある黄色ブドウ球菌が侵入してくると、高度な医療ケアが必要になります。老人ホームにこれらの患者が入院しているときは、普段と違う症状はないか、よく観察・確認しなければなりません。
一見すると怖いMRSAですが、老人ホームに入所している高齢者についてはそれほど心配する必要はありません。「無菌室にいなければならないくらい抵抗力が落ちている方」はほとんどいませんので、MRSAが口腔内や鼻の粘膜、皮膚に付着していても大きなトラブルにはなりません。MRSAが体についた状態を「保菌」とよびますが、菌をもっているからと言って、すぐに敗血症や髄膜炎、肺炎、腸炎、骨髄炎になるわけではないのです。健康な人にとってMRSAは、特別怖い細菌ではない、ということをご理解いただきたいと思います。
みんなの介護では、MRSAに対応できる老人ホームが2,060か所紹介されています。全体の施設掲載数が約9,000か所なので、約22%の老人ホームでMRSAに対応できることになります。
ブドウ球菌感染症(MRSA)とは?
前項でも触れましたがMRSAとは、メチシリンとよばれる抗生物質に耐性をもった黄色ブドウ球菌のことです。つまりMRSAは黄色ブドウ球菌の一種です。黄色ブドウ球菌の大きさは1000分の1ミリ、人の目にはみえません。小さな丸い球状の細菌で、名前のとおりブドウの房のようにつらなっていることから「ブドウ球菌」と命名されています。特殊な細菌ではなく、どこにでも見られるものです。人間の皮膚や口腔内、のど、乳腺内、傷口などに存在しています。黄色ブドウ球菌は増殖するさいに「エンテロトキシン」とよばれる毒素をつくりだし、この毒素が食中毒を発生させます。
MRSAは通常の黄色ブドウ球菌の特徴にくわえ、メチシリンやペニシリンといった抗生剤では除菌できない特性をもっています。黄色ブドウ球菌だけではありませんが、細菌の細胞内には代謝酵素があり、抗生剤を体内で分解し無効化させる力をもった細菌が出現すると、その遺伝子がほかの細菌に広がることで「特定の抗生剤で駆逐されない耐性型の細菌」が登場することとなります。MRSAも特定の抗生剤に耐性をもつ細菌です。
このように聞くと「なんだか怖い細菌」と感じてしまいますが、メチシリンに耐性をもっていても、通常の黄色ブドウ球菌と同じく、丁寧な手指の消毒が有効です。アルコール消毒も加えればさらに効果的ですが、アルコールで手指が荒れる場合は手洗いだけでも十分です。
このMRSAの感染経路は「接触感染」となっており、医療従事者や介護スタッフの手を介して菌が広がっていきます。そのためMRSA保菌者の介護をしたときは、その後、手指を入念に洗って菌を完全に除去します。老人ホームでは同じ施設のなかに多くの入居者や介護スタッフがあつまっているため、MRSAに限らず感染防止のためのケアは必須です。感染対策には十分な対策がおこなわれています。
MRSAが問題になるケースはほとんどが病院内です。MRSAは極端に体力・免疫力の衰えた方や、大きな手術を受けた直後、免疫疾患にかかっている方、抗がん剤を投与されている方にとってMRSAは怖い細菌です。敗血症や肺炎、腹膜炎、髄膜炎を起こす原因になりますし、抗生剤が効かないことから命にかかわることも。ところが健康な方にとって、MRSAはとくに問題にはなりません。皮膚や口のなかに入っても、常在菌のはたらきで自然に排出されます。尿カテーテルや静脈中心栄養の患者がいない老人ホームでは、MRSAに対して必要以上に警戒し、過剰反応する必要はありません。
MRSA感染者を介護するときのポイント
老人ホームでMRSA感染者を介護するときのポイントですが、MRSAは接触感染によって細菌が拡大しますので、介護ケアをおこなった後にはかならず手指をしっかりと洗うことが重要ですね。しっかりとした手洗いや消毒は、MRSA感染者の有無にかかわらず徹底しておこないます。
老人ホーム内にMRSA感染者がいる場合も洗濯ものの取り扱いですが、汚れがひどい、汚物がついているということがなければ、通常の洗濯・乾燥で十分です。漂白剤の使用が可能であればその方がさらに安心ですが、必須ではありません。MRSAは水や洗剤で洗うことにより除去できるため、特殊な洗剤や洗浄方法などはとくに必要ありません。
老人ホーム内で使用する食器ですが、とくに感染者の使用する食器を分ける必要はありません。感染者が食器を使用することでMRSAが付着したとしても、その後食器を洗浄することで菌を洗い流せるため、とくに問題はありません。入浴に関してもそれほど神経質になる必要はありませんが、感染者の体にキズがある、尿などでお湯がMRSAに汚染されるおそれがある場合は最後に入浴してもらいます。老人ホームによっては、MRSA感染者は最後に入浴してもらう施設も。各施設によって対応には違いがあります。
MRSA感染者の介護をおこなうときは、細菌を介護者の体内にいれないためにマスクは必須です。特殊なガウンを着用する必要はありません。老人ホームの場合、高齢者が集団生活していることから細菌が広がることをおそれ、過剰反応する可能性があります。感染者を隔離したり入所を断るなどの対応は過剰反応と言えますが、MRSA感染者が認知症を発症し、不潔な行為をする場合は入所を断られるケースも…。MRSA感染者が老人ホームへの入所を希望する場合は、感染の有無だけではなく、入所希望者の詳しい状態もまじえて、入所できるかどうかを判断することになります。