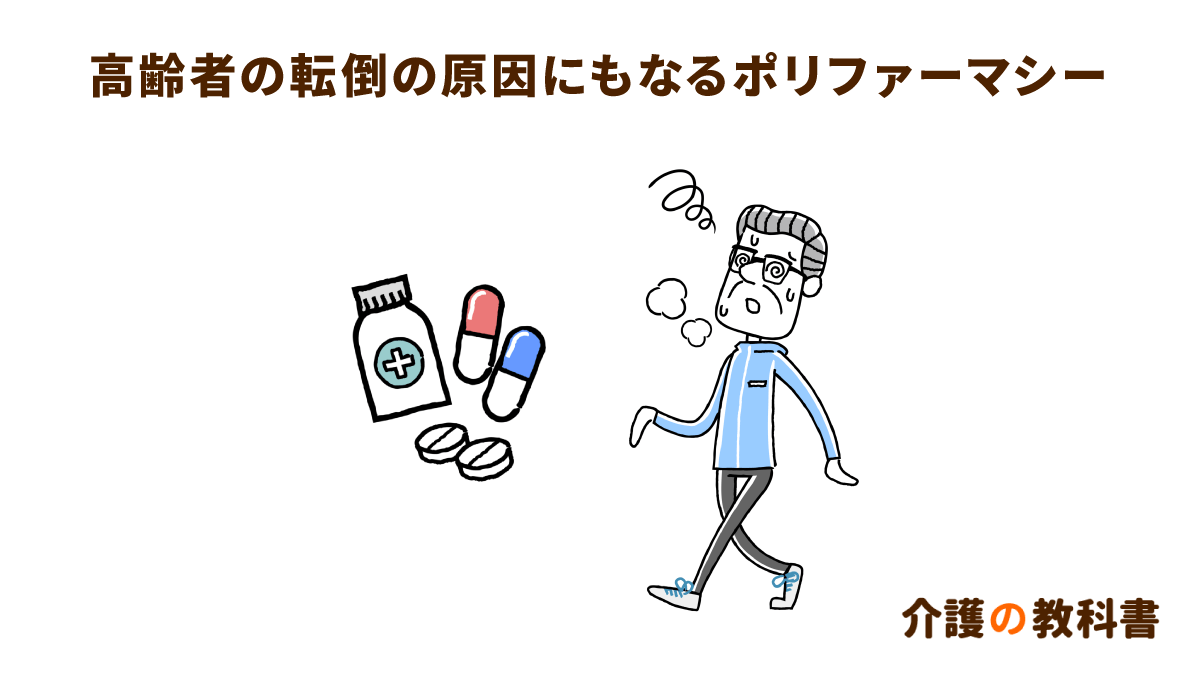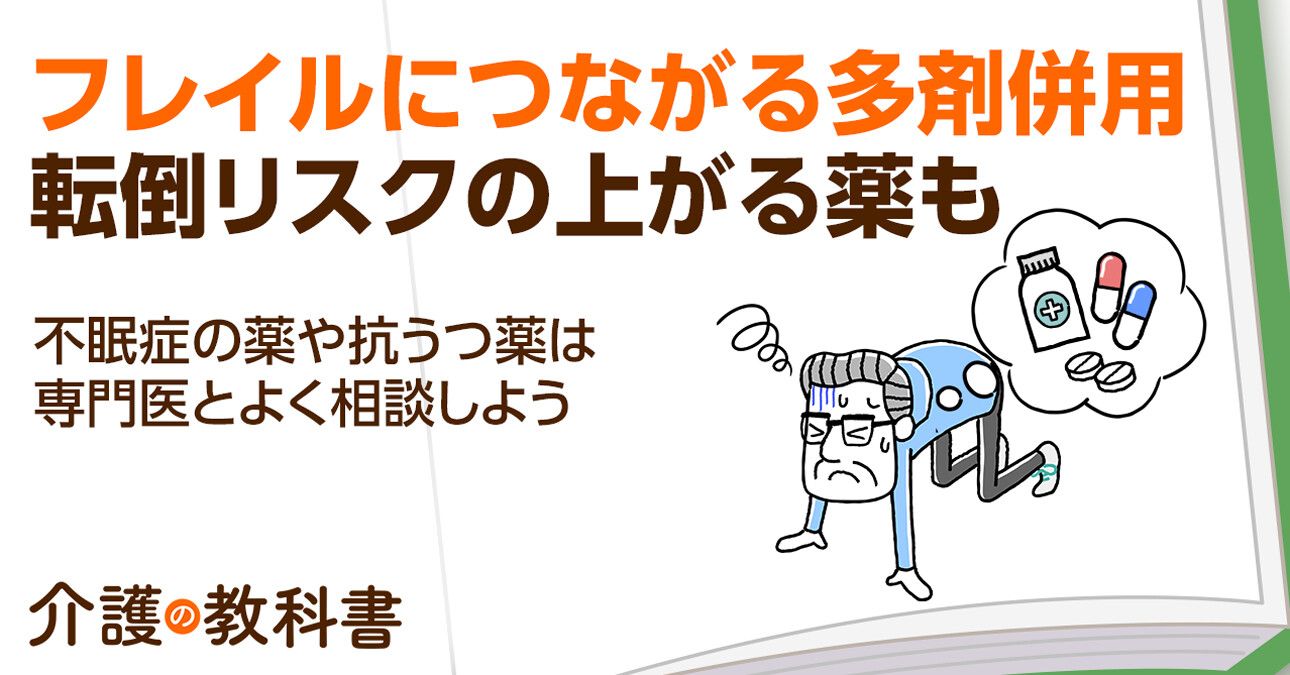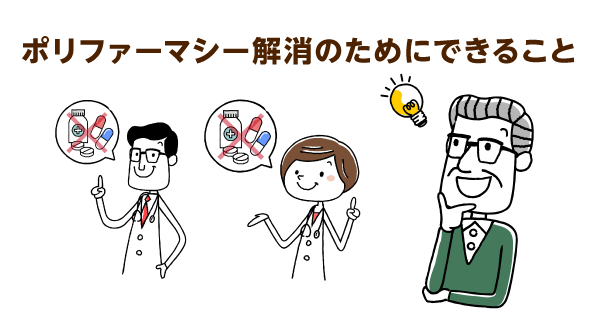高齢になると複数の持病を抱える人が増加します。70歳以上の高齢者は平均6種類以上の薬を服用し、75歳以上では約4人に1人が平均7種類以上の薬を使用していると報告されています。
薬が増えて問題となるのが副作用の発現です。副作用はたった一剤の服用でも発現することがあり、薬の数が増えるほど副作用も起こりやすい傾向があります。5~6種類以上の服用によって、害をもたらす多剤併用を「ポリファーマシー」と呼びます。そこで今回は、ポリファーマシーと、その影響による転倒リスクを解説いたします。
ポリファーマシーで起きやすい副作用
体内に入った薬は、肝臓や腎臓で代謝して排泄されます。高齢者は肝機能や腎機能が低下していることが多く、一般成人より代謝や排泄に時間がかかります。薬が体内に留まる時間が長くなると副作用が発現しやすくなります。そのため、高齢者はポリファーマシーについて特に注意が必要となります。
高齢者に起こりやすい副作用は、ふらつき・転倒、物忘れです。特にふらつき・転倒は、5つ以上の薬を使う高齢者の4割以上に起きているという報告もあります。また、転倒による骨折をきっかけとして、寝たきりになったり、要介護状態になったり、寝たきりが認知症を発症する原因となったりすることもあります。そのほかに、うつ、せん妄(頭が混乱して興奮したり、ぼーっとしたりする症状)、食欲低下、便秘、排尿障がいなどが起こりやすくなります。
高齢者は複数の診療科を受診していることが多く、それぞれの医師からは少量の薬しか処方されていなくても、それらが合わさると結果的にポリファーマシーとなってしまうことがよくあります。お薬手帳を使用していなかったり、かかりつけ薬局がなかったりすると、医師や薬剤師がほかの診療科で処方されている薬の内容を把握できず、ポリファーマシーに気づくことが遅れてしまうことがあるので、注意しなければなりません。

自己判断で服用を中止するのは危険
高齢者は薬による副作用を起こしやすいため、できれば使用を控えたい薬があります。日本老年医学会では「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」において、75歳以上の人や75歳未満で介護を受けている人、要介護になる少し手前の人を対象に、「特に慎重な投与を要する薬物」を発表しました。
例えば、認知機能低下を引き起こす可能性の高い薬として、「三環系抗うつ薬」や「H2受容体拮抗薬(胃薬)」などが挙げられます。また、転倒・骨折を引き起こす可能性の高い薬として「睡眠薬」「α遮断薬(高血圧の薬)」などです。そのほかにも便秘の副作用を引き起こす可能性の高い「糖尿病薬」や、「過活動膀胱治療薬」などがリストアップされています。
一つ注意していただきたいのは、ここにリストアップされている薬を現在服用しているからといって、ただちに服用を中止すべきではないということです。
このガイドラインが発表された後、週刊誌などで「飲むと危険な薬」や「使ったら認知症になる薬」のような過激な表現で報道されてしまい、それを読んだ人が自己判断で服用を中止したことで、かえって健康被害を被ってしまうということがありました。このリストに掲載されている薬はあくまでも、専門家の管理下のもとで慎重に投与する薬のリストであり、ただちに服用を中止すべき薬のリストではないという点をご留意ください。
定期的に服用している薬を見直そう
しかし、副作用を最小限に抑えるには、使用する薬を減らすことには変わりありません。
これまでに、副作用が起きやすくなるのは、薬の種類が増えるからという話をさせていただきました。必要な薬を服用し続けながらも、皆さんが服用している薬が本当に今も必要な薬かどうか、定期的に見直すことが大切です。
痛みのあるときに処方してもらった痛み止めを、症状が改善してもなお飲み続けていませんか?花粉症の季節に出たアレルギーの薬を年間通じて飲み続けていませんか?
症状が改善したときは、改善した旨を医師や薬剤師に伝えて処方を止めることが可能かもしれません。使う薬の種類が減れば、副作用の発現頻度を減らすことにつながります。

一度処方された薬だからといって、ずっと服用し続ける必要のある薬ばかりではありませんので、定期的に今使っている薬を再検討してみましょう。ご自身で難しいときには医師、薬剤師と一緒に症状と使用している薬を照らし合わせて確認すると良いと思います。