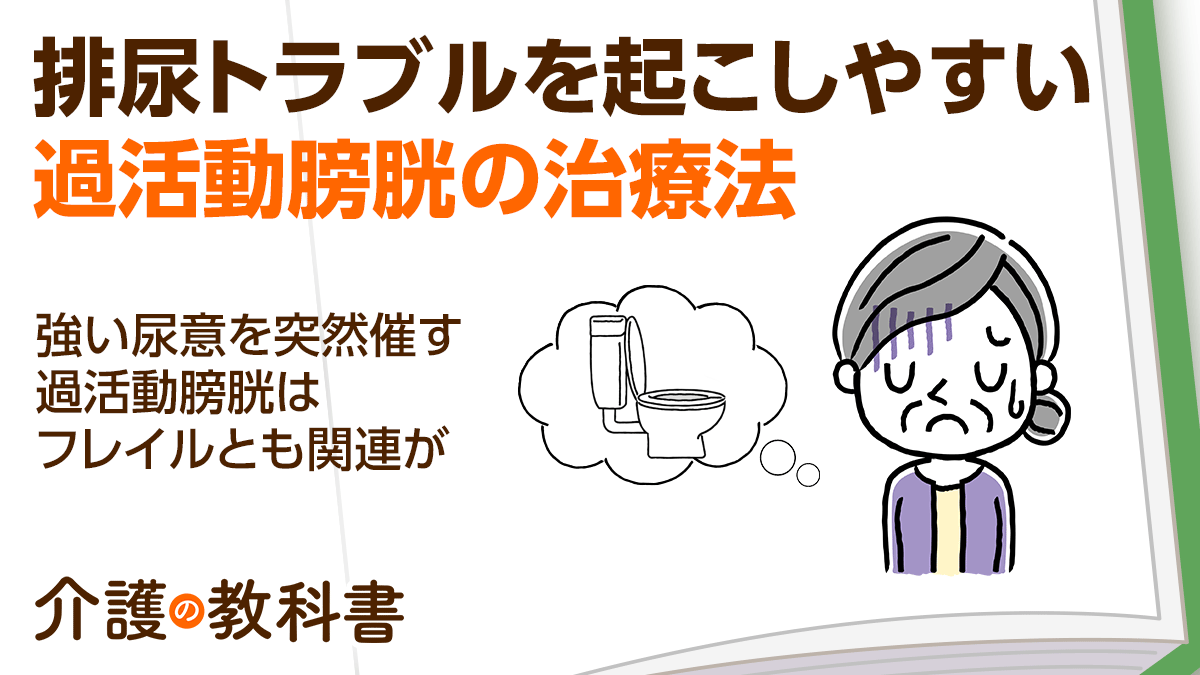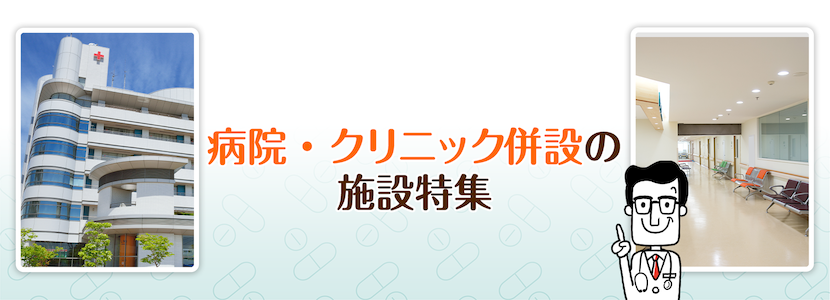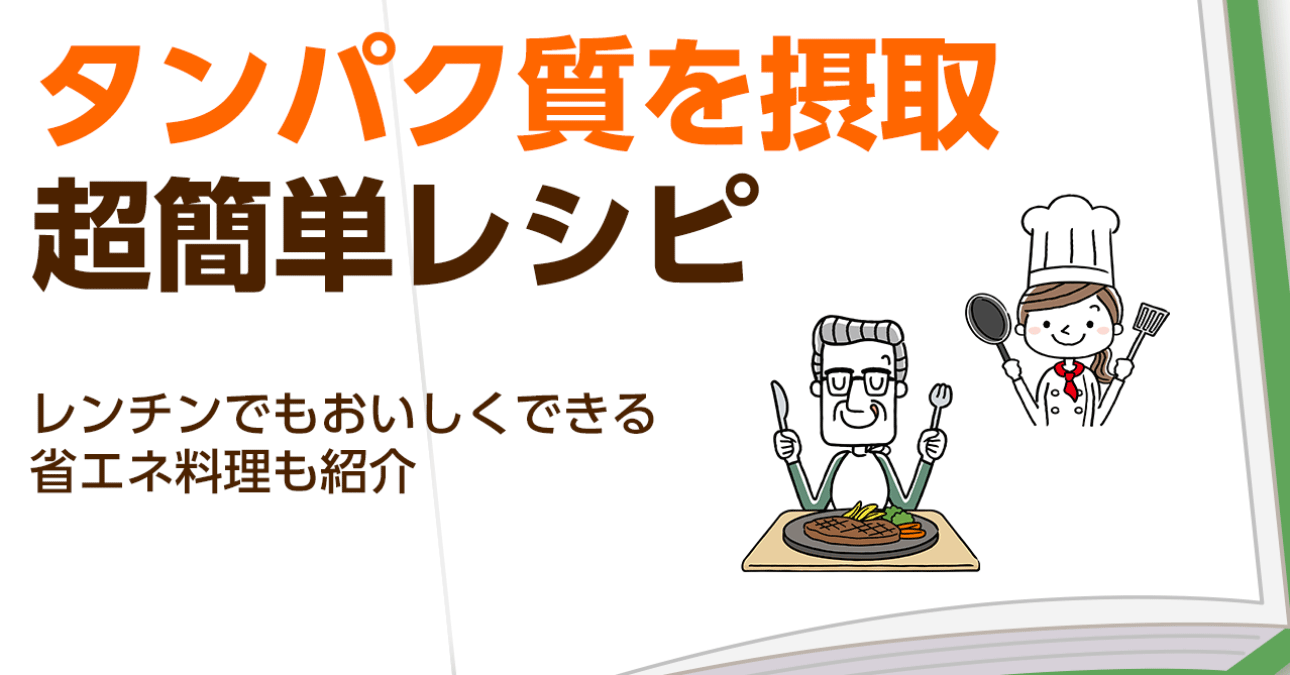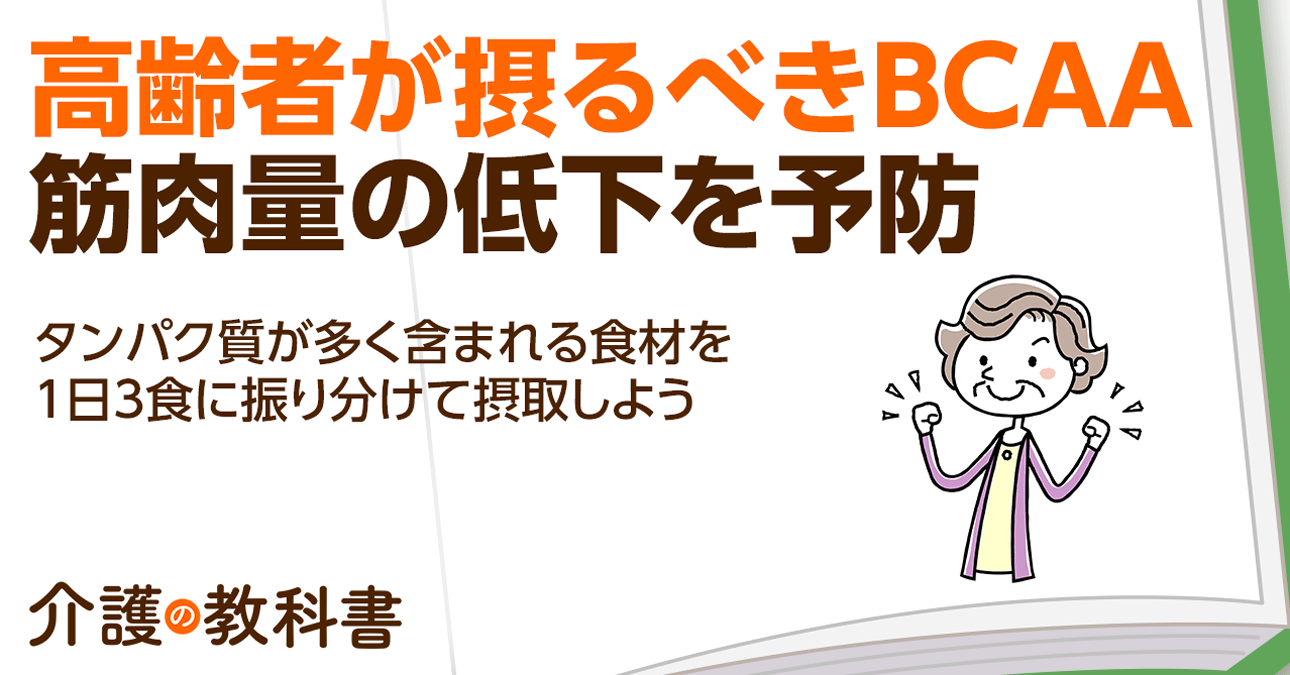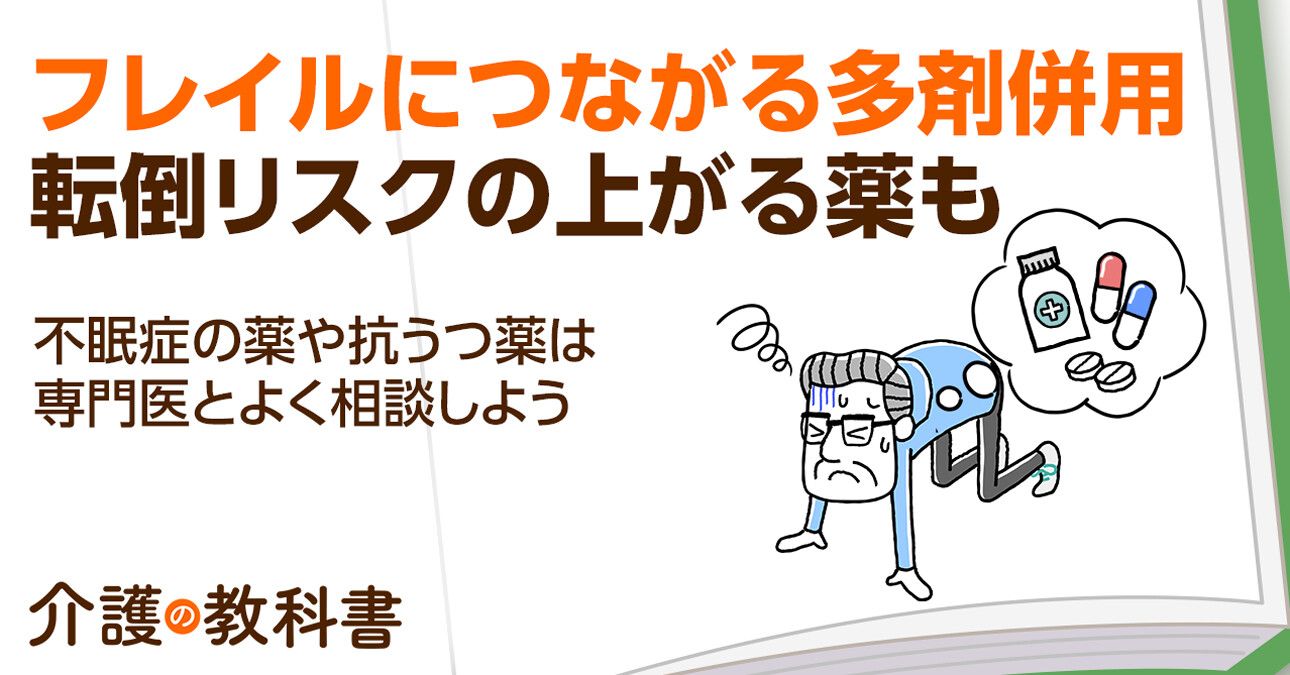年を重ねるにつれて「トイレが近くなる」、あるいは「急に我慢できない尿意を感じる」といった、排尿に関する健康問題が起こりやすくなります。
通常の尿意とは明らかに異なる突然の強い尿意で、日常生活に支障をきたしている状態を過活動膀胱と呼びます。
また、加齢によって筋力や体力、認知機能などの低下を招き、病気とは言えないまでも心と体に衰えが生じることもあるでしょう。このように心身が衰えた状態をフレイルと呼びますが、最近ではフレイルと過活動膀胱の関連性に注目が集まっています。
この記事では、過活動膀胱の原因やフレイルとの関連性を解説したうえで、過活動膀胱の診療方針を定めたガイドラインの改訂動向や、その治療薬をご紹介します。
過活動膀胱の特徴と原因
過活動膀胱は、「急に我慢できない尿意」があり、その尿意が「通常の尿意とは明らかに異なる」場合に診断される病気です。「トイレが近くなる」といった症状を伴うことが多く、寝ている間にトイレに起きてしまい、睡眠が妨げられることも少なくありません。
日本排尿機能学会が行った調査では、40歳以上の日本人の12.4%が過活動膀胱を患っていると報告されており、その実数は810万人と推定されています。
この調査ではまた、年齢が上がるとともに過活動膀胱を患う人が増えることも報告されており、80歳以上の37%が過活動膀胱を患っていると見積もられています。
過活動膀胱を発症する原因は一つではなく、脳梗塞、認知症、パーキンソン病などの脳神経の病気や、加齢による膀胱機能の変化、骨盤の底に位置する筋肉(骨盤底筋)の弱体化、女性ではホルモンバランスの変化も原因になり得ると考えられています。
フレイルと評価のための基準
歳を重ねると、病気とは言えないまでも、さまざまな体の機能が衰えていきます。運動機能が衰えてしまうと、外出をする機会も減っていくことでしょう。人と接する機会も減ってしまうかもしれません。
このような状態が長く続くと、次第に心の状態や認知機能も衰え、体力のみならず気力も低下してしまう(フレイル)こともあり得ます。
フレイルが病気とは異なる点が、適切な生活支援や介護支援により、生活を維持する能力の改善が期待できることです。
フレイルは、完全に介護に依存しなければ生活できない状態と、健康な状態の中間点にあるともいえ、高齢化が進む現代社会においては、フレイルを早期に発見し、適切な治療や予防をすることが重要だと考えられています。
米国の老年医学専門医であるリンダ・フリードは、フレイル状態になると次のような要素が目立つようになるとしました。
- 体の縮み
- 疲れやすさ
- 活動の少なさ
- 動作の鈍さ
- 弱々しさ
フリードらが提唱したフレイルの基準は、国際的にも広く採用されており、次の5項目中3項目に該当するとフレイル、1~2項目に該当した場合はプレフレイル(フレイルの手前の状態)、いずれも該当しない場合は健常と判断されます。
フリードらが提唱するフレイルの基準
- 意図しない体重減少
- 何をするのも面倒だと感じる(主観的な疲労感)
- 歩行速度の低下
- 握力の低下
- 身体活動量の低下
また、日本疫学会誌に掲載された2017年の論文によれば、65歳以上の高齢者において、7.4%がフレイルに、48.1%がプレフレイルに該当すると報告されています。
高齢者の2人に1人がプレフレイル、つまりフレイルになりやすい人である可能性が示されているのです。
過活動膀胱とフレイルの関連性
フレイルの状態だと、さまざまな病状の悪化につながることが知られています。例えば、心不全を患っている高齢者は、フレイル状態にない人と比べて、フレイル状態にある人の方が心不全に関連した死亡リスクや入院リスクの増加が報告されています。
また、さらには、65歳以上の日本人高齢者2,953人を対象とした研究で以下のようなことがわかりました。
| フレイルの状態 | 過活動膀胱を患っていた割合 |
|---|---|
| あり | 34.3% |
| なし | 16.5% |
つまり、過活動膀胱と診断される人はフレイル状態にある可能性が高いことが示されています。
また、65歳以上の1,363人を調査した米国の研究では、過活動膀胱を患っている人は患っていない人に比べて、日常生活における基本的な動作が鈍い可能性を報告していました。
もちろん、過活動膀胱がフレイルをもたらす直接的な原因というわけではありませんし、フレイルだからといって必ずしも過活動膀胱になってしまうわけではありません。
しかし、両者の間には密接な関連性があることが、研究データによって明らかにされつつあるのです。
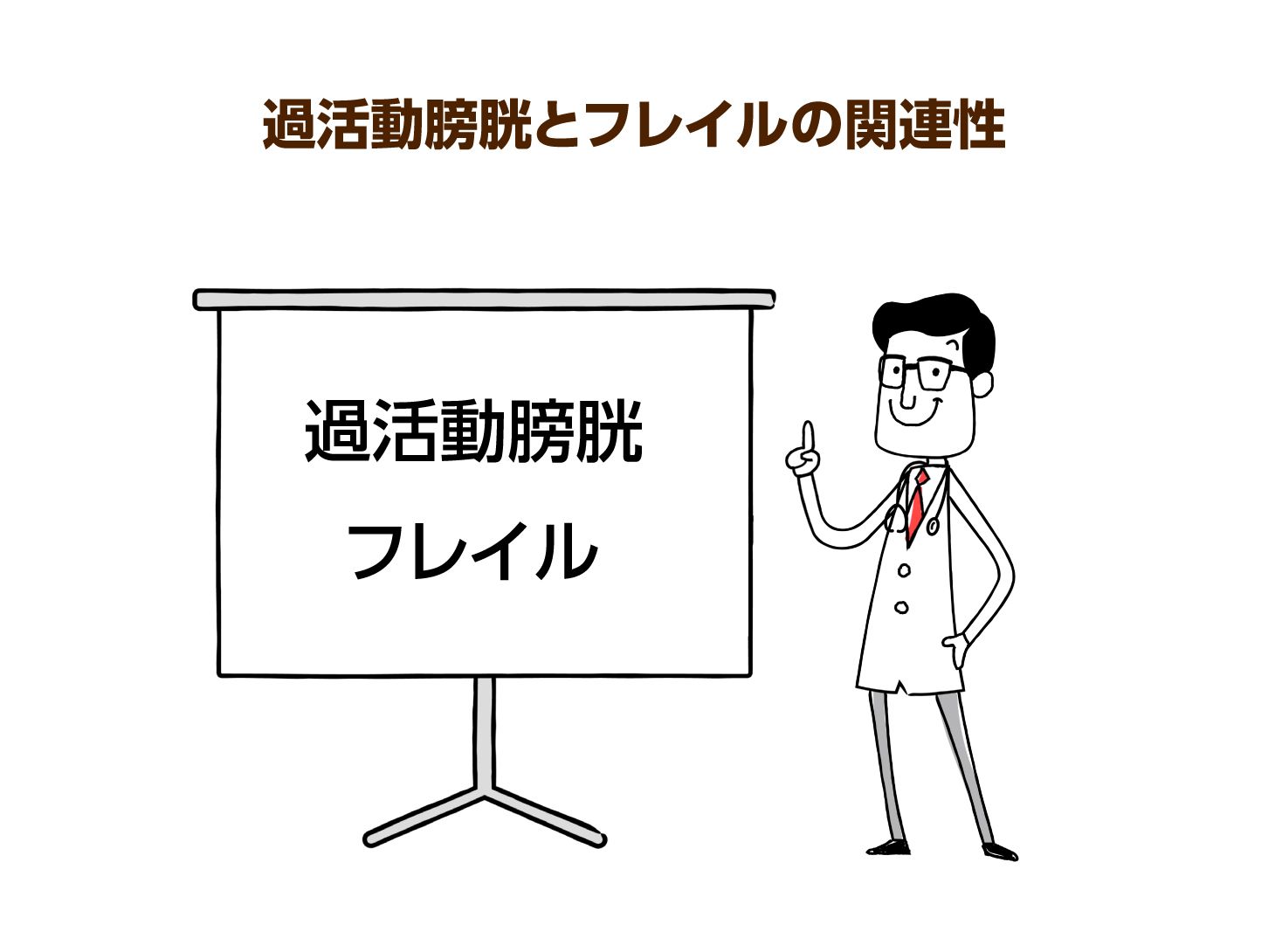
過活動膀胱に関する診療ガイドラインの改訂
フレイルと過活動膀胱の関連性が明らかになってきた背景を受け、日本サルコペニア・フレイル学会と国立長寿医療研究センターは、2021年4月に「フレイル高齢者・認知機能低下高齢者の下部尿路機能障害に対する診療ガイドライン2021」を公開しました。
診療ガイドラインとは、病気の予防や診断、治療法などに関する最新の科学的根拠や手順を、医療従事者向けにまとめた指針のことです。また、下部尿路機能障がいとは排尿に関連した健康問題の総称で、当然ながら過活動膀胱も含まれます。
上記ガイドラインでも、過活動膀胱とフレイルに関連性に注目し、フレイルと評価された高齢者に対して、積極的に排尿トラブルの有無を確認するよう推奨しています。
2022年9月に改定された、日本排尿機能学会および日本泌尿器学会の「過活動膀胱診療ガイドライン 第3版」では、フレイル状態にある高齢者の排尿トラブルに関して、早期発見・早期治療に対する関心が、より高まっていくものと考えられます。
過活動膀胱の治療に用いられる薬と副作用
過活動膀胱の治療薬は、ムスカリン受容体拮抗薬とβ3受容体作動薬に分けることができます。主な治療薬は以下の通りです。
| 種類 | 薬名 |
|---|---|
| ムスカリン受容体拮抗薬 |
|
| β3受容体作動薬 |
|
過活動膀胱は、尿をためておく膀胱が収縮することによって、強い尿意をもたらします。膀胱が過剰に収縮(活動)してしまうことから過活動膀胱と呼ばれるのです。
ムスカリン受容体拮抗薬やβ3受容体作動薬は、膀胱が収縮する働きを弱めることで強い尿意を緩和します。
過活動膀胱の治療に広く用いられているムスカリン受容体拮抗薬は、頻尿症状に対する有効性に優れています。しかし、便秘やのどの渇きなどの副作用が出やすいことが知られています。
一方、β3受容体作動薬は、ムスカリン受容体拮抗薬特有の副作用が出ることはほとんどありません。ただし、患者さんが実感できる有効性については、ムスカリン受容体拮抗薬に劣る可能性を報告した研究もあります。
薬の副作用の出やすさや、過活動膀胱による排尿症状の度合いは人それぞれで異なります。そのため、自分の状態に適した薬を処方してもらえるよう医師の診察を受けることが大切です。
排尿トラブルでお困りの方は、かかりつけ医に相談してください。
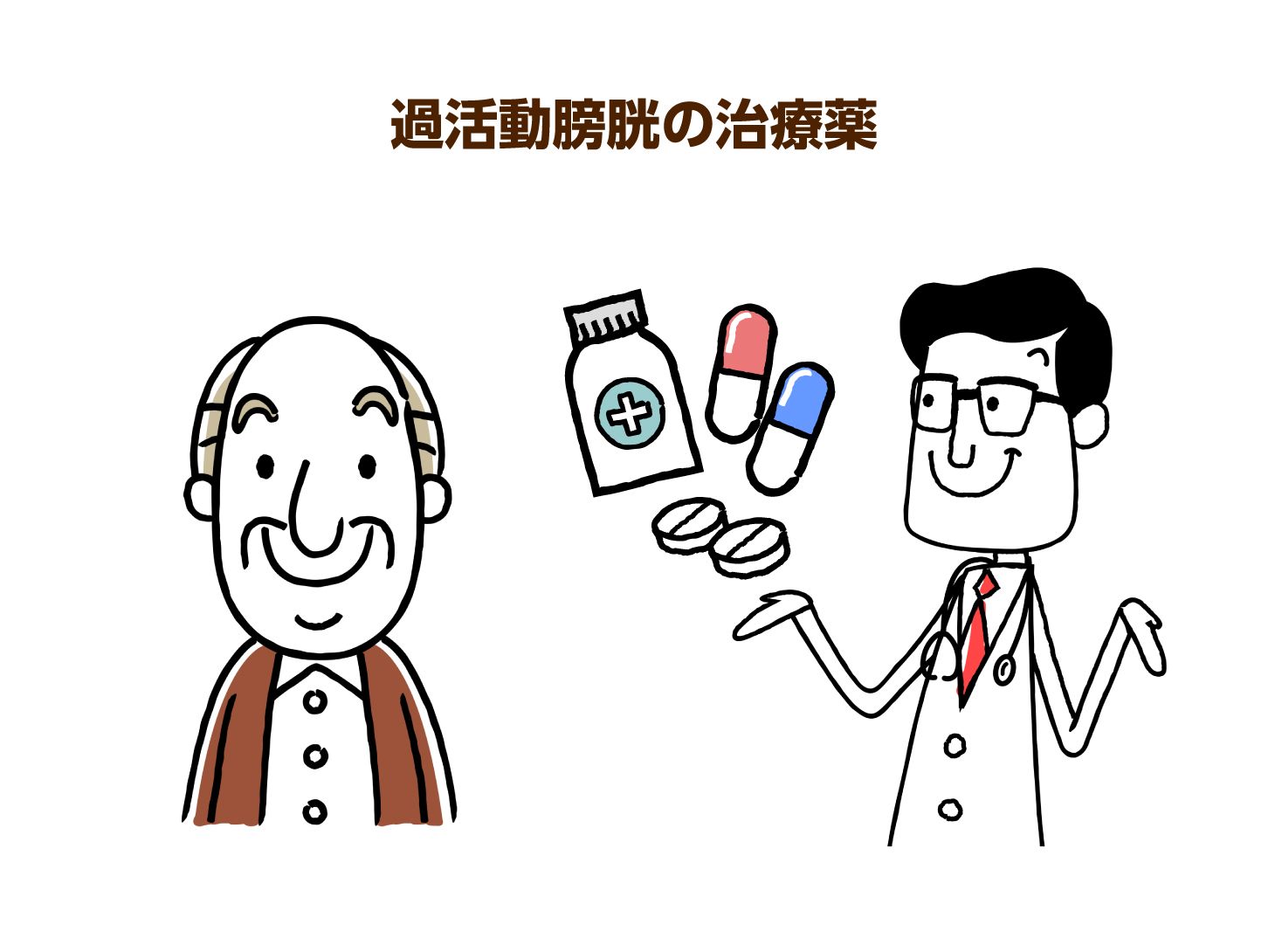
【参考文献】
BJU Int . 2005 Dec;96(9):1314-8.
日本老年医学会雑誌. 2022 年 59 巻 2 号 p. 115-130
Curr Urol. 2018 Mar;11(3):117-125
日本老年医学会 フレイルに関する日本老年医学会からのステートメント
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001 Mar;56(3):M146-56.
Clin Interv Aging. 2014 Mar 19;9:433-41.
J Epidemiol. 2017 Aug;27(8):347-353.
J Geriatr Cardiol. 2018 Nov;15(11):675-681.
Eur J Heart Fail 2016 Jul;18(7):869-75.
BMC Geriatr. 2022 Jan 21;22(1):68.
Urology 2017 Aug;106:26-31.
フレイル高齢者・認知機能低下高齢者の下部尿路機能障害に対する診療ガイドライン2021
過活動膀胱診療ガイドライン 第3版
Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jan 18;1:CD005429.
Low Urin Tract Symptoms. 2018 May;10(2):148-152.