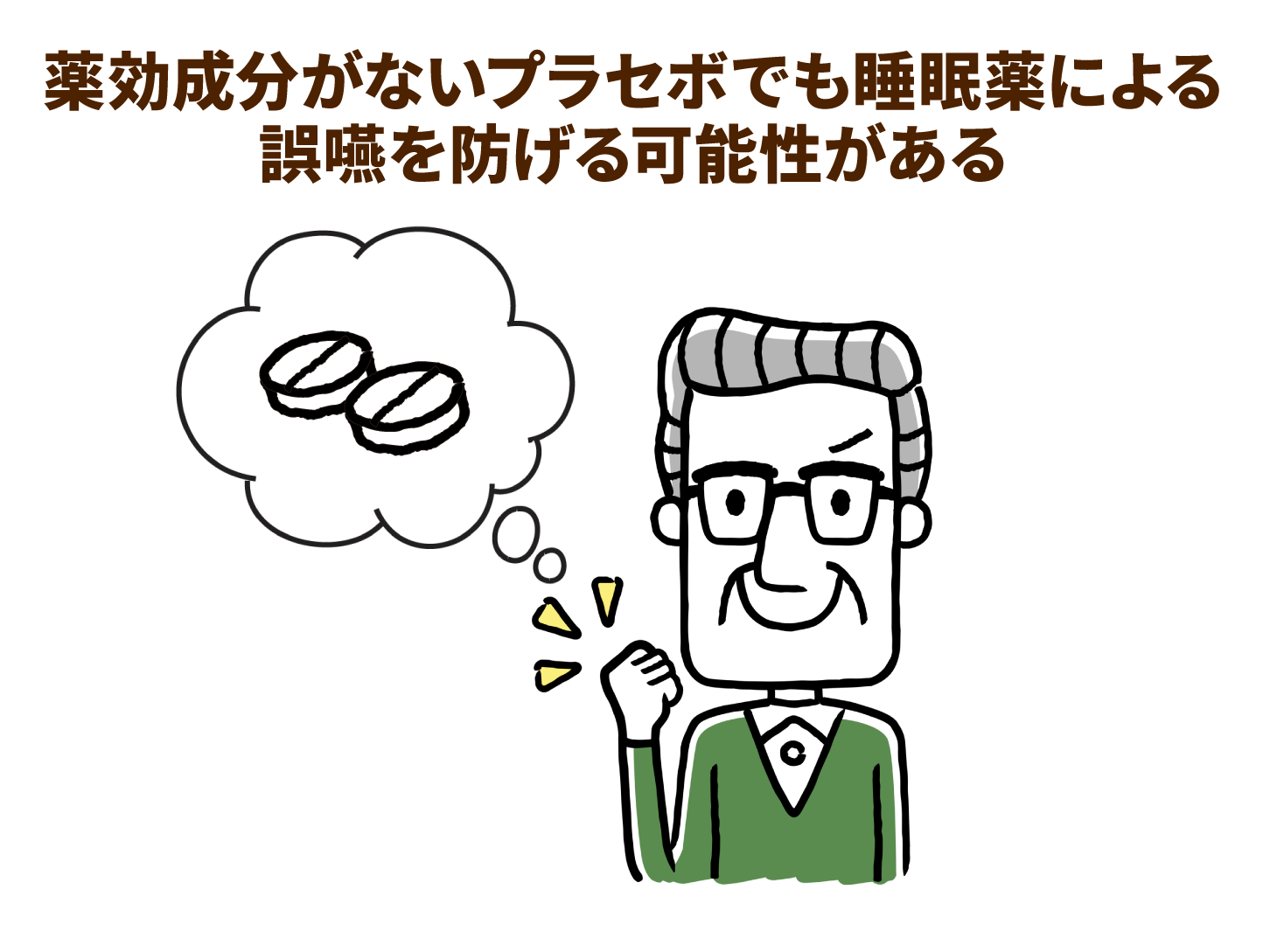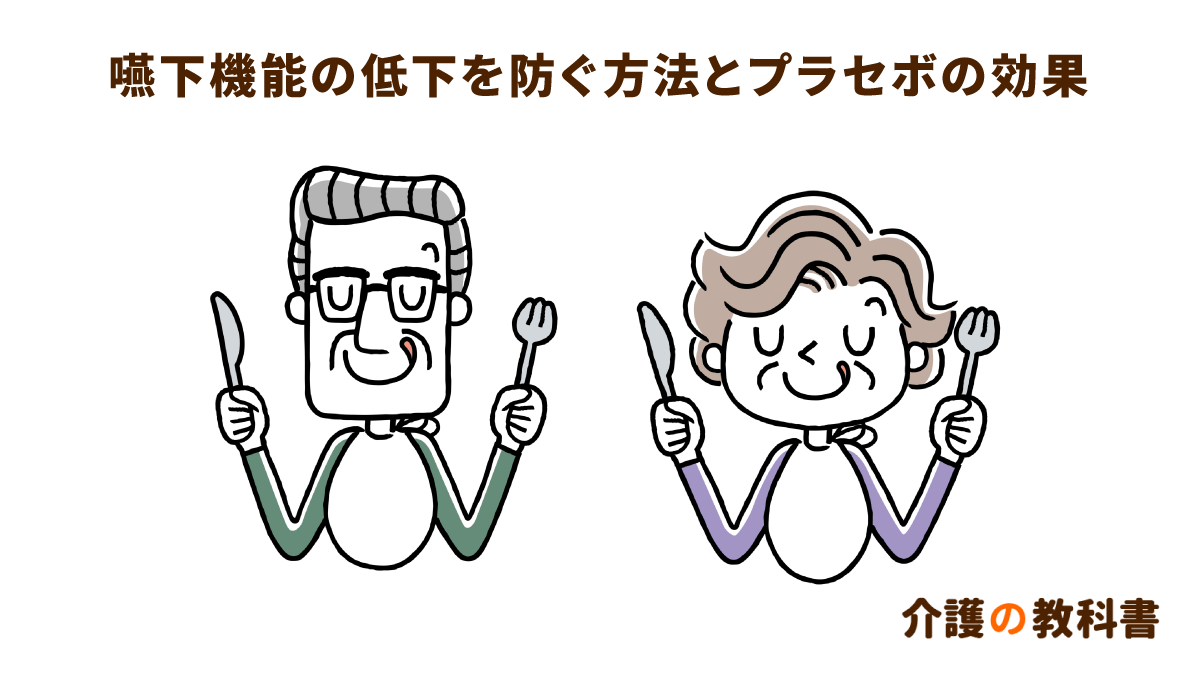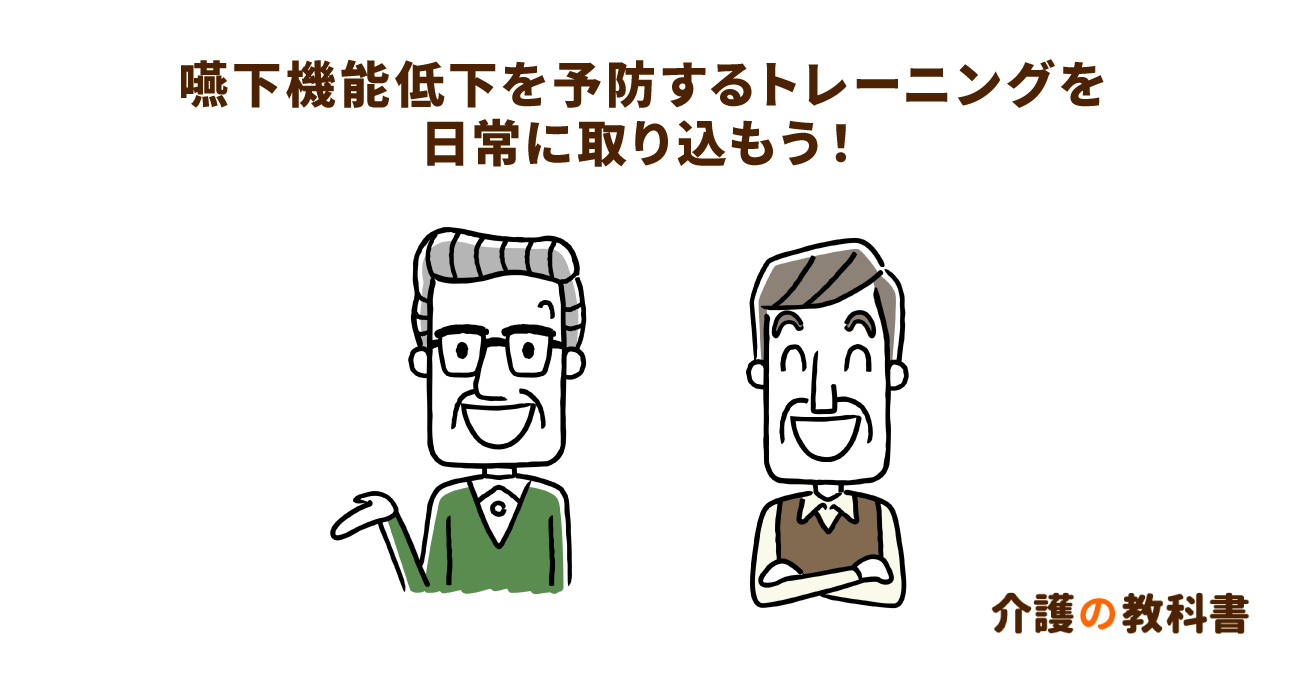私たちにとって、食事は生きるために必要な栄養素を取り入れるだけでなく、おいしさを感じたり、家族や社会とのつながりを深め、日常生活に豊かさをもたらしてくれます。しかし、歳を重ねるにつれて、食事をするという動作にも衰えが生じます。
高齢者は食べ物を胃の中に飲み込む嚥下機能が大きく低下します。嚥下が適切に行われず、食べ物が胃の中ではなく、肺に通じる気管に入ってしまうことを誤嚥と呼びます。
このような状態が繰り返されると、命にかかわる病状につながりかねません。そこで、改めて嚥下の仕組みや、誤嚥がもたらす健康への影響と対処法、プラセボ(偽薬)を用いた誤嚥予防の可能性について紹介します。
嚥下動作の5つのプロセスと誤嚥性肺炎
嚥下はさまざまな筋肉や神経が連携しながら、連続的に行われます。その過程は、一般的に5つの段階に分けられています。なお、口腔とは「口の中」、咽頭とは「喉の奥から胃の手前にある食道までの部分」を指します。
- 先行期:食べ物を認識して、口の中に入れるまでの段階
- 準備期:口に入れた食べ物を噛み、唾液と混ぜ合わせた食塊(しょっかい)を作る段階
- 口腔期:舌を使って食塊を喉の奥に運ぶ段階
- 咽頭期:食塊が喉の奥を通過し、食道に入る段階(嚥下反射)
- 食道期:食塊が胃へ運ばれる段階
食べ物が認識されると食欲を感じ、唾液が出たり、胃や腸の運動が活発になります。口に入れた食べ物は舌と歯によって噛み砕かれ、唾液と混ざり合いながら嚥下しやすい塊がつくられていきます。この塊を食塊と呼びます。
喉の奥に送られた食塊は1秒以内で咽頭を通過し、食道まで送られます。この一瞬の間に、咽頭から肺につながる気管が塞がり、食塊は胃へと続く食道を流れていきます。
この動作は「嚥下反射」と呼ばれ、人の意識ではコントロールできず、無意識に行われるものです。「ごっくん」と表現されるような食べ物を飲み込む動作を、自分の意識でコントロールすることは難しいものです。
嚥下反射は食べ物を食道に送り込む重要な働きを担っており、嚥下反射の能力は嚥下機能そのものといえます。嚥下機能が低下していると、嚥下反射がうまく働かず、食塊が気管に入ってしまい、誤嚥を引き起こします。
65歳以上の7~13%が、嚥下に障がいがあるといわれており、この割合は歳を重ねるとともに増加します。特に認知症やパーキンソン病などを患っている方では嚥下機能が大きく低下します。
健常者であれば、誤嚥が起こったとしても、せき込むことで気管に入り込んだ食塊が食道まで戻され、適切な嚥下が行われます。
しかし、嚥下機能が低下している高齢者は頻繁に誤嚥を起こしたり、せき込む力が弱いために、食塊や飲み物が気管や肺の内部に留まってしまうことがあります。このような状態が続くと、時に肺が炎症を起こしてしまいます。この肺炎を誤嚥性肺炎と呼びます。
一般的に肺炎は、ウイルスや細菌に感染することによって肺が炎症を起こした状態を指しますが、日本で行われた肺炎に関する調査では、高齢者肺炎のうち7割以上が誤嚥性肺炎だったと報告されています。嚥下機能が低下しやすい認知症やパーキンソン病、あるいは過去に脳卒中を起こしたことがある方では、誤嚥性肺炎の危険性が高くなるため注意が必要です。
高齢者が誤嚥性肺炎を発症すると、適切な治療を行っているにも関わらず、1~3割の方が亡くなってしまうという報告もあります。また、症状が回復した後も再発を繰り返しやすいのが誤嚥性肺炎の特徴です。そのため、嚥下機能が低下している方は、誤嚥に十分注意し、予防をすることが重要です。
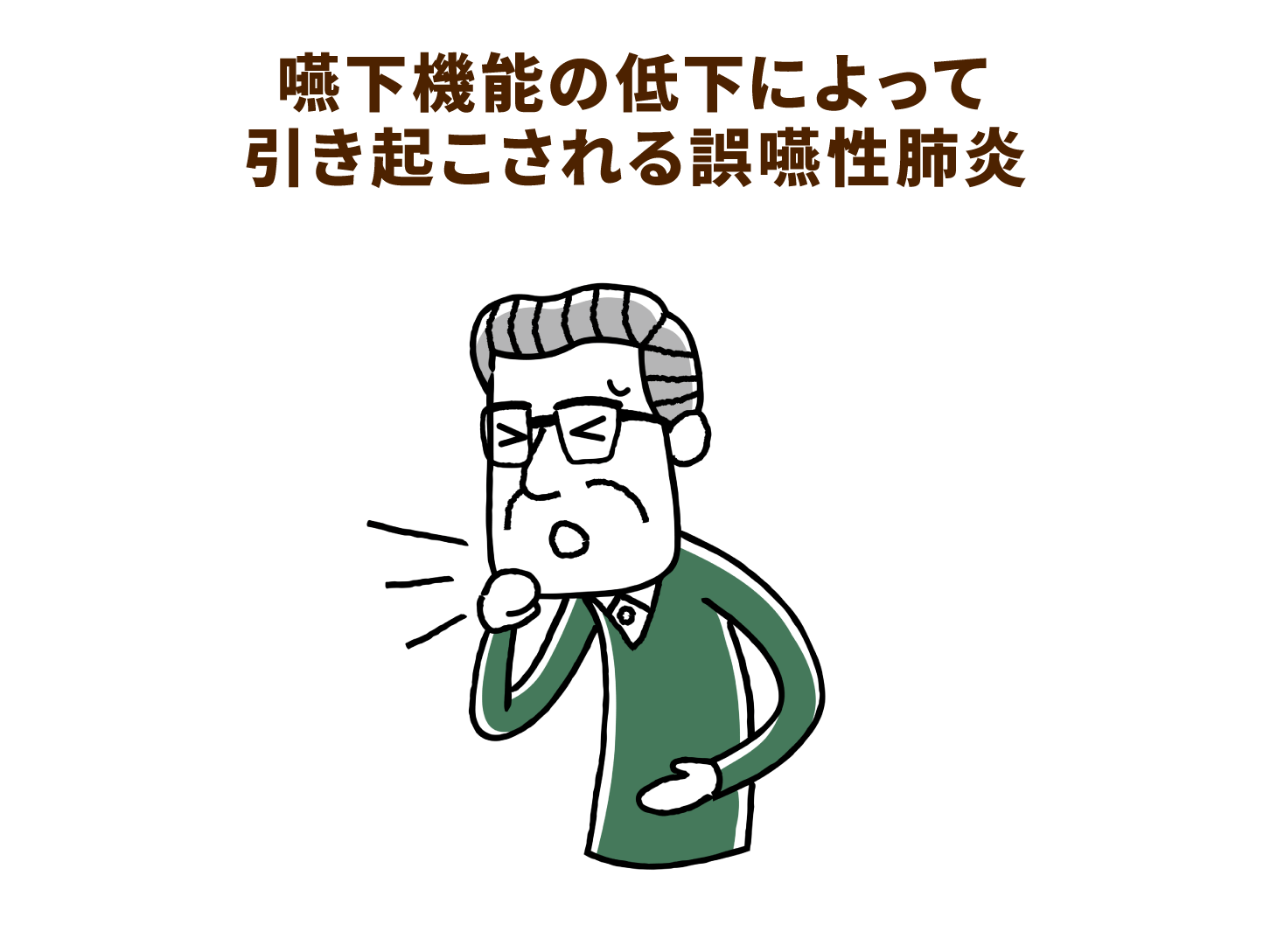
誤嚥を防ぐためにできること
嚥下機能に影響を及ぼす要因はさまざまです。認知症やパーキンソン病、脳卒中などの病状に加え、口の中の衛生状態や歯の本数、体の姿勢なども嚥下機能に影響していることが知られています。
75歳と80歳の日本人高齢者4,676人を対象に、嚥下に困難を引き起こす原因を調査した研究によれば、「入れ歯を適切に装着していない人」「喉が渇いている(口渇)状態」「口の中の衛生状態が悪い方」で嚥下が難しかったと報告されています。
適度な水分摂取、適切な入れ歯の装着、口の中を清潔に保つことが、誤嚥や誤嚥性肺炎の予防に効果的といえるでしょう。
また、寝たきりの方では誤嚥の危険性が高くなります。加えて食事中の姿勢は、口の中の舌に関する機能に影響を与えることが知られており、姿勢を適切に維持することも誤嚥予防に重要な要素です。
姿勢が悪い状態で食事をすれば、むせやすくなることは想像しやすいと思います。健常者186人の(平均32.7歳)を対象に、姿勢と嚥下しやすさの関連性を調査した研究では、背筋を伸ばして座った状態が最も嚥下しやすく、頭や首を曲げた状態、頭や首が後ろにのけぞった姿勢、仰向けに寝た状態では嚥下しにくいことが報告されています。
食事をする際には椅子に腰かけ、やや下にうつむき、顎を引いた姿勢が良いといえるでしょう。
車椅子を利用している方でも、基本的には身体をまっすぐにして、うつむき加減で食べると、誤嚥の予防に有効です。車椅子に腰かけても顎が上向きになってしまう場合は、背中にクッションを挟むようにすると良いでしょう。特に背中が丸くなっている方では、椅子に深く腰掛けてしまうと顎が上がってしまい、嚥下しづらくなってしまうので注意が必要です。
寝たきりで食事の介助を受けている方では、リクライニングベッドを使用し、食事の際に30~45度くらいまで持ち上げると良いでしょう。この状態で頭がベッドの先端にくるように移動し、顎を引いた姿勢で食事をしていただければ、誤嚥の危険性を大きく減らせます。
誤嚥性肺炎のもう一つの原因
薬の中には、眠気を催すことで嚥下反射を鈍くさせてしまったり、口の中を乾燥させてしまう働きがあるものも少なくありません。このような薬を長く服用していると、誤嚥の危険性を高めてしまう恐れもあります。
処方されている薬の数が多い状態をポリファーマシ―と呼びますが、薬の数が増えれば、嚥下機能に影響を及ぼす薬が処方される可能性も高まります。60歳以上の高齢者1,138人(平均74.1歳)を対象とした海外の調査によれば、薬の数と嚥下障がいに関連性を認めることが報告されています。
一方で、加齢とともに処方される薬の数は増加します。歳を重ねるにつれて患う病気も増え、それぞれの症状に対して治療薬が追加されるためです。したがって、薬が多いことが誤嚥の危険性を高めているのか、誤嚥しやすい人で薬をたくさん飲んでいる人が多いのか、その判別は困難だといわざるを得ません。
実際、34種類の薬と誤嚥の関連性を調査した研究によると、多くの薬は誤嚥の危険性と関連するものではありませんでした。しかし、この研究ではベンゾジアゼピンと呼ばれる睡眠薬が誤嚥と関連していることがわかりました。
ただ、寝つけないことや、寝ている途中で目が覚めてしまう睡眠障がいは、生活の質を低下させる大きな原因になります。そのため、誤嚥の危険性があるからといって、安易に睡眠薬の服用を中止したり、服用量を減らせるものではありません。
また、睡眠薬は適切な方法で中止や減量をしないと、不安や不眠などの症状(離脱症状)が現れることもあります。
誤嚥予防にプラセボは効果的か
プラセボとは、見かけは本物の薬ですが薬効成分の入っていない偽薬のことです。薬効成分が入っていないため、本来はプラセボを服用しても有効性は期待できません。しかし、実際には何らかの効果が得られることが多く、これをプラセボ効果と呼びます。プラセボは「プラセプラス」の商品名で市販されており、実際に購入することもできます。
これまでに報告されている不眠症の治療薬に関する研究では、プラセボによる治療でも不眠症状の改善が報告されています。一般的にはプラセボを本物の薬と思い込むことによって、プラセボ効果が得られると考えられますが、プラセボとわかってプラセボを飲んでも、不眠症状が改善したという研究報告もあります。
当然ながら、プラセボには副作用の危険性はほとんどありません。そのため嚥下機能に与える影響も少ないと考えられます。
「薬の服用」に伴う安心感や不安の解消は、私たちが思う以上に大きなものです。そういう意味では、誤嚥の危険性を減らすために睡眠薬を中止するのではなく、プラセボに切り替えてみることも選択肢の一つといえるかもしれません。
もちろん、病状によっては、効果が期待できないだけでなく、不眠や不安症状がひどくなってしまうことも考えられます。プラセボの利用を検討される前に、必ず主治医に相談してください。