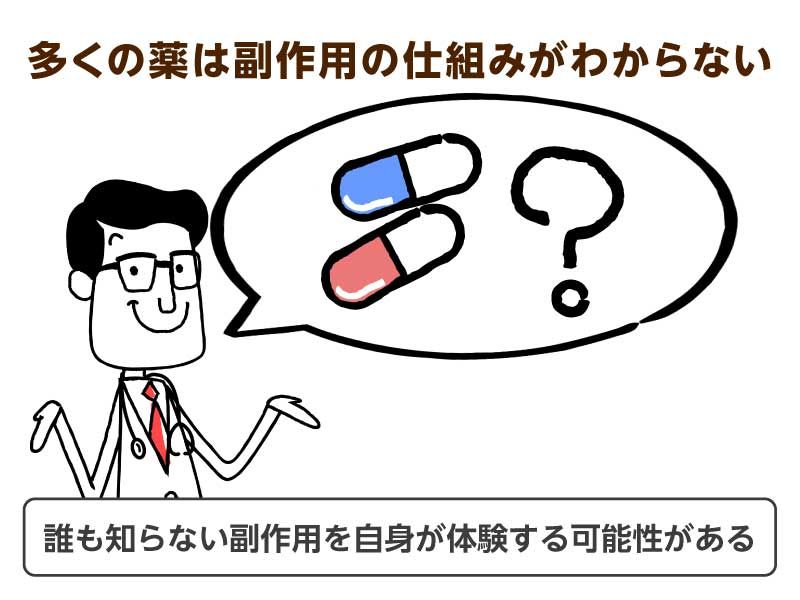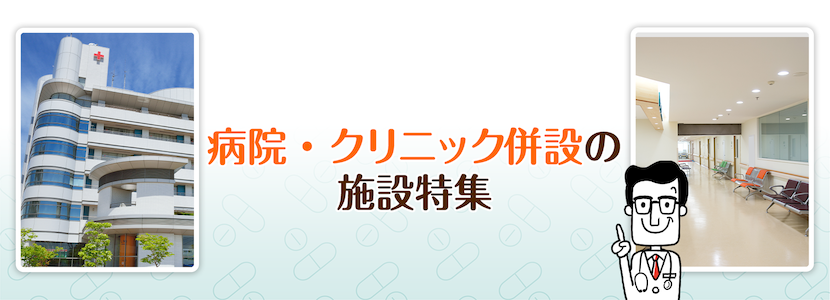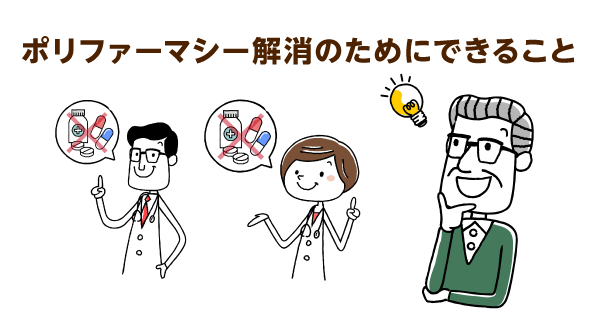こんにちは。薬剤師の雜賀匡史です。
今回のテーマは、「薬の副作用について」です。第4回の記事で副作用の概要についてご紹介させていただいたので、そちらも併せてご覧いただけると、より理解が深まると思います。
皆さんの中に、風邪薬や花粉症の薬を飲んで眠気を感じたことがある人はいませんか?これは自覚症状として現れるので、気づきやすい副作用の1つですね。では、なぜ風邪薬や花粉症の薬を飲むと眠気が出るのでしょうか?今回はこれを主軸にして、お話していきたいと思います。
異物を体外に出すために放出される「ヒスタミン」
私たちの体は、生まれながらにして異物など侵入者を排除する機能を持っています。この「侵入者」で代表的なのが花粉です。目、鼻、口などの粘膜から私たちの体内に侵入します。侵入してきた花粉に対して、体は防衛反応として体外に排除しようと涙や鼻水を出したりくしゃみをします。このとき、体が異物(花粉)を外に出そうとした結果、現れてしまう残念な症状が花粉症。風邪をひいたときに出る鼻水やくしゃみの症状も同様で、ウイルスや細菌を体外に排出しようとする体の防衛反応の結果となります。
これらの異物を排除するうえで重要なのが、体内でつくられている「ヒスタミン」と呼ばれる物質です。外からの刺激によって放出されたヒスタミンは、「H1受容体」、「H2受容体」に代表される受け皿に結合します。鼻の粘膜細胞に存在するH1受容体に結合したヒスタミンは、鼻を詰まらせたり鼻水を出す作用があります。胃内のH2受容体に結合したヒスタミンには胃酸分泌作用があります。

抗ヒスタミン薬により覚醒・興奮作用が失われて眠くなる
それぞれの受容体によって異なる作用を引き起こすヒスタミンですが、これらの症状で苦しむ思いはしたくありません。そこで考えられた薬が「抗ヒスタミン薬」と呼ばれる薬です。
抗ヒスタミン薬とは、ヒスタミンが受容体に結合して作用を引き起こすことを阻止する薬。抗ヒスタミン薬は胃薬や風邪薬、花粉症の薬などに使われています。
ところが厄介なことに、抗ヒスタミン薬は鼻や胃だけに的を絞って効果を発揮することが苦手です。H1受容体は鼻粘膜だけでなく脳内にも存在します。脳内H1受容体におけるヒスタミンは、覚醒作用や興奮作用をもたらします。
抗ヒスタミン薬が血液に乗って脳内のH1受容体にたどり着いてしまうと覚醒や興奮作用が失われ、「眠気」となって症状が現れます。眠気の作用を望んでいたわけではないので、「副作用」として考えられます。風邪薬や花粉症の薬には抗ヒスタミン薬の成分が多く含まれているため、これらを飲むと眠気の副作用が出やすいのはこの理由からです。
眠気の副作用がある薬を使用するときには、車の運転のように危険を伴う機械の操作には十分注意しましょう。
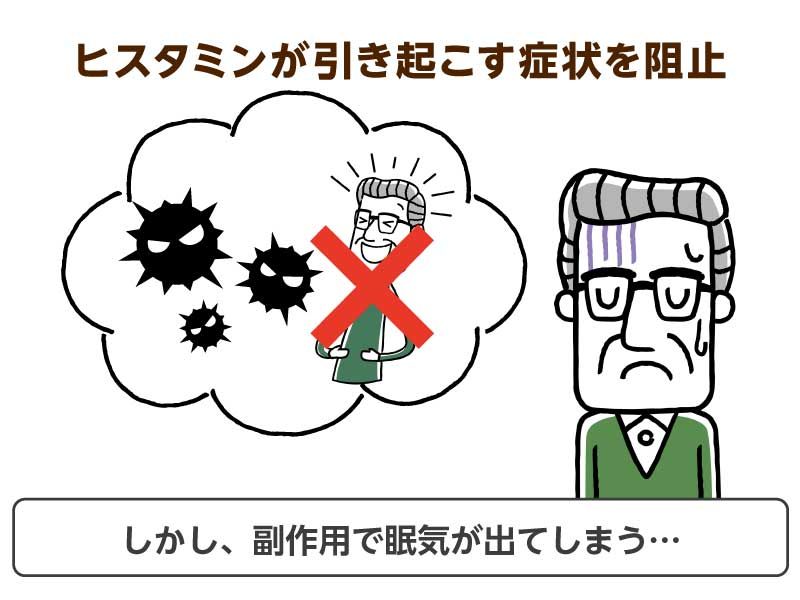
副作用が利用された薬がある!?
最近では、眠気の副作用が少ない抗ヒスタミン薬が発売されています。これらは薬が血液に乗って脳までたどり着かないように改良された薬です。「改良された薬があるのなら、眠気の強い薬なんてなくしてしまえばいいのに」と思うかもしれません。しかし、古い薬にもさまざまな点から存在価値はあるのです。
例えば、眠気の副作用を上手に利用した薬として市販されている睡眠改善薬があります。これは抗ヒスタミン薬が起こす眠気の副作用を逆手にとって、不眠で困っている人に利用しようと考えられた薬です。
薬の使用で異変を感じたら医療従事者に相談を
今回紹介した抗ヒスタミン薬は誕生してからの歴史が古いこともあり、副作用のメカニズムがある程度解明されています。しかし、現在使われている多くの薬は副作用発現のメカニズムまではわかっていません。
私たちが患者さんに薬の説明をするときには、世界中から集められた副作用の報告などを参考にし、発現頻度が高いものや頻度は低いけれど重大な内容を優先してお伝えするよう心がけています。
とはいえ、予測不能な副作用が一定数存在するということは皆さまに意識していただきたいところです。つまり、今までに1度も報告のない副作用を、皆さん自身が世界で最初に体験する可能性が常にあるということです。薬の使用に関して体調の異変に気づいたときには、必ず医療従事者に相談してくださいね。