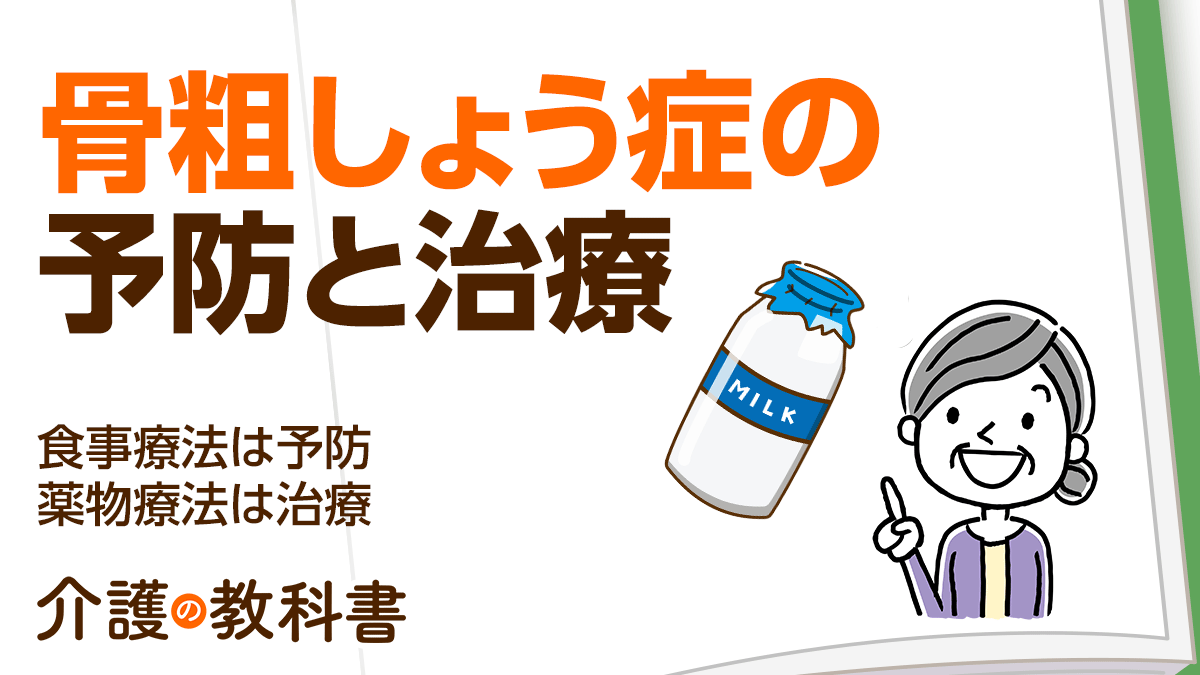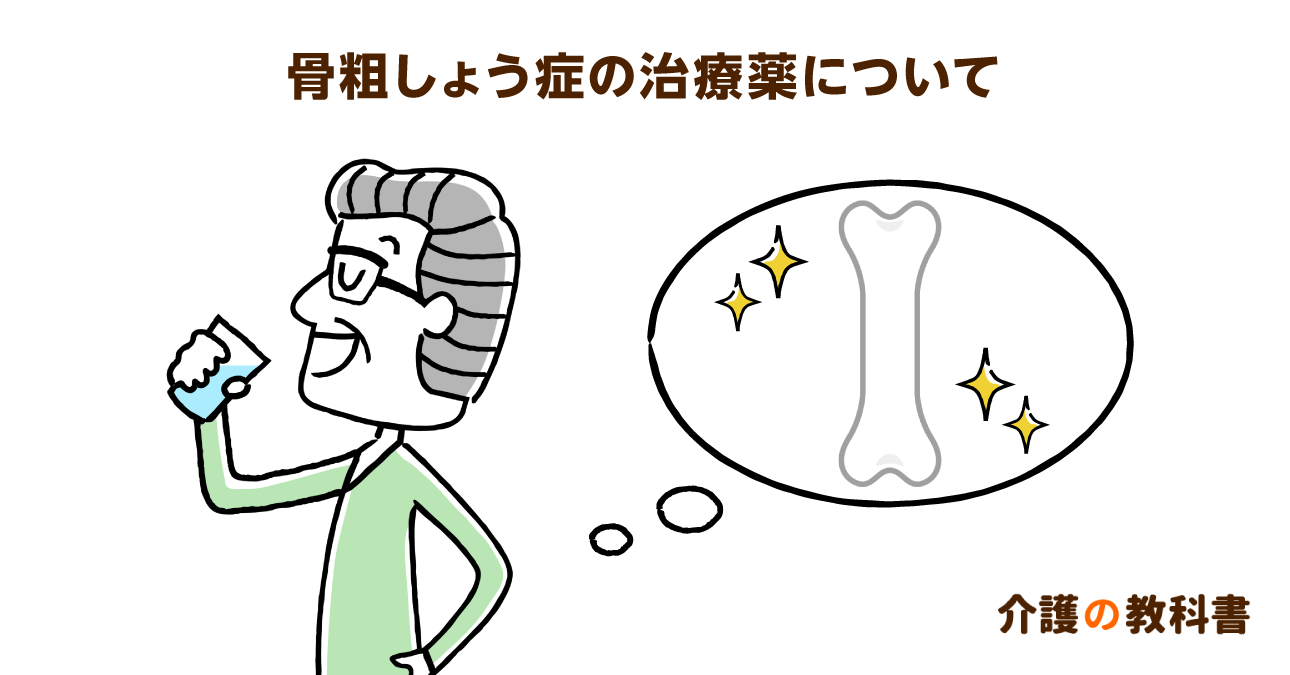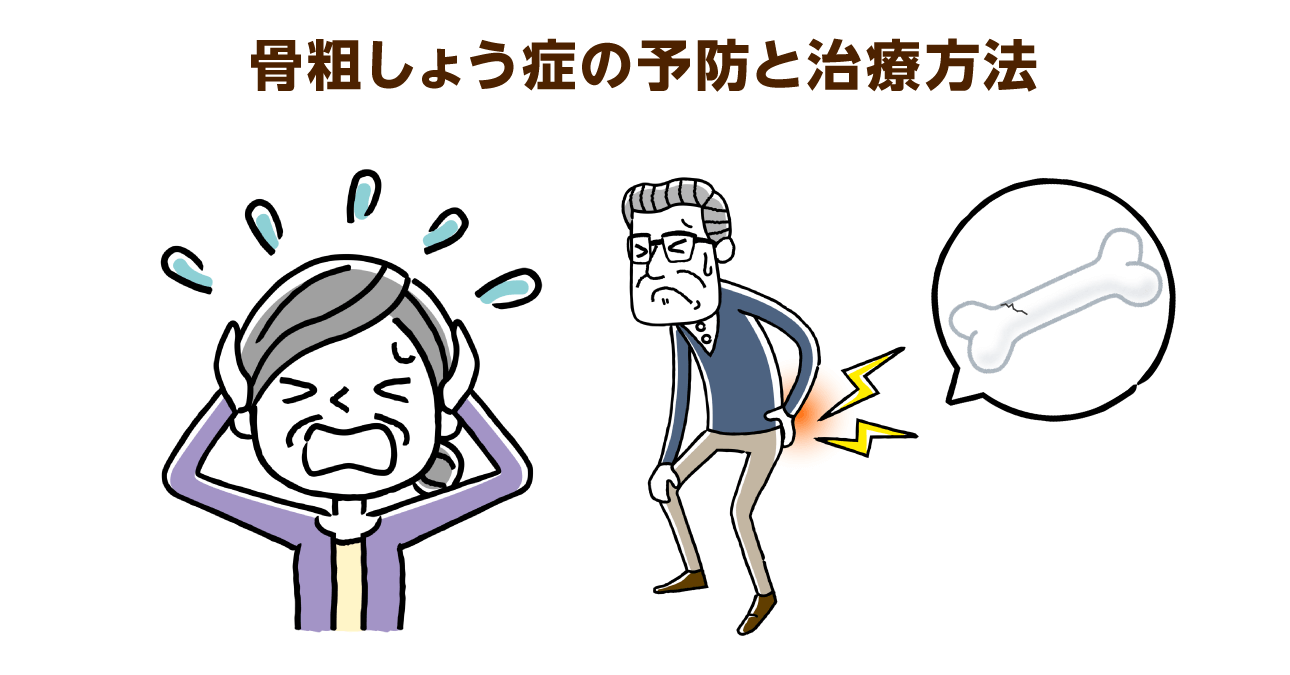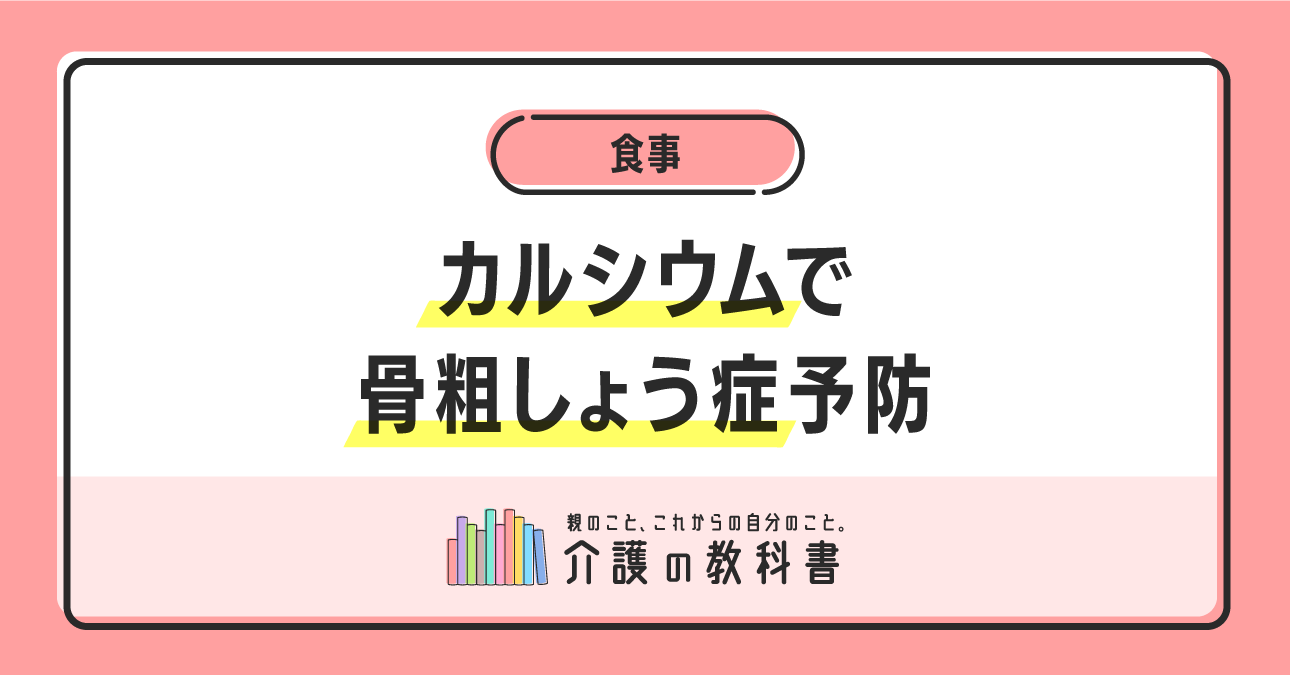骨粗しょう症は、骨がもろくなり、骨折しやすい状態となってしまう病気です。
骨に含まれるカルシウムなどのミネラル成分量は骨量(骨塩量)と呼ばれ、骨の単位面積(cm2)あたりに含まれる骨量を骨密度と呼びます。
一般的に、骨密度は20歳前後でピークを迎え、40歳ごろまでは横ばいで推移します。その後は、歳をとるごとに骨密度が減少していきます。
骨密度が、若年成人の平均値から30%低下すると、骨粗しょう症と診断されることがあります。特に、閉経後の女性では、エストロゲンというホルモンが不足することで、骨密度が低下しやすくなります。そのため、高齢女性は骨粗しょう症になりやすいといえるでしょう。
高齢化が進む現代社会では、骨粗しょう症を患う人も増加しています。そこで、この記事では骨密度の維持が期待できる食事療法や、骨粗しょう症に対する薬物療法について解説します。
骨粗しょう症と骨折の危険性
高齢化が急速に進んでいる先進国では、骨粗しょう症を患う人も増えていますが、日本では、実に約1500万人が骨粗しょう症を患っていると見積もられています。また、世界各国の骨粗しょう症関連団体が加盟している国際骨粗しょう症財団の統計によると、一生のうちに骨粗しょう症を発症する人は、50歳以上の女性の3人に1人、50歳以上の男性の5人に1人と推計されています。
骨粗しょう症と診断されたとしても、すぐに日常生活に支障をきたすわけではありません。しかし、高血圧が脳卒中の危険性を高めるのと同じように、骨粗しょう症は骨折の危険性を高めます。
もちろん骨粗しょう症以外の原因でも骨折は起こりますが、大腿骨頸部(足のつけね側にある大腿骨の端の部分)や脊椎(背骨を構成する骨)の骨折は骨粗しょう症と関連性が強いと言われています。加えて、高齢者や、骨折の経験がある方、リウマチを治療中の方、喫煙や飲酒習慣のある方の場合、さらに骨折の危険性が高まります。
転倒や骨折の発生率が年を重ねるごとに増えていくことは経験的にもわかりやすいように思います。また、大腿骨頚部を骨折すると、その後の健康寿命が極めて短くなってしまうことが知られています。
骨密度の低下を予防するための食事療法
骨密度の低下を遅らせることができれば、骨粗しょう症を予防できますが、そのためにはバランスの良い食習慣が大切です。さまざまな栄養素の中でも、特に意識したいのが骨を構成する重要なミネラル成分であるカルシウムです。
骨は、皮膚の新陳代謝のように、古くなった部位が壊され、新しい骨に置き換わるというサイクルを繰り返しています。骨が新しく置き換わることにより、骨の強さが保たれているのです。ですが、カルシウムの摂取量が不足すると、新しい骨がつくられにくくなり、骨密度や骨の強度の低下をもたらすことになります。
ですので、骨の健康を維持するためには、適度な量のカルシウムを摂取することが重要です。厚生労働省が公開している日本人の食事摂取基準によれば、1日当たりのカルシウムの推奨摂取量は75歳以上の男性で720㎎、女性で620㎎となっています。ちなみに、コップ1杯の牛乳(200ml)には227mgのカルシウムが含まれており、1日の推奨摂取量の約3分の1を補うことができます。
ただし、骨の健康を維持するためにはカルシウム以外にも、カルシウムの吸収を促進するビタミンD、骨へカルシウムの取り込みを助けるビタミンKなどの栄養素が必要です。牛乳だけをたくさん飲んでも、必ずしも骨折を予防できるとは限りません。そのため、骨粗しょう症を予防するためには、規則正しく、バランスのとれた食事をとることが大切です。
食事摂取のパターンと骨密度や骨折リスクに与える影響を検討した研究報告によれば、いわゆる地中海食の積極的な摂取は骨折リスクの低下を期待できます。地中海食とは、イタリア、ギリシャ、スペインなどの地中海沿岸の国々の人が食べている伝統的な料理で、果物や野菜が豊富、乳製品や肉料理よりも魚料理が多い、オリーブオイル、ナッツ、豆類、全粒粉などの未精製の穀物を多く使用するなどの特徴があります。
地中海食を積極的に食べている人では、そうでない人に比べて、骨折のリスクが21%低下したことを報告した研究もあります。一方、加工食品や赤身肉の摂取が多い食事は、骨密度の低下と関連することが報告されています。
骨粗しょう症の薬物療法と、その効果
骨粗しょう症に対する薬物治療の目的は、骨密度を高めるだけでなく、骨折のリスクを低下させることです。骨粗しょう症治療薬は、古くなった骨を破壊してしまう破骨細胞に作用する骨吸収抑制薬と、新しく骨をつくる作用を促す骨形成促進薬に分けることができます。
主な骨吸収抑制薬として、ビスホスホネート剤、抗ランクル抗体薬、選択的エストロゲン受容体モジュレータと呼ばれる薬があります。また、骨形成促進薬として、副甲状腺ホルモン剤、抗スクレロスチン抗体薬があります。カルシウムの吸収を助けるビタミンDを配合した薬も広く用いられています。
| 分類 | 成分名 | 主な商品名 | |
|---|---|---|---|
| 骨吸収抑制薬 | ビスホスホネート剤 | アレンドロン酸 | フォサマック® ボナロン® |
| リセドロン酸 | アクトネル® ベネット® |
||
| ミノドロン酸 | ボノテオ® | ||
| イバンドロン酸 | ボンビバ® | ||
| 抗ランクル抗体薬 | デノスマブ | プラリア® | |
| 選択的エストロゲン受容体モジュレータ | ラロキシフェン | エビスタ® | |
| バゼドキシフェン | ビビアント® | ||
| 骨形成促進薬 | 副甲状腺ホルモン製剤 | テリパラチド | テリボン® フォルテオ® |
| 抗スクレロスチン抗体 | ロモソズマブ | イベニティ® | |
| その他の薬 | 活性型ビタミンD製剤 | エルデカルシトールなど | エディロール® |
数ある骨粗しょう症の治療薬の中でも、最も広く用いられている薬がビスホスホネート剤と呼ばれる薬です。ビスホスホネート剤は、骨折の危険性が高い人に対する骨折予防効果が高く、プラセボ(偽薬)と比べて30~50%ほどのリスク低下が期待できます。
一方で、骨折リスクの低い人では、ビスホスホネート剤に限らず、薬物治療の効果は必ずしも大きくはありません。このような人では、まずは食事療法がすすめられることもあります。
ビスホスホネート剤はまた、薬剤成分が体に吸収されにくく、空腹時に服用しないと、十分な薬効を期待できません。さらに、ビスホスホネート剤は食道の粘膜に炎症(食道炎)を引き起こしやすいことが知られています。そのため、ビスホスホネート剤は起床時に、多めの水と一緒に服用する必要があります。薬をなめたり、かみ砕いたりしてはいけません。口の中の粘膜が荒れてしまうことがあるからです。
薬を飲んだあとは、少なくとも30分の間、立位姿勢(立っている状態)もしくは座位姿勢(座って上半身を起こしている姿勢)を維持する必要があり、横になってはいけません。横になると、飲み込んだ薬が食道にとどまりやすく、粘膜が障害されて食道炎を引き起こしてしまう危険性が高まります。むろん、薬を服用してから30分間は朝食も食べてはいけません。
ビスホスホネート剤を服用する際の注意点
- 起床してすぐに服用し、服用後は少なくとも30分は水以外の飲食をしない
- 食道炎の副作用が発生しやすいので、立位あるいは坐位の姿勢を保ち、十分量(約180mL)の水とともに服用する
- 薬を服用する差異は、錠剤を噛み砕いたりなめたりせず、服用してから30分は横たわらない
ビスホスホネート剤は、服薬する手間や負担が大きい薬であり、飲み忘れる方も少なくありませんでした。しかし、週に1回、あるいは月に1回の服用ですむビスホスホネート剤が開発されてからは、服薬に関わる手間や負担が大きく減りました。
食事療法と薬物療法の違い
骨粗しょう症は、骨密度が低下することによって、骨折が起こりやすい状態になってしまう病気です。食事療法は、骨密度の維持に重要であり、骨粗しょう症を予防する効果が期待できます。また、地中海食を積極的に食べている人では、骨折リスクの低下も期待できるかもしれません。
一方で、薬物療法は骨粗しょう症と診断された方に対して行われます。薬物治療の大きな目的は、骨密度の低下を防ぐことだけでなく、骨折を予防することにあります。ただし、もともと骨折の危険性の低い人では、薬物療法の効果を期待できないことも少なくありません。
また、ビスホスホネート剤には食道炎を起こしやすいなどの副作用もあります。そのため、患者さんの将来的な骨折リスクなどの見積もりなどを踏まえたうえで、薬物療法の開始が判断されます。
骨粗しょう症の予防・改善には、バランスの良い食事が大切です。日頃から栄養素に気をつけ、薬物療法が必要のない生活が送れるように意識しましょう。
【参考文献】
[1]厚生労働省 e-ヘルスネット
[2]Clin Calcium. 2012 Jun;22(6):797-803
[3]Eur J Rheumatol. 2017 Mar;4(1):46-56
[4]J Clin Epidemiol. 2011 Jan;64(1):46-53
[5]Joints. 2018 Jun 14;6(2):122-127
[6]Curr Osteoporos Rep. 2008 Dec;6(4):149-54
[7]CMAJ. 2009 Sep 1;181(5):265-71
[8]「日本人の食事摂取基準」(2020年版)
[9]雪印メグミルク株式会社
[10]J Bone Miner Res. 2011 Apr;26(4):833-9 [11]Nutrients. 2020 Jul 3;12(7):1986
[12] Eur J Nutr. 2018 Sep;57(6):2147-2160.
[13]Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23:(1):CD004523
[14]Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23:(1):CD001155 [15]Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23;2008(1):CD003376
[16]Arch Osteoporos. 2015;10:231