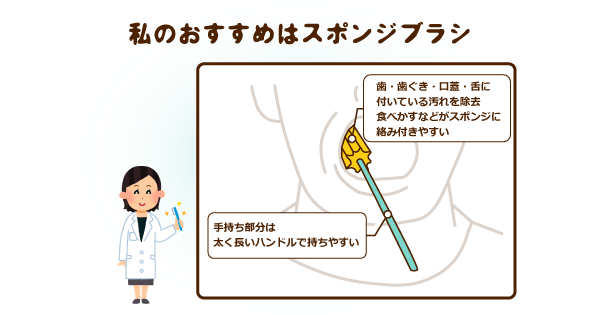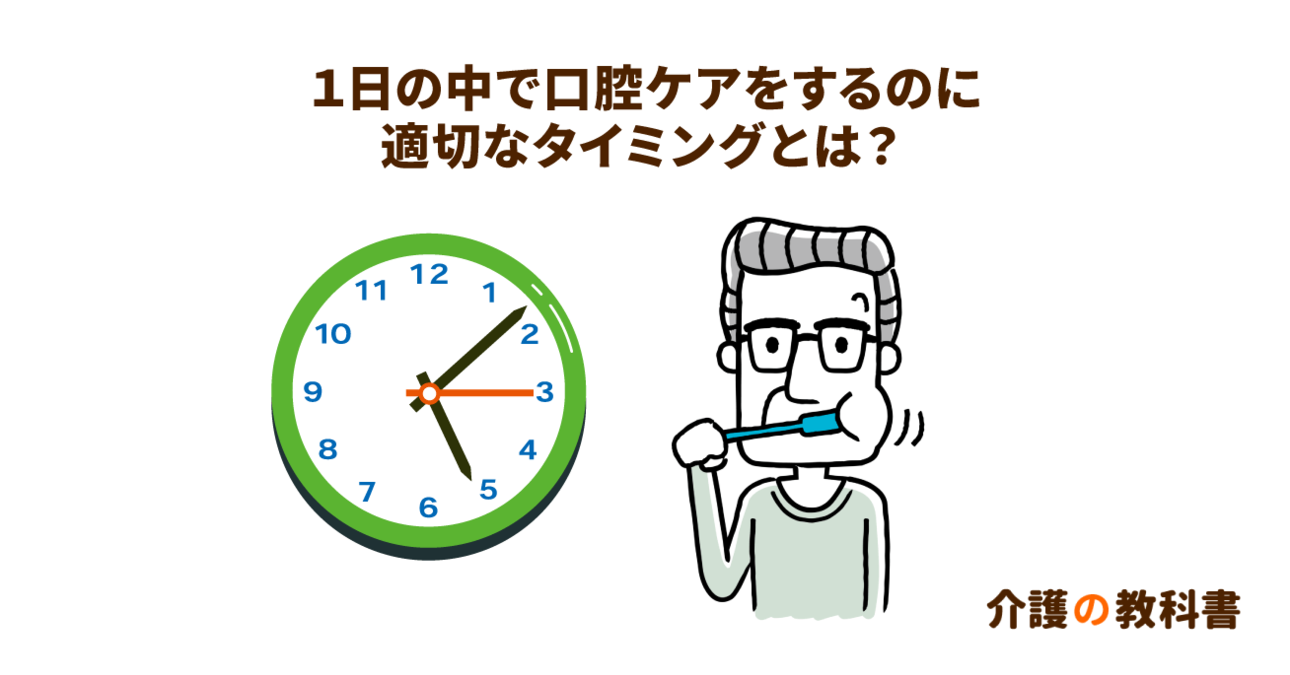口腔ケアを受ける高齢者が、 より快適になる3つのポイント

こんにちは。口腔ケア部門を担当している口腔ケア部門を担当している日本デンタルスタッフ学院・学院長の田中法子です。
「毎回、歯みがきの準備をしてベッドサイドに持っていくとお父さんが顔をしかめるんです。その顔をみると、いたたまれなくなります。」
こんなご相談を受けたことがあります。
この教科書をお読みいただいている読者のみなさんの中にも、このような経験ってありませんか?介護が必要な場合に限らず、お子様をお持ちの方なら必ず「歯みがきを嫌がって困った」という経験があると思います。
歯みがきをしてあげるという「善い行い」をがんばっているにも関わらず、嫌な顔をされて心が折れる…。もちろん私にも経験があります。
大雪の日にやっと、到着したお宅の利用者さんに「さあ!お口きれいにしますよー!」といって近づいた途端、目の前5cmのところまで“グー”でパンチが飛んできました。驚いたのと悲しいのとで愕然としてしまい、その日の口腔ケアはできないまま帰宅したことがあります。
十数年前のこの一件をきっかけに、老年精神医学や認知症ケアを学んでみて、わかったことがあります。それは、「歯みがきをしますよ〜」では受ける側に伝わっていない、ということです。
もしかしたら、みなさんのご家族もしくは利用者さんは、「なんだなんだ?!棒もって近づいてきたぞ!」という恐怖感を持っているかもしれません。そこで、今回は、受ける側がより快適になる3つのポイントを紹介していきたいと思います。
口腔ケアを気持ちよく受けてもらうためのポイント1
「準備段階から説明する」

「ウチのお父さん、説明してもわからないから」そう言われることもあるかもしれませんが、わかってもらえてもそうでなくても、しっかり準備を声に出しながら笑顔で行なってみましょう。
など、会話をしながら準備します。私自身、準備をしているときにふと目の前にあった洗面台の鏡に映る自分の表情に”ぎょっ”としたことがあります。すごくこわい顔になっていました。笑
口腔ケアを気持ちよく受けてもらうためのポイント2
「身ぶり手ぶりでもコミュニケーション」

お口の周りだけが移るような鏡を用意します。鏡を怖がるようならやめてください。もしくは、自分の口に(自分の歯ブラシを)入れるようなしぐさをします。「お父さんの歯はキワが大事なんだって。歯医者さんが言ってたの。」というように、これもわかってもわからなくても耳の側で伝えます。
口腔ケアを気持ちよく受けてもらうためのポイント3
「明るく焦らずに口腔ケアを行う」

「このブラシできれいにしようと思うんだけど、いいかなあ?」と許可を求めます。もし、それでもイヤという場合は「じゃあこの歯1本だけ」というように部分的に行なうようにしてください。少しでも歯ブラシが口に入ると、以外とすんなり全体をさせてもらえることが多いです。そんなときは、「ありがとう!よく見えるなあ〜!」と言って、行なった後は、「さっぱりするよね!つるつるになったよ!」と、ポジティブに褒めてあげてください。
「話して・見せて・行なう」行動調整法
“まわりくどい!”と感じてしまうかもしれませんが、何回か連続でこのような方法を行なうと、「歯みがき=気持ちいい」ということが少しずつ伝わります。
これらを、学術的な言い方では「行動調整法」と呼びます。行動調整法にはいくつかありますが、今回はその中でも「Tell- Show-Do法」という「話して・見せて・行なう」という方法をご紹介しました。もっとも基本的な方法なので、みなさんにも実践できると思います。ぜひ行なってみてください!
次回は、口腔ケアがもっと楽になる、たったひとつの裏ワザをお伝えします。