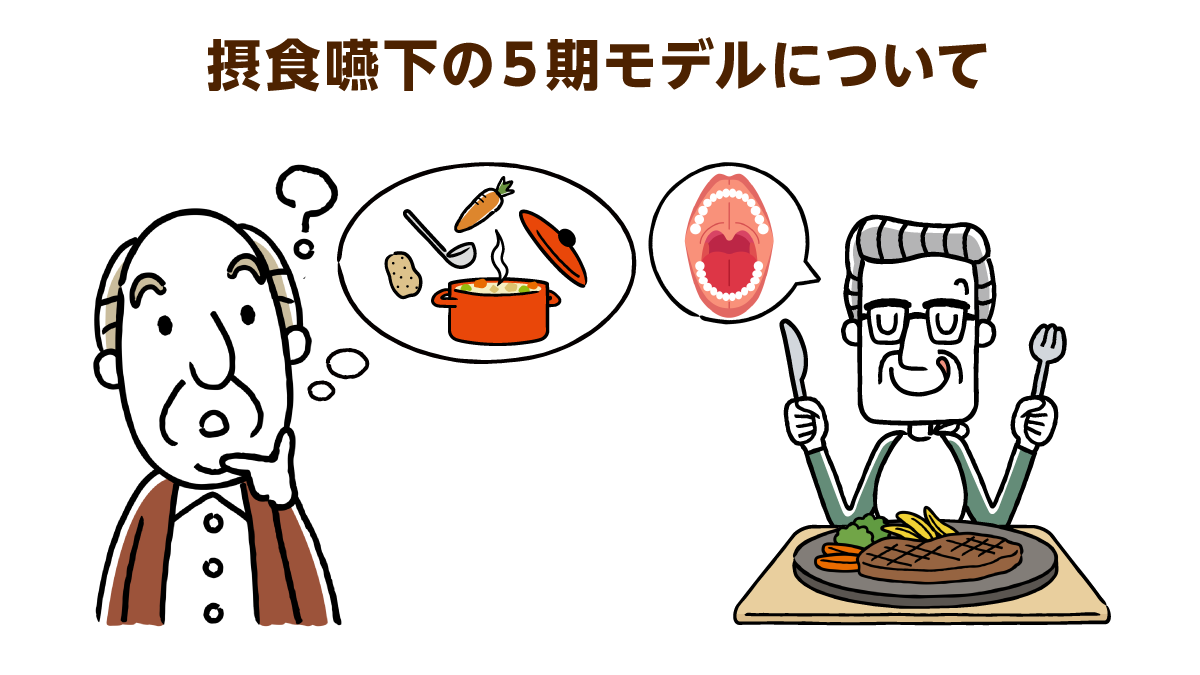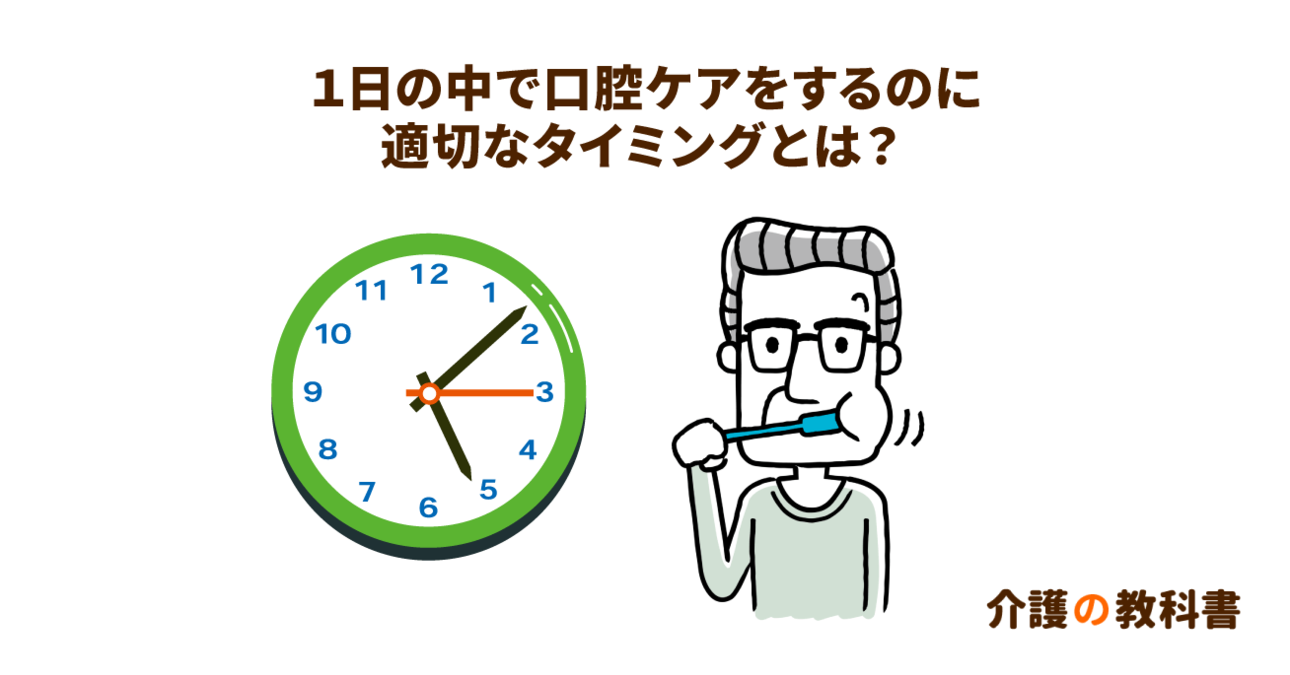こんにちは、リハビリテーション科医の新田実です。
今回は「摂食嚥下(えんげ)の5期モデル」について解説したいと思います。
摂食嚥下には5つの段階がある
摂食嚥下の5期モデルとは、摂食嚥下=「食べる+飲み込む」をわかりやすく説明するために一般的に用いられるモデルのことです。
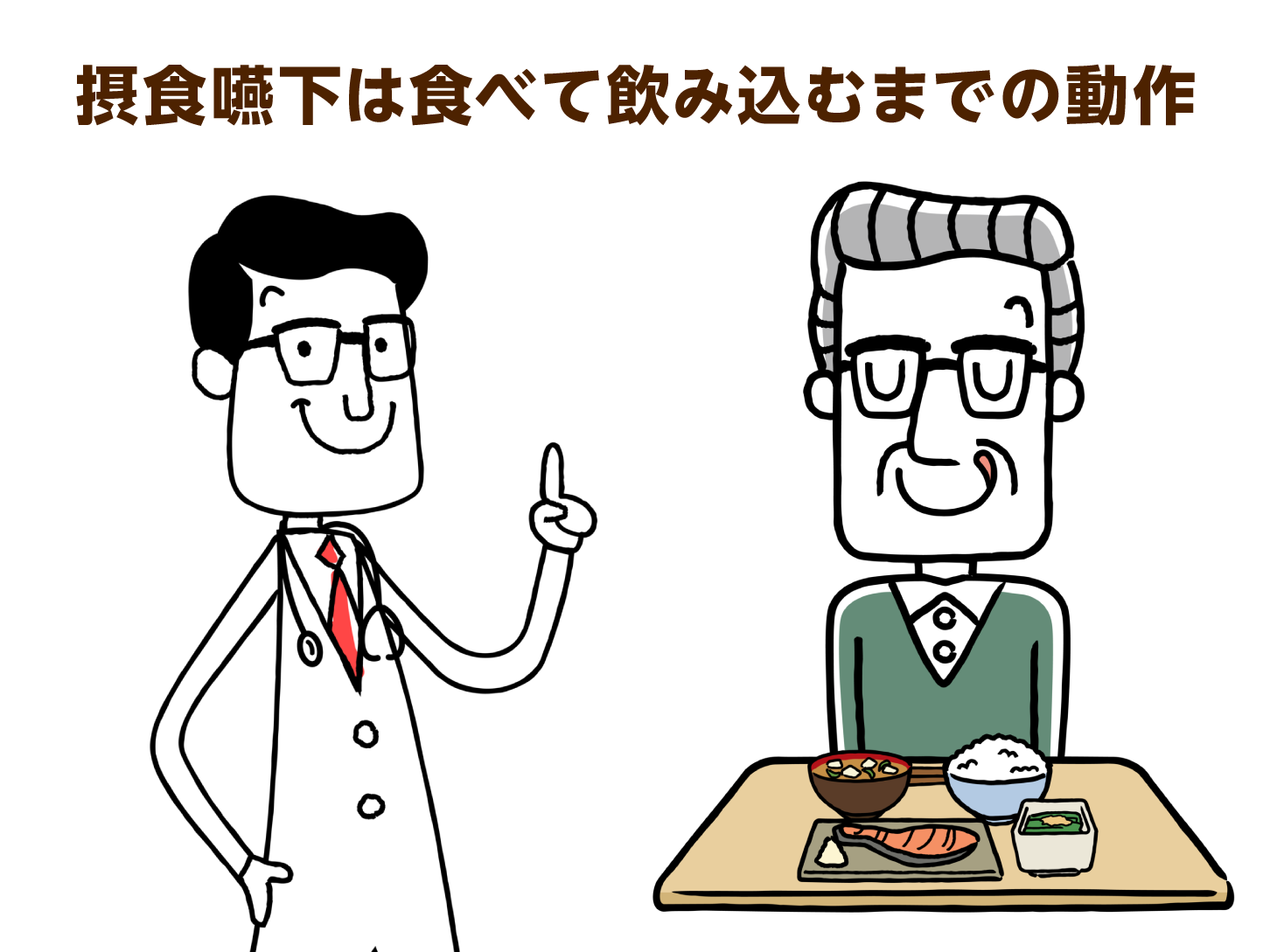
具体的には摂食嚥下=「食べる+飲み込む」を「先行期」「準備期」「口腔期」「咽頭期」「食道期」の5つの段階に分割して考えます。それぞれの期を簡単に説明すると、以下のようになります。
先行期:食べものを認識して口に入れるまでの段階
準備期:食べものを口に入れて咀嚼(そしゃく)する段階
口腔期:咀嚼した食塊をのどへ送り込む段階
咽頭期:食塊を飲み込み(咽頭から食道へ運ぶ)段階
食道期:食塊を食道から胃へ運ぶ段階
それぞれの段階を正しく理解することによって「食べること」や「飲み込むこと」をより深く知ることができますので、それぞれの段階を細かく解説していこうと思います。
摂食嚥下の5期モデルにおける機能説明
食べものを認識して口に入れる先行期
先行期とは「食べものを認識して口に入れるまでの段階」のことなのですが、「そんなことは当たり前で、わざわざ分類する必要があるのかな」と思った方もいると思います。特に障がいや機能低下のない方にとっては、「食べものを認識して口に入れる」という行為はごく当たり前で、意識することはないでしょう。
しかし、認知症や高次脳機能障がいなどで認知機能が低下した方や、意識障がいや食欲不振のある方にとっては、「食べものを認識して食べ始めること自体がとても難しい行為」なのです。「食べものが目の前にあっても食べ始めない」「食べる意欲がわかない」「食べものを掴んでも上手く口に運べない」などはすべて先行期の障がい(以下、先行期障がい)と捉えることができます。
そういった障がいのある方に対しては、食べものを認識しやすくするために食事の彩りや香りを工夫したり、食器を工夫して華やかさや季節感の演出を行います。また、意識障がい(なんとなくぼーっとしている)のある方の場合は、原因となる薬を内服していないかどうかなどをチェック。それぞれの症状・状態に対するアセスメントと対応策を検討することが重要です。
さらに、上肢機能(片麻痺や関節可動域制限、振戦(体に起こるふるえのこと)など)の問題で食べものを食器から口までうまく運べない場合も先行期障がいに含まれます。そういった場合も食事介助や食具の工夫、上肢機能に対するアプローチなど、それぞれの症状・状態に対する解決策を検討しましょう。まとめると、先行期障がいとは認知機能や上肢機能の問題で「食べものを口まで運ぶ」段階に障がいが起こったことを表します。

食べものを咀嚼する段階の準備期
準備期とは「食べものを咀嚼する」段階なわけですが、いわゆる食事における「もぐもぐ、ごっくん」のもぐもぐの部分に該当します。「咀嚼=食べものを噛む機能」と思われる方も多いと思いますが、摂食嚥下における咀嚼は食べものを噛む以外にもいろいろと重要な機能を兼ね備えています。咀嚼の機能は大きくわけて以下の3つが主な役割です。
- 食塊形成
- 消化吸収促進作用
- 味覚伝達作用
食塊形成
咀嚼によって食べものを粉砕し、唾液と混合して嚥下しやすい(飲み込みやすい)形態へ変化させる機能のことです。硬い食べものやバラバラでまとまりのない食べものはそのままではとても嚥下しにくく、誤嚥や窒息の原因となります。咀嚼によってしっかり食塊形成をして飲み込みやすい食形態へ変化させることは、とても大切な機能です。
消化吸収促進作用
咀嚼によって食べものを消化しやすいように粉砕し、さらに唾液や胃液の分泌を促進して食べものの消化吸収を補助する機能です。咀嚼が不十分だと消化吸収が上手く行われず、消化不良や小腸閉塞などの原因となりますので、咀嚼における消化吸収促進作用もとても大切な機能となります。
味覚伝達作用
咀嚼することによって舌で味覚を感じやすくする機能のことです。このほかにも、歯根膜(歯と骨の間にある膜状の組織のこと)で食感を感じさせることも含まれます。
食事の楽しみ方として、味だけでなく「カリカリ」「パリパリ」など食感も非常に重要であり、咀嚼はその作用の一端を担っています。以上が摂食嚥下における咀嚼の主な機能となりますが、準備期における「咀嚼」の重要性がご理解いただけたと思います。
咀嚼した食べものをのどに送り込む口腔期
口腔期とは「咀嚼した食塊をのどへ送り込む段階」のことで、いわゆる食事における「もぐもぐ、ごっくん」のちょうど中間の段階となります。この段階では、咀嚼した食塊を舌によってスムーズに咽頭(いんとう:のど)へ送り込むことが必要となってきます。
その際には「舌」がとても重要な機能を担っており、この舌の機能が低下した方ではうまく食塊の送り込みができず、誤嚥(ごえん)や窒息の原因となってしまうのです。とくにパーキンソン病の方の場合、舌の運動機能が低下して、なかなかのどへ送り込めない(なかなか嚥下が起こらない)といった症状が見られることもあります。
こういった口腔期における問題のある方に対しては舌の筋力である舌圧を鍛えたり、舌の働きを補うために舌接触補助床(PAP)と呼ばれる補綴装置を利用することが解決策の一つ。また、姿勢を傾ける(リクライニング30度)ことによって重力の力を利用してのどへの送り込みを補助する方法などもあります。
舌の機能が低下(舌圧や舌の巧緻動作)していないかしっかりと確認することが重要です。最近では歯科医院で「舌圧測定」も可能となってきていますので、舌の機能低下が気になる方は一度ご相談するのも良いのかも知れません。
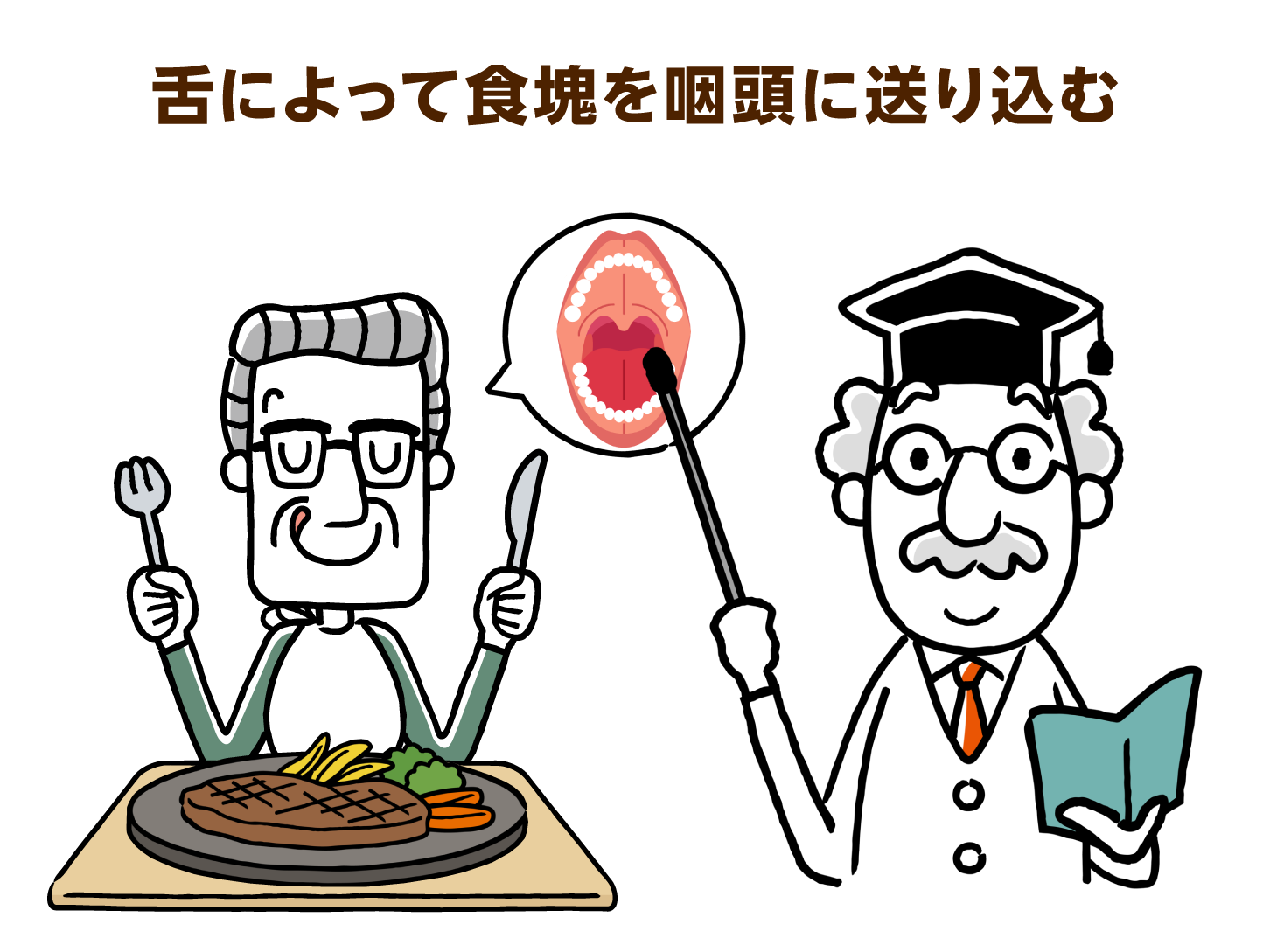
食べものを食道へ運ぶ咽頭期
咽頭期とは「食塊を飲み込む(咽頭から食道へ運ぶ)段階」で、いわゆる「もぐもぐ、ごっくん」の「ごっくん」の部分に該当します。
この段階では舌や咽頭(のど)の筋力を利用して約0.5秒程度の短い時間の間に一気に食塊を食道へと送り込みます。この短い間に正確に食道へ送り込む機能は非常に精密に制御されており、私たちが自分でコントロールできるのは嚥下反射のごく一部です。
したがって脳卒中や神経疾患で嚥下反射・嚥下機能が低下した場合は、失われた機能を回復するために嚥下反射・嚥下機能に対するリハビリテーションを行いますが、機能回復が不十分な場合にはその代償手段(機能回復以外の手段)を考えなければなりません。
その代償手段の代表例が、とろみをつけることと姿勢の調整です。とろみをつけることによって食塊の流動性を低下させ、嚥下反射惹起遅延(えんげはんしゃじゃっきちえん:加齢や疾患で飲食物が流れ込む速度に嚥下反射が追いつかず、誤嚥してしまうこと)などの機能低下に対応しやすくします。
姿勢の調整はリクライニング30度や側臥位(ぎょうがい:あおむけ)などに姿勢を変更することによって、食塊の流速を遅くしたり、誤嚥しにくい場所を通過させることが可能となります。嚥下機能の改善が認められない場合にはとろみや姿勢などの代償手段を利用することがあるというのを覚えていただければと思います。
食べものを食道から胃へ運ぶ食道期
食道期とは「食塊を食道から胃へ運ぶ段階」です。日常生活の食事場面でこの食道期を意識することはあまりないと思いますが、食道は皆さんが意識していない状態でも「蠕動運動(ぜんどううんどう:収縮運動)」によって食塊を胃へと送り込んでくれています。
食後にすぐに横になってしまうと、重力の影響で胃に運ばれた食塊が逆流しやすくなってしまいますので、食後30分程度はなるべく横にならないように注意しましょう。胃食道逆流症は胸のむかつきなどの症状以外にも、高齢者の方の誤嚥性肺炎の原因ともなりますので、嚥下機能の低下した高齢者の場合には特に注意して頂きたいと思います。
機能を知ることで「食べる」「飲む」の意味を理解しよう
以上が摂食嚥下の5期モデルの説明となります。それぞれの段階を知ることによって、「食べること」や「飲み込むこと」がどういった機能であるかということがより深く理解できると思います。