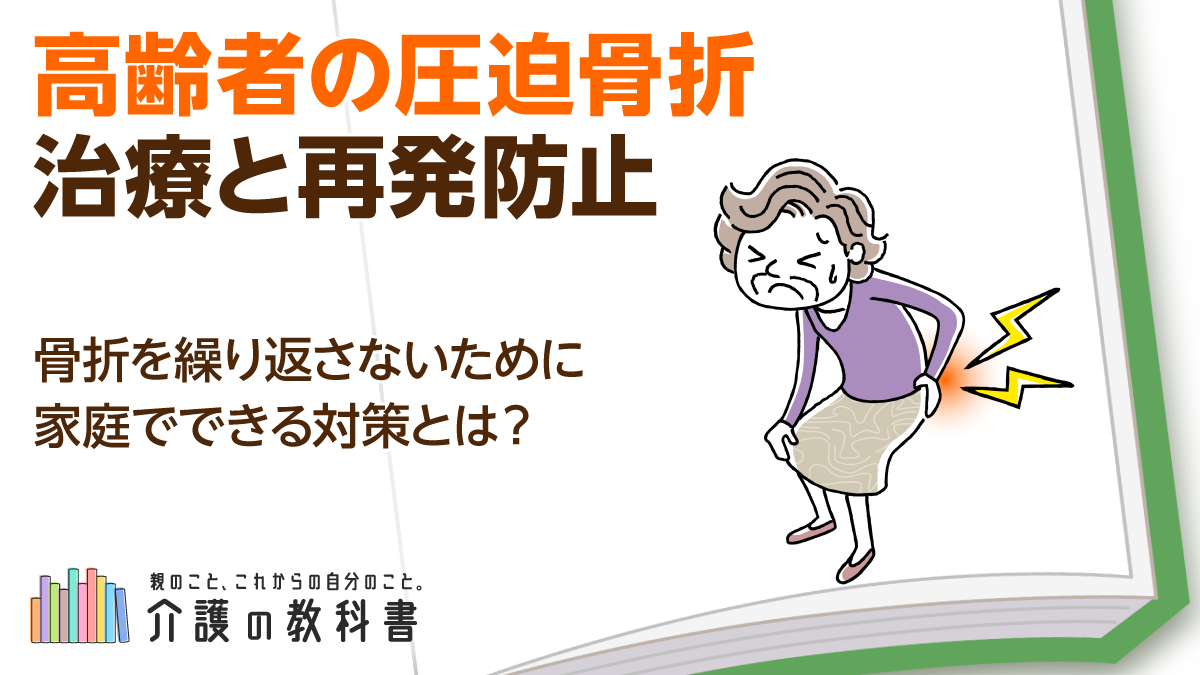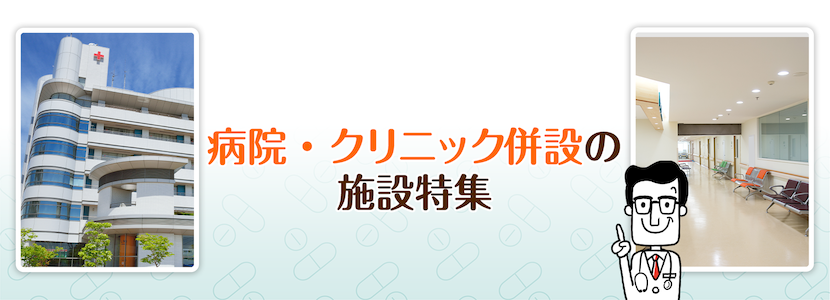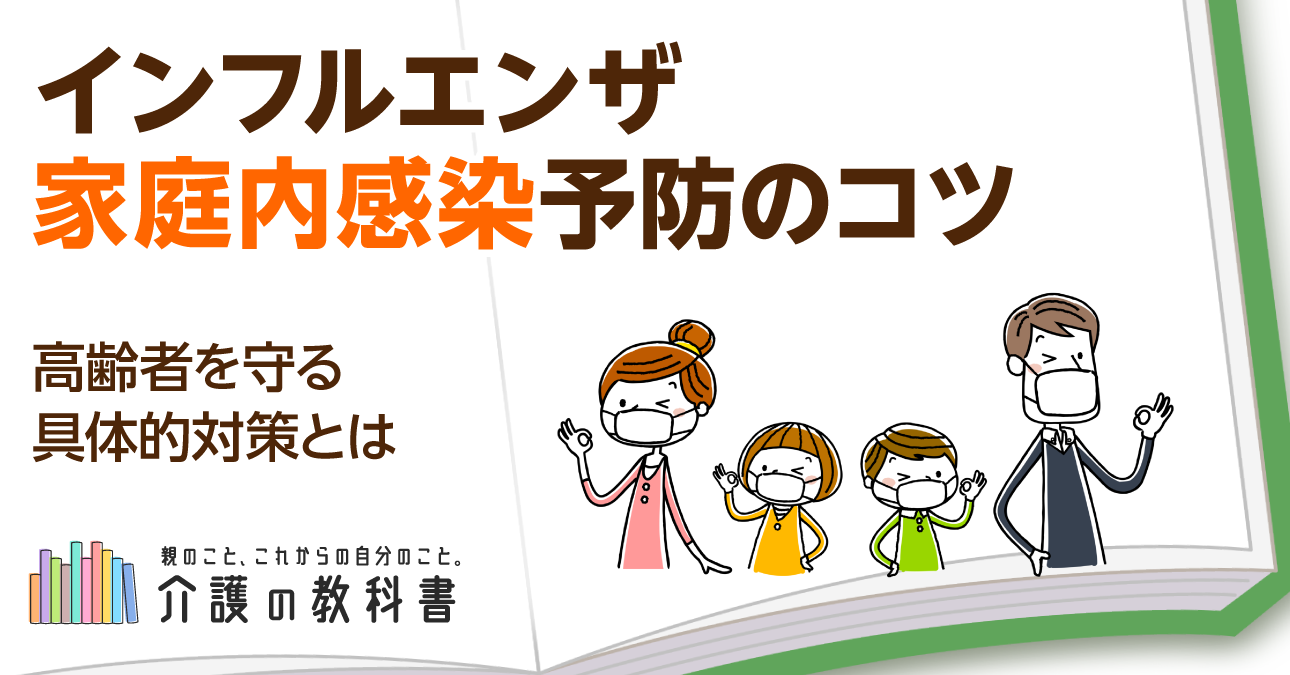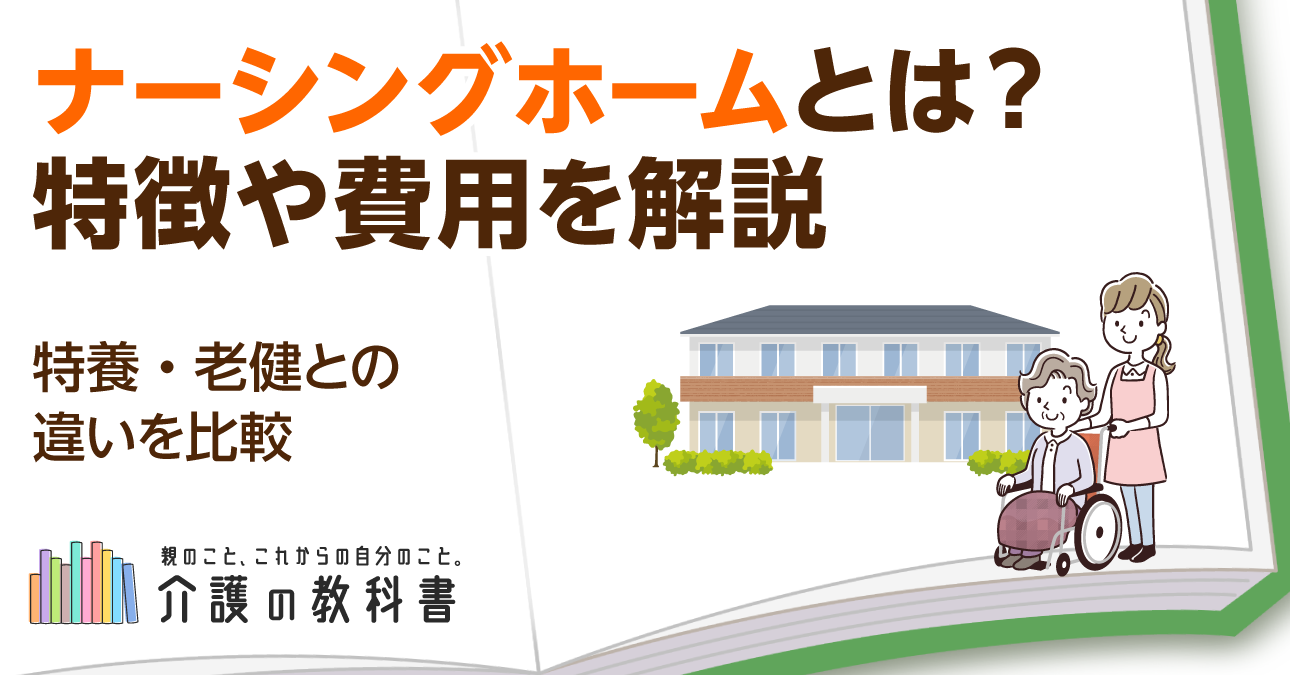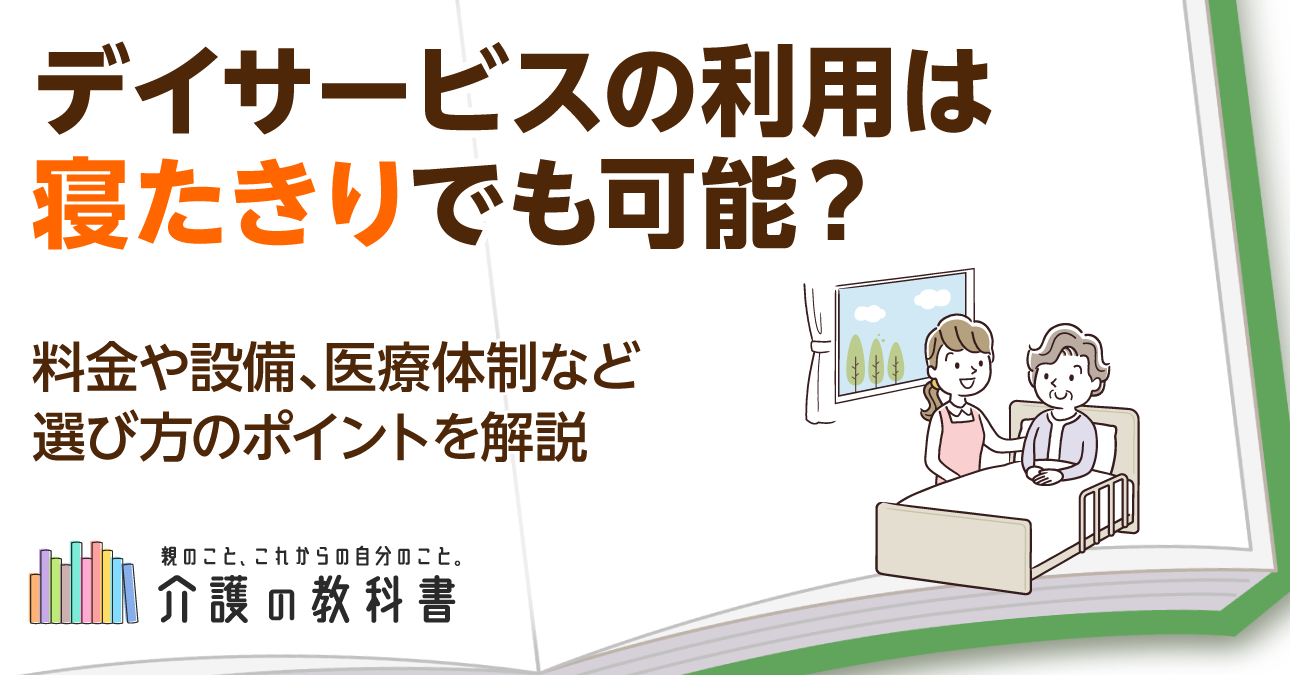高齢者に多い圧迫骨折とは?原因と症状の基礎知識
高齢者にとって身近な骨折である圧迫骨折。軽い転倒でも起こりやすく、「いつのまにか骨折」とも呼ばれます。まずは圧迫骨折がどのような骨折なのか、なぜ高齢者に多いのか、どのような症状が現れるのかを詳しく見ていきましょう。
圧迫骨折とは?背骨に起こる特殊な骨折
圧迫骨折は、背骨を支える椎体という骨が上下から押し潰されて変形・破折する特殊な骨折です。もともとは高所からの落下など強い衝撃で起こるものと認識されていましたが、近年では高齢化に伴い、脆くなった背骨に圧迫骨折が起こるケースが急増しています。
高齢者の圧迫骨折では、軽い尻もち程度の転倒、重い荷物を持ち上げた拍子、長時間の中腰作業など、健康な骨であれば問題ない動作でも骨折してしまうこともあります。特に骨密度が低下している高齢者では、くしゃみや咳など些細なきっかけでも骨折することがあります。中には痛みを伴わないまま骨折が進行していることもあり、それらの骨折は『いつのまにか骨折』と呼ばれます。
圧迫骨折は背骨の境目付近に起こりやすい傾向があります。この部分の椎体が潰れることで発生し、背骨の骨折の中でも比較的弱い力で起きる特殊な骨折として位置づけられています。

高齢者に圧迫骨折が多い理由
高齢者に圧迫骨折が頻発する最大の理由は、骨粗しょう症による骨の脆弱化です。加齢や閉経によって骨密度が低下すると、背骨が耐えられる力が大幅に減少します。
健康な人の椎体は強い力に耐えられますが、骨粗しょう症の人では大幅に耐久力が低下すると報告されています。
例えば、体重50kgの人が尻もちをつくと、背骨には約6.5~9倍(325~450kg)の力がかかるため、骨が脆い高齢者ではそれだけで骨折しやすくなります。このように小さな衝撃でも折れてしまうため、高齢者には圧迫骨折が頻発する傾向があります。
また、特に高齢女性に多いのも大きな特徴といえます。これは女性ホルモン低下の影響で閉経後に骨密度が下がるためです。年齢とともに骨折リスクは累積し、骨粗しょう症を放置していると骨折を繰り返しやすくなってしまいます。
圧迫骨折の代表的な症状と放置の危険性
脊椎の圧迫骨折では、突然の背中や腰の強い痛みが主な症状です。特に寝返りや起き上がりなど体を動かす瞬間に鋭い痛みが走り、一度立ち上がってしまえば比較的和らぐという特徴があります。このような動作時の痛みがある場合は、一度医療機関を受診しましょう。
圧迫骨折を複数ヵ所で起こすと背中が丸く曲がり(円背)、身長が縮むことがあります。骨折による姿勢変化で慢性的な腰背部痛に悩まされたり、内臓が圧迫されて呼吸や消化に支障が出る場合もあります。
放置すると骨片がさらに潰れて神経を圧迫し、しびれや脱力、排尿障害などを起こす場合があります。
適切に治療せず慢性化すれば背骨が曲がったままになってしまい、痛みで動けなくなって寝たきり状態に陥るリスクも指摘されています。
高齢者の圧迫骨折は治るのか?入院期間と自宅療養の実際
圧迫骨折と診断されると、多くの高齢者やご家族は「治るのだろうか」「入院が必要なのか」と心配になることもあるかと思います。実際の治療方法や入院期間の目安、自宅療養での注意点について、具体的にご説明します。
圧迫骨折の主な治療方法
高齢者の圧迫骨折でも、適切に治療すれば多くの場合は治癒します。実際、脊椎圧迫骨折の9割は手術をせずコルセット固定や安静などの保存的治療で症状が改善すると報告されています。
圧迫骨折の基本的な治療は、骨折部が動かないよう硬めのコルセットを装着し、前かがみになる動作を避けて安静に過ごす保存療法です。
痛み止めの内服や湿布などでケアを行い、安静に努めることで多くの場合は数週間で改善が見られます。コルセットの着用は骨が固まるまで通常数ヵ月間(おおよそ3ヵ月程度)必要な場合が多いです。
骨折後約1ヵ月間は、骨折部位が不安定で変形しやすいため特に注意が必要で、痛みが落ち着くまでは起き上がる回数もできるだけ減らします。
こうした保存的な経過を数週間みても痛みが強く日常生活が困難な場合には、手術が検討されます。
高齢者の圧迫骨折における入院期間の目安
治療法によって入院期間は異なります。保存療法のみで対応する場合、症状が軽ければ入院せずにコルセット固定で通院治療も可能です。
強い痛みがあって自宅での安静が難しい場合は、痛みが和らぐまで数日~1週間程度の短期入院で経過を見ることがあります。
実際、安定した圧迫骨折で背骨の神経への影響がない場合、受傷後1週間以内の安静で痛みが落ち着きベッドから起き上がることが可能になることも多いとされています。
一方、骨の欠け方によっては2~4週間程度の安静とリハビリ期間を設けて経過を見る場合もあります。
背骨にセメントを注入する手術を行う場合、入院期間は概ね1週間程度で、手術翌日から歩行可能となり比較的早期に退院できる場合もみられます。
この手術は手術時間が短く切開範囲も小さいため、高齢者でも合併症がなければ短期間で退院できることもありますが、金属の器具で背骨を固定する大掛かりな手術になった場合は1~2週間前後の入院が必要になることがあります。
いずれの場合も、退院後も引き続き骨の治癒経過を観察するための定期受診が欠かせません。特に骨粗しょう症が原因の骨折では、治療後に別の背骨が折れる可能性もあるため、骨粗しょう症の予防・治療を含めた継続的なケアが必要です。
ただ現状として、圧迫骨折では入院させてもらえないケースも多くあります。独居高齢者は痛みがあると生活に支障があり日常生活が困難となりますが、痛みがあったり治療行為があるとショートスティなどの利用を断られる場合もあるため、注意が必要です。
入院中にある程度痛みが取れても油断せず、医師の指示通りにリハビリや生活動作の練習を行い、安全に自宅復帰できる状態を事前に整えておくことが大切でしょう。

圧迫骨折後の自宅療養で注意すべきこと
退院後や自宅療養中は、骨折部位を安定させながら日常生活に戻す工夫が必要です。医師の指示に従いコルセットを正しく着用しましょう。
骨が完全に治癒する前に外してしまうと、再び痛みが出たり治癒が遅れる可能性があります。
基本は安静第一ですが、ずっと寝たきりでは筋力低下が進み回復を妨げるため注意が必要です。骨折後2~3週間の急性期は無理な動作を避けつつ、担当医や理学療法士と相談して痛みの出ない範囲でベッド上や室内での軽い動きを始めます。
例えば、寝たまま足首を動かす、痛みが少ない時に室内を歩くなど、無理のない範囲で徐々に活動を増やします。
ただし前屈みになってものを拾う、体をひねって後ろのものを取る、顔を洗うために腰を深く曲げる、といった背骨に負担をかける姿勢や動作は禁止です。床に落ちたものは無理に拾おうとせず、誰かに手伝ってもらうか道具を使いましょう。
また、布団ではなくベッドで生活するのも一案です。ベッドであれば立ち上がる動作が楽になり腰への負担を減らせるため、畳での寝起きが辛い場合は介護用ベッド等の使用を検討します。
痛みが強い間は無理をせず家族や介護サービスなどにサポートを依頼しましょう。
圧迫骨折の再発防止のための対策
一度圧迫骨折を起こすと、再発のリスクが高くなります。しかし、骨粗しょう症の治療、転倒防止対策、筋力維持の取り組みにより、再発は十分に予防できます。ご本人とご家族が協力して実践できる具体的な対策をご紹介します。
家の中の転倒対策を徹底する
骨折の再発防止には、日常生活での転倒予防が不可欠です。高齢になると筋力や平衡感覚が低下し、家の中でも転びやすくなります。
実際、自宅での高齢者の事故原因の8割以上が転倒と報告されており、わずかな段差や滑りやすい床でも大きな障害になり得るのです。
こうした骨折を防ぐため、自宅環境を見直し、転倒リスクを徹底的に減らすことを心がけましょう。
- 部屋や廊下の段差を解消
- 敷居や敷ものなど小さな段差につまずく事故が多いため、段差解消スロープを設置したり不要な敷ものは撤去します。 床にものを置きっぱなしにせず、電気コード類も整理してつまずきの原因を排除します。
夜間のトイレ移動などで転倒しやすいため、廊下や寝室には足元灯を設けるなど十分な照明を確保しましょう。 - 手すりの設置
- 高齢者が歩く経路や立ち座りをする場所に適切に手すりを取り付ければ、自分で体を支えられるので転倒防止につながります。
例えば廊下や階段、お手洗い、浴室、ベッド脇など、動作の起点になる場所には手すりや掴まれるバーを設置すると安心でしょう。 - 移動時には杖やシルバーカー(歩行器)を使う
- 杖や歩行器を使用すれば歩行時の姿勢が安定し、転倒のリスクを軽減できます。
特に屋外だけでなく家の中でも杖を積極的に活用し、ふらつきを感じるときは無理に歩かないようにします。 - 滑り止め対策
- 浴室には滑りにくいマットを敷き、靴下は滑り止め付きのものを使用するなど工夫します。
室内でも踵のある履きものを履き、かかとのないスリッパは避けた方が安全です。 実際、スリッパ着用中に滑って尻もちをつき圧迫骨折に至った例もあります。
このように住環境と生活動線を整えることで、骨折リスクを大きく減らすことができます。
住宅の改修は行政に申請し許可が下りてからの着工となり、許可されないこともあるため、至急対応が必要な場合は福祉用具のレンタルも合わせて検討しましょう。

骨粗しょう症治療で再発を防ぐ
圧迫骨折を経験した高齢者では、骨粗しょう症の適切な治療が再発防止の鍵となります。骨粗しょう症があると軽い衝撃でも骨折を繰り返してしまうこともあるため、治癒後には必ず骨密度検査を行い、必要に応じて専門的治療を始めます。
実際、加齢や骨密度低下に加えて過去の脆弱性骨折の既往があると新たな骨折リスクが飛躍的に高まることが明らかになっています。
日本には約1,000万人以上の骨粗しょう症患者がいると言われますが、治療せず放置すれば骨折を繰り返してしまう恐れもあります。再発を防ぐため、整形外科や内科で処方される骨粗しょう症の治療薬をきちんと内服・継続しましょう。
現在、骨粗しょう症の薬物療法にはビスフォスフォネート、ラロキシフェン、活性型ビタミンD₃、カルシトニン、ビタミンK₂、イプリフラボン、カルシウム製剤などさまざまな薬剤が使われています。
これらの薬は骨の吸収を抑制したり形成を促進したりする作用があり、骨密度の改善に有効とされています。長期的な薬物療法により骨密度が改善し、再発リスクを下げる効果が期待できます。
また、痛みが治まったからといって通院を中断したりせず、定期的に骨密度検査を受けながら適切な管理を続けることが重要です。
筋力維持と生活習慣の工夫
骨と同時に筋力の維持・向上も圧迫骨折の再発予防に大切です。高齢者では太ももや背中の筋力低下により姿勢保持が難しくなり、バランス能力も落ちて転びやすくなります。
筋力が弱いと体を支える力が不足し、ちょっとした動作でも背骨に集中する負担が大きくなってしまう場合があります。そのため、骨折が治癒した後は可能な範囲で筋力トレーニングにも取り組んで行きましょう。
担当医や理学療法士の指導のもと、無理のない範囲で徐々に体を慣らしていくのがポイントです。背筋や腹筋、太ももの筋肉を中心に鍛えることで背骨への荷重を筋肉で支えられるようになり、再び骨折するリスクを抑えられます。
例えば椅子に座ったままできる軽い腹筋運動や、ベッド上での足上げ運動、背筋を伸ばすストレッチ、散歩の際に少し大股で歩く歩行訓練など、日常生活に取り入れやすい運動から始めると長続きします。
また、筋力トレーニングと並行してバランス能力の向上も図りましょう。片足立ちやステップ運動などバランストレーニングを行うことで、転倒しにくい体づくりにつながるでしょう。運動習慣がない方も、最初は簡単な体操を毎日継続することからスタートし、習慣化することが大切です。
一方、生活習慣の工夫も骨と筋肉の健康には欠かせません。骨や筋肉を強く保つには栄養バランスの良い食事が基本です。カルシウムやビタミンD、良質なたんぱく質、マグネシウムなどを十分に摂取し、骨の新陳代謝を促しましょう。
特にカルシウムは牛乳、ヨーグルト、小魚などから、ビタミンDは鮭、イワシなどの魚やキノコ類から効率よく摂取できます。ビタミンDは日光に当たることで体内合成もされるため、適度な日光浴も有効です。
たんぱく質は筋肉の材料になるため、大豆製品や肉・魚、卵などをバランス良く取り入れてください。睡眠や休養をしっかり取り、ストレスを溜めないことも体機能の維持には大切です。
総合的に生活習慣を見直し、運動+栄養+休養のバランスを整えることで、骨折の再発リスクを下げ、健康寿命を延ばすことができます。骨折を機に得た教訓を日々の生活に活かし、無理なくできる範囲で筋力の維持向上と生活習慣の改善に取り組んでいきましょう。
まとめ
高齢者の圧迫骨折は、骨粗しょう症による骨の脆弱化が主な原因で起こる身近な骨折です。適切な治療によりほとんどは手術なしで治癒が期待でき、重度の場合も入院期間も数日から数週間程度となる場合が多いです。重要なのは治療後の再発防止です。
骨粗しょう症の継続治療、家庭内の転倒対策、適度な運動と栄養管理を組み合わせることで、再発リスクを大幅に下げることもできます。できる限りの対策を行い、安全で質の高い生活を維持していきましょう。