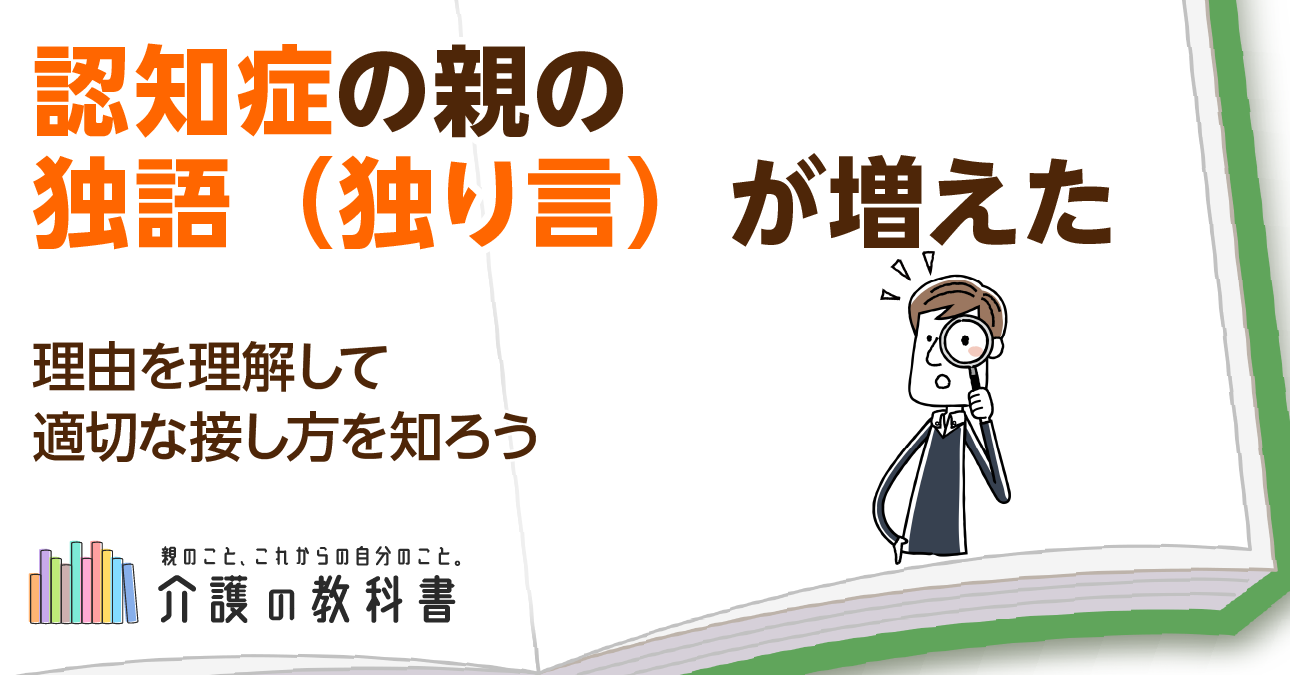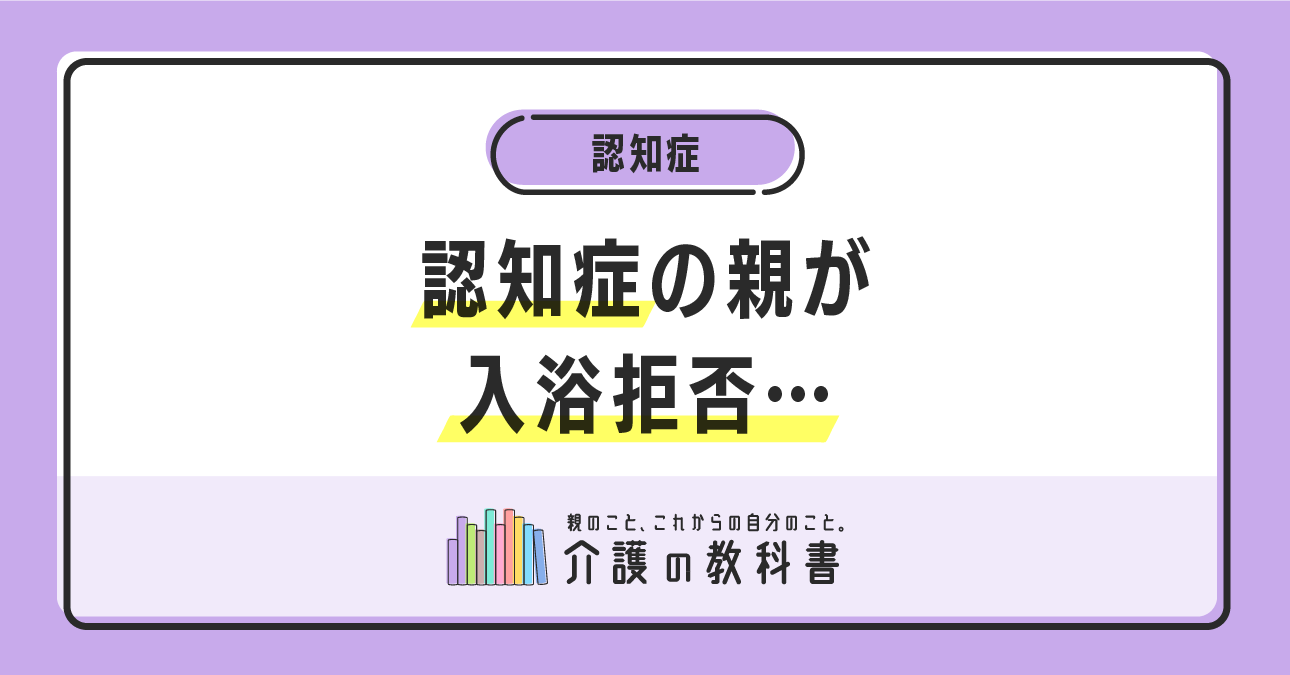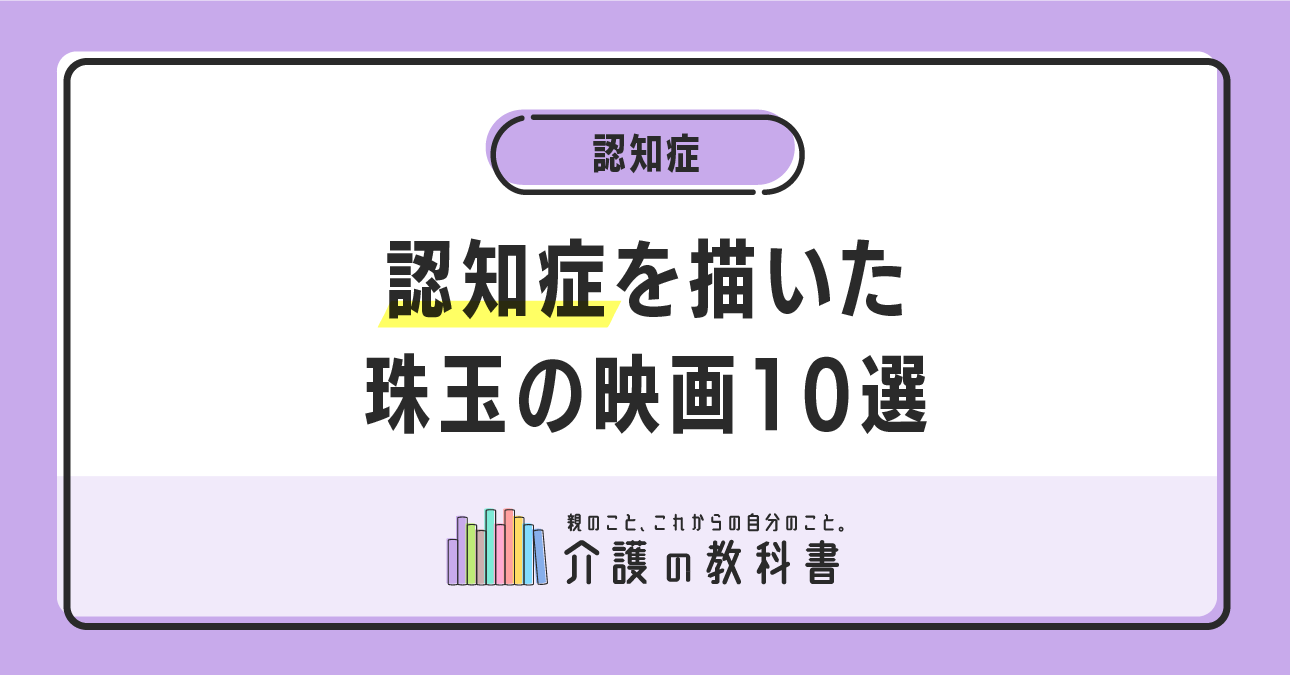こんにちは。デイサービスで看護師として勤務している、認知症LOVEレンジャーの友井川 愛です。在宅介護で奮闘しているみなさんに、看護師目線で認知症介護のポイントをお伝えしていきます。
今回は、4大認知症のなかでも近年、分類方法が変わったことから把握が難しいと言われている「前頭側頭型認知症」についてお話します。
前頭側頭型認知症は3段階に分けられる!

前頭側頭型認知症には、「ピック型」「前頭葉変性型」「運動ニューロン疾患型」の3種類があるのですが、全体の95%はピック型が占めており今回はピック型を主にして説明していきますね。
ピック型はピック病と呼ばれ、前頭葉と側頭葉に限定された萎縮がありピック球という変性組織が大脳皮質に発生する認知症です。特徴として人格変化や脱抑制、反社会的行動がみられ言葉の意味がわからなくなり会話が通じない意味性認知症、言葉の意味はわかるが発語ができない進行性非流暢性失語があげられます。
なぜこのような症状が出るのかというと、前頭葉は理性や意欲、計画性という人間らしい機能を司る部位であり、側頭葉は言葉の意味を理解する言語中枢野がある部位だからです。発症年齢は40~50歳代と若い方が多く男女差はあまりありません。そのほとんどが遺伝性がみられず孤発性と言われています。
では、初期から順に経過と症状を説明していきます。
- 初期
- 初期前頭葉のコントロールが利かなくなるので人格変化がみられたり反社会的行動、嘘を平気でついたり身だしなみに気を使わなくなる、家がごみ屋敷になるなど。また、特有の症状に万引き行為があります。不愛想、無表情、怒りっぽい、面白い場面でもないのに笑う(強制笑い)他人に気を配れなくなり横柄な態度で接するようになります。
- 診察を受けているのに途中でいきなり立ち去る(立ち去り行為)認知症の方に多い徘徊とは違い、周徊(しゅうかい)と呼ばれる一日に何回も同じ道のりを早足で歩き続ける症状があります。また、迷子にならないのも特徴です。
- しかし、問題は歩行中に信号無視をしたり高速道路を逆走するなど脱抑制(衝動性の亢進)がみられることです。また時刻表のように決まった時間に決まった行動する時刻表生活、同じ物(特に甘い物)ばかり食べ続ける常同的食行動、他人の物を勝手に盗って食べたり、口の中一杯に食べ物を詰め込む幼い子供のような行動もみられます。
- 中期
- 言葉が短くなり会話の内容が乏しくなったり、相手が言った言葉をオウム返しするなど、言語障害がみられるようになります。
- 後期
- 食欲低下による体重減少、関節のこわばりから運動機能の低下が起こる拘縮、不潔、精神の荒廃が起こります。
簡単にまとめますと初期は人格変化、反社会的行動が目立ちます。中期は自発性の低下や言語障害がみられ、後期では認知機能や身体機能の低下から衰弱死に至ります。
前頭側頭型認知症の方をケアする方法

次に、前頭側頭型認知症の方に対するケアについてお話しします。まず、初期の段階では短期記憶は保たれておりこの時点でデイケア、デイサービスなどの職員と顔馴染みになっておくと良いです。理由は、身だしなみに気を使わなくなり入浴を嫌うようになります。
在宅でいずれ入浴ができなくなる時期が来てからあわててデイサービスで入浴を考えても、そのときには入浴嫌いになっているのでなかなか入浴してもらえない状況が起こります。相性の良い職員がいますから本人との関係作りも兼ねて初期の段階からデイサービスなどで入浴の習慣をつけておくと良いですよ。
一旦、習慣になればその後も入浴をしてくれるでしょう。これは、前頭側頭型認知症の方の症状を上手に用いているんです。さきほどもお話しした常同行動を上手に用いて同じ事を同じ時間にしてもらうと良いですね。
散歩や運動など本人が嫌がらない内容で行ったり、できることを把握し繰り返し行ってもらい落ち着いてもらう方法もあります。本人の趣味だったことや楽しんでできることをおすすめしましょう。
よく、暴力行為が典型的行動だと言われるのですがこれには理由があります。常同行動を無理やりやめさせようとしたり、生活習慣を邪魔したことから本人は混乱し暴れてしまうのです。いつもの時間にいつも座っているソファーに、他の人が座っていると混乱しますので周りの人が気をつけて誘導しましょう。
立ち去り行為が起きたら事前に本人が興味のあるものを準備しておいて関心をひきましょう。このときに気を付けてほしいことは、「無理やり誘わないこと」と「高圧的に制止しないこと」が重要。止めようとすると返って逆効果になりやすいです。
最後に誤診のパターンについてです。反社会的行為を行うことから、統合失調症と診断される。自発性の低下があることからうつ病、言葉の意味がわからなくなるためアルツハイマー型認知症、ピック病が原因で万引きしても知能検査の点数が良いので認知症と診断されず正常とされるなどがあります。こうした誤診を防ぐためにも病院受診の際は、ご家族も一緒に受診され医師や看護師に説明をしましょう。次回は、脳血管性認知症についてお話ししますね。