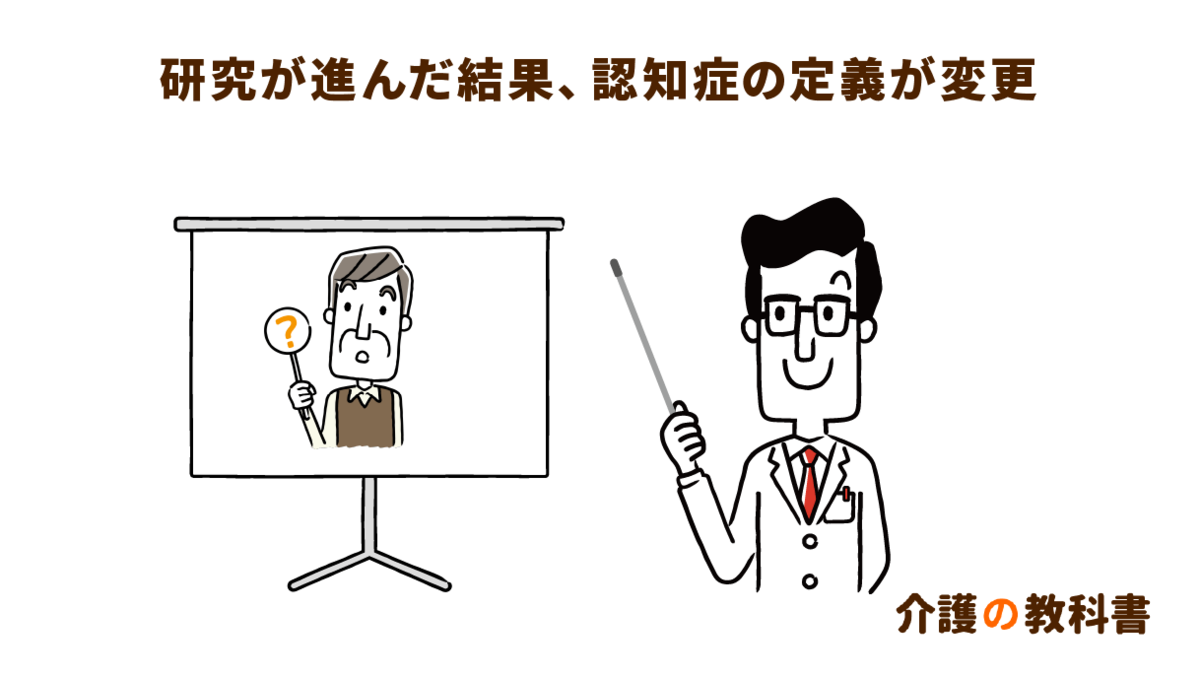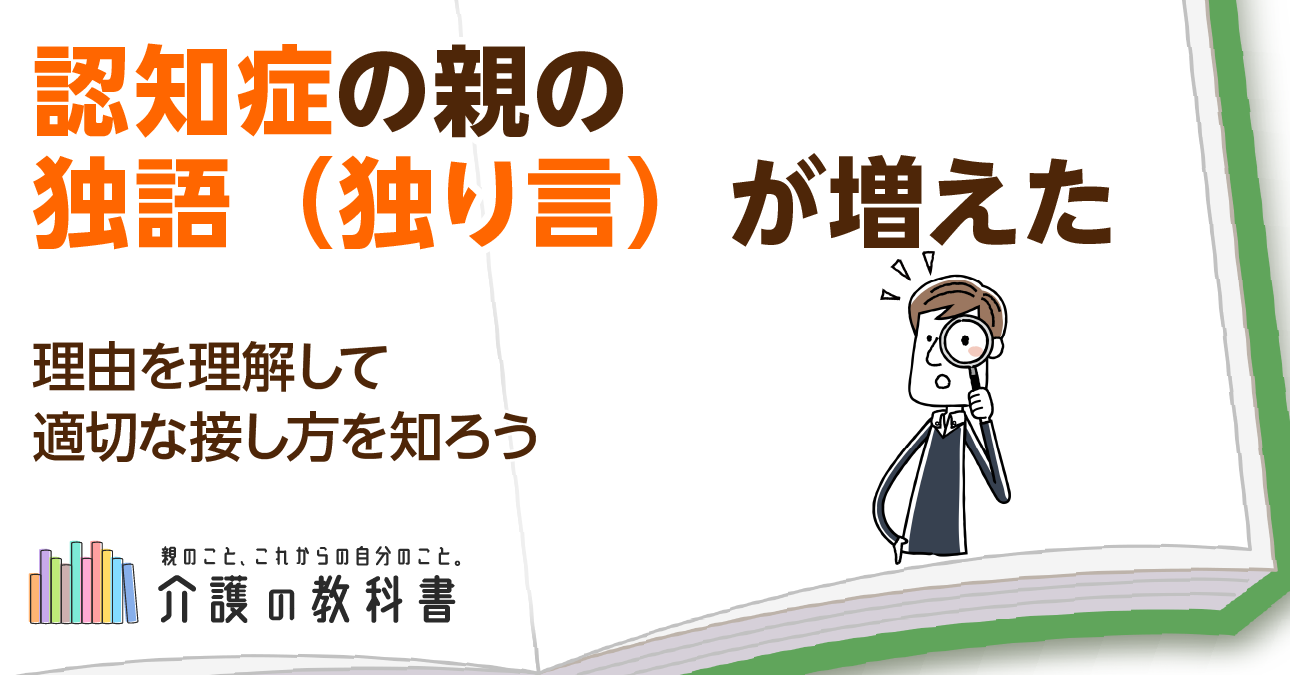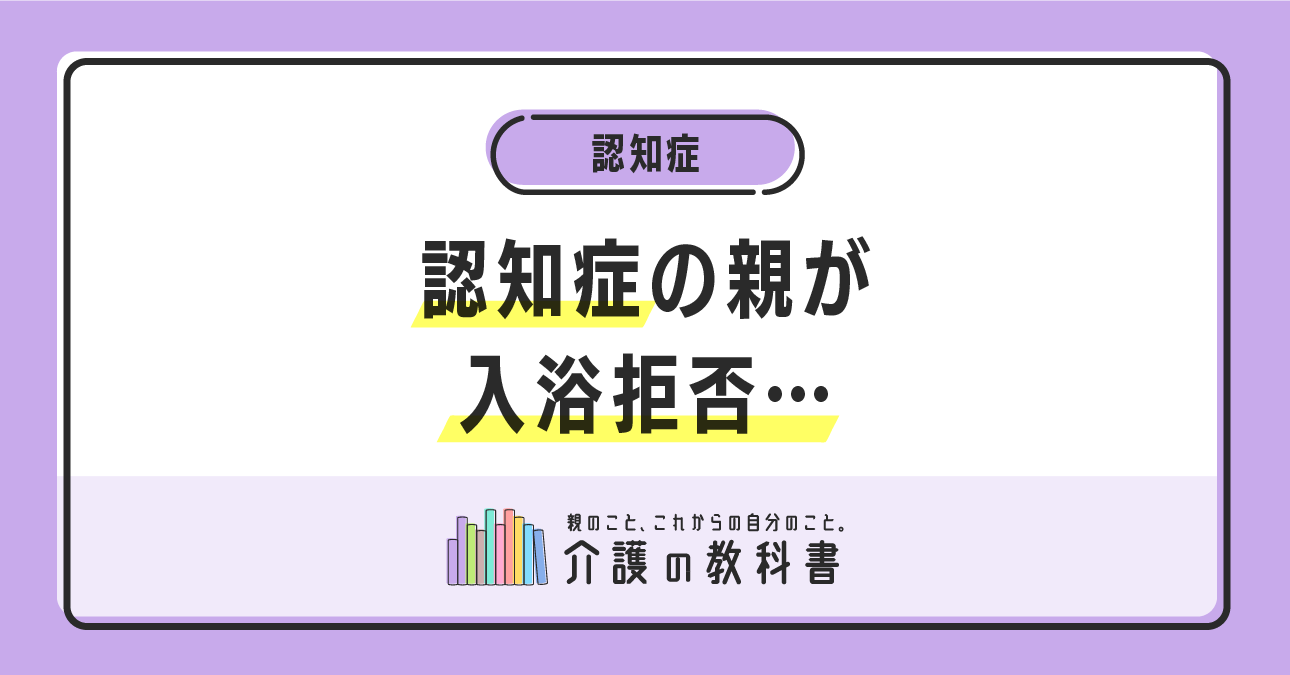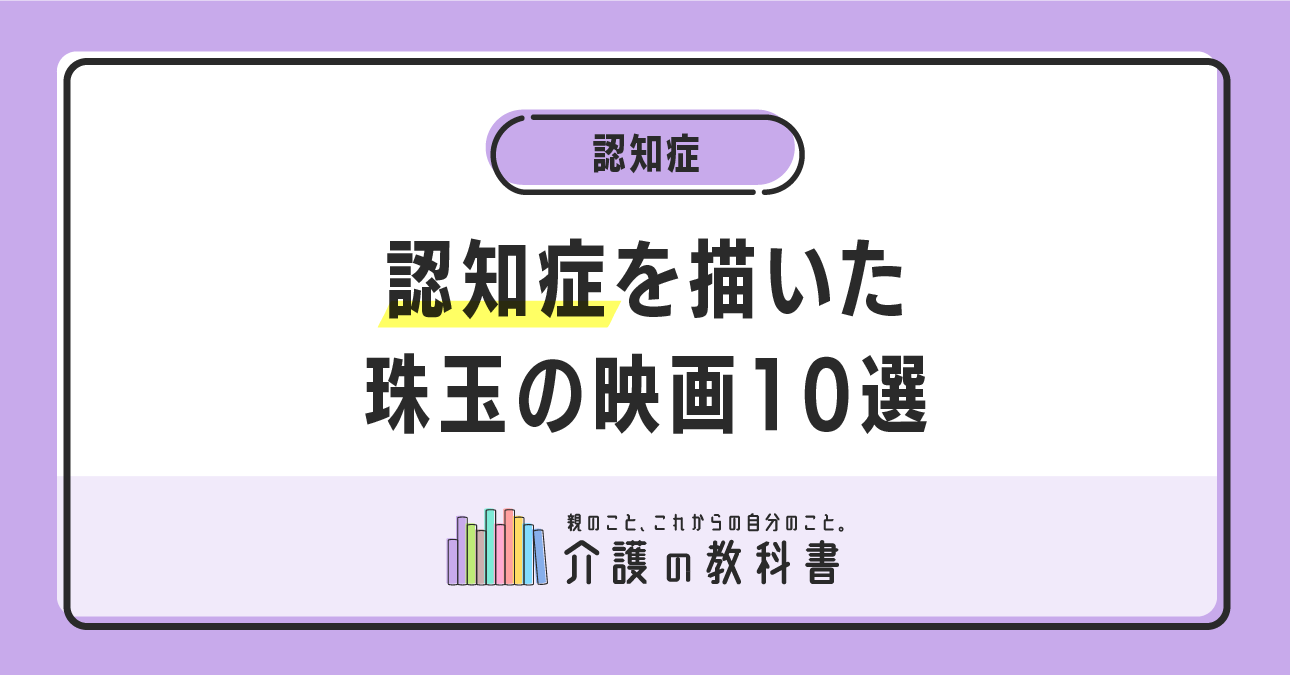株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
ずいぶん前になりますが、第4回の記事の中で、介護保険法(第五条の二第一項)には「認知症の定義」が記されていることを紹介させていただきました。
2021年4月、その定義が介護保険法の一部改正によって変更されました。介護保険法に認知症とはどのような状態を指すのか(定義)が記されるようになったのは、「痴呆」という呼称を「認知症」に変更した2006年の介護保険法改正からです。ですので、15年ぶりに定義が見直されたことになります。
改正のポイントを解説
では、改正前と改正後の認知症の定義を確認してみましょう。
- (改正前)
- 脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいう
- (改正後)
- アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう
読み比べてみると、認知症の「原因疾患の定義の変更」と「脳の器質的な変化の削除」、そして「状態の定義の変更」が行われています。。少しわかりにくいので、文章を2つに分けて改めて変更点を確認してみましょう。
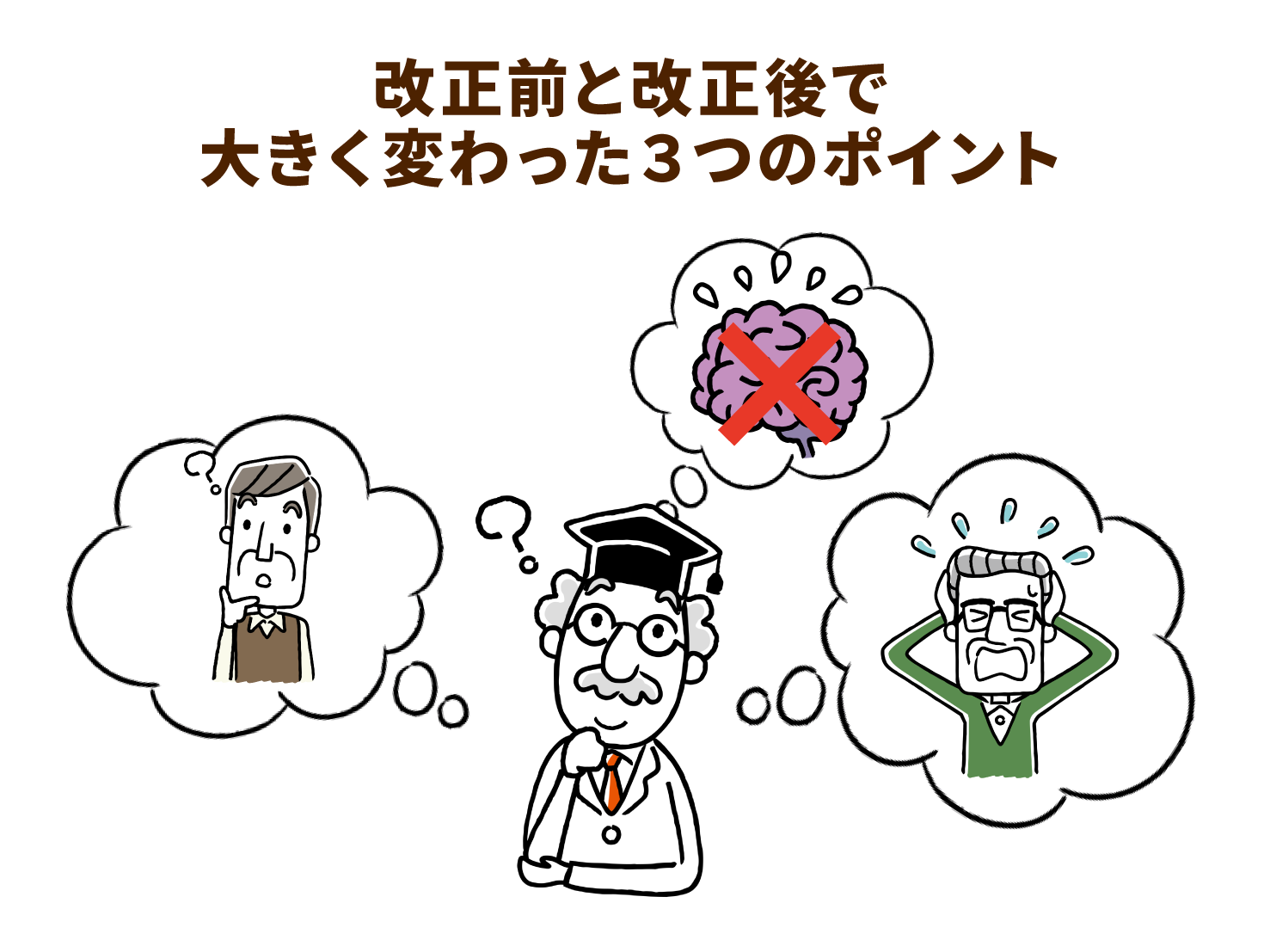
「原因疾患の定義の変更」と「脳の器質的な変化の削除」
(改正前)脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により
(改正後)アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により
近年、アルツハイマー病などは、脳の神経の変性や神経細胞死を伴う病気「神経変性疾患」であるとされています。『認知症疾患診療ガイドライン2017』(日本神経学会)においても同様に分類されていますので、「アルツハイマー病その他の神経変性疾患」と定義したと考えられます。
対して、脳血管疾患は、脳の血管のトラブルによって脳細胞が障がいを受ける病気であり、アルツハイマー病やレビー小体病が分類される神経変性疾患とは異なります。そこで、神経変性疾患と分けた記述にしたのだと思います。
このように、アルツハイマー病などの神経変性疾患と脳血管疾患は、どのような病気なのかが明確になりました。そのため、これまでの「脳の組織や細胞が元の形態にもどらないような変化が起こること」を指す「脳の器質的な変化」が削除されたと考えられます。
「状態の定義の変更」
(改正前)日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいう
(改正後)日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう
おそらく改正前の認知症における「状態の定義」は、世界保健機関(WHO)による国際疾病分類第10版(ICD-10)の認知症の定義を用いたものだと考えられます。ICD-10における認知症の診断基準は、「(1)記憶力の低下、(2)認知能力の低下、が存在し、(1)により、日常生活動作や遂行能力に支障をきたす」とされているからです。
しかし、日本神経学会の『認知症疾患診療ガイドライン2017』内にある「認知症で認められる認知機能障がいにはどのようなものがあるか」では、「注意、遂行機能、記憶、言語、計算、視空間認知、行為、社会的認知」などが、認知機能として挙げられています。記憶機能も認知機能の一つとしているわけです。このように、改正後の認知症の「状態の定義」は、医療現場の診断基準の変化に応じたものだと言えるでしょう。
ちなみに改正後の「日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう」に明記されている政令で定める状態については、介護保険法施行令第一条の二に次のように示されています。
生活習慣病予防が認知症予防にもなる!
ここまで15年ぶりに見直された認知症の定義を確認してきましたが、改正前も改正後も変わっていないのは、認知症そのものが病気ではなく、認知症は病からきた状態(病態)ということです。
(改正前)脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態
(改正後)後天的な脳の障害により、日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態
そして、この状態となる原因をつくるのが以下の通りです。
(改正前)脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因
(改正後)アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患
改正前も改正後も、認知症の予防は「認知症という状態にしてしまう原因疾患(病気:アルツハイマー病、レビー小体病、脳梗塞等)に罹らないこと」であることも変わりません。
ただ、認知症の原因疾患の約70%を占めるといわれる神経変性疾患は、研究が進んできたとはいえ、未だに根治する治療法や治療薬は現時点で存在しません。テレビや雑誌の認知症特集では「認知症の予防には○○を食べると良い」とか、「○○トレーニング、○○体操をやると効果絶大」といったものを見かけますが、「予防の決め手」となるものもありません。
ですが、原因疾患の中でも脳血管疾患に含まれる脳梗塞は予防(罹患の軽減)ができます。脳梗塞の原因は生活習慣病が大きな割合を占めていると言われていますから、「生活習慣病の予防=脳梗塞の予防=脳血管性認知症の予防」ということになるわけです。
それではここで、生活習慣病の予防のポイントをおさらいしておきましょう。
- 喫煙をしない
- 飲酒は適量を守るか、飲まない
- よく噛んで三食を規則正しく食べ、偏食をしない
- 体を多く動かす(まずはよく歩くことが大切。日常生活の活動量を増やして身体能力を高める)
- 睡眠(休養)をしっかりとる(標準的には6~8時間)
- 多くの人、事柄、物に接して、創造的な生活を行うこと
こうして見てみると、生活習慣病の予防は脳梗塞(脳血管性認知症)の予防のためだけでなく、健康寿命を延伸するために必要なことだということわかります。

じゃあ僕はできているかと言ったら怪しいものがいくつも…(笑)。でも、30年近く吸っていたたばこは1年前にやめました。次は、体を動かすことを始めようかと思っている今日この頃です。