皆さん、こんにちは。認知症支援事業所 笑幸 代表の魚谷幸司です。
筆者が経営している事業所は“介護保険では対応できないこと”に特化したサービスを提供している事業所ですが、最近になって増えているご依頼が「高齢者の方の病院への付き添い」です。今回は、利用の流れに沿って注意点をお話したいと思います。
病院に向かう車中で本人の性格や特徴を把握する
まず付き添いの多くは、自宅または施設にお伺いし、介護タクシーに同乗する形で病院へ向かいます。はじめて利用される方の場合、筆者はタクシーの車内で本人がどういった方なのかを掴むようにしています。例えば、お話が好きな方なのかそうでない方か、認知症があるのかないのかなどです。
もちろん、サービスの利用前に利用者の方とお会いしますし、関係者の方からもお話を聞いています。しかし、その先入観にとらわれずに直接お会いしたときの感覚を大切にし、支援に活かすようにしています。

院内で起こる車椅子の事故に注意
病院についた後、院内での対応で1番気をつけているのが「移動中の事故を起こさないこと」です。中でも車椅子を使っての移動となったときはより注意しなければなりません。
理由としては、まず「来院している方のうち、車椅子を意識している方は少ない」ことが挙げられます。人は目線が近ければものを認識しますが、目線より低い位置にあるものに対しては認識が難しくなります。そのため、急に後ろを振り向いた方が車椅子にぶつかってしまうことも珍しくありません。なので、車椅子を押しながら周りの人の動きにも注意する必要があるのです。
また普段は自立歩行している方でも、慣れない場所や長時間での歩行となると車椅子を使われる方もいます。そのとき、車椅子を介助側が押しているにもかかわらず、サービス利用者が「自分でも動かそう」と車椅子の横にあるハンドル(ハンドリム)を操作してしまうケースには注意が必要です。タイヤのすき間に指を挟まれてしまう場合があるからです。
認知症の方でない場合は、ご本人の親切心からの行動なのかもしれません。しかし認知症の方の場合は、手を足の上に置いてもらうか、危険性が予測される場合はハンドリムのない介助用の車椅子を使用する必要があります。さらに、足を乗せている場所(ステップ)から急に足を下ろそうとするのも大きな事故につながる恐れがあります。

待ち時間にはご本人の性格やペースにあった対応を
診察を待つ間は、病院に着くまでの車内で得た感覚を基に対応していくことになります。話し好きの方であれば、待ち時間を短く感じてもらえるように、こちらからいろいろな話をするのも1つの方法です。会話の内容によっては介助側にとってもその人の多くの面を知ることができ、今後の支援に役立ちます。
もちろん、人によっては話をするのが苦手な方や、話しかけられたくない方もいらっしゃいます。そのときは無理に話す必要はありません。日常の場面でもそうなのですが、「何か話さないと」と気負うのではなく、近くにいるだけでも立派な対応だということを覚えておくと良いと思います。なお、これらの対応は帰りの車中でも当てはまります。
ご本人の状態に関する情報を医師に説明しよう
診察では、どのように対応すれば良いでしょうか。ここではまず、自身がどのような立場できているかを医師に伝えることが大切です。今回で言えば「付き添い」となりますが、筆者は家族や施設職員から頼まれてきていることも忘れず伝えるようにしています。
その理由は「付き添い」とだけ答えた場合、「ただの付き添いなんだ」と医師側に思われてしまい、上辺の話しかされない可能性があるからです。きちんとただの付き添いでないことを伝えたうえで、家族や施設職員から聞いたことを、本人の状態を配慮して医師に伝えています。
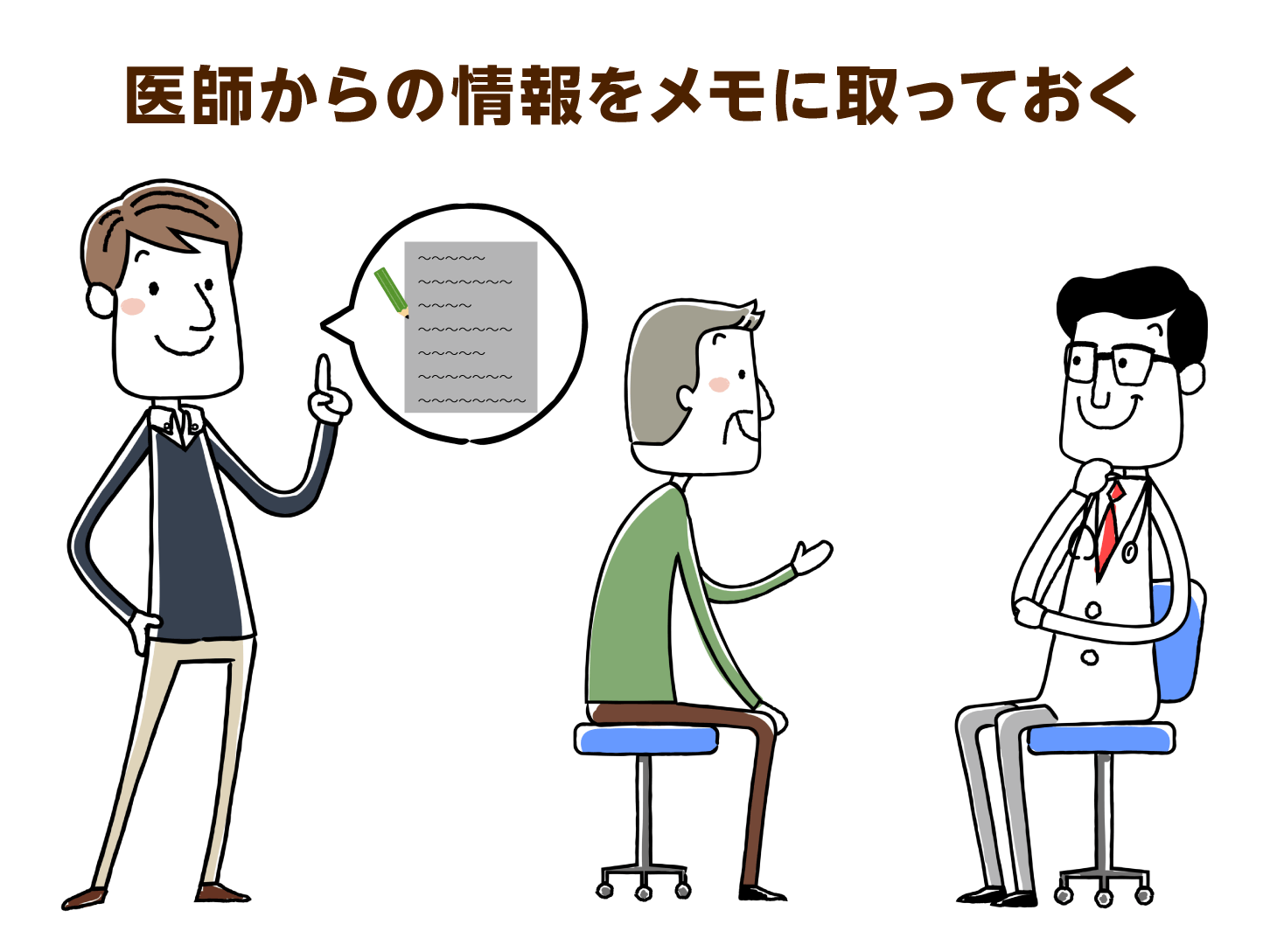
また認知症の方を付き添っている場合、認知症であることを医師などへ伝え適切な対応をしてもらうことも必要になります。そして聞いた必要な情報はメモを取るなどして忘れないようにすることです。
診察を終えて自宅または施設に帰った際に大切なのは、家族または施設職員への報告です。車中や院内での様子、診察で聞いた話は簡潔にまとめましょう。そして、ここでも診察での場面と同様に、本人に配慮することを忘れないようにしてください。





















