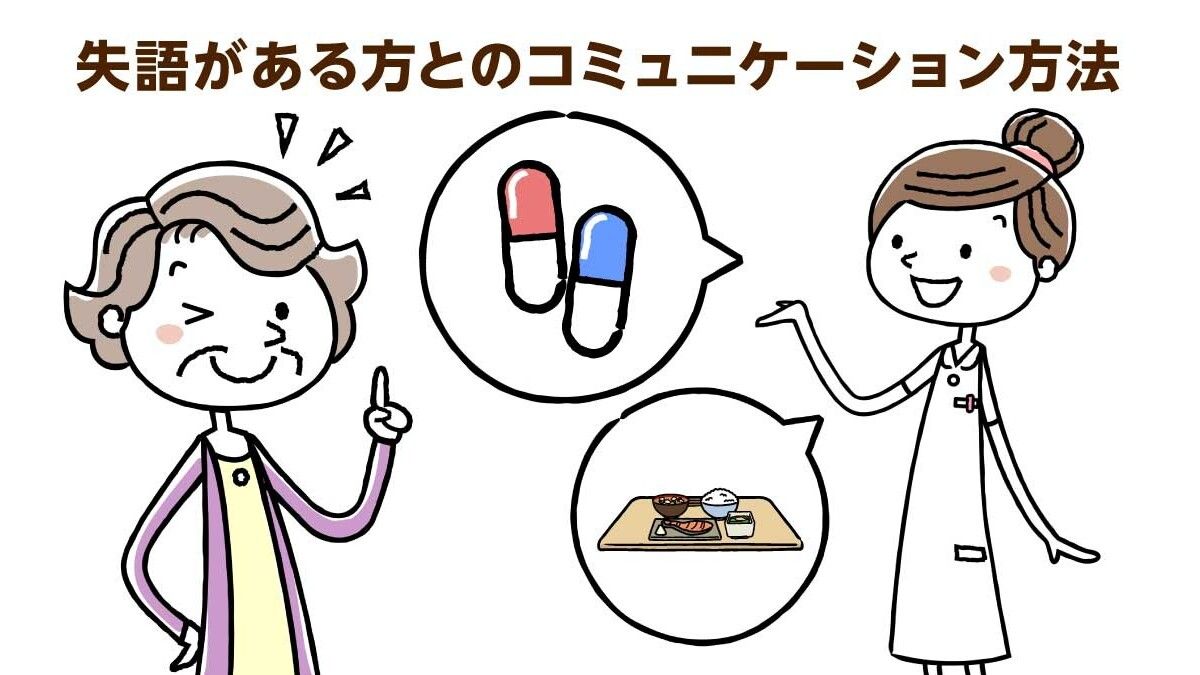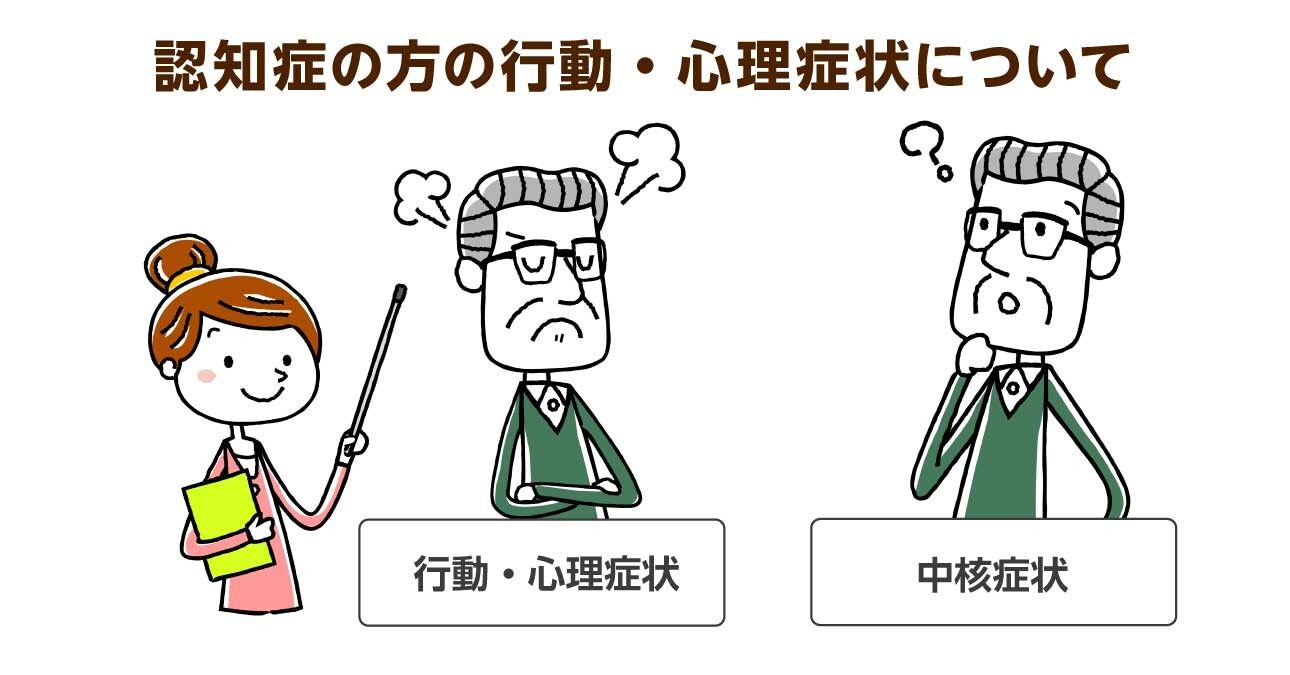こんにちは。特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。
今回は「認知症の状態で失語がある方とのコミュニケーション」について、考えていきたいと思います。
「失語」は中核症状の1つ
認知症になると現れる症状の1つに「中核症状」があります。中核症状とは、脳の細胞が死んでしまい「高次脳機能」が低下することによって現れる症状を指します。この高次脳機能とは、言語や認知・判断、感情などといった人にしかない高度な機能のことです。私たちが目の前にあるものを理解したり今何をしたら良いか判断したり不自由なく言葉を発してコミュニケーションを図ることができるのは、高次脳機能が正常に機能しているからです。
代表的な中核症状の例は、主に以下の通りです。
記憶障がい
覚えていたものを忘れてしまう、新しいことを覚えられない
見当識障がい
時間、場所、人などの認識ができなくなる
失認
視力や聴力などの感覚障がいがないのに、対象を認知できなくなる
失行
手足など身体的な問題がないにもかかわらず、以前できていた行為ができなくなる
失語
聴覚や言葉を発する機能に問題はないが、言葉を理解できなかったり、言語表現ができなくなる
今回は、このうちの「失語」について説明していきます。
ご本人が発する「サイン」を受け取る
まず、認知症状態で失語がある方とのコミュニケーションについて、事例を通してお話いたします。
Aさんはアルツハイマー型認知症の状態で、失語の症状が見られていました。「ご飯を食べませんか?」「トイレに行きませんか?」と意思を確認しても、「食べる」「トイレに行く」という言葉を理解できません。そのため、食事のときは職員が左手に茶碗、右手に箸を持ってご飯を食べる動作をやって見せると、Aさんはご飯を食べてくれます。
違う方ですが、「箸で食べてください」と伝えてもわからない人に箸を持たせると、食べ始める方もいます。このように言葉で伝えても理解が難しくなっている方には、身振り手振りを使うことによって伝わる可能性もあるのです。

本人の行動パターンから読み取る
また、Aさんは排泄について言葉でコミュニケーションをとっても伝わらず、紙に「トイレに行きましょう」と書いても理解が難しい状態でした。しかしAさんとのかかわりを続けていくと、Aさんが時折「自分の鼻をつまむ」行為を見せることに職員が気づきました。職員は疑問に感じ、もしかしたらトイレのサインではないかと考えました。
試しにトイレにお連れしてみると、Aさんは失禁することなくトイレで排尿することができたのです。それまではパット内に失禁することがほとんどで、その都度パット交換を実施していました。これをきっかけに、Aさんが鼻をつまむ行為が見られたときはトイレにお連れするようになったのです。
失語のある方は、自分の思いを言葉で的確表現することが難しい状態になりますが、本人が使える(残っている)能力のすべてを使って、"サイン"を発していることがあります。そのことに専門職が「気づいて」「疑問に感じ」「考え」「実行する」ことが重要です。
相手の能力に応じて表現方法をアレンジ
コミュニケーションをキャッチボールに例えてお話します。キャッチボールは、お互いにボールを投げあって取るものです。仮にあなたがこれから野球未経験の子どもとキャッチボールをするとしましょう。きっと怪我をさせないようにビニール製のボールを選んだり、近距離で下からふわっとしたボールを投げたりするのではないでしょうか。
しかし相手が野球経験者であれば、硬いボールを使用して遠距離から全力でボールを投げることでしょう。コミュニケーションもこれと同じ。相手の能力に応じて、投げ方やスピードなどを意図的に変えるわけです。つまり、投げる側も相手に気配りと配慮をするから、受けては気持ちよくキャッチができるというわけですね。
私たちが対象とする利用者の方は、加齢や疾患などによって、さまざまな能力が低下している可能性がある方々です。特に前述した認知症の状態にある方は、中核症状によってさまざまな脳の機能が低下している状態ですので、コミュニケーションではかなりの気配りと配慮が必要となります。
介護者が対象者の能力や状態を見極めずに言葉を発したりジェスチャーすると、対象者が混乱したり、不安や恐怖感を感じる可能性があるということです。先ほどのキャッチボールに例えれば、野球未経験の子どもに遠距離からスピードボールを投げるようなものです。
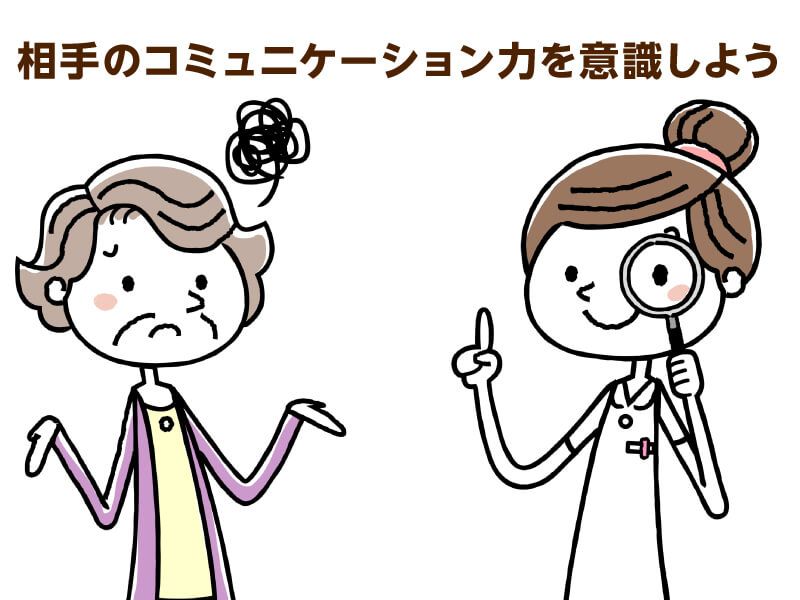
コミュニケーションのポイント7つ
次に、認知症で失語がある方とのコミュニケーションのポイントを紹介します。意識しながらかかわってみてください。
- 1.ゆっくりはっきり話して、答えを急かさない
- 認知症で失語がある方は、情報を理解し判断することが難しくなっています。時間の流れを遅くすることを意識すると、対象者は安心できます。
- 2.対象者の視線や表情に注目する
- 言葉は出てこなくても、視線や表情から対象者の感情を推し量ることもできます。
- 3.話を遮ろうとしない
- 対象者からなかなか言葉が出てこないかもしれませんが、対象者が何を伝えようとしているのか、5秒間待ってみてください。先回りして「○○ですよね?」と決めつけたり、「何が言いたいのですか?」と責めないように意識しましょう。
- 4.身振り手振りなどジェスチャー、写真やイラストを活用する
- 先述した事例のように、言葉ではなく身振り手振りを活用することで対象者に伝わることもあります。写真やイラストなど、視覚的に訴えることも筆者の経験上有効です。
- 5.一文を区切ってシンプルに伝える
- 言葉が理解しにくくなっている状態の方には、「今から食事になりますから、食堂に行く前に洗面所に寄って、手を洗いましょうね」などと一気に伝えても、対象者を混乱させてしまう可能性があります。そのため、一動作につき一声かけましょう。「食事の時間です」「手を洗いましょう」というようにシンプルに伝えることが重要です。
- 6.対象者が理解できる言葉を使う
- 私たちが普段何気なく使うカタカナ言葉や抽象的な表現を、対象者は理解ができない可能性があります。例えば「あっちを向いてください」と言われても、「あっち」がどっちなのか伝わりません。
- そのため、「右を向いてください」と具体的に伝えたり、それでも伝われなければ対象者に向いてほしい側の肩や腕をさすったり、やさしく叩いたりと、指を使って示すのが有効です。
- 7.環境を整える
- 騒々しい場所ではコミュニケーションが図りにくいのが一般的です。できるだけ静かな環境に場所を移したり、対象者が安心して伝えられそうな場所(居室など)を選ぶなど、環境を整えましょう。