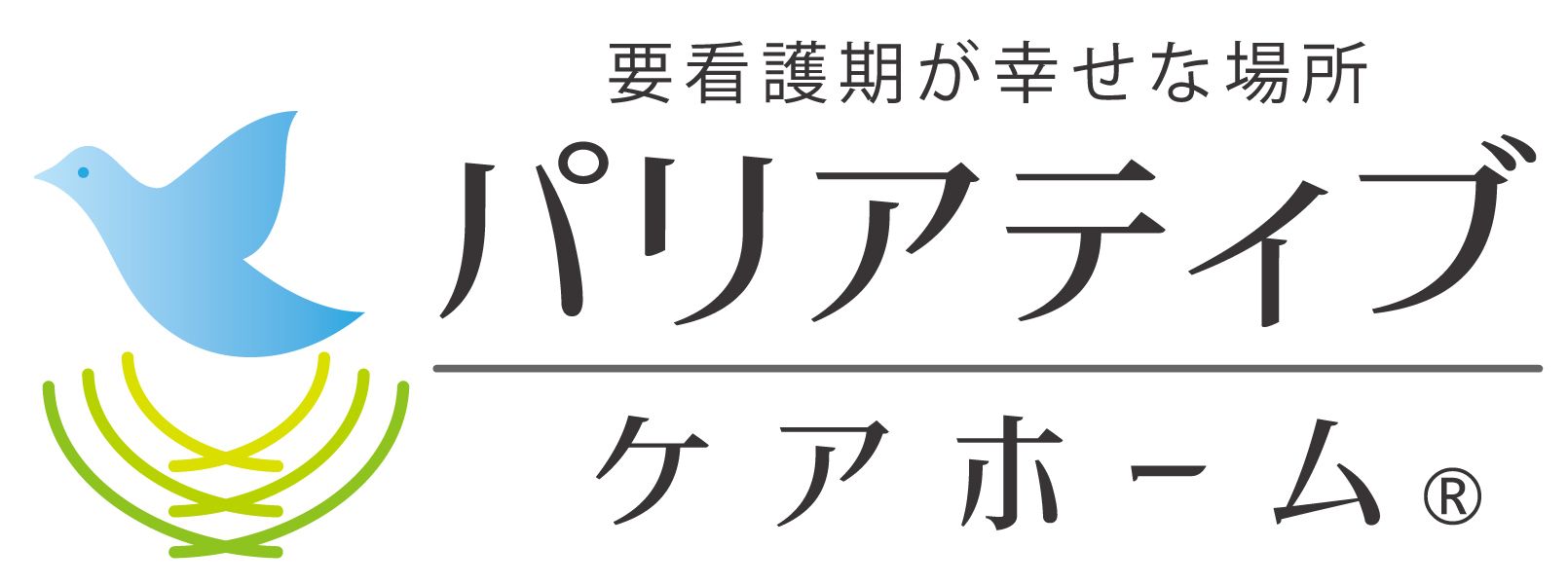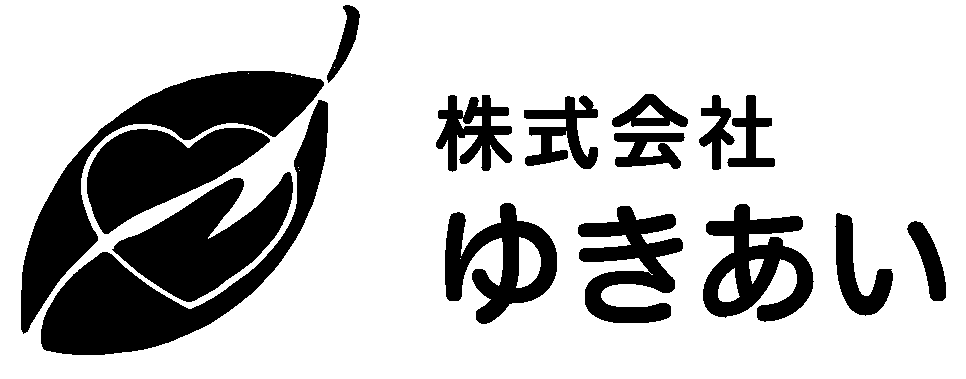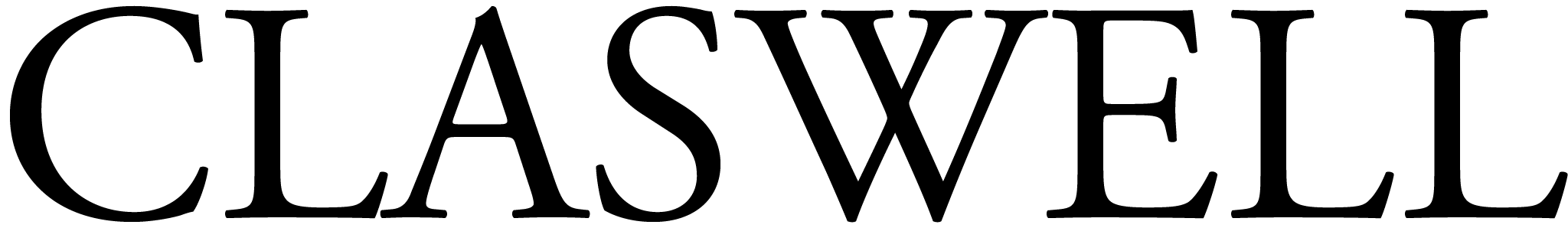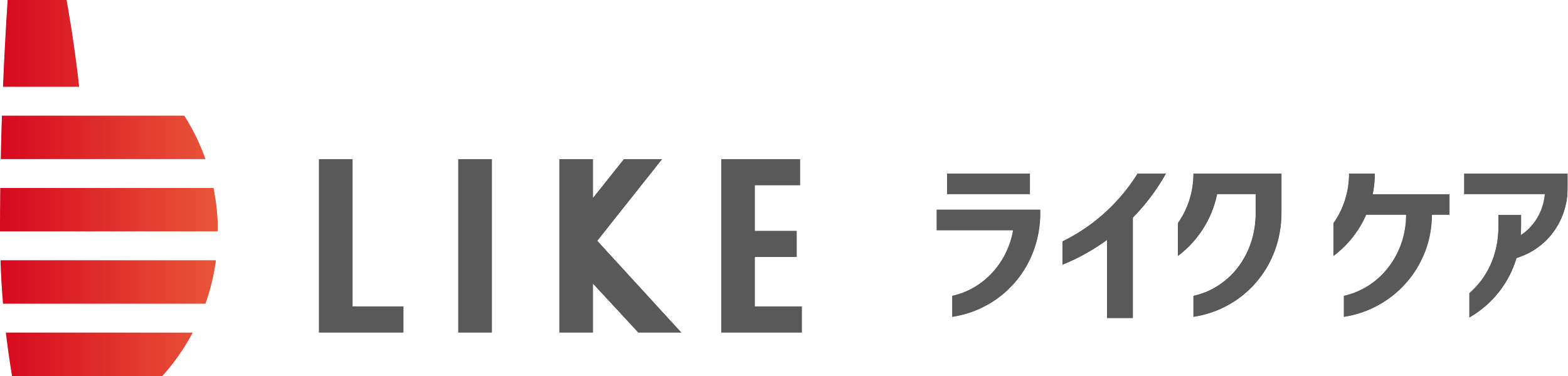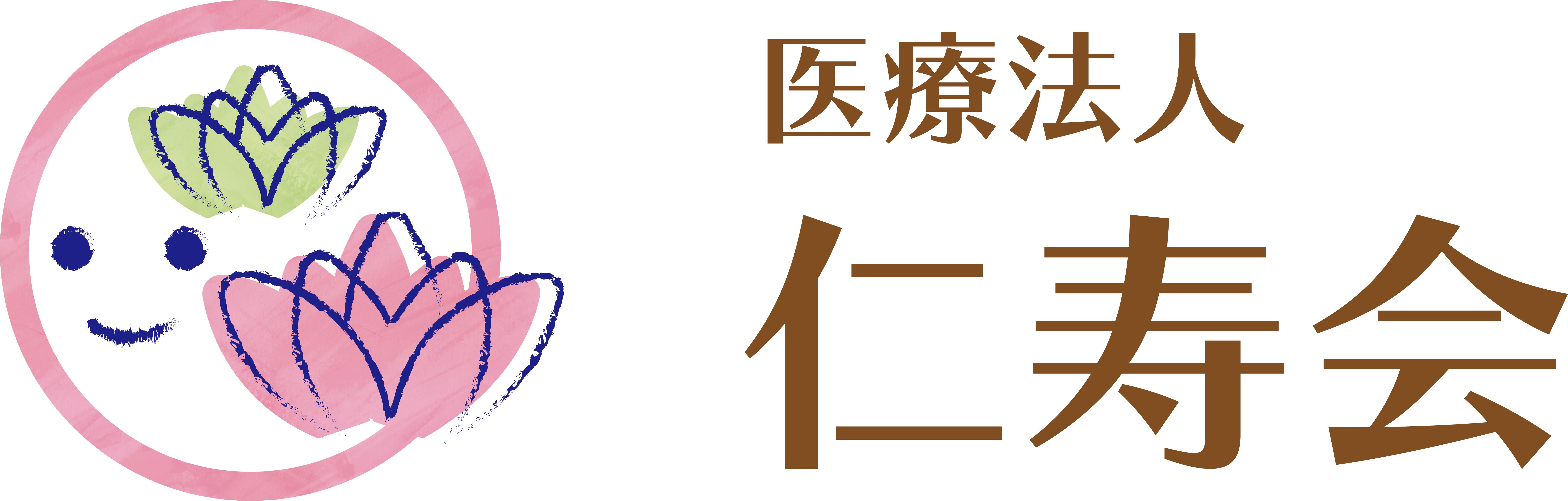言語聴覚士(ST)がいる施設特集
言語機能が低下した方などは、言語聴覚士による回復訓練が受けられる施設を

失語症や聴覚障がい、嚥下機能の低下などの障がいを持つ方の生活を、障がいを持つ前に近い状態に改善できるよう支援する専門家である「言語聴覚士(ST)」。専門領域である“口”の持つ機能に特化したケアを受けられる介護施設は先進的なケアに対する考え方とサービスの充実を図っている施設であると言えるでしょう。嚥下機能障がいや言葉によるコミュニケーションに問題がある方が施設入居を検討する方にとって、こうしたリハビリを受けられる施設はまだまだそれほど多くなく、とても魅力的です。
言語聴覚士がいる老人ホームは貴重な物件!?
言語聴覚士(ST)は、理学療法士や作業療法士と並び、リハビリの専門知識を持つ国家資格保有者です。
例えば、脳卒中など脳血管性疾患により「うまく話せない」などの言語障害を持つ方やこう頭ガンなどで声帯を失い声を出すことが難しい音声障害を持つ方といった言葉によるコミュニケーションに問題がある方だけでなく、筋力低下などにより上手に噛む・飲み込むなどの動作ができない嚥下機能障害を持つ方などが言語聴覚士のリハビリ対象となっています。
「話す」「聞く」「食べる」など言葉によるコミュニケーションや摂食・嚥下に関するリハビリテーションが専門分野となる言語聴覚士は、介護施設はもちろんのこと、医療機関や教育機関でも活躍する専門職と言えますが、まだまだ人数が少ないのが現状です。2016年時点で言語聴覚士の国家資格保有者は2万7,274人。理学療法士が2016年3月末時点で13万9,203人いることを考えると、その数の少なさは一目瞭然です。
| 1999年(4003人) | |
| 2003年(7767人) | |
| 2007年(12564人) | |
| 2011年(18960人) | |
| 2016年(27274人) |
| 医療(69.7%) | |
| 老健・特養(8.0%) | |
| 福祉(7.2%) | |
| 養成校(1.7%) | |
| 学校教育(1.9%) | |
| 研究・教育機関(1.1%) | |
| その他(1.4%) | |
| 不明(9.0%) |
そのため、介護施設でもまだまだリハビリ専門職としての言語聴覚士(ST)は数が少ないのが現状で、今後ますますニーズが高まってくると言える仕事です。
介護現場では貴重な存在とも言える言語聴覚士(ST)ですが、その専門分野は、介護現場でこそ必要とされていると言えるでしょう。
理学療法士や作業療法士が言語聴覚士の資格を併せて保有している場合もあるなど、人によってはより幅広いリハビリニーズに対応するために言語聴覚士の資格を取得する人が増えつつあるとも言われていますから、理学療法士や作業療法士がいる施設でも、併せて言語聴覚士の資格を持つスタッフがいるのかを確認してみるといいかもしれません。
会話や食べる障害がある高齢者には言語聴覚士(ST)のサポートが最適
言語聴覚士(ST)が専門とするのは、「話す」「食べる」と言った口を使うことに対するリハビリです。
国家資格である言語聴覚士の仕事は、一人ひとりのリハビリニーズのある方に対して、適切なリハビリテーション計画を立て、それに基づいたリハビリや生活環境の整備を行うこと。もともと言語聴覚士を指すSTは「Speech Language Hearting Therapist」の略。会話やコミュニケーションに関するリハビリをセラピストとしての立場から行っていく専門職です。
また、会話以外にも読み書きや、口を使って行う「食べる」こともリハビリの大切な要素の一つです。
そのため、例えば脳卒中により失語症や聴覚障害などが見られた方や、老化により嚥下機能が低下した方など高齢者介護の分野でもとても大切な役割を担っっているのです。
会話に障害がある方に対しては、本人への直接的なリハビリテーションはもちろんのこと、家族や介護者がコミュニケーションを取れるように文字盤を使ったコミュニケーション方法を提案することもある言語聴覚士(ST)。食事の際に安全に飲み込む動作ができるよう設備を調整し、姿勢をセッティングするなど設備面での環境づくりといったことは言語聴覚士が活躍する分野です。
そのため、会話や食べることに障害を持つ方は、言語聴覚士がいる介護施設などを選ぶことで、適切なリハビリテーションが受けられることが期待できます。
言語聴覚士(ST)によるリハビリが効果的な疾患は?
「話す」「読む」「聞く」「食べる」など生活に欠かせない動作を改善することを主な目的としている言語聴覚士(ST)によるリハビリは、主に医療機関やリハビリ専門病院などで受けることができますが、近年介護施設でもとてもニーズが高まっています。
言語聴覚士によるリハビリが効果的な疾患例としては事故の後遺症や脳卒中、喉頭がんなどで言語麻痺・摂食障害・嚥下機能低下などが見られる患者さんです。当然ながら、介護施設へ入居する方の中にもこうした疾患をお持ちの方は少なくなく、必然的に言語聴覚士の活躍の場として注目されているのです。
例えば「食べること」に関する障害では具体的に食べ物がうまく飲み込めない、むせてしまう、食べ物が口からこぼれてしまうなどそれぞれの事象に対して原因を特定し、必要に合わせた器官の訓練などを行なっていきます。
また、成人言語障害という、認知症や脳卒中、事故などが原因となる言語機能障害は、患者さん一人ひとりでその原因が異なります。それぞれの障害の発生メカニズムや症状などを加味しながら、適したリハビリ計画を策定し、リハビリが行われる言語聴覚士はまさにコミュニケーションと摂食に関するリハビリの専門家と言えるのです。
言語聴覚士(ST)がいる老人ホームの一日の流れ
実際に言語聴覚士(ST)がいる介護施設ではどのようなリハビリテーションやサポートが受けられるのでしょうか。言語聴覚士の1日を通じて、具体的に言語聴覚士によって受けられるサポートを見ていきましょう。
例えば、朝9:30から始まる失語症の治療では、絵が描かれたカードを使いながら、カードにあるものの名前を言っていくリハビリが行われます。失語症とは、脳卒中などにより言葉を理解したり使うことが困難になってしまう障害です。認知症や脳卒中などにより引き起こされることの多い失語症の症状は、人によって現れ方がそれぞれ異なります。そのため、治療には一人ひとりの入居者の方に合わせた失語症が行われることも少なくありません。
その他にも唇や舌を使って声を出すための構音障害に対するリハビリや、食べることを訓練する摂食・嚥下障害のリハビリ、高次脳機能障害のリハビリなど、多様なニーズに合わせてリハビリを実施します。
なかでも、高次脳機能障害は、脳腫瘍や脳血管障害などによって脳が損傷することで問題が生じた状態を指します。失語症や記憶障害、判断力の低下、時間や場所の感覚がなくなる見当識障害など認知症とよく似ています。認知症と高次脳機能障害の違いは、認知症の場合は進行性であるのに対して、高次脳機能障害の場合早期リハビリにより障害が回復する可能性がある点です。
| 8:40~8:50 | 朝のミーティング |
|---|---|
| 9:00~10:00 | 失語症の治療 |
| 10:30~11:30 | 構音障害の治療 |
| 13:30~14:30 | 摂食・嚥下障害の治療 |
| 15:00~16:30 | 高次脳機能障害の治療 |
| 16:30~17:00 | 記録の作成 |
| 17:30~18:00 | 勉強会 |
介護現場でも混同されやすい高次脳機能障害に対して、適切なリハビリを行える言語聴覚士(ST)の存在は、適切なケアを行うためにもとても大切な存在ということがわかりますよね。
介護スタッフと相談しながら、入居者の方が食事しやすい姿勢を維持するためのアドバイスや、入居者の方とのコミュニケーションをよりスムーズにするための提案なども行う言語聴覚士(ST)。
言語聴覚士を配置している老人ホームではより専門的なリハビリが受けられますが、まだまだ数が少ないのも現状です。今後ますます言語聴覚士が介護現場で活躍していくことが期待されます。