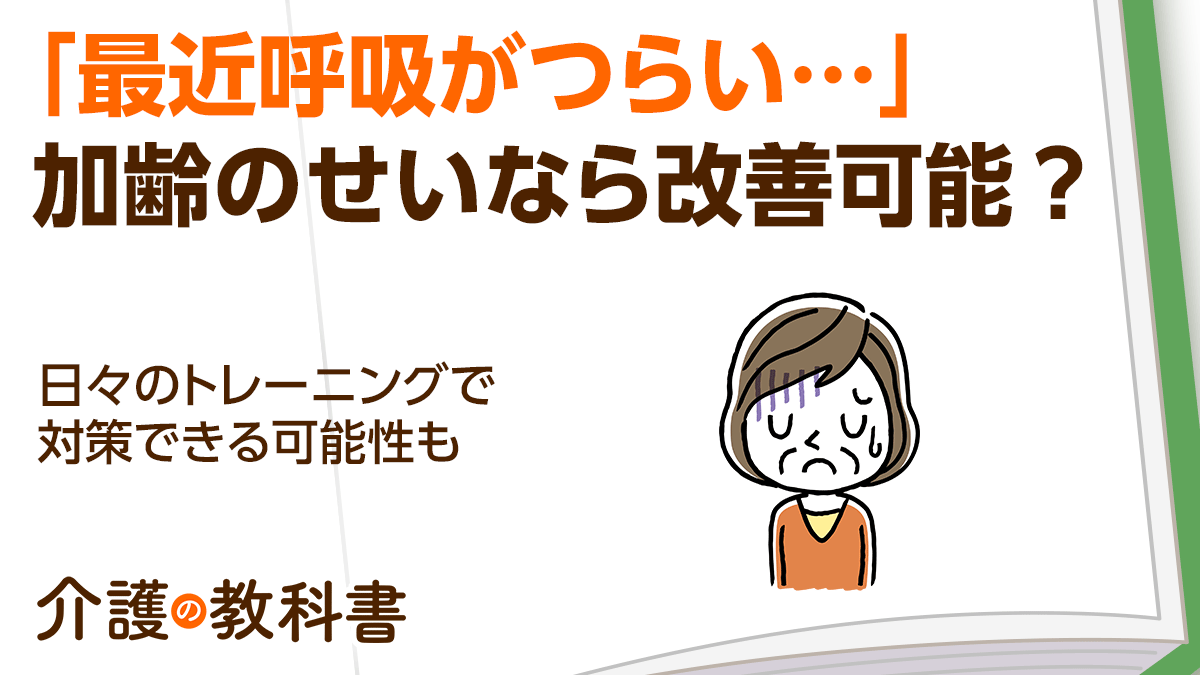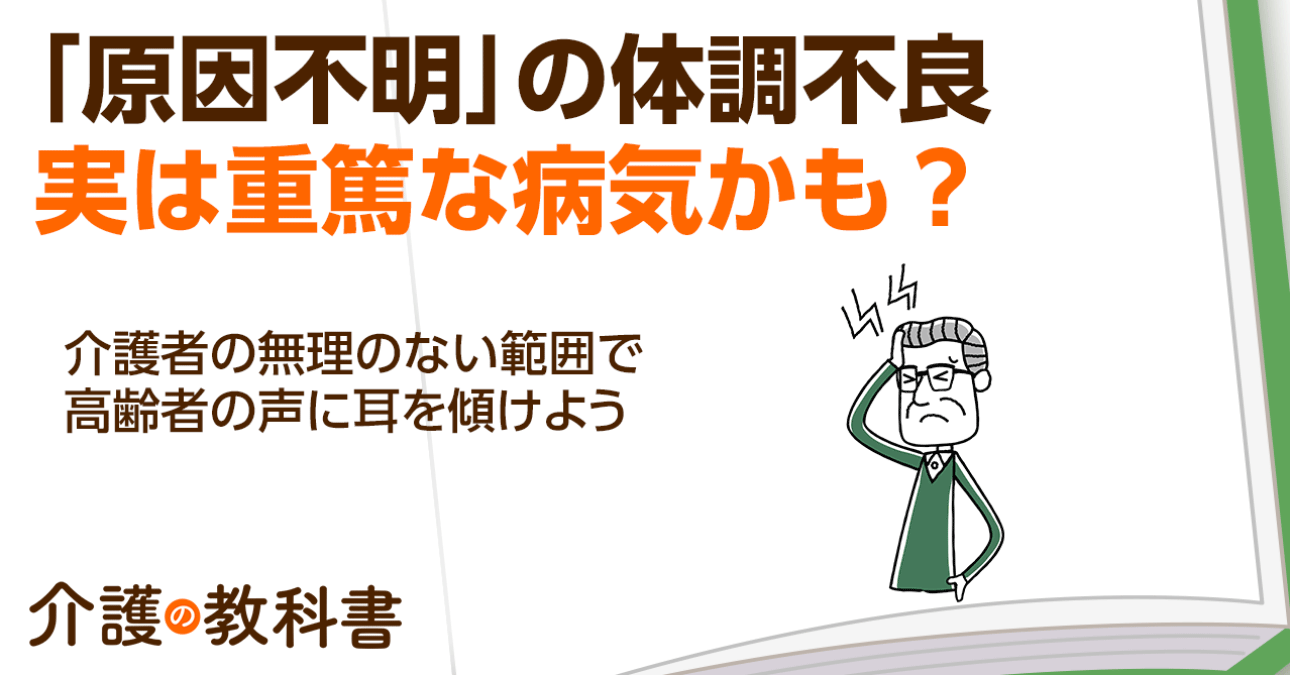動いたときに息苦しさを強く感じるようになると、何かの病気なのではないかと不安になりますよね。息苦しさは呼吸器に関する病気でも現れますが、加齢にともなって生じることも珍しくありません。
この記事では、息苦しさを感じる原因やおすすめの呼吸トレーニングの方法についてご紹介します。息苦しさが現れるきっかけを把握しつつ、解消するための方法を学んでいきましょう。
息苦しさをともなう呼吸器疾患
息苦しさを感じたときは呼吸器疾患を疑う必要があります。それでは代表的な呼吸器疾患についてご紹介します。
気管支喘息
気管支喘息とは、気管が何らかの原因によって慢性的な炎症が起きることで発症します。気管は刺激や慢性的な炎症によって空気の通り道が細くなり、以下のような症状が現れるのが特徴です。
- 呼吸困難
- 咳
- 「ゼーゼー」とした呼吸音
これらの症状は夜から早朝までの時間帯に現れやすいため、就寝中も気管支喘息によって悩まされることも。気管支喘息の原因としては、ダニやカビ、ハウスダストなどのアレルギー反応によるものがあげられます。
COPD
COPD(Chronic Obstructive Pulmonary Disease)は「慢性閉塞性肺疾患」と呼ばれる病気です。肺や気管支などの炎症によって肺の機能が低下して、以下のような症状が現れます。
- 咳
- たん
- 少し動くだけでも息切れしやすい
- 「ゼーゼー」「ヒューヒュー」などの呼吸音
これらは気管支の炎症によって空気が通りにくくなったり、肺へ酸素がうまく取り込めなくなったりすることで起こる症状です。気管支喘息と症状が似ていますが、COPDは進行性の病気なので、処置しないと徐々に状態が悪化していきます。
また、COPDで最も多い原因は「喫煙」という点から、肺の生活習慣病といわれることもあります。そのほかにも、汚染した空気によるものや子ども時代の呼吸器感染、遺伝なども原因の1つです。
間質性肺炎
間質性肺炎とは、肺のなかにある空気を入れ替える働きのある「肺胞」が、炎症や損傷によって線維化して硬くなる病気です。小さな袋のような形をした肺胞が線維化すると、空気を入れ替えにくくなり、体内に酸素を十分に取り込めなくなります。
そのため、運動時に息切れをしやすくなったり、痰をともなわない咳が出たりなどの症状が現れます。間質性肺炎が発症する原因としては以下の通りです。
- ホコリやカビなどを慢性的に吸っている
- 薬物やサプリメントなどによるアレルギー反応
- 関節リウマチや強皮症などの膠原病(こうげんびょう)
なかには原因がわからないケースもあり、それを「特発性間質性肺炎」と呼びます。
心不全
心不全とは、全身に血液を送る働きのある心臓の機能が低下して、さまざま症状が現れる状態のことです。心不全になると血液の循環が不十分となるので、酸素や栄養の共有が追いつかなくなり、以下の症状を引き起こします。
- 運動時の息切れ
- 動いたあとの疲れやすさ
- 呼吸困難
- むくみ
- 体重の増加
動脈硬化や高血圧などの生活習慣病によるもの、先天的な心臓病から派生するものなど、心不全を引き起こす原因はさまざまです。また心不全の種類も1つではなく、心臓のどの場所が悪くなったかによって症状が変わります。
狭心症
狭心症とは、心臓の血管が狭くなり、血流が流れにくくなることで発症する「虚血性心疾患」です。血液が流れにくくなると心臓に酸素や栄養を十分に送れなくなり、心臓の強い痛みや胸の圧迫感などの症状が現れます。
これらの症状は前触れなく突然出現することもあり、数分から十数分ほど持続します。
血管が完全に詰まって血液が流れなくなる「心筋梗塞」も虚血性心疾患の1つです。こちらは最悪の場合死に至る危険性もあるので、早急な処置が必要です。
狭心症を含めた虚血性心疾患のおもな原因は、以下の3つだといわれています。
- 喫煙
- 高いコレステロール値
- 高血圧
加齢によって息苦しくなることも
息苦しさを覚えるのは、呼吸器疾患を発症したときだけではありません。加齢によって身体機能が低下すると、徐々に息苦しさが現れることもあります。その原因として、以下のような呼吸に関係する機能の低下が考えられます。
- 肺機能の低下
- 胸郭の可動域制限
- 呼吸筋の筋力低下
肺の機能が低下すると、酸素をうまく取り込みにくくなるため、運動時に息が苦しくなったり疲れやすくなったりします。胸郭の動きが悪くなると酸素を取り込んだときに胸が広がりにくくなるため、肺活量が低下する原因にもつながるでしょう。また呼吸するために必要な筋肉が衰えると、酸素を十分に取り込めなくなります。
先ほど紹介した呼吸器疾患に心当たりがない場合は、加齢による影響を疑ってみましょう。
息苦しさの程度を把握するための評価
息苦しさの程度を把握するために、医療機関では以下のような評価が用いられています。
- MRCスケール
- 修正Borg Scale
MRCスケールは呼吸困難の程度を、修正Borg Scaleは運動時のきつさを測るための評価法です。それぞれの評価内容についてご紹介します。
MRCスケール
MRCスケールでは日常生活の活動能力について0~5の6段階に分かれています。
| グレード0 | 息切れを感じない |
|---|---|
| グレード1 | 強い運動で息切れを感じる |
| グレード2 | 平地を急ぎ足で歩く、緩やかな坂を登るときに息切れを感じる |
| グレード3 | 同年代の人よりも平地歩行で歩くスピードが遅い。または自分のペースで歩いても息切れで休む必要がある |
| グレード4 | 約100m歩いた後に息切れで休む必要がある。または数分間歩いた後に息切れで休む必要がある |
| グレード5 | 息切れが強くて外出できない。または衣服を着脱するときでも息切れする |
修正Borg Scaleでは、運動中の主観的なきつさについて0~10までの12段階で評価します。
| 0 | なんともない |
|---|---|
| 0.5 | 非常に楽 |
| 1 | かなり楽 |
| 2 | 楽である |
| 3 | 中ぐらい |
| 4 | ややきつい |
| 5 | きつい |
| 6 | |
| 7 | かなりきつい |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | 非常にきつい |
息苦しさを軽減するためのトレーニング方法
胸郭の可動域訓練
加齢によって胸郭周囲の筋肉が硬くなって可動域が制限されると、横隔膜をはじめとした呼吸筋の筋力低下につながります。胸郭の硬さによる息苦しさを改善するために、可動域訓練で筋肉をストレッチして酸素を十分に取り込めるようにします。
胸郭の可動域訓練の内容は以下の通りです。
【可動域訓練のやり方①】
- あお向けになって両膝を立てる
- 両手を持った状態で息を吸いながら頭の上まで手を上げる
- 手を上げたら息を吐きながら下げる
- 2~3の手順を10回、2~3セット行う
肩に痛みがある方はムリのない範囲で動かしましょう
【可動域訓練のやり方②】
- 座った状態で肩に手をつける
- 円を描くように肩甲骨を10回ほど回す
- 反対向きで10回ほど回す
- 2~3の手順を2~3セット行う
こちらの運動も肩の痛みが出ない範囲で動かしましょう
有酸素運動
有酸素運動をすることで心肺機能が高まり、息切れの改善につながります。そのほかにも、有酸素運動は生活習慣病をはじめとした病気の予防も期待できるでしょう。有酸素運動には水泳やジョギング、サイクリングなどがありますが、そのなかでも高齢者におすすめなのがウォーキングです。
運動の目安としては軽く汗ばむ程の負荷量で1回15分以上、週に3回以上行うのが理想的です。最初のうちは時間や頻度を落としてもかまいませんので、少しずつ有酸素運動に慣れていきましょう。
筋力トレーニング
筋力が低下すると息苦しさが助長されるので、有酸素運動と一緒に筋力トレーニングも行うのがおすすめです。筋力トレーニングの内容は以下の通りです。
【スクワット】
- 肩幅よりやや広く開きながら立ち、手すりや椅子などの支えを持つ
- 背筋を伸ばしたままゆっくりと息を吐きながら膝を曲げる
- ムリのない範囲まで曲げたら、ゆっくりと息を吸いながら膝を伸ばす
- 2~3の手順を10回、2~3セット行う
スクワットは膝を曲げすぎると痛みを生じる恐れがあるので注意してください。
【立った状態の腕立て伏せ】
- 壁の前に立ち、両手を壁につける
- ゆっくりと腕立て伏せを行う
- 10回を2~3セット行う
【腹筋のトレーニング】
- あお向けの状態で両膝を立てる
- おへそを見るイメージで頭を上げる
- ゆっくりと頭を下げる
- 2~3の手順を10回、2~3セット行う
まとめ
息苦しさは呼吸器疾患によるものだけでなく、加齢によって身体機能が衰えるときにも現れます。そのため、普段の日常で運動をする機会が少ない方は注意が必要です。
加齢による息苦しさを改善するためには、呼吸に関するトレーニングを習慣にすることが大切です。最近息苦しさを感じる方は、今回の記事を参考にしてトレーニングを行ってみましょう。
【参考文献】
独立行政法人国立病院機構“気管支喘息(喘息)”(参照2023-06-19)
近畿中央呼吸器センター 診療部“気管支喘息”(参照2023-06-19)
東京都福祉保険局“COPD (慢性閉塞性肺疾患)”(参照2023-06-19)
兵庫医科大学病院“間質性肺炎”(参照2023-06-19)
国立研究開発法人国立循環器研究センター“心不全”(参照2023-06-19)
国立研究開発法人国立循環器研究センター“虚血性心疾患”(参照2023-06-19)
厚生労働省“狭心症・心筋梗塞などの心臓病(虚血性心疾患)”e-ヘルスネット.(参照2023-06-19)
齊藤正和、作山晃裕、森沢知之、髙橋哲也.「加齢に伴う呼吸・循環・腎臓機能の変化」『医学療法学』2014,第48巻第5号p.542-547
中村健、岡村正嗣、佐伯拓也「特集 息切れのリハビリテーション 2.息切れの評価法」.『Jpn J Rehabil Med』2017,p.2-3
厚生労働省“心肺持久力(しんぱいじきゅうりょく)”e-ヘルスネット.(参照2023-06-19)
髙橋仁美、菅原慶勇、本間光信、佐竹將宏、塩谷隆信「運動療法─在宅での継続を目指して─」.『日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌』2007,p.1