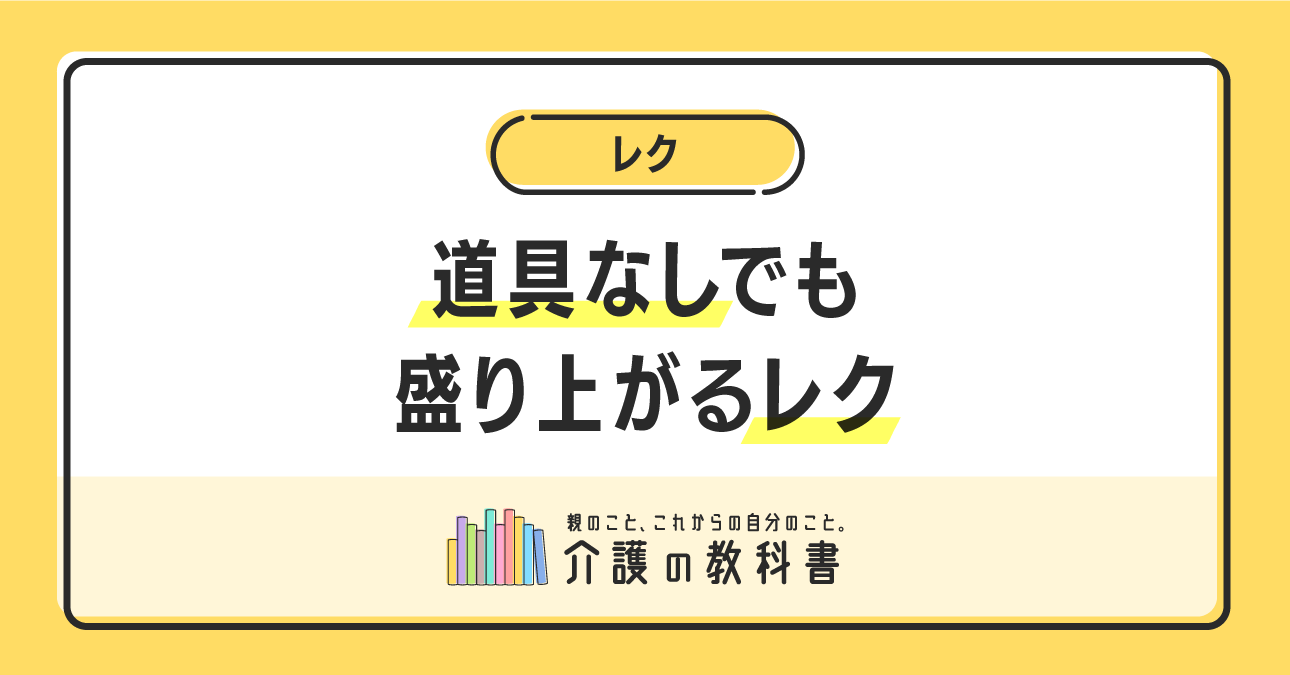全国からのご意見第一位 「家庭でも出来るトレーニングを教えてほしい」
「1分でわかるやさしい介護の教科書」レクリエーション分野を担当する介護エンターテイナーの石田竜生です。日本全国を周り、介護施設に笑いあふれる体操を届ける活動や、レクリエーションやリハビリの技術や知識を研修で伝えてきました。
私のイベントに参加してくれるのは、介護施設で働く介護職やリハビリ職。ケアマネ、地域サロンで活動する一般の方もいれば、介護を必要としている高齢者やそのご家族など。 さまざまな立場の人達からたくさんの生の声を頂きます。
- その中でも上位に入るのがコチラ
-
- 家にいるおじいちゃんおばあちゃんが何もやることもなくボーっとしているだけ。
- 寝転びながらずっとTVを見ているだけ。
- 週に数回介護施設に通ってくれても、家で動いてくれないとリハビリの効果が無い気がする。
- 地域のサロンで体操教室を開いても、そこまで通うことが出来ない人がたくさんいる。
そう、家にいる間に「何もしていない」高齢者がとても多いのです。特に、車がないと生活できない地方では、高齢者はスーパーに買い物に行くこともできません。地域のサロンにも通えません。唯一外に出ていくのは週に数回の介護施設。そこでリハビリをしたとしても、家に帰れば引きこもっているだけなのです。
外に出ることが少なくなれば、身体が衰える。
↓
身体が衰えると運動をする意欲がなくなっていく。
↓
運動をしなくなると出来ないことが増えていく。
↓
今まで出来ていたことが出来なくなると「健康な人には会いたくない」「なぜ私だけ」と、精神的にも落ち込んでいき、さらに家に閉じこもるようになる。
↓
刺激のない時間が増えると脳も衰えていき認知症のリスクが高まる。
↓
さらに運動する気力がなくなる。

このような負のサイクルが高齢者の心身機能を低下させていきます。負のサイクルを断ち切るには「家庭でも出来る運動やリハビリ」を継続してもらうことが重要です。
本連載では、「家庭でも出来る脳と身体のトレーニング」を紹介していきます。ご家族みんなで出来て、簡単なのに心身ともに元気になるようなものを提案できたらと思います。 もちろん介護施設でも応用できますので、介護施設で働いている皆さんは、レクリエーションや体操の時間に利用者さんに実践してみてください。
「家庭でも出来る脳と身体のトレーニング」は、どんなものが理想なの?
本連載が目指す「家庭でも出来る脳と身体のトレーニング」3つのポイントです。
①簡単にできる
誰でもすぐに出来ないとトレーニングは長続きしません。○○筋を刺激しながら△△筋を意識して、呼吸は◆秒で息を吸いながら……なんていわれても無理ですよね。
専門家が家まで来てくれるわけではないのですから。ベッドの上でも出来て、寝室で椅子に座って出来て、リビングで家族と一緒に出来る。そんな脳と身体のトレーニングを紹介していきます。
②使用する道具が身近なモノ
新聞紙やペットボトル、タオルなど、どこの家庭にもある道具や、100円ショップの商品を使ったトレーニングを提案していきます。
iPadなどのタブレット端末を使った脳トレ、最新のリハビリ機器を使った体操、数十万円のトレーニングマシーンで筋力トレーニングなど。効果は期待できるかもしれませんが、当然一般家庭には存在しません。 (タブレット端末はあるかもしれませんが、使いこなせる高齢者は少ないでしょう)
100円以内のアイテムで数十万円のトレーニングと同等の効果を目指す!「100均トレーニング」も紹介していきますのでご期待ください。
③家族間のコミュニケーションが図れるもの
せっかく「家庭で出来る」なら、家族みんなで取り組めたらいいですよね。みんなでやればきっと会話も増えていくでしょう。おじいちゃんおばあちゃんの意外な表情も見ることができるかもしれません。
何より家族全員の介護予防にもつながります。 一人でのトレーニングは意欲が湧きにくいので、なかなか継続しません。家族みんなの力が必要です。
道具を使わず認知症予防!家族とのコミュニケーションも増える『いぬねこ体操』
「家庭でも出来る脳と身体のトレーニング」第1回目『いぬねこ体操』
●準備物
特になし
●効果・ねらい
認知症予防 家族とのコミュニケーションUP
●ポイント
「瞬時に頭で考え答えを出すこと」は認知症予防にとても効果的です。
道具を使わずに言葉だけで簡単に出来ます。
笑いが生まれるので家族間のコミュニケーションにも最適です。
詳しくは動画をご覧ください。
熱血主婦!香織の介護奮闘物語 -いぬねこ運動編-
『この物語は、ある家庭の介護問題に戦いを挑んだ、熱血主婦の記録である。一般家庭においては、全く介護知識のない無名の主婦が、荒廃の中から健全な精神を培い、わずか数年で義母の健康と、家族関係の回復を成し遂げた奇跡を通じて、その原動力となった信頼と愛とトレーニングを、余す所なくドラマ化したものである。』(スクールウォーズから引用)
香織は義母(梅子)との関係に悩んでいた。最近物忘れの激しくなってきた梅子。本人もそれに気がついているようで、将来に不安を抱えているようだ。次第に自室に引きこもるようになり、どこかイライラしているようにも感じる。そのせいか二人の会話も減っていき、生活する上で必要最低限のやり取りしかしなくなっていった。
コミュニケーションとは他愛もない一言から始まる。だが、香織にも梅子にもその余裕はなかった。
もともとは上手くいっていると思っていた。そう半年前、夫の携帯を覗くまでは。携帯の着信履歴には確かにあの女の名前があった。香織は知ってしまったのだ……
(話を元に戻そう)
香織の目を遮るものは深い霧。とにかく香織は、先が見えない梅子との関係性も、梅子の健康状態も、考えるだけで筆舌に尽くしがたい不安に襲われるのであった。 部屋に引きこもりボーっとしているだけの梅子を何とか救いたい。まずは会話から始めてみよう。
香織は深い霧の中から一歩を踏み出したのだ。
『いぬねこ体操』方法
- STEP①まずは動機づけから始まります。
-
動機づけとは簡単にいえば「行動を起こさせるためのきっかけ」です。急に「体操をしましょう」と言われても「なんでそんなことしないといけないの?」と疑問を感じてしまいます。人は理由がなければ動きません。なぜそのトレーニングをするのか。トレーニングをすることでどうなってもらいたいかを説明しましょう。相手が納得してからがスタートです。
例)
香織:おかあさん、最近物忘れするようになったって言っていましたね?
梅子:そうだね~。このままボケていくのかしら…
香織:不安になりますよね。でもね、脳を刺激していくような体操をしていくと良いんですって!お医者さんも脳を刺激することで認知症の予防になるって言っているのよ。(←医者・NHKなど高齢者の信用に繋がるキーワードを入れるのもポイント)
梅子:でも面倒くさいことはしたくないよ。
香織:大丈夫。何もいらないの。私の質問に答えるだけでいいんです。
梅子:そうなのかい。じゃあやってみようかね… - STEP②犬と猫の鳴き声を聞き取ります。
-
例)
香織:おかあさん犬ってどんな風に鳴く?
梅子:ワン?
香織:そうですね。じゃあ猫は?
梅子:ニャーだね
香織:そうそう! - STEP③犬と言ったら「ワン」猫と言ったら「ニャー」と答えるルールを説明します。
-
例)
香織:じゃあ私が犬と言ったらワン、猫と言ったらニャーと言ってくださいね。
梅子:(うなずく)
香織:犬
梅子:ワン
香織:犬
梅子:ワン
香織:猫
梅子:ニャー
(同じように数回繰り返す) - STEP④次は動物の「鳴き声」に対して、その鳴き声の「動物」を答えてもらいます。
-
例)
香織:次は、私が鳴き声をいうから、その鳴き声の動物を言ってね。だから、「ワン」と言ったら「犬」だし、「ニャー」と言ったら?
梅子:「猫」ね。
香織:そう! じゃあニャー
梅子:猫
香織:ワン
梅子:犬
香織:ワン
梅子:犬
香織:ニャー
梅子:猫
(同じように数回繰り返す) - STEP⑤最後にランダム(無作為)に『動物を言ったら「鳴き声」』『鳴き声を言ったら「動物」』をランダムに質問していきます。
-
例)
香織:じゃあ今度はぐちゃぐちゃに言っていきます。だから動物を言ったら「鳴き声」、鳴き声を言ったら「動物」を答えてもらいたいの。
梅子:難しそうね。でもやってみるわ!
香織:ワン
梅子:犬
香織:ワン
梅子:犬
香織:ワン
梅子:犬
香織:猫
梅子:猫
香織:あら!おかあさん!!
梅子:ふふふふふっ
香織:あははは!間違えちゃいましたね!(…なんだろうこの感覚)
香織:ニャー
梅子:猫
香織:犬
梅子:ワン
香織:猫
梅子:ニャー
香織:猫
梅子:ワニャン
香織:ははは!
梅子:はははは!
香織:おかあさんワニャンって鳴く動物なんていましたか?
梅子:いないね~ふふふふっ
香織:ですよね~(おかあさんの笑顔。あぁ久しぶりに見たわ。不思議な感覚。なんだか暖かい。)
香織は目の前の霧が晴れていくような気がした。梅子の笑顔が太陽のように香織の周りを温めていく。こんな単純な体操でも2人の関係を再構築させていくきっかけになるのかもしれない。香織は小さな希望を感じていた。
ガチャ
突然玄関のドアが開いた。
香織の目の前をまた深い霧が覆っていく。夫の帰宅が香織の表情を暗くした。
忌々しい。あいつは数分前にお義母さんと私とが感じたあの温かい空気を一瞬で冷たくする。また何も言わずにソファーに座って新聞を読むだけなのね。あの新聞さえも憎らしく感じるわ。
新聞め。新聞め。新聞め。……新聞?
次回は
新聞を使った「家庭でも出来る脳と身体のトレーニング」です。どうぞご期待ください。