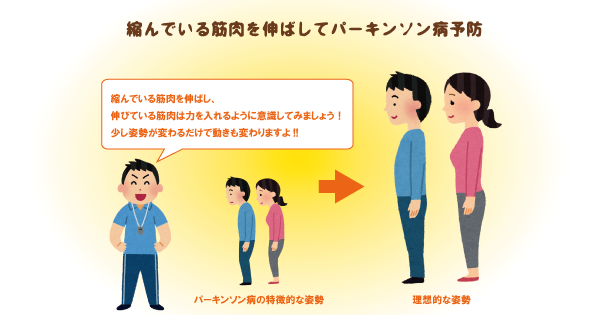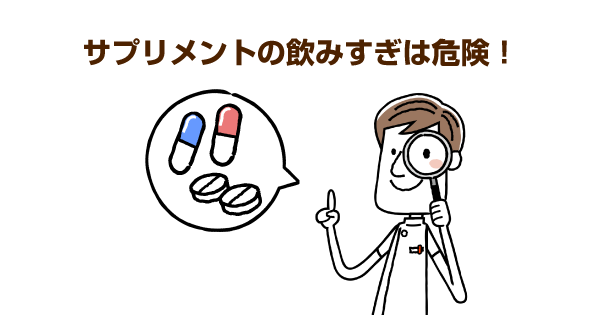病気や怪我などで自覚症状のある人を有訴者(ゆうそしゃ)と呼びます。厚生労働省が実施した2019年の『国民生活基礎調査』によれば、歳を重ねるごとに有訴者の割合は増加し、男性では腰痛を、女性では肩こりを訴える人が最多でした。
女性ではまた、人口1,000人あたりで70人の割合で、手や足の関節が痛むと感じている人もいました。
高齢の方は、健康食品やサプリメントを定期的に服用されている方も多いと思います。東京の総合病院で行われたアンケート調査では、関節痛に良いとされるコンドロイチンやグルコサミンを日頃から服用している人が多いことがわかりました。
関節痛の治療に関して、自己判断でサプリメントや漢方薬を服用することはおすすめできません。サプリメントや漢方薬の効果がはっきりと認められた研究データが限られているためです。また、関節痛がおこる原因の中には、見逃してはいけない病気もあります。そのため、関節痛が気になる方では、まずは医療機関の受診をおすすめします。
そのうえでこの記事では、高齢者にとって身近な健康問題の一つである関節痛と、関節痛に効果があるとされるサプリメントについて解説します。
関節痛の原因となる疾患
運動の影響や怪我以外で関節が痛む場合、主な原因として変形性関節症と痛風が考えられます。そのほか、関節リウマチや感染症によっても関節痛が起こります。
変形性関節症
関節の柔らかい骨(軟骨)と、その周囲に損傷が起こる慢性的な病気です。慢性的な病気とは、症状が急激に悪化しないものの、時間をかけて徐々に進行する病気を指します。
変形性関節症では、痛みや関節のこわばりだけでなく、症状が進行すると手足の運動機能に支障をきたすなど、日常生活に大きな影響を及ぼします。
また、歳を重ねるごとに発症率が高まり、そのピークは70~79歳といわれています。男性よりも女性の発症が多く、関節に負担がかかるような生活環境も発症のしやすさに関連しています。
痛風
血液中に含まれる尿酸という物質の濃度が高くなることで発生する病気です。尿酸の血中濃度が高くなると、関節やその周囲で結晶化しやすくなり、激しい痛みを伴う炎症を起こします。
痛風は、体温が低く尿酸が結晶化しやすい足の親指の付け根に多く見られます。なお、尿酸ではなく、ピロリン酸カルシウムと呼ばれる物質が関節に集まることで起こる関節痛を偽痛風(ぎつうふう)と呼びます。
関節リウマチ
免疫の異常によって関節が炎症を起こし、関節周囲の痛みや腫れが生じる慢性的な病気です。進行すると、関節の変形や歩行機能などに支障をきたすこともあります。病状の進行は人によってさまざまですが、炎症は徐々に広がり、関節だけでなく目や心臓、肺など、全身に拡がることもあります。
感染症による関節痛
細菌が膝などの関節で感染症を起こすと、激しい痛みや炎症を起こすことがあります。感染症による関節痛は症状の進行が早く、感染後数時間から数日の間に現れます。また、発熱や倦怠感など、全身の症状が現れることも特徴です。
関節に痛みが生じたら医療機関に受診を
関節痛が慢性的に続く場合や、耐えがたいほどの痛みや炎症がある場合、発熱や倦怠感など全身の症状がある場合は、すみやかに医療機関を受診しましょう。
特に、感染による関節痛は、病状の進行が早いため、迅速な対応が必要です。また、関節リウマチは、発症の早い段階から適切な治療を受けることで、病状の進行を抑えることができます。
痛風による関節の痛みも同様に、医療機関で適切な治療を受けることによって予防が可能です。
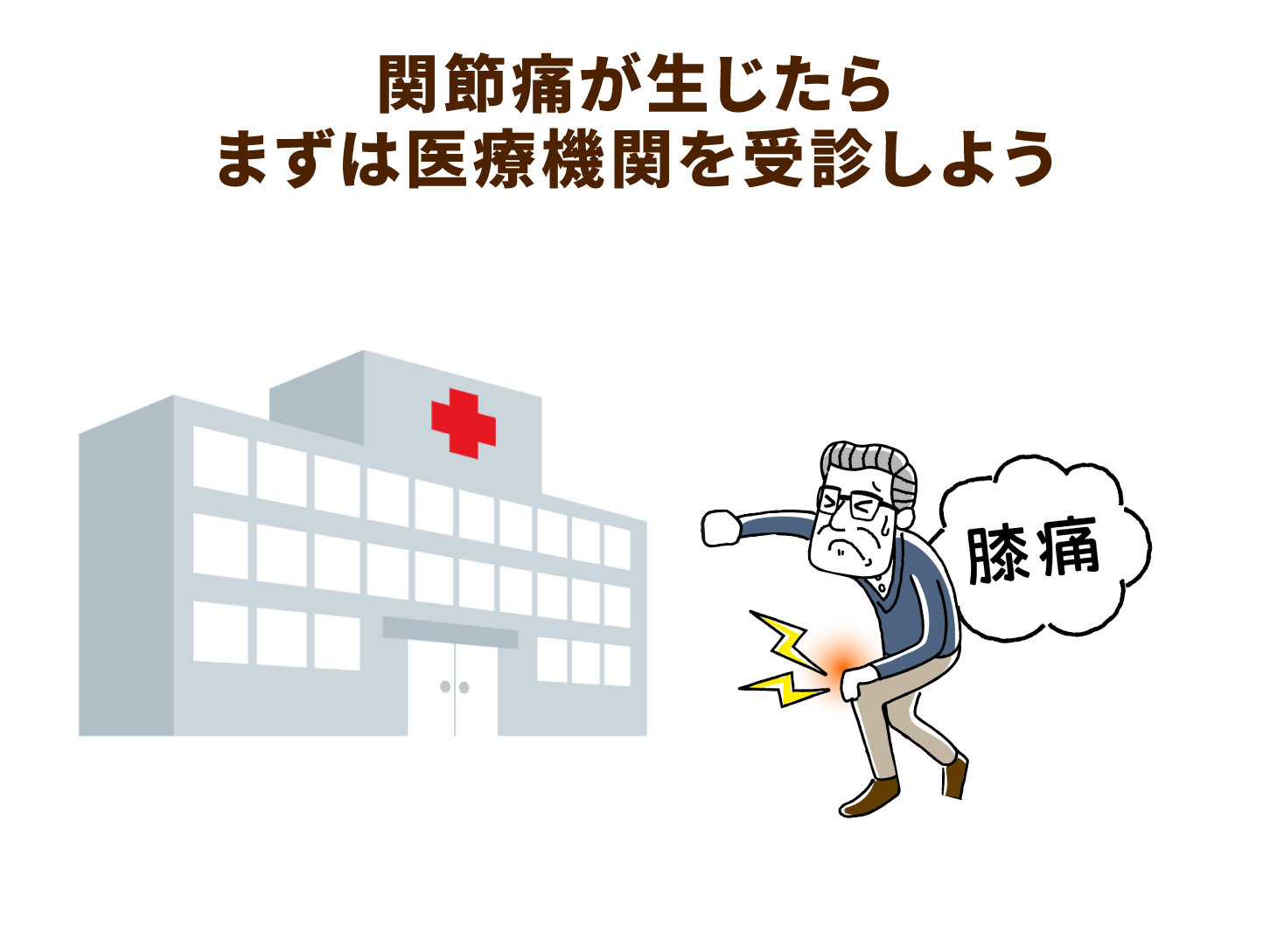
そのため、関節痛でサプリメントや市販薬(漢方薬を含む)を使うケースは、次のような3つのパターンに限られると考えられます。
- 関節痛を予防する目的
- 関節に負担がかかるような生活環境にある人で痛みが軽い場合
- 変形性関節症の治療を医療機関で受けているにも関わらず膝の痛みが気になる
なお、③の状況でも、かかりつけの医師や薬剤師に相談してからサプリメントや市販薬を使うようにしてください。
サプリメントの効果
関節にある軟骨は、運動時の衝撃をやわらげたり、関節の動きを滑らかにする役割を担っています。変形性関節症などによって軟骨が損傷すると、関節を動かしたときに激しい痛みが生じます。
膝の痛みに効くとされるコンドロイチンやグルコサミンは、軟骨を構成する成分です。
「サメ軟骨」のような製品も発売されていますが、「軟骨の成分を補うことが目的」という意味では、コンドロイチンやグルコサミンのサプリメントと類似の製品と考えて良いでしょう。
ここからは、高齢者における関節痛の主な原因である変形性関節症に対してサプリメントで何が期待できるのか、世界の研究を元に検討してみます。
コンドロイチン
変形性関節症に対するコンドロイチンの有効性については、コクランと呼ばれる質の高い医療情報を発信している国際的な組織が、2015年に論文を発表しています。
この論文によれば、コンドロイチンはプラセボ(偽薬)に比べて、変形性関節症による関節痛を10%ほど低下させることが報告されています。
一方で、コンドロイチンに明確な効果がないことを報告した研究論文も報告されています。コンドロイチンに有効性が期待できるとしても、個人差が大きいといえるかもしれません。
なお、関節痛の予防に対するコンドロイチンの効果については、質の高い研究報告が存在せず、その有効性は不明です。
グルコサミン
変形性関節症に対するグルコサミンの有効性を調査した論文が、2017年に報告されています。この論文によれば、痛みや運動機能の改善に対するグルコサミンの有効性は示されていません。
一方で、2018年に報告された論文では、グルコサミンがわずかに痛みを改善する可能性を報告されています。ただし、関節痛の予防に対するグルコサミンの効果については、コンドロイチンと同様に質の高い研究報告はありません。
論文によって報告されている有効性が異なる理由として、コンドロイチンやグルコサミンの効果がとても小さいということが挙げられます。
小さい効果であるがゆえに、ある人にとっては有効性が実感できても、別の人では有効性が実感できず、研究が行われた状況や被験者となった患者背景(年齢や性別など)の違い、あるいは研究で使われた製品の違い(含まれている成分量など)によって、調査結果がばらついてしまうのでしょう。
なお、コンドロイチンやグルコサミンの安全性は高く、用法用量を守って服用している限り、重い副作用がでることは極めて稀です。
効果が期待できる漢方薬
一方、漢方薬については、関節痛への効果が期待できるものもあります。例えば、オオツヅラフジというツヅラフジ科の植物には、炎症を抑えるシノメニンという成分が含まれており、中国では、伝統的に関節痛に対する薬草として用いられてきました。
オオツヅラフジの茎は防已(ぼうい)と呼ばれ、防己を配合した代表的な漢方薬が防己黄耆湯(ぼういおうぎとう)です。
膝関節に痛みがある日本人50人を対象とした研究によれば、防己黄耆湯を服用することで身体機能(運動能力)の改善が見られたと報告されています。
また、手足が冷えることで関節痛が強くなる方には、桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶどう)という漢方薬が用いられることもあります。
膝関節に痛みのある日本人80人を対象とした研究によれば、桂枝加朮附湯はプラセボ(偽薬)と比べて、膝の痛みを明確に改善しなかったものの、鎮痛剤の使用量が減少したと報告されています。
鎮痛薬の使用を少しでも減らしたいという方では、桂枝加朮附湯を試してみるのも良いでしょう。
関節痛に対する治療効果の多くはプラセボ効果?
変形性関節症の治療は、薬だけでなく運動療法や手術が行われることもあります。
治療の方針は、症状の進行度合いや患者さんの病状に応じて決められますが、コンドロイチンやグルコサミンのようなサプリメント、あるいは漢方薬だけで治療することは難しいでしょう。
ただ、変形性関節症の治療では、プラセボ効果の影響も大きく、関節痛の緩和に対するプラセボ効果(偽薬でも得られる治療効果)の影響は、効果全体の7割以上を占めるともいわれています。
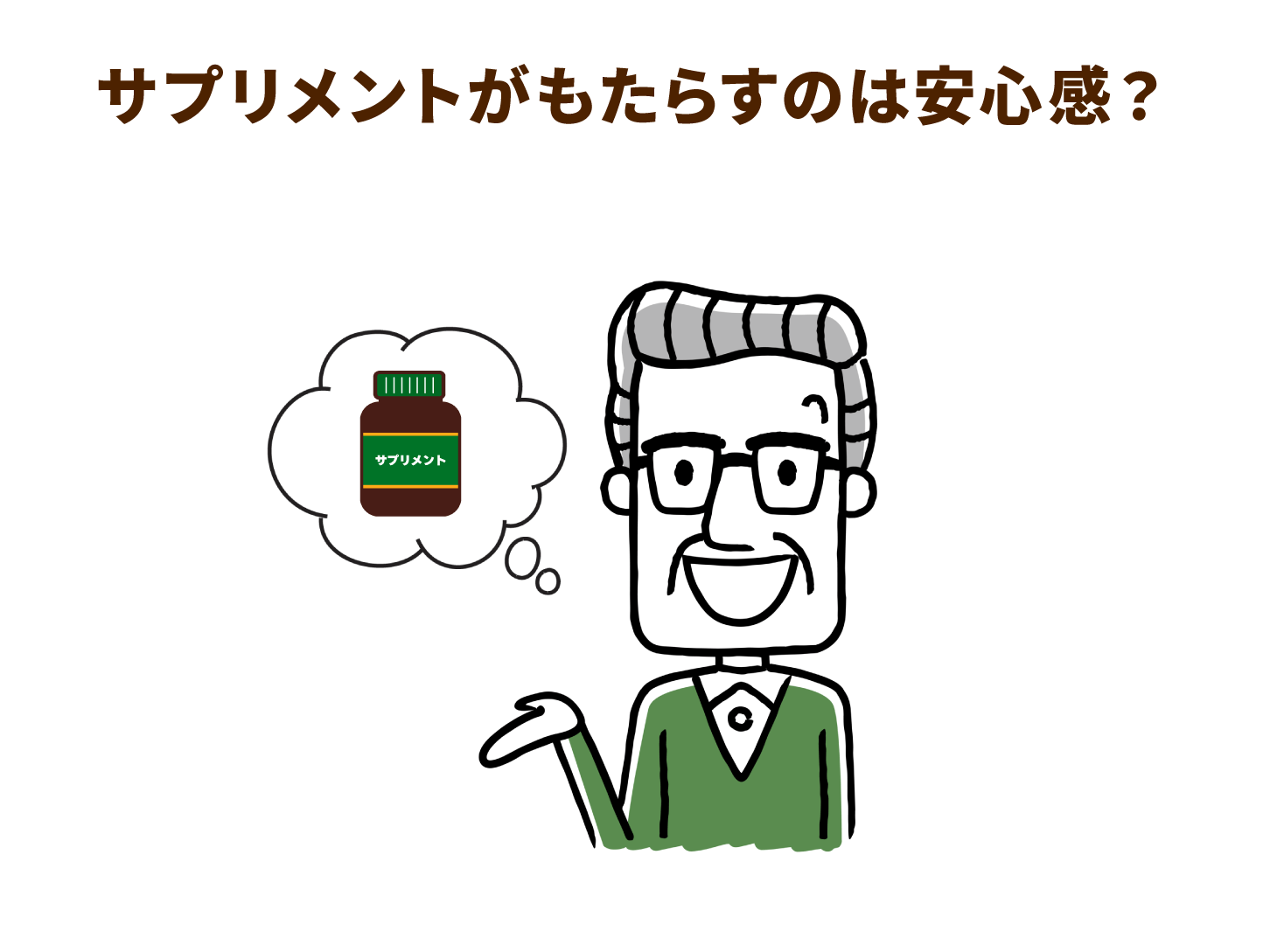
薬やサプリメントの有効成分が関節に働きかけ、痛みや炎症を直接的に改善しているというよりは、医療機関を受診していることの安心感、薬を定期的に服用しているという状況、あるいは運動療法に参加し、生活習慣に対するアドバイスを受けることなど、治療と関係するさまざまな生活要素が、関節痛の緩和をもたらしていると考えられます。
医療機関で適切な治療を受けていることが前提となりますが、サプリメントや漢方薬について、かかりつけの薬剤師に相談してみるのも良いでしょう。
相談をきっかけに生まれる安心感や、定期的にサプリメントを服用するといった生活要素が、関節痛を和らげる最大の治療薬かもしれません。