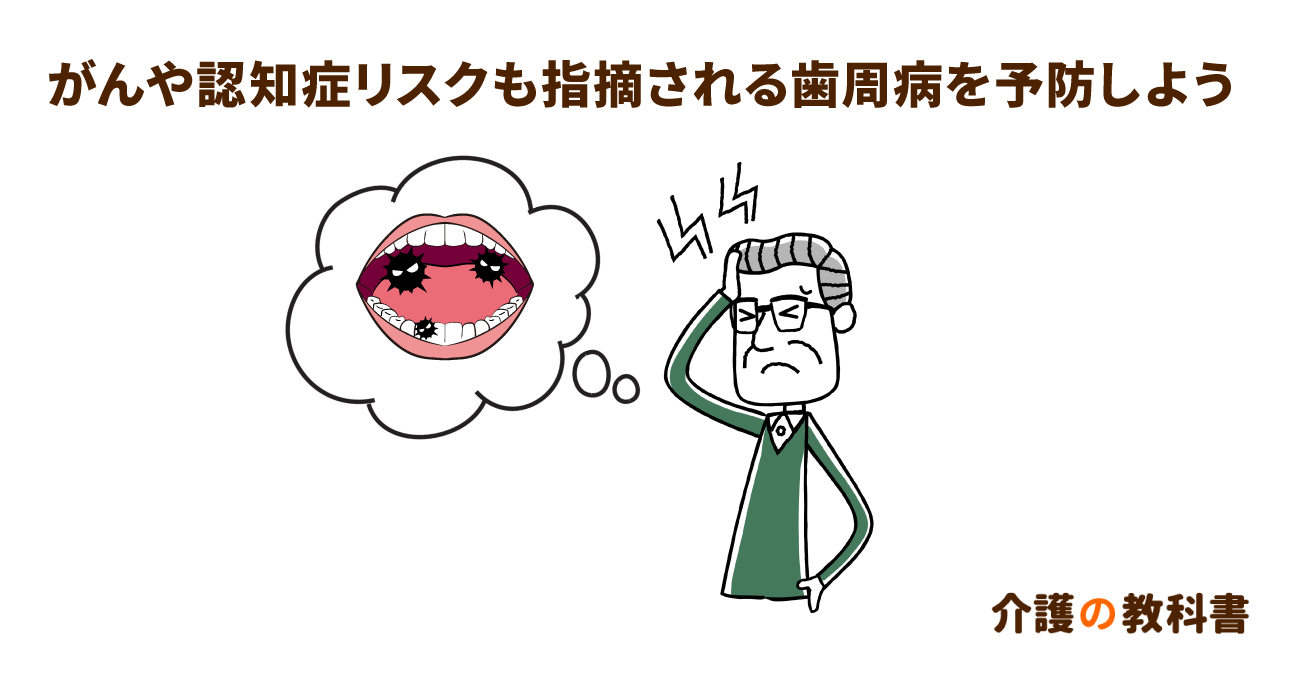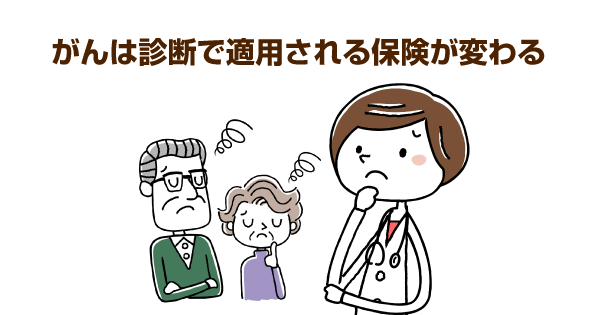今回は医療用麻薬の概要をご紹介いたします。
麻薬と聞くと怖いイメージがあると思いますが、がん患者をはじめ、強い痛みを和らげるためには欠かせない治療薬です。
がんを患うと大半は痛みが生じる
国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」によると、日本人の約2人に1人は生涯のうちに「がん」になり、約3人に1人は「がん」が原因で死亡するというほど、身近な病気です。
がん患者の大半は、病気の経過中に何らかの痛みを経験すると言われています。がんを患っただけでも不安なところに、痛みまで伴うという話をすると、不安だけでなく恐怖心まで抱いてしまうかと思います。しかし、ほとんどの痛みは治療によって和らげることができるのでご安心ください。
日本人は我慢強い人が多いので痛みを感じても訴えなかったり、誰にも相談せずに一人で耐えてしまう方がいらっしゃいますが、痛みを我慢する必要はまったくありません。
また、痛みの治療でよくある勘違いとして「痛みを訴えるとがんの治療を中止されてしまう」「痛み止めは寿命を縮める」「早くから使うと痛み止めが効かなくなる」「強い痛み止めは中毒になる」といったものがありますが、これらはすべて間違いです。
がんによる痛みの種類と治療法
がんによる痛みの治療法にはWHO(世界保健機関)が定めた「WHO方式がん疼痛治療法」と呼ばれる治療法があります。これに基づいて治療を行うと、80%以上の患者さんは痛みを和らげることができるとされており、日本でもこの治療法に基づいた治療が行われています。
痛みを取る治療では、薬だけでなく放射線照射や神経ブロックと呼ばれる治療を行うこともあります。がんの部位やその人の状態、痛みの程度によって治療法が決められます。

痛みの種類
がんによる痛みは、重いような痛み(鈍痛)やズキズキ・ヒリヒリする痛み(体性痛)、抗がん剤の副作用などに多いしびれ感のある痛み(神経障害性疼痛)などがあります。また精神的な不安や孤独なども痛みの一種として扱われています。
鎮痛薬の種類
がんによる痛みは、私たちが日常生活で感じる痛みよりも強い痛みを感じることもあるため、痛みの程度によって使う薬も異なります。
軽度から中等度の痛みには、市販でも売られているようなアセトアミノフェンやアスピリンのような痛み止めが使われます。中等度以上の痛みの場合、アセトアミノフェンなどでは対応できないこともあり、オピオイド鎮痛薬と呼ばれる痛み止めが使われ始めます。これが医療用麻薬にあたります。
医療用麻薬とは?
医療用麻薬とは、痛みを脳に伝える神経の活動を抑制させ、痛みを感じにくくさせる薬です。市販されている鎮痛薬では効果の得られにくい強い痛みにも効果を示すことができます。
麻薬という単語が入ると、中毒や依存症といったイメージを持たれる方もいるかと思いますが、非合法の麻薬と異なり、製薬会社でつくられている医療用麻薬は有効成分の量が正確に保たれており、不純物などが混入している心配もありません。
また痛みのあるときは通常時とは異なり、麻薬を使用しても快楽物質「ドーパミン」が出にくいことがわかっています。これにより異常な快楽を感じることがなく、正常な状態を保つことができます。
さらに、使用については医療用麻薬を取り扱うことのできる免許を持った医師が処方し、医療用麻薬を取り扱うことのできる免許を持った薬局で調剤され、在宅医療現場では訪問看護師による管理も行われています。このようにさまざまな医療従事者の目が常に行き届いた環境下で使用することになります。そのため、安全に治療を継続することができます。
医療用麻薬の種類
日本で使用されている医療用麻薬は複数種類あり、痛みの程度によって使い分けられています。飲み薬、貼り薬、坐薬、注射薬など薬の剤型も多様なので、使いやすい薬を選ぶことができます。
代表的な副作用には便秘、吐き気、眠気、呼吸抑制などがあります。副作用に応じて下剤や吐き気止めなどを使用することがあります。また、副作用が出やすくなってきた場合には、医療用麻薬の種類を変えることで軽減することがあります。

今回は、医療用麻薬の概要をご紹介いたしました。またの機会に、それぞれの薬の特徴をや使い方などを詳しく説明させていただきたいと思います。