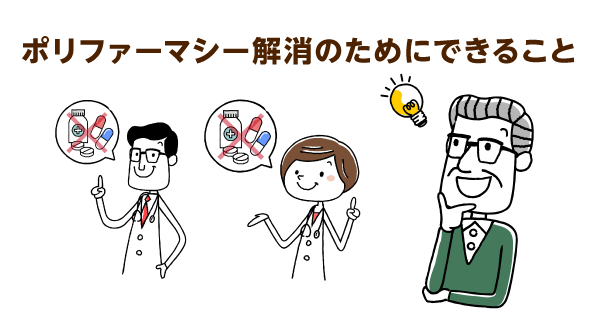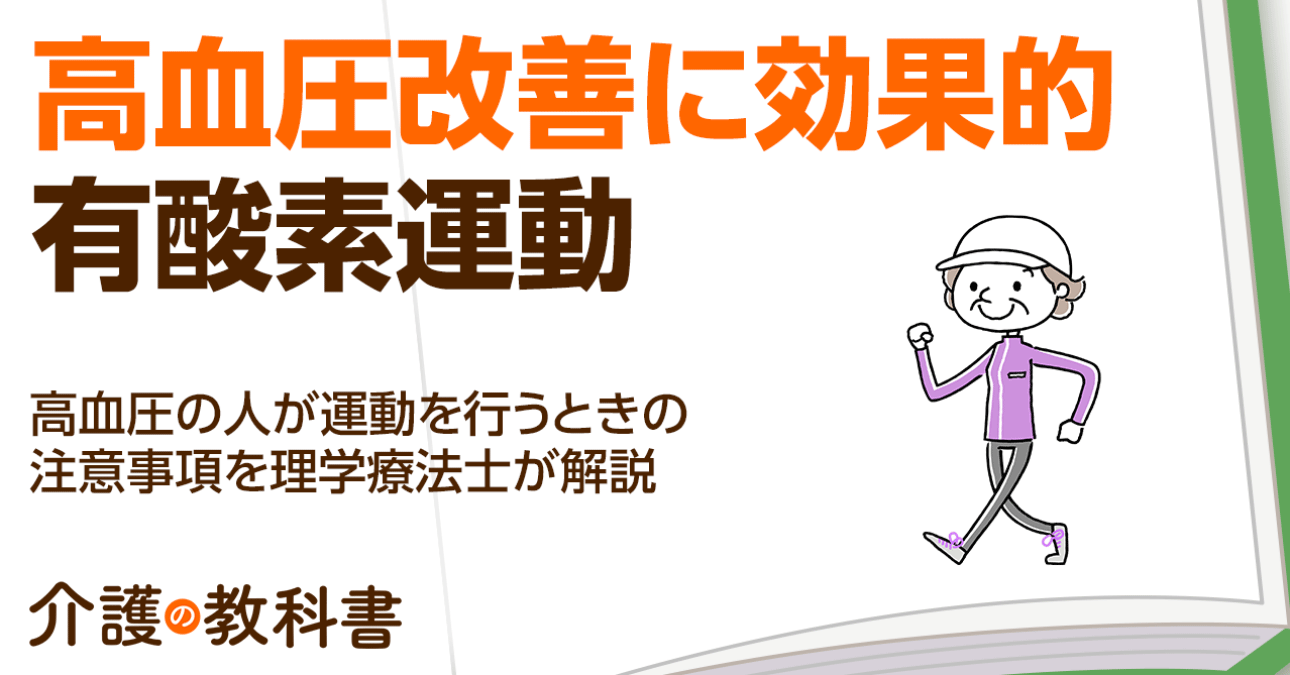こんにちは。薬剤師の雜賀匡史です。
現在、日本には約4,300万人の高血圧の方がいると推定されています。また、日本で高血圧に起因する脳血管病死亡者数は年間約10万人と言われており、脳心血管病死亡の最大の要因となっています。
血圧が120/80mmHgを越えると、脳心血管病や慢性腎臓病などの罹患・死亡リスクが高まり、とても危険な病気の一つです。
今回は高血圧の病態や治療薬についてご紹介いたします。
高血圧の基礎知識
高血圧は血圧管理が重要
血液は、心臓がポンプのように縮んだり広がったりすることで、全身に送り出されます。送り出された血液が、血管の壁を押すときの圧力を「血圧」といいます。高血圧はこの圧力が高くなっている状態を指します。
診断基準は、上が140mmHg以上、下が90mmHg以上です。ただし、130-139/80-89mmHg以上の高値血圧の人や、血圧上昇に伴い脳心血管病リスクが上がる120/80mmHg以上のすべての人は、血圧管理を行う必要があります。
血圧が高い状態が続くと血管に過度の負担がかかり、血管の壁は厚くなったり傷つきやすくなったりします。これに加え、コレステロールなどが付着して血管の内側が狭くなると、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの病気の原因となるのです。
なぜ塩分がダメなのか
高血圧の方は、塩分を控えるように言われた経験があると思います。高血圧症と診断された方は、日本高血圧学会で推奨する1日の塩分6グラム未満をなるべく守る必要があります。しょう油だと大さじ2杯程度の量です。
塩分を摂り過ぎると、血液中のナトリウム量が増えます。濃くなった血液を薄めるため、血液中に水分が引き込まれ、体内を循環する血液量を増やします。これによって血圧が高くなるのです。
水道の蛇口にホースを取りつけた状態を想像してみてください。少量の水を流したときと、大量の水を流したときとではホースにかかる圧力が違いますよね。塩分を摂り過ぎると、血管というホースの中を流れる血液の量が多くなってしまうのです。

高血圧は自覚症状が現れにくい
高血圧の状態を放っておくと、心筋梗塞や脳卒中のような重大な病気を突然引き起こすことがあります。
しかし自覚症状が現れない人もいるため、病気の進行に気づきにくく、治療も遅れがちになります。ここが高血圧の怖いところです。
自宅でのリラックス状態で血圧を測定することが重要
高血圧の治療をしている人は、家でも毎日血圧を測定するように言われていると思います。通常、病院に行き白衣を着た先生を前にすると、緊張して血圧が通常時より上がる傾向があります。
家のようにリラックスした状態のときに測定することで、正確に診断することが可能となり、その後の治療効果を高めることができます。血圧手帳をつくって毎日の測定結果を記録し、受診時に医師や薬剤師に見てもらいましょう。
高血圧の治療法
生活習慣の改善が大前提
高血圧の治療では減塩、運動、肥満の解消など、生活習慣を改善することが基本となります。飲酒や喫煙も血圧を上昇させる因子なので、高血圧の人はできるだけ控えるようにしましょう。
生活習慣を改善しても血圧が下がらない場合に、薬物治療を行います。
治療薬の副作用を事前に把握しよう
血圧を下げる薬は複数種類があります。血管を広げて血圧を下げる薬、血管から水分と塩分(血液量)を抜いて血圧を下げる薬、心臓の過剰な働きを抑えて血圧を下げる薬、血管を収縮させる物質をブロックして血圧を下げる薬など、効果を示す仕組みもさまざまです。
血圧のレベルや状態、そのほかの病気の有無などによって使用する薬が決められています。種類が豊富なので、複数の薬を組み合わせて治療を行うこともあります。
高血圧治療薬の副作用には、めまい、ふらつき、動悸、尿量増加、顔のほてり、歯肉の腫れ、空咳(痰がらみのない咳)、脱水などがありますが、使用する薬によって現れる副作用が異なります。ご自身が使っている薬の代表的な副作用については、医師、薬剤師から情報をもらい、事前に把握しておくことが大事です。
生活習慣の改善で薬の服用をやめられる
高血圧の治療薬を飲みはじめると、「生涯にわたって飲み続けなければならない」と思われている方がいらっしゃいます。ですが、運動や食事管理など生活習慣の改善を継続することで、やがて薬の服用を卒業できることがあります。治療薬を使用している間も、生活習慣の見直しは継続的に行いましょう。

今回は高血圧についてご紹介いたしました。自覚症状の少ない病気なので、薬を飲み忘れたり、飲むことを自己判断で止めてしまいがちですが、命にかかわる疾患を招くリスクの高い病気です。
甘く考えずに、しっかりと治療を行っていきましょう。