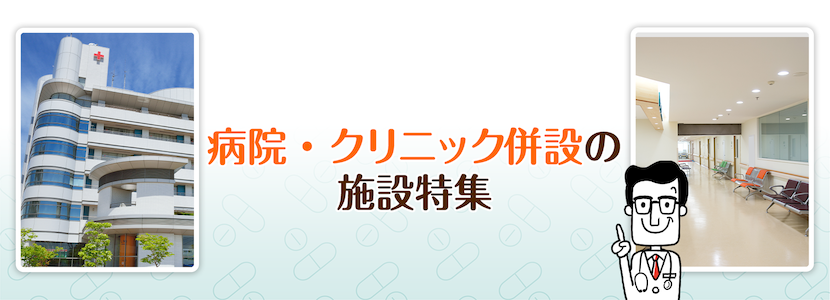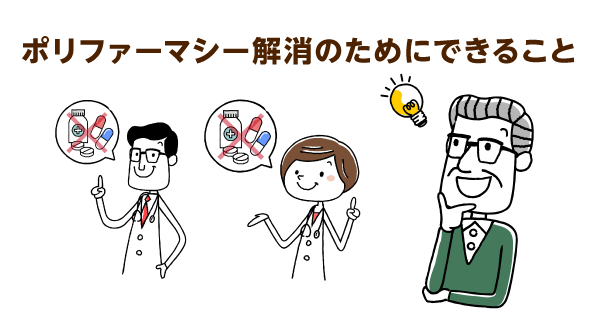こんにちは。薬剤師の雜賀匡史です。
皆さんは薬をご自宅でどのように保管していますか?無頓着の方もいれば、食品と同じように大切に冷蔵庫にしまっている方もいらっしゃると思います。
薬は、生き物と同じように、それぞれ適した環境が異なります。
今回は、薬の正しい保管方法についてご紹介しますね。
薬も卵も基本的に湿気に弱い
皆さんは購入した卵を冷蔵庫に入れて保管していますよね。
しかしスーパーで卵を購入するときには常温販売されています。
なぜだと思いますか?
卵がスーパーで常温販売されている理由は、結露による傷みを防ぐことが目的です。
卵の殻には気孔と呼ばれる呼吸に必要な穴が無数に空いています。
温度・湿度差によって表面に結露ができると、気孔から水分と雑菌が内部に入り込んでしまうことがあるのです。
同様のことが薬にも言えます。
一般的な薬は湿気に弱いため、温度・湿度変化によって生じた結露の水分が薬の成分に影響を及ぼすことが考えられるのです。
このことから、「薬はすべて冷蔵庫保管」というのは間違った認識になります。
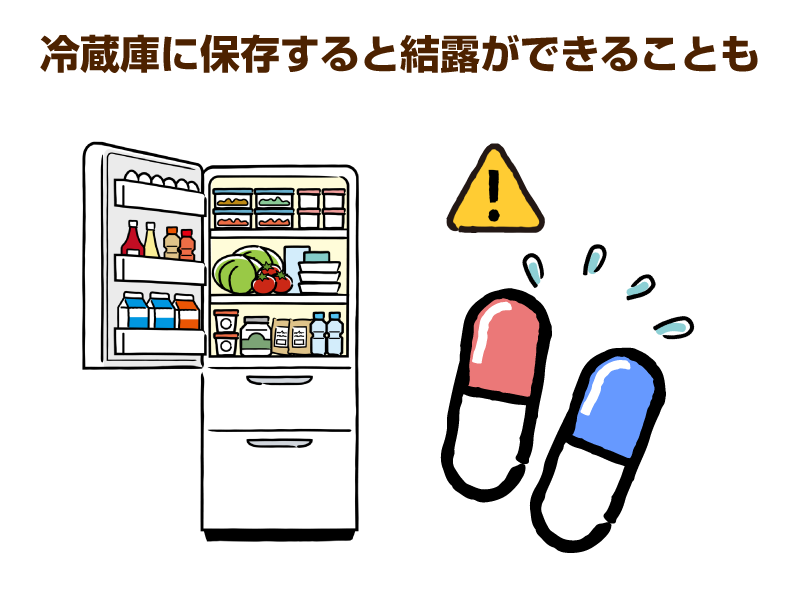
薬は人間と同様、「高温・多湿・直射日光」を嫌う
薬は温度、湿度、光の影響を受けると分解や変質をし、薬効(薬の効きめ)が変化してしまうことがあります。
薬の正しい保管方法を考えるとき、私たちの日常生活を考えると覚えやすいです。
というのも、薬は人間と同じで高温、多湿、直射日光を嫌います。
一方で暑すぎず、寒すぎず、風通しの良いムシムシしていない場所を好みます。
私たち人間が快適に過ごせる場所というのは、基本的に薬にも快適な場所だといえます。
光による分解や変質を防ぐには、直射日光や強い光に薬をさらさないことです。
窓際などの直射日光の当たる場所はNGです。
ご自宅に光を遮断できる容器があれば、それに入れて保存することも良いですし、引き出しの中に入れて保管することも良いでしょう。
ただし、引き出し保管でもタンスの引き出しのように湿気が溜まりやすい場所はNGです。
特に決められた保管指示のない薬は、室温保存が望ましいでしょう。
室温とは1~30℃のことを言いますが、できれば常温15~25℃が最適な温度です。
夏場の車中などは50℃以上の高温になりますので、車内に放置しないように注意しましょう。
湿度にも気を付ける必要があります。
例えば台所、洗面所、お風呂場などの近くは湿度が高いため、保管には不適です。
風通しの良い場所を探して保管場所を検討してみましょう。
おせんべいなどを保管するときに乾燥剤を使用するように、乾燥剤を使って湿度上昇を防ぐことも効果的です。

薬の種類ごとの保管場所を解説
薬には錠剤、散剤、カプセル剤、水剤、坐薬、点眼剤、軟膏剤、注射剤などさまざまな形態があります。
これらの形態によっても保管場所が異なることを理解しておきましょう。
水剤は冷所保管が基本
一般的な錠剤、散剤、カプセル剤は室温保管が好ましいことは先述の通りですが、水剤に関しては冷所保管が基本となります。
一般的に水剤は高温で変質しやすく、またカビや雑菌の繁殖を防ぐためにも冷所で保管したほうが良いのです。
冷所とは1~15℃の範囲です。
家庭用冷蔵庫の温度は10℃以下ですので、冷所保管する場所は家庭用冷蔵庫で良いでしょう。
冷蔵庫保管する際に注意したい点は、食品と一緒に保管しないこと、食品の入っている容器や瓶に入れ替えないことです。
子どもがジュースなどと薬を誤認して口にしてしまうと、重大な事故を引き起こす可能性もあります。
薬と食品は必ず分けて保管するようにしましょう。
薬専用のタッパーなどに入れて保管するのも良いと思います。
「冷凍庫で保管しても良いですか?」と聞かれることもありますが、家庭用冷凍庫の温度はマイナス12℃以下です。
冷凍庫保管した薬が室温に戻ったときに結露の原因となりますし、薬によっては冷凍によって結晶化することで変質してしまうものがあります。
このため、特に指示がない限りは冷凍庫保管をしてはいけません。
坐薬は、冷所保管or室温保管のいずれか
坐薬は冷所保管の指示があるものと、室温保管でも大丈夫なものと2種類存在します。
肛門から挿入し直腸で体温で溶ける坐薬は、あたたかいところに置いておくと溶けてしまうので、冷蔵庫保管となります。
しかし、水分を吸収して溶けるタイプの坐薬は冷蔵庫に入れる必要はありません。
保管方法は坐薬の種類によって異なりますので、それぞれの具体的な保管方法を薬剤師に確認しておきましょう。
点眼剤は、冷所保管or室温保管のいずれか
点眼剤は冷所保管の指示があるものは冷蔵庫で保管しましょう。
しかし、冷所保管の指示がない点眼剤を冷蔵庫で保管すると、薬の成分が変質したり、点眼剤先端の目詰まり原因になったり、目に与える刺激が増すこともありますので、室温保管が好ましいでしょう。
その際、遮光袋に入れて外からの光を遮るなどの工夫が必要なものもあるので注意しましょう。
軟膏剤は室温保管が基本
軟膏剤の一部は冷所保管が必要ですが、多くの軟膏剤は室温保管で問題ありません。
引火性のある薬もあるため、しっかりとふたを締めて火元から離れた場所で保管しましょう。
注射剤は、冷所保管or室温保管のいずれか
注射剤は冷所保管と室温保管とが混在しています。
インスリンのように凍結を避ける注射剤もあれば、高温を避けるものも存在します。
出先で使用する際でも決められた保管方法を守るような工夫が必要なこともあるので、困ったときは薬剤師に相談して解決策を一緒に考えてもらうと良いでしょう。
一包化薬の処方時は、分割調剤サービスを検討しよう
一包化(※)された薬は、既製のPTPシート(※)よりも、湿気、光にさらされやすい条件となっています。
※一包化…一回に複数の薬を服用する場合などに、まとめて一袋にしておくこと。錠剤の紛失・飲み忘れなどの防止につながる。 一包化は、医師の指示のもと薬剤師が行う。
※PTPシート…錠剤やカプセルを包装する、アルミニウムとプラスチックなどでできたシート
また、薬剤師による一包化時に一度外気に触れているため、既製品よりも保管期間が短くなります。
一包化された薬を、一回の処方日数内で使い切る分にはほとんど問題がありません。
しかし、長期処方の一包化調剤を一度で行うことは推奨されていません。
こういったケースでは、分割調剤のサービスにより、一枚の処方せんを使用して、複数回に分けて調剤することが可能ですので、薬剤師に相談してみましょう。

最後に一言
今回は薬の正しい保管方法についてご紹介致しましたが、薬によってそれぞれ保管方法が異なりますので、一般論としてご理解いただければと思います。
わからないときには、調剤した薬剤師に相談されると良いでしょう。
また、家の中での薬の保管場所が正しいのか不安なときには、訪問薬剤管理指導のサービスを利用することで、適した保管場所を薬剤師に直接教えてもらうことも可能です。
正しい保管方法を理解して、有効かつ安全に薬を使用できる環境を整えていきましょう。