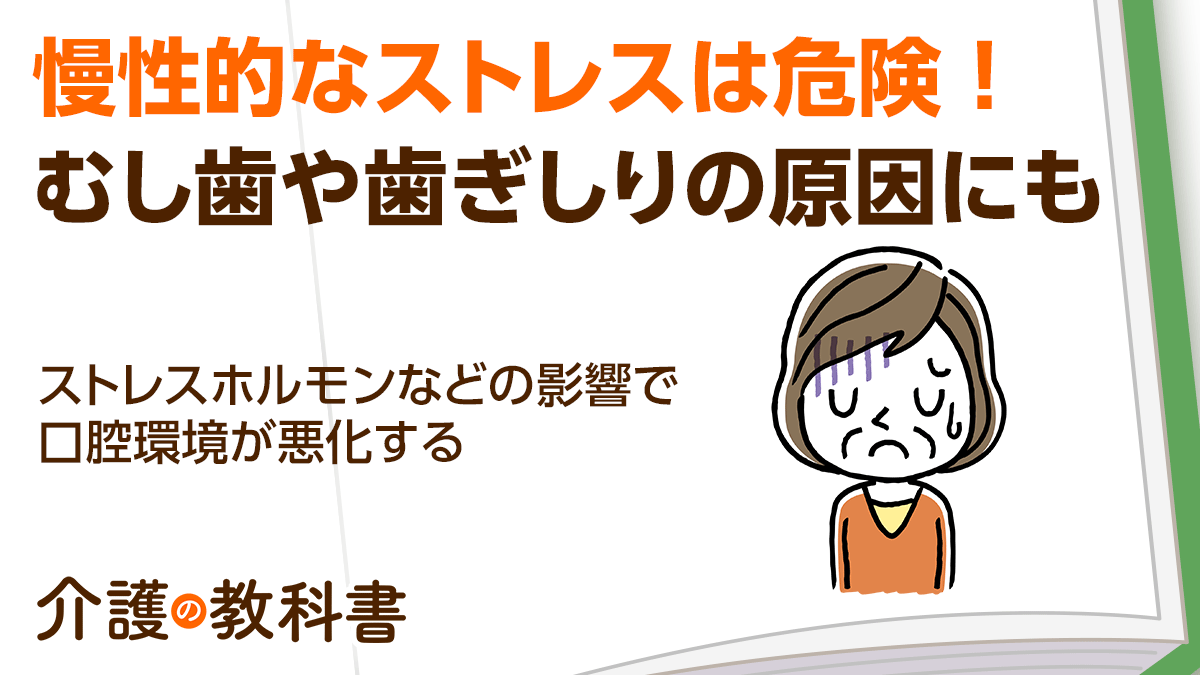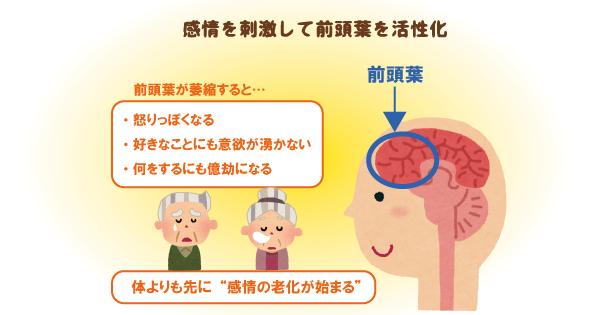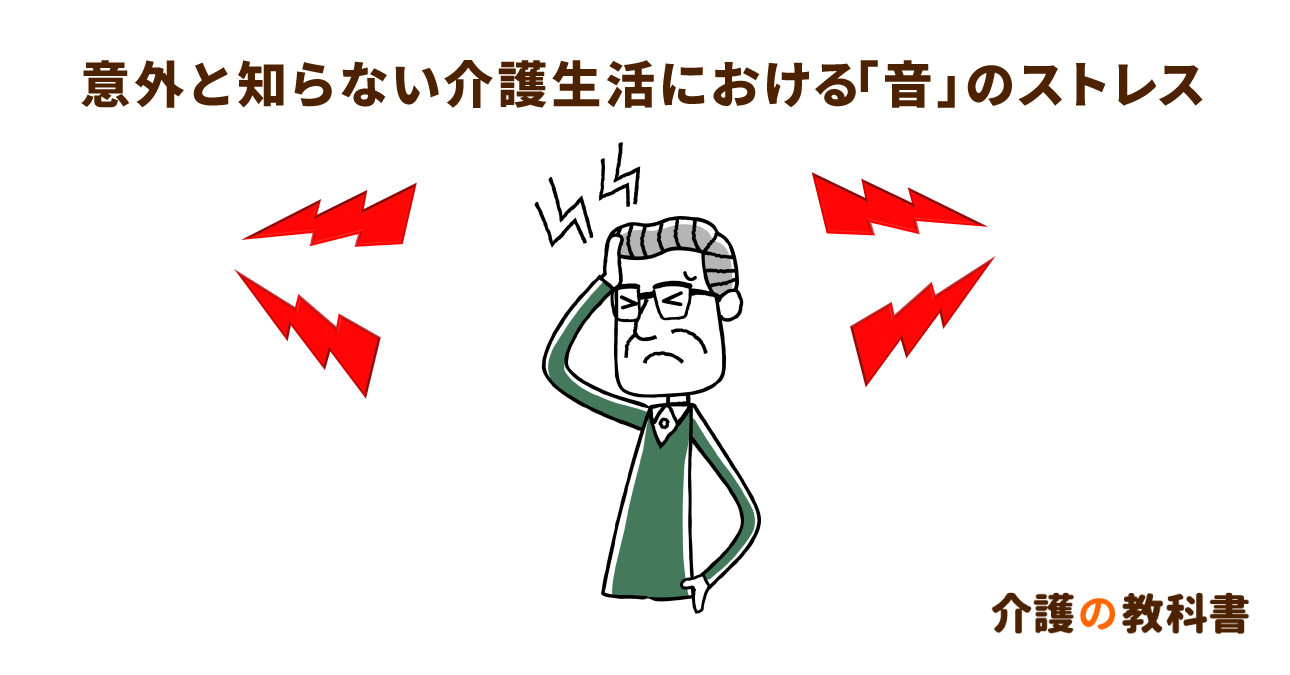ストレスと口腔の状態ときかれると、一見関係がなさそうに思われる方も多いかもしれませんが、ストレスは口腔の状態に深く関係しています。
そこで、ストレスが与える口腔への影響や対策についてお伝えします。
ストレスホルモンが長時間分泌されると糖分が欲しくなる!
ストレスが口腔へ与える影響として、大きくは体の機能に関する生理的影響と、歯などに力がかかる物理的影響があります。
生理的影響
人間は何らかのストレスを感じると、ストレスに対する生理的反応を起こします。その反応の一つがストレスホルモンの分泌です。
自律神経である交感神経―副交感神経の関係では、コルチゾールというストレスホルモンが分泌されます。
また、脳の視床下部―下垂体―副腎髄質の活動においては、アドレナリンというストレスホルモンが分泌されます。
さらにクロモグラフィンという物質もストレスによって唾液中に分泌されていることがわかっています。
コルチゾールは、精神的・肉体的ストレスの両方に反応して分泌されますが、このクロモグラフィンは精神的ストレスのみに反応して分泌されるという特徴があります。
これらのストレスホルモンは、日常的なちょっとしたストレスにおいても分泌されています。人の前で話さないといけない、初めての場所に行ったときなど精神的不安などに対して分泌されたりしているからです。
ストレスホルモンは一時的なストレスでは、あまり大きな問題にはなりません。
しかし、慢性的にストレスが続くと、心の安定やリラックスを与えるドーパミンやセロトニンといった物質を脳が正常に放出できなくなることがあり、問題を生じやすくなります。
ドーパミンやセロトニンといった物質が放出できなくなると、脳がそのことを補うために、糖を栄養として摂取して血糖値をあげようとする二次的な体の反応が起こります。
つまり、甘いものが欲しくなるのです。
甘いものを食べることで脳に安らぎを与えることがわかると、血糖値を上げるような甘い飲み物や食べ物をさらにたくさん食べたくなってきます。
こうして、甘いものを食べ過ぎてしまい、食生活が乱れて口腔環境に悪影響をもたらすことが考えられています。
そのため、長期間ストレスがある状態では、むし歯が増えやすくなり、特に高齢者では、加えて歯周病の危険性も高まります。
もう一つの問題は、ストレスによる唾液の防御機能の低下です。
脳は緊張などのストレスを感じると、自律神経の交感神経が優位になります。唾液はリラックスした状態で副交感神経が優位になっているほうが分泌が促進しやすくなります。
逆に、交感神経が優位な場合は、唾液の分泌は抑制されます。それだけでなく、交感神経優位では、水分の少ないネバネバした唾液が分泌されやすくなるため、口が渇きやすくなってしまいます。
唾液の防御機能を高めるためにもリラックスすることは大切になります。
ストレスが続くと噛みしめによる弊害が出やすい
物理的影響
ストレスがかかると、無意識に噛みしめてしまうことが多くなってきます。
口を閉じたときの正しい歯の位置は、わずかに上下の歯の間に隙間がある状態です。
しかし、ストレスがある状態では、歯の間の隙間がなくなるくらい噛みしめていたりします。
舌の両サイドにギザギザな歯型がついている場合は、知らない間に噛みしめていることがあるので要注意です。
歯の噛みしめは、夜間の寝ている間に起こっていることもあり、強く噛みしめて歯を全体的に横に動かす歯ぎしりを行っていることもあります。
ストレスにより、夜間だけでなく日中にも噛みしめていることが習慣化してくると問題が生じやすくなります。
噛みしめが習慣化し、長期間続くと、歯や顎に余計な負担をかけてしまうからです。
歯への負担をかけすぎると、歯の咬合面※が摩耗しやすくなり、顎に負担をかけすぎると顎関節症を引き起こしてしまいやすくなります。
顎関節症になってしまうと、口を開けるたびに痛みが生じやすくなり、普段のケアにも支障が出ることもあるので注意が必要です。
※口を閉じたときに上下の歯が緊密に相接する面
また、噛みしめが長期化した場合に、口蓋隆起という、口蓋(上顎)が腫瘍のように盛り上がった状態になることがあります。
口蓋隆起の原因は、遺伝的要因などさまざまな要因がありますが、噛みしめもその一つです。
口蓋隆起になるだけでは、特に生活に支障はなく、気づかれないことも多くあり、それほど心配する必要はないと言われています。しかし、いざ義歯が必要となったときに、上顎の義歯の装着が難しくなることがあるので注意が必要です。
1日1回落ち着いてお茶を飲むだけでも違う
高齢者では、環境の些細な変化でもストレスに感じることがあります。しかし、一時的なものではなく、長期間のストレスには注意しましょう。
認知症の方など、自らストレスを表出できない場合は、口腔内の環境悪化で、ストレスを発見することも可能です。そのため、日々の口腔内の観察を行うことが、ストレスの発見につながることもあります。
また、噛みしめがある場合は、早期の歯科受診が大切です。噛みしめによる問題が生じた場合は、夜間にマウスピースを装着するなどして、歯を守ることが可能になるからです。
しかし、噛みしめは無意識に行っている場合が多いため、噛みしめを気にしすぎると、それが反対に心理的なストレスとなり、精神的に不安定な状態になる危険性もあります。
そのため、噛みしめを意識するのではなく、自然とリラックスできる環境をつくることがとても大切です。
また、質のよい唾液に分泌のためにも、リラックスは大切です。
このように、口腔内の環境を良好に保つためには、リラックスした生活が大切になってきます。
しかし、リラックスできる生活は個人によってさまざまです。
お気に入りの音楽をかける、親しい友達と会う時間をつくる、笑える楽しい時間をつくる、お散歩するなど、その方にあったリラックス方法を取り入れてみましょう。
1日1回ゆったりとした環境で、お茶を飲むだけでも違ってきます。
今回は、ストレスと口腔内の影響についてお伝えしましたが、ストレスは口腔内の影響以外にも、下痢などの消化器系の症状、頭痛、不安、不眠などさまざまな身体的・精神的な問題が生じる原因となります。
そのため、ストレスが持続するときは、医療機関を受診するようにすることも大切だということを覚えておきましょう。