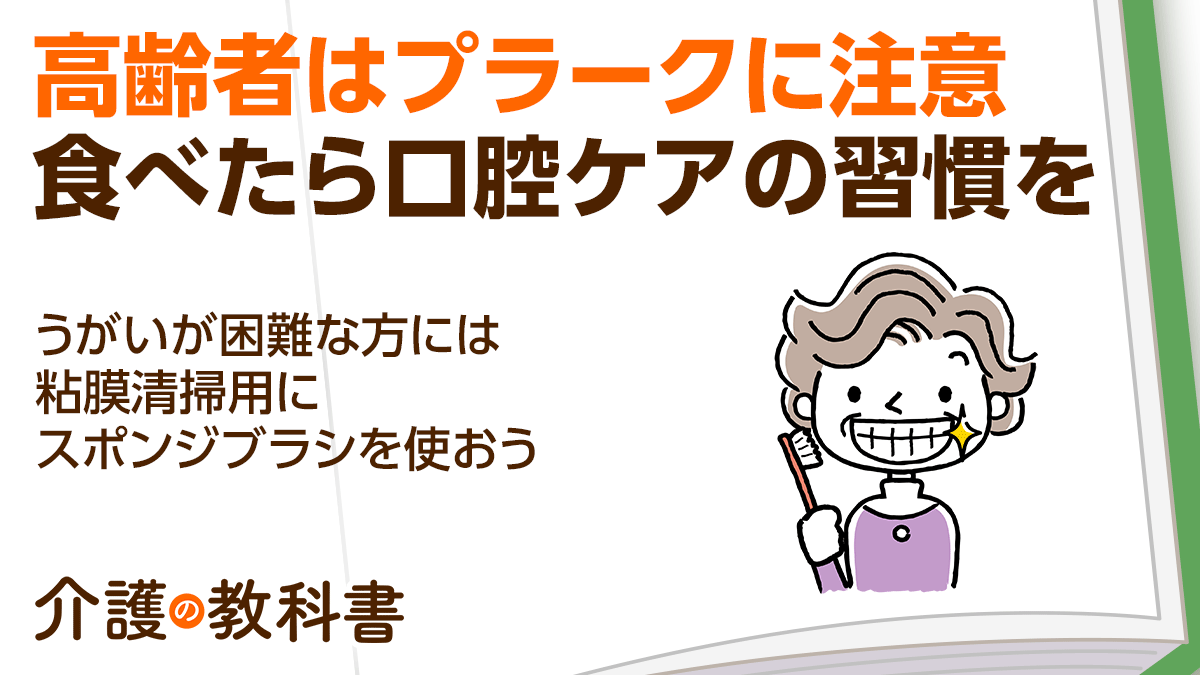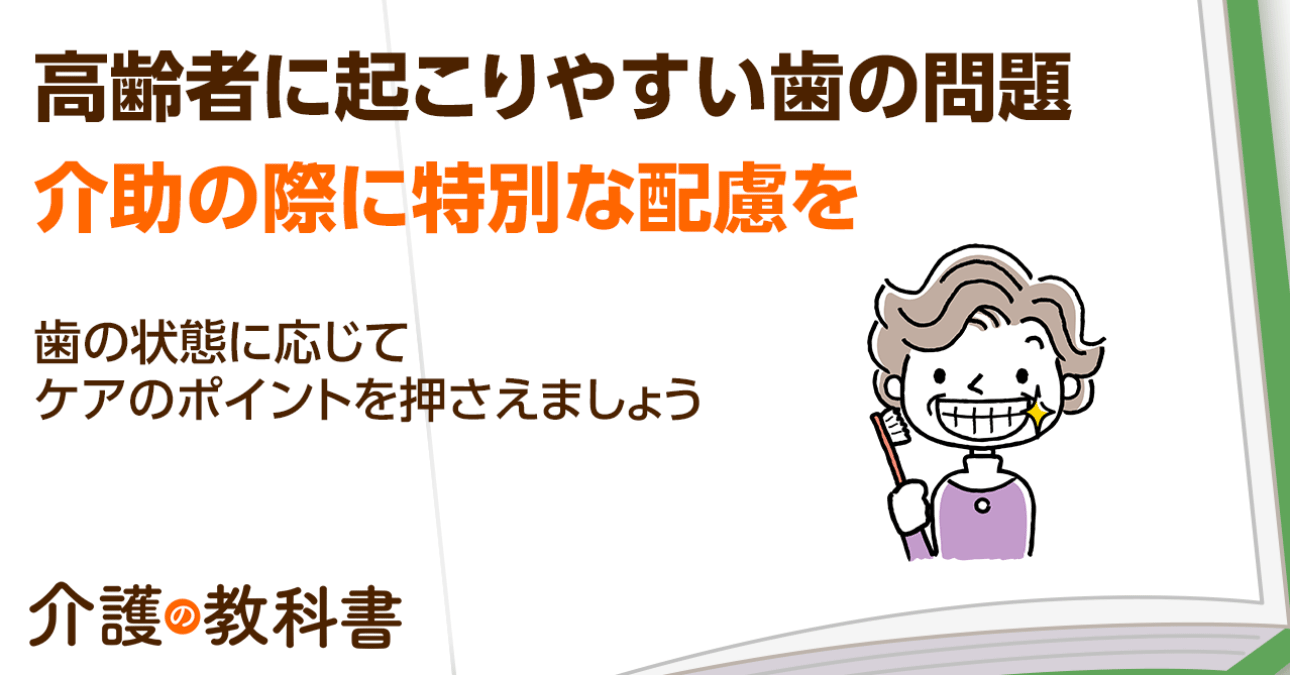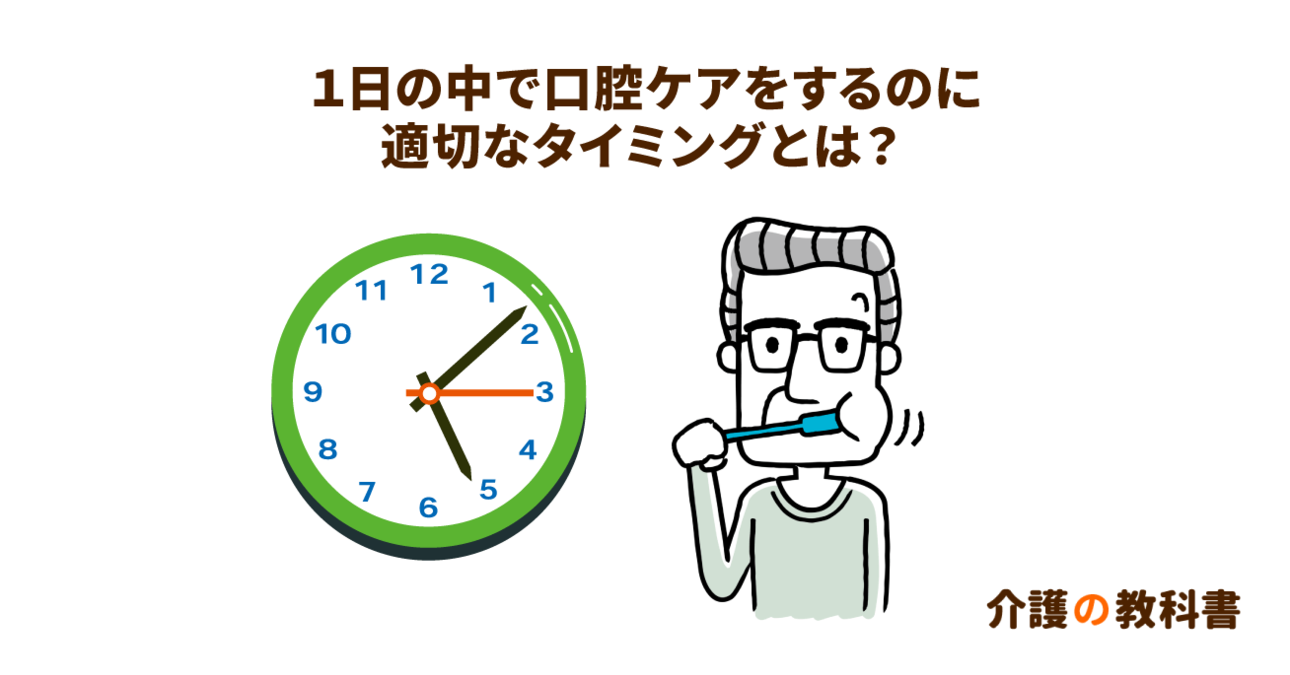プラークは歯垢とも言われ、よく知られていますが、どのようにできるかまで知っている人は少ないのではないでしょうか?
そこで、今回はプラークができる経過やプラークによって引き起こされる問題、日頃のケアにおける注意点について紹介いたします。
なぜプラークはできる?
プラークは、歯垢やバイオフィルムと呼ばれることが多い細菌の集団のことです。起床時などに歯にネバネバしたものがついていることがあるかと思います。このネバネバしたものがプラークです。
プラークは以下の5つのステップでつくられ、さらに増殖していくと言われています。
- 口腔内を浮遊している700種類を超える数百億個の細菌が、歯や粘膜の表面に細菌群をつくる
- 細菌群はネバネバした物質を介して細菌の集団をつくる
- 唾液や歯肉、粘膜からのしみ出た液体を主な栄養源として細菌は互いに信号を出しながら増殖。プラークを形成する
- プラークが成熟していくと、細菌の分布が変わり、多種・多様な細菌が共存できるようになり、細菌が住みやすい環境になる
- 細菌はさまざまな代謝を行うようになり、一部の細菌はプラークから出て、さらに新たなプラークをつくる
口腔内は細菌が増えるための湿度や温度、栄養の揃った環境にあります。形成されたプラークを放置しておくと、どんどん増殖してしまうので注意が必要です。
プラークによって生じる問題
口腔内のプラークは、口腔内の環境を悪化させてしまうだけでなく、むし歯や歯周病、口臭、味覚低下の原因となります。
また、プラークは全身の病気の原因になっていることも指摘されています。
誤嚥性肺炎や肺炎などの呼吸器の病気だけでなく、心臓疾患、動脈硬化、糖尿病、関節リウマチ、早産などにもプラークがかかわっていると言われています。
プラークコントロールについて
プラークコントロールとは、プラークを取り除き、口腔内環境を正常に保つことを意味します。プラークは、ネバネバした粘着物であり、細菌と細菌が産生する菌体外粘性多糖体(グリコカリックス)で守られています。
排水溝などのネバネバした物質と同じようなものと思ってください。そのため、抗生物質などの薬剤や、消毒液では十分にプラークの中まで浸透しません。もし浸透しても、これらはプラークへの効果がほとんどないと言われています。
そこで、プラークを機械的に破壊する必要があります。
よく、「食後にうがいをしたら大丈夫」と思われ、食事の最後にお茶などでうがいをされる方がおられます。緑茶のカテキンなどは確かに効果があるとも言われていますが、プラークはうがいだけではほとんど除去できません。
逆に、お茶や紅茶でうがいしたままでは、歯に色素沈着が生じ、むし歯の発見が遅れる要因となることもあり注意が必要です。
排水溝のネバネバした物質に洗剤をかけてもなかなか除去できませんが、ブラシでこすると簡単に除去できるのと似ています。歯のプラーク除去には歯ブラシや歯間ブラシでの機械的な破壊が大切です。

高齢者のプラークコントロールの注意点
近年は、多数の歯がある高齢者が増えてきています。しかし、加齢とともに歯周病が多くなり、歯の根元のむし歯の問題も生じやすくなっています。
歯周病で進行して残っている歯がぐらぐらとしている場合は、ブラッシングで痛みを感じやすくなり、プラーク除去が困難になることもあります。
また、高齢者では、生理的に免疫機能が低下しやすく、さまざまな病気や薬による影響を受けやすくなっています。唾液の減少や、口腔周囲の筋力が低下すると、プラークを自然に洗い流す自浄作用も低下してしまいます。
さらに、脳卒中や認知症などの病気により、口腔ケアをしっかりと行えない場合、増えてほしくない細菌が増えやすくなり、プラークが形成されやすい状況になります。
高齢者ではプラークコントロールがより大切な意味をもっていることを知っておきましょう。
食を楽しみながらプラークコントロールをしていきましょう
プラークを少なくしていくには、日常の食生活を見直すことも大切です。食事以外の間食回数を少なくすることも一つの方法です。
特に甘いものの間食は、プラークのエサとなりやすいと言われていますので、なるべく避けたほうが良いかもしれません。
しかし、認知症の方の場合などは、甘い物を好んでいたり、甘い物でないと食べてもらえないことも。また、1回の食事で必要な栄養量をとることができない場合は、間食が大切な栄養補給の機会にもなります。
このように、間食を減らすことによって低栄養の状態になったり、楽しみの機会が失われることがあり、間食の機会を減らさないほうが良い場合も多々あります。
そこで大切なのが食後の口腔ケアです。
食事をした後、お茶を飲みながら、お菓子を食べて過ごすこともあるかもしれません。そのような場合でも、食事の後はまずは口腔ケアを。そして、おやつの後も口腔ケアといった、食べた後はすぐに口腔ケアを行う習慣が大切です。
少しでも食べた後は口腔ケアを行う習慣を持つようにしましょう。
プラークコントロールには日々の歯ブラシや歯間ブラシを用いたケアが重要ではありますが、日々のブラッシングだけでは、十分にプラークは除去できないとも言われています。
また、プラークが唾液中のカルシウムによって硬化すると歯石になります。歯石は歯に強固に付着しているため、プラークのようにブラッシングだけでは除去することができず、歯科による専門的ケアを受けなくてはなりません。
そのため、日々のケアに加えて、定期的に歯科での専門的ケアを受けておくと安心できるでしょう。プラークや歯石を除去していくことが、プラークコントロールには大切です。