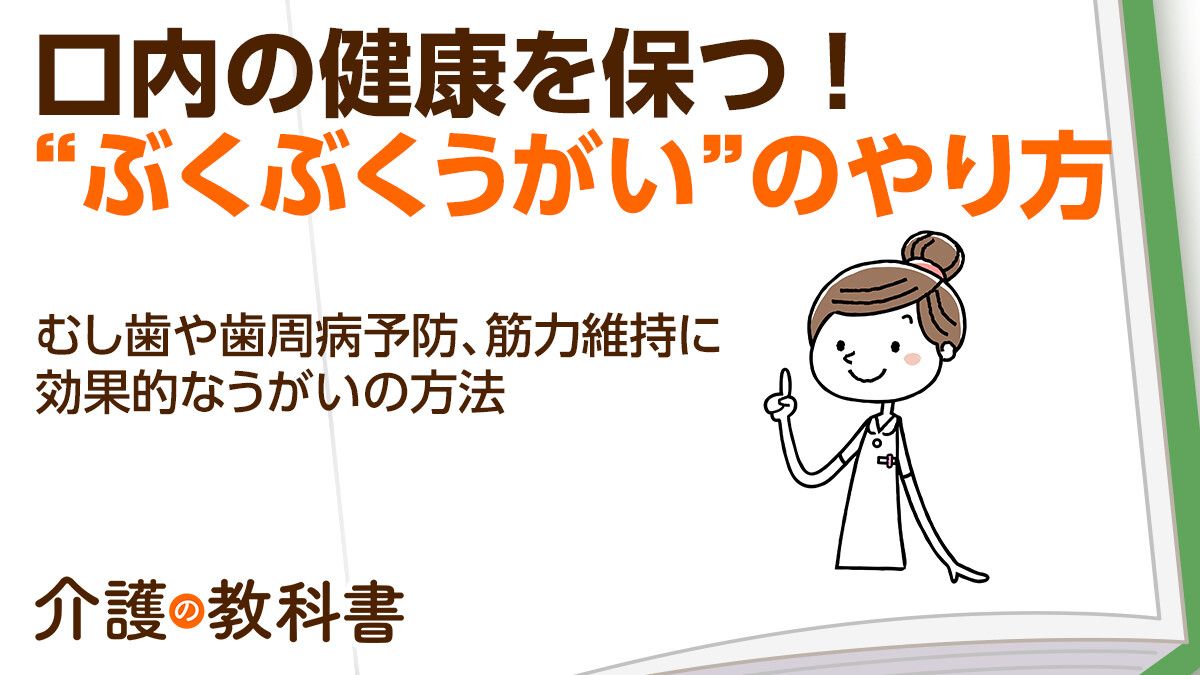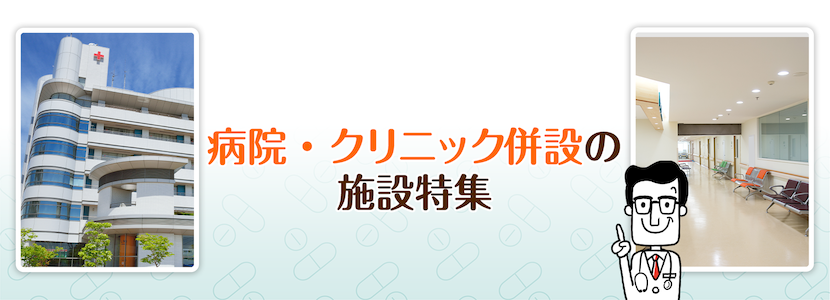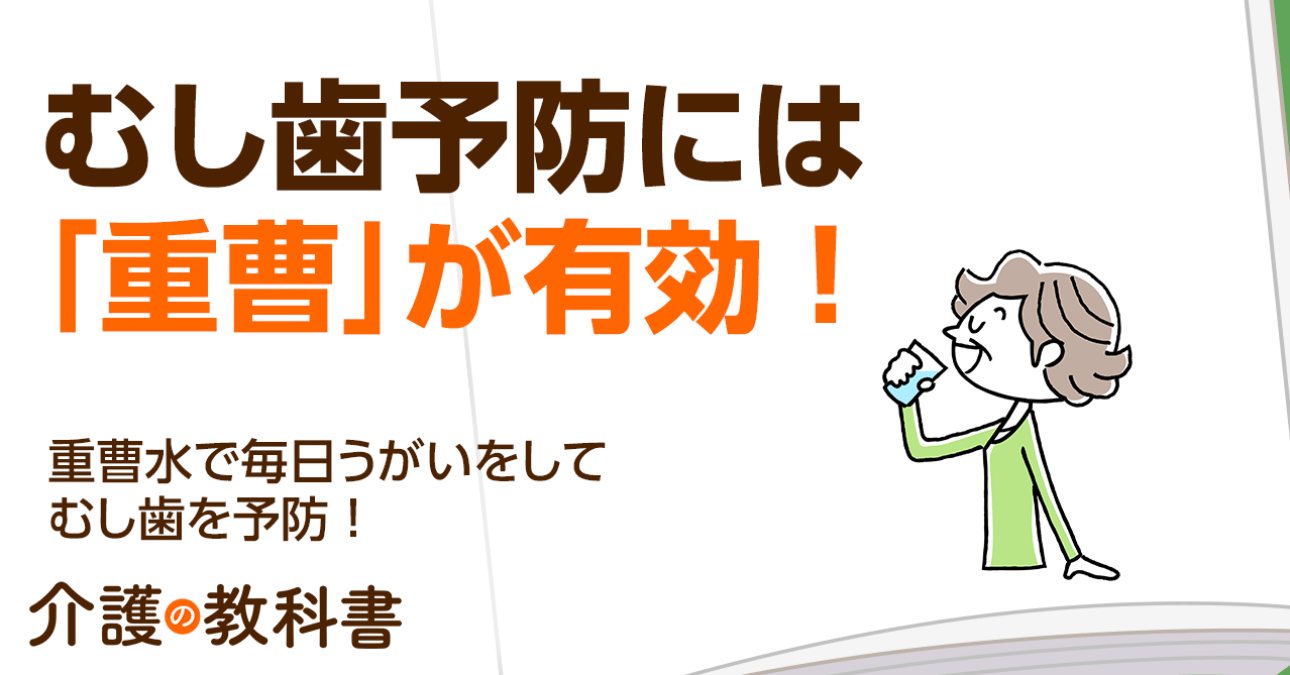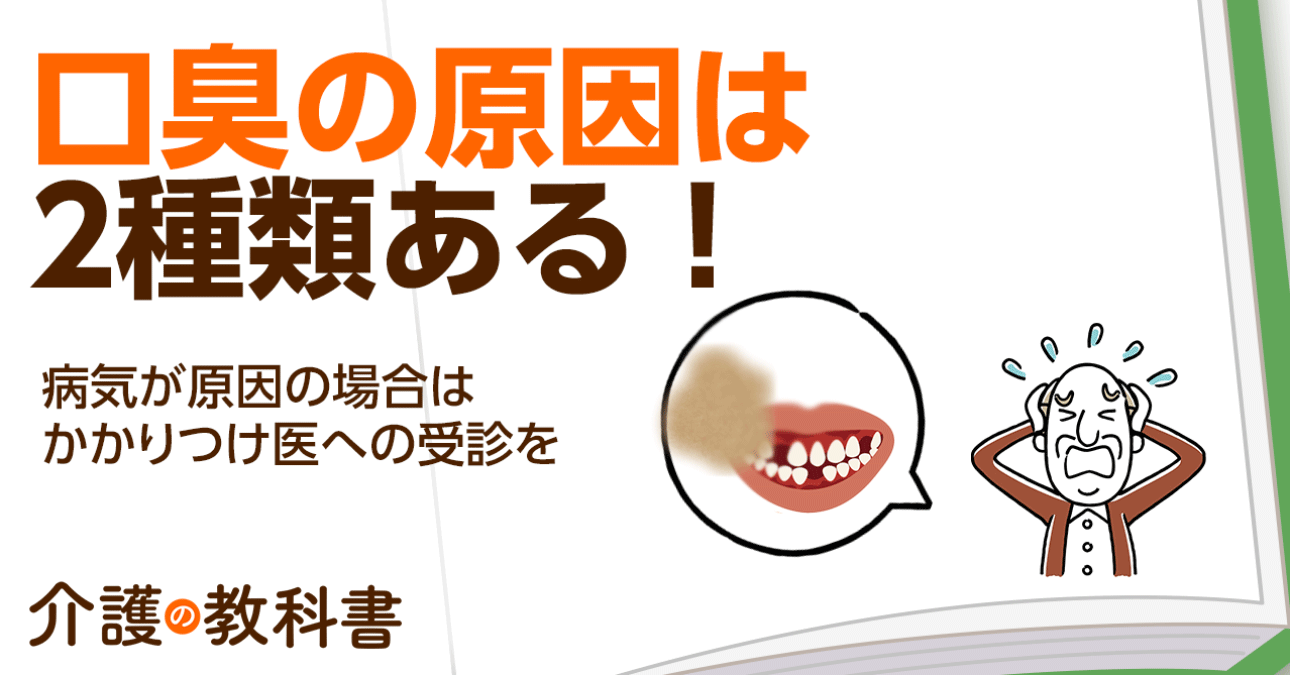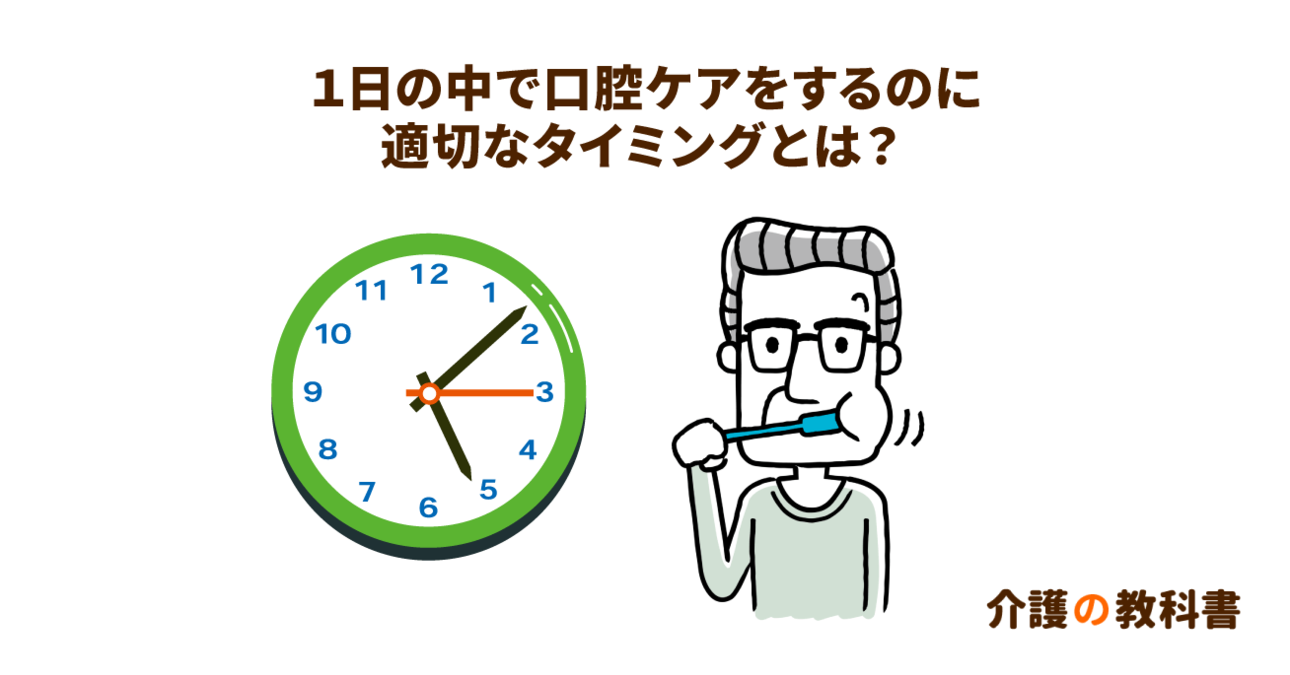近年は感染予防のため、うがいを日常的に行っている方が増えています。
しかし、うがいの具体的なやり方や注意点についてはあまり知られていません。
うがいには、口の中で行う「ぶくぶくうがい」と、上を向いて行う「がらがらうがい」があります。
特に高齢者にとって、口の健康維持に効果的であるぶくぶくうがいについて、その効果や洗口液の種類と注意点、効果的なやり方について解説いたします。
うがいの効果
ぶくぶくうがいの効果には、むし歯や歯周病の予防、口の周りの筋力維持があります。
- むし歯や歯周病の予防
- 口の中に水をめぐらすことで、細菌数を減少させ、むし歯や歯周病を防ぎます。また、細菌が減るので口臭予防の効果も期待できます。
- 口の周りの筋力維持
- ぶくぶくうがいは、しっかり口を閉じて舌や頬を動かすため、口唇や舌、頬の筋力を維持できます。
それだけでなく、嚥下機能の維持や顔の表情をいきいきと保つことにもつながります。さらに、うがいの際に唾液腺が刺激されるため、自然な唾液分泌を促す効果も期待できます。
洗口液の種類と注意点
多くの種類の洗口液(マウスウォッシュなど)が市販されているため、選択に迷ったり、飲料をうがいに代用される方もいらっしゃいます。
高齢者が洗口液を使用する場合には、いくつか気をつけたい成分と注意点があります。
歯周病予防に効果的な洗口液
特に高齢者には、歯周病を持つ方が多いため、歯周病予防に効果的な洗口液の成分を知っておくとよいでしょう。
歯周病予防に効果がある洗口液には、歯周ポケットの中にある細菌の塊に浸透して殺菌できるものや、歯肉の炎症を抑える効果がある成分が含まれています。
代表的なのは、クロルヘキシジングルコン酸塩、ベンゼトニウム塩化物などです。
しかし、これらの成分が配合されている市販の洗口液には、アルコール成分を含んでいるものが多いため注意が必要です。
アルコール成分を含んだ商品は、使用時にピリピリした刺激を感じたり、使用後に口の中が乾燥しやすくなるため、粘膜の弱い高齢者は避けた方が良いでしょう。
ポビドンヨードのうがい薬について
ポビドンヨードうがい薬は、うがい薬としてよく用いられており、口の中のほぼすべての細菌に対して強い殺菌作用をもっています。
しかし、口の中の乾燥や耐性菌の繁殖といった問題も生じやすくなるため注意してください。
エタノールを含むポビドンヨードのうがい薬は、口腔内を乾燥させてしまう可能性が高く、乾燥によって粘膜に傷をつける危険性が高くなります。
また、口の中で良い働きをしている菌までなくしてしまったり、使っている抗菌薬に対して耐性菌を生じたりすることもあります。
これらの点からも、ポビドンヨードのうがい薬を使用する場合は適正な濃度に調整して、1日に何回も使用しないように気をつけましょう。また、口の中に異常が出てきた際には使用を中止したほうが良いでしょう。
その他注意したいもの
緑茶は抗菌作用があると言われ、洗口液として用いられることがあります。同じような考え方で、ウーロン茶や紅茶が用いられることもあります。
しかし、これらの茶葉は歯を茶色に着色してしまい、むし歯の発見が遅れる原因になることもあるため、あまりおすすめはできません。
また、コーヒーやジュース、お酒類でうがいをされる方をみかけることもありますが、コーヒーは油脂、ジュースやビールには糖分が含まれているので、歯に残ってしまうと細菌のエサになります。
これらの飲料は、ぶくぶくうがいには使用せず、歯みがきや水でぶくぶくうがいを行うようにしましょう。

また近年は、水やぬるま湯(30℃程度まで)でしっかりとうがいを行えば、洗口液はあえて使う必要がないともされています。
効果的なぶくぶくうがいのやり方
ぶくぶくうがいだけでは歯垢を十分に取り除くことはできません。
そのため、食後には義歯を取り除き、歯みがきや歯間ブラシなどによる口腔ケアを行いましょう。その後にぶくぶくうがいを行うことが前提となります。
ぶくぶくうがいは毎食後や起床時、寝る前、外出から帰宅したタイミングで行うと良いでしょう。ポイントは以下の通りです。

- 多すぎず少なすぎない水を口に含む
- おちょこ1杯くらい、約30mlを口の中にいれましょう。水が多すぎても、少なすぎても効果が低下してしまいます。口の中で水を動かすことができる量が目安です。
- 順番を決めてぶくぶくうがいを行う
-
うがいは日常的に行っていますが、下の歯などは意識して行わないと効果的にうがいができていないことがあります。そこで、次のように順番と回数をある程度決めて行うと良いでしょう。
- 口の中全体に水をめぐらし、3回程度ぶくぶくして吐き出す
- 前の上の歯あたりで上口唇をしっかり膨らますように10回程度ぶくぶくして吐き出す
- 前の下の歯あたりで下口唇をしっかり膨らますように10回程度ぶくぶくして吐き出す
- 右の頬あたりで10回程度ぶくぶくして吐き出す
- 左の頬あたりで10回程度ぶくぶくして吐き出す
- 口の中全体に水をめぐらし、3回程度ぶくぶくして吐き出す
ぶくぶくうがいは可能な限り力強く行うと効果的です。口が疲れやすい方は、うがいの回数を少なめにし、慣れてきてから徐々に回数を増やしていくようにすると良いでしょう。
- 水は吐き出してから次の水を口に含む
-
ぶくぶくうがいをした後の水は細菌を多く含んでいるため、そのまま飲み込んでしまわないように注意しましょう。しっかり吐き出すことを意識してください。
今まで、口に水を入れて2~3回すすぐだけ、水を含んだらすぐに口から出してしまっていたような方は、ぜひうがいのやり方を見直してください。
ただし、抜歯やインプラントなどの外科的手術を受けた場合、数日はぶくぶくうがいは避けるようにして、水を口にいれて吐き出す程度のうがいを心がけましょう。
まとめ
今回はぶくぶくうがいについて解説しましたが、がらがらうがいにも、のどの細菌を少なくさせるなどの効果があります。
しかし、嚥下機能が低下している高齢者は、がらがらうがいで誤嚥を起こす危険性が高まります。
がらがらうがいをしてる間に水を飲み込んでしまう、むせるなどがある場合は、がらがらうがいは行わず、ぶくぶくうがいをしっかり行いましょう。
また、水分で誤嚥の可能性などがありうがいができない、ぶくぶくうがいが十分できない場合は粘膜ケアが必要になってきます。
日々のうがいを効果的に行い、口の健康を維持していきましょう。