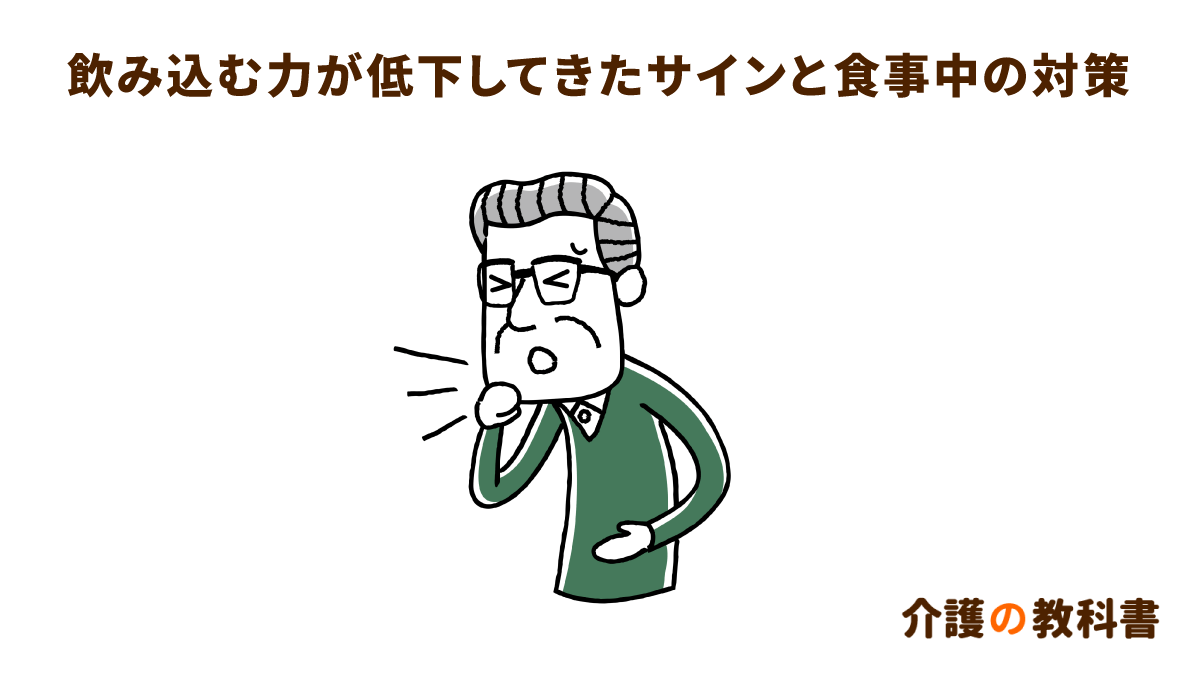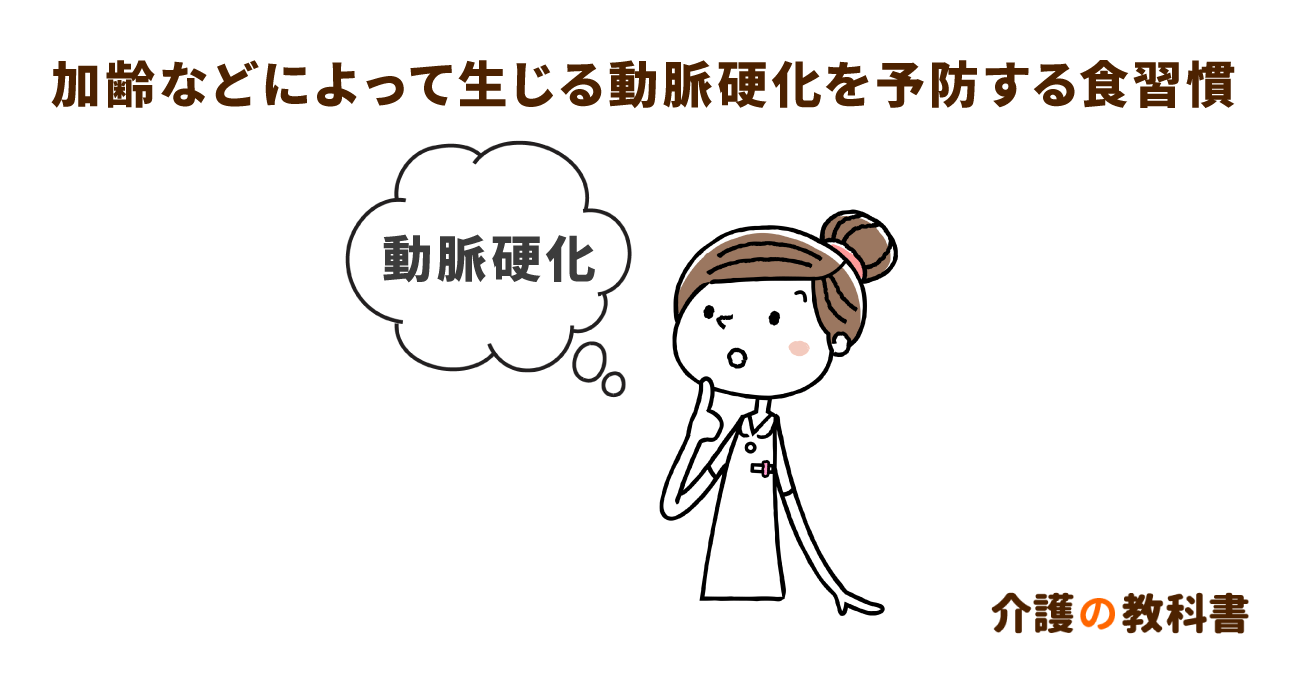加齢とともに、飲み込む力が弱くなってきたと感じる方も多いのではないでしょうか。
そうすると、誤嚥性肺炎などの危険性が高くなるので注意が必要です。
今回は、飲み込む力が低下してきたときのサインと、日頃から家庭で気をつけたい食事中の行動についてご説明します。
飲み込む力が低下してきたときのサイン
頻繁にむせてしまう
普段、食事中に飲み込みを意識することはあまりありません。しかし、少し意識を向けると、ちょっとしたサインに気づくことができます。一番気づきやすい症状は「むせ」です。
喉には、気管に食べ物などが入りそうになると、危険を伝えるサインとして「むせ」が生じる機能があります。
誰もがむせた経験があると思いますが、高齢者が食事中にいつも咳をしていたり、頻繁にむせてしまう場合は注意が必要です。
飲み込もうと思ってないのに、喉に入ってしまう
自分が思ってもいないタイミングで喉に食べ物が入る原因は、舌の筋力低下や、飲み込むタイミングが遅くなっていることなどが考えられます。
例えば、ミニトマトを食べたときに、「思いがけず水分だけが喉に入ってしまい、飲み込めずに気管に入った感じがした」「豆を噛んでいるうちに、思いがけず噛まずに飲み込んでしまった」というような場合です。
咀嚼する際は、舌で食べ物を奥歯に持っていき、咀嚼したものは徐々に舌によって喉に送り込まれていきます。その後、喉にある程度入った段階で、さらに噛んだ食べ物と一緒に飲み込んでいきます。
舌の筋力が弱くなると、食べ物を口腔内に保つ力が低下するため、意図しないタイミングで飲み込んでしまいやすくなります。
なお、飲み込みのタイミングには、主に食べ物を感じる力と、喉の筋力が関わっています。
喉は食べ物が入ってきたことを感じ取って脳へ伝えます。そして、脳からの指令にしたがって、飲み込みに関する筋肉が動きます。「うまく飲み込めなかった」と感じたときは、この感じ取る力が低下している可能性があります。
加えて、脳卒中などの病気や、薬の影響を受けることもあります。特に向精神薬や眠剤を服用している場合に、うまく飲み込めないことが頻繁にあったり、痰が増えたり、発熱する場合は、医療機関に相談しましょう。
喉の筋力も重要です。喉は前上方向に持ちあがり、収縮して食べ物を食道に送っています。
筋力が低下すると、喉が持ち上がりにくくなる、喉の収縮が不十分になりやすい、飲み込んだ後に食べ物や飲み物が残りやすい、むせるといった症状の要因となることがあります。
日頃から、飲み込みに関係する筋力を維持するために、「あいうべ体操」(第32回参照)などを行うと良いでしょう。
声質が変化した
次に気づきやすいのは、声質の変化です。
飲食後にうがいをしているようなガラガラした声は「湿性嗄声(しっせいさせい)」といい、飲み込んだ後も食べ物や飲み物が残っているサインです。
このように喉に残ったままの状態にしておくと、いつの間にか誤嚥していることがあるので、「ゴホン!」としっかり咳払いを行い、唾液を飲み込んで、喉に残ったものを飲み込むことが大切になります。
しわがれ声ともいわれる、かすれた声になった場合も注意してください。
声は声帯の動きや、声帯の適度な重さや柔らかさなどによって変わってきます。病気によって声帯の動きが悪くなったり、体重の減少で声帯が痩せてしまうと、左右の声帯の間に隙間ができ声がかすれることがあるのです。
この隙間が誤嚥の原因になることがあるので、日頃から痩せすぎないように食事をしっかり摂り、体重を定期的に測定していきましょう。

気をつけたい食事中の行動
誤嚥しやすいものは「さらさら」した飲み物
誤嚥しやすいといわれているものには、水分などの「さらさらしたもの」、餅などの「べたべたしたもの」、ゆで卵などの「ぱさぱさしたもの」、わかめなどの「ぺらぺらしたもの」などがあります。
特に誤嚥しやすいものは、さらさらした飲み物です。ゴクゴクと一気に飲むような行動には気をつけましょう。
また、ペットボトルは口元が狭いため、多くの水分を口に入れて飲んでしまいやすくなります。加えて、首を後ろに倒して飲むため、気管に飲み物が入りやすい姿勢になり、誤嚥の危険性が高くなります。
飲み物は口の広い浅めのコップに移し、コップから少しずつ飲むように心がけることが大切です。
そのほか、果物など噛んで水分が出るもの、汁物や薬と水などといった固形物と水分を一緒に口に入れるものにも注意が必要です。
食べるときの速度や環境
「昔から早食いだった」という方もいるかもしれませんが、ゆっくり食べる食習慣を身につけておくことが大切になります。
特に、麺類は吸いながら、ほとんど噛まずに食べていることが多いため、意識してゆっくり食べるように気をつけましょう。
また、テレビを観ながらだと目の前の食事に集中しづらくなります。反対に、テレビを消して食事に集中できる環境で食べると、食べるスピードや飲み込みを意識できるようになり、安全性が増します。食事中の環境にも気をつけていきましょう。

むせの頻度の増加や、声質の変化。
これらのサインの頻度を意識し、誤嚥しやすいものを知って対策を取ることが大切です。早食いや、ながら食べには気をつけ、ゆっくり味わって食べる習慣と環境をつくっていきましょう。
今回は、高齢者が飲み込む力が低下してきた際のサインと、家庭でできる対策について解説しました。
喉の筋力は、手足の筋力と同じように、加齢の影響を受けやすくなっています。筋力を維持できるように、日頃から口周りなどを動かしておきましょう。
飲み込む力の低下を示すサインが頻繁に見受けられたら、早めに医療機関に相談するようにしてください。