食と生を支えるコンサルタントナースの西です。
一般的に食事は「よく噛んで食べることが大切」といわれています。
この噛む行為は咀嚼と呼ばれ、食物を粉状態に細かく砕き、唾液と混ぜていく過程を指しています。
『令和元年国民健康・栄養調査報告』によれば、「何でも噛んで食べることができる」と回答した割合は75%で、年々増加傾向にあることがわかっています。
しかし、食事中の様子について「左右両方の奥歯がしっかり噛みしめられない」と回答した人の割合は、60代で45.8%、70歳以上で43.3%に上ります。このことから、4割以上の高齢者が咀嚼に何らかの問題を抱えていると考えられています。
今回は、この咀嚼について解説し、身体機能とのつながりや日頃から行いたいケアについてお話します。
咀嚼のメカニズムと基礎知識
咀嚼には、箸やスプーンで口の中に食物を入れたときに、どのようなものが入ったか「わかる」ことと、「食物を細かく砕く処理をする」ことの2つの過程があります。
「わかる」とは、舌が食物を口蓋(口の中の上側の部分)に押しつけ、硬さや温度などの食物の性質や状態などを調べる過程です。
ほんの一瞬なので、私たちはほとんど意識したことがないかもしれませんが、有害なものでないかどうかもこのときに調べています。
調べた結果、豆腐のような軟らかいものであれば、そのまま舌と口蓋で押しつぶします。
しかし、硬い食物とわかると、臼歯部(奥歯)へ舌で持っていって、舌と頬によって上下の歯の間に保たれ、「食物を細かく砕く処理をする」過程に入ります。
砕く処理をしている間は、下顎がリズミカルな動きと、舌や頬との協調運動で複雑な動きをしています。この過程では、食物は粉状に砕かれるだけでなく、唾液と混ざり、飲み込みやすい食塊(食物の塊)がつくられます。
食塊は、主に舌の運動でのどに送られ、飲み込まれます。
このように咀嚼には、歯や歯のまわりの組織、頬の筋肉、顎関節、舌など多くの器官がかかわっています。また、歯とともに適合した義歯も大切になります。
これらの器官に一つでも動きが悪いところがあったり、義歯が合っていなかったりすると、咀嚼が不十分になる可能性があります。
咀嚼は普段何気なく行っている行為です。
噛むことを意識してしまうと、時に舌を噛んでしまうこともあり、意外と上手くいかない特徴があります。
これは、食べ物が口に入ることで、頭の脳幹といわれている咀嚼中枢が刺激され、リズミカルな咀嚼運動を自動的に生み出していることと、食物を噛んだときの感覚が脳の大脳皮質に伝えられ調整されているからです。
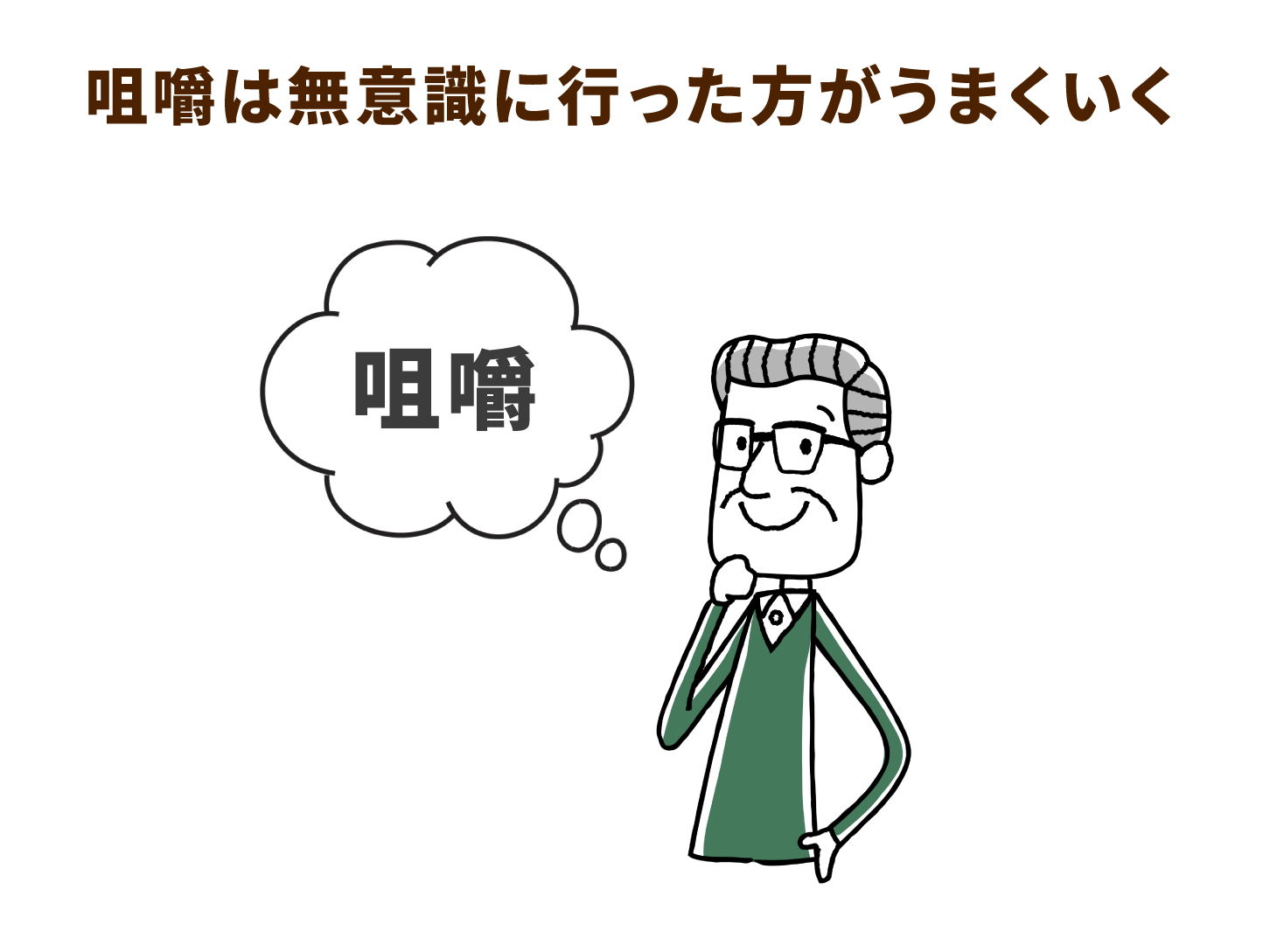
身体機能とのつながり
咀嚼機能が低下すると、硬い野菜やお肉などを避けて、軟らかいご飯などを好んで食べる傾向があるため、タンパク質、ミネラル、ビタミン類の摂取量が減少しやすくなり、炭水化物の摂取量が増えやすくなります。
特に、タンパク質は筋肉をつくる大切な栄養素であるため、不足すると筋力低下につながります。
また、認知機能維持のために、無理をしてもよく噛むようにしていたり、本人が軟らかい食事を希望していても、硬い食事を選ばされているという状況もあります。
本人の咀嚼機能に適していない硬いものを用意することで、食事摂取量が減少したり、美味しく食べることができず、食事が苦痛になったりすることもあります。
特に、噛み合わせや顎の関節に問題がある場合や、歯周病を持っている人が無理に硬いものを噛むと、強すぎる負荷を加えることとなり、かえって症状を悪化させてしまうこともあるので注意が必要です。
無理なく咀嚼でき、かつ楽しく味わえる食事を用意しましょう。
また、脳の機能を活性化させるためには、食べるときの”良い感覚”がポイントになります。
食事の見た目、味や香り、温度などで、五感を刺激し、脳へより多くの感覚を伝えることが脳の活性化につながります。
美味しいと思えるものを食べて、負担なく咀嚼することが認知機能にも良い影響を与えます。
日頃から行いたいケアや運動
咀嚼の回数は意識しない方が良い
咀嚼について「30回以上はよく噛んで食べたほうがいいですか」という質問を受けることがあります。しかし、回数を意識して噛むという行為はあまりおすすめしません。
味のあるガムを噛んでいるときは、脳の循環がわずかに増加するのは確かです。ただ、味のないガムを噛んでも脳の循環は変わらないと言われています。
美味しいと感じる範囲で楽しんで咀嚼することが、結果として脳にも良い記憶として残ります。
そうすると、次に同じものを食べたときに、その記憶がよみがえることもあります。食欲が出てきたり、楽しい気持ちになったりし、良いホルモンが分泌され、体にも良い影響をもたらすことが期待されます。
咀嚼に関わる器官のケア
咀嚼機能の維持には、咀嚼に関わる器官を日頃から動かしておくことが大切です。
特に、舌は咀嚼時に形を変え、必要な場所に食物を移動させる、とても大切な器官です。
舌を思いっきり出す、引っ込めるといった運動を行なったり、なるべく声を出す機会を多くしたりして、舌の運動を意識して行うと良いでしょう。
次に、咀嚼に大切なのが、健康な歯です。齲歯(むしば)と歯周病で歯を失わないために口腔ケアがとても大切になります。
毎食後に加えて、眠る前と起床時にも口腔ケアを習慣的に行いましょう。
また、歯科を定期的に受診し、義歯を使用している場合は良い状態で使用することも大切です。
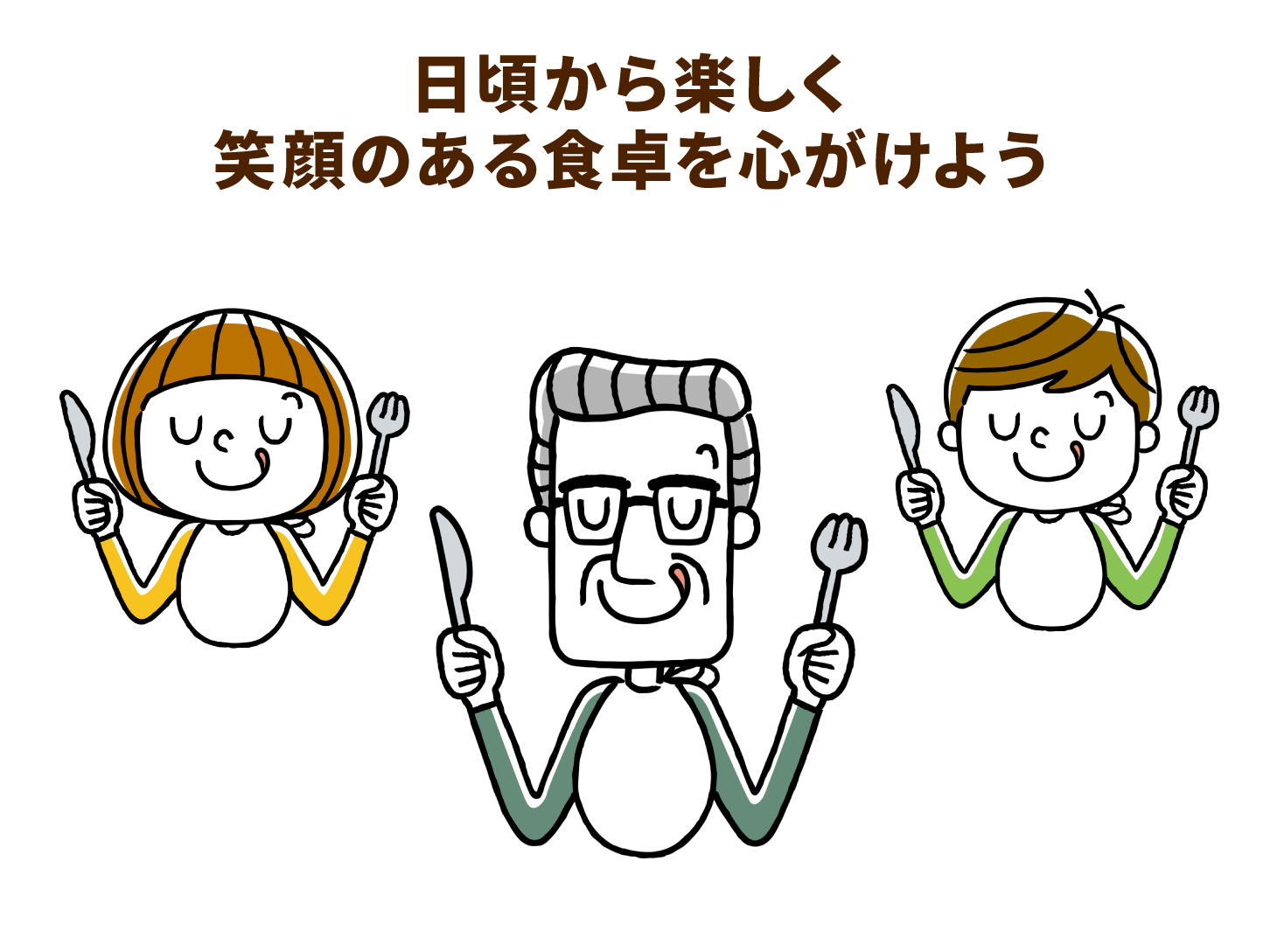
咀嚼機能は加齢とともに問題が生じやすくなる機能の一つです。咀嚼機能が低下すると、食べるものに変化が出やすいので、栄養状態の低下には気をつけましょう。
日頃からしゃべる、歌う、笑顔になるような食事を心がけ、よく味わって、楽しく食べることが、認知機能の維持にもつながります。
「よく噛んで」ではなく、「ゆっくり味わって」食べることを大切にしてください。
なお、硬いものが食べにくくなったときには、ほかにもさまざまな病気の可能性もありますので、早めに医療機関に相談してください。





















