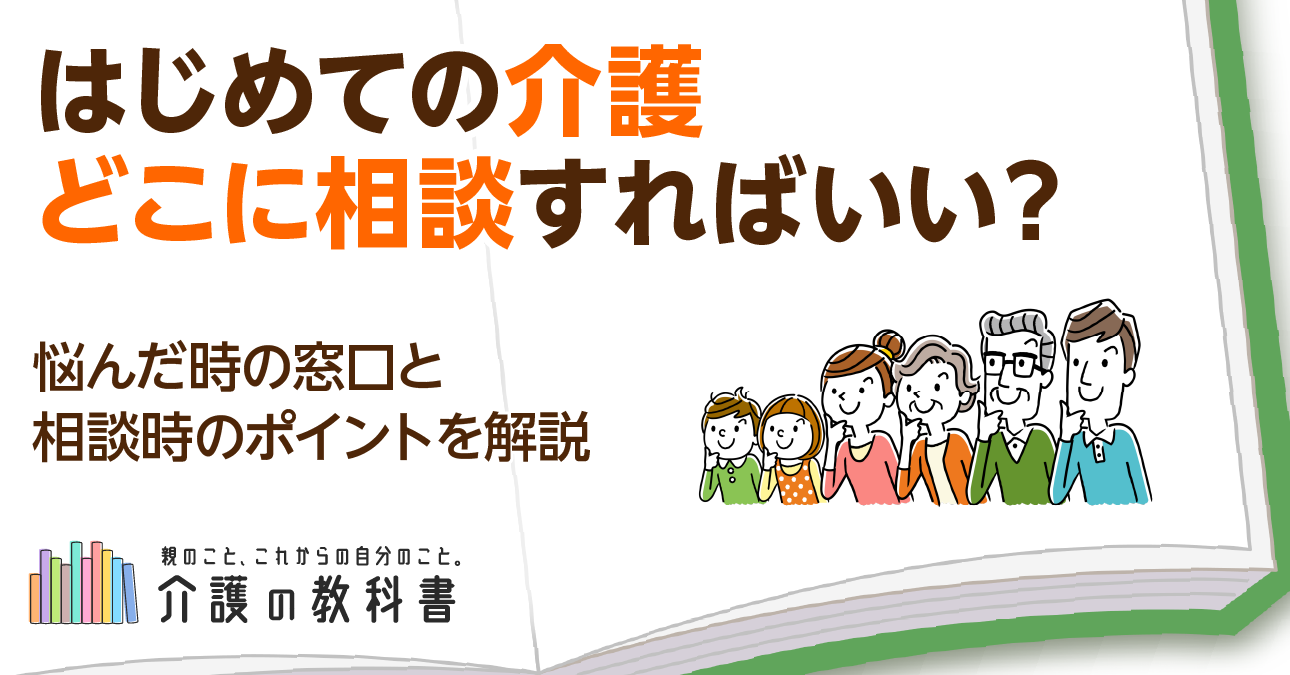こんにちは。「介護✕メンタル」を担当する「3Sun Create」代表で、介護職専門コーチ・研修講師の三田村 薫です(4月20日「介護リーダー養成1日集中講座」参加受付中)。
介護リーダー研修をしていると、リーダーの皆さんからさまざまな相談や質問を受けることがあります。今回は、よく相談される内容とその対応策をお伝えします。介護業界で働いている方は、思っていてもなかなか口に出せないということが多々あると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
その問題はどうなることが、あなたにとっての解決ですか?

私の研修では、スタッフとのコミュニケーションの質を高めるための手法やスタッフ育成法などを主にお伝えしているのですが、ときどき、「施設長や上司が現場のことを理解してくれない」「施設長の考え方がまったく理解できない」といったような、上司との関わり方についての相談も受けます。
先日の研修会で特養のフロアーリーダーさんからこんな相談を受けました。
業務を覚えられないスタッフがいて困っているが、何とか他のスタッフと一緒にフォローしてあげることで日常業務をこなしている。でも、施設長は「仕事が覚えられないようなら辞めてもらったらどうだ?」と言ってくる。今でも人員が足りない中でやっているのに、1人スタッフが減ってしまうとますます他のスタッフの業務量が増えてしまう。
求人広告を出しても応募がない中で辞められては困る。現場スタッフの中では「覚えの悪いスタッフでも居ないよりはマシだから仕方ない」と、スタッフ全員で協力しながらやっているのに、施設長が今度の面談でその覚えの悪いスタッフに退職についての話をする言っている。どうしたら良いですか?
簡単にまとめますと、「困ったスタッフに対して現場スタッフは辞めて欲しくないと思っているが、施設長は辞めてもらった方が良い」ということですね。現場ではその逆のケースもあります。困ったスタッフに対して現場スタッフからは辞めて欲しいと言っているけれど、施設長やフロアーリーダーは辞めてもらっては困ると言っているというケースもよくあると思います。
私がいつもさまざまな相談を受けて最初に伺うのは、「その問題はどうなることが、あなたにとって解決ですか?」ということです。この事例の場合は、どうなることが解決(理想)なのでしょうか?
問題解決力を身につけるためには、その問題について「考える」必要があります。当たり前のことのようですが、問題について「考える」ことが問題を解決するためには必要です。でも、その考え方の方向性を間違えると、ますます問題が大きくなり八方塞がりになってしまうのです。
仕事をしていると、解決しやすいものから難しいものまで、たくさんの「問題」が発生します。早い段階で問題を解決するためにはまず、「何が問題なのか?」を明確にする。そして、「どうなることが解決なのか?」「これが解決だ!」「これが理想だ!」と思える状況を考える必要があります。ですが、実際はほとんどの人が自分の理想となる状態を明確にしないまま、問題だけにフォーカスしてしまっているのです。理想となるゴール、これが解決という状態が定まっていなければ、自分が行うべき対応策がわからないのは当然です。
人は、目の前の問題や課題に囚われていると「人がいない」「時間がない」「業務が山積している」「スタッフ同士の仲が悪い」と自分以外の環境や他人に目が向いてしまいがちです。これは、安心安全を保つための人の本能だと言えますが、問題を解決するためには、自分が影響を及ぼすことができるところに意識を向けた方が問題を解決するための近道になります。
覚えが悪い人はメモのとり方が下手? メモの上手なとり方を教えよう!
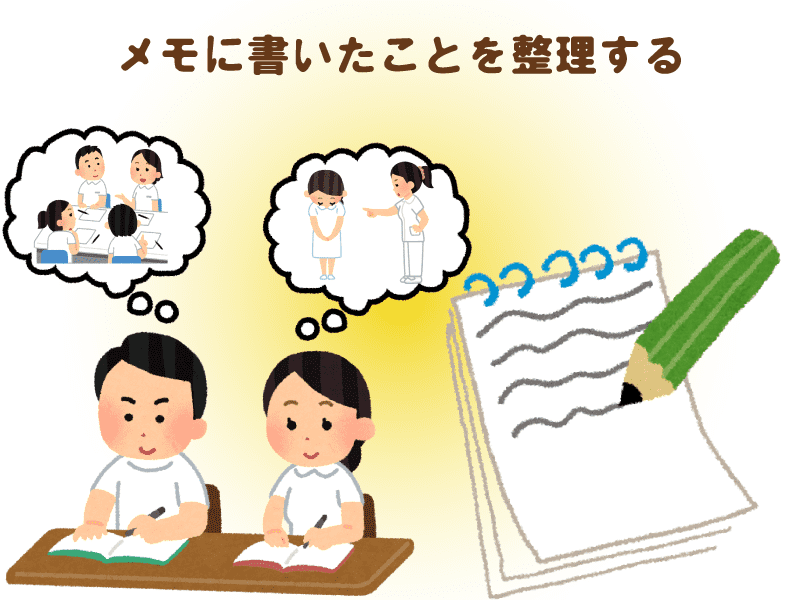
私たちの意識は基本的にひとつのことにしか向けることはできません。つまり、同時に複数のことに意識を向けることは難しいのです。例えば、楽しかった思い出と悲しかった思い出を同時に思い出してくださいと言われても難しいはずです。また、私たちは自分の興味関心のあるものをキャッチするという特性があります。
あなたも、介護を行うようになってから、または介護職になってから、街を歩いていても〇〇デイサービスというデイサービスの社用車を見かける回数が増えたような気がしたり、新聞を読んでいても「介護」や「高齢者」、「〇〇施設」などの介護に関連する見出しが目に入ってきたり、スーパーに買い物に行っても、杖やクツといった介護用品売り場を見かけることが多くなったりした気がするといったことがあるのではないでしょうか?これは、私たちの脳が自分の興味関心のあることをキャッチしやすいということを表しています。このように、意識はひとつのことしかキャッチしません。
そうすると、「スタッフ同士の仲が悪いからチームケアができない」「業務を覚えてくれないスタッフがいて困る」「人が足りないから、私が残業するしかない」と問題だけにフォーカスしてしまうと、余計に問題が増えていくことになります。
当たり前のことのようですが、目の前の問題を自分の意識で考え解決策を発想しなければなりません。しかし、意識が問題だけにとらわれていると視野が狭くなり、柔軟な考え方ができなくなります。解決策を発想するためには、柔軟な思考が必要なのです。問題を早い段階で解決するためには脳の機能からいっても、目の前の問題や課題に目を向けるのではなく、その問題や課題が「どうなったらいいのか?」「どうなるのが理想なのか?」「どうなることが解決なのか?」を先に考えることです。
ご相談をお受けした事例の場合は、「どうなることが解決ですか?」と伺うと、「今のスタッフが仕事を覚えてくれることです」という解決案が出てきました。
私:「今のスタッフが仕事を覚えてもらうためにできることは何ですか?」
リーダー:「スタッフ自身も仕事が覚えられないことは自覚していて、細かく業務内容をメモしてもらっているんですけど…」
私:「そのメモを見たことありますか?書いているメモが間違っている可能性はないですか?」
リーダー:「そうですね。一度もメモを確認はしたことないです。確認してみます」
私:「では、辞めてもらおうと言われている施設長には、どんな風に話をもっていきますか?」
リーダー:「…どうしましょう?」
実は、業務がなかなか覚えられないスタッフで多く見られるのは、メモのとり方やまとめ方自体が上手ではないのです。どこにメモしたのかわからない、メモに何か書いてあるけど何のことかわからない、メモが時系列になっていない、メモ帳が何冊もあってすぐに確認できない、こんな風に、メモ帳がバラバラということは、スタッフの頭の中が整理されているはずがありません。この事例の場合はひとまず、業務が覚えられないスタッフが書いているメモ自体を確認してみるということになりました。
リーダーもメモをとることで人に上手く伝えられるようになる!
では、意見の違う施設長には、どんな風に話をすればとスムーズにいくのでしょうか?言いにくいことはさらっと言ってしまいたい、それとなく言いたい、はっきりと伝えたい気持ちはあるものの、職場での人間関係において角が立つような状況はできるだけ避けたいというのも本音です。「あぁでもない」「こうでもない」と伝え方をあれこれ悩み続けていると、いっそだんまりを決め込んだ方が楽かもしれないと思ってしまう。
私も以前は言いにくいことをはっきりとは言えず、それとなく伝えたり、何もなかったようにだんまりを決め込んでみたりと、改善を相手に委ねるタイプでした。しかし、リーダーになれば言いにくいことを相手にハッキリと伝えないと自分の業務が進みません。後々になって「言い忘れ」があったり、伝えたこととまったく逆の意味で伝わっていたりで、余計に面倒な事態になることもしばしばありました。
自分の言いたいことを言わない、自己主張しないことに慣れてしまうとストレスが溜まるばかりでなく、リーダーとしての信頼を失いかねません。言いにくいことであろうとも主張した方が後の人間関係のためには大事なのではないかと思います。とはいえ、伝えようとすればするほど上手くいかずにギクシャクすることも多々あります。いったいなぜなのでしょうか?言いにくいことが言えないのは、言った後の相手の反応が気になり、「こんなこと言って傷つけたらどうしょう」、「気まずくなったらどうしよう」と考えるからではないでしょうか?
言いにくいことを伝えるときこそ大切なのは、決して感情的にならないこと。感情的になると自分本位な話し方が目立ち、相手をより不快にさせ、話を聞き入れたくない状態にしてしまいます。冷静さを保っていれば、相手の立場を理解し、聞き入れてもらいやすい話し方もできるはずです。
「とにかくやってみる!」はダメ、何事も計画は大事に練る
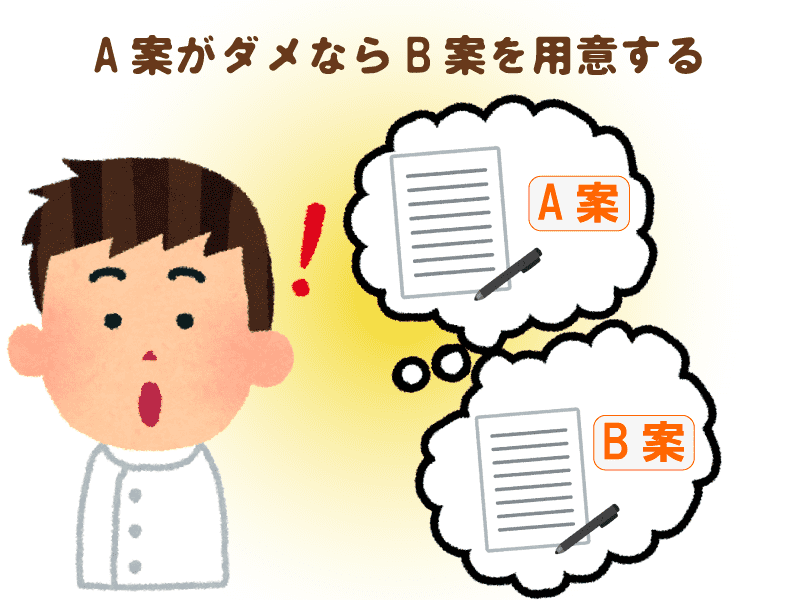
私は、言いにくいことはあらかじめ紙に書いて用意し、「○○さんにどう受けとられるか心配だから紙に書いてきたの」と正直に話してから伝えていました。そうすると、「正直に話してくれてありがとう」と好意的に受け取ってくれ、言ったあとから「あのこと言い忘れた」ということもなくなりました。
①現状、②私の想い、③要望・提案、④(③に対する)私の想い、というステップを踏む文章を組み立てみましょう。
- ①現状:今現在の状況を簡潔に伝える。
- ②私の想い:「私は」を主語にして今の気持ちを伝える。
- ③要望・提案:現実的かつ具体的な要望や提案をします。
- ④(③に対する)私の想い:「助かる」「うれしい」などを伝える。
今回の事例の場合なら…
(①現状)現場のスタッフは、人が減って業務量が増えるより、多少のフォローが必要であっても今のスタッフに仕事を覚えてもらった方が良いと思っています。
(②私の想い)何ヵ月も求人広告を出しても応募がない中では、すぐに応募があるとも思えませんし、人員が減って、今以上に他のスタッフの業務負担が大きくなることは避けたいんです。
(③要望・提案)それでも、施設長が辞めてもらって新しい人に来てもらおうと言われるのであれば、新しい人が決まってからにしてください。
(④要望に対する私の想い)この件に関して再度、3ヵ月後(〇月〇日)にご相談させてもらえると嬉しいです。
この事例のように、すぐに答えが出ないような場合は、期間を区切って再度話し合う日時を決めておくとことで、A案がダメだったらB案というように、絶対にA案じゃないとダメだというプレッシャーが軽減され、一人で抱え込まずに済みます。
言いにくいことはさらっと言ってしまいたい、それとなく言いたいと思わず、言いにくいことだからこそ丁寧に自分の気持ちや想いを相手へ伝えることが大切なのではないでしょうか?丁寧に伝えることで、「そんな風に伝わっていると思わなかった」「そんなつもりで言ったわけじゃないんだけど」と後々になって面倒な状況を作ってしまうことを防ぐことができます。
介護職員研修をしていて感じるのは、目の前の物事に対して何の予備知識や準備もすることなく、とにかくやってみるといった人が多いことです。私自身も含め、とにかくやってから考えるといった傾向にあります。行動力があるとも言えますが、反面では計画性がないとも言えます。計画性がない分、継続することが苦手だったり、定期的な点検や見直しが苦手だったりします。あなたの目の前の問題が解決されずに同じことを繰り返しているのであれば、やり過ごしてきたことを見直してみてください。言いにくいことだからこそ、事前に準備して丁寧に伝える。そうすることで結果は違ってくるはずです。