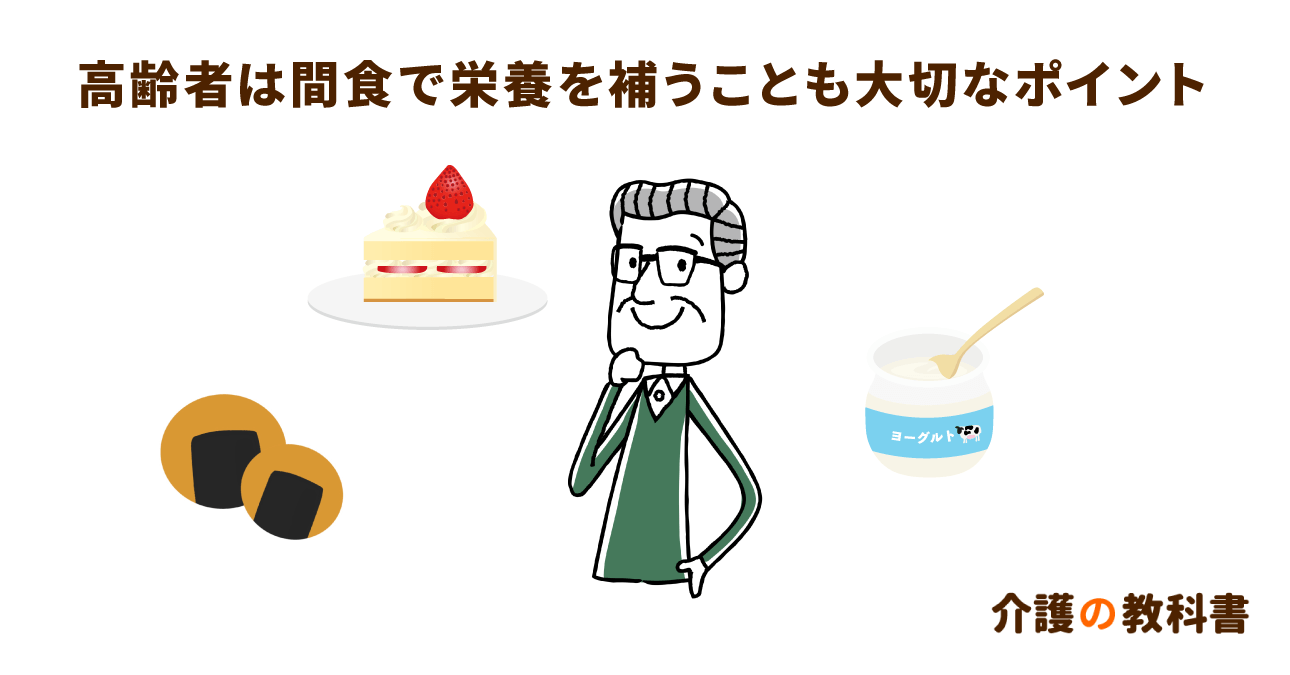今年も暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。9月に入っても脱水にはまだまだ気を付けなくてはなりません。
脱水は日頃の生活の中で予防ができます。日頃の食べ物に注意しながら安心して毎日を過ごしましょう。
1日で体を出入りする水分量
水分は私たちが生きていくために不可欠なものです。私たちの体の水分量は、体内の約60%だといわれています。
生きていくために常に一定の水分量を保っていますが、それぞれの生活環境(気温・湿度)や日々の活動によって変わります。
私たちは平均的に飲料水から約1,200ml、食事から約1,000mlの水分を摂取しています。体内で栄養素がエネルギーになるときに生成される「代謝水」約300mlも水分となるので、1日合計約2,500mlに及びます。
一方、体外に排出される水分の主な要因は、排尿や排便です。1日約1Lから1.5Lの水分が出ています。下痢や嘔吐があると、その分、多くの水分が出ていきます。
季節によっても出ていく水分は違います。夏場は気温の上昇により大量に発汗することもあります。冬場でも感染症による下痢が続いた場合や、こたつに入っている場合など、持続的に汗が出るシーンがあります。
また、呼吸や唾液からも1日約1L程度の水分が出ています。
毎日出入りをしている水分は、一度にたくさん飲んで体に貯めておけないので、必要な水分を毎日摂取することが大切です。
高齢になると、喉の渇きを感じにくくなったり、水分を飲み込みにくくなることで水分の多い食品が食べにくくなり、食事から摂る水分量が減ってしまうこともあります。つまり、脱水になりやすい状態になるのです。
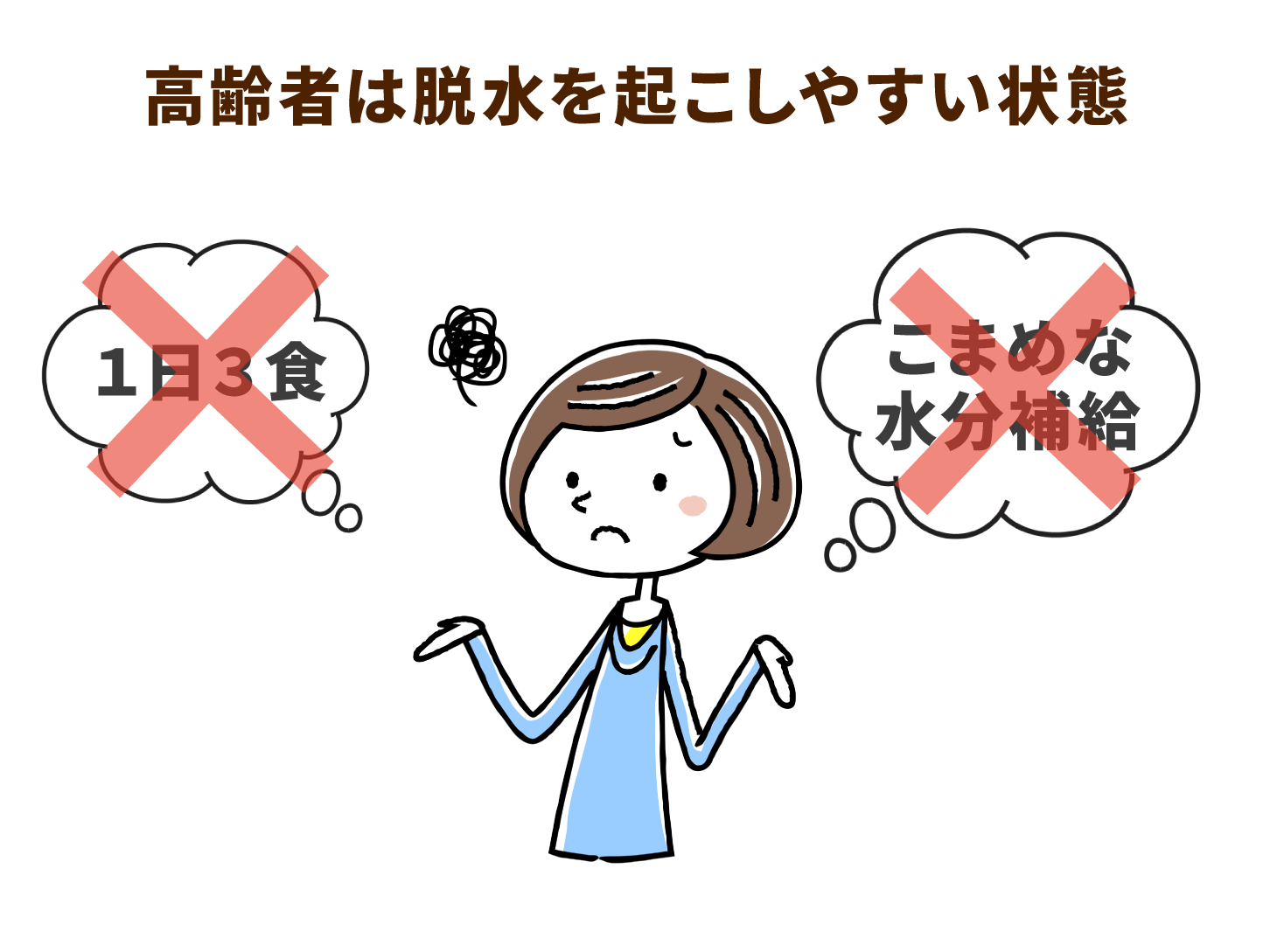
脱水になったときの症状と対策法
脱水の症状を軽度・中度・重度の程度別に分けてそれぞれの対策法を紹介しましょう。
軽度
- 皮膚の乾燥・唇のかさつき・口の中の乾燥
- 手の甲の皮膚をつまみあげてすぐにもどらない
- 爪を押してから色がすぐに戻らない
このような症状が続く場合は、脱水症を疑う必要があります。このほか、めまいやふらつきなどの症状がでていたり、血流が悪くなって手先や足先が冷たくなってしまうこともあります。
対策法
水分と体の機能を調節してくれるミネラル(電解質)を効率よく摂るために経口補水液をおすすめします。
経口補水液はスーパーやドラックストアで販売していますので、脱水しやすくなる夏場は数本準備しておくと便利です。経口補水液が準備できない場合は、普通の水でも大丈夫です。
中度
- 軽度の状態から症状が悪化し、頭痛や吐き気などを訴える
- 身体の水分量が不足し、汗や尿の量が減る
- 身体の中の水分が減ったことにより体重が減る
- 嘔吐や下痢などの症状が出る
対策法
まず脱水の症状に気づいたらすぐに経口補水液を多めに飲みましょう。下痢がある場合は、トイレの後にこまめに経口補水液を摂取しましょう。
嘔吐がある場合は飲みこむのも大変だと思いますが、吐いた後にも経口補水液を飲み、症状が落ち着かない場合は病院に受診しましょう。
重度
- 意識がもうろうとする
- 声かけをしても反応が悪い
- 意識を失ったり、けいれんを起こす
対策法
意識を失ったり、けいれんがある場合は、すぐに病院に行くことをおすすめします。

脱水を防ぐ自宅での工夫
1日に必要な水分量を知る
1日に必要な水分量の目安は、体重1kg当たり30~40mlといわれています。体重50㎏の方であれば毎日1,500ml~2,000mlの水分が必要になります。
毎日3食食べていると、食事で約1,000mlの水分は摂取できていますので、残りの約1,000mを食事以外で摂取する必要があります。
家で使っているコップにどのくらいの水が入っていて、何杯飲めば目標量の1,000mlになるのかを知っておくことをおすすめします。

部屋の湿度や温度を調整する
新型コロナの感染予防のために室内で過ごす時間が増えた方も多いのではないでしょうか。
換気やエアコンによって普段いる部屋の環境を整えることで身体の水分を保つことができます。夜寝ている間にも身体から水分が出るため、必要な水分量が摂れていないと脱水症になる可能性もあるので注意してください。
必要なタイミングで水分を補給する
- 起床時:寝ている間に出ている水分を補給します
- 食事前:空腹時は身体の水分が減っている状態になっています
- 運動や家事を行う前後:運動や家事を行う前も水分補給が必要です
- 入浴後:入浴は汗で身体の中から水分が出ています
- 飲酒後:飲酒により尿の量が増え身体から水分が出てしまうため、飲酒後にもきちんと水分補給を行いましょう
このほか、汗をかいたり、下痢や嘔吐がある場合もこまめに水分補給が必要です。
好みにあった飲み物を準備する
脱水予防のためにと思い、経口補水液など飲み慣れない物を買っていても、高齢者にはなかなか飲んでいただけないことがあります。
その場合は無理に飲み慣れない物を飲ませる必要はありません。まずは、好きな飲み物を購入し準備しておくことで普段から少しずつ飲んでもらえるよう工夫しましょう。
水分が多い食べ物で水分を補給する
高齢者は飲み込むときにむせたり、喉の渇きを感じないことなどから水分を飲むことが苦手な方も多くいます。そのような方には食べ物から水分を摂る方法もあります。
食事から摂取できる水分量の目安は以下の通りです。
| 食品名 | 1食の平均量(g) | 水分量(g) | |
|---|---|---|---|
| ごはん | 茶碗1杯 | 150 | 90 |
| 全粥 | 茶碗1杯 | 150 | 125 |
| 食パン | 6枚切1枚 | 60 | 24 |
| ロールパン | 1個 | 30 | 9 |
| あんぱん | 1個 | 100 | 37 |
| クリームパン | 1個 | 100 | 36 |
| ゆでうどん | 1玉 | 200 | 150 |
| ゆでそば | 1玉 | 160 | 109 |
| 里芋 | 皮むき中1個 | 約55 | 46 |
| じゃがいも | 皮むき中1個 | 135 | 109 |
| ゆでじゃがいも | 皮むき中1個 | 140 | 113 |
| 木綿豆腐 | 1/4丁 | 75 | 64 |
| 絹豆腐 | 1/4丁 | 75 | 66 |
| カボチャの煮物 | 約1/8個 | 100 | 84 |
| キャベツ | 外側1枚 | 80 | 74 |
| キュウリ | 1本 | 100 | 84 |
| タマネギ | 1/2個 | 90 | 81 |
| なす | 中1/2本 | 35 | 33 |
| ニンジン | 中1/3本 | 45 | 40 |
| ほうれんそう | 1/4束 | 45 | 42 |
| サニーレタス | 1枚 | 30 | 28 |
| いちご | 3個 | 45 | 40 |
| みかん | 1個 | 80 | 70 |
| りんご | 皮なし1/4個 | 53 | 45 |
| バナナ | 皮なし中1本 | 96 | 72 |
| 真アジ | 皮つき水煮1匹 | 90 | 63 |
| サケ | 皮つき除く1切 | 80 | 48 |
| 牛モモ肉 | 脂身つき生(薄切り4枚) | 75 | 46 |
| 豚モモ肉 | 脂身つき生(薄切り4枚) | 75 | 51 |
| 若鶏ムネ肉 | 皮つき生1枚 | 100 | 73 |
| 卵 | 生1個 | 55 | 41 |
| 牛乳 | 普通牛乳 | 200ml | 175 |
| ビール | 1缶 | 350ml | 325 |
調理法により、食品の水分量がそのまま身体に入るわけはないですが、改めて数字で見ると、食品から摂っている水分も多いことに気づくと思います。
食べ物に関しては、採取する季節や環境で水分量をはじめとして、栄養量も変化しますが、上の表を見てみると、牛乳などの飲み物では水分量が多く、高齢者でも摂りやすいことがわかります。
野菜も水分が多い食材ですが、高齢になると歯の状態や飲み込む力が弱くなり、普段から野菜をたくさん食べることが大変になる方もいます。
このような方は野菜をゆでる、炒める、そのほかスープに入れることで食べやすくなりますので、どの調理法なら食べやすいか好みや状態に合わせて工夫してみてください。
間食などでは、水分を多く含むフルーツ、ゼリーや水ようかんなどからも水分摂取に有効です。「水を飲まなきゃ」と高齢者本人が意識しなくてもおいしく食べられるため、自然と水分を摂取しやすくなります。
次に料理として食べるものから摂れる水分量を示しましたので、本人の好みや体調に合わせて、用意してみてください。
| 料理名 | 100gに含まれる水分量 |
|---|---|
| 八宝菜 | 86 |
| 麻婆豆腐 | 80 |
| 青菜の白和え | 79.7 |
| いんげんのごま和え | 81.4 |
| 豚汁 | 94.1 |
| なます | 80.3 |
| 筑前煮 | 80.4 |
| 肉じゃが | 79.6 |
| ひじき炒め煮 | 80.8 |
| アジ南蛮漬け | 78 |
| チキンカレー | 75.2 |
| ビーフカレー | 78.5 |
| 卵豆腐 | 85.2 |
| コーンクリームスープ | 80 |
| オレンジゼリー | 77.6 |
| バニラアイス | 65.6 |
脱水は夏場だけと考えがちですが、1年中注意が必要です。毎日できる脱水予防を意識しましょう。