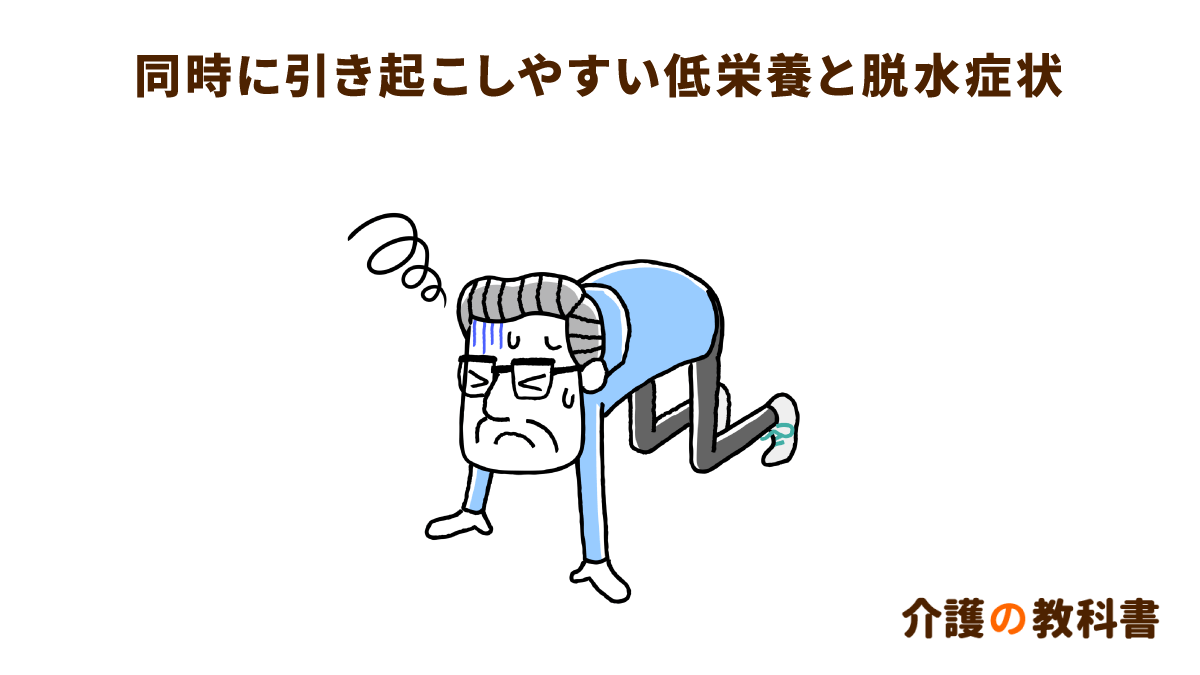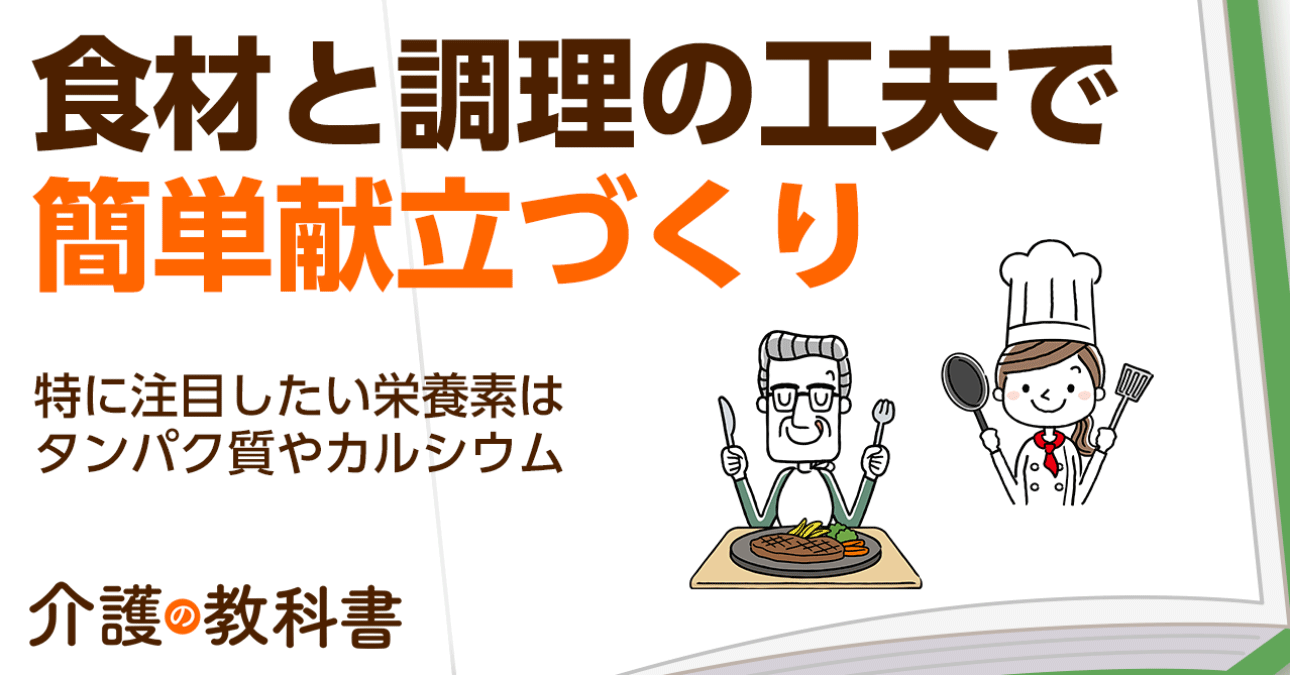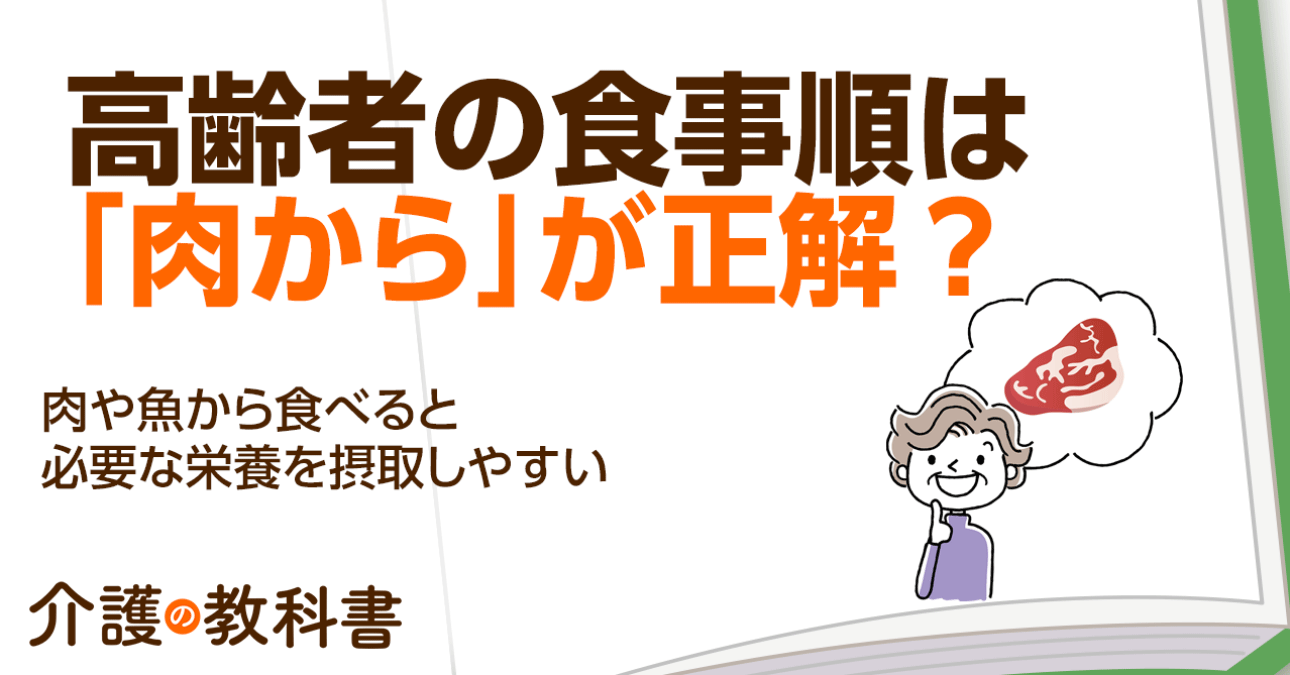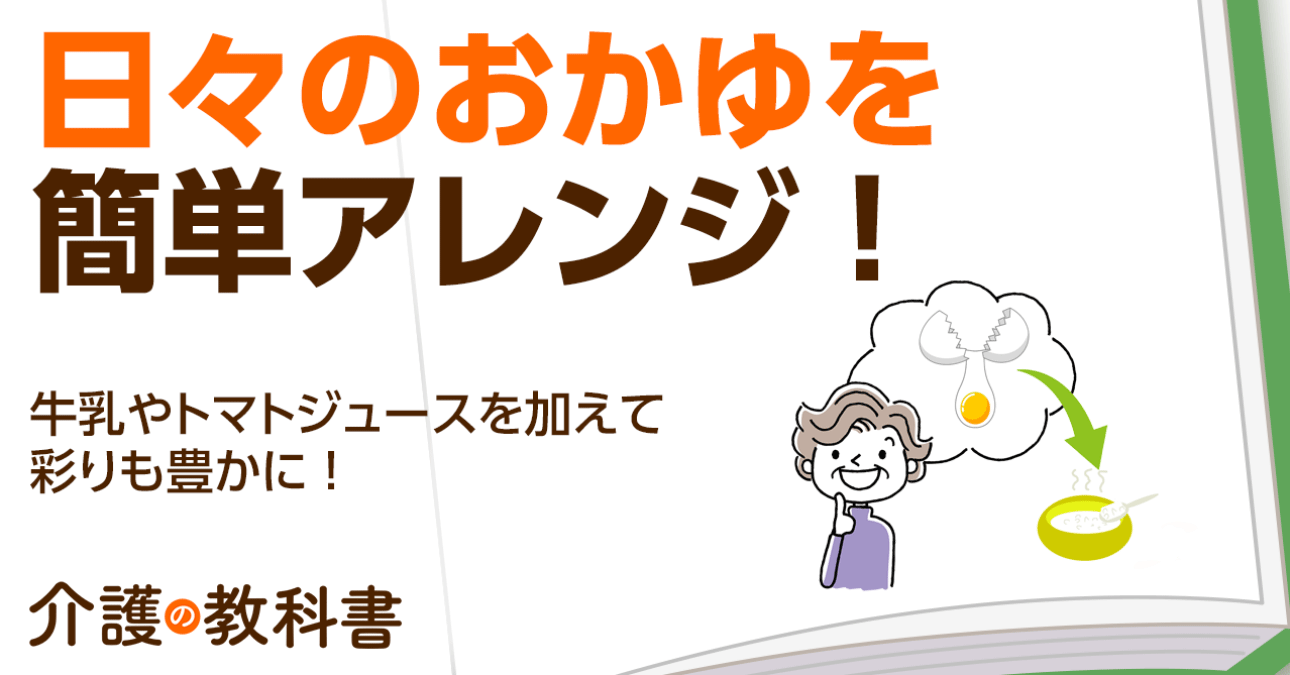高齢者は身体機能や気力の低下によって、食事量が減るケースが多くみられます。食事量が減ると、低栄養だけでなく、脱水症状の危険も高まります。低栄養と脱水症状は一見関係がないようにみえますが、同時に起こりやすいのです。
今回は、低栄養と脱水症状が同時に起こる理由と症状、予防のための食事例について紹介します。
低栄養と脱水症状が同時に起こる理由
もともと、高齢者は脱水症状のリスクが高い状態です。高齢者は喉の渇きを感じる機能が低下しているため、脱水に気づきにくくなっています。
実際に喉の渇きを感じても、その後トイレに行くのが面倒だったり、尿失禁を心配して、水分を十分に摂らない可能性があります。
さらに、体にため込める水分量も減っているため、発熱や下痢などの体調不良で、水分が容易に失われてしまいます。
また、脱水症状が起こる際、同時に低栄養になっていることも多くあります。その理由を詳しく説明します。
食欲低下
食欲低下によって食事量が減ると、十分な栄養素が確保できず、低栄養につながります。また、水分摂取量も減りがちです。
一般的に、食事から摂取できる水分量は1日当たり約1,000mlとされています。しかし、食欲低下によって十分な食事を摂れない状況が続くと、水分摂取量が減り、脱水症状を起こしやすくなるのです。
身体機能低下
膝や腰の痛みなどで、動く気力が低下している高齢者も多くいます。すると、台所まで飲み物を取りに行くのが面倒だったり、食事を用意したりする気が起きなかったりして、低栄養や脱水症状につながってしまうのです。
低栄養と脱水症状で見られる症状
低栄養と脱水症状それぞれで見られる症状を説明します。
低栄養で見られる症状
- 体重減少
- 感染症にかかりやすい
- 筋力低下
- 下半身や腹部のむくみ
- 傷(褥瘡など)の治りにくさ
低栄養と脱水症状に共通する症状
- 皮膚の乾燥
- 唇や口の中が乾燥している
- 食欲不振
- 唾液がねばつく
- 無気力
- ふらつきが見られる
介護をしている方は、要介護者に低栄養や脱水症状に該当する症状が見られないか、注意深く観察しておきましょう。脱水症状は放っておくと命の危険があります。

万が一、いつもより反応が鈍かったり、ぐったりしていたら、スポーツドリンクや経口補水液などで速やかに水分補給をしましょう。
ただし、症状が改善しない場合や、嘔吐、意識障がいなど中等度以上の脱水症状がある場合、早急に医療機関にかかってください。
低栄養を早期に発見する3つの指標
低栄養かどうかを判断する3つの指標があります。
1.BMI
BMIは肥満度をあらわす指数のことです。下記の計算式でBMIが算出できます。
『日本人の食事摂取基準2020年版』によると高齢者の目標BMIは以下のようになっています。
目標BMI
65~74歳:21.5~24.9
75歳以上:21.5~24.9
BMIが19を切ると、危険信号です。一度計算をしてチェックしてみましょう。
体重の減少率
体重の減り方によっても、低栄養のリスクがわかります。体重が6ヵ月で10%以上、あるいは1ヵ月で5%以上減少した場合、低栄養のリスクが極めて高いとされています。
普段から体重を測ることで、低栄養のリスクが高いかどうか判断しやすくなります。
血液検査の結果
血液検査のうち「血清アルブミン」「総コレステロール値」「総リンパ球数」などが、栄養状態を判断する主な指標となります。少なくとも1年に1回は医療機関で血液検査を受けてみましょう。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 血清アルブミン | 3.5g/dL以下 |
| コレステロール値 | 160mg/dL以下 |
| 総リンパ球数 | 1200~2000(軽度低栄養) |
| 800~1199(中等度低栄養) | |
| ~799(高度低栄養) |
低栄養と脱水症状を防ぐための食事例
低栄養と脱水症状の両方を防ぐには、食事に気をつけることが大切です。そこで、どういった食事が適しているのか紹介します。
低栄養を防ぐ食事例
低栄養を防ぐには「炭水化物」「脂質」「タンパク質」の三大栄養素をまんべんなく摂りましょう。
炭水化物や脂質は、体を動かすエネルギー源となるため、欠かせません。ごはん、パン、麺、油脂などは、毎食取り入れましょう。
タンパク質は体をつくる材料です。肉や魚、卵、大豆製品、乳製品などから摂りましょう。特に、肉はタンパク質の量が多く、積極的に食べてほしいところですが、加熱をすると固くなりやすいという欠点があります。
無理に食べさせるのではなく、「ひき肉を使う」「圧力鍋で調理をする」といった工夫をしましょう。
脱水症状を防ぐ食事例
1日の食事から摂れる水分量の目安は、約1,000mlです。飲み物だけで補うのではなく、水分が多い食事を意識して取り入れてください。
また、食後のデザートやおやつに、水分量が多いゼリーやヨーグルトなどを取り入れると良いでしょう。
両方を組み合わせた食事例
低栄養を防ぎ、脱水症状を予防するための食事の一例を紹介します。
- シーフードあんかけチャーハン(炭水化物・脂質・タンパク質・水分)
- 豆腐ハンバーグきのこあんかけ(タンパク質・水分)
- なすと肉団子の煮びたし(タンパク質・水分)
- トマトとオクラの納豆和え(タンパク質・水分)
- フルーツヨーグルト(タンパク質・水分)
高齢者におすすめしたいのが、あんかけ料理です。だしで薄味のあんを作ることで、自然と水分補給ができ、のどごしもよくなるので一石二鳥です。

低栄養と脱水症状は、どちらも命にかかわります。こまめな水分補給はもちろん、食事を工夫して必要な水分量を確保しましょう。