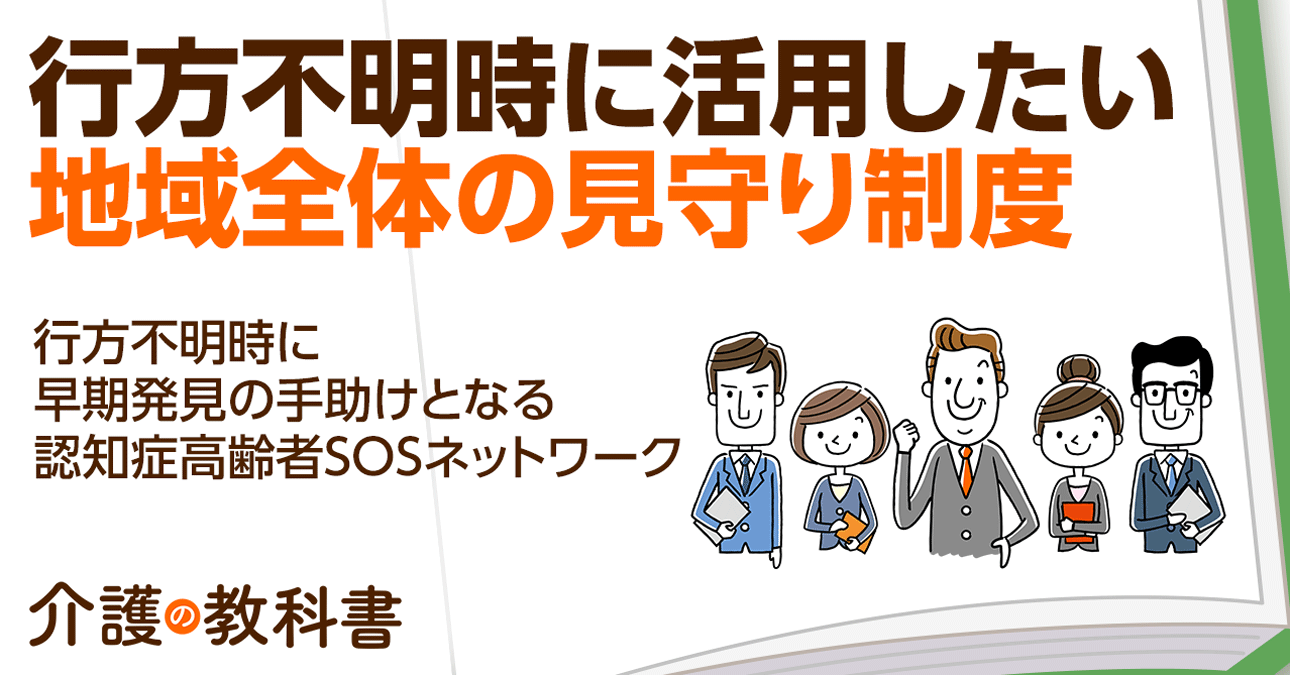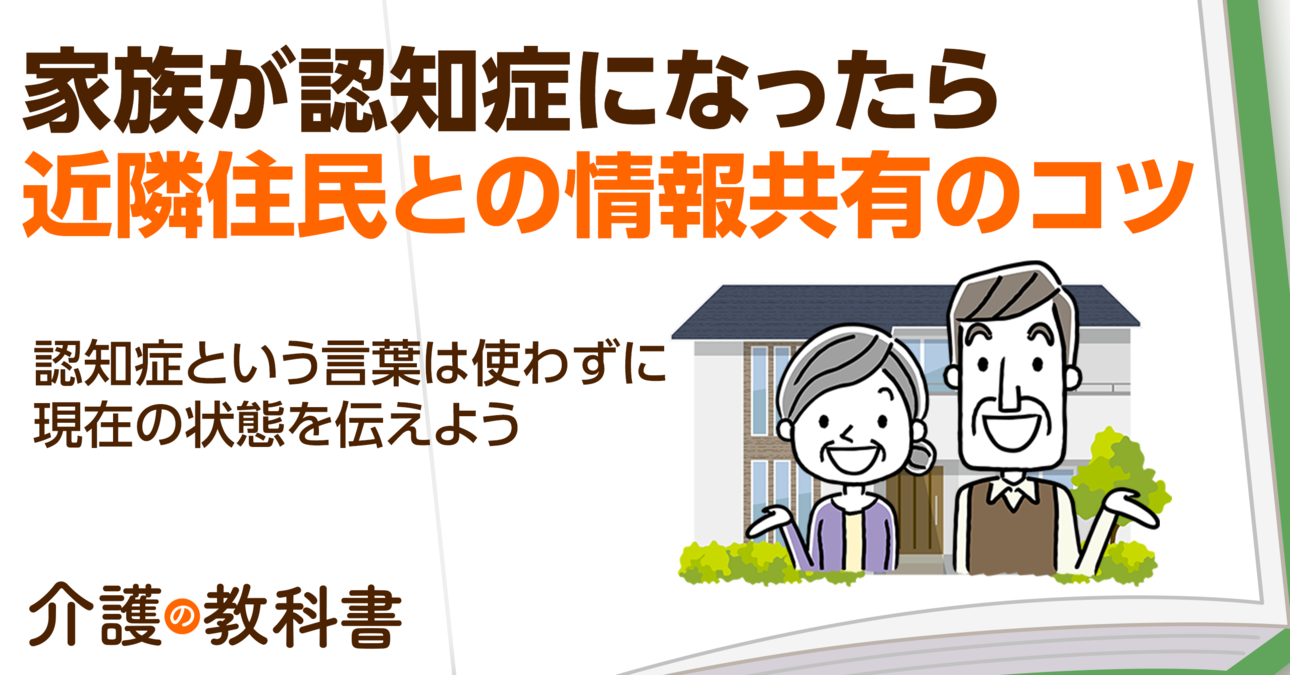こんにちは。甲斐・広瀬法律事務所の弁護士で、「介護事故の法律相談室」を運営している甲斐みなみと申します。
今回は、認知症患者が帰宅願望などによって、利用中の施設から外出し、行方不明となった場合の賠償責任について解説したいと思います。
徘徊の社会問題化
認知症の周辺症状に、徘徊があります。徘徊というのは、あてもなくうろうろと歩き回る行動のことです。徘徊は、第38回で述べた帰宅願望や、どこにいるのかがわからず迷ってしまうことなどによって起こります。周囲からは、ただうろうろしているように見えるかもしれませんが、本人は家に帰ろうとしているとか、屋内でもトイレを探しているなど、目的や理由があって行動しているとされています。
認知症による徘徊は、年々社会問題化しています。警視庁の統計によると、認知症やその疑いがあり、徘徊などで行方不明になったとして届出のあった人は、2020年で1万7,565人にのぼり、統計を取り始めた2012年から毎年増え続け、これまでで一番多くなっています。
徘徊をしていた認知症患者が、線路内に立ち入って電車にはねられて死亡した事故で、鉄道会社が本人の親族に損害賠償請求した事件(最判平成28年3月1日、家族の賠償責任を否定)も記憶に新しいところです。
認知症患者が行方不明になると命にかかわる
認知症患者が自宅から外出して行方不明となることは多くあります。さらに、施設利用時に、外に出てしまって行方不明となる事故も起こっています。認知症患者がひとたび施設外に出てしまうと、自力で自宅や施設に帰ることは難しくなります。また適切な支援を第三者に求めることも困難です。徘徊を続けた末、冬であれば凍死や低体温症による死亡、夏であれば熱中症による死亡、あるいは事故で死亡することも想定されます。

桜美林大学老年学総合研究所が行った、認知症などで行方不明となった人の家族に対する調査(回答数204人)では、5日目以降の発見では生存者がゼロでした。さらに、行方不明になった後に死亡したの死因としては、溺死、凍死、事故などだったそうです。
そのため、多くの介護施設では、まず、徘徊や帰宅願望のある認知症患者の動静を見守るようにしています。また、認知症のある利用者が施設から外出してしまうことのないよう、ドアを開けたりエレベーターを利用するのに、暗証番号入力を必要としたり、カードキーを必要としたりするなど、ハード面でも対策を講じています。
施設から出て行き死亡した事故の賠償責任
では、認知症患者が、利用中の施設から出て行方不明となってから死亡した場合、施設側の責任はどうなるのかを、「福岡地裁平成28年9月9日判決」を基にした事例で、検討してみたいと思います。
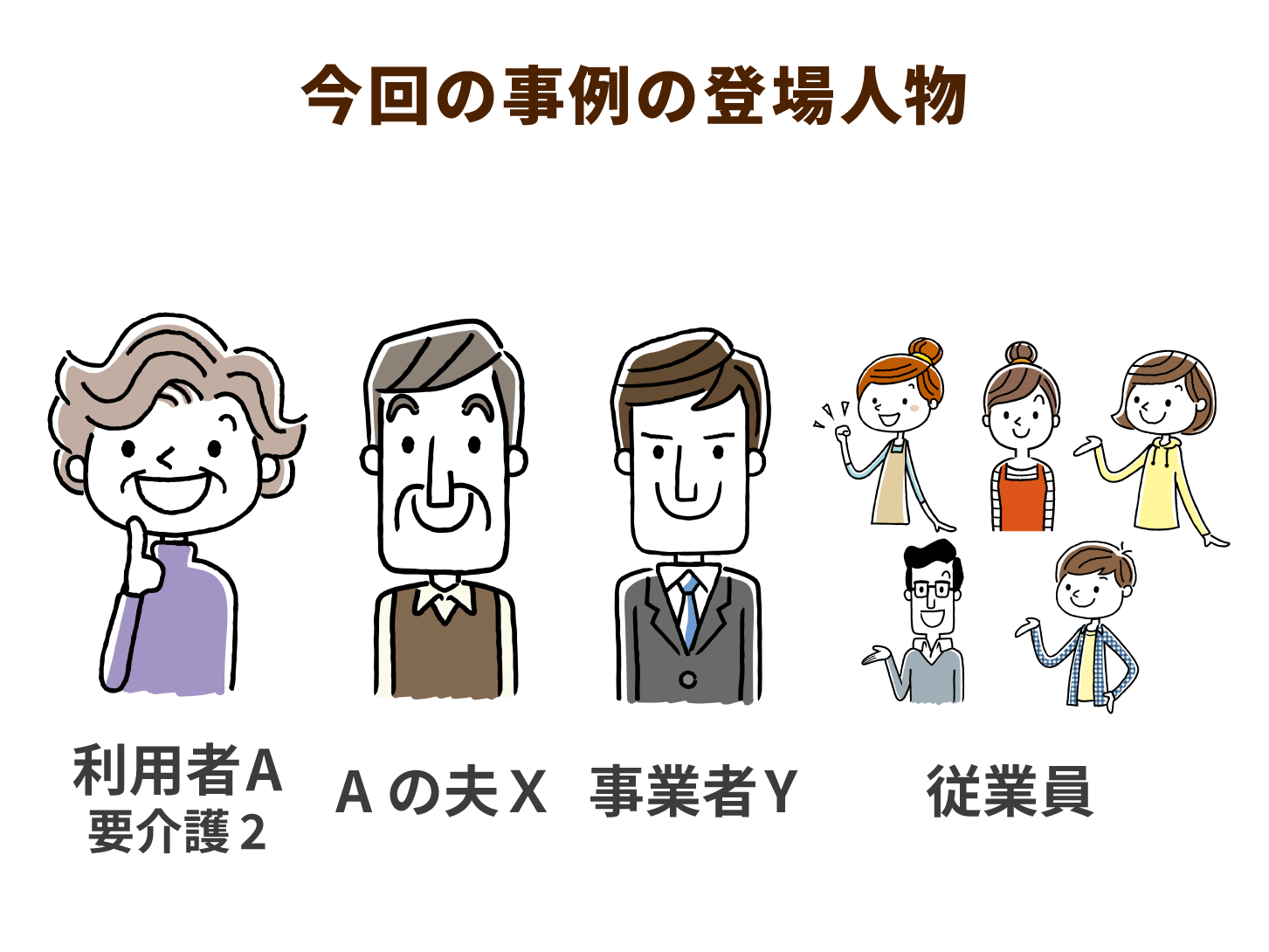
Aさんは、数年前にアルツハイマー型認知症となりました。最近では、玄関付近や家の周囲を徘徊したり、外出して戻れなくなって警察に保護されたこともありました。夫のXさんはAさんに徘徊がみられることなどを伝え、事業者Yの開設するデイサービスを利用し始めました。
Yのデイサービスは、特別養護老人ホームなどと一体となっている建物の2階の一区画となっていました。デイサービスエリアには、正面出入口、建物正面玄関に通じる非常口、特別養護老人ホームに通じる非常口がありました。正面出入口は施錠されておらず、人の出入りがあると鈴の音がなる自作の器具が設置されていました。非常口の方は、施錠されておらず、音が鳴る器具も設置されていませんでした。また、建物自体の正面玄関も施錠されておらず、音が鳴る器具や人の出入りを監視する体制はありませんでした。
デイサービスを利用し始めて約1ヵ月後でした。真冬のある日、Aさんはお昼過ぎに施設から出てしまい、行方不明となりました。
Aさんは、その日の午前中から強い帰宅願望を訴えていました。昼過ぎにはデイサービスフロア内で着席していました。しかし、椅子から立ち上がり、キッチン付近にいる職員に話しかけた後、職員らの横を通ってデイサービスフロアを横断。トイレの方向に向かって、建物正面玄関に通じる非常口の扉を開け、建物正面玄関から敷地外に出ました。
その日は、デイサービスの利用者が28名、介護職員が9名がいました。Aさんが行方不明となったときは、昼休憩の時間帯で、介護職員9名のうち4人は休憩中で、残り5人で利用者の対応をしていました。5人のうち2人は、利用者の口腔ケアやその準備にあたっており、1人は利用者の相談に応じていました。残り2人はキッチン付近で下膳作業をしていました。Aさんは職員のいるフロアを横断して出て行きましたが、出て行くところは誰も見ていませんでした。
その後、Aさんがいないことに気づいた職員が、建物内及び周辺を捜索し、警察や役場にも連絡して、警察犬による捜索や町内放送などもされました。しかし、Aさんは発見されず、3日後に畑で遺体となって発見されました。死因は低体温症(凍死)でした。
動静を見守る義務(注視義務)違反
Aさんについては、徘徊に関して以下の点が問題となっていました。
- 最近は徘徊が問題となっていた
- 外出して戻れなくなり、警察のお世話になったこともあった
- 行方不明になった当日も、強い帰宅願望を訴えていた
このような状態のAさんがフロア内を横断して非常口から出て行くのを、誰も見ていなかったということは、施設として利用者の安全に配慮する義務を果たしたと言えるのでしょうか。
「福岡地裁平成28年9月9日判決」も、Aさんの徘徊癖や当日の帰宅願望から、施設から抜け出すことについて警戒をすべきだったとしました。そして、Aさんが椅子から立ち上がり、フロアを横断して非常口方向に向かっていることは、施設から抜け出す危険な兆候ととらえるべきだとしました。
このようなAさんの兆候に対し、Yの職員らとしては、Aさんの行き先を目で追い、所在の確認をすべきでした。しかし、実際には、Yの職員らは一人もAさんの行動を注視せず、抜け出させています。そのため、動静を見守る義務(注視義務)に違反したと判断し、Aさんの死亡による損害について、Yに賠償責任があると判断しました。
他方、福岡地裁判決は、デイサービスエリアの正面入口を除き、人が出入りした際に音が鳴る器具がついていなかったことについて、職員が利用者の動静を適切に見守れば、利用者の抜け出しを防止できるのであるから、物的体制の不備とまではいえないと判断しました。
ハード面の対策不備が問題となった事案
上記事例では、昼休憩とはいえ職員が5人おり、口腔ケアなどにあたっていた2人を除き、3人はAさんを含む利用者がいるエリアにいました。そのため、適切に動静を見守れば足り得るはずでした。出入口の物的設備の状況についても不備はないと判断されています。
しかし、施設の利用者および職員の配置状況によっては、職員の注視義務違反を否定し、逆にハード面の対策不備について義務違反を認めている判例もあります。
「さいたま地裁平成25年11月8日判決」は、小規模多機能型居宅介護施設で宿泊サービスを利用していた認知症患者男性が、施設から抜け出して外に出てしまい、3日後に死亡しているところを発見された事例です。こちらでは施設設備の設置義務違反が認められました。
この小規模多機能型居宅介護施設は、2階建て民家を改装したもので、その日は利用者3名に対し、介護職員が1人勤務していました。介護職員は、その男性が何度も外に出ようとしていたことは把握していたので、別の利用者のトイレ介助をしながらも、その男性の動静に注意を払い、物音がしたらリビングの方を見に行くなどしていました。そのため、当該職員としては十分注意を払っており、注視・監督の義務違反はないと判断されました。
しかし職員が気づかないうちに、その男性は内側から鍵のかかっていた勝手口を空けて外に出てしまいました。勝手口の鍵は回せば開くサムターンタイプで、ドアが開いたら音が鳴るような器具はついていませんでした。そのため、施設設備の設置義務違反で賠償責任が認められたのです。
注視義務違反と施設設備の設置義務違反の両方に注意しよう
人員の関係で、どうしても動静に注意を払うことができないような環境であれば、ハード面の義務違反が問われやすくなります。一方で、それなりに職員がいて、動静を払うことが可能なのであれば、注視義務違反が問われやすいということです。
施設としては、不注意による事故を起こさないよう、ハード面も整えておいた方が良いでしょう。